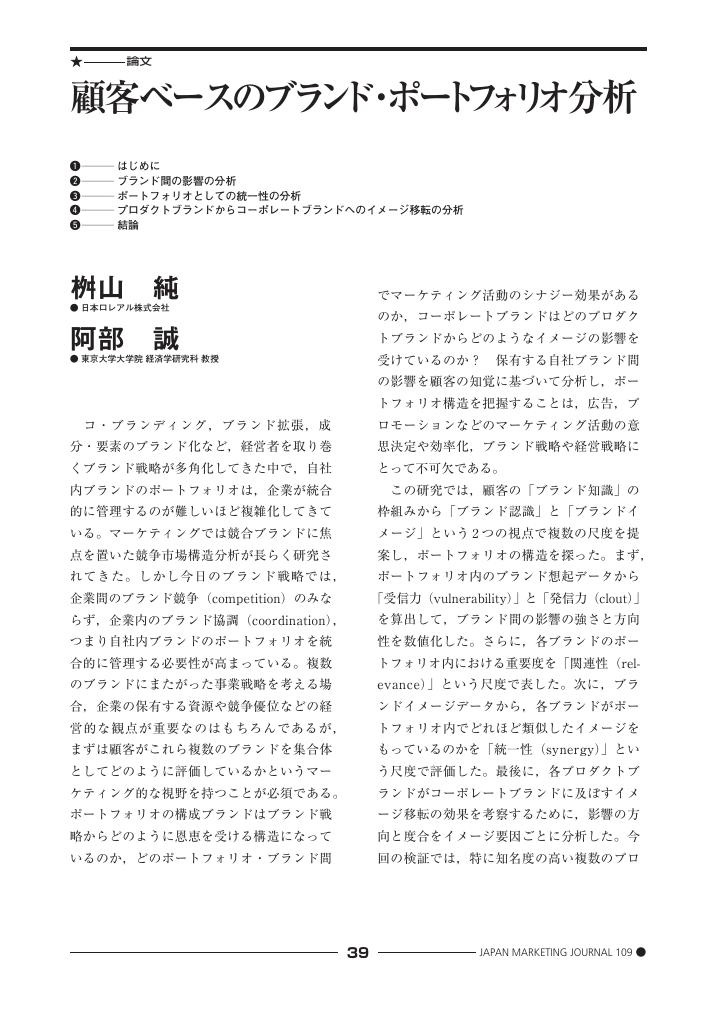1 0 0 0 OA ウイメンズヘルス学からみた自動車運転
- 著者
- 立岡 弓子
- 出版者
- 一般社団法人 日本交通科学学会
- 雑誌
- 日本交通科学学会誌 (ISSN:21883874)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.14-21, 2020 (Released:2021-07-23)
- 参考文献数
- 4
女性にとって、自動車運転は身近な移動手段となっている。女性は、性周期により、またエストロゲン分泌状態により、男性に比べて体調に変化が生じやすい。この女性の性と生殖に関する健康状態について、ホルモン動態を中心に理解し、さらに心理社会的健康への影響についても包括的にとらえていく健康科学分野にウイメンズヘルス学がある。ウイメンズヘルス学の考え方から、女性の自動車運転への影響を女性のライフサイクルごとに解説した。女性の性周期による体調の変化は、自動車運転に影響を与えているが、これまで交通医学や交通科学において、ウイメンズヘルスの視点から交通事故への影響要因は検証されていない。今後は、男性とは異なる視点で女性特有の自動車運転への影響要因について、ウイメンズヘルスの視点から交通科学の知見を再考していくことを願っている。
- 著者
- 馬塲 美年子 一杉 正仁
- 出版者
- 一般社団法人 日本交通科学学会
- 雑誌
- 日本交通科学学会誌 (ISSN:21883874)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.42-49, 2020 (Released:2021-07-23)
- 参考文献数
- 8
近年、体調変化に基づいた健康起因事故が問題となっており、特定の病気に罹患している運転者の事故に対して、一定の要件の下に危険運転の適用が可能となる法律が新設された(2014年)。また免許取得・更新の際、免許の欠格事由となる一定の病気に対するチェックが強化された(2014年)。しかし、健康起因事故は特定の病気や一定の病気だけでなく、いわゆるcommon diseases or symptomsに基づく体調変化でも起こり得る。日常的に誰もが経験する体調変化は、運転に際してのリスクとして意識されにくいが、死傷事故の原因となり得る。 そこで、健常な人であっても日常的に経験することが多いcommon diseases or symptomsに起因した交通事故の予防策を講じる知見を得ることを目的として、かぜ症候群、腹痛、誤嚥(むせ)に基づく事故事例および判例について検討した。対象は15例で、事故当時の平均年齢は51.1±13.3歳であった。職業運転者が3分の2(10人)を占めていた。疾患・症状は、かぜ・くしゃみが各5例、インフルエンザが2例、咽頭炎・腹痛・誤嚥(むせ)が各1例であった。刑事処分結果が明らかな事例は8例あり、被疑者死亡による不起訴の1例を除き、全例有罪判決が下された。有罪7例中、6例は運転中止義務違反、1例は運転避止義務違反で過失が認められた。一定の病気や特定の病気に罹患している運転者と同様に、比較的軽微な疾患・症状であっても、体調不良時の運転は避けること、運転を継続しないことが重要であると考えられた。実刑判決は3例あり、いずれも職業運転者であった。職業運転者の健康起因事故では、事業者も法的責任が問われることがある。事業者もcommon diseases or symptomsの運転リスクを認識し、日頃からの基本的な対策を怠らないことが必要である。
- 著者
- 岡 正俊
- 出版者
- 中央労働災害防止協会
- 雑誌
- 安全と健康 (ISSN:18810462)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.46-48, 2016-01
1 0 0 0 OA 顧客ベースのブランド・ポートフォリオ分析
- 著者
- 桝山 純 阿部 誠
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.39-55, 2008-06-30 (Released:2021-06-03)
- 参考文献数
- 21
1 0 0 0 大正二年司法部大改革再考
- 著者
- 吉田 満利恵
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.126, no.4, pp.1-33, 2017
大正二年、司法部刷新のための五法案が成立し、全国で 312 の区裁判所の内 128 の廃止、1510 人の判事及び検事の内 232 人の休職が定められた。また、裁判所構成法に判事の反意転補を可能にする規定が追加された。本稿の目的は、この司法部大改革を巡る議論を通して、この時代における司法問題の扱われ方とその影響を明らかにすることである。<br>判検事の休職法では、本来定員が別に定められ、その身分保障に差のあった判事と検事が同列に扱われ、休職となる判検事の合計数しか規定されなかった。その結果、判事の定員が大幅に削減されたのに対して検事の定員は微減に止まった。また、検事の精選が行われ、定員の減少数を大幅に上回る数の検事が休退職処分となった。<br>休職法と裁判所構成法改正案は裁判官の独立を侵害する危険を持っていたが、区裁判所廃止という人民の利害に直接関わる問題に議論が集中したことで、議会での審議は低調のまま終わった。判事の身分保障を脆弱にする危険のある新法律・条項案が提出されても、議会で争点となりやすい他の論点の存在によって、十分に審議されない傾向があった。<br>そして、当該法案がほとんど批判のないまま成立したことにより、判事の身分保障を規定する憲法五八条二項の「職」という文言を「官」の意味であると解し、裁判「官」であることさえ免じなければ「職」を免じても良いとする解釈が、大正十年に採用された。<br>明治憲法下において司法権の独立が不十分であったのは、裁判所構成法に、裁判所に対する司法省優位の性質があったからだけでなく、行政によって漸次的に法律解釈が変更されたことや 、新法律・条項が追加されたこと、また、それに抵抗する議員や判事、在野法曹が少なくなったことにも要因があるといえる。大正二年司法部大改革は、司法省、議会、そして法曹界自身によって、裁判官の独立の形骸化が促進された事例の一つであった。
1 0 0 0 OA 弓道における「早気」に関する研究
1 0 0 0 OA 弓道における異常な運動(いわゆるイップス)―頻度,分類,危険因子の検討―
- 著者
- 西尾 誠一郎 林 祐一 加藤 新英 大野 陽哉 和座 雅浩 長尾 洋一郎 向野 晃弘 中根 俊成 下畑 享良
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- pp.cn-001568, (Released:2021-07-17)
- 参考文献数
- 16
弓道において,弓を放つ際,「早気,もたれ,びく,ゆすり」と呼ばれる4種類の状態が生じ,上達に支障を来す.種々のスポーツで認めるイップスの定義に当てはまるが,これまでほとんど検討されていない.これらの頻度や分類の意義,危険因子について明らかにすることを目的に,大学生を対象とした検討を行った.アンケートを行った65名中41名(63.1%)にいずれかの経験があり,「早気」が最も多かった(のべ35名;85.3%).イップス発症の危険因子として,経験年数が長いことが関与していた.病態は未だ不明なことが多いが,「もたれ」のみ単独で出現し,その特徴からも動作特異性局所ジストニアの関与の可能性が疑われた.
1 0 0 0 OA 山陰地方における海浜植生の成帯構造と地形
- 著者
- 中西 弘樹 福本 紘
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.225-235, 1991-12-31 (Released:2017-05-24)
- 被引用文献数
- 8
The vegetational zonation of sandy coasts in the San in District was studied in relation to depositional topography. The vegetation was divided into four zones (Z1-Z4). The first (Z1) was pioneer zone where only young plants were found in places. The second (Z2) was of grass communities which were divided into two subzones (Z2-a, Z2-b). Carex kobomugi was a dominant of Z2-a and Ischaemum anthephoroides of Z2-b. The third (Z3) was occupied by scrub demarcated by dominant growth of Vitex rotudifolia, and the fourth (Z4) was represented by plantations of Pinus thunbergii and Robinia pseudo-acasia. The Izumo coast faces north-west and receives prevailing NW-wind in winter and sand dunes develop. As dune height increases, Z2-a becomes narrower and Z2-b becomes wider. The Yumigahama coast, however, does not have prevailing winds in its front, so that dunes do not develop to make flat topography. The vegetation was found far from the shore-line. The Hojyo coast has well-developed dunes which are comparatively stable, because of the coarse beach sediments, leeward place and snow accumulation in winter. On the stable dune the narrow grasses of Z2 zone and Artemisia capillaris and Heteropappus hispidus var. arenarius on the third zone (Z3) were commonly found. The relationship between the zonation of the dune vegetation and topography was discussed with respect to the prevailing winds and the particle of the beach sediments.
1 0 0 0 IR プロジェクト法を用いた「読書と豊かな人間性」の実践
- 著者
- 瀬田 祐輔 牧 恵子
- 出版者
- 愛知教育大学実践総合センター
- 雑誌
- 愛知教育大学教育実践総合センタ-紀要 (ISSN:13442597)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.91-100, 2010-02
学校図書館司書教諭講習科目「読書と豊かな人間性」は,司書教諭が,読書指導の直接の担い手となることばかりではなく,全校の読書指導の推進者としての役割を果たすことをも見据えた内容となっている。しかしながら,子どもを読書に誘うための個々の手法を実習または演習として組み込むのみでは,それらを駆使した計画・実践ができる力,いわば応用のきく力として身につけさせることは困難である。そこで本稿においては,この問題を解決しうる授業方法を探るべく,プロジェクト型の学習形態(「第2回科学・ものづくりフェスタ@愛教大」に参加し,科学読み物を中心とした読書材の読み聞かせ企画を受講生に運営させるという形)を組み込んだ授業を構想し,実施を試みた。その結果,「読書と豊かな人間性」において,プロジェクト型の学習形態を採用することには,読書指導に関する知識や技能を応用のきく力として身につけさせるという点で,一定の効果を見出すことができた。
- 著者
- 後藤 真孝
- 出版者
- 京都産業大学法学会
- 雑誌
- 産大法学 (ISSN:02863782)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, pp.1032-1018, 2007-03
1 0 0 0 11油脂
- 著者
- 浅原 照三 山下 健二郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本分析化学会
- 雑誌
- 分析化学 (ISSN:05251931)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.12, pp.115R-120R, 1961
1959~60年の間の油脂の分析に関する研究発表の概要をここにまとめてみることにする.なお,わが国の油脂全般の研究業績についてはすでにまとめられている.以下便宜的に植物油脂,動物油脂,脂肪酸,ロウ,ステロイド,複合脂質,洗剤およびその他の各項目にわけて記述する.
1 0 0 0 OA 人間行動進化学から見た今どきの若者
- 著者
- 長谷川 寿一
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.301-305, 2019-06-01 (Released:2020-02-28)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA 大腸穿孔6症例の検討
- 著者
- 石川 正美 太田 宏 高原 信敏 大野 昭二 三浦 則正 稲垣 嘉胤 渋沢 三喜 石井 淳一
- 出版者
- Japan Surgical Association
- 雑誌
- 日本臨床外科医学会雑誌 (ISSN:03869776)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.3, pp.331-336, 1984-03-25 (Released:2009-02-10)
- 参考文献数
- 19
1982年1月から10月までの10ヵ月間に, 6例の大腸穿孔による,汎発性糞便性腹膜炎を経験したので報告する.同期間における当病院の大腸手術例は68例で,大腸穿孔が占める割合は8.8%であった. 手術はexteriorizationおよびHartmann法を症例によって使いわけ,腹腔ドレナージの他に,術中に腹膜潅流用チェーブを挿入して,術後間歇的腹腔内洗浄を行った.術後合併症のうち,創〓開に対して縫合創に全層マットレス減張縫合を加えて良好な結果を得,未然に防止可能と考えられた.術後endotoxin shockから離脱した後に,心筋梗塞を合併して死亡した症例を経験し,初期shockから回復した後も,発生し得る2次的合併症に対する厳重な観察が必要と考えられた. 汎発性糞便性腹膜炎において,白血球数は比較的早期から低下することが示唆され,発症より14時間を経た症例は全例がshockを発生し, 16時間を経た症例の転帰は極めて不良であった.全体の死亡率は50%であったが, shock合併例の死亡率は75%と高値を示し,発症から手術までの時間に大きく左右されることが示唆された.
1 0 0 0 ポリグリコリドの合成反応
- 著者
- 浅原 照三 山下 健二郎 片山 志富
- 出版者
- The Chemical Society of Japan
- 雑誌
- 工業化学雑誌 (ISSN:00232734)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.485-489, 1963
- 被引用文献数
- 3
最も簡単な脂肪族オキシ酸であるグリコール酸より導びかれるポリグリコリドに関して,その生成原料の検討,反応速度,反応温度の決定などについての研究を行なった。ポリグリコリド生成の原料としては,グリコール酸,モノクロル酢酸およびモノクロル酢酸ナトリウムを用いた。グリコール酸およびモノクロル酢酸ナトリウムは触媒の存否にかかわらず反応するがモノクロル酢酸の反応は触媒が存在しなければ進行しない。グリコール酸の脱水反応は無触媒の場合にも酸化アンチモンの場合にもともに見掛けの3次反応である。酸化アンチモンを加えれば,反応速度は大きくなるが,分解反応も激しくなるので,無触媒のほうが高重合度のポリマーを与える。臭化カリウムを用いたモノクロル酢酸の反応は見掛けの2次反応であった。それぞれの場合の反応速度の解析値が得られた。常圧における最適反応温度は219℃ であるが,ポリグリコリドの融点や溶融粘度を考慮して,225~230℃ が望ましいと考えられる。
1 0 0 0 OA 中学3年英語聞き取り検査作成の研究
- 著者
- 芳賀 純
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.82-84,132, 1969-10-15 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1 1
北海道全域から抽出した中学校3年生1267名を被検者にしてNHKラジオ放送によつて英語聞き取り検査を施行し, 標準化した。この検査は6項目の聞き取り能力の下位検査からなり, ペーパーによる英語標準検査とは.780の相関値をもつ。問題の録音吹込みは経験を経た日本人教師によつてなされたために, この聞き取り検査は教室場面で経験を経た英語教師がテープなしに問題を読むことによつて近似的に生徒の能力を測定・評価することも可能である。なお今後の研究は, この結果を基礎として外人教師が問題を吹込んだ場合との比較および分析が必要である。
- 著者
- 川又 英紀
- 出版者
- 日経BP
- 雑誌
- 日経アーキテクチュア = Nikkei architecture (ISSN:03850870)
- 巻号頁・発行日
- no.1191, pp.54-61, 2021-05-13
コロナ収束後の週2回出社を促す職場づくりZOZOが2021年2月に、本社を千葉市の海浜幕張から西千葉に移転。大空間のオフィスをつくった。吊り屋根を採用して柱を少なくしたスペースには、働き手が選べる多様な場をちりばめた。
1 0 0 0 IR 中学生における心理状態と食品摂取との関係
心理状態と食品摂取の間に相関関係があるのか調べるため,平成14年9月に栃木県南河内町の中学校2年生200名を対象とし,多枝選択式による自記式食事調査票と心理状態に関する質問票の2種類のアンケート調査を実施し52%の有効回答を得た。データはプログラムBDHQL2を用いて算定し,食生活の傾向は食品摂取頻度および栄養素摂取量の2つのパラメーターによって評価した。心理状態と食品摂取との関係では,「カッとしやすさ」と「醤油・ソース頻度が高いこと」・「外食と比べたおかずの量が少ないこと」とに,同じく「イライラ感」と「骨ごとの魚食べる頻度が少ないこと」・「主食のある朝ご飯を食べる頻度が少ないこと」とに,「根気のなさ」と「骨ごとの魚頻度が少ないこと」・「海草摂取量の少ないこと」とに,「疲れやすさ」と「キャベツの摂取量の少ないこと」と・「きのこ摂取量の少ないこと」とに,「登校忌避感」と「生サラダ(レタス,キャベツ,トマト除く)を食べる頻度の少ないこと」・「主食のある朝ご飯を食べる頻度の少ないこと」に,相関が認められる結果となった。また栄養素に関しては「疲れやすさ」において「灰分」・「ナトリウム」・「ビタミンC」・「n-6系脂肪酸」・「多価不飽和脂肪酸」・「n-3系脂肪酸」と負の相関が見られる結果となった。
1 0 0 0 改良Smith-Petersen氏釘
- 著者
- ピドコック
- 出版者
- 一般社団法人 日本医療機器学会
- 雑誌
- 医科器械学雑誌 (ISSN:00191736)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.8, 1937