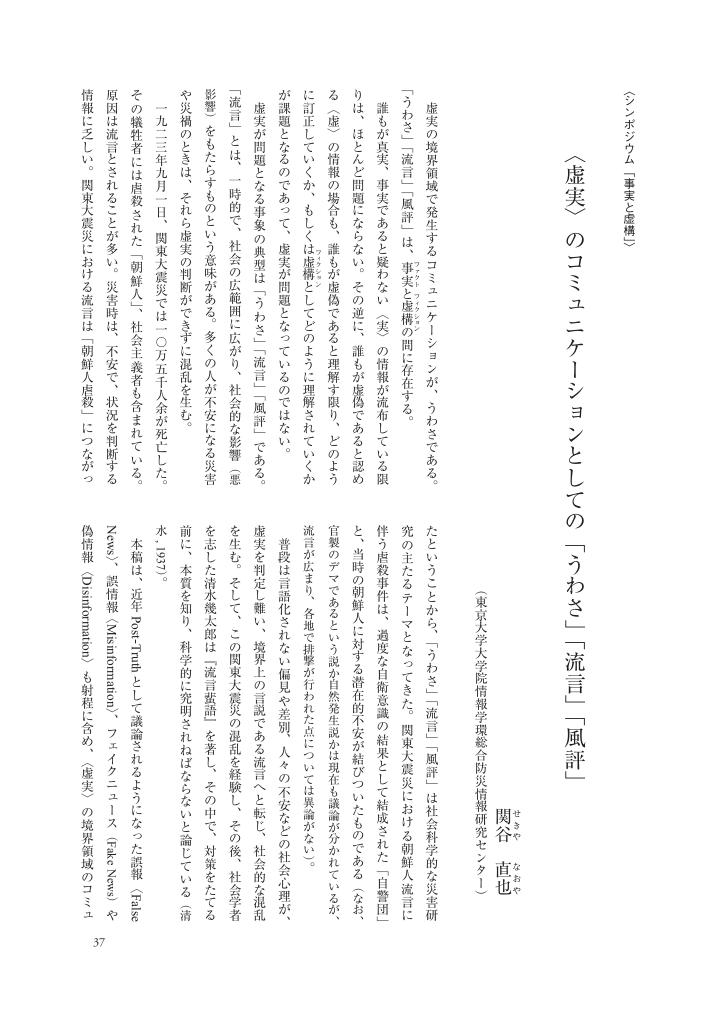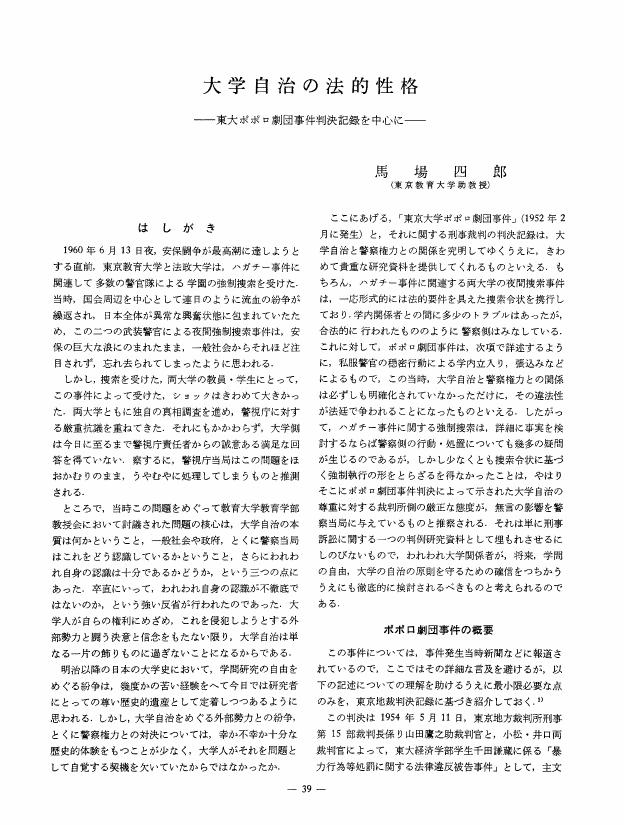6 0 0 0 OA 〈虚実〉のコミュニケーションとしての「うわさ」「流言」「風評」
- 著者
- 関谷 直也
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, no.73, pp.37-47, 2022-04-01 (Released:2022-07-21)
- 参考文献数
- 21
6 0 0 0 OA 外来昆虫の引き起こす問題 —外国産クワガタムシの輸入をめぐって
- 著者
- 五箇 公一 小島 啓史
- 出版者
- 日本環境動物昆虫学会
- 雑誌
- 環動昆 (ISSN:09154698)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.137-146, 2004 (Released:2005-12-16)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
6 0 0 0 OA 小学生における朝食欠食が学業成績および感情に及ぼす影響
- 著者
- 小林 仁美 多賀 昌樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本食育学会
- 雑誌
- 日本食育学会誌 (ISSN:18824773)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.33-38, 2021-01-25 (Released:2021-06-10)
- 参考文献数
- 23
Eating breakfast is very important for the health and development of children. However, few studies have explored the correlates of children’s academic performance. Therefore, we aimed to investigate the associations of breakfast and scholastic performance.Six hundred fifty-five children, aged 8 to 12 years, were surveyed using original questionnaires. Breakfast skipping was defined as having missed any food between waking and the commencement of morning school classes at least 1 school day during the past week.Eight percent of participants reported skipping breakfast at least once time per week. Children who ate breakfast everyday scored higher on Japanese language test than children who did not eat breakfast (71.6±18.9 vs 65.9±18.0, p<0.05). Furthermore, students who did not had breakfast had higher negative emotion than those who always ate breakfast.Breakfast is not only promoted to improve health, but also to improve scholastic performance. We suggest further studies on the relationship between meal content, and scholastic performance.
6 0 0 0 OA 特定健診・特定保健指導の効果に関する最新のエビデンス
- 著者
- 津川 友介 福間 真悟
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.5, pp.417-423, 2021-05-15 (Released:2022-05-15)
- 参考文献数
- 5
6 0 0 0 OA 病院前救護活動における血液の絞り出しおよび穿刺部位の違いが血糖値に与える影響
- 著者
- 藤森 隆史 竹中 ゆかり 仲村 佳彦 江藤 茂 三渕 拓司 吉村 健清
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.1-5, 2018-02-28 (Released:2018-02-28)
- 参考文献数
- 16
血液の絞り出しおよび穿刺部位の違いが血糖値に与える影響を検討した。①非絞り出し群と絞り出し群,②指腹で穿刺した群(指腹群)と爪脇で穿刺した群(爪脇群)をそれぞれ2群間で比較した。①の血糖値は非絞り出し群が113(83 〜303)mg/dl,絞り出し群が116(89〜275)mg/dlであった。その差は5.0(−45 〜20)mg/dlで,絞り出しにより有意に血糖値は上昇した(p<0.001)。②の血糖値は指腹群が116(87 〜162)mg/dl,爪脇群が116(82 〜170)mg/dl であった。その差は−1.0(−28 〜14)mg/dlで,有意差を認めなかった(p=0.151)。穿刺部位の違いが血糖値に与える影響はないが,絞り出しにより,血糖値は有意に上昇した。絞り出しを避けるまたは絞り出しにより血糖値が上昇することを考慮した上でのブドウ糖溶液投与プロトコールの作成が望まれる。
6 0 0 0 OA 大麻主成分の臨床適性使用に向けた予防薬学的基礎研究
米国において、大麻主成分のテトラヒドロカンナビノール(THC)はがん患者などでモルヒネが効かない重篤な痛み緩和の目的で投与される。本研究は、がん患者、特に乳がんに注目し、THCの臨床適正使用に向けた基礎研究である。THCは分子中に、女性ホルモンと類似した部分を有していた。女性ホルモンは乳がん増殖を促進したが、THCの共存下でその効果が消失した。低女性ホルモン条件下(閉経後乳がんモデル)でTHCを添加した場合、逆に増殖の促進が見られた。本研究により、THCは女性ホルモンと相互作用し、乳がん増殖に影響を与える可能性が示唆された。
6 0 0 0 OA 牧口常三郎『人生地理学』の地理学史上の再評価
- 著者
- 岡田 俊裕
- 出版者
- THE JAPANESE SOCIETY FOR GEOGRAPHICAL SCIENCES
- 雑誌
- 地理科学 (ISSN:02864886)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.4, pp.197-212, 1994 (Released:2017-04-27)
- 参考文献数
- 70
- 被引用文献数
- 1
牧口常三郎『人生地理学』(1903年初版,1908年訂正増補8版)は,当時の非アカデミズム地理学徒に歓迎され高い評価を受けたが,アカデミズム地理学の形成者たちには1970年代前半ごろまで無視ないし軽視されてきた。しかし本書は,環境論的な立場からの地人関係の考察が優れているだけでなく,分布論・立地論による経済地理学的・社会地理学的・政治地理学的な分析に先駆的かつ現代的な意義が認められる。なかでも,チューネン圏を最も早く地理学研究に導入した点が注目される。ただし牧口は,それを原典に忠実に導入することはせず,現実社会への適用および有効性を考慮しつつ吸収しようとした。この応用や実践への志向,および実学的な傾向が彼の学風の特徴であった。アカデミズム地理学者のなかで牧口に最も近い存在は,在野的な人文地理学者で,しかも「郷土会」の活動を共に行った小田内通敏であったと考えられる。しかし小田内でさえ,なぜか牧口とその著書について論及することがなかった。それは,前アカデミズム地理学の成果がアカデミズム地理学にあまり継承されなかったということを示唆していると考えられる。
6 0 0 0 OA 海底下深部開発計画の概要 (高島二子)
- 著者
- 井上 健一 有田 健三 堀川 次男
- 出版者
- 一般社団法人 資源・素材学会
- 雑誌
- 日本鉱業会誌 (ISSN:03694194)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.845, pp.942-948, 1958-11-25 (Released:2011-07-13)
- 著者
- Wataru Aoki Naoki Endo Shuji Ushijima Hiroyuki Nagai Tetsuro Ito Masaki Fukuda Akiyoshi Yamada
- 出版者
- The Mycological Society of Japan
- 雑誌
- Mycoscience (ISSN:13403540)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.5, pp.307-321, 2021-09-20 (Released:2021-09-20)
- 参考文献数
- 60
- 被引用文献数
- 2 5
“Kakishimeji” identified as Tricholoma ustale and belonging to Tricholoma sect. Genuina is a common poisonous mushroom in Japan. Kakishimeji contains the toxic compound ustalic acid and causes digestive trouble. However, this fungus is consumed in some regions of Japan without any digestive issues. We clarified the probable species complex of Kakishimeji based on a phylogenetic analysis. We collected 89 basidioma specimens of Kakishimeji and related species from various forest sites in Japan and conducted phylogenetic analyses using 7 nuclear and mitochondrial gene sequences. Kakishimeji was found to consist of four distinct phylogenetic clades based on all DNA regions tested. Of these, two clades included European T. stans and T. albobrunneum type specimens. Another two clades consisted of sister clades to T. pessundatum and T. ustaloides. In addition, all four phylogenetic clades of Kakishimeji had different spore and basidium sizes. Therefore, we regarded the latter two clades as two new Tricholoma species: T. kakishimeji and T. kakishimejioides.
6 0 0 0 OA パーソナリティ研究の現状と動向
- 著者
- 渡邊 芳之
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.79-97, 2018-03-30 (Released:2018-09-14)
- 参考文献数
- 122
- 被引用文献数
- 2 5
2016年7月から2017年6月にかけての日本におけるパーソナリティ研究の現状と動向を分析するために,120件の学会誌論文と375件の学会発表をパーソナリティ関連研究として抽出して分類し,いくつかの量的な側面から調べた。日本におけるパーソナリティ関連研究は,この期間に主要な学会誌8誌に掲載された論文のうち48.0%を,2つの学会における発表のうち47.2%を占めている。1年間の研究協力者の総数は222,986名にのぼり,132個の新しい個人差測定尺度や項目が開発されている。こうした研究にはSEMに代表される統計的因果分析の技法が広く用いられている。研究テーマの動向や,パーソナリティ関連研究のこうした動向がパーソナリティ心理学や「個人差科学」に対して持つ含意についても検討した。
- 著者
- Minoru Murayama
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.322-328, 2021 (Released:2021-04-06)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 6
[Purpose] We aimed to evaluate knee joint movement and muscle activity ratio changes in stroke hemiplegic patients in recovery phase after using a knee-ankle-foot orthosis with an adjustable knee joint for 1 month; we also aimed to discuss the practical implications of our findings. [Participants and Methods] The participants were 8 hemiplegic patients in the recovery phase of stroke who were prescribed knee-ankle-foot orthosis with adjustable knee joint. We measured knee joint angles and electromyographic activity of the vastus medialis and biceps femoris during walking in two conditions: the knee-ankle-foot orthosis knee joint fixed in the extended position and the knee joint moved from 0° to 30° in the flexion direction. Measurements were taken 2 weeks after completion to account for habituation of the orthosis and repeated 1 month later. [Results] When the knee joint was moving from 0° to 30° in the flexion direction, the knee joint angle at initial contact and the minimum flexion angle of the gait cycle decreased significantly between the first and second measurements. When knee joint flexion was 30°, the muscle activity ratio of the vastus medialis increased significantly in the loading response and mid-stance compared to when it was fixed. [Conclusion] Setting the knee joint of a knee-ankle-foot orthosis in accordance with the knee joint movement may increase the muscle activity ratio of the vastus medialis from loading response to mid-stance.
6 0 0 0 OA ルネサンス末期の文学実験工房─「アカデミア・デッリ・アルテラーティ」(1569-1634年)における詩と批評(BML Ashb. 561写本からBAV Vat. Lat. 8858写本まで)
- 著者
- ロレンツォ・アマート
- 出版者
- イタリア学会
- 雑誌
- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, pp.1-26, 2023 (Released:2023-11-15)
- 参考文献数
- 69
1569年から1634年まで、「アカデミア・デッリ・アルテラーティ」と呼ばれるフィレンツェの小さな私設アカデミーが、市の最有力家門の若き子弟たちの館で開かれていた。集まったのは、トンマーゾ・デル・ネーロ、ネーロ・デル・ネーロ、ピエロ・デル・ネーロ、会の中心人物となったジョヴァン・バッティスタ・ストロッツィ・イル・ジョーヴァネ、シピオーネ・アンミラート、ヴェルニオ伯ジョヴァンニ・デイ・バルディ、オッタヴィオ・リヌッチーニなどの当代知識人である。アカデミーの『日誌』Diario(フィレンツェ、ラウレンツィアーナ図書館Ashburnham 558写本)には、修養の機会としての「書くこと」の重要性が頻繁に語られている。そのため詩作品を制作してアカデミーに持参し、投稿箱に提出するように定められた。およそ月に一度、箱が開けられ、作品は「査読者」の手にわたって評価と批評がなされる。次いで「弁護人」に回され、今度は逆に、彼らは作品を擁護しなければならない。このディベートは間違いなく詩作品の欠点を正し、質を高めたに違いない。同時に、自説を論理立てて展開することができるように、また、詩的基準にもとづいて判断を精緻化できるように、アカデミーのメンバーたちを育てていったに違いない。ここでの詩的基準とは、韻律論、文体論、言語論、象徴的含意、「権威たる著者たち」の伝統との整合性などを指す。こうした査読と弁明のプロセスは、部分的にだが、現在まで伝えられている。ラウレンツィアーナ図書館Ashb. 560・561写本と、フィレンツェ国立図書館Ginori Conti 27b手稿には、実際、アルテラーティの何百もの詩が保存されているのである。それらの草稿には、時には多くの削除・訂正がほどこされ、また時には査読者や弁護人による評価が付されている。これらの写本は、アカデミー詩作品の「草稿」集成である『雑録』Zibaldoneの残滓である。他に現在まで伝わっている写本に、ヴァチカン図書館Vat. Lat. 8858写本(1575-1585年の間に筆写)があるが、こちらは「秀作」と判定された会員作品の公式アンソロジー(『日誌』で『アルテラーティ二次詞華集』とされる本)を伝える。Vat. Lat. 8858に収録された詩の一部は、Ashb. 560・561所収のものと突き合わせることが可能である。『雑録』にある詩が、作品の私的第一稿とみなし得るのに対し、Vat. Lat. 8858の詩は、例えばAshb. 561に書きとめられているような賛否両論のディベートを通じて提案された集団的見直しに従って到達した「集団的」決定稿とみなすことができる。これらのディベートを読み進めてゆくことは、したがって、極めて興味深い作業となる。なぜなら、ディベートがアカデミーのメンバーたちの教養や審美的嗜好を明らかにしてくれるからである。それゆえ、本論文では、Ashb. 561とGinori Conti手稿に見える査読と弁明の何節かを、可能な限りVat. Lat. 8858の最終稿とも突き合わせながら、分析する。ディベートで触れられた多くの重要な論点のうち、本論文第2章では、修辞・文体・言語にかかわる諸問題を集中的に扱う。そこから明らかになるのは、アカデミーのメンバー個々の様々な立場の違いを超えて、アカデミー全体がもつ「同時代主義者」という天性がいかに立ちあらわれ、口語を正真正銘の「権威たる著者」の基準とみなす「博識ある多様性」へと向かってゆくかである(クルスカ学会が当時求めていたのとは正反対の方向だ)。他方、本論文第3章では、16世紀末におそらくもっとも流行した詩のジャンルであったマドリガーレに焦点を当てる。実際、マドリガーレはVat. Lat. 8858を代表するジャンルとなるのである。もっとも、アルテラーティの最有力メンバーであったジョヴァン・バッティスタ・ストロッツィ・イル・ジョーヴァネは、かの偉大なマドリガーレ作者、ストロッツィ・イル・ヴェッキオの後裔であり、さらには、1574年にフィレンツェ・アカデミーで口述されたマドリガーレ講義の著者その人であったのだが。その意味で、以下のようなことが実証されたとしても驚くにあたらない。『二次詞華集』に認められる実際のマドリガーレ作品においてだけでなく、Ashb. 561に見えるマドリガーレへの批評や弁明においてもまた、支配しているのは奇想的な詩的言語の探求であり、その関心は自然さを犠牲にしてでも「驚異」の方へ、わかりやすさを犠牲にしてでも音楽性の方へ向かっている。アルテラーティ写本に見られる詩的実験は、実際、ほどなく初期オペラの実現につながる歌詞としての詩を準備する。他方それは、ガブリエッロ・キアブレーラの韻律的実験の先駆けをなしているようにも思われる。もっとも、『日誌』からわかるところでは、キアブレーラが範としたピエール・ド・ロンサールは、実際にアカデミーを訪問する以前からすでに、アルテラーティ内では読まれ、論評されていたのだが。そういうわけで、このルネサンス末期の詩と批評の正真正銘の実験工房が残したものを研究することは、後に続くイタリアン・バロックの詩的・音楽的美意識の形成をよりよく理解するために、重要なのである。
6 0 0 0 OA 統計学的にみて必要なサンプル数について
- 著者
- 磯 博康 嶋本 喬
- 出版者
- 社団法人 日本循環器管理研究協議会
- 雑誌
- 日本循環器管理研究協議会雑誌 (ISSN:09147284)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.262-265, 1999-10-30 (Released:2009-10-16)
- 参考文献数
- 7
6 0 0 0 OA 大学自治の法的性格 -東大ポポロ劇団事件判決記録を中心に-
- 著者
- 馬場 四郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.39-44, 1962-03-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 5
- 著者
- 和佐野 喜久生 湯 陵崋 劉 軍 王 象坤 陳 文華 何 介均 蘇 哲 厳 文明 寺沢 薫 菅谷 文則 高倉 洋彰 白木原 和美 樋口 隆康 藤原 宏志 佐藤 洋一郎 森島 啓子 楊 陸建 湯 聖祥 湯 陵華 おろ 江石 中村 郁朗
- 出版者
- 佐賀大学
- 雑誌
- 国際学術研究
- 巻号頁・発行日
- 1992
本学術調査は農学及び考古学の異なる専門分野から、東アジアの栽培稲の起源に関する遺伝・育種学的研究および中国の古代稲作農耕文化の発祥・変遷・伝播についての中国での現地調査、考古遺物・文献・資料の収集とその研究解析、現地専門家との討論を行うことであった。これまでの3回の海外調査によって、多くの研究成果を得ることができた。研究代表者の和佐野がこれまでに行った古代稲に関する調査は、中国の長江のほぼ全流域、黄河の中下流域、山東半島、遼東半島および海南島の中国全土にわたるものとなった。また、調査・測定した古代稲の実時代は、新石器時代の紀元前5,000年から前漢時代までの約5,000年の長期間に及び、その遺跡数も18カ所になった。稲粒の粒大測定は、大量にあるものからは約100粒を任意抽出し、それ以下のものは全粒を接写写真撮影によって行った。また、中国古代稲の特性を比較・検討するために、韓国の2カ所および日本の14カ所の古代遺跡の炭化米の調査も並行して行った。以上の調査結果に基づいて、次のような結論を得ることができた。(1)紀元前5,000年ころの気温は現在より2度は高かったこと、および北緯30度周辺に位置する城背渓および彭頭山遺跡文化(紀元前6,000-7,000年)の陶器片および焼土中に多くの籾・籾殻・稲わらの混入が発見されたことから、紀元前6,000-7,000年頃には北緯30度付近に稲(野生か栽培されたものかは分からない)が多く生育していたと考えられる。彭頭山遺跡の籾粒は6ミリ前後のやや短粒であった。(2)古代稲粒の大きさ・形の変異の状況および稲作遺跡の時代的新旧の分布状態から、東アジアの稲作は、長江の下流域・杭州湾に面した河姆渡および羅家角両遺跡を中心とした江南地方に、紀元前5,000年以上溯る新石器時代に始まったと考えられる。(3)長江の中流域には、紀元前6,000-7,000年の城背渓および彭頭山遺跡から稲粒が発見されているが、稲作農耕の存在を証拠づけるものがまだ発見されていないこと、河姆渡および羅家角両遺跡と同時代の紀元前5,000年頃の稲作遺跡が存在しないこと、中流域に分布する多くの遺跡が紀元前3,000-4,000年のものであること、などから、稲作は下流域から伝播したものと考えられる。(4)長江の最上流域の雲南省の稲作遺跡は紀元前1,000-2,000年の新しいものであり、稲粒も粒が揃った極端な短円粒であること、さらには、雲南省の最古の稲作遺跡である白羊村遺跡の紀元前2,000年頃には、黄河流域からの民族移動の歴史があること、などから、稲作のアッサム・雲南起源説は考えられない。アッサム・雲南地域は、周辺地域から民族移動に伴って生じた稲品種の吹きだまり(遺伝変異の集積地)の可能性が強いことを提唱した。(5)黄河の中下流域の前漢時代の古代稲は、長大粒で日本の現在の栽培稲とは明らかに異なるものであったが、淮河流域の西周時代の焦荘遺跡の炭化米は、九州の弥生中期の筑後川流域のものによく類似した。(6)山東半島の楊家圏遺跡(紀元前2,300年)の焼土中の籾粒は日本の在来の稲品種によく類似したが、遼東半島の大嘴子遺跡の炭化米は短狭粒で、韓国の松菊里遺跡(紀元前500年)、あるいは日本の北部九州の古代稲粒のいずれとも異なるものであった。このことから、稲作が朝鮮半島の北から内陸を南下したとは考えられない。(7)山東半島の楊家圏遺跡、松菊里遺跡(紀元前500年)、および日本の北部九州最古の稲作遺跡・菜畑遺跡のやや小粒の古代稲粒は、浙江省呉興県の銭山漾遺跡の炭化米粒の中に類似するものがかなり見られた。このことは、日本への最初の稲作渡来が江南地方から中国大陸の黄海沿岸に沿って北上し、山東半島から韓国の西海岸を南下しながら北部九州に上陸した可能性を示すものである。森島、湯および王は、雲南省と海南島の野生稲の現地調査を行い、中国の野生稲の実態を明らかにした。佐藤は河姆渡遺跡の古代稲の電子顕微鏡写真撮影によって、同遺跡の稲が野生稲の特徴である芒の突起を有すること、さらに小穂の小枝梗の離層が発達していることを確認した。藤原と湯は、江蘇省青浦県の草鞋山遺跡(紀元前3,400年)周辺を発掘し、当時の水田遺構の確認および稲のプラントオパール分析を行い、当時の稲作の実態を明らかにした。樋口、白木原、高倉、菅谷および寺沢は、それぞれの専門から研究を行い、現在報告書の成作を完了した。厳、蘇、陳、何および劉は、新石器時代の稲作文化および古代民族移動に関する報告書を作成した。
6 0 0 0 OA 韓国インフラ産業の海外市場拡大に向けた取組み
- 著者
- 魏鍾振
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 技術と文化による日本の再生 : インフラ、コンテンツ等の海外展開
- 巻号頁・発行日
- vol.総合調査報告書, 2012-09
6 0 0 0 OA 野菜の加熱にともなうグアニル酸の生成
- 著者
- 堀江 秀樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.5, pp.346-351, 2012 (Released:2014-01-31)
- 参考文献数
- 12
グアニル酸がグルタミン酸の味を強めることはよく知られている。何種類かの野菜(ナス,トマト,ニンジン,ダイコン,ネギ,ホウレンソウ)の蒸し処理によりグアニル酸が生成することを見いだした。ニンジンジュースへのグアニル酸の添加(蒸し野菜に含まれる濃度レベル(10 mg/l))をパネルは官能的に判定できた。蒸し野菜に含まれるグアニル酸はグルタミン酸のうま味を強めることにより,味に寄与することが示唆された。トマトのオーブン加熱は呈味成分を濃縮し,グアニル酸も生成した。焼いたトマトのうま味は,濃度の増加したグルタミン酸とグアニル酸の間の相乗効果のために,生のトマトよりも非常に強いものとなる。グアニル酸含量は調理野菜の味研究における重要な指標となるものと考えられる。
6 0 0 0 OA 『尋常小学算術』の目的にみる1930年代思想統制の影響 「数理思想」に着目して
- 著者
- 桜井 恵子
- 出版者
- 日本数学教育史学会
- 雑誌
- 数学教育史研究 (ISSN:13470221)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.25-33, 2022-10-31 (Released:2023-11-13)
6 0 0 0 OA 日本に広く分布するローム層の特徴とその成因(<特集>堆積物による火山噴火史研究)
- 著者
- 早川 由紀夫
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 火山 (ISSN:04534360)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, pp.177-190, 1995-07-31 (Released:2017-03-20)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 13
Loam is an international scientific term, however, it has been used in a peculiar way in Japan. Japanese loam is a massive, brown, weathered rock unit composed of silt, clay, sand and occasional lapilli. It extensively covers coastal terraces, river terraces, ignimbrite plateaus and other uplands around volcanoes. Loam is not a product of soil forming process operated beneath the earth surface against rock bodies ; but it is a sediment accumulated slowly on the earth surface. Small-magnitude volcanic eruptions play a very minor role for the sedimentation. An eolian reworking process of pre-existing fine-grained deposits by the wind plays a major role. This is proved by following facts : 1) loam has accumulated even during the time when no ash-fall was observed ; 2) a volcano infrequently erupts explosively and the intensity of ash fallout is far lower than the sedimentation rate of loam ; it is about 0.1 mm/year ; 3) loam is hardly thickening toward a volcano. Very small particles carried from continental China by the westerlies at a high altitude are contained in loam, however, in the area around volcanoes their contribution is little for the formation of loam compared with eolian dust carried from nearby bare grounds by local winds at a low altitude. Loam does not accumulate all the year round. Just before and during fresh verdure, occasional strong winds pick up fine particles into the air from a bare ground which is dried up by a high-angle sunlight and high-temperatures. Eventually fine particles will settle down in vegetation. The most favorable season for loam deposition is April to May, in which more than half of an annual amount is achieved. It is convenient and practical to define a single eruption by a tephra layer which is not interbedded with loam. The thickness of loam can be used for the quantitative measurement of geologic time intervals, in years to thousands years, on certain conditions. Lithology of Japanese loam and the mechanism of sedimentation are identical to those of loess in other areas, such as China, northern Europe, northern America and New Zealand. There is no reason to hesitate to designate Japanese loam loess.