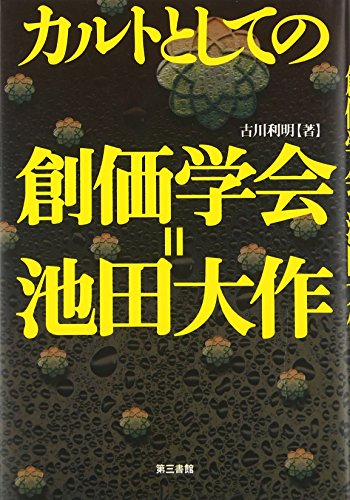6 0 0 0 OA 一般消費者を対象としたOTC点眼薬の適正使用に関する知識および理解度に関する調査
- 著者
- 秋山 滋男 土井 信幸 田沼 和紀 堀 祐輔 宮本 悦子
- 出版者
- 日本アプライド・セラピューティクス(実践薬物治療)学会
- 雑誌
- アプライド・セラピューティクス (ISSN:18844278)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.103-118, 2022 (Released:2022-09-15)
- 参考文献数
- 22
一般消費者は疲れ目、アレルギー症状などの軽度な眼疾患の予防や治療を目的にOTC点眼薬を使用している。しかし、点眼薬は無菌製剤であることから不適切な使用による汚染などが原因となりトラブルが発生することが予測される。そのため、薬剤師・登録販売者はOTC点眼薬の購入者に対して適正使用に関する情報提供を行わなければならない。 本研究では、OTC点眼薬の購入経験・使用歴のある一般消費者(以下、購入経験者)を対象として、OTC点眼薬の購入方法とその選択基準や理由、OTC点眼薬の適正使用に関する知識および理解度についてのアンケート調査を実施した。 薬剤師・登録販売者から購入経験者への商品に関する説明状況について尋ねた結果、「特に説明はなかった」が70.7%と最も高い割合であった。OTC点眼薬の開封後に添付の説明書(以下、添付文書)を読むかの設問では、「添付文書を読む」と回答した割合は52.9%(254/480)であった。同様に、購入経験者の適正使用のための主体的な行動指標項目と考えられる「使用時に添付文書を読んでいる」、「薬剤師・登録販売者へコンタクトレンズの使用状況を伝える」、「お薬手帳を提示している」などの項目について実施している割合は低かった。薬剤師・登録販売者からの一般消費者に対するOTC点眼薬販売時に使用目的や患者背景の確認が行われておらず、適正使用に関する指導も不十分である可能性が高く、OTC点眼薬購入者は相互作用、有害事象、副作用などを誘発しやすい状況にあると考えられた。
6 0 0 0 OA 副作用評価におけるシグナル検出
- 著者
- 藤田 利治
- 出版者
- 一般社団法人 日本薬剤疫学会
- 雑誌
- 薬剤疫学 (ISSN:13420445)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.27-36, 2009 (Released:2009-09-30)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 53 47
During the post-approval period, hypotheses about potentially new adverse drug reactions (ADR) have traditionally emerged from passive surveillance systems that collect large volumes of spontaneous case reports of suspected adverse drug reactions. With signal detection by traditional (or conventional, or manual) methods, quantitative (or statistical, or automated) methods for spontaneous reporting system (SRS) databases were introduced in the late 1990’s in order to detect serious ADR as early as possible. Most quantitative methods rely on comparisons of relative reporting frequencies, also known as disproportionality analyses. In FY 2009, the Pharmaceuticals and Medical Device Agency (PMDA) plans to introduce the quantitative methods (data mining method) used on Japanese SRS database. This paper introduces the recent situation on signal detection and signal management of adverse drug reactions.
6 0 0 0 OA 軍事・社会・政治への革命的影響に関する人造硝石の史的研究
- 著者
- 戸田 善規
- 出版者
- 日本社会臨床学会
- 雑誌
- 社会臨床雑誌 (ISSN:21850739)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.49-69, 2020 (Released:2021-11-10)
6 0 0 0 OA 歯周組織の炎症に対するクルクミンの効果
- 著者
- 秋月 達也 三辺 正人
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯周病学会
- 雑誌
- 日本歯周病学会会誌 (ISSN:03850110)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.70-75, 2015-06-28 (Released:2015-07-06)
- 参考文献数
- 32
6 0 0 0 OA 8. 脊髄小脳変性症
- 著者
- 武市 紀人
- 出版者
- 一般社団法人 日本めまい平衡医学会
- 雑誌
- Equilibrium Research (ISSN:03855716)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.4, pp.239-246, 2023-08-31 (Released:2023-10-03)
- 参考文献数
- 23
Spinocerebellar degeneration (SCD) is a group of neurodegenerative disorders characterized by progressive cerebellar ataxia with or without symptoms/signs of pyramidal, extrapyramidal, or peripheral nerve involvement. Patients frequently exhibit unsteadiness of gait associated with nystagmus, which could also be observed in patients with peripheral vestibular impairment. Thus, some of these patients often initially seek consultation with an otolaryngologist. To distinguish SCD from other peripheral vestibular disorders, it is necessary for otolaryngologists to understand the characteristics of SCD. Brainstem and cerebellar lesions affect physiological eye movements, so that the patients often present with various eye movement abnormalities. Slow saccades, saccade dysmetria, down-beat nystagmus, and impairment of smooth pursuit are some of the typically observed abnormalities. Reduced bilateral VOR has been observed in MJD/SCA3 patients, especially developed more those with a disease duration of longer than six years. SCA6 patients, considered as showing pure cerebellar ataxia, show dissociation between control of gaze tracking during smooth pursuit and VOR cancellation. This result indicates that the cerebellar Purkinje cells are not involved in the non-pursuit VOR cancellation system. Therefore, it is important for otorhinolaryngologists to be alert to typical eye movement impairments.
6 0 0 0 OA アリのケミカルコミュケーション
- 著者
- 勝又 綾子 尾崎 まみこ
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.3-17, 2007 (Released:2007-10-02)
- 参考文献数
- 77
私達が野外や屋内で何気なく見かけるアリは,分布域の広さとバイオマスの大きさによって,生態系において圧倒的な優位性を示す。高度に組織化されたアリの社会は,それぞれの種が進化過程で培った高度なケミカルコミュニケーションの多様性,すなわちコロニーメンバーが分業し活動を協調させるための,通信コードとしての情報化学物質の豊富さに支えられている。 それではアリ達は具体的に,どのような情報化学物質を,どのように処理して,統制のとれた複雑な行動を示すのだろうか? 本稿では,アリの社会における代表的なケミカルコミュニケーションを紹介し,そこで用いられる重要なフェロモン,化学受容器,一次感覚中枢(触角葉など),高次中枢における情報処理系の最近の研究について触れる。
- 著者
- 三上 純
- 出版者
- 日本スポーツ社会学会
- 雑誌
- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.59-75, 2023 (Released:2023-10-26)
- 参考文献数
- 21
本稿の目的は、固定的なジェンダー観の形成に寄与する運動部活動文化に着目し、それが体育教師志望といかに結びついているのかを、統計分析によって明らかにすることである。先行研究の概観から以下の3つの仮説を設定し、その検証を分析課題とする。①体育教師志望に与える様々な運動部活動経験の影響は、運動部顧問志望に媒介されて生じる。②運動部活動を通じた男性体育教師との結びつきが、体育教師志望に影響する。③運動部活動における性に関わる指導者の言動や仲間同士のコミュニケーションが、体育教師志望に影響する。 本稿では、日本の中学校・高校に通っていた大学生・大学院生を対象に、2021年2~3月(以下、1期調査とする)および同年4~7月(以下、2期調査とする)に実施したオンラインのアンケート調査によって得られたデータを使用する。1期調査では、筆者の知人や大学に勤務する教員を通じてEメールまたはLINEで、約1600人に回答リンクを配布し397人から回答を得た。2期調査では、大学に勤務する教員が受け持つ授業を通じて約3000人に回答リンクを配布し、755人から回答を得た。本稿では2つのデータを統合して使用する。 体育教師志望を従属変数とするロジスティック回帰分析と、運動部顧問志望を媒介変数とするKHB法による媒介分析の結果、仮説①および仮説②は支持されたものの、仮説③は支持されなかった。しかし、体育教師志望を強く規定する運動部顧問志望を従属変数として多項ロジスティック回帰分析を行った結果、運動部活動における性に関わる指導者の言動や仲間同士のコミュニケーションは運動部顧問志望の規定要因となることが示された。このことから、固定的なジェンダー観の形成に寄与する運動部活動での指導者や仲間との関係性が、運動部顧問志望を経由して体育教師のジェンダー観に影響すると考えられた。
- 著者
- 片岡 樹
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第52回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.23, 2018 (Released:2018-05-22)
近代以降の神仏分離、神社合祀、政教分離といった一連の政策が、我が国の宗教的景観を一変させてきたという認識は大筋では正しいとしても、一部に過大評価を含んでいるのではないか。本報告では、愛媛県今治市菊間町の神社・仏堂の現状に関する悉皆調査の結果から、そうした国家主導の宗教再編をかいくぐるうえで未公認の小社や小堂が果たしてきた役割について再検討する。
6 0 0 0 OA 「ホーム」の地理学をめぐる最近の展開とその可能性―文化地理学の視点から―
- 著者
- 福田 珠己
- 出版者
- 一般社団法人 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.5, pp.403-422, 2008 (Released:2018-01-06)
- 参考文献数
- 120
- 被引用文献数
- 5 7
In the last decade, geographers, especially cultural geographers, have conducted a considerable number of studies on home and domestic space. The topic of home, which was considered to be familiar and banal and had been neglected in the discipline of geography, has now been given renewed focus from various perspectives. This paper aims to review the current studies of geographies of home by considering some theories in cultural geography. Subsequently, it aims to explore the possible ways of developing critical studies of geographies of home in Japanese contemporary society.The trend toward geographies of home is examined from the following three viewpoints: The first is in moving beyond the separation of public and private spheres. Although humanistic geographers emphasized emotions and subjective meanings in their anthropocentric thought, feminist geographers have made great contributions towards conquering dualistic thinking. They have considered the idea of home as political, ambiguous, fluid, and multiscale. The second viewpoint is the oscillating consideration between mobility and stability, which stems from postcolonial studies. This involves focusing on the politics of belonging and alienation, that is, roots and routes, spatial politics and gendered geographies, and collective memory and its materialization. The third viewpoint is non-representational theory in the discipline. This theory includes a variety of ideas―materiality, performativity, post-human, affect, hybridity, etc. It can be said that parts of current research are going beyond the interpretation of representation and focusing on the ‘here and now.’ From the viewpoint of geographies of home, materiality and perfomativity are rather important for both theoretical development and social practice.How are the recent studies on geographies of home influencing Japanese academia ? It is very important to directly face the current conditions of Japanese homes. These conditions in Japanese society can be considered as a ‘cult of domesticity.’ Home plays a critical role both in policymaking and in space consumption. The fixed idea of home is definitely not adequate in deepening our consideration of home and geography. At present, it is important for us to develop critical thinking of home at the points of intersection between the material and immaterial, public and private, and mobility and stability.
6 0 0 0 OA 免疫抑制薬内服下での弱毒生ワクチン
- 著者
- 亀井 宏一
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児腎臓病学会
- 雑誌
- 日本小児腎臓病学会雑誌 (ISSN:09152245)
- 巻号頁・発行日
- pp.rv.2021.0003, (Released:2021-10-22)
- 参考文献数
- 29
免疫抑制薬内服中は,国内外の添付文書やガイドラインでは生ワクチンは併用禁忌とされている.一方で,免疫抑制薬内服中は感染症が重症化するリスクが高い.免疫抑制薬内服下での生ワクチン接種はこれまで 21 報告あり計 400 名に 816 回接種されており,致命的な合併症の報告はない.当センターでは,一定の免疫学的条件(CD4 細胞数≥500/mm3,PHA リンパ球幼若化反応のstimulation index≥101.6,血清 IgG≥300 mg/dL) を満たす場合,免疫抑制薬内服下での生ワクチン接種を施行してきた.抗体獲得率は麻疹 80.0~95.7%,風疹 100.0%,水痘 59.1~61.9%,ムンプス 40.0~69.2%で,ワクチン株ウイルス感染症は 1 名のみ(水痘ワクチン,免疫基準設定前の症例)であった.また,全国多施設研究でも約 2/3 の専門医が免疫抑制薬内服下での生ワクチン接種を必要と感じており,781 名の接種者中ワクチン株ウイルス感染症を発症したのは 2 名のみであった.免疫抑制薬下でも弱毒生ワクチンは有効で安全である可能性が高い.今後は,添付文書やガイドラインの文言の修正などを行っていくことが必要である.
6 0 0 0 OA Active control of Lubricant Flow Using Dielectrophoresis and Its Effect on Friction Reduction
- 著者
- Motoyuki Murashima Kazuma Aono Noritsugu Umehara Takayuki Tokoroyama Woo-Young Lee
- 出版者
- Japanese Society of Tribologists
- 雑誌
- Tribology Online (ISSN:18812198)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.6, pp.292-301, 2023-10-31 (Released:2023-10-31)
- 参考文献数
- 61
- 被引用文献数
- 1
With the increasing demand for active friction control, we newly proposed to use dielectrophoresis to change the flow of PG-droplet-containing PAO4 to reduce the friction coefficient. The friction result with a 1-mm roller shows 20% reduction in friction coefficient (from 0.065 to 0.052) at AC 100 V, and in situ observation exhibits that PG tracks are formed over the contact area. On the other hand, at a high bias of 1000 V, the friction coefficient increases to 0.065. In this situation, in situ observation exhibits that PG forms a horseshoe-shaped track covering only the roller edges. Controlled friction tests and FEM analysis using 5-mm rollers revealed a unique behavior; a balanced bias effectively attracts the PG to the roller surface, and surface forces can resist mild dielectrophoretic forces to spread the PG across the roller surface. The present study strongly suggests the importance that the bias strength should be controlled to achieve a balance between surface force and dielectrophoretic force in order to obtain excellent lubrication conditions.
6 0 0 0 OA 金属曝露と神経発達症
- 著者
- 塚原 照臣
- 出版者
- 信州医学会
- 雑誌
- 信州医学雑誌 (ISSN:00373826)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.157-159, 2018-04-10 (Released:2018-06-13)
- 参考文献数
- 5
6 0 0 0 OA 井上寿一著『危機のなかの協調外交-日中戦争に至る対外政策の形成と展開』
- 著者
- 臼井 勝美
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.1995, no.109, pp.197-200, 1995-05-20 (Released:2010-09-01)
6 0 0 0 OA リン酸塩処理の基礎
- 著者
- 石井 均
- 出版者
- 一般社団法人 表面技術協会
- 雑誌
- 表面技術 (ISSN:09151869)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.216-216, 2010-03-01 (Released:2010-09-28)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 1 2
6 0 0 0 カルトとしての創価学会=池田大作
6 0 0 0 【コラム】PPI と低マグネシウム血症
- 著者
- 坂口 悠介
- 出版者
- 日本メディカルセンター
- 雑誌
- 臨牀透析 (ISSN:09105808)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.209-210, 2019-02-10
2011 年,米国Food and Drug Administration(FDA)はプロトンポンプ阻害薬(PPI)の長期使用(多くは1 年以上)時にまれに発生する重度の低マグネシウム(Mg)血症に関して注意喚起を行った.とくに基礎疾患のないPPI 内服者が低Mg血症からtorsades de pointes をきたしたというケースも報告されており,PPI 長期投与例では定期的な血清Mg 濃度のモニタリングが望ましい.PPI による低Mg血症はこの薬剤のclass effect であり,いずれのPPI でも発生しうる.低Mg 血症を生じる機序として腸管でのMg 吸収障害説が有力視されており,経口Mg 補充のみでは血中Mg 濃度は十分に上昇しないが,原因薬剤の中止によって数日以内に軽快することが多い.腸管でのMg 吸収を司る主たるトランスポーターであるtransientreceptor potential melastatin type 6(TRPM6)の活性は腸管内局所のpH に依存しており,PPI 使用による腸管内pH の上昇がTRPM6 を介したMg 吸収を減弱させると考えられている.なお,ヒスタミンH2 受容体拮抗薬による低Mg 血症の報告はない.PPI を長期投与されている133 例を対象としたオランダの研究では,TRPM6 の一塩基多型(rs3750425,rs2274924)をもつ集団で低Mg 血症のオッズ比が5 倍以上上昇しており,PPI によるこの副作用の発現に遺伝的背景が一部関与している可能性が示唆される.
6 0 0 0 OA 外耳道癌と耳かき頻度の相関性の検討
- 著者
- 石浦 良平 飯田 拓也 柿木 章伸 安藤 瑞生 吉田 昌史 齊藤 祐毅 山岨 達也 光嶋 勲
- 出版者
- 日本頭頸部癌学会
- 雑誌
- 頭頸部癌 (ISSN:13495747)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.76-78, 2017-04-25 (Released:2017-06-16)
- 参考文献数
- 7
外耳道癌は稀かつ予後不良な疾患である。その危険因子として過剰な耳かきが臨床上推測されているが,統計学的に検討した報告は少ない。今回,我々は当科で加療を行った外耳道癌患者14例を対象とし年齢,性別,耳かき頻度,耳かきに使用する道具の材質,罹患側,病理組織について検討した。また,本研究に同意を得た健常人69名を対象とし,年齢,性別,耳かき頻度,耳かきに使用する道具の材質について調査し患者群と比較検討した。その結果,50歳未満の若年群における患者群と健常人群間において,有意に耳かき頻度,および硬質素材を用いる率が高かった。今回の結果から,過剰な刺激の耳かきが外耳道癌発生を誘発する可能性が示唆された。
6 0 0 0 OA ケニア・カンバにおけるキジーツ
- 著者
- 上田 将
- 出版者
- Japan Association for African Studies
- 雑誌
- アフリカ研究 (ISSN:00654140)
- 巻号頁・発行日
- vol.1977, no.16, pp.23-35, 1977-03-30 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 14
In this paper I consider kithitu (pl. ithitu) among the Kamba, a ‘Bantu speaking’ people in Central Kenya. Kithitu is a kind of magical medicine (muthea) in a broad sense. Its form is a medicine container, such as an animal's horn or a human tibia, in which magical medicine is packed. Medicine is mainly made from plants, but it is very difficult to know the constituents of medicine because secrecy about the ingredients is strictly kept.There are many kinds and many uses of ithitu among the Kamba, but in this paper I examine Kilonzo's kithitu which is very well-known in the northern part of Kitui District. There are many oral traditions and much gossip about the kithitu in which its potency and the people's fear of it are always expressed.Here I consider how the Kamba explain the various qualities and power of the kithitu, including:1. The owner must keep his kithitu in the bush (kitheka) far away from his homestead (musyi). If he puts it in his homestead, the people of his homestead will die because of the strong effective power of the kithitu.2. After using the kithitu, the owner and the persons concerned must not leave it without wiping off their eyes, hands and the soles of their feet with a mixture of juice from some plants and the soil of an ant hill, or with mwoyo (the undigested contents of a goat's stomach), because they have to cleanse the destructive power of the kithitu before coming back to their homes.3. The kithitu sometimes comes near to the owner's homestead from the bush and cries like a man asking a goat's blood to drink. On such occasions, the owner must kill a goat and take the blood to the kithitu immediately. It is said that if he neglects this, all the members of his homestead will die.4. The owner of strong kithitu can not have his real sons. It is believed that his real sons die young one after another because he always uses the kithitu.5. The kithitu is used in oaths as kuya kithitu (to eat kithitu). It has the power to judge the truth. The accuser and the accused go to the bush and each of them swears over the kithitu, saying that if he tells a lie the kithitu may kill him. But people don't swear over the kithitu directly without kusuna kavyu (to lick a hot knife), ordeal as the first step, because the kithitu is so dangerous that a liar is killed with it. Swearing over the kithitu is connected with law, morals, values, legal procedure, clan conferences (mbai), political power and so on.The kithitu is used as uoi (magical power to knock down an enemy or a rival). When some person encounters serious difficulties brought by his enemy, he visits and asks the owner of the kithitu to kill his enemy. The owner chants a spell against the enemy, striking the kithitu with a twig.The Kamba categorize uoi into two parts: Uoi wa mundu ume (uoi of man) and uoi wa mundu muka (uoi of woman). The kithitu belongs to the category of uoi of man. It has the characteristics shown below:(1) A person who wants to use the kithitu must pay money to the owner. It costs about three hundreds shillings (equivalent to about fifteen thousands yen). Kuthooa kithitu (to buy kithitu) means to use kithitu as uoi.(2) Women and children cannot approach and use the kithitu because administering it is always attended by some danger and secrecy. Only the male adults can use it.(3) It is forbidden to use the kithitu without socially justified reasons. To use kithitu is basically permitted by the society, but only if people follow the prescribed pattern of usage. The kithitu as uoi is deeply related to the kamba magico-religious beliefs a