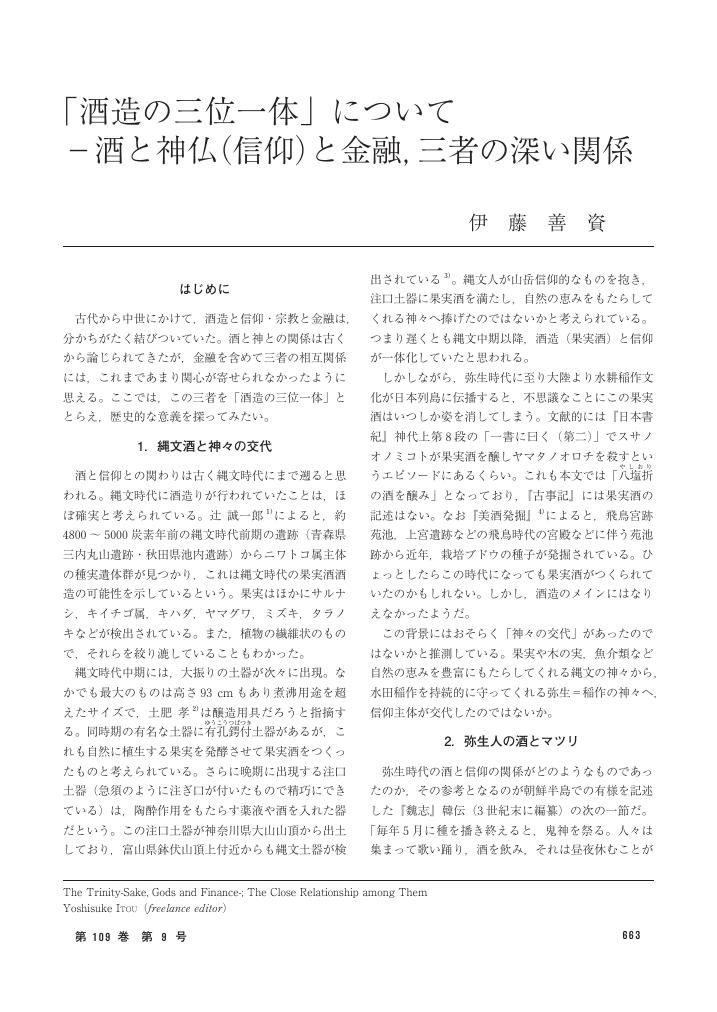6 0 0 0 OA DNA付加体の網羅的分析を目指したHILIC分離条件の検討
- 著者
- 岩政 衣美 三木 雄太 井上 嘉則 江坂 幸宏 村上 博哉 手嶋 紀雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本分析化学会
- 雑誌
- 分析化学 (ISSN:05251931)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.8, pp.479-484, 2018-08-05 (Released:2018-09-08)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 3 3
The concept of comprehensive DNA adducts analysis (called DNA adductomics) has recently been attracting attention, and the development of a highly sensitive and accurate quantitative method for DNA adductomics has been desired. In our previous research on LC-ESI-MS/MS, hydrophilic interaction chromatography (HILIC) was found to be effective for improving the sensitivity concerning the quantitation of DNA adducts. Although HILIC-ESI-MS/MS is useful for the quantitation of DNA adducts, the improvement of HILIC separation for DNA adductomics must be still needed. In this paper, we describe the improvement of HILIC separations for DNA adductomics by investigating the composition of mobile phases and the commercially available HILIC columns with four difference polar groups. While the elution order for four 2'-deoxynucleosides and the two DNA adducts was not drastically changed by varying the HILIC columns, the separation of each dN and DNA adducts was improved by adding alcohols and by varying the alcoholic concentration.
6 0 0 0 アクティブサーチ
日本における科学技術分野の女性比率は他国と比べても極端に低い。日本社会に根付くジェンダーステレオタイプが女子の趣向から進学・キャリアの選択に至るまで影響を与えているようだ。よって、Tik TokやYouTube教育プラットフォームで、反ステレオタイプ的女性ロールモデルとの対談やストーリーを定期的に発信し、10代から親世代までのジェンダーステレオタイプに対する意識の変化を促し、その変化の継続性と10-20代女子の理系進学率を含めた追跡調査のためのプラットフォームを構築することを目指す。本研究は、理系分野に限らず全ての女性がステレオタイプから解放される、女性エンパワーメントの取り組みに貢献すると考える。
6 0 0 0 OA アルコール性肝障害機序の最先端
- 著者
- 池嶋 健一
- 出版者
- 一般社団法人 日本肝臓学会
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.7, pp.342-350, 2018-07-20 (Released:2018-07-27)
- 参考文献数
- 48
アルコール性肝障害はその初期像としての脂肪肝からアルコール性肝炎を繰り返して肝硬変へと進行するが,近年増加傾向が注目されている非ウイルス性肝硬変の成因の約半数を占めており,非ウイルス性肝癌の発生母地としても重要である.アルコール代謝酵素の遺伝子多型は飲酒習慣や依存形成に関与する一方,patatin-like phospholipase encoding 3(PNPLA3)などの遺伝子多型が脂肪肝形成から肝病態の進展に関わるリスク因子であることが明らかになっている.アルコール性肝障害の発症・進展には,アルコール代謝過程で生じる活性酸素種(ROS)などによる細胞障害に加えて,腸内細菌叢の変化(dysbiosis)とそれに対する自然免疫系の反応が主軸的な役割を演じていることが明らかにされつつある.
6 0 0 0 OA 陸上養殖された無毒化トラフグの肝臓の食味特性
- 著者
- 西念 幸江 小澤 啓子 生方 恵梨子 峯木 真知子 野口 玉雄
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成21年度日本調理科学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.2048, 2009 (Released:2009-08-28)
【目的】無毒化されたトラフグの肝臓(フグ肝)について,食料資源としての可能性および価値を検討してきた.ゆでたフグ肝を用いた官能検査では,その色,匂い,脂っぽさの点から,高い評価は得られなかった.そこで,料理を調製して,官能評価および組織観察より食味特性を調べた. 【方法】フグ肝は,佐賀県唐津市呼子にある(株)萬坊で室内水槽(100t)により,養殖されているトラフグ2年魚から腑分けされたものを試料とした(2009年1月).このフグ肝は食品衛生検査指針・理化学編中のフグ毒検査法に準じて,フグ毒を抽出し,マウス毒性試験を行い,毒性がすべて認められなかったことを確認した.その後,-50℃で冷凍保存し、使用時に流水で解凍し,血抜後,酒水,長葱および生姜の中に浸漬した(5℃、3時間)後、6種の調理法による料理を調製した(刺身、味噌汁、蒸し物、西京焼き、照り焼き、天ぷら). フグ肝の調理による重量変化を求めた。フグ肝の下処理については,円卓法による官能評価で検討した.各料理は,5段階評点識別試験と嗜好試験(1-5点)を行った.調理されたフグ肝の試料は卓上型電子顕微鏡(TM-1000,(株)日立ハイテクノロジーズ)で観察した. 【結果】重量減少率は、味噌汁および蒸し物で大きかった。フグ肝料理の分析型官能評価では, 匂いの強さが平均2.5点でやや弱く,香りのよさは平均3.8点でややよく、油っぽさについては,2.5-4.0点の範囲であった。嗜好型官能評価では,いずれの料理も,「料理としての好ましさ」の評点が3.5以上で高かった.組織観察では、調理法による脂肪の違いが観察された。
6 0 0 0 OA 慢性疼痛の病態形成における不動の影響 ―筋萎縮,筋性拘縮,筋痛のメカニズムも踏まえて―
- 著者
- 沖田 実 本田 祐一郎 田中 なつみ 坂本 淳哉
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.11, pp.1221-1228, 2021-11-18 (Released:2022-01-14)
- 参考文献数
- 11
運動器の外傷や外科術後などに生じる痛みが顕著な場合や持続して認められる場合は,患部やその周囲は運動を回避し,不動状態となる.また,傷害部位の治癒促進を目的に行われるキャスト固定などは不動状態を強いることになる.すると,運動器,中でも可塑性に富んだ骨格筋は筋萎縮や筋性拘縮,筋痛など,重複化,重篤化した病態を呈し,これらは慢性疼痛の病態形成にも影響を及ぼす.加えて,不動そのものが痛みの増悪や新たな痛みの発生といった慢性疼痛の病態形成に直接的に影響することも最近明らかになっている.そこで本稿では,筋萎縮,筋性拘縮,筋痛のメカニズムも踏まえ,慢性疼痛の病態形成における不動の影響を概説した.
6 0 0 0 OA 横浜市で捕獲されたアライグマの食性分析例
- 著者
- 高槻 成紀 久保薗 昌彦 南 正人
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.87-93, 2014-05-30 (Released:2017-08-01)
- 被引用文献数
- 3
北アメリカからの外来哺乳類であるアライグマは1960年代に日本で逸出し、1980年代以降各地に生息するようになった。アライグマは水生動物群集に影響を及ぼすといわれるが、食性情報は限定的である。原産地では、水生動物も採食するが、哺乳類、穀類、果実なども採食する広食性であることが知られている。横浜市で捕獲された113のアライグマの腸内容物を分析した結果、果実・種子が約半量から50〜75%を占めて最も重要であり、次いで哺乳類(体毛)が10〜15%、植物の葉が5〜20%、昆虫が2〜10%で、そのほかの成分は少なかった。水生動物と同定されるものはごく少なく、魚類が春に頻度3.0%、占有率0.2%、甲殻類が春に頻度3.0%、占有率0.1%、貝類(軟体動物)が夏に頻度3.4%、占有率<0.1%といずれもごく小さい値であった。腸内容物は消化をうけた食物の残滓であることを考慮しても、水生動物が主要な食物であるとは考えにくい。アライグマが水生動物をよく採食し、水生動物群集に強い影響を与えているかどうかは実証的に検討される必要がある。
6 0 0 0 OA 日本原子力学会誌
- 著者
- 清水 誠
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌 (ISSN:00047120)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.94-102, 1981-02-28 (Released:2010-03-08)
- 参考文献数
- 13
6 0 0 0 未来を想像して,動機づけを高める
6 0 0 0 OA 「酒造の三位一体」について
- 著者
- 伊藤 善資
- 出版者
- Brewing Society of Japan
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, no.9, pp.663-674, 2014 (Released:2018-04-06)
- 参考文献数
- 54
6 0 0 0 OA 日本語のかき混ぜ文の主要部前と主要部駆動処理に関する視線計測研究
- 著者
- 玉岡 賀津雄 Michael P. Mansbridge
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.155, pp.35-63, 2019 (Released:2019-10-02)
- 参考文献数
- 47
動詞を読む前の予測処理がかき混ぜ文の処理に影響すると報告されている。しかし,これらの研究は,文の同じ位置で名詞を比較しておらず,名詞の種類も異なっていた。そこで,高使用頻度の人名を文の同じ位置に配置して,他動詞の単文とそれらを埋め込んだ複文の2つの実験で,短距離・長距離のかき混ぜを句ごとに視線計測した。NP-ACC(ヲ)とNP-NOM(ガ)が連続して現れる場合は,2つ目の名詞句のNP-NOM(ガ)の部分で,両実験のかき混ぜ文の通過時間が有意に長くなった。これは,埋語補充解析が始まることを示唆している。しかし,その後,動詞を読んでからの再読時間と読み戻り頻度が,埋語が想定される付近の名詞句を中心に観察された。意味的な手掛かりが欠如する場合には,動詞の情報に準拠した主要部駆動処理に強く依存することが示された。手掛かりの有無によって,主要部前処理か主要部駆動処理かの依存の度合いが異なってくると考えられる。
6 0 0 0 OA ブラックバス問題の現状について考える
- 著者
- 濁川孝志
- 出版者
- 立教大学
- 雑誌
- 立教大学コミュニティ福祉学部紀要
- 巻号頁・発行日
- no.3, 2001-03-31
6 0 0 0 OA 子どもの傷害を予防する
- 著者
- 山中 龍宏
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.4, pp.228-235, 2015-08-15 (Released:2016-07-30)
- 参考文献数
- 9
事故による子どもの傷害は多発しており,重要な健康問題となっている.子どもが事故に遭遇しやすい理由は「発達」するからである.昨日まで寝返りできなかった子どもが,今日,寝返りをしてベッドから落ちてしまう.子どもの事故は,何歳になったら,どんな事故が起こるかはわかっており,多くの場合,どうしたら予防できるかもわかっている.傷害予防に取り組む場合は,重症度や発生頻度が高く,増加している事故について優先的に取り組む必要がある.予防するためには,傷害が発生した状況や製品・環境の詳しい情報が不可欠であり,また,いろいろな職種の専門家が連携する必要がある.傷害が起こった時の情報を,「変えたいもの」「変えられないもの」「変えられるもの」の3 つに分け,「変えられるものを見つけ,変えられるものを変える」ことが予防なのである.
6 0 0 0 OA うわさ否定行動の意図せざる結果
- 著者
- 籠谷 和弘
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.4, pp.584-599, 1999-03-30 (Released:2010-11-19)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1 1
うわさに対する否定行動は, 多くの場合望ましい成果をもたらさない。逆に否定そのものが原因で, 陰謀論との結びつきなど, うわさの背後にある「物語」の強化が起こることがある。本研究ではこの問題に取り組むために, 「不完備情報ゲーム」を用いた数理モデル分析を行う。まずうわさの伝播に影響を与える要素について検討し, 三要因 (不確実性, 心理的緊張, うわさへの信用度) を取り出す。次に伝播行動に対するうわさを信じる者の利得について, その二側面, 「選好」と「大きさ」を考え, その意味を考察する。そしてこれら三要因と利得の二側面とを考慮に入れた数理モデルを構築し, 分析を行う。その結果, うわさの否定が功を奏するための, いくつかの条件が導出される。ほとんどは自明なものであるが, 一つの興味深い条件が存在することが明らかになった。これはうわさを信じる者にとっての, ゲームの価値に関するものである。その内容は, うわさが虚偽である (否定が正しい) ときに, うわさを伝えることから被るリスクが大きい, というものである。これに対し, うわさが本当であるときに問題の重要性が高い場合, 人々はうわさを伝え続ける。これはうわさが, 陰謀論と結びつきやすいことを説明するものである。
6 0 0 0 OA 官房-原局関係からみた文部省の政策立案過程の分析(III 研究報告)
- 著者
- 青木 栄一 荻原 克男
- 出版者
- 日本教育行政学会
- 雑誌
- 日本教育行政学会年報 (ISSN:09198393)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.80-92, 2004-10-08 (Released:2018-01-09)
Although several attempts were made to change educational policy in the 1970s and 1980s in Japan, substantial changes were not realized until the second half of the 1990s. Why did the change occur only in the late 1990s? One explanation has been that the Ministry of Education was forced to change its former policy because of external pressures brought by ad hoc committees and councils set up in the cabinet during the 1990s. This argument appears to exaggerate the strong tendency of the Ministry as a whole to preserve the status quo and often ignores internal processes that enable changes in attitudes within the Ministry. This paper attempts to explore such internal factors in terms of the power relationship between various bureaus in the Ministry. The paper focuses on the relation between the Minister's Secretariat ('kanbou') and other bureaus ('genkyoku') such as the Elementary and Secondary Education Bureau. These two types of bureaus entail a difference in responding to the demands for change. In contrast to the other bureaus that are responsible for the implementation of specific policy, the main role of the Minister's Secretariat (MS) is to exercise a comprehensive coordinating function over all bureaus ('kanboukinou') ; and thus, the MS is more flexible when it comes to policy change than are other bureaus. We hypothesized that the MS's coordinating function was strengthened during the 1990s and that this allowed the Ministry to change its overall behavior. To examine this hypothesis, we analyzed the status of the MS within the Ministry concerning three points: (1) changes in the organizational structure of the MS; (2) the career pattern of the Director-General, or the chief, of the MS; and (3) the frequency of contacts between the Director-General of the MS and the Prime Minister. Results of our research found that, first, the sections responsible for investigation, statistics, and policy planning within the Ministry were integrated into the MS by the 1970s; in the 1980s, a Senior Deputy Director-General was newly established in the MS; and the Deputy Director-Generals of the other bureaus were transferred to the MS. These reorganizations reinforced the structure of the MS. Second, through analyzing the career pattern of the people who were appointed as Director-Generals of the MS, the paper demonstrates that, though being equal in rank to other bureau chiefs, the position grew important during the late 1990s in terms of the status which it has related to its influence on the ministry's behavior. Third, whereas there was hardly any contact between the Director-General of the MS and the Prime Minister in the 1980s, such contact sharply increased in the late 1990s. These analyses revealed that whereas the structure of the MS was empowered during the 1980s, the position of the MS's Director-General remained unimportant within the Ministry. It was in the late 1990s that the MS properly performed its coordinating function attaining its high status among the bureaus as well as relying on its reinforced structure. This empowerment of the MS's function then enabled the Ministry to change its policy during the same period.
6 0 0 0 OA 薬剤性L‐カルニチン欠乏症と治療
- 著者
- 伊藤 哲哉 中島 葉子
- 出版者
- 日本外科代謝栄養学会
- 雑誌
- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.57-61, 2020 (Released:2020-05-15)
- 参考文献数
- 4
薬剤性L‐カルニチン欠乏症は医原性に生じる二次性L‐カルニチン欠乏症の一種である. 原因となる薬剤としては, 抗てんかん薬, 抗菌薬, 抗がん剤, 局所麻酔剤, イオンチャンネル阻害剤, AIDS治療剤, 安息香酸ナトリウムなどの報告があるが, 長期投与を必要とする抗てんかん薬や, カルニチン欠乏のリスクが高い乳幼児期に投与される薬剤には特に注意が必要である. バルプロ酸ナトリウムの副作用として肝障害や高アンモニア血症が知られているが, これらはカルニチン欠乏やカルニチン代謝の異常が大きく関与すると考えられており, L‐カルニチン投与を行うこともある. また, ピボキシル基含有抗菌薬では腸管からの吸収後に生じるピバリン酸がL‐カルニチンと結合して尿中へ排泄されるためL‐カルニチン欠乏を生じる. 副作用として, L‐カルニチン欠乏からくる低血糖, 意識障害, 痙攣などの重篤な症状が報告されているが, これらの副作用は長期投与ばかりでなく短期間の服用でも認める例があるため, 抗菌薬投与の必要性やその選択について十分吟味したうえで適正に使用することが重要である.
6 0 0 0 OA 皮電計と陰謀
- 著者
- 中谷 義雄
- 出版者
- 日本良導絡自律神経学会
- 雑誌
- 良導絡 (ISSN:09130942)
- 巻号頁・発行日
- vol.1961, no.15, pp.5, 1961-09-15 (Released:2011-10-18)
- 著者
- 野口 康彦
- 出版者
- 法と心理学会
- 雑誌
- 法と心理 (ISSN:13468669)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.8-13, 2013 (Released:2017-06-02)
本稿では、子どもの心理発達のプロセスを踏まえたうえで、親の離婚を経験した子どもの心理について、特に喪失体験とレジリアンスについて言及した。また、親の離婚を経験した大学生を対象として、ベック抑うつ尺度(Beck Depression Inventory)の日本語版を用いた調査を行った。調査の結果から、親の離婚時と子どもの年齢は子どもの精神発達と密接に関連しており、思春期以降に親の離婚を経験した子どもは、親の離婚の影響を受けやすい傾向が示された。親の離婚に起因する子どもの心理的な問題の多くは、親が離婚する前の家庭環境が大きく関与している。親の離婚を経験した子どもが思春期において、親に対する葛藤をどのように体験するのかという点が重要である。
6 0 0 0 OA 中国の日系自動車メーカーにおけるディーラーの 分布と修理・メンテナンス用部品の管理体制
- 著者
- 阿部 康久 林 旭佳 高瀬 雅暁
- 出版者
- The Japan Association of Economic Geography
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.117-132, 2019-03-30 (Released:2020-03-30)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 2
本稿では,広汽トヨタ社を事例として日系自動車メーカーの中国市場におけるディーラーの分布と修理・メンテナンス用部品の管理体制について検討していく.調査手法として,広汽トヨタ社のあるディーラーを通じて,ディーラーの全国的な分布状況と部品物流倉庫の立地状況,修理・メンテナンス用部品のストックの状況や配送システム等についての情報を入手した.調査結果として,同社は全国に437店舗のディーラーを持つが,人口比を考慮すると,店舗の分布が沿海部に偏っており,近年,自動車の需要が高まっている内陸部への進出が遅れている.その一方で,地域別のGDP総額と店舗数の間には高い相関関係があり,同社では比較的経済規模が小さい内陸部の消費者向けに低価格な車種を販売するよりは,経済規模が大きい沿海部の大都市で高価格車を販売することを重視しているといえる.また同社において店舗数の拡大が進まない要因として,同社が重視する十分なアフターサービスを行えるディーラーを確保することが難しい点も挙げられる.同社では,ディーラーには修理・メンテナンス用部品のうち,最低でも1,500点以上をストックさせる方針を採っている.また,メンテナンス用部品を交換する際には,顧客に十分な説明と同意を得ることで顧客満足度を高めることを要請している.そのため,同社のディーラーには長期的な視点で事業を続けられる資金力が必要になるが,このようなディーラーは限られていることや,メーカーとディーラーの間での利益配分も難しい点が指摘できる.