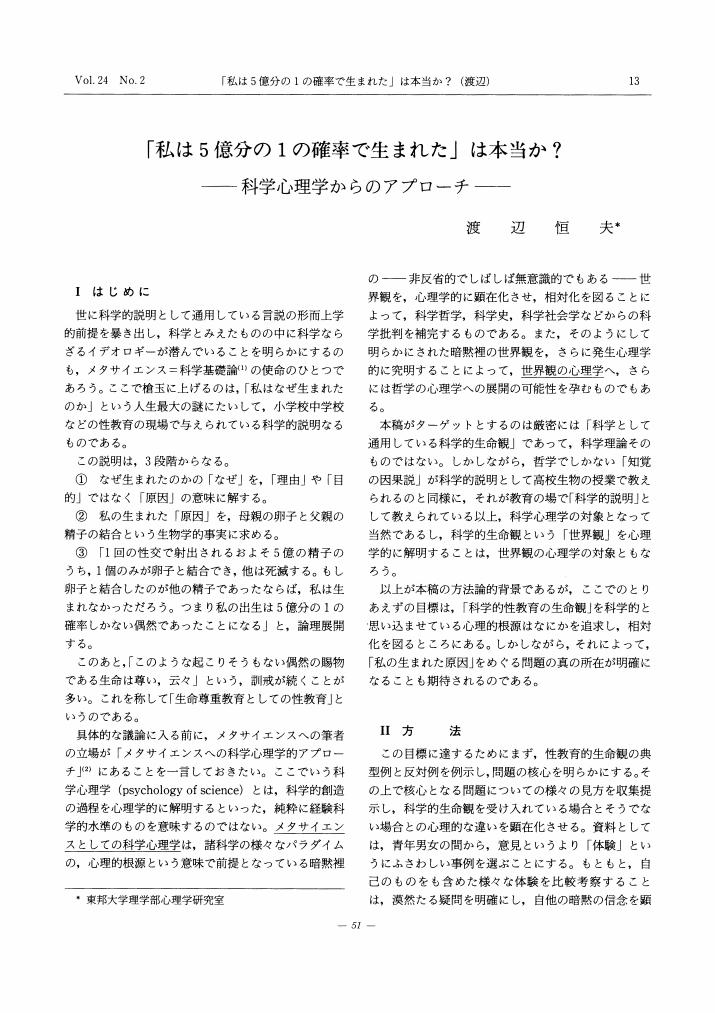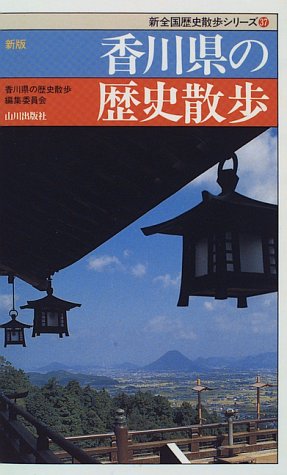6 0 0 0 OA 日本で市販されている食品中のヨウ素含有量
- 著者
- 菊池 有利子 武林 亨 佐々木 敏
- 出版者
- 一般社団法人日本衛生学会
- 雑誌
- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.724-734, 2008 (Released:2008-09-30)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 5 6
Objective: In the present study, we determined iodine concentration in commonly consumed foods in Japan. Methods: One hundred thirty-nine foods and beverages were purchased from local markets and convenience stores. These samples were examined for iodine concentration by using gas chromatography after ashing or extraction. Results: The iodine concentrations in various food groups were as follows, The concentrations in cereals, sugar, sweeteners, vegetables, fruit, milk, and meat were too low to be detected (<0.05 mg/100 g). The iodine concentrations of algae and dashi (Japanese broth or stock) from algae were <0.05–225 mg/100 g; Japanese seasoning, <0.05–10.5 mg/100 g; and iodine-rich eggs, 1.09–2.00 mg/100 g. Conclusions: Food and beverages with high iodine concentrations need to be taken into account in the nutritional survey for health hazards and benefits in the evaluation of daily nutritional intake.
6 0 0 0 OA 複線径路・等至性モデル(TEM)による送球イップス経験者の心理プロセスの検討
- 著者
- 向 晃佑
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学研究 (ISSN:24357065)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.159-170, 2016 (Released:2020-07-10)
- 被引用文献数
- 2
イップスは競技中必要な動作が練習場面においても上手くいかなくなるという点であがりやスランプと異なる特有の状態であり,このことが原因で競技を辞めている選手が多く存在している。本稿ではイップス状態に陥る前からイップス状態から抜け出すまでの過程に着目し,複数の体験を比較し,その心理的プロセスを類型化することを目的とした。野球における送球イップスの経験のある7名の男性の調査協力者を対象に半構造化面接を行い,複線径路・等至性モデル(TEM)を用いて分析を行った。結果として,イップスの症状は「限定的な場面で暴投が続く段階」と「送球全般で暴投が続く段階」の2段階に分けられた。またイップス経験者は「暴投の原因を精神的なものと思う」という経験をしていた。この経験は暴投の原因が技術的なものか精神的なものかという葛藤の苦しみを軽減する一方で,暴投を繰り返す悪循環を強化するような経験であることが示された。イップス状態から抜け出す過程においては,できる送球を繰り返し成功体験を積み重ねていく,時間的な間を置くといった送球に対する捉え方が変化するような経験の有効性,また周囲の理解が早期克服につながることが示された。
- 著者
- 千賀 則史
- 出版者
- 日本コミュニティ心理学会
- 雑誌
- コミュニティ心理学研究 (ISSN:13428691)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.176-195, 2016-02-29 (Released:2019-04-13)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1
Exploring a suspected sexual abuse case of a junior high school girl, this study examines the approach to a child for family reunification after intervention by a child guidance center. The safety planning approach from the Partnering for Safety (PFS), which integrates various theories including the Solution-Focused Approach (SFA), the Signs of Safety Approach (SoSA) and others, was applied for the case by a child psychologist at the temporary shelter of a child guidance center. ln order to involve the child in the family reunification process, the tools of PFS such as ‘The Future House’, ‘The Family Safety Circles’ and ‘The Safety House’ were applied. Although the child was defensive and her parents continued to deny the sexual abuse change, the tools of PFS focusing on the child's hope and safety acted as a catalyst to build constructive relationship among the child, her parents and the workers of a child guidance center. Eventually, family reunification was achieved as her opinion was reflected in the safety planning. This study shows that supports for children and their parents can be developed interactively by using the tools of PFS, and that it is important for the worker to have an ecological perspective on the person-environment fit.
6 0 0 0 OA 医療放射線被ばくの疫学とリスク推定に関する最近のトピックス
- 著者
- 浜田 信行 吉永 信治
- 出版者
- 日本保健物理学会
- 雑誌
- 保健物理 (ISSN:03676110)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.3, pp.136-145, 2018 (Released:2018-11-27)
- 参考文献数
- 66
- 被引用文献数
- 1
Ionizing radiation has long been indispensable in medicine. Such medical exposures can broadly be divided into two categories, namely, therapeutic exposures and diagnostic exposures. On one hand, therapeutic exposures generally occur at high dose and/or high dose rate, in which health effects of main concern are tissue reactions (formally called deterministic effects) and second cancer. Of these, mounting epidemiological evidence for tissue reactions has attracted particular attention to circulatory disease and cataracts. Diagnostic exposures, on the other hand, occur at relatively low dose and/or low dose rate, where cancer is the major health effect of concern. Epidemiological evidence from diagnostically exposed populations is still subject to uncertainties in dose (e.g., lack of individual doses) and potential biases (e.g., confounding by indication and reverse causation), which render direct risk estimation of diagnostic exposures unreasonable. This raises the need for the extrapolation from epidemiological evidence in other populations exposed to high dose and/or high dose-rate radiation. From radiation protection viewpoints, recent discussions include individual risk estimation, and individual radiation responses. This review paper provides a brief overview of recent topics in epidemiology and risk estimation for medical exposures.
6 0 0 0 OA 中国式眼の保健体操
- 著者
- 福地 孝
- 出版者
- 日本良導絡自律神経学会
- 雑誌
- 日本良導絡自律神経学会雑誌 (ISSN:09130977)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.11, pp.266-268, 1996-11-15 (Released:2011-10-18)
6 0 0 0 OA 中央アジアのウラン資源, 特に砂岩型ウラン鉱床について
- 著者
- 武内 寿久祢
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.5, pp.666-667, 1996-10-25 (Released:2009-11-12)
6 0 0 0 OA ボツリヌス中毒およびその発生防止法をめぐる最近の問題点
- 著者
- 安藤 芳明
- 出版者
- Japanese Society for Food Hygiene and Safety
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.6, pp.455-461, 1981-12-05 (Released:2009-12-11)
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 2 1
6 0 0 0 OA アンスコムの実践的知識論
- 著者
- 鴻 浩介
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, no.68, pp.169-184, 2017-04-01 (Released:2017-06-14)
- 参考文献数
- 16
According to G. E. M. Anscombe’s proposal, agents have a special way of knowing about their own intentional actions - they have the capacity to know what they are intentionally doing without relying on any evidence from observation, inference and so on. Anscombe dubbed this special knowledge “practical knowledge” and took it to be an essential mark of agency. This article attempts an explanation and vindication of this Anscombean approach to agency.The discussion falls into four sections. In the first section, I clarify the nature of Anscombe’s practical knowledge and argue that the principal task for us is to spell out how one can be justified in believing not just what one intends, but what one is intentionally doing without any evidence. In Section II, I discuss what is generally considered to be the most promising way of dealing with this task: the reliabilism strategy. On this view, practical knowledge is justified because there is a reliable efficient-causal link between an agent’s intention to φ and his/her actually doing φ. I am willing to accept the reliabilism strategy as being basically on the right track. However, in Section III, I argue that the reliabilism strategy overlooks an important element of Anscombe’s discussion, namely that practical knowledge is the “formal cause” of what it understands, i.e., intentional actions. With this observation in place, we can give an even more comprehensive account of the nature of practical knowledge. In Section IV, I close with a suggestion that the structure of practical knowledge so understood is surprisingly similar to the structure of the knowledge that makers of artifacts are said to have, and this similarity can support the claim that practical knowledge is knowledge about an objective, public world.
6 0 0 0 OA 「原子力の夢」と新聞 : 1945~1965年における『朝日新聞』『読売新聞』の原子力報道に関する一考察(<特集>メディアは原子力とどう向き合ってきたのか-原子力・原発報道の史相を探る-)
- 著者
- 山本 昭宏
- 出版者
- 日本メディア学会
- 雑誌
- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, pp.9-27, 2014-01-31 (Released:2017-10-06)
- 参考文献数
- 20
The purpose of this paper is to propose a hypothesis about the process through which the media builds up collective expectations concerning nuclear power (the Nuclear Dream) and the transformation of such expectations. We focus on the Asahi and Yomiuri Newspapers and study not only editorials, but also regular features that are likely to have affected public opinion as much as editorials. The period targeted in this paper is the 20 years from 1945 to 1965. We divide these 20 years into three periods based on changes in the Nuclear Dream: the dream of war deterrence (1945 to 1949) ; the dream of peaceful use (1949 to 1957) ; and the dream of nuclear power generation (1957 to 1965). Japanese newspapers were unknowingly trapped in the Nuclear Dream that they built up through their own discourse; while they detached themselves from the Nuclear Dream in the late 1950s, they expanded the dream again in the 1960s. By describing this process, we examine how it is possible to meet collective expectations built up by the media.
6 0 0 0 OA 1 反原発運動における女性の役割——仏プロゴフと三重県芦浜の事例から
- 著者
- 吉井 美知子
- 出版者
- 日本平和学会
- 雑誌
- 平和研究 (ISSN:24361054)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.81-107, 2021 (Released:2022-01-31)
- 参考文献数
- 24
フランスと日本はともに世界屈指の原発推進国であるが、すべての建設計画が実現したわけではない。本研究では市民の大規模な反対運動によって計画が撤回された仏プロゴフと三重県芦浜を事例に、運動のなかで女性の果たした役割について考察する。プロゴフは仏西部ブルターニュ半島の先端近くに位置する。ここで1970年代後半に持ち上がった大規模な原発計画を、地元の村落女性を中心に始まった運動で封じ込めた。男性は遠洋航海の仕事で長期に不在、留守番の女性たちは夜ごとに道路をバリケード封鎖したり、終日村の広場に座り込んだりと、粘り強く運動に取り組んだ。芦浜は三重県南部の海岸で、1980年代から二度目の原発計画が持ち上がる。1994年、計画容認決議を取らせまいと、漁家の女性たちが夜を徹して古和浦漁協前の最前列に座り込み、計画阻止に大きく貢献した。地域の分断にも長期に耐えた。プロゴフ女性は、女性だからできた、毎日毎夜の活動は男性には忍耐力がなくて無理だと証言する。古和浦女性は、男性は世間体や面子を優先するが、女性は子孫に海を引き継ぐことを考えたと述べる。両事例は1970年代のフランスや1990年代の日本で、社会的地位の低かった女性が、しがらみのなさを逆手に取って、家族に海を残そうと闘った成果である。女性の地位が向上した現在、今後は女性が権力を持つ側に回り、原発をなくす方向に社会を動かしていくことに期待したい。
6 0 0 0 OA 水筒の細菌汚染および使用実態調査
- 著者
- 山田 正子 松尾 美砂 細山田 康恵
- 出版者
- 日本食生活学会
- 雑誌
- 日本食生活学会誌 (ISSN:13469770)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.66-70, 2016 (Released:2016-07-28)
- 参考文献数
- 13
In recent years, many people have been carrying water-bottles and drink beverages from these bottles at any time. We investigated the microorganisms of both the bottle’s mouth and the bottle’s beverages to understand the sanitary condition. Standard plate counts of 103-105 cfu/cm2 and 104-107 cfu/mL were detected on the mouth of the water-bottle and in the beverages, respectively. Coliform bacteria also were detected, the counts of which were less than the standard plate counts. The causes of the microbial condition were insufficient washing of the water-bottle and mixing of oral bacteria. It is necessary to keep the bottle at a low temperature and consume the beverage as soon as possible.
6 0 0 0 OA 「私は5億分の1の確率で生まれた」は本当か? 科学心理学からのアプローチ
- 著者
- 渡辺 恒夫
- 出版者
- 科学基礎論学会
- 雑誌
- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.51-57, 1997-03-31 (Released:2009-07-23)
- 参考文献数
- 8
6 0 0 0 OA 料理本の巻末索引の調査分析
- 著者
- 藤田 節子
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.82-88, 2017-02-01 (Released:2017-02-01)
わが国の料理本の索引の実態を調査するため,2014,2015年の「料理レシピ本大賞in Japan」で一次選考を通過した,27冊の巻末索引を詳細に分析調査した。その結果,レシピ名と材料を索引対象として,体系順に配列された材料の分類の下に,レシピ名が50音順あるいは頁順に配列されている索引が多いことがわかった。相互参照や凡例はなく,見出し語の選択,副見出しの記述,配列のしかたなどに課題が見られ,料理本の索引が不十分であることが明らかになった。今後,料理本の著者や編集者,出版社に,索引に関する知識や索引作成技術の普及が必要であろう。
6 0 0 0 OA ゲーム、実況者、視聴者の関係性からみるゲーム実況生放送の構造
- 著者
- 根岸 貴哉
- 出版者
- 立命館大学ゲーム研究センター
- 雑誌
- REPLAYING JAPAN (ISSN:24338060)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.91-98, 2023-03
6 0 0 0 香川県の歴史散歩
- 著者
- 香川県の歴史散歩編集委員会編
- 出版者
- 山川出版社
- 巻号頁・発行日
- 1996
6 0 0 0 OA 特集:ここまでわかった絶滅した日本の狼の起源―はじめに―
- 著者
- 大舘 智志
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.3-4, 2023 (Released:2023-02-09)
- 参考文献数
- 4
6 0 0 0 OA ウクライナにおける大学生の日本語学習動機
- 著者
- 大西 由美
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.147, pp.82-96, 2010 (Released:2017-02-15)
- 参考文献数
- 22
本稿では,ウクライナの大学において日本語を専攻する学習者を対象に,日本語学習動機調査を行った。ウクライナは日本との人的・経済的交流が少ない「孤立環境」と呼ばれる地域である。日本語学習者は増加傾向にあるが,卒業まで意欲的に学習できない学生が多いことが問題となっている。 一方,日本語学習者を対象とした動機づけ研究では,環境が大きく異なるにも関わらず,他地域の動機づけ尺度を基に調査が行われる傾向がある。 そこで,本稿では,日本語学習動機を自由記述によって収集し,先行研究にはない項目を含む35項目の尺度を作成した。5大学の学生を対象に質問紙調査を行い,180名分のデータを得た。学年層別の因子分析の結果,低学年と高学年では動機づけの構造が異なることが明らかになった。低学年の学習者は文化に関する動機と仕事に関する動機の相関が高く,これらの動機が対立するものだとしている他地域の先行研究とは異なる結果となった。
6 0 0 0 OA 日本人小児における乳歯・永久歯の萌出時期に関する調査研究 II その1.乳歯について
- 著者
- 日本小児歯科学会 有田 憲司 阿部 洋子 仲野 和彦 齊藤 正人 島村 和宏 大須賀 直人 清水 武彦 石通 宏行 松村 誠士 尾崎 正雄 石谷 徳人 濱田 義彦 渥美 信子 小平 裕恵 高風 亜由美 長谷川 大子 林 文子 藤岡 万里 茂木 瑞穂 八若 保孝 田中 光郎 福本 敏 早﨑 治明 関本 恒夫 渡部 茂 新谷 誠康 井上 美津子 白川 哲夫 宮新 美智世 苅部 洋行 朝田 芳信 木本 茂成 福田 理 飯沼 光生 仲野 道代 香西 克之 岩本 勉 野中 和明 牧 憲司 藤原 卓 山﨑 要一
- 出版者
- 一般財団法人 日本小児歯科学会
- 雑誌
- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.45-53, 2019-02-25 (Released:2020-01-31)
- 参考文献数
- 18
日本人乳歯の萌出時期および萌出順序を明らかにし,乳歯の萌出に変化が生じているか否かを検討する目的で,全国的に3 か月から3 歳11 か月の小児8,724 名を調査し,以下の結果を得た。1 .男児の乳歯萌出は,A が5 か月-9 か月,A が7 か月-11 か月,B が9 か月-1 歳2 か月,B が9 か月-1 歳3 か月,D が1 歳1 か月-1 歳6 か月,D が1 歳1 か月-1 歳7 か月,C が1 歳2 か月-1 歳8 か月,C が1 歳2 か月-1 歳9 か月,E が1 歳11 か月-2 歳7 か月,E が2 歳0 か月-2 歳11 か月の順だったが,BB 間とD, D, C およびC の間には有意な差は認められなかった。2 .女児の乳歯萌出は,A が6 か月-9 か月,A が7 か月-11 か月,B が9 か月-1 歳1 か月,B が9 か月-1 歳2 か月,D が1 歳1 か月-1 歳7 か月,D が1 歳1 か月-1 歳7 か月,C が1 歳3 か月-1 歳9 か月,C が1 歳4 か月-1 歳9 か月,E が1 歳11 か月-2 歳7 か月,E が2 歳1 か月-2 歳10 か月の順だったが,AA 間,AB 間,BB 間,DD 間,CC 間には有意な差は認められなかった。3 .性差は大部分の歯で認めず,C とC の萌出時期にのみ有意な差を認め,いずれも男児が1 か月早く萌出していた。4 .前回報告(1988 年)に比べて,男児はA, A, C, D の,女児はA とD の,萌出時期が有意に早くなっていることを認めた。
6 0 0 0 OA 土耳其国軍艦エルトグルル号
- 著者
- 駐日土耳其国大使館 編
- 出版者
- 駐日土耳其国大使館
- 巻号頁・発行日
- 1937