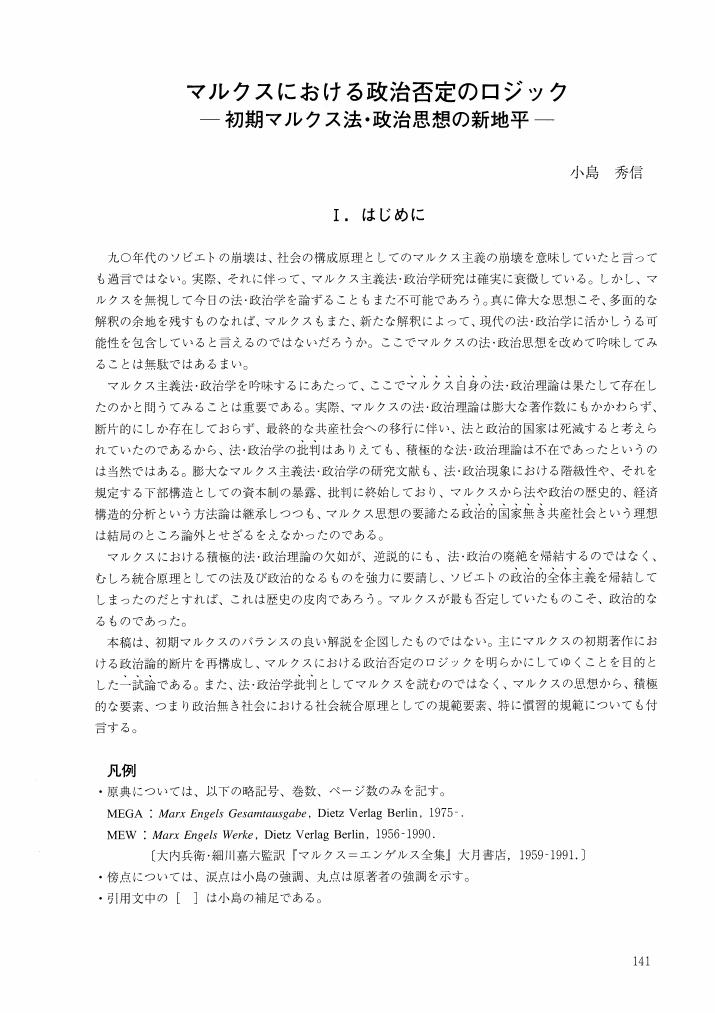3 0 0 0 OA 障害がある有権者に対する選挙情報の保障をめぐる政策の現状と課題
- 著者
- 大倉 沙江
- 出版者
- 公益財団法人 情報通信学会
- 雑誌
- 情報通信学会誌 (ISSN:02894513)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.23-30, 2018 (Released:2018-08-21)
- 参考文献数
- 5
高齢化の進展に伴い、中途障害者が増加している。このことから、聴覚障害者は手話、視覚障害者は点字といったステレオタイプを超えて、障害の種類や程度、コミュニケーション手段の違いに応じた情報提供が求められている。本稿は、障害がある有権者に対する選挙情報の保障に関わる国レベルの政策の現状と課題を明らかにすることを目的とする。具体的には、政見放送への手話通訳・字幕の付与、選挙公報の点訳・音訳を中心に、審議会の会議録や新聞記事を用いて検討を行った。分析の結果、政見放送については、衆議院議員総選挙の比例代表では字幕の付与が、参議院通常選挙の選挙区では手話通訳および字幕の付与が認められていないことが確認された。また、選挙公報については、点字版はすべての都道府県で作成されているものの、拡大文字版は半数以上の都道府県で作成されていないことが確認された。選挙情報の保障に向けて、障害がある有権者の選挙情報の保障をいかに、誰の責任で実現するかという点に関する政策決定者や有権者の間の合意形成を図ることが緊要であり、将来の政策展開に必要な課題が整理された。
3 0 0 0 OA スイッチトリラクタンスモータの課題と対策
- 著者
- 内藤 治夫
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会誌 (ISSN:13405551)
- 巻号頁・発行日
- vol.128, no.4, pp.227-230, 2008-04-01 (Released:2008-04-01)
- 参考文献数
- 14
本記事に「抄録」はありません。
3 0 0 0 OA 住民と観光客の意識からみる住民参加による観光まちづくりの利点と課題
- 著者
- 白 りな 十代田 朗 津々見 崇
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.13-22, 2016-04-25 (Released:2016-04-25)
- 参考文献数
- 13
本研究は韓国ドンピランを対象とし、「地域住民が主体となる観光まちづくりは住民にも観光客にも魅力ある地域づくりにつながる」という過程の下、観光まちづくりの展開を整理し、住民意識、観光客の動態・評価、及びそれらの対応関係を明らかにし、住民参加による観光まちづくりの利点と課題を考察した。当地での観光まちづくりの展開を3期に区分して特徴を見たところ、発展期では住民参加による活動が見られ、こうした活動は観光公害の減少、経済的利益の還元など、観光の実利を伴いながら生活空間を向上させることから、利点として認められる。一方課題も表出しており、観光業従事者である一部住民のみが活動に主に参加しており、一部住民の意見が地域社会の総意として扱われる恐れがある。また、彼らの意識が経済面に集中してしまい、魅力的な生活空間の形成や観光地としての持続的な成長を防げる可能性があることが指摘された。
3 0 0 0 OA Spatial Patterns of Winter Precipitation in the North-Central Region (Hokuriku District) of Japan
- 著者
- Kengo Arai Kazuaki Yasunaga
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- SOLA (ISSN:13496476)
- 巻号頁・発行日
- pp.2019-016, (Released:2019-03-26)
- 被引用文献数
- 1
This study examines dominant precipitation patterns during winter in the north-central region (Hokuriku District) of Japan, based on empirical orthogonal functions (EOFs) analysis. The pattern of the first leading component is similar to that of the mean precipitation, and the second leading component shows a dipole structure in which positive and negative regions are separated by the coast line. This dipole pattern across the coast line is robust regardless of data stratifications for the EOF calculation. Composites reveal that maritime and inland precipitation is relatively enhanced before and after the passage of a mid-level trough, respectively. In the former case, the temperature is higher and westerly or southwesterly wind prevails, while northwesterly wind dominates in the latter case. It is suggested that interactions between cold air over the land and warm air over the ocean are essentially important to the distinct precipitation patterns; offshore winds wedge the inland cold air under the maritime warm air, and intensifies the precipitation over the ocean. On the other hand, the northwesterly monsoonal flow pushes the maritime warm air onto the inland cold air, and more precipitation is brought about around the mountain range.
3 0 0 0 OA 腎細胞がん骨転移の右骨盤腫瘍による疼痛に対する鍼灸と湯液の併用治療の1症例
- 著者
- 三島 怜 小川 恵子 有光 潤介 津田 昌樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.29-33, 2017 (Released:2017-07-05)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
一般的にがん終末期においては,症状は右肩下がりに悪化し,症状の改善を図ることは非常に困難である。中でも骨転移疼痛のコントロールは難しい。症例は67歳男性,左腎癌右骨盤骨転移にて,緩和的化学療法や疼痛緩和治療が施行されていたが,疼痛コントロールが不十分であった。当初盗汗を主訴に湯液治療を開始し,さらに骨転移疼痛に対する疼痛緩和目的で鍼灸治療の併用を開始した。併用治療により,十分かつ,迅速な疼痛緩和が得られたため報告する。
- 著者
- 柴田 徹
- 出版者
- 日本産業教育学会
- 雑誌
- 産業教育学研究 (ISSN:13405926)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.41-48, 1998-07-31 (Released:2017-07-18)
The Shoho no Radio (once subtitled the 'Beginner's Radio') which was the Japanese earliest monthly radio magazine mainly for boys and girls (referred to here simply as 'youngsters') in Japan had first published in 1948 by Seibundo Shinkosha Publishing Co., Ltd., and had continued until 1992. This magazine originally had a brotherly relationship between the Musen to Jikken (subtitled 'The Radio Experimenter's Magazine' at that time) which was the traditional senior radio monthly already published. This study clarified a philosophy of the first issue of the Shoho no Radio through the analyses of the contents of some articles included in both brotherly radio monthlies in the same period, and argued about the educational meanings of a philosophy of the first issue of the Shoho no Radio. The Shoho no Radio had come out of the conceptual background of science and technology publishing tradition involved a viewpoint for youngsters, as the Japanese earliest monthly radio magazine for youngsters, also thinking ahead to promote the brotherly monthly Musen to Jikken. Substantial analyses showed that the Shoho no Radio had provided manufacturing articles encouraging practically to complete electro-technically inexperienced work of youngsters and explanatory ones encouraging directly to acquire electro-technological knowledge from the beginning of youngsters, whichever using plainer illustrations and sentences, and then, that the said monthly would had sincerely wanted to popularize electronics technology spreading over the youngster's generation. And we can consider that it reflects a certain philosophy of the first issue of the Shoho no Radio. In 1947, the year before the first issue of the Shoho no Radio, the Kyoiku Kihon Ho (the Fundamental Law of Education), the Gakko Kyoiku Ho (the School Education Law) and others had established in Japan, namely, the postwar-Japanese new school-educational systems and practices had already launched out. However, from a viewpoint of electronics technology education as universal education, the contemporary curricula of primary and secondary schools had been less adequate than the present ones in point of the system, and we should hesitate to say that the opportunities for study of electronics technology for youngsters had secured satisfactorily. In these circumstances, the Shoho no Radio which would have enlarged the opportunities for study of electronics technology for youngsters periodically from the outside of school education had involved a definite important meanings in a point of creating and enlarging the opportunities for study. And as stated above, the Shoho no Radio had involved a fundamentally sincerely and gently attitude toward electro-technically inexperienced youngsters as readers in the contents of its articles. This will reinforce the formal meanings of creating and enlarging the opportunities for study in point of the contents. Therefore, it seems that the historical and painstaking study of the contents of a series of the Shoho no Radio are significant not only in a context of the historical study of enlightenment and popularization of technology but also in a viewpoint of the basic study of technology education.
3 0 0 0 OA 5 治療と対策(患者の治療)(シンポジウム1 化学物質過敏症)
- 著者
- 坂部 貢
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.9-10, pp.807, 2002-10-30 (Released:2017-02-10)
- 著者
- Seri SEKI Kenji TESHIMA Daisuke ITO Masato KITAGAWA Yoshiki YAMAYA
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.18-0475, (Released:2019-04-12)
- 被引用文献数
- 6
The present study used data from anesthetic records to analyze variables of intracranial pressure (ICP) during brain tumor surgery or in the early postoperative period as prognostic indicators in dogs. Data from 17 dogs which were scheduled to undergo elective craniotomy for brain tumor surgery from 2009 to 2012 were included. Of these, five (29.4%) died during 14 days after the surgery because of respiratory failure following pneumonia (n=2), euthanasia due to difficulty in treatment of status epilepticus (n=1), tumor-bed hematoma (n=1), and unknown reason (n=1). In the 12 surviving dogs, neurological signs were improved or resolved at discharge. All dogs were administered midazolam and droperidol-fentanyl as premedication. General anesthesia was induced using propofol maintained on isoflurane and oxygen. Direct ICP was obtained via a Codman Microsensor strain gauge transducer. ICP hypertension (>13 mmHg) measured after 15 min of recovery from the moment after discontinuation of anesthesia by turning off the vaporizer dial was associated with poor prognosis (odds ratio, 20.00; 95% confidence interval, 1.39−287.60, P=0.028). This suggests that intracranial pressure influences the postoperative mortality rate in dogs undergoing brain tumor surgery.
3 0 0 0 OA マルクスにおける政治否定のロジック
- 著者
- 小島 秀信
- 出版者
- 政治思想学会
- 雑誌
- 政治思想研究 (ISSN:1346924X)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.141-162, 2004-05-10 (Released:2012-11-20)
3 0 0 0 OA 歐米に於ける平爐製鋼の管見
- 著者
- 絹川 武良司
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉄鋼協会
- 雑誌
- 鐵と鋼 (ISSN:00211575)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.163-174, 1939-03-25 (Released:2009-07-09)
3 0 0 0 OA 現代東京語の姓のアクセント
- 著者
- ローレンス ウェイン
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.3, pp.1-16, 2011-07-01 (Released:2017-07-28)
本稿では13,610の姓からなる苗字アクセントデータベースに基づいで、複合語構造の姓はアクセントの付与の仕方によって三つのタイプに分かれることを提案する。無標のタイプ(姓の三分の二以上)ではアクセント型が姓の後部成素の長さによって決定される。二つ目のタイプ(姓の約四分の一)では、特定の音環境に適用する規則が姓を有標のアクセントにする。残りの姓(六パーセント程度)は例外的に語形の一部としてその不規則的なアクセントを習得せざるを得ない。
3 0 0 0 OA ハーツホーンからハーヴェイヘ
- 著者
- 松本 正美
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.10, pp.655-668, 1976-10-01 (Released:2008-12-24)
- 参考文献数
- 45
筆者は1975年の6月に Harvey の処女作“Explanation in Geography”(第15章まで)の邦訳を完了した.それを機会に,現代地理学め歴史と構造とを整理してみようとしたのが本稿である.我が国のこれまでの地理学史や地理学方法論は,地理学の「対象」や,それを取り扱う「方法」に関する議論に終始している.しかし,そのような「対象」や「方法」の論理は,「主体」の論理に先行されねばならない.本稿はその論理を「人間の人間化」と規定し,その論理を詳述するとともに,それをHartshorneからHarveyへの流れに沿って具体化している.人間が「生理的人間」から「知的存在」を経由して「志向的意識の主体」へと純化されるにつれ,その各段階にそれぞれの地理学が存在し,しかも人間の規定様式が地理学の内容を制約するのである.現代地理学の構造と歴史は,英文要旨の中に図表化しておいた.これらの認識が,地理学そのものを洞察する唯一の手段であると信じる.
3 0 0 0 OA モロッコ・フェズにおける都市型隊商施設(フンドゥク)の建築類型と商業的機能について
- 著者
- 山田 幸正
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.482, pp.199-210, 1996-04-30 (Released:2017-01-28)
- 被引用文献数
- 2 2
This paper refers to a few observations on plan and structure of the funduqs in the Medina of Fez, reporting some results based on a field survey in July and August, 1988. Paying attention to their forms composing the courtyard-facade, 63 existent funduqs can be classified five architectural typos as follows : (1) Gallery type ; with colonnaded galleries surrounding the courtyard on the second and third floors, (2) Terrace type ; with open-terraced passageway around the courtyard on the second floor. (3) Composite typo ; with colonnaded gallery on the second floor and open-torraced passageway on the third floor, (4) Wall type ; having neither the gallery nor the terrace on the upper floors, the wall facing the. courtyard, (5) One-story type ; having no upper floor. It is the Gallery type (33 examples) that characteristic of funduqs in Fez. Two-story gallery type is simpler in design and more practical in use. Three-story gallery type might assume a significant function, distinguished from the others.
3 0 0 0 OA 自転車の進行方向に着目した交差点自転車事故の分析
- 著者
- 萩田 賢司 森 健二 横関 俊也 矢野 伸裕
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.5, pp.I_1023-I_1030, 2014 (Released:2015-05-18)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2
交差点における自転車事故の実態を把握するために,事故当事者の進行方向別の事故発生頻度を明らかにした.千葉県東葛地域の交差点自転車事故を分析対象として,緯度経度情報,当事者の進行方向矢印と事故類型などをもとに,自動車と自転車の相対的な進行方向を求めた.その結果,信号の有無により自転車事故の発生形態が大きく異なっており,信号交差点では,自転車と平行して道路を走行している自動車の右左折に伴う事故が大半を占めていた.無信号交差点では,自動車が交差点を通過する際の手前側の交錯点を走行している自転車との事故が多発していることが示された.また,夜間においては,自動車は交錯する自動車と逆方向から進入してくる自転車と衝突しやすいことが示された.
- 著者
- Keiichi Itoh Shoji Masumori Daisuke Mukai Hiroyuki Sakakibara Michiko Yasuda Kayoko Shimoi
- 出版者
- The Japanese Society of Toxicology
- 雑誌
- The Journal of Toxicological Sciences (ISSN:03881350)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.273-282, 2019 (Released:2019-04-03)
- 参考文献数
- 46
- 被引用文献数
- 3
Previously, we reported that the frequency of micronucleated reticulocytes (MNRETs) in the peripheral blood of male C3H/He mice intraperitoneally administered ethylnitrosourea (ENU) (25 mg/kg body weight) in the dark period (zeitgeber time, ZT15) was higher than in the light period (ZT3). In this study, to clarify the mechanism underlying this phenomenon, we investigated the differences in micronucleus (MN) induction observed between ZT3 and ZT15 using five chemicals, methylnitrosourea (MNU), ethylmethane sulfonate (EMS), mitomycin C, cyclophosphamide and vincristin. MNU and EMS, monofunctional alkylating agents, showed higher frequencies of MNRETs in the ZT15 than the ZT3 treatment similar to ENU. However, no differences were observed for the other chemicals. In the comet assay, more DNA damage was induced by ENU in the ZT15 than the ZT3 treatment. Furthermore, the plasma erythropoietin (EPO) level, a known effector of MN induction with anti-apoptotic activity mediated by Bcl-xL expression, was higher in the dark than in the light period. EPO did not increase the frequency of MNRETs. However, in the ENU treatment group at ZT3 following EPO injection a significant increase of MNRETs was observed similar to the ZT15 treatment. Higher expression of apoptosis-related genes such as Bcl-xL was induced in bone marrow cells from mice treated with ENU at ZT15 compared with ZT3. From these results, it was speculated that the differences in MN induction in the peripheral blood of mice exposed to monofunctional alkylating agents such as ENU depend on apoptotic or anti-apoptotic conditions related to the circadian rhythms of EPO in bone marrow.
3 0 0 0 OA ブリモニジン酒石酸塩点眼液(アイファガン®点眼液0.1%)の薬理学的特性および臨床効果
- 著者
- 金子 恵美 和田 智之 南川 洋子 井上 優
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.140, no.4, pp.177-182, 2012 (Released:2012-10-10)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 3 4
アイファガン®点眼液0.1%(AIPHAGAN®)は,アドレナリンα2受容体作動薬であるブリモニジン酒石酸塩を主成分とした新規の緑内障・高眼圧症治療薬である.その眼圧下降効果は,房水産生の抑制およびぶどう膜強膜流出路を介した房水流出の促進という2つの機序に基づくと考えられている.このことからアイファガン®点眼液0.1%は,房水産生を抑制するアドレナリンβ受容体遮断薬(β遮断薬)や房水流出を促進するプロスタグランジン関連薬(PG関連薬)等との併用効果も期待できる.第III相臨床試験では,原発開放隅角緑内障(広義)および高眼圧症患者でPG関連薬の併用におけるさらなる眼圧下降効果が,また52週間の長期投与試験でも安定した眼圧下降効果が示されている.承認時までに実施した臨床試験における副作用は,総症例444例中122例(27.5%)であった.主な副作用は結膜炎(アレルギー性結膜炎を含む)38例(8.6%),点状角膜炎30例(6.8%),眼瞼炎(アレルギー性眼瞼炎を含む)20例(4.5%)および結膜充血17例(3.8%)であった.なお,本剤では点眼剤の保存剤として本邦で初めて亜塩素酸ナトリウムを使用している.
3 0 0 0 OA ブリーチ剤を用いた毛髪の脱色における配合成分の効果
- 著者
- 前川 昌子 梁 善美
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.6, pp.387-392, 2008 (Released:2010-07-29)
- 参考文献数
- 15
3種の市販ブリーチ剤を用いて毛髪の脱色処理を行ったところ,酸化剤,アルカリ,過炭酸ナトリウムなどブリーチ剤の含有成分の違いにより脱色効果に大きな差があることがわかった.そこで, 主要な酸化剤成分である過酸化水素を用いて処理液のpHを変化させて漂白実験を行い,脱色効果と強伸度, 表面形状の変化に対するpHの影響を検討した.その結果,pHが9以上で大きくなるにつれて脱色効果は大きくなるが,一方で高いpHでは毛髪の強度低下と表面の損傷が起こることがわかった.また,過炭酸ナトリウムは過酸化水素にアルカリを加えて行った結果よりすぐれた脱色効果を示し,毛髪の損傷も幾分抑えられることが示唆された.
3 0 0 0 OA 日本産トゲトビムシ科の分類
- 著者
- 須摩 靖彦
- 出版者
- 日本土壌動物学会
- 雑誌
- Edaphologia (ISSN:03891445)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, pp.25-56, 2009-03-31 (Released:2017-07-20)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1
トゲトビムシ科の形態的な特徴と,分類指標になる上唇毛式,転節器官,茎節棘式と端節を中心に特徴を述べた.日本産トゲトビムシ科は5属3亜属29種2亜種を数える.これらを検索図,識別形質表,そして属・種の各論に分けて解説した.
3 0 0 0 OA 2 . 言い間違いの言語学的意味
- 著者
- 外池 滋生
- 出版者
- 日本失語症学会 (現 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会)
- 雑誌
- 失語症研究 (ISSN:02859513)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.537-541, 1984 (Released:2006-11-22)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA ブタのモノ化と擬人化
- 著者
- 比嘉 理麻
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第48回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.64, 2014 (Released:2014-05-11)
いわゆる「工場畜産」と呼ばれる環境下で、飼育される家畜たちは、エージェンシーなき客体、あるいは肉を生み出す単なる機械なのだろうか。この問いを出発点に、本発表では、産業化の進んだ沖縄の養豚場の事例から、人とブタの個別具体的なかかわりを明らかにすることで、産業家畜と人間の関係について別の見方を提示することを目指す。