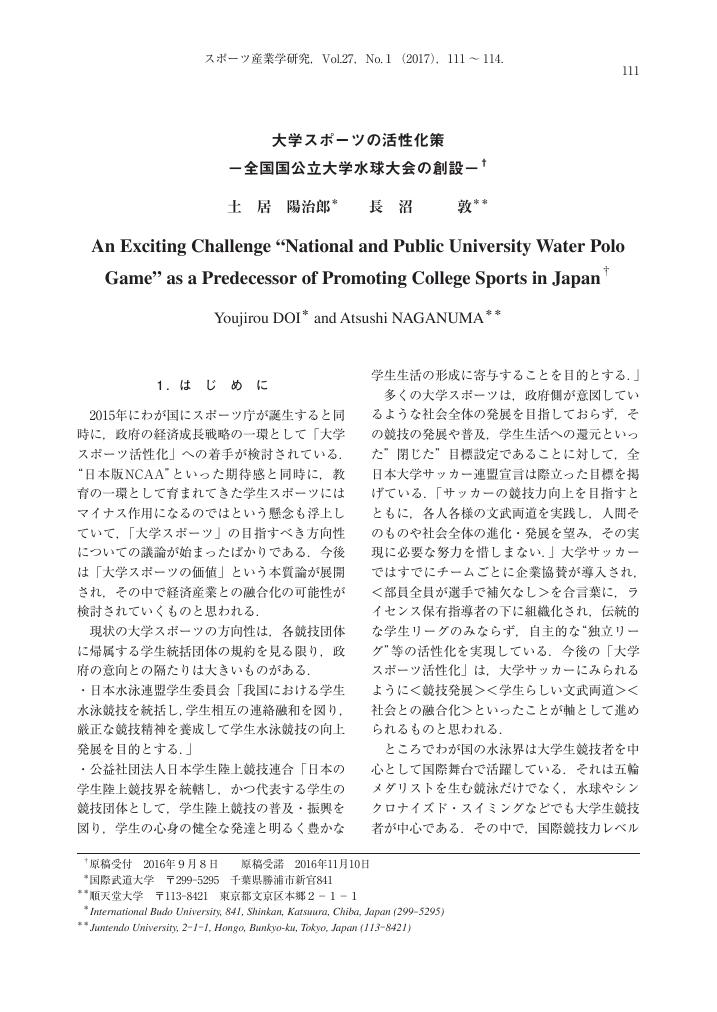3 0 0 0 OA 「正常性の構築」としての排除
- 著者
- 山口 毅
- 出版者
- 関東社会学会
- 雑誌
- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.19, pp.13-24, 2006-07-31 (Released:2010-04-21)
- 参考文献数
- 23
Previous works concerning the form of exclusive interaction have focused on practices in which the excluded persons are deprived of positions as the “subject”. From this perspective, it is difficult to criticize ambiguous exclusion. Focusing on the fact that the normality of the excluded people is constructed through mutual interaction, I describe the methods of exclusion that are used even when the position as the “subject” is maintained. In order to criticize such ambiguous exclusion, we should be aware that there are alternative methods by which participants can construct mutual normality without exclusion and advocate an interactional culture where ambiguous exclusion is considered to be improper.
3 0 0 0 OA ニコチン性アセチルコリン受容体に作用する殺虫剤の無脊椎動物における薬理学
- 著者
- Andrew J. Crossthwaite Aurelien Bigot Philippe Camblin Jim Goodchild Robert J. Lind Russell Slater Peter Maienfisch
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- pp.D17-019, (Released:2017-07-29)
- 参考文献数
- 158
- 被引用文献数
- 53
ニコチン性アセチルコリン受容体(nAChR)は,カチオン選択性細孔の周囲に配置された5つのタンパク質サブユニットからなるリガンド作動性イオンチャネルである.いくつかの天然および合成殺虫剤は,nAChRと相互作用することによってその効果を表す.ここでは,ネオニコチノイドとその関連化合物の標的害虫に対する薬理作用についてまとめた.無脊椎動物に内在するnAChRを構成するサブユニットの量比は不明であるが,昆虫の受容体調製物において,ネオニコチノイド結合部位の存在が明らかにされ,これら殺虫剤は広範囲のnAChRに対して異なる薬理作用を表すことが示された.スピノシンは,主に鱗翅目のような咀嚼害虫を防除するために使用されるに対して,ネライストキシン類縁体は接触および浸透作用を介してイネおよび蔬菜害虫に使用されるが,これら殺虫剤の薬理作用は特有で,ネオニコチノイドの薬理作用とは異なる.
3 0 0 0 OA 表情が印象判断に及ぼす影響における性差
- 著者
- 上田 彩子 廼島 和彦 村門 千恵
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 認知心理学研究 (ISSN:13487264)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.103-112, 2010-02-28 (Released:2010-11-25)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 3
主に顔の形態特徴の情報処理を基に行われる顔認知過程において,表情情報が影響を及ぼすことは,多くの研究で示されている.また,表情認知に性差があることも示唆されている.表情認知における性差が,顔認知過程で表情が及ぼす影響に関与する可能性がある.そこで,本研究では,顔の印象決定において表情が及ぼす影響に性差が認められるかどうか実験的に検討した.刺激の顔の形態変化にはメイク手法を用いた.被験者は,刺激の相貌印象と表情表出強度について評価を行った.その結果,表情認知能力に性差は認められなかったが,相貌印象判断に表情が与える影響は女性のほうが大きいことが示された.
3 0 0 0 OA 脅威アピールでの被害の記述と受け手の脆弱性が犯罪予防行動に与える影響
- 著者
- 島田 貴仁 荒井 崇史
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.88.16032, (Released:2017-07-10)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 7
A field experiment was conducted to examine the factors in threat appeal responsible for maintenance of crime-prevention behavior. At four public bicycle parking lots, 256 riders with variable receiver vulnerability characteristics were encouraged to use an extra bicycle lock. They were randomly presented with one of three threat messages featuring victims of bicycle theft (identifiable victim, statistical victim, or control), followed by either high- or low-efficacy preventative-messages. After extra locks were installed on their bicycles, participants’ use of the lock was observed five times within 28 days after the intervention. A mixed-effect generalized linear model revealed that vulnerability of the participants increased the use of the lock immediately after the intervention. Meanwhile, highly vulnerable participants who were presented with an identifiable victim and high-efficacy messages decreased their use of the lock significantly compared to low-vulnerability participants and those who were presented with the low-efficacy message. The result implies that threat appeal strategies differ depending on receiver vulnerability and the type of preventative behavior.
3 0 0 0 OA ネコが反応を示すマタタビ中の揮発性成分の検索
- 著者
- 大江 智子 大畑 素子 有原 圭三
- 出版者
- 日本ペット栄養学会
- 雑誌
- ペット栄養学会誌 (ISSN:13443763)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.Suppl, pp.Suppl_52-Suppl_53, 2013-07-03 (Released:2013-09-27)
- 参考文献数
- 3
ネコは、マタタビに含まれるイリドミルメシンやアクチニジンなどの揮発性成分に対し、特徴的な反応を示す。本研究では、ネコが反応を示すマタタビ中の新たな成分の検出を目的とし、高真空香気蒸留法およびガスクロマトグラフ質量分析(GC-MS)装置を用いて検討した。マタタビの葉に含まれるモノテルペン化合物類に着目して同定したところ、7種類が検出された。このうち、ネコの反応との関係性が詳細には判明していないモノテルペン化合物で、標品として入手可能な4種類を用いて、ネコへの曝露実験を行ったところ、プレゴンで反応が確認された。
- 著者
- Yuki SAITO Shinnosuke TAKAMICHI Hiroshi SARUWATARI
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- IEICE Transactions on Information and Systems (ISSN:09168532)
- 巻号頁・発行日
- vol.E100.D, no.8, pp.1925-1928, 2017-08-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 19
This paper proposes Deep Neural Network (DNN)-based Voice Conversion (VC) using input-to-output highway networks. VC is a speech synthesis technique that converts input features into output speech parameters, and DNN-based acoustic models for VC are used to estimate the output speech parameters from the input speech parameters. Given that the input and output are often in the same domain (e.g., cepstrum) in VC, this paper proposes a VC using highway networks connected from the input to output. The acoustic models predict the weighted spectral differentials between the input and output spectral parameters. The architecture not only alleviates over-smoothing effects that degrade speech quality, but also effectively represents the characteristics of spectral parameters. The experimental results demonstrate that the proposed architecture outperforms Feed-Forward neural networks in terms of the speech quality and speaker individuality of the converted speech.
3 0 0 0 慶應義塾大学における図書館員の海外研修への取り組み
- 著者
- 関 秀行
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.8, pp.405-409, 2017-08-01 (Released:2017-08-01)
日本の大学図書館においては,図書館員を一定期間海外の図書館に派遣する滞在型の海外研修が人材育成の手段として一つとして実施されている。本稿では,図書館員の海外研修派遣の事例として,慶應義塾大学メディアセンターが長年に渡って実施している派遣の実績を紹介する。また,派遣を調整する立場からの視点で,海外研修の実施に当たって重視すべき要素として,研修者の人選,英語力の強化,研修先機関との互恵関係への配慮,経費補助のための財源確保に焦点を当て,慶應義塾大学の実状に触れながら,それぞれの重要性について述べる。
- 著者
- Cheng Chen Janet Wei Ahmed AlBadri Parham Zarrini C. Noel Bairey Merz
- 出版者
- 日本循環器学会
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.1, pp.3-11, 2016-12-22 (Released:2016-12-22)
- 参考文献数
- 127
- 被引用文献数
- 66
Angina has traditionally been thought to be caused by obstructive coronary artery disease (CAD). However, a substantial number of patients with angina are found to not have obstructive CAD when undergoing coronary angiography. A significant proportion of these patients have coronary microvascular dysfunction (CMD), characterized by heightened sensitivity to vasoconstrictor stimuli and limited microvascular vasodilator capacity. With the advent of non-invasive and invasive techniques, the coronary microvasculature has been more extensively studied in the past 2 decades. CMD has been identified as a cause of cardiac ischemia, in addition to traditional atherosclerotic disease and vasospastic disease. CMD can occur alone or in the presence obstructive CAD. CMD shares many similar risk factors with macrovascular CAD. Diagnosis is achieved through detection of an attenuated response of coronary blood flow in response to vasodilatory agents. Imaging modalities such as cardiovascular magnetic resonance, positron emission tomography, and transthoracic Doppler echocardiography have become more widely used, but have not yet completely replaced the traditional intracoronary vasoreactivity testing. Treatment of CMD starts with lifestyle modification and risk factor control. The use of traditional antianginal, antiatherosclerotic medications and some novel agents may be beneficial; however, clinical trials are needed to assess the efficacy of the pharmacologic and non-pharmacologic therapeutic modalities. In addition, studies with longer-term follow-up are needed to determine the prognostic benefits of these agents. We review the epidemiology, prognosis, pathogenesis, diagnosis, risk factors and current therapies for CMD.
3 0 0 0 OA 大学スポーツの活性化策-全国国公立大学水球大会の創設-
- 著者
- 土居 陽治郎 長沼 敦
- 出版者
- Japan Society of Sports Industry
- 雑誌
- スポーツ産業学研究 (ISSN:13430688)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.1_111-1_114, 2017 (Released:2017-01-25)
- 参考文献数
- 3
- 著者
- Makoto Hibino Tetsuri Kondo
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.197-201, 2017-01-15 (Released:2017-01-15)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 12
Although the influenza vaccine is relatively safe and effective, serious complications can develop in rare cases. We encountered two cases of interstitial pneumonia that developed after vaccination during the 2014-2015 influenza season. Overall, nine cases, including the two presented here, have been recorded in PubMed and the Cochrane library; eight patients were treated with corticosteroids, and all nine survived, suggesting a good prognosis. Interstitial pneumonia is rare; however, we found an increase in its incidence after 2009. Therefore, clinicians must be aware of the possibility of this complication and duly educate all patients in advance.
3 0 0 0 OA 市区町村における外国人の社会増加と日本人の社会減少
- 著者
- 清水 昌人
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.85-100, 2017 (Released:2017-07-27)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 5
本稿では2014年と2015年の住民基本台帳のデータを用い,外国人の社会増加が日本人の社会減少を量的にある程度以上補っている市区町村を観察した.筆者らは先の論稿で2014年の転出入を分析したが,集計値等を再検討すると,外国人の出国の多くが「その他」の職権消除に分類されていると推測されるため,本稿では転出入に「その他」の記載・消除(国籍変更等除く)を含めて社会増加・減少を分析した.その結果,外国人の社会増加が日本人の社会減少を完全に補う地域は,転出入のみで社会増加・減少を見た前稿に比べて大幅に減った.ただし完全にではないが,前者が後者を半分以上カバーし,かなりの程度補っている地域を加えた数は,2015年には少ないながら一定数にのぼる.2014年と2015年の比較では,これら市区町村の増加は三大都市圏から離れた地域等で小さいこと,かなりの程度以上補われている状態への移行やそこからの離脱は頻繁に起きること等を示した.
3 0 0 0 OA 心的状態の推測方略:投影とステレオタイプ化
- 著者
- 石井 辰典 竹澤 正哲
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- pp.0941, (Released:2017-02-10)
- 参考文献数
- 24
It has been argued that people selectively use two strategies, projection and stereotyping, to infer the mental state of others. Through a series of studies, Ames (2004) confirmed the hypothesis that people project their own mental state to the other when the target person is perceived to be similar to oneself, while the stereotype of a group or category to which the target person belongs is used for mental state inferences when the target is perceived to be dissimilar. Four replication studies of Ames (2004), however, consistently provided counterevidence against this hypothesis. Participants employed projection consistently, regardless of the perceived similarity to the target person. This result suggests that further examination of conditions that trigger different mental state inference strategies is needed.
3 0 0 0 OA 自尊心のレベル・変動性と将来への肯定的な期待との関連
- 著者
- 福沢 愛 山口 勧 先崎 沙和
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.117-130, 2013-11-30 (Released:2013-12-04)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 2
不安定な高自尊心を持つ人は,他罰的傾向などの望ましくない特性を持つことが,先行研究で示されてきた。これに対して本研究は,自尊心変動性とポジティブな機能との関連を検討した。不安定な高自尊心を持つ人は,ネガティブな出来事によって自尊心が脅威を受けた後,脅威軽減のために,遠い将来への期待を高く持つのではないかと予測した。146名のカナダ人大学生(男性40人,女性106人)を対象に7日間の日記式調査を行い,自尊心レベル,自尊心変動性,ネガティブな出来事の頻度,時期を想定しない将来への期待,5年後への期待を測定した。予測どおり,人間関係に関するネガティブな出来事を多く経験した高自尊心者の間で,自尊心変動性と,時期を特定しない将来,5年後への期待との正の関連が見られた。このことは,遠い将来への肯定的な期待が,不安定な高自尊心を持つ人にとって,ネガティブな出来事によって受けた脅威を軽減する機能を持つことを示唆している。
3 0 0 0 OA ヤマメのせっそう病に対するチョウモドキの寄生の影響の検討
- 著者
- 志村 茂 井上 潔 工藤 真弘 江草 周三
- 出版者
- 日本魚病学会
- 雑誌
- 魚病研究 (ISSN:0388788X)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.37-40, 1983-06-30 (Released:2009-10-26)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 4 9
1) ヤマメを供試魚として,せっそう病の発症およびそれによる斃死に関するチョウモドキの寄生の影響を,感染実験(菌浴法)を行なって調べた。2) チョウモドキ寄生区での斃死率は非寄生区のそれよりも明らかに高かった。3) せっそう病患部と寄生部位との相関関係は特に認められなかった。4) 斃死魚1尾あたりのせっそう病患部の面積は,寄生区の斃死魚の方が著しく大きかった。
3 0 0 0 OA 情報の信頼性
- 著者
- 福井 逸治
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.8, pp.651-661, 1994-11-01 (Released:2008-05-30)
本稿は第172回技術情報活動研究会における講演を編集, 収録したものである。演者は毎日新聞社での記者活動および現在務める紙面審査に関わる職務の経験を基に, 新聞やテレビ報道における虚報と誤報のいくつかの事例を挙げながら, 情報の信頼性について様々な角度から分析を行った。虚報や誤報や事実を故意にねじ曲げた曲報など, 真実ではない情報がなぜ生まれたのか, その過程を解き明かすことによって, 情報の持つ不完全性を示した。そして情報とは主観の集大成であるとして, そのことを充分に認識して, 受け手は受け取る力を養う必要があり, 作り手もまた真実を追求する努力を常に行う必要があると説いた。それらを怠ると情報は, 人権侵害をも引き起こすことを, 具体例を挙げて示した。
3 0 0 0 OA ニホンウナギ(Anguilla juponica)卵巣由来細胞株について
- 著者
- 陳 秀男 郭 光雄
- 出版者
- 日本魚病学会
- 雑誌
- 魚病研究 (ISSN:0388788X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.3, pp.129-137, 1981-11-30 (Released:2009-10-26)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2 13
ニホンウナギの(Anguilla japonica)卵巣から株化細胞EO-2を確立した。その細胞は32±1℃下で,10%の牛胎児の血清を加えた培地Leibovitz's L-15を用いて,19ケ月の間に110代継代している。また20~37℃の範囲でEO-2株化細胞を維持できた。本株化細胞は,大型または小型の核をもつ線維芽性細胞から成っている。大部分の培養細胞中に多核細胞が存在していた。100個の細胞分裂中期のEO-2細胞について計数した染色体数は,38を中心にして22から74の範囲であった。低い濃度で細胞を接種すると,8%しか付着しなかった。EO-2細胞はEVE, EVEX及びEVAに対して感受性を示した。この3種のウイルスに対するEO-2細胞の感受性は, RTG-2, FHM細胞のそれよりも高かった。この株化細胞は,細菌,真菌及びマイクロプラズムに感染していないことがわかった。
3 0 0 0 OA 柿の表象表現にみる風景観の変遷に関する研究
- 著者
- 工藤 豊 小野 良平 伊藤 弘 下村 彰男
- 出版者
- 公益社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.5, pp.369-372, 2007-03-30 (Released:2009-03-31)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 3
Kaki is one of the most familiar fruit trees in Japan and a landscape with kaki tend to be connected with a nostalgic image of an autumn rural landscape. In this respect, a landscape with kaki can be seen as a Japanese “prototype-landscape.” The point we have to focus on here is that common image and feeling about kaki are shared among the Japanese. It is due to our “landscape viewpoints”, a common “way of seeing” shared in a specific social group. This study considers how our landscape viewpoints have been changed by analyzing the representation (waka, haiku and painting) of kaki as an expression of landscape. Kaki might have been one of the most familiar fruits in Japan throughout the history. It was, however, after the latter half of the 17th century, when haiku had been established and spread, that a landscape with kaki started to be expressed positively. This can be explained that our “landscape viewpoints” had been turned from the traditional one, in which waka played the most important part, into the modernized one, through some new cultural activities which began in the Edo era. New landscape discovered by new culture in the Edo era had been combined with rural landscape, and have been regarded as Japanese prototype-landscape.
3 0 0 0 OA 機能性発声障害
- 著者
- 牧山 清 松崎 洋海 平井 良治
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.117, no.9, pp.1173-1178, 2014-09-20 (Released:2014-10-07)
- 参考文献数
- 21
機能性疾患とは解剖学的あるいは病理学的な異常がないにもかかわらず臓器や器官などの働きが低下する疾患を指す. しかし, 国内外では喉頭ファイバー検査上で器質的な異常がなく, かつ運動麻痺がない疾患群を臨床的な意味での機能性発声障害と呼ぶことが定着している. 本稿では狭義の機能性発声障害, 変声障害, 心因性発声障害, 痙攣性発声障害, 喉頭振戦症について診断のポイントを述べる.
3 0 0 0 OA 広域METROSによる首都圏のヒートアイランドの解析
- 著者
- 亀野 勝彦 永谷 結 柄澤 孝和 梅木 清 本條 毅 三上 岳彦
- 出版者
- 一般社団法人 環境情報科学センター
- 雑誌
- 環境情報科学論文集 Vol.22(第22回環境情報科学学術研究論文発表会)
- 巻号頁・発行日
- pp.197-202, 2008 (Released:2011-01-07)
本研究では,ヒートアイランド分布への風向の影響を首都圏スケールで明らかにすることを目的とし,夏季における広域METROSの気温データおよびAMeDASの降雨量と風向,風速データを使用して,観測領域内で1日の内に卓越する風向を東西南北別に解析に用いた。気温差を時系列解析した結果,ヒートアイランドは夜間に都心を,日中に都心および関東平野中央部を中心とし,風向変化から影響を受け,風下側に移動することが明らかになった。この移動は2~3時間の短い期間の風向変化に伴って,急速に起こることがあった。また南東の時には神奈川県沿岸部で,東京湾沿岸部と比較して,海風による強い冷却効果を受けることが明らかになった。
3 0 0 0 OA 心因性視力障害の視野
- 著者
- 須田 和代 森 由美子 調 広子 大池 正勝 山本 節
- 出版者
- 公益社団法人 日本視能訓練士協会
- 雑誌
- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.151-158, 1992-11-20 (Released:2009-10-29)
- 参考文献数
- 24
従来,心因性視力障害患者の視野には管状視野・螺旋状視野・求心性狭窄等の特有なものが検出されることがあるとの報告がされているが,視野とは視覚感度の分布であるという定義に基づくと,その視野には矛盾する点がみられる。我々は心因性視力障害疑いの患者に対しても,本来の概念に基づいて視野検査を行ってきた。その結果,他院から異常視野として紹介された症例も含め,全例正常視野を得,他の器質的疾患を否定する一助に充分なり得た。特有な視野が心因性に限るものではないことから,心因性視力障害疑いの患者に対しては,その心因的要素を取り除くよう配慮し,可能な限り正確に診断できる検査結果を得るべく努力すべきであると考える。