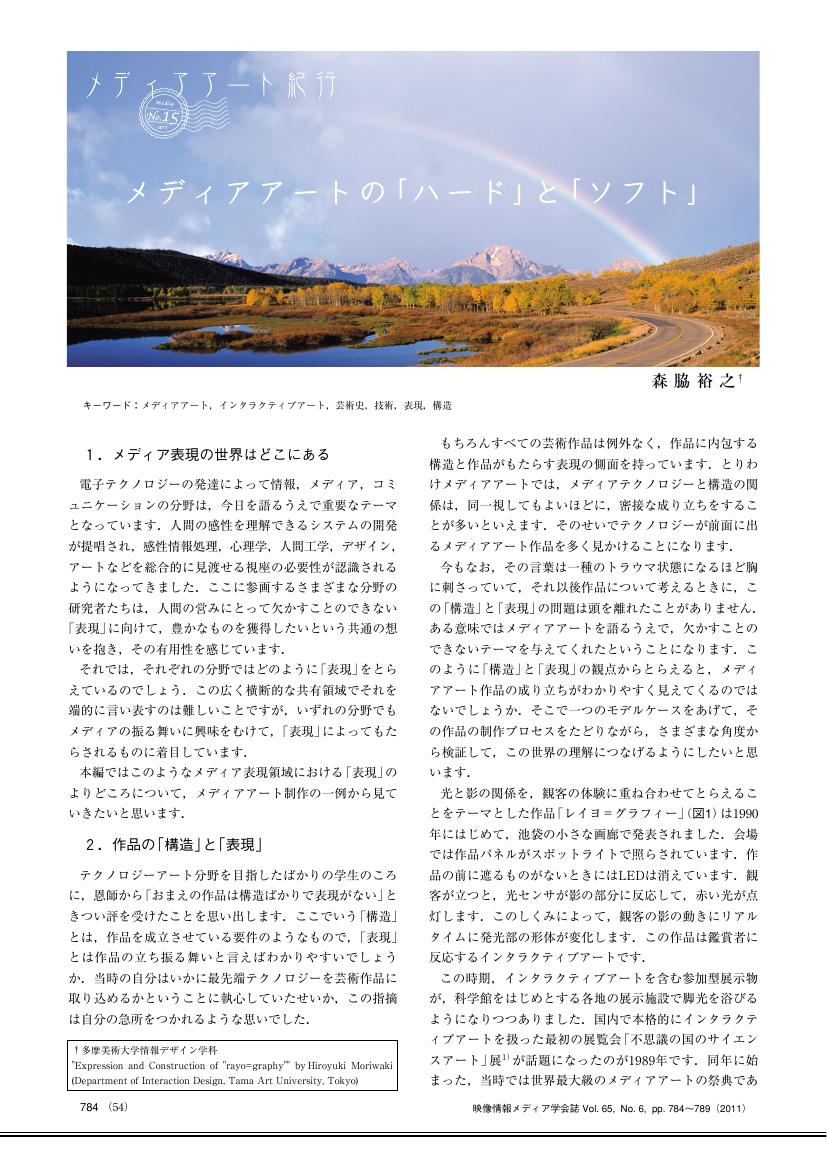2 0 0 0 OA 島嶼性固有植物の保全ゲノミクス
2 0 0 0 OA 時間について
2 0 0 0 OA 脅威性の知覚が男性顔に対する魅力評定に与える影響
- 著者
- 高橋 翠 遠藤 利彦
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 認知心理学研究 (ISSN:13487264)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.165-173, 2013-02-28 (Released:2013-04-05)
- 参考文献数
- 25
顔の魅力に対する進化心理学的アプローチは,異性の容貌において繁殖に寄与する資質の手がかりがヒトに普遍的な魅力規定因であると仮定する.しかし,男性顔において「男らしさ」が知覚される容貌は優れた資質のシグナルであるが,女性は必ずしも魅力を知覚しない.本研究では,「男らしい」容貌から知覚される脅威性もまた,そうした容貌に対する魅力評価を抑制している可能性に着目した.男性顔(無表情・直視)に対する印象評価の多変量解析的検討(研究1),および表情(無表情・笑顔)と視線(直視・逸視)の異なる条件下での魅力評定(研究2)を通じて,評定者の性にかかわらず,脅威性(および脅威表情)の知覚が「男らしい」容貌に対する魅力評価を抑制している可能性が示唆された.ただし研究2では,男女で異なる結果として,女性評定者のみで脅威性が相対的に知覚されにくい場合に「男らしさ」の優れた資質のシグナルとしての側面が魅力として知覚されるようになる可能性も示唆された.
2 0 0 0 OA 少子化を考える 女性の立場から
- 著者
- 伊藤 セツ
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.40-44, 1999-01-01 (Released:2009-12-21)
2 0 0 0 OA 異種移植の未来動向
- 著者
- 佐原 寿史 関島 光裕 山田 和彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本移植学会
- 雑誌
- 移植 (ISSN:05787947)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.016-023, 2015-03-10 (Released:2015-03-31)
- 参考文献数
- 49
Although improvements in operative techniques and immunosuppressions have paved the way for increases in the organ donor pool through living donor kidney donations, a vast disparity remains between the number of organs available for transplantation and the demand. Indeed, though progress has been made in the fields of regenerative medicine and stem cell technologies, neither de novo nor regenerated tissues are currently capable of sustaining life in animal models. Xenotransplantation would provide an inexhaustible supply of donor organs. Although there have been reports of severe immunologic response between swine and humans, much progress has been made in the past decade largely because of advances in our understanding of the xenoimmunobiology of pig-to-nonhuman primate transplantation as well as the availability of pigs that have undergone genetic modifications, including the alpha 1,3-galactosyltransferase gene knockout (GalT-KO) swine. The results of preclinical transplantation studies with pig organs or cells have been encouraging when co-stimulatory blockade or more-advanced tolerance-inducing treatment strategies were used. In these studies, the survival times for heterotopic heart grafts were more than a year, for life-supporting kidneys it was approximately three months, and for islets, six months. In this review, we summarize recent progress in the field and discuss strategies for successful clinical trials of xenotransplantation.
2 0 0 0 OA 私の履歴書
- 著者
- 鈴木 正三
- 出版者
- 公益社団法人 全国大学体育連合
- 雑誌
- 大学体育 (ISSN:02892154)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.45-50, 1986-03-15 (Released:2017-07-03)
2 0 0 0 OA 誤概念の修正に有効な反証事例の使用方略
- 著者
- 進藤 聡彦 麻柄 啓一 伏見 陽児
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.162-173, 2006-06-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 2 1
これまで学習者の誤概念を修正するために, 反証例を用いる方法と用いない方法の2つのタイプの教授法が提案されてきた。しかし, これらの方法はそれぞれに短所を持つ。本研究ではこれら2つの教授法を組み合わせた新しい方法を提案した。それは以下の方法であった。まず, 誤概念を適用した場合には正しい解決ができない問題を提示する。続いて誤概念を持っていても解決可能な類似の問題を提示する。その問題での正しい解決に基づいて, 学習者に正しいルールを把握させ, さらにそのルールを一連の類似問題に対して適用できるようにするというものである。この方法と従来の2つの方法が誤概念の修正に及ぼす効果を検討した。76名の大学生が3群のいずれかに割り当てられた。被験者の多くは, 真空は物を吸い寄せるという誤概念を持っていた。実験の結果, 今回提案した方法は他の2つの方法より次の3点で優れていることが明らかとなった。まず, 学習者の誤概念を最も効果的に修正できた。また, 自分の知識が変化したという意識を学習者に持たせやすかった。さらに学習者の興味を喚起した。今回提案した方法は誤概念の修正に効果的であることが明らかとなった。この方法は「融合法」と名づけられた。
2 0 0 0 OA 放射線事故時におけるセシウム除去としてのプルシアンブルー
- 著者
- 小林 信義 山本 泰 明石 真言
- 出版者
- Japan Health Physics Society
- 雑誌
- 保健物理 (ISSN:03676110)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.323-330, 1998 (Released:2010-02-25)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 7 8
Prussian blue, a blue pigment, belongs to the ferric cyanoferrate (II) group. It binds univalent metal ions, and the binding activity depends on their ionic radius. Prussian blue is not absorbed from the gastrointestinal tract in a significant amount. The cesium is entero-enteric cycled through the intestine. Prussian blue inhibits the reabsorption of the cesium. Many studies using experimental animals showed that the oral administration of Prussian blue increases the rate of the fecal excretion of radiocesium which results in shortening its biological half life. The accident in Goiania, Brazil, in 1987 showed that Prussian blue effectively accelerated the removal of radiocesium without toxicity. In the present review, we describe Prussian blue from a biological aspect and discuss its clinical application for the decontamination of cesium in radiation accidents.
2 0 0 0 OA 家族称呼からみた家族関係
- 著者
- 津留 宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.12-20,61, 1969-10-15 (Released:2013-02-19)
小学校五年生を通してみた603世帯, 約3500名の家族相互の称呼において, 比較的多数を占めた呼び方は次の通りである。夫→妻1. 名前の呼び捨て (45%) 2. 「お母ちやん」「お母さん」 (合せて29%)妻→夫1. 「お父さん」「お父ちやん」 (合せて73%)子→父1. 「お父ちやん」 (67%) 2. 「お父さん」 (27%)子→母1. 「お母ちやん」 (78%) 2. 「お母さん」 (18%)父→子1. 名前の呼び捨て (83%) 2. 名前または略名に「ちやん」付け (13%)母→子1. 名前の呼び捨て (67%) 2. 名前または略名に「ちやん」付け (27%)父→祖父「おじいさん」「おじいちやん」 (合せて70%)母→祖父「おじいさん」「おじいちやん」 (合せて80%)父→祖母「おばあさん」「おばあちやん」 (合せて70%)母→祖母「おばあさん」「おばあちやん」 (合せて80%)祖父→父1. 名前の呼び捨て (60%) 2. 「お父さん」「お父ちやん」 (合せて25%)祖母→父1. 名前の呼び捨て (44%) 2. 「お父さん」「お父ちやん」 (合せて40%)祖父→母1. 名前の呼び捨て (80%) 2. 「お母さん」「お母ちやん」 (合せて24%)祖母→母1. 名前の呼び捨て (63%) 2. 「お母さん」「お母ちやん」 (合せて10%)兄→弟1. 名前の呼び捨て (71%) 2. 名前または略名に「ちやん」付け (23%)姉→弟1. 名前の呼び捨て (60%) 2. 名前または略名に「ちやん」付け (32%)兄→妹1. 名前の呼び捨て (66%) 2. 名前または略名に「ちやん」付け (32%)姉→妹1. 名前の呼び捨て (55%) 2. 名前または略名に「ちやん」付け (43%)弟→兄1. 「兄ちやん」「お兄ちやん」またはこれの付くもの (合せて62%) 2. 名前または略名に「ちやん」付け (17%)妹→兄1. 「兄ちやん」「お兄ちやん」またはこれの付くもの (合せて59%) 2. 名前または略名に「ちやん」付け (22%)弟→姉1. 「姉ちやん」「お姉ちやん」またはこれの付くもの (合せて63%) 2. 名前または略名に「ちやん」付け (17%)妹→姉1. 「姉ちやん」「お姉ちやん」またはこれの付くもの (合せて68%) 2. 名前または略名に「ちやん」付け (20%)尚, 調査結果全般を通し次のような傾向が看取される。1夫婦間の称呼は一般に甚だ不明確であり, 特に妻→夫の場合は瞹眛である。多くは子が父を呼ぶ呼び方を借りている。2一般標準語とされる子→父母の「お父さん」「お母さん」, 弟妹→兄姉の「兄さん」「姉さん」は意外に少い。一般に家族間は「さん」よりは「ちやん」付けが多い。但し「おじいさん」「おばあさん」はこの限りでない。3夫婦間及び子, 祖母の父に対する称呼よりみて, 尚母よりは父に対して敬意が強い。4きようだい間の呼び方は, よく家庭の教育的配慮の如何を反映している。5農村には全く不当な称呼がかなりみられる。住宅地にはこれがない。一般に敬称の点では農村, 工業地がより乱れている。6家族称呼は一般に子供本位の呼び方になろうとする。日本の家庭の子供本位的性格を表わしている。7家族称呼にも明らかに過渡期的様相がみられる。即ち従来の標準的な家族称呼が崩れて新しい称呼が生じつつある。旧い称呼の権威的, 序列的, 形式的なものが, より平等的, 人間的, 親愛的な呼び方にとつて代わられようとしている。恐らくこれは家族制度の変化と共に, 封建的家族意識の減退, 個人意識の昂揚等によるものであろう。8尤も農村と住宅地の一部では標準的な称呼に尚, 関心が強いようにみえる。これは次のように解せられる。即ち日本の家族称呼の標準語はやや保守的なものであるが, 農村はその家族制度の保守性からこれを残し, 住宅地の知識階級では保守的というのではなくむしろ教育的配慮から標準語に依ろうとしているのであろう。従つて両方の性格を欠く商工地では最も称呼の乱れがみられるのである。
- 著者
- 長谷川 元洋 上野 顕子 新谷 洋介 清水 克博
- 出版者
- 日本消費者教育学会
- 雑誌
- 消費者教育 (ISSN:13451855)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.123-133, 2021 (Released:2021-10-27)
- 参考文献数
- 11
The purpose of this study was to develop a consumer education lesson which enables deep active learning in online classes. We constructed the lesson using a matrix for designing lessons to realize “deep learning”, which was to ensure the lesson quality in online classes. In addition, information tools were selected and combined so that the students were able to do group work in the online classes. We used the text mining system to analyze and compare papers submitted by students who attended in-person classes in 2019 to ones handed in by students who attended mainly online classes for the same course in 2020. As a result, it was confirmed that deep active learning could be realized even in the online classes.
- 著者
- 北條 理恵子 坂本 龍雄 黒河 佳香 藤巻 秀和 小川 康恭
- 出版者
- 独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
- 雑誌
- 労働安全衛生研究 (ISSN:18826822)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.51-56, 2011 (Released:2011-09-30)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
室内空気中の化学汚染物質による健康障害と考えられる,シックハウス症候群(SHS)と化学物質過敏症(CS)の発症や増悪には「におい」が関与することが報告されている.しかしながら,今までに室内空気汚染物質の健康影響を「におい」自体からとらえた実験研究はほとんどない.今後,労働衛生の重要な課題として不快な「におい」発生の予防と対策が必要である.我々は,職場で問題となる揮発性有機化合物(VOCs)および真菌由来揮発性有機化合物(MVOCs)の「におい」に焦点をあて,「におい」そのものが引き起こす健康影響を実験動物により検討する嗅覚試験法の確立を計画している.本稿では,近年問題となっている室内空気汚染物質による健康影響について解説したのち,嗅覚試験系の確立のため,我々が開発した基盤的な試験法を紹介する.
2 0 0 0 OA 撥水性表面上に形成する空気膜を利用した流体摩擦抵抗の低減
- 著者
- 徳永 純一郎 延永 尚志 中谷 龍男 岩崎 徹 福田 和廣 國武 吉邦
- 出版者
- The Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers
- 雑誌
- 日本造船学会論文集 (ISSN:05148499)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.183, pp.45-52, 1998 (Released:2009-09-16)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1 3
This paper proposes a new concept for the frictional drag reduction technique. The new technique makes use of a specific coating surface (Super-Water-Repellent Surface) which has a highly repellent effect and an ability to form a thin air film over it under water. When supplying a small amount of air to the specific coating surface from the outside continuously, the supplied air (secondary air) is absorbed in and joined with the primary air film and spread to form a filmy air flow along the surface. This technique reduces the frictional drag because of this phenomenon.A frictional drag test in the rectangular pipe flow and a resistance test of horizontal flat plate were carried out in order to verify the validity of this technique. As a result of these tests, it was confirmed that drag reductions of about 80% and about 55% were obtained for flow velocities of 4 m/s and 8 m/ s, respectively.
2 0 0 0 OA パソコン作業による疲労の軽減に関する研究 アイマスクを使用した場合
- 著者
- 佐々 尚美 左達 秀敏 矢田 幸博 梁瀬 度子
- 出版者
- 一般社団法人 日本人間工学会
- 雑誌
- 日本人間工学会大会講演集 日本人間工学会第50回記念大会
- 巻号頁・発行日
- pp.510-511, 2009 (Released:2011-05-20)
- 著者
- 亀田 豊 山下 洋正 尾崎 正明
- 出版者
- 公益社団法人 日本水環境学会
- 雑誌
- 水環境学会誌 (ISSN:09168958)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.7, pp.367-374, 2008 (Released:2010-01-09)
- 参考文献数
- 27
The occurrence of sixteen synthetic fragrance materials and nine organic UV filters was investigated in influent, effluent, and excess sludge in 47 sewage treatment plants (STPs) in Japan. Their loads into the STPs and into an aquatic environment via STPs were estimated according to their influent and effluent concentrations. Highest loads in influent into the STPs and effluent into the aquatic environment were 1.79 mg · day-1 · inch-1 for homosalate and 0.31 mg · day-1 · inch-1 for ethylhexyl methoxy cinnamate (EHMC), respectively. Removal ratios of the fragrance materials and organic UV filters in the STPs were also calculated. The removal ratios varied markedly among compounds. The minimums of the removal ratios were higher than 90 % for benzyl acetate, methyl dihydrojasmonate, octyl salicylate, homosalate, benzyl salicylate, isoamyl-p-methoxycinnamate, and octocrylene, moreover, the lowest removal ratio was approximately 50 % for EHMC. The removal ratios due to adsorption onto the sludge to the total removal ratio were evaluated from the concentrations of compounds in the return sludge. The highest ratio of the removal due to adsorption onto the sludge to the total removal ratio was 40 % for 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl-cyclo-penta-[g]-2-benzo-pyrane and 7-acetyl-1,1,3,4,4,6-hexamethyl tetrahydro-naphthalene. Many of the organic UV filters measured were evaluated to be less removed by adsorption because of the markedly higher adsorption to the influent sludge than to the return sludge. Further research on their adsorption and biodegradation in the STPs is required.
2 0 0 0 OA 伊豆諸島三宅島における亜種ヤマガラの初記録
- 著者
- 山本 裕 樋口 広芳
- 出版者
- Yamashina Institute for Ornitology
- 雑誌
- 山階鳥類学雑誌 (ISSN:13485032)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.144-148, 2004-03-20 (Released:2008-11-10)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 2 3
ヤマガラParus variusの1亜種オーストンヤマガラParus varius owstoniの分布域である伊豆諸島南部の三宅島(34°05'N,139°32'E)で,亜種ヤマガラP.v.variusと思われる2個体が1996/1997年の秋冬期に観察された。これら2個体は,羽色や計測値から,亜種ヤマガラP.v.variusと判断された。これら2羽は,三宅島南部のスダジイCastanopsis cuspidata var. Sieboldiiが優占する常緑広葉樹林で,1997年4月まで継続して観察されたが,その後,姿を消した。亜種オーストンヤマガラの分布域での亜種ヤマガラの確認は,本報告が初めてである。
2 0 0 0 OA 食糧市場における公的管理・規制の意義
- 著者
- 三島 徳三
- 出版者
- Japan Society for Distributive Sciences
- 雑誌
- 流通 (ISSN:09149937)
- 巻号頁・発行日
- vol.1992, no.5, pp.31-39, 1992 (Released:2010-08-05)
2 0 0 0 OA メディアアートの「ハード」と「ソフト」
- 著者
- 森脇 裕之
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.6, pp.784-789, 2011 (Released:2013-06-01)
- 参考文献数
- 3
- 著者
- 山本 雅史 福田 麻由子 古賀 孝徳 久保 達也 冨永 茂人
- 出版者
- 一般社団法人 園芸学会
- 雑誌
- 園芸学研究 (ISSN:13472658)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.7-12, 2010 (Released:2010-01-26)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 8 9
奄美大島の東側に位置する喜界島特産の在来カンキツであるケラジミカン(C. keraji hort. ex Tanaka)の来歴について検討した.Inter Simple Sequence Repeat(ISSR)分析において,多型が認められたバンドを用いて共有バンド率を算出した.ケラジミカンはクネンボ(C. nobilis Lour.)と最も共有バンド率が高く(0.823),次いでキカイミカン(C. keraji hort. ex Tanaka)との共有バンド率が高かった(0.688).ケラジミカンに認められた16本のバンドはすべてキカイミカンまたはクネンボにも出現した.この3者間でケラジミカンのみに出現する独自のバンドは無かった.この結果から,ケラジミカンがクネンボとキカイミカンとの交雑種である可能性は否定できなかった.葉緑体DNA分析においてはケラジミカン,クネンボおよびキカイミカンは常に同一のバンドパターンを示し,識別できなかった.いずれも自家不和合性であるケラジミカン,キカイミカンおよびクネンボ間の交雑では,ケラジミカンとキカイミカンの正逆交雑において不和合関係が認められ,両者の不和合性に関する遺伝子型が一致することが確認できた.この両者はクネンボとは交雑和合性であった.クネンボとキカイミカンがケラジミカンの親であると仮定した場合,キカイミカンが花粉親の場合に,ケラジミカンはキカイミカンと不和合性になる.以上から,ケラジミカンはクネンボを種子親,キカイミカンを花粉親として発生した可能性があることがわかった.
2 0 0 0 OA 手根管症候群手術時にみられた正中神経反回枝の変異
- 著者
- 今村 宏太郎
- 出版者
- West-Japanese Society of Orthopedics & Traumatology
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.170-173, 2001-03-25 (Released:2010-02-25)
- 参考文献数
- 12
One hundred twenty-nine median nerves of 105 cases were reviewed for variations during operations to treat carpal tunnel syndrome. The variations in the course of the motor branches (Poisel. 1974) were the extraligamentous type in 122 hands (94.6%), the subligamentous type in 2 hands (1.6%), and the transligamentous type in 5 hands (3.9%). Accessory branches were found in 10 hands (7.8%), a high division of the median nerve in 4 hands (3.1%) and median artery in 4 hands (3.1%). In 123 (95.3%) of 129 hands, the recurrent baranch arose from the radial aspect of the median nerve, in 3 hands (2.2%) from the central-radial aspect, in 3 hands (2.2%) from the central aspect, and in no hands from the ulnar side. To avoid the injuryy of the motor branches during operation of the carpal tunnel syndrome, special attention must be paid to the variation of the recurrent branch.
2 0 0 0 OA 小学生における上半身トレーニングが運動能力に及ぼす効果
- 著者
- 新本 惣一朗 山崎 昌廣
- 出版者
- 日本生理人類学会
- 雑誌
- 日本生理人類学会誌 (ISSN:13423215)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.67-73, 2011-05-25 (Released:2017-07-28)
- 参考文献数
- 17
The purpose of this study was to investigate the effects of a continuous general upper-body strength training regime on athletic ability in 10-11 year-old elementary school children. During physical education class, the children performed push-ups, abdominal muscle training and flexibility training twice a week for seven months. Through the training regime, the boys improved their throwing distance, abdominal muscle strength, grip strength and running speed. However, the girls only showed an improvement in their grip strength. The training program produced no effect with regards to agility or jumping power in either sex. Moreover, there was no significant improvement in flexibility for either sex. This study indicates that although upper-body training during elementary school physical education classes is effective for improving physical fitness, the effects are different for boys and girls even with the same training.