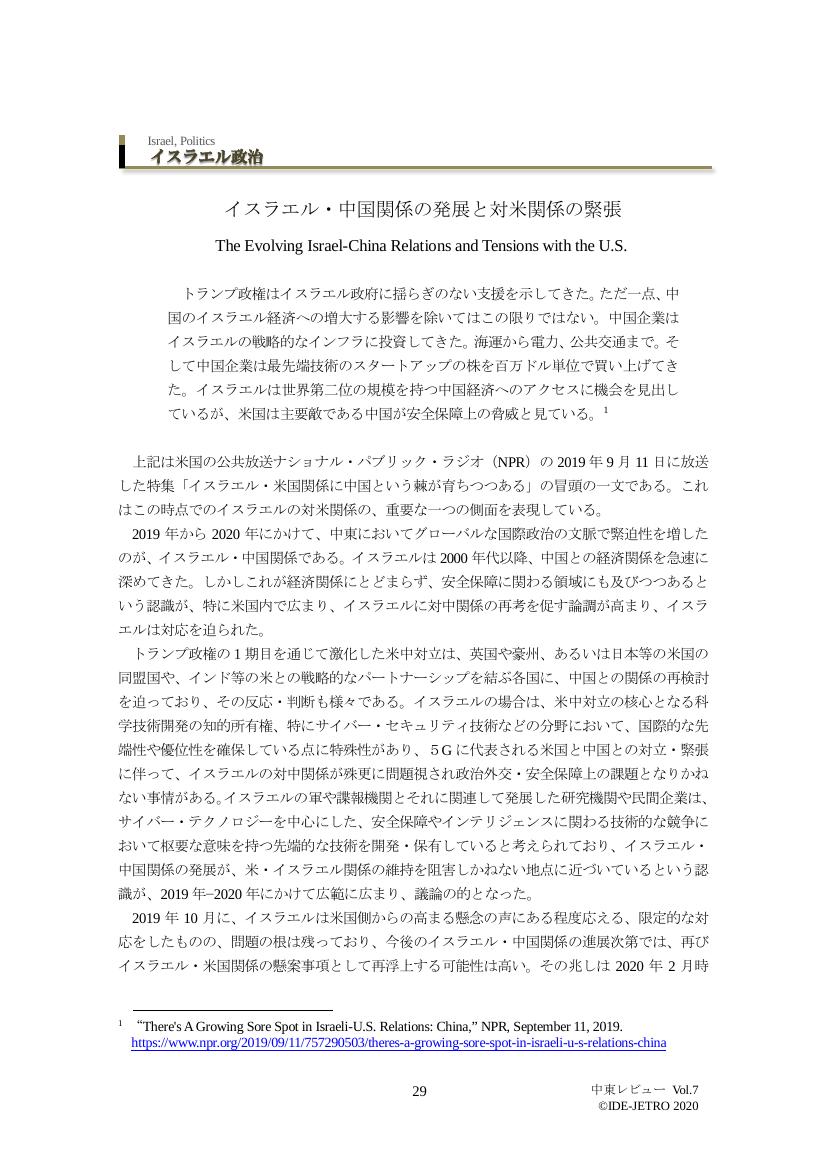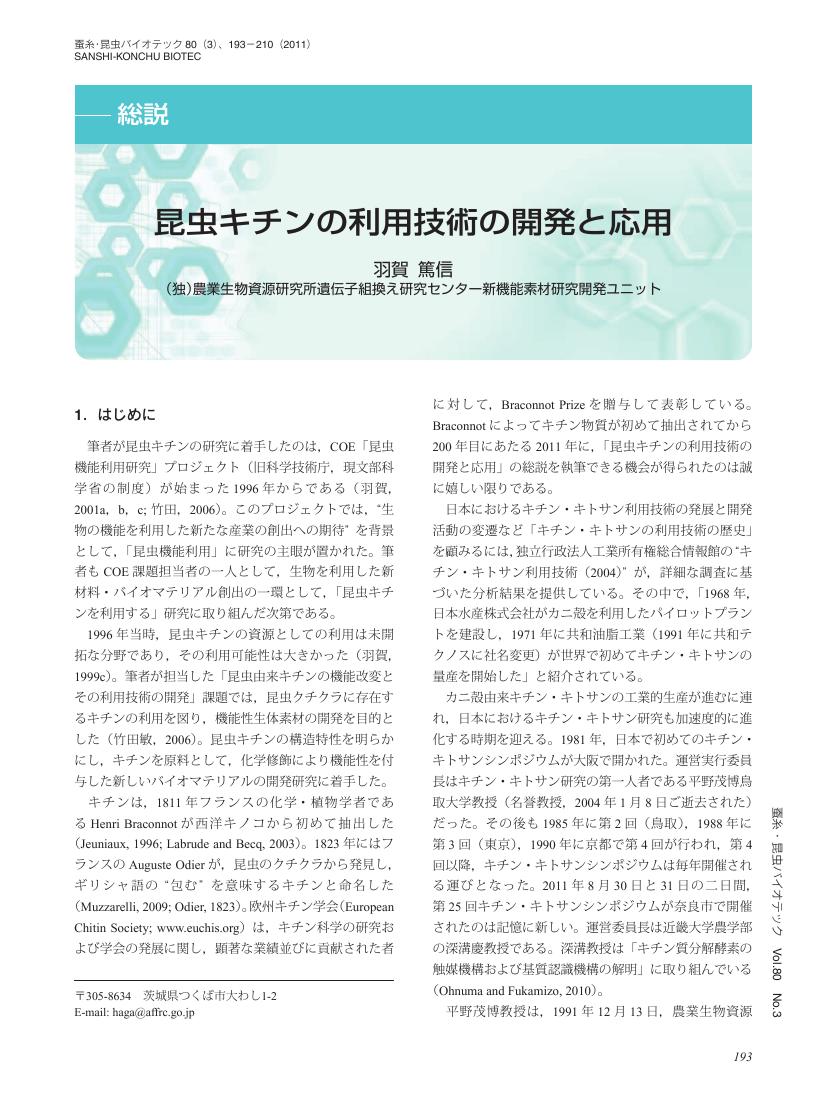126 0 0 0 OA 人工地震による日本列島の地殻構造
- 著者
- 吉井 敏尅
- 出版者
- 公益社団法人 日本地震学会
- 雑誌
- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.4, pp.479-491, 1994-03-14 (Released:2010-03-11)
- 参考文献数
- 124
- 被引用文献数
- 5 5
The Research Group for Explosion Seismology of Japan, founded in 1950, have continuously conducted many explosion seismic observations in various regions of the Japanese Islands. Active investigations of the Group have provided important data about the crustal structure beneath the Japanese Islands which is quite useful as the most basic information for various researches of geosciences. After ages of the cradle in 1950's, the Group experienced large scale investigations under the International Upper Mantle Project and the International Geodynamics Project in 1960's and 1970's, and general features of crustal structure beneath the Japanese Islands became clear through the investigations in this period. Since 1979, the Group has conducted the investigations under the Japanese Earthquake Prediction Project in order to accumulate basic data for earthquake prediction researches. The series of these investigations have been conducted through highly dense observations, and the obtained data have revealed quite complex structure of the crust beneath the Japanese Islands. Application of some of data processing techniques in reflection survey to those data also revealed clear images of the subducted Philippine Sea plate beneath the Japanese Islands.
126 0 0 0 OA 量子エネルギーテレポーテーション(<シリーズ>量子論の広がり-非局所相関と不確定性-, 解説)
- 著者
- 堀田 昌寛 遊佐 剛
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.9, pp.613-622, 2014-09-05 (Released:2019-08-22)
現在広範なテーマを巻き込みながら,量子情報と量子物理が深いレベルから融合する量子情報物理学という分野が生まれ成長しつつある.なぜ様々な量子物理学に量子情報理論が現れてくるのだろうか.それには量子状態が本質的に認識論的情報概念であるということが深く関わっていると思われる.ボーアを源流とする認識論的な現代的コペンハーゲン解釈は量子情報分野を中心に定着してきた.この量子論解釈に基づいた量子情報物理学の視点からは存在や無という概念も認識論的であり,測定や観測者に対する強い依存性がある.本稿ではこの「存在と無」の問題にも新しい視点を与える量子エネルギーテレポーテーション(Quantum Energy Teleportation;QET)を解説しつつ,それが描き出す量子情報物理学的世界観を紹介していく.QETとは,多体系の基底状態の量子縺れを資源としながら,操作論的な意味のエネルギー転送を局所的操作と古典通信(Local Operations and Classical Communication;LOCC)だけで達成する量子プロトコルである.量子的に縺れた多体系の基底状態においてある部分系の零点振動を測定すると,一般に測定後状態の系は必ず励起エネルギーを持つ.これは基底状態の受動性(passivity)という性質からの帰結である.このため情報を測定で得るアリスには,必ず測定エネルギーの消費という代償を伴う.またアリスの量子系は量子縺れを通じてボブの量子系の情報も持っている.従ってアリスは,ボブの系のエネルギー密度の量子揺らぎの情報も同時に得る.これによって起こるボブの量子系の部分的な波動関数の収縮により,測定値に応じてアリスにとってはボブの量子系に抽出可能なエネルギーがまるで瞬間移動(テレポート,teleport)したように出現する.一方,この時点ではまだボブはアリスの測定結果を知らない.またアリスの測定で系に注入された励起エネルギーもまだアリス周辺に留まっており,ボブの量子系には及んでいない.従って対照的にボブにとってはボブの量子系は取り出せるエネルギーが存在しない「無」の状態のままである.このように,現代的コペンハーゲン解釈で許される観測者依存性のおかげで,エネルギーがテレポートしたように見えても因果律は保たれている.非相対論的モデルを前提にして,系のエネルギー伝搬速度より速い光速度でアリスが測定結果をボブに伝えたとしよう.アリスが測定で系に注入したエネルギーはボブにまだ届いていないにも関わらず,情報を得たボブにも波動関数の収縮が起こり,自分の量子系から取り出せるエネルギーの存在に気付く.そしてボブは測定値毎に異なる量子揺らぎのパターンに応じて適当な局所的操作を選び,エネルギー密度の量子揺らぎを抑えることが可能となる.その結果ボブは平均的に正のエネルギーを外部に取り出すことが可能となる.これがQETである.このQETは量子ホール系を用いて実験的に検証できる可能性が高い.一方,相対論的なQETモデルはブラックホールエントロピー問題にも重要な切り口を与える.
126 0 0 0 OA 日本における学術研究団体(学会)の現状
- 著者
- 埴淵 知哉 川口 慎介
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.137-155, 2020 (Released:2020-04-04)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 5 3
近年,学術研究団体(学会)における会員数の減少が懸念されている.本稿では,日本学術会議が指定する協力学術研究団体を対象として,日本の学会組織の現状および変化を定量的に俯瞰することを試みた.集計の結果,学会のおよそ3分の2は会員数1,000人未満であり,人文社会系を中心に小規模な学会が多数を占める現状が示された.過去10年余りの間に個人会員数が減少した学会は3分の2にのぼるものの,それは理工系,中小規模,歴史の長い学会で顕著であり,医学系や大規模学会ではむしろ会員数を増加させていた.また,学会の新設に対して,解散は少数にとどまっていた.結果として,既存学会の維持および会員数の選択的な増減,そして新設学会の増加が交錯している状況が示された.そして,地理学関連学会は学術界全体の平均以上に会員減少が進んでおり,連合体や地方学会を含めてそのあり方を検討する必要性が指摘された.
126 0 0 0 OA 中国古典様式家具の日本への影響に関する研究 : 坐臥具の牀・榻・〓を中心として
- 著者
- 石丸 進 石村 真一
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3, pp.1-10, 2004-09-30 (Released:2017-07-19)
- 参考文献数
- 25
本研究は,わが国の室内・家具と中国家具文化とのかかわりを,坐臥具を中心に比較・検証した。その結果,次のことが明らかとなった。(1)中国坐臥具の床(牀ともかく)は寝台であり,日本の「床の間」「床几」「床子」などの語源や形態に影響した。(2)「榻」は,日本の縁台や店棚形式の坐具と類似する。(3)中国北方の寝床「?」での起居様式は日本と同じ床坐であった。?で使用する「?卓」は、日本の「座卓」の原型であった。(4)?の起源は,古代中国の俎を原型とし,小?子は,日本の踏台や風呂腰掛けと同一構造・形態であった。(5)条?は,日本の床几と構造・形態で一致し,使用法も類似していた。
126 0 0 0 OA 日本人における自尊感情の性差に関するメタ分析
- 著者
- 岡田 涼 小塩 真司 茂垣 まどか 脇田 貴文 並川 努
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.49-60, 2015-07-31 (Released:2015-08-07)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 10 5
本研究では,メタ分析によって日本人の自尊感情の性差を検討した。また,性差の程度に影響を与える調整変数として,年齢段階,調査年,翻訳種の効果を検討した。包括的なレビューを通して,Rosenberg Self-Esteem Scaleを用いて日本人の男女ごとの自尊感情を測定している研究を検索した。検索の結果,1982年から2013年に発表された50研究を収集した。収集された研究をもとに効果量を推定したところ,その値はg=.17 (Hedgesのg)であり,女性よりもわずかに男性の方が高かった。また,調整変数については,年齢段階と調査年によって,自尊感情の性差の程度が異なっていた。本研究の知見は,日本人における自尊感情の性差について論じるための実証的な基盤となり得るものである。
126 0 0 0 OA 怪異の類型と分布の時代変化に関する定量的分析の試み
- 著者
- 鈴木 晃志郎 于 燕楠
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.55-73, 2020 (Released:2020-02-22)
- 参考文献数
- 134
- 被引用文献数
- 3
今日の地理学において,幽霊や妖怪を含む怪異は,専ら民俗学的な手法に依拠して検討されている.しかし隣接分野では,定量的な手法に基づいた知見が数多く存在し,客観性と厳密性を確保することによって学術的信頼性を高める試みが多くなされている.そこで本研究は富山県を対象とし,今からおよそ100年前(大正時代)の地元紙に連載された怪異譚と,ウェブ上に書き込まれた現代の怪異に関するうわさを内容分析し,(1) 怪異を類型化して出現頻度の有意差検定を行うとともに,(2) カーネル推定(検索半径8 km,出力セルサイズ300 m)とラスタ演算による差分の算出により,怪異の出没地点の時代変化を解析した.その結果,現代の怪異は大正時代に比して種類が画一化され,可視性が失われ,生活圏から離れた山間部に退いていることが示された.
126 0 0 0 OA 就学前期における自閉症児の母親の障害受容過程
- 著者
- 夏堀 摂
- 出版者
- 一般社団法人 日本特殊教育学会
- 雑誌
- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.11-22, 2001-11-30 (Released:2017-07-28)
- 被引用文献数
- 5 1
本研究の目的は、障害種別による母親の障害受容過程の差異を検討することである。対象者は、自閉症児の母親55名とダウン症児の母親17名。調査は質問紙法を用い、選択方式および自由記述方式で回想法により回答を求めた。その結果、以下の点が明らかになった。(1)種別によって、障害の疑い、診断、療育開始の時期、心理的混乱がもたらされる時期に有意差が認められた。(2)受容までに要する時間は、ダウン症群に比べ自閉症群の方が有意に長かった。(3)障害種別間で有意な関連が認められた7つの変数は、診断の困難さに関係している変数であった。(4)自閉症児の母親の心理的反応には、障害の疑いから診断までの第一次反応と診断後に生じる第二次反応があった。診断が確定され障害認識に至っていても新たな問題の生起によって、母親の障害受容は阻害されていた。
- 著者
- Takahiro Sanada Tomoko Honda Fumihiko Yasui Kenzaburo Yamaji Tsubasa Munakata Naoki Yamamoto Makoto Kurano Yusuke Matsumoto Risa Kohno Sakiko Toyama Yoshiro Kishi Takuro Horibe Yudai Kaneko Mayumi Kakegawa Kazushige Fukui Takeshi Kawamura Wang Daming Chungen Qian Fuzhen Xia Fan He Syudo Yamasaki Atsushi Nishida Takayuki Harada Masahiko Higa Yuko Tokunaga Asako Takagi Masanari Itokawa Tatsuhiko Kodama Michinori Kohara
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- pp.JE20210324, (Released:2021-11-13)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 18
Background: Tokyo, the capital of Japan, is a densely populated city of >13 million people and thus at high risk of epidemic severe acute respiratory coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection. A serologic survey of anti–SARS-CoV-2 IgG would provide valuable data for assessing the city’s SARS-CoV-2 infection status. This cross-sectional study therefore estimated the anti–SARS-CoV-2 IgG seroprevalence in Tokyo.Methods: Leftover serum of 23,234 hospital visitors was tested for antibodies against SARS-CoV-2 using an iFlash 3000 chemiluminescence immunoassay analyzer (Shenzhen YHLO Biotech) with an iFlash–SARS-CoV-2 IgG kit (YHLO) and iFlash–SARS-CoV-2 IgG-S1 kit (YHLO). Serum samples with a positive result (≥10 AU/mL) in either of these assays were considered seropositive for anti–SARS-CoV-2 IgG. Participants were randomly selected from patients visiting 14 Tokyo hospitals between September 1, 2020, and March 31, 2021. No participants were diagnosed with coronavirus disease 2019 (COVID-19), and none exhibited COVID-19–related symptoms at the time of blood collection.Results: The overall anti–SARS-CoV-2 IgG seroprevalence among all participants was 1.83% (95% confidence interval [CI]: 1.66%-2.01%). The seroprevalence in March 2021, the most recent month of this study, was 2.70% (95% CI: 2.16%-3.34%). After adjusting for population age, sex, and region, the estimated seroprevalence in Tokyo was 3.40%, indicating that 470,778 individuals had a history of SARS-CoV-2 infection.Conclusions: The estimated number of individuals in Tokyo with a history of SARS-CoV-2 infection was 3.9-fold higher than the number of confirmed cases. Our study enhances understanding of the SARS-CoV-2 epidemic in Tokyo.
126 0 0 0 OA 各種消毒薬の殺ウイルス効果
- 著者
- 野田 雅博 山下 秀之 佐藤 多津雄 中西 英三 千田 広文
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.174-179, 1988-03-20 (Released:2011-06-17)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
逆性石けん系1種, 両性石けん系1種, ヨウ素系1種, クロロフェノール系1種, オルソジクロールベンゼン・クレゾール系1種, 塩素系2種, アルデヒド系4種, アルコール系1種の計12種の消毒薬の殺ウイルス効果を, DNAウイルスの牛ヘルペスウイルス1型, ワクシニアウイルスおよび犬アデノウイルスの3種, RNAウイルスの鶏ニューカッスル病ウイルス, 牛エンテロウイルスおよび牛ロタウイルスの3種を用い, 血清蛋白質の非存在および存在の条件下で試験した.塩素系および一部のアルデヒド系消毒薬はすべてのウイルスに対し有効であった. 逆性石けん系, 両姓石けん系, クロロフェノール系, オルソジクロールベンゼン・クレゾール系および一部のアルデヒド系消毒薬はエンベロープを有するDNA, RNAウイルスに対し, さらにクロロフェノール系, オルソジクロールベンゼン・クレゾール系および一部のアルデヒド系消毒薬はエソベロープを欠く一部のDNAウィルスに対し有効であった.血清蛋白質の存在は, 逆性石けん系および両性石けん系消毒薬の殺ウイルス効果に強く影響した.
126 0 0 0 OA 環境調節が味覚におよぼす影響に関する官能審査的研究
- 著者
- 斉藤 進 高間 総子 豊巻 孝子
- 出版者
- The Japanese Society of Nutrition and Dietetics
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.4, pp.165-168, 1972-07-25 (Released:2010-10-29)
- 参考文献数
- 9
環境条件が味覚にどのような心理的影響を与えるかについて実験するため, 温湿度, 照明, 音響などを調節できる特殊な官能審査室を設け, John, W. Mitchell が行なった1:2点官能審査法を採用し, パネルによる審査をした。その結果, 総合的に温湿度, 照明, 音響などの環境要素を変えた場合と, 照明のみを変えた環境条件下で行なった場合では何れも5%の水準で有意差があり, 環境が味覚の心理に影響したものと思われた。
125 0 0 0 OA First Records of Uropterygius oligospondylus (Anguilliformes: Muraenidae) from Minami-iwo-to Island, Southern Japan
- 著者
- Yusuke Hibino Kaoru Kuriiwa Tetsuya Yamada Kiyotaka Hatooka Kar Hoe Loh Tetsuro Sasaki
- 出版者
- The Japanese Society of Systematic Zoology
- 雑誌
- Species Diversity (ISSN:13421670)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.177-182, 2020-08-07 (Released:2020-08-07)
- 参考文献数
- 12
Four specimens from Minami-iwo-to island of Volcano Islands were identified as Uropterygius oligospondylus Chen, Randall, and Loh in Loh et al., 2008. It is the first identified record from Japan and the northernmost record of the species. Uropterygius oligospondylus can be characterized by the following characters: total vertebrae 100–103; body gray with blackish reticular pattern; jaws teeth in two or three rows; anus close to mid-body; head 13.7–16.7% TL; trunk 32.8–36.6% TL; body depth at gill opening 5.8–8.3% TL; eye diameter 3.9–5.3% of head length; snout 16.2–20.3% of head length; and presence of a distinct notch above mid-eye. A new Japanese standard name “Kobu-kikai-utsubo” is proposed for the species. The position of the fourth infraorbital pores from original description should be revised as “far behind posterior end of eye”.
125 0 0 0 OA 副咽頭間隙に刺入した乳児箸異物例
- 著者
- 河野 敏朗 石戸谷 淳一 遠藤 亮 佃 守
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, no.11, pp.899-903, 2007-11-01 (Released:2011-10-07)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 3 1
We sometimes experience infant cases leading to unexpected deaths due to foreign bodies. It is often difficult to identify the cause or foreign body invasion by asking questions directly to a child. We experienced an infant case of a chopstick passing through the soft palate, reaching the parapharyngeal space near the inner carotid artery circumference. At the first medical examination, we could not detect the tip of the chopstick, in the pharynx. Using 3-directional-CT images, we could locate the tip of the chopstick in the parapharyngeal space near the inner carotid artery circumference. Under general anesthesia, we could remove the tip of the chopstick from the parapharyngeal space near the inner carotid artery with an endoscope trans-orally.It is important to investigate positional conditions between a foreign body and the vessels in the parapharyngeal space. Images such as enhancing 3-directional-CT before the operation is useful.Furthermore, we have to be careful of the late neurosis by pencil-injury in the region and pay close attention to respiratory tract management.
125 0 0 0 OA イスラエル・中国関係の発展と対米関係の緊張
- 著者
- 池内 恵
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.29-33, 2020 (Released:2020-03-27)
125 0 0 0 OA 「セクハラ」をめぐる言説を再考する:ことばの歪みの源泉をたどる
- 著者
- 佐々木 恵理
- 出版者
- 現代日本語研究会
- 雑誌
- ことば (ISSN:03894878)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.17-35, 2018-12-31 (Released:2018-12-31)
- 参考文献数
- 20
女性への性暴力への抗議と性被害を告発する「#MeToo」運動をきっかけとして、日本でもセクシュアルハラスメント(セクハラ)の議論が活発になっている。報道の姿勢や世論の反応から、セクシュアルハラスメントは重大な人権侵害であるという認識が浸透していることがわかる。一方、セクシュアルハラスメントが正しく理解されているとは言いがたい状況もある。セクシュアルハラスメントは、職場や労働の場で権力関係を背景に起きると定義されるが、日常で起きる性暴力や性被害を「セクハラ」と表現したり、性的な発言や身体接触の様子を象徴的に「セクハラ」と描写したり、ふざけたりからかったりする意図で「セクハラ」が使われたりしている。本論では、まずセクシュアルハラスメントの定義を確認し、次に、さまざまな場面での誤用・誤解例を示す。さらに、こうしたことばの混乱が起きた源泉を探り、セクシュアルハラスメントの問題解決のためのよりよい表現を考えたい。
- 著者
- Kenji Suetsugu Shun K. Hirota Koji Yonekura Atsushi Abe Yoshihisa Suyama Tian-Chuan Hsu
- 出版者
- The Japanese Society for Plant Systematics
- 雑誌
- Acta Phytotaxonomica et Geobotanica (ISSN:13467565)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.2, pp.121-129, 2023-07-31 (Released:2023-09-08)
The present study documents the first record of Thrixspermum annamense (Orchidaceae) from Iriomote Island, Ryukyu Islands, Japan, expanding its known distribution beyond Vietnam, Thailand, Taiwan, China, and Malaysia. While the morphologically similar taxon T. fantasticum is present on the island, it can be distinguished from T. fantasticum by its somewhat narrower and more rigid leaves, slightly narrower sepals, densely hairy midlobe of the lip, and the absence of two horn-like appendages at the base of the midlobe. A detailed morphological analysis also revealed that the plants discovered on Iriomote Island closely resemble T. annamense from Taiwan but show consistent morphological and molecular distinctions from T. annamense from Vietnam, the type locality. Despite those differences, the high similarity in gross morphology and most lip structures of the plants from Japan, Taiwan, and Vietnam indicates that they all belong to T. annamense at the species level. Consequently, considering the genetic and morphological differences, we propose resurrecting the name T. devolianum, originally described from Taiwan, and reclassifying it as a variety of T. annamense (T. annamense var. devolianum). A neotype for T. devolianum is also designated.
125 0 0 0 OA 身の回りにあふれる線形代数
- 著者
- 田中 聡久
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.4, pp.284-288, 2019-03-01 (Released:2019-03-01)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 1
125 0 0 0 OA 上皮細胞成長因子の工業的生産と新しい採毛技術
- 著者
- 高木 広明
- 出版者
- 日本緬羊研究会
- 雑誌
- 日本緬羊研究会誌 (ISSN:03891305)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.35, pp.28-33, 1998-12-20 (Released:2011-04-22)
125 0 0 0 OA 昆虫キチンの利用技術の開発と応用
- 著者
- 羽賀 篤信
- 出版者
- 社団法人 日本蚕糸学会
- 雑誌
- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.3, pp.3_193-3_210, 2011 (Released:2014-05-21)
- 参考文献数
- 122
125 0 0 0 OA 円柱形つまみの回転操作における指の使用状況について
- 著者
- 松崎 元 大内 一雄 上原 勝 上野 義雪 井村 五郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.5, pp.69-76, 1999-01-31 (Released:2017-07-21)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 4
つまみ・水栓金具・ふた等の操作具を前提とした円柱の回転操作において, 使用する指の状況が円柱の直径の変化によって, どのように推移するかを検討するため, 32名(19〜20歳の男性23名, 女性9名)の被験者で実験を行った。実験の方法は以下のようなものである。直径が7mm〜130mmの間で異なる木製の円柱(高さ50mm)を45本用意し, 無作為に選択された各円柱を, 順に台上の回転軸に差し込み, 右手で時計回りに回転させる。操作の状況は, 下方からビデオカメラで撮影し, 得られた画像から各指と円柱の接触状況を判断した。その結果, 回転操作開始時に使用する指の本数が変化する境界値を, 相対的に図示し把握することができた。また, 円柱の直径が増大するのに伴って, 各指の接触位置がどのように推移するかを二次曲線で近似でき, その傾向が明らかになった。この結果は, 回転操作機器の形状デザインに役立てることができる。
125 0 0 0 OA 西成特区構想の展開と課題 —あいりん地域の新たなセーフティネットづくりを中心に—
- 著者
- 白波瀬 達也
- 出版者
- 学校法人 関西学院大学先端社会研究所
- 雑誌
- 関西学院大学先端社会研究所紀要 (ISSN:18837042)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.41-46, 2019 (Released:2019-07-10)