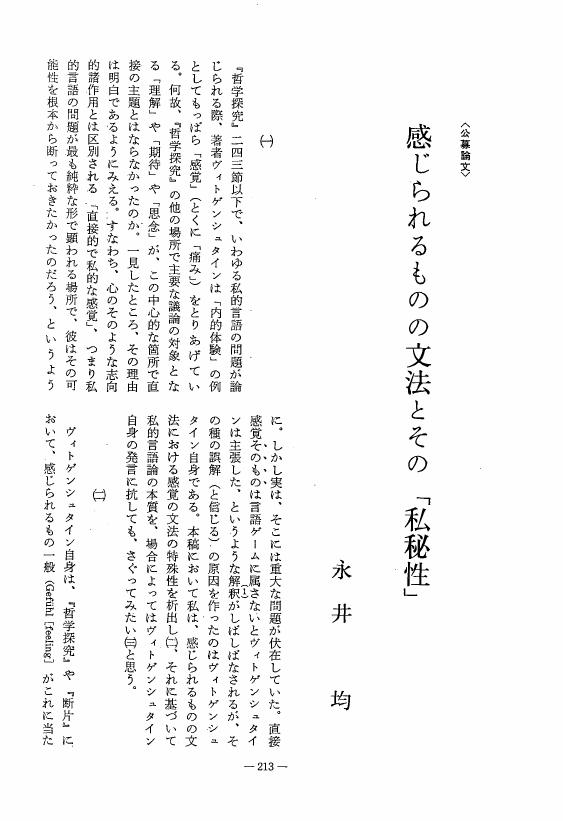3 0 0 0 OA 顔パターン認識の特殊性とその成立過程
- 著者
- 山口 真美
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.12, pp.1747-1752, 2004-12-01 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 32
3 0 0 0 OA 倫理的直観主義の背後にあるもの イギリス道徳哲学の場合
- 著者
- 柘植 尚則
- 出版者
- 関西倫理学会
- 雑誌
- 倫理学研究 (ISSN:03877485)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.3, 2012 (Released:2018-03-15)
3 0 0 0 OA 親鸞にとっての承久の乱の思想的意義と後高倉和讃の意味
- 著者
- 亀山 純生
- 出版者
- 武蔵野大学仏教文化研究所
- 雑誌
- 武蔵野大学仏教文化研究所紀要 = Journal of Institute of Buddhist Culture, Musashino University (ISSN:18820107)
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.146-126, 2023-02-28
3 0 0 0 OA 中国占領地の宗教対策 : 興亜院華北連絡部の武田凞と中野義照
- 著者
- 大澤 広嗣
- 出版者
- 武蔵野大学仏教文化研究所
- 雑誌
- 武蔵野大学仏教文化研究所紀要 = Journal of Institute of Buddhist Culture, Musashino University (ISSN:18820107)
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.33-62, 2023-02-28
3 0 0 0 OA 日本の刑事裁判 : その近代化と現代化
- 著者
- 田宮 裕 タミヤ ヒロシ Hiroshi Tamiya
- 雑誌
- 立教法学
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.1-33, 1998-07-20
3 0 0 0 OA ジャイロとその応用
- 著者
- 河田 伸一
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密機械 (ISSN:03743543)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.12, pp.1698-1707, 1983-12-05 (Released:2009-07-23)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA 「星の王子さま」日本語訳対照研究 : sérieuxの訳語をめぐって
- 著者
- 志村 響
- 出版者
- 東京都立大学 西山雄二研究室
- 雑誌
- Limitrophe = リミトロフ = Limitrophe (ISSN:24370088)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.183-206, 2023-03-31
3 0 0 0 OA 木漏れ日の静止映像等による心理的ストレス低減効果に及ぼす印象評価・個人特性の影響
- 著者
- 高山 範理 藤澤 翠 荒牧 まりさ 森川 岳
- 出版者
- 公益社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.5, pp.565-570, 2012 (Released:2013-08-09)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 4 5
The purpose of this study was to clarify; 1) the psychological stress reduction effect (PSRE) that "sunshine filtering through foliage (SFTF)" brings visually, 2) the relation between the effect and the subjective appraisal (SA) of the forest environment otherwise the personality and other traits (PAOT), 3) the system of PAOT- SA- PSRE based on Lazarus’s acting stress model. We showed 2 images such as photos with and without SFTF in the forest as a simulation for 17 subjects, and examined the change in the psychological feelings (POMS; 3-times) by some indexes (PSRE and SA (SD Method; twice)) for each stimulation before and after the experiment in an artificial weather room. As a result, in comparison the presence of SFTF stimulation with the control, it was clarified that "Tension-Anxiety" and "Fatigue" significantly decreased with the control. In comparison the presence of SFTF stimulation with the other, "Vigor" was significantly higher than that of the absence of SFTF otherwise "Tension-Anxiety" was significantly lower. Furthermore, some evaluation indexes of the SA related to PARE received from the both of SFTF, and those evaluation indexes were affected by the respondents’ PAOT such as “Extraversion” and so on.
3 0 0 0 OA 競走馬の橈骨遠位端骨折の関節鏡手術について
- 著者
- 及川 正明 久保 理江 大浪 洋二
- 出版者
- 日本家畜臨床学会 ・ 大動物臨床研究会
- 雑誌
- 日本家畜臨床学会誌 (ISSN:13468464)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.165-168, 2008-12-31 (Released:2013-05-16)
- 参考文献数
- 7
3 0 0 0 OA 減らない脆弱性 - 隠れオープンリゾルバ -
- 著者
- 鈴木 常彦
- 出版者
- THE JAPAN SOCIETY FOR MANAGEMENT INFORMATION (JASMIN)
- 雑誌
- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集
- 巻号頁・発行日
- pp.291-294, 2023-01-31 (Released:2023-01-31)
送信元IPアドレスが詐称されたDNSクエリが到達してしまう隠れオープンリゾルバを多く発見した。これは未対策のネットワークが各種の送信元IPアドレス詐称攻撃に脆弱であることを意味しており早急な対策が必要と考えられるが、継続調査において対策があまり進んでいないことが明らかになっている。調査対象10万のIPアドレスのうち全体では約7%、PTR が JP のものでは約24%が現在も脆弱なままである。本論文をもって脆弱性が放置されている現状に対しての議論と啓発・対策の進展に寄与したい。
- 著者
- 児嶋 由枝
- 出版者
- イタリア学会
- 雑誌
- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, pp.167-188, 2015 (Released:2017-03-27)
- 参考文献数
- 145
Nel Museo dei Ventisei Martiri della città di Nagasaki si conserva un kakejiku (pittura su rotolo di carta) denominato Madonna della Neve, tramandato dai cristiani clandestini della zona di Sotome, in provincia di Nagasaki. Questo dipinto è stato attribuito a uno o più discepoli di Giovanni Cola, pittore e gesuita originario del Regno di Napoli e fondatore di una sorta di accademia di Belle Arti in Giappone. I discepoli di Cola, per rispondere all’incremento della richiesta di immagini sacre da parte dei cristiani giapponesi, riproducevano immagini di incisioni o di pitture portate dai missionari dall’Europa. Nelle epistole e nelle relazioni eseguite dai Gesuiti in Giappone si legge che i discepoli di Cola erano così bravi che anche gli occidentali facevano fatica a distinguere gli originali portati dall’Europa dalle copie eseguite in Giappone. Il nome autentico del gesuita-pittore, tuttavia, non risultava registrato con chiarezza, essendo indicato talvolta nei documenti e registri della Compagnia sotto varie forme, quali ad es. Niccolò, Nicolao, Nicolaus e Cola. Dalle ricerche eseguite sui documenti consultabili presso l’Archivio diocesano di Nola, sua città natale, risulta però che il nome esatto deve essere Cola. Sembra inoltre molto probabile che questi, prima del suo ingresso nella Società di Gesù, abbia lavorato a Napoli come apprendista presso la bottega di Giovanni Bernardo Lama, sempre di Nola. Sul titolo Madonna della Neve pesano poi diversi dubbi e a tale proposito sono state avanzate varie proposte, che sembrano concludere che il titolo originario sarebbe stato Immacolata Concezione oppure Madonna con Cristo dormiente. Tuttavia, alla luce delle analisi iconografiche, storiche e religiose, è ragionevole affermare che il titolo autentico sia stato effettivamente Madonna della Neve. Nel periodo della Riforma cattolica o Controriforma, infatti, la Chiesa tendeva ad esaltare le immagini taumaturgiche ereditate del periodo medioevale, quale ad es. l’icona denominata Salus populi romani di Santa Maria Maggiore a Roma e la Madonna della “Antigua” della Cattedrale di Siviglia. A questo si aggiunge il fatto che in Giappone permangono anche tracce, risalenti allo stesso periodo, che sembrano indicare la venerazione della Madonna della Neve. Per esempio, a Sotome, dove si trovava la Madonna della Neve attualmente conservata a Nagasaki, si tramandava tra i cristiani clandestini una storia miracolosa, giapponesizzata, che riguardava la Madonna della Neve. All’arrivo dei gesuiti nell’isola di Iki nel 1578, inoltre, la prima messa venne celebrata proprio il 5 agosto, ricorrenza della Madonna della Neve. Interessante è inoltre il confronto che mette in luce aspetti affini fra la Madonna di Nagasaki e una tavola raffigurante la Madonna col Bambino dell’altare maggiore della Chiesa Madre di Francofonte in provincia di Siracusa. La similitudine riguarda non l’aspetto stilistico ma quello compositivo e permette di evidenziare come anche le parti danneggiate del dipinto siano quasi uguali. La tavola di Francofonte, eseguita nel Quattrocento, venne venerata come Madonna della Neve solo dagli anni Settanta del XVI secolo a causa di un miracolo legato alla neve. È significativo il particolare della storia secondo il quale già allora la tavola aveva subito gli stessi danni visibili oggi. La copia di questa tavola doveva quindi imitare anche queste parti: nel periodo della Riforma, infatti, anche i danni presenti sulle immagini miracolose del Medioevo erano considerati importanti.(View PDF for the rest of the abstract.)
3 0 0 0 死面列伝、旅芸人始末[書] : 異国遍路 . 明治会見記
- 著者
- [宮岡謙二筆] . [樋口配天著]
- 出版者
- クレス出版
- 巻号頁・発行日
- 2007
3 0 0 0 OA 高強度運動における筋疲労の要因 : 無機リン酸, グリコーゲンおよび活性酸素種の影響
- 著者
- 和田 正信 坂本 誠 杉山 美奈子 松永 智
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.4, pp.399-408, 2006 (Released:2008-01-25)
- 参考文献数
- 51
- 被引用文献数
- 6 4
Skeletal muscles induced to contract repeatedly respond with a progressive loss in their ability to generate a target force or power. This decline in function, referred to as muscle fatigue, has a complex etiology that can involve various metabolic and ionic factors. Of these, intracellular acidosis due to lactic acid accumulation has been regarded as one of the important causes of muscle fatigue that occurs with intense exercise. Recent surveys, however, have demonstrated little direct effect of acidosis on muscle function at physiological temperatures, and in fact several putative mechanisms by which intracellular changes can attenuate contractile function have been proposed. The most likely mechanisms to explain muscle fatigue include elevated inorganic phosphate concentrations that result from phosphocreatine breakdown, compartmentalized depletion of endogenous muscle glycogen and/or modification by reactive oxygen species that are produced extensively in contracting muscle fibers. This brief review seeks to examine how these three alterations contribute to muscular fatigue processes.
3 0 0 0 OA 筋疲労
- 著者
- 片山 憲史 田中 忠蔵 西川 弘恭 平澤 泰介
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.4, pp.309-317, 1994-08-01 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA 環境プルトニウムの存在状態に関する研究
- 著者
- 山本 政儀 Yamamoto Masayoshi
- 出版者
- 金沢大学自然計測応用研究センター
- 雑誌
- 平成15(2003)年度科学研究費補助金 基盤研究(C) 研究成果報告書 = 2003 Fiscal Year Final Research Report
- 巻号頁・発行日
- vol.2002-2003, pp.7p., 2004-03-01
本研究は、陸上環境における放射性物質の最大のリザーバーである大地、すなわち土壌中でのPuのスピシエーション(存在状態、存在形態)を重点的に行なった。フィールドとして国内のPu汚染レベルの数〜数百倍高い旧ソ連核実験場セミパラチンスク内外の表層土壌を用いた。土壌の粒径分画、磁気分画とバイオイメージングアナライザー法を組み合わせて、種々の粒径の放射性物質を含む粒子Hot-particle(放射能の強い粒子)を定量的に探査する手法をまず確立し、それら粒子の特性を走査型電子顕微鏡(SEM)、エネルギー分散型蛍光X線分液装置(SEM-EDX)等で観察し、全体及び個々の粒子のPu測定も実施して、粒子特性とPuの関係、全体としての粒子Puの存在割合を明らかにする。また、微粒子に対しては、アルファー・トラック法を併用してPuの存在特性を考察することを目的に研究を進めてきた。 セミパラチンスク核実験場周辺のドロン村で採取した高濃度Pu汚染土壌を用いた。この地域の^<239,240>Pu及び^<137>Cs蓄積量はそれぞれ530-14,320Bq/m^2,790-10,310Bq/m^2であった。その後、試料をサイズ別に<0.45,0.45-32,32-88,88-125,125-250,250-500,500-2000μmに分画し、それぞれの分画中のPu濃度の測定を測定し、アルファー・トラック法でHot-particleの存在を確かめた。その結果、土壌の125μmを境にして<125μmで^<239,240>Pu濃度が高く更にHot-particle数が多いことが解り、土壌の再浮游からの吸入被曝経路の重要性が示唆された。Hot-particleの探査については、数-数十μmの勢多くのHot-particleの存在を確認(Pu由来)したが、定量的評価には更なる検討が必要で有り、顕微鏡下での自動測定を放医研の研究者と共同で研究を進めている。
3 0 0 0 OA 幼児におけるネガティブではない泣きの直接観察事例の分類 : 保育者への質問紙調査から
- 著者
- 和田 由美子 井﨑 美代
- 雑誌
- 心理・教育・福祉研究 : 紀要論文集 = Japanese journal of psychology, education and welfare
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.49-59, 2020-03-31
ネガティブではない泣きが幼児期から見られるか否か明らかにするために,保育者を対象に,ネガティブではないと思われる状況で幼児が泣いたエピソードについて,自由記述で回答を求めた。76名から得られたエピソードの内容を検討した結果,ネガティブではない泣きに該当すると判断されたエピソードは82件中33件,報告者数は76名中25名(32.9%)であった。泣きの生起状況の類似性に基づき,エピソードをKJ法で分類した結果,親が迎えや担任の出勤時に泣く<愛着対象との再会>が13件,自分または人が勝利・成功した時に泣く<成功・勝利>が11件,自分または他者が危機的な状況から解放された時に泣く<危機からの解放>が3件で,33件中27件(81.8%)がこの3つのカテゴリーに含まれた。エピソードの報告件数は,男児より女児で有意に多かった。大学生の回想から,幼児期にネガティブではない涙が見られることは報告されていたが(和田・吉田,2015),保育者の「直接観察」によっても,同様の結果が裏付けられた。
3 0 0 0 OA 母親の情動共感性及び情緒応答性と育児困難感との関連
- 著者
- 小原 倫子
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.92-102, 2005-04-20 (Released:2017-07-24)
- 被引用文献数
- 2
本研究の目的は, 母親の情動共感性と情緒応答性が, 育児困難感にどのように関連するのかについて検討することである。0歳児を持つ母親78名と1歳児を持つ母親40名を対象に, 育児困難感と情動共感性について質問紙調査を行った。また, 情緒応答性の把握について, 日本版IFEEL Picturesを実施した。日本版IFEEL Picturesとは, 30枚の乳児の表情写真を母親に呈示し, その写真を通して, 母親が乳児の感情をどう読み取るかという反応特徴から, 母親の情緒応答性を把握するツールである。その結果, 母親の情動共感性及び情緒応答性と, 育児困難感との関連は, 子どもの年齢により異なることが示された。0歳児を持つ母親の育児困難感には, 母親の情動共感性が関連しており, 1歳児を持つ母親の育児困難感には, 母親の情緒応答性が関連していることが示された。母親の育児困難感は, 母親としての経験を重ねるにつれて, 母親要因である情動共感性よりも, 母子相互作用から生じる情緒応答性が関連要因となる可能性が考えられた。
3 0 0 0 OA 感じられるものの文法とその「私秘性」
- 著者
- 永井 均
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.1983, no.33, pp.213-223, 1983-05-01 (Released:2009-07-23)
3 0 0 0 OA 高等学校教諭普通免許状「家庭」の授与に指定されている科目・内容に対する教員の意識
- 著者
- 鈴木 洋子 永田 智子 赤松 純子 榊原 典子 中井 昌子 野田 文子 矢野 由起
- 出版者
- 日本家庭科教育学会
- 雑誌
- 日本家庭科教育学会誌 (ISSN:03862666)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.130-135, 2009-07-01 (Released:2017-11-17)
- 参考文献数
- 8
教育職員免許法上の指定科目と現行の学習指導内容及び教員養成上の必修科目が一致していることは必須であるが,教育職員免許法施行規則に設定されている家庭科に関する専門科目は,教科に求められている時代の要請に比べ,大幅な変革がなされていない。そこで,教育職員免許法施行規則に示された「教科に関する科目」と現行家庭科の学習指導内容の整合性を確認し,問題点の究明と改善の方策を探る際の示唆を得ることを目的に,高等学校教員の現行教育職員免許法施行規則に指定の「家庭」の教科に関する科目に対する意識を調査した結果,以下のことが明らかになった。・高等学校普通科における普通教科「家庭」の履修科目は,「家庭基礎」57%,「家庭総合」14%,であった。専門科目「家庭」の中の科目については「フードデザイン」と「発達と保育」の履修が多かった。・高等学校教諭普通免許状「家庭」の授与に指定されている科目・内容のうち,必要性が高かったのは食領域の「調理実習」「栄養学」「食物学」「食品学」と「保育学」であった。必要性が低かった科目・内容は「家庭電気・機械」「製図」「情報処理」「家庭看護」「家庭経営学」であった。不必要とされる理由に「他の教科で学習したほうがよい」「家庭総合・家庭基礎にない」の回答が多かった。「家庭電気・機械」「製図」「情報処理」は,中学校においては技術科の内容であることを考慮し,削除も含めて今後検討する必要があるのではないかと考える。・教育職員免許状では必要な科目・内容として指定されてはいないが,高等学校で家庭科を指導する上で教員養成上必要と思われる科目・内容に,「消費生活」「福祉」「環境と資源」「高齢社会」の回答が多かった。低かったのは「キャリア教育」,「ジェンダー」,「生活文化」,「少子化問題」であった。
3 0 0 0 OA 新入生オリエンテーションへの謎解き活動の導入とその効果
- 著者
- 長谷 亜蘭
- 出版者
- 埼玉工業大学出版会
- 雑誌
- 埼玉工業大学工学部紀要 = Journal of the Faculty of Engineering, Saitama Institute of Technology (ISSN:13492411)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.9-14, 2022-12-31