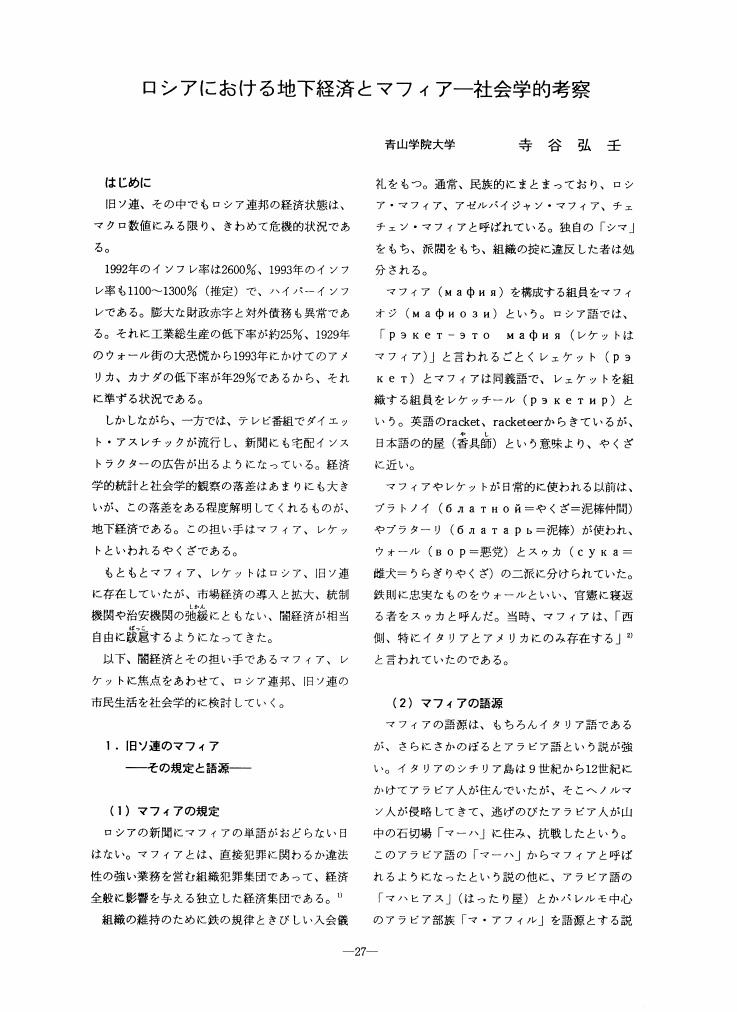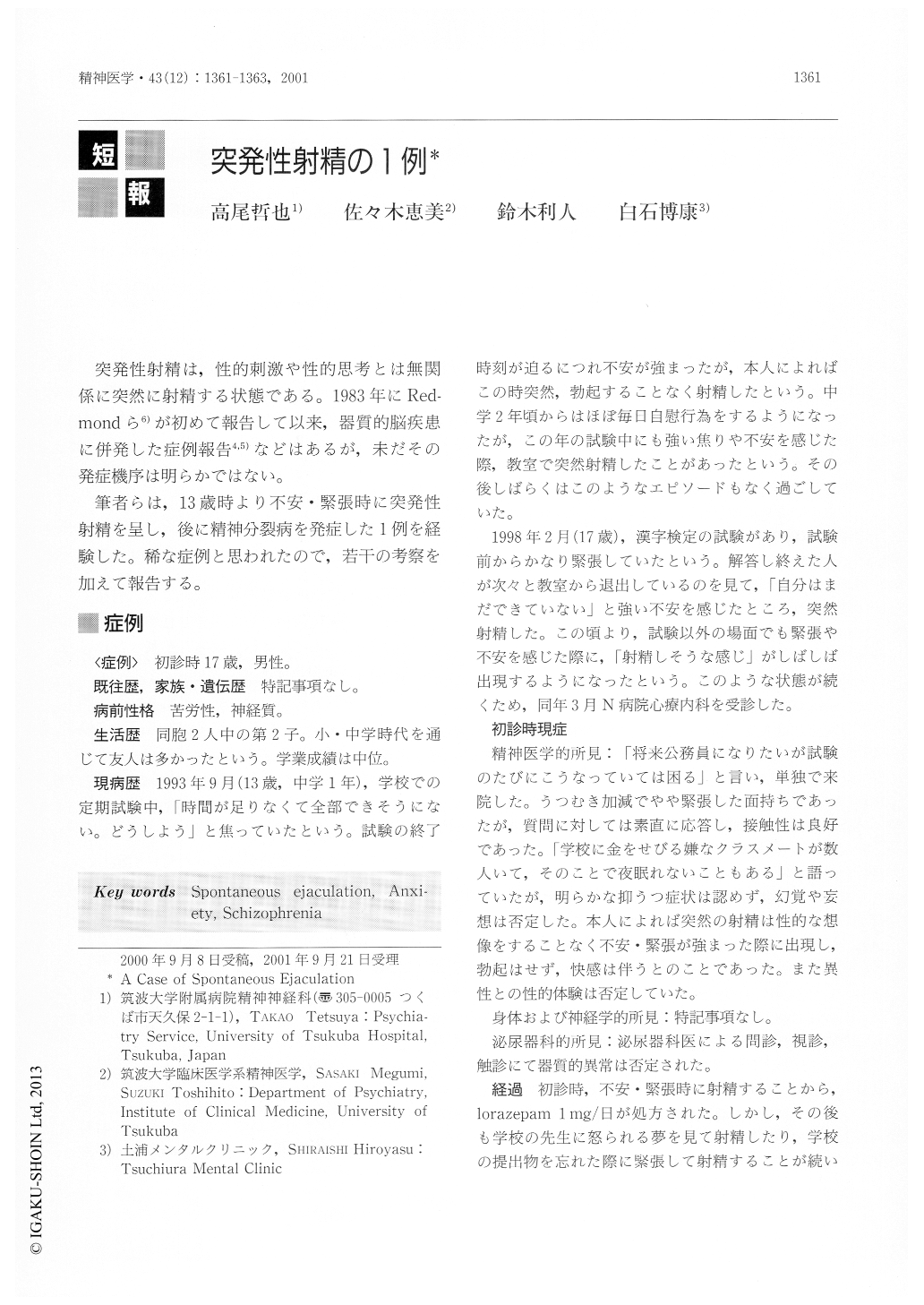2 0 0 0 OA 第2章 高速スイッチングサイリスタ
- 著者
- 蒲生 浩
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.5, pp.385-389, 1978-05-20 (Released:2008-04-17)
- 参考文献数
- 21
2 0 0 0 OA 「ララ」の記憶 : 戦後保育所に送られた救援物資と脱脂粉乳
- 著者
- 岩崎 美智子 Iwasaki Michiko イワサキ ミチコ
- 出版者
- 東京家政大学博物館
- 雑誌
- 東京家政大学博物館紀要 (ISSN:13433709)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.19-32, 2009
2 0 0 0 OA 終助詞化した「し」
- 著者
- 栗原 さよ子 Sayoko Kurihara
- 出版者
- 学習院大学文学部国語国文学会
- 雑誌
- 学習院大学国語国文学会誌 (ISSN:02864436)
- 巻号頁・発行日
- no.52, pp.1-15, 2009-03-31
2 0 0 0 OA ラスキにおける 「二つの全体主義」 認識の変容と自由民主政への批判的省察
- 著者
- 大井 赤亥
- 出版者
- 日本政治学会
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.2_288-2_308, 2012 (Released:2016-02-24)
The early 20th century was marked by the advent of both communism and fascism, and their challenges against the traditional western civilization. This paper examines the historical dynamism shown by those political struggles in the early 20th through the works of Laski. In the 1920s, Laski considered both communism and fascism as the negation of the legacies of western civilization. However, the political turmoil in the 1930s had led Laski to distinguish Soviet Union and Nazi Germany, and he thought Soviet communism as a “new civilization” which had been overcoming capitalist societies. But Laski's appreciation of Soviet communism was different from other British socialists in that Laski evaluated social welfare in Soviet Union as long as it served as the basis for individual freedom. This paper concludes that those Laski's ideas contain an actual potentiality in making contemporary criticism to liberal democracy after the collapse of Soviet communism.
- 著者
- 野瀬 由季子 大山 牧子 大谷 晋也
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.176, pp.48-63, 2020-08-25 (Released:2022-08-26)
- 参考文献数
- 28
内省を通して実践を創造していく自己研修型教師としての日本語教師の養成・研修は喫緊の課題であり,その一手法として授業観察が存在する (岡崎・岡崎 1997)。授業観察の支援環境の構築を目指して,本研究では,国内の日本語学校で教師研修として実施される授業観察を対象に,観察者と授業者の授業観察への目的意識を明らかにする。日本語学校の常勤3名 (観察者) と非常勤3名 (授業者) に半構造化インタビュー調査を実施し,逐語録に対してSCAT (大谷 2019) による質的分析をおこない,授業観察に対する目的意識を,筆者らが作成した【評価志向型】【実践公開志向型】【内省共有志向型】の枠組みで考察した。その結果,各観察者/授業者は基本的に特定の志向型を軸に授業観察を捉えながらも,同時に別の志向型の要素を持ち合わせていたり,軸とする志向性を徐々に変容させたりしていくことが明らかになった。このことから日本語学校での役割や教師間の関係性を考慮した活動デザインの重要性が示唆された。
- 著者
- 孟 盈
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.178, pp.185-199, 2021-04-25 (Released:2023-04-26)
- 参考文献数
- 25
日中漢字類似性が中国語を母語とする日本語学習者(以下,CLJ)の単漢字和語動詞の習得に与える影響を明らかにするため,単漢字和語動詞を「同義同形類」,「同義異形類」に分類し,CLJとインドネシア語を母語とする日本語学習者(以下,ILJ)に対して,産出テストと理解テストを行った。その結果,「同義同形類」では,日中漢字類似性がCLJの産出と理解の双方に正の転移をもたらし,書字的類似性だけで習得が促進されることが明らかとなった。「同義異形類」の理解テストでは,書字的類似性による表記親近性効果が生じ,CLJはILJより理解度が高い傾向であった。一方,産出テストでは,同意味を表す日本語には中国語と書字的類似性がないため,CLJとILJに差はなかった。このことから,CLJは「同義異形類」について意識的な学習を行う必要があることが示唆された。
2 0 0 0 OA ノンネイティブ日本語教師認知研究の動向分析 ―オンライン学術文献データベースを用いて―
- 著者
- 雍 婧
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.178, pp.170-184, 2021-04-25 (Released:2023-04-26)
- 参考文献数
- 23
本稿は,ノンネイティブ日本語教師(以下,NNT)認知研究の動向を分析し,今後のNNT認知研究の方向性を考察したものである。本調査では,オンライン学術文献データベースによる検索で抽出された1991年から2020年までの81本の研究論文を対象とし,年代別・地域別・研究課題の3つの観点から分析した。分析の結果,NNTを対象とする教師認知研究の論文は,社会の多様化が進み,教師の自己研修や成長に注目が集まったことを背景に,2010年代に急増していることが確認された。また,2010年までは東アジアを対象とした論文が多いが,2011年に入ると東南アジアに注目した研究が急増している。さらに,計量テキスト分析で研究課題が確認され,日本語教育学研究の関心領域の多様化及び,多文化共生社会におけるNNTの葛藤への関心により,NNT認知の変容プロセスへの注目度が高まっていることが明らかになった。
2 0 0 0 OA 『日本語教育』掲載論文の引用ネットワーク分析 ―日本語教育研究コミュニティの輪郭描写―
- 著者
- 田中 祐輔 川端 祐一郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.178, pp.79-93, 2021-04-25 (Released:2023-04-26)
- 参考文献数
- 24
日本語教育研究史についてはこれまでに複数の重要なサーベイが存在しているが,多くは研究領域の分類や取り組みの方向性に関する考察を行ったもので,定量的知見は不足している。また,研究間や研究者間での相互関係や互いの影響については明らかにされていることが極めて少ない。本研究では,日本語教育学及びその研究コミュニティの輪郭を把握するための試みの一つとして,日本語教育学会の機関誌『日本語教育』第1 ~ 175 号(1962~2020 年)の掲載論文1,803 点と,これらの論文中で引用された文献16,205 点及びそれらの著者を対象として,引用参照関係の時系列変化やネットワーク構造の分析を行った。その結果,研究コミュニティ内における共通の知的基盤の形成,研究動向の変化,グローバルな言語・教育研究との関連等について,いくつか重要な事実が明らかになった。また,その背景や示唆について,先行研究の知見も踏まえながら考察を行った。
2 0 0 0 OA 単語埋め込み技術を用いた人狼BBSにおける役職推定
- 著者
- 木村 優里絵 尾崎 知伸
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第32回 (2018) (ISSN:27587347)
- 巻号頁・発行日
- pp.1H2OS13b02, 2018 (Released:2018-07-30)
不完全情報ゲームの一つである人狼ゲームでは,ゲーム中の会話から,他プレイヤの役職を推定することが重要となる.本論文では,役職推定の更なる精度向上を目的とし,複数のベクトル表現と多様な集計方法を用いて各プレイヤの発言をベクトル化する手法を提案する.また人狼BBSのログデータを対象に,種々の分類モデルを用いて提案手法を評価する.
2 0 0 0 OA 「製品の身分」と作業状況の可視化 ――空間編成の方法と共同作業への参加可能性――
- 著者
- 三部 光太郎
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.3, pp.466-481, 2020 (Released:2021-12-31)
- 参考文献数
- 16
本稿は,「ひきこもり」(および「ニート」)支援を掲げるNPO において,スタッフと地域のボランティア,支援の利用者たちが共在する空間が,どのように相互行為を通じて編成されているのかを分析する.分析の焦点は,調査対象たる支援組織の活動への参加に対する「入口」として位置づけられている,軽作業(自動車用ワイヤーハーネスの組み立て)の空間編成の実践である.分析を通じて,参加者,とりわけ利用者の共同作業への参加可能性が,どのような方法によってもたらされるのかを検討することが,本稿の目的である. 分析による知見は,以下の3 点である.1)作業の進行において,参加者はテーブルに積み上げられたハーネスの身分の区別(すでに集計された「束」/まだ集計されていない「山」)を,他の参加者に可視化する.2)製品の身分の可視化を通じて,参加者各自の作業の進行状況の区別(集計作業/組み立て作業)も周囲に可視化され,互いに重複しうる各自の作業空間の境界が管理される.以上1)と2)は,まずは製品の集計における間違いを避ける実践である.しかし3)作業の進行状況の可視性は,ひるがえって,他の参加者が共同で集計作業に従事することを可能にする仕掛けにもなっている.最後に分析の知見を踏まえ,複数の参加者が1 つのテーブルを囲む形式で作業が行われることが,利用者の支援空間への参加にあたってどのような意義を持ちうるのかを考察する.
2 0 0 0 OA 津山城の石垣の石:津山石
- 著者
- 能美 洋介
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 第126年学術大会(2019山口) (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- pp.347, 2019 (Released:2020-08-28)
2 0 0 0 OA 1920–30年代の東京市における低所得層の出産と医療施設
- 著者
- 由井 秀樹
- 出版者
- 日本保健医療社会学会
- 雑誌
- 保健医療社会学論集 (ISSN:13430203)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.40-50, 2020-07-31 (Released:2021-08-06)
- 参考文献数
- 48
都市部において、低所得層向けに設立された施設を中心に、1920年代から医療施設出産が普及しはじめていたことが近年の研究で明らかになってきた。本稿では、この議論を精緻化させるため、行政の社会調査を主な素材に、1920–30年代の東京市における①低所得層の利用できた施設の分布状況、②低所得層のなかでも生活のより厳しい人々が施設の利用をためらった要因を検討した。結果、以下が明らかになった。①施設は市の中心部に集中していた。②減額されていたとしても、利用料の負担が重く、利用手続きが手間であったことなどが、低所得層のなかでも生活の厳しい妊婦に施設の利用をためらわせていた。彼女たちは、修練のため低価格で出産介助を行う資格取得後間もない産婆を利用することがあったが、低所得の施設利用者は、専門職養成や医学研究のための学用患者でもありえたことを考慮すれば、学用患者の階層化が生じていたといえる。
2 0 0 0 OA 職場における熱中症の現状と予防対策
- 著者
- 川波 祥子
- 出版者
- 公益財団法人 産業医学振興財団
- 雑誌
- 産業医学レビュー (ISSN:13436805)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.91, 2022 (Released:2022-09-06)
日本の職場における2021年の熱中症の死亡災害件数は20件で、COVID-19による件数を除き業務上疾病による死亡災害で最多を占めた。労作性熱中症がほとんどで、建設業、製造業等の高温多湿な職場で発生し、暑熱未順化者が多かった。夏の労働環境が厳しくなる中で熱中症による死亡災害を無くすには、熱中症発症の危険因子を理解し、環境・作業・衣服のリスクを評価した上で効果的なリスク低減対策を実践することが重要である。
2 0 0 0 OA ロシアにおける地下経済とマフィアー社会学的考察
- 著者
- 寺谷 弘壬
- 出版者
- ロシア・東欧学会
- 雑誌
- ロシア・東欧学会年報 (ISSN:21854645)
- 巻号頁・発行日
- vol.1993, no.22, pp.27-38, 1993 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 33
2 0 0 0 OA 延喜式諸国日数行程と移動コスト分析
- 著者
- 清野 陽一
- 雑誌
- じんもんこん2011論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, no.8, pp.37-42, 2011-12-03
本研究では『延喜式』内の主計式に見える地方の国府と平安京との移動日数に関して,これまで文献史学で行われてきた研究成果を参考にしつつ,GIS を用いてあらためて今日的視点からシミュレーションを行うことによって,その具体的数字の意味するところを再度検証し,数値のもつ意味を考えた.その結果,文献史学では史料内からしか考察できない材料に対して,外部の客観的なデータをもってその検証作業を行うことができた.加えて,移動コスト分析において留意すべき点,更には現状の検討材料における問題点を整理し,今後どのようなデータが整備され,分析が行われれば研究が進展するかについての提言を行った.
2 0 0 0 OA ゲーデルの数学観と不完全性定理
- 著者
- 大出 晁
- 出版者
- 科学基礎論学会
- 雑誌
- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.129-134, 1991-12-25 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 1
2 0 0 0 OA 元素及び重元素同位体組成による農産物の産地判別技術
- 著者
- 有山 薫
- 出版者
- 公益社団法人 日本分析化学会
- 雑誌
- 分析化学 (ISSN:05251931)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.205-220, 2014-03-05 (Released:2014-03-31)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 2 1
食品の産地表示は商品選択において最も基本的な情報であり,消費者の関心が高いことから,正しい表示がなされていることが食品の信頼性を保つ上で重要である.また,産地表示はブランド戦略にも利用されており,高い付加価値を持つ産地ブランドを維持するために表示の偽装は見逃すことができない.そこで,食品の産地を科学分析により判別する研究が偽装防止のために行われてきた.本稿では,食品の産地判別法として日本で最初に実用化された,誘導結合プラズマ質量分析法を用いた多元素の濃度組成による判別法がいかに開発されたかについて紹介する.別の判別指標として重元素同位体比は地質情報を中心とした生育地の情報がそのまま農産物等に移行するため,信頼性の高い産地判別を可能とする.この指標を用いた産地判別法の開発が待ち望まれていたが,重元素としてSrとPbの同位体比を用いた方法がようやく実用化に至ったことから,この判別法の最新の研究例を紹介する.
2 0 0 0 OA 非致死性トラウマ体験後の認知尺度の作成と信頼性・妥当性の検討(資料)
- 著者
- 伊藤 大輔 鈴木 伸一
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.155-166, 2009-05-31 (Released:2019-04-06)
本研究の目的は、非致死性トラウマ体験者を対象として、トラウマ体験後の認知を測定する尺度(CognitionsInventoryofNon-lethalTrauma;CINT)を作成し、その信頼1生、妥当性を検討することであった。大学生302名を対象に、非致死性トラウマ体験後の否定的な考えについて自由記述による回答を求め、項目を作成した。次に、大学生902名を対象に、CINT暫定版を実施した。探索的因子分析を行った結果、「自己の能力や価値に対する否定的な認知」「出来事の対処についての後悔の念」「他者関係性に対する否定的認知」「周囲の不安全・将来に関する否定的認知」の4因子19項目から成るCINTが作成された。また、CINTは十分な信頼性と内容的妥当性、基準関連妥当性、併存的妥当性を有することが確認された。最後に、CINTの臨床的有用性に関して議論がなされた。
2 0 0 0 OA 自閉症のドパミンD1受容体の機能変化に関するPET研究
自閉症によくみられる多動性・衝動性の基盤には、脳内ドパミン系が重要な役割を果たしていると考えられている。例えば、自閉症ではこれらの症状に関係の深い眼窩前頭皮質(OFC)においてドパミン・トランスポーター結合が増加していることが分かっている。本研究では、自閉症のOFCにおけるドパミン系機能をさらに調べるために、成人自閉症者を対象にドパミンD1受容体結合をPETで計測した。その結果、自閉症ではOFCのドパミンD1受容体結合が有意に増加していたが、その増加は臨床症状と相関しなかった。この結果から、自閉症ではドパミン系が機能不全に陥っており、それを代償すべく受容体が増加しているものと推測された。