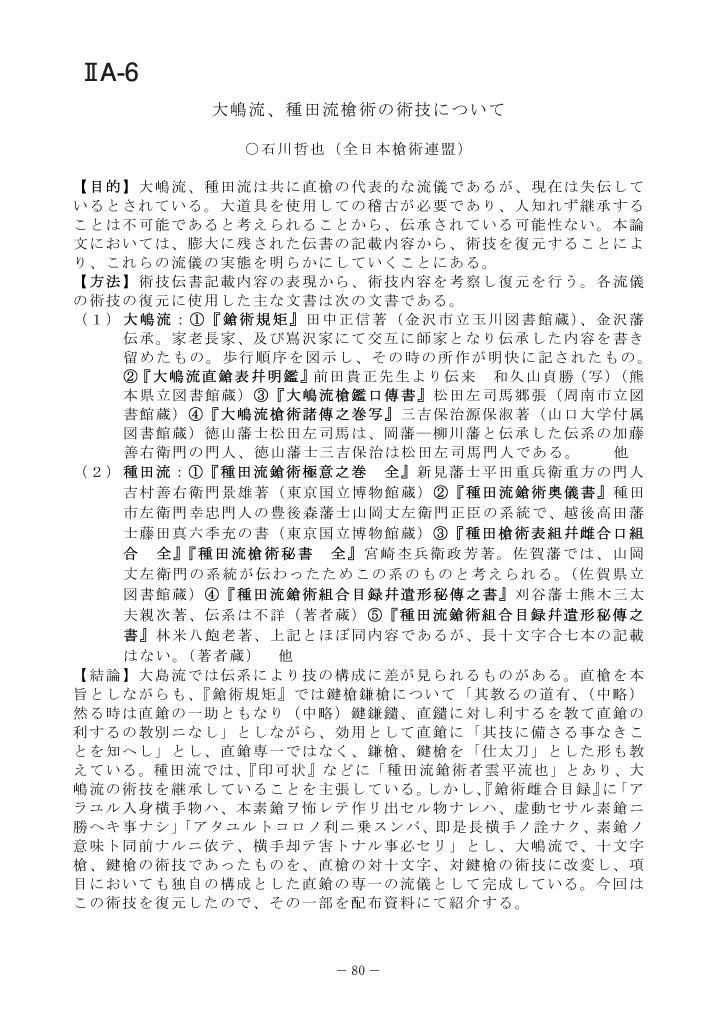2 0 0 0 OA 大嶋流、種田流槍術の術技について
- 著者
- 石川 哲也
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.Supplement, pp.S_80, 2016 (Released:2018-03-12)
2 0 0 0 OA 呼吸法の違いによる血中酸素、皮膚電気抵抗、および脈波フラクタル次元の変化
- 著者
- 足達 義則 青木 孝志
- 出版者
- International Society of Life Information Science
- 雑誌
- 国際生命情報科学会誌 (ISSN:13419226)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.84-89, 2001-03-01 (Released:2019-04-30)
- 参考文献数
- 4
呼吸の仕方は、ある程度意識的に変化させることができる。これによって、他の不随意器官に影響が現れることが知られ、安静や瞑想に用いられている。本研究では、3種類の呼吸法;普通呼吸(何も意識しない通常の呼吸)、丹田呼吸(下腹部に意識を集中した腹式呼吸)、および腹筋振動呼吸(笑いと模倣した、呼気を短く強く数回に分けて行う呼吸)について、血中酸素濃度、皮膚電気抵抗、および脈波形への影響について調べた。特に、脈波形についてはフラクタル次元解析を用いて変化の様子を検証した。これらの検討により、呼吸法を変えることによって脈波形、ノイロ値、血中酸素溶存率は大きく変化し、他の器官に影響している可能性が見いだされた。
2 0 0 0 江戸期における産業技術と先端科学技術の接点-醸造技術を中心に-
日本酒、醤油、藍、硝石などを製造する醸造/発酵技術は、日本国内において独自に発展を遂げた代表的な在来技術のひとつである。これらは江戸末期に相当な水準にあり、明治期にもいくつかの重要な改良が行われた。本研究では、博物館、製造業者などが所蔵する醸造/発酵技術関係史料を調査し、史料の体系化とともに、在来技術の発展過程における蘭学(当時の先端科学技術)との接点を明らかにする。本年度は日本酒の補足調査を行うとともに、硝石と藍を中心に史料の探索と複写を行った。(1)硝石は火薬、花火、それに硝子の主原料であり、金属加工にも欠かせない存在であって、肥料の主成分のひとつでもある。史料が残されている富山県五箇山の製造技術(硝石培養法)は戦国時代に始まり、のちに改良されて製品は国内で最高の品質と位置づけられていた。(2)当時の日本の硝子は中国に由来する鉛カリ硝子であり、硝石・鉛・硅砂を原料としていた。長崎に始まった硝子の製法は、江戸中期には京都、大坂、江戸など各地に広がった。蘭書の輸入解禁(1720年)により、品質が優れた輸入の洋硝子はソーダ硝子であって原料と製法が異なることが明らかにされた。(3)外国語を理解する研究者集団(蘭学者、洋学者)の周辺には、そこで得られた西洋科学技術の知見をもとに、既存技術の発展を企図する集団(彼ら自身は蘭書や洋書は直接読めない)が生まれた。彼らは既存技術と新規に得られた知識を折衷させて試行錯誤をおこなったり、新たな主張を提示して技術の向上を達成させた。しかし、日本酒や藍などの有機化学分野では、日本と西洋の自然環境のちがい、原料となる穀物や植物のいちじるしい差異のため、この時点で西洋の技術を受容することはできなかった。これら日本の在来技術は、明治期に行われた化学技術の体系的な摂取によって再編へ向かうこととなった。
2 0 0 0 OA デザインエンジニアリングによる熱電変換素子のデザイン開発
- 著者
- 尾方 義人 川崎 和男
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会和文論文誌 (ISSN:13472879)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.76-80, 2006-03-25 (Released:2010-03-08)
- 参考文献数
- 19
The expected nuclear powered battery is the isotope battery, which applies photoconduction or radiant rays, in other words, releases electron. Because of its lightweight and constant stability and 80 years long (=half time of radiant rays energy) running span, this battery is very effective for artificial satellites, desert island, and artificial hears. For this small battery, production method, waste disposal method, and emergency risk management need to be designed as international standards. To make that possible, design of the battery should achieve universal consensus with its form and shape. True meaning of peace could be shared worldwide, this isotope battery will be international standard.And, On this research as Design Development of Thermoelectric Generator by Design Engineering, we used a "Design Activities Theory" in which the activities involved in Knowledge Management and Project Management aimed at ensuring the efficiency of that Knowledge Management function as a single system.
2 0 0 0 所得格差の拡大はあったのか
- 著者
- 大竹文雄
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- 日本の所得格差と社会階層
- 巻号頁・発行日
- pp.3-20, 2003
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 十分に医療化されていない疾患を患うことの困難と診断の効果
- 著者
- 野島 那津子
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.3, pp.3-19, 2015-02-28 (Released:2019-05-24)
- 参考文献数
- 26
The purpose of this paper is to investigate the difficulties when suffering from an incompletely medicalized disease and the effects of its diagnosis using the narratives of spasmodic dysphonia sufferers. Spasmodic dysphonia (SD) is a chronic voice disorder. It leads to a characteristic strained and strangled voice (Gündel et al. 2007). Its etiology is unknown and there is no fundamental treatment. In Japan, SD is a rare disease and most physicians have little experience treating it. Few physicians can diagnose SD. In addition, as SD is virtually unknown among the public, its characteristic voice is not perceived as a symptom of a disease, neither by others nor by sufferers themselves. Considering this situation, we can say that SD is an incompletely medicalized disease. While medicalization has been criticized for its aspect of social control and its tendency to individualize social problems, incomplete medicalization has been relatively less discussed and few empirical studies of those diseases have been conducted. In this paper, I focus on SD as an example of incomplete medicalization and examine the problems of incomplete medicalization from sufferer’s point of view.Based on interviews with fifteen people suffering from SD, the three main difficulties identified are: an inability to explain their condition and loneliness, inappropriate definition of a SD’s unique voice by others, and a visible negative reaction. One common underlying cause for these difficulties is the lack of a definitive diagnosis. Receiving a diagnosis could be an opportunity to reduce those difficulties. Obtaining a diagnosis opens possibilities of refusing incorrect interpretations, providing plausible explanations and disclosing their suffering to others. In the case of SD, I suggest that simply suffering does not constitute a “disease” in our society. Adequate medical diagnosis is a requisite condition for the social existence of the “disease.”
2 0 0 0 OA 岡山地方のはげ山について (2)
- 著者
- 千葉 徳爾
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.158-166, 1954-04-25 (Released:2008-12-24)
- 参考文献数
- 39
1. It is held that bare hills result from two primary causes: one is a natural cause rooted in geological and climatological conditions while the other is cultural in origin and related. to forest denudation. for purposes of salt and china manufacturing. Natural conditions should be considered as a constant for a period of a few hundred years, hence only cultural factors are considered here. 2. China manufacturing prospered in the 18th century but after that time it declined and denudation of forests was largely halted. As a result, forests which had been cutover became relatively thick. 3. Based on manuscripts dating back to the 18th century, it may be presumed that salt manufacturing started at that time. Since 1840 or 1850, coal has been used for fuel in salt manufacturing, however before that time, twigs provided the bulk of the fuel used. These were obtained from shoots growing in the neighboring private forests rather than from public ones. As the twigs cut in the district were not sufficient to meet the demand of salt manufacturers. along the Okayama coast, prior to 1790, they were brought down from the northern mountains and from the west by river craft and used in the manufacture of salt and in other local industries. Since that time, hilltops along the coast began to become bare. 4. Most of these hills were originally covered by commonly-owned forests from which the people in the community gathered their fuel needs. Ho-wever, they were prohibited from gathering fuel for the production of salt, china, charcoal, fish fertilizer etc. without pern-fission. In the prohibition had been violated, disputes would have occurred and recorded bemuse the Okayama clan recorded a great many cases of such disputes over forest right. But, since no such case can be found concerning commonly-owned forests, it is believed that the regulations were followed. 5. The above-mentioned points way be summarized as follow: Forests where fuel for manufacturing was gathered are not now denuded, but the commonlyowned forests from which domestic fuel needs were gathered are bare. It is concluded that bare hills may not have originated froin the supply of fuel needs to salt and other industries, but rather should be attributed to faulty control of the commonly-owned forest.
2 0 0 0 OA 困難に直面している人への言葉かけに関する基礎的研究
- 著者
- 尾之上 高哉 井口 豊
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.Suppl., pp.193-196, 2023-02-13 (Released:2023-03-28)
- 参考文献数
- 6
困難に直面している人に,「皆にその能力があるわけではない」「あなたには別の強みがある」といった言葉かけ(以後,comfort と表記する)を行うと,その領域での相手の動機づけを低下させてしまう可能性がある.先行研究では,「その領域で必要な能力を“固定的”に(つまり,変わりにくいものとして)捉えていると,comfort を行い易くなる」との知見が報告される.本研究の結果は,その知見が,相対的にみた時に,当該の能力が“固定的に捉えられ易い領域”と,“可変的に捉えられ易い領域”の両方で追認されることを示した.先行研究と本研究の結果は,能力の捉え方と言葉かけとの関連に注意を向ける必要性を示している.
- 著者
- 水上 聡子 井口 豊
- 出版者
- 一般社団法人 日本環境教育学会
- 雑誌
- 環境教育 (ISSN:09172866)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.1_3-13, 2023-03-31 (Released:2023-04-29)
- 参考文献数
- 16
Conclusions were drawn by analyzing the potential of residential citizen education based on the design and implementation of Fukui Prefectural education for climate change titled, ‘Problem-solving workshop using the Jigsaw method.’ The following results were obtained:1) Discussions were carried out for the purpose of acquiring ‘knowledge,’ ‘raising consciousness’ and ‘instilling the skills’ that are important for educating citizens. To a certain degree, this enabled students to consider existing issues and possibilities, future visions, and measures to realize them.2) All 10 elements of competencies improved. The lower the scores were before the class, the greater the demonstrable change evident after the class. The elements such as ‘strategic,’ ‘anticipatory’ and ‘critical thinking’ of the four competencies that were explained in the class showed measurable improvement.3) The changes in the 10 competencies were categorized as ‘collaboration’ and ‘independence.’ It was shown that, as a result of collaborative activities, competencies closely related to ‘collaboration’ improved significantly. On the other hand, it was evidenced that a characteristic of the Jigsaw method is to enhance each person’s independence by contributing to the team through his/her role playing.4) After a certain period, the research demonstrated that there are changes in consciousness and behavior for not only everyday issues such as conservation of electricity and water, but also for more diversified areas. It also indicated that efforts are needed to broaden visions and there is a need for cooperation using various means, such as gathering information and discussions between family members.
2 0 0 0 OA 国産旅客機;光と陰
- 著者
- 水野 洋
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.638, pp.55-59, 2007-03-05 (Released:2019-04-22)
- 参考文献数
- 8
2 0 0 0 OA 我が国におけるアルミニウム製器具・容器包装由来のアルミニウム摂取量の推定
- 著者
- 河村 葉子 馬場 二夫 渡辺 悠二 六鹿 元雄
- 出版者
- 日本食品化学学会
- 雑誌
- 日本食品化学学会誌 (ISSN:13412094)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.1-8, 2016 (Released:2016-04-28)
- 参考文献数
- 32
Aluminum is the third most abundant element in the earth’s crust and is widely used by humans including aluminum kitchen utensils and food packages. The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) revised the provisional tolerable weekly intake (PTWI) for aluminum to 2 mg/kg body weight/week in 2011. The estimated range of mean dietary aluminum intake was 2-19 mg/person/day based on the literature. Aluminum kitchen utensils and food packages have the possibility to release aluminum into foods during cooking or storage, though the estimated aluminum intakes from them were reported very few. Therefore, Japanese aluminum intake was estimated based on our test results and Japanese food consumption data. The estimated aluminum intake from aluminum kitchen utensils and food packages was the highest for an adult per person, however, it was the highest for a child based on body weight. They ranged from 0.277-0.570 mg/person/day (0.06-0.12 mg/kg bw/week) on average and 0.677-1.333 mg/person/day (0.15-0.29 mg/kg bw/week) at a maximum. All of these results were sufficiently lower than the PTWI.
2 0 0 0 OA 内観併用絶食療法の手技とその効果の実態(心身医学領域における治療の実態)
- 著者
- 鈴木 仁一
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.5, pp.451-458, 1982-10-01 (Released:2017-08-01)
- 被引用文献数
- 1
From time immemorial, it has been well known that fasting has an excellent effect on various diseases and has been practiced in world-wide areas as a religious asceticism. However, nowadays, it has being practiced as a proper medical therapy for psychosomatic disorders. Our scientific study of fasting started from 1967,and has been carried out in 576 cases with an efficacy rate of 87%.The following diseases were considered as suitable indications for the therapy; irritable colon, abnormal eating behavior, functional disorders of the digestive organ, neurocirculatory asthenia, borderline hypertension, variable psychosomatic symptoms of puberty, hyperventilation syndrome, bronchial asthma, various kinds of neurosis especially conversion hysteria, reactive depression and many others of psychosomatic diseases.The patient is put on 10-day fasting allowing to have only drinking water and 5% pentose solution by I.V., after that a 5-day recovery dieting period with settled menu is programed. During the fasting period, NAIKAN therapy is performed which is a special self-examination that method based on Buddhism. With regard to the mechanism of effectiveness, our conclusion is the regulating of the peripheral and central autonomic nervous system and of the endocrine system may change psychophysiological functions. At the result, a spontaneous deconditioning of maladaptive bodily and mental behavior might be induced and led to a homeostatic adjustment of the human body.
2 0 0 0 OA 第5回 大木伸夫さんインタビュー
- 著者
- 長田 裕臣
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.108-111, 2014 (Released:2016-04-05)
薬学出身でありながら他分野で活躍されている方にインタビューするコラム「薬学がくれた私の道」,今回はロックバンドACIDMANを率いるミュージシャンの大木伸夫さんのご登場です.
2 0 0 0 OA 生体分子シミュレーションに関する発展
- 著者
- 岡本 祐幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.6, pp.388-389, 2019-06-05 (Released:2019-10-25)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
特別企画「平成の飛跡」 Part 2. 物理学の新展開生体分子シミュレーションに関する発展
2 0 0 0 OA 間合いと身体知
- 著者
- 諏訪 正樹 坂井田 瑠衣 伝 康晴
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.255-262, 2017-03-01 (Released:2020-09-29)
2 0 0 0 OA 「札幌市パートナーシップ宣誓制度」の導入過程におけるSNSを介したフレーム伝播
- 著者
- 横尾 俊成
- 出版者
- 一般社団法人 社会情報学会
- 雑誌
- 社会情報学 (ISSN:21872775)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.65-79, 2019-06-30 (Released:2019-07-10)
- 参考文献数
- 16
本稿は,渋谷区の「同性パートナーシップ条例」から波及した札幌市の「札幌市パートナーシップ宣誓制度」を事例に,その導入過程における「フレーム伝播」と呼ぶべき現象を捉え,現代の日本において,地方自治体の新政策の波及にSNSを用いた社会運動がどのような影響を持ち得るのかを実証的に分析するものである。札幌市の制度の特徴は,首長からの発案ではなく,社会運動からの提案の結果つくられた点にある。札幌市でみられた社会運動は,組織による資源動員,さらにSNSを活用した「フレーム増幅」と「フレームブリッジ」の組み合わせからなる「フレーム伝播」を経て,市長や職員,議員の判断に影響を与えた。また,世田谷区での運動のキーパーソンは,制度の波及を意識した区議会議員,札幌市のキーパーソンは,渋谷区や世田谷区の事例に学び,行政にアプローチしたLGBT当事者であり,どちらもSNSの影響力を意識していた。新政策の波及に住民による運動が影響を与えた背景には,SNSやそれが生み出すネットワークによって,住民が多くの人の共感を生み出す発信力と受信力を持ったことが大きい。人々は,投稿によって社会的な認知をつくり出し,行政などに対して多数の賛同者の姿を見せられるようになったのである。
2 0 0 0 OA AI/IoT社会における規範問題を考える計算社会科学とポスト・ヒューマニティ
- 著者
- 遠藤 薫
- 出版者
- 一般社団法人 社会情報学会
- 雑誌
- 社会情報学 (ISSN:21872775)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.1-18, 2019-12-31 (Released:2020-01-18)
- 参考文献数
- 40
20世紀後半に始まった「情報社会」は,21世紀に入って,より高度なレベルに達した。現代では,単に高機能のコンピュータおよびそのネットワークによって社会が効率化されるというだけでなく,人工知能(AI)技術や,世界のあらゆるモノが常時相互にネット接続されるIoT (Internet of Things)技術が,すでに深くわれわれの生活に浸透している。このような状況の中で,いま注目されている学術領域が,社会情報学とも密接に関係する「計算社会科学(Computational Social Science)」である。計算社会科学とは,張り巡らされたデジタル・ネットワークを介して獲得される大規模社会データを,先端的計算科学によって分析し,これまで不可能であったような複雑な人間行動や社会現象の定量的・理論的分析を可能にしようとするものである。この方法論によって,近年社会問題化している,社会の分断,社会関係資本の弱体化,不寛容化など,個人的感情や社会規範,世論などの形成過程の解明に新たな可能性を切り開くことが期待される。その一方で,社会規範を逸脱する目的にこのような手法が応用されれば,かえって社会監視を密にしたり,情報操作を巧妙化したりする具になり,先に挙げた社会の分断などの問題を再帰的に拡大することも起こりうる。本稿では,計算社会科学をキーワードとして,ポスト・ヒューマンの時代を射程に入れつつ,社会を解明する具としての科学と,社会の動態とが入れ子状になった今日のAI/IoT社会の規範問題について考察する。
- 著者
- 日高 真人 松田 裕貴 諏訪 博彦 多屋 優人 安本 慶一
- 出版者
- 一般社団法人 社会情報学会
- 雑誌
- 社会情報学 (ISSN:21872775)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.23-36, 2021-12-31 (Released:2022-01-25)
- 参考文献数
- 36
スマートツーリズムは,世界的に注目を集めている。その構成要素の一つとして,ユーザの観光履歴や嗜好に基づく推薦システムが多く提案されている。一方で,マーケティングの分野では,近年,パーソナリティや動機などの心理的要素に着目した推薦の研究がなされているが,観光分野では少ない。そこで,本論文では,どのような特性のユーザにどのような推薦をすべきかを明らかにするために,観光客のパーソナリティに着目し観光行動との関係性を分析する。具体的には,「観光客のパーソナリティの違いによって観光行動(観光行動エリア・観光行動カテゴリ)が異なるか」について検証を行う。検証のために,1,000人に京都観光を想定したアンケート調査を実施している。検証の結果,観光客のパーソナリティの違いによって観光行動が異なることを確認している。具体的には,外向性が低い観光客は清水寺などの人気のある観光エリアに行きやすいなど,を明らかにしている。また,その結果に基づいて,外向性が低い観光客に対しては観光スポットの人気度を示したり,他の観光客からのレビューを表示したりするなど,パーソナリティに合わせた観光推薦について考察している。