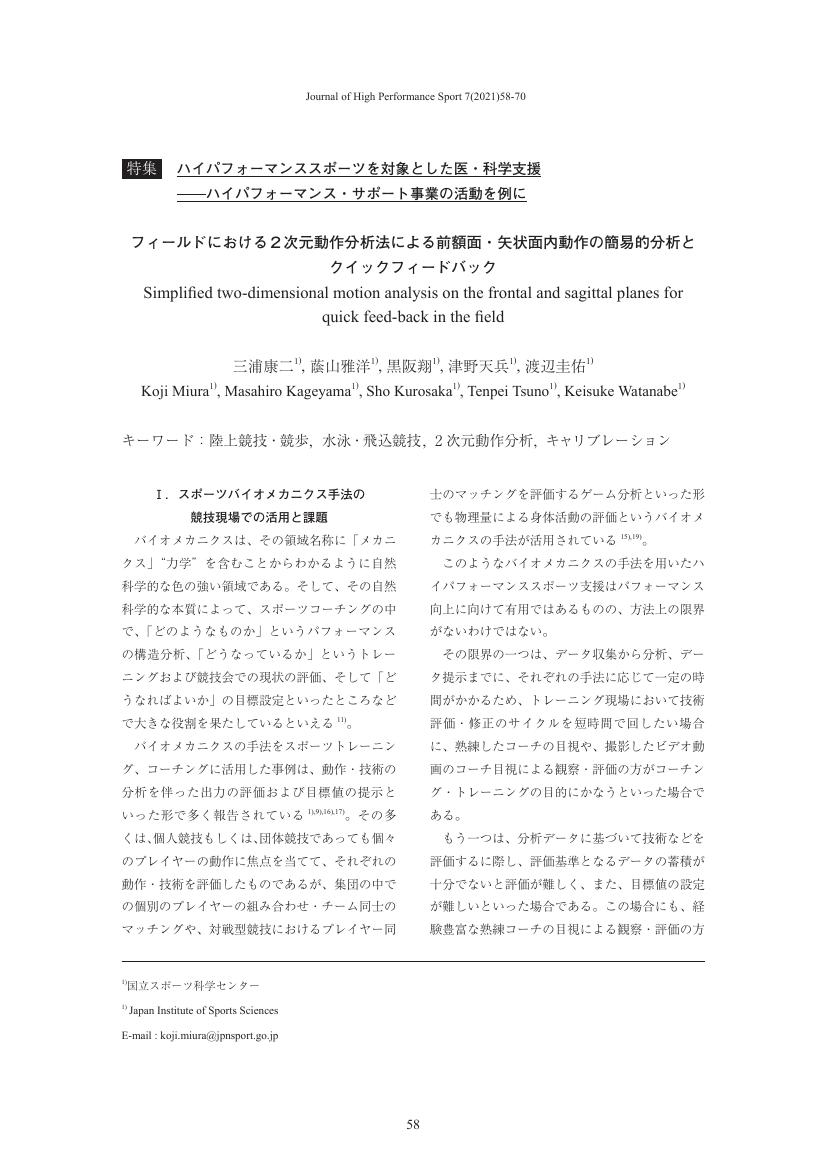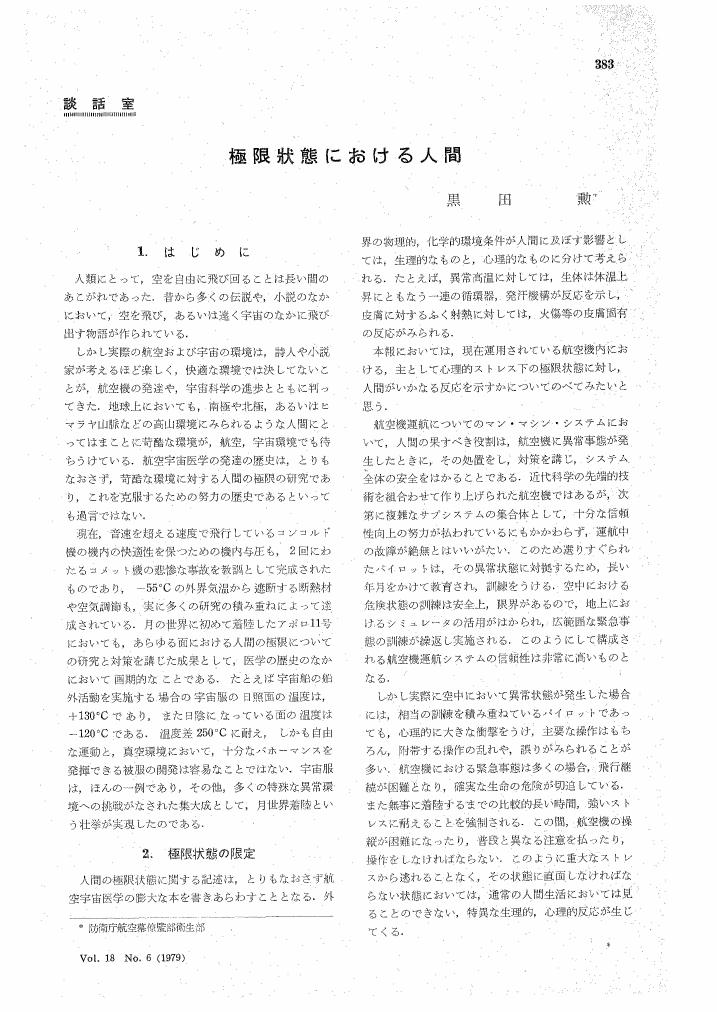- 著者
- 三浦 康二 蔭山 雅洋 黒阪 翔 津野 天兵 渡辺 圭佑
- 出版者
- 独立行政法人 日本スポーツ振興センター国立スポーツ科学センター
- 雑誌
- Journal of High Performance Sport (ISSN:24347299)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.58-70, 2021 (Released:2021-12-29)
- 参考文献数
- 20
- 著者
- 菅野 康夫
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.64-65, 2019-01-15 (Released:2020-02-15)
- 参考文献数
- 6
2 0 0 0 OA 漢方薬の煎液およびエキス製剤の成分分析 -カンゾウ配合漢方薬中のグリチルリチン酸量-
- 著者
- 黒田 明平 木下 歩美 椎 崇 社本 典子 三巻 祥浩
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.11, pp.619-629, 2017-11-10 (Released:2018-11-10)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 3 3
Pseudohyperaldosteronism and associated hypokalemia are serious adverse effects caused by glycyrrhizinic acid (GA) present in Kampo medicines containing Glycyrrhizae Radix (GR); GA is the major component of GR. To obtain knowledge about the effective and safe use of Kampo medicines, we analyzed the quantities of GA in Kampo medicines by HPLC. The quantities of GA in 13 Kampo decoctions containing GR (2-6 g/day) were found to be almost 2-3.5 fold higher than those of the corresponding Kampo extract products. Among the Kampo extract products containing GR (3 g/day), the GA quantity in Shoseiryuto was significantly lower compared with that in the others, and Pinelliae Tuber as well as Schisandrae Fructus were found to contribute to the decrease in GA quantity. The GA quantity in the Yokukansakachinpihange decoction was found to be lower than that in the Yokukansan decoction; this was caused by the presence of Pinelliae Tuber and Citri Unshiu Pericarpium. Analysis of inter-product variations in GA quantities among the Kampo extract products revealed a maximum 2.6-fold difference in the quantities in the Shoseiryuto extract products from different companies. Our analyses show that GA quantities in Kampo medicines are influenced by the presence of concomitant crude drug constituents. This results in differences in GA quantities between decoctions and extract products having the same Kampo formula, and also among the Kampo extract products from different companies. It is recommended that GA quantities in Kampo extract products should be presented to prevent the adverse effects caused by GA.
2 0 0 0 OA 《書評》 永嶺 重敏 著『オッペケペー節と明治』
- 著者
- 長島 平洋
- 出版者
- 日本笑い学会
- 雑誌
- 笑い学研究 (ISSN:21894132)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.87-88, 2019 (Released:2019-11-30)
2 0 0 0 OA 沖縄地方のリスク層の若者の移行状況に関する聞き取り調査
本研究はこれまで焦点の当てられることのなかった、地方在住のリスクを抱える若者の移行過程の聞き取り調査である。調査において特に注目したのは、これまでの移行調査では扱われることのなかった暴力や性の問題である。暴力や性の問題は、①当事者との合意が形成しづらく、②バッシングに転化しやすいことからこれまで記述されることがなかった。本調査研究では、そうした問題が起こるのかを、かれらの資源の枯渇状況を描くとともに、当事者の合意を経ながら記述をすすめることで、貧困研究においてえがかれることのなかった、暴力や性の問題を記述することができた。
2 0 0 0 自信過剰が男性を競争させる
本稿では,なぜ男性は女性と比べて,自身の成果のみに依存した報酬体系よりも他人の成果にも依存する報酬体系を好むのかについて,日本人学生を対象に実験を行うことで原因の解明を試みる.分析の結果は次の通りである.(1)男女でパフォーマンスの差はないが,女性より男性のほうが競争的報酬体系(トーナメント制報酬体系)を選択する確率が高い.(2)そのトーナメント参入の男女差の大部分は,男性が女性よりも相対的順位について自信過剰であることに起因する.(3)男女構成比は相対的順位に関する自信過剰に影響を与える.男性は女性がグループにいると自信過剰になり,女性は男性がグループにいないと自信過剰になる.(4)相対的自信過剰の程度をコントロールすると,トーナメント参入の男女差に対する競争への嗜好の男女差による説明力は弱い.
2 0 0 0 OA メディアと戦争柄着物
戦争柄の着物(着物、襦袢、帯などに軍艦、銃、国旗等の軍事的モチーフを染め、又は織り出したもの)と、それらの制作された同時代におけるメディア(新聞記事、絵はがき、雑誌挿絵、ニュース映画など)との関連を探った。大きく分類すると絵はがき、新聞紙面などをそのまま写した図柄と、ニュース映画などに基づいたことを示すことが目的かと考えられる図柄とがある。その両方ともに再現性が高く、抽象的な要素もある銃や軍艦などの図様との両方の手法を混在させた着物図柄の規矩による意匠化である。これらの意匠は基本的には商業的な目的において製造、販売されたにすぎないが、その故に大きな社会的な影響力を有したと考えられよう。
2 0 0 0 OA ステレオビジョンを用いた移動ロボットの人物追従制御
- 著者
- 佐竹 純二 三浦 純
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.9, pp.1091-1099, 2010 (Released:2012-01-25)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 10 9
This paper describes a stereo-based person detection and tracking method for a mobile robot that can follow a specific person in dynamic environments. Many previous works on person detection use laser range finders which can provide very accurate range measurements. Stereo-based systems have also been popular, but most of them have not been used for controlling a real robot. We propose a detection method using depth templates of person shape applied to a dense depth image. We also develop an SVM-based verifier for eliminating false positive. For person tracking by a mobile platform, we formulate the tracking problem using the Extended Kalman filter. The robot continuously estimates the position and the velocity of persons in the robot local coordinates, which are then used for appropriately controlling the robot motion. Although our approach is relatively simple, our robot can robustly follow a specific person while recognizing the target and other persons with occasional occlusions.
- 著者
- 安藤 徹哉 小野 啓子 ウァントゥラポーチ ピーチャイ
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.595, pp.165-172, 2005-09-30 (Released:2017-02-11)
- 参考文献数
- 28
Keikamotsu is officially cargo service, but informally, it has been providing passenger service in Naha, Okinawa after World War Two. It is illegal for Keikamotsu to provide passenger service and although the number of vehicles has significantly decreased after the revision of law in 1985, Keikamotsu is still used today by the elderly and students as it is more convenient than buses and cheaper than taxies. This paper looks at the history, operation and usage features of Keikamotsu and examines the possibility of formally incorporating paratransit service into the local transportation system based on the experience of Keikamotsu. While conventional transportation service is in crisis in many regional small cities in Japan, this study aims to consider cost- and time-effective ways of improving local transportation system.
2 0 0 0 OA サディズムとマゾヒズム : ジャン= ポール・サルトルにおける性的態度について
- 著者
- 竹本 研史
- 出版者
- 法政大学人間環境学会
- 雑誌
- 人間環境論集 = 人間環境論集 (ISSN:13453785)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.1-42, 2016-12-21
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1617, pp.54-59, 2011-11-21
クライマックスシリーズ(CS)で、シーズン優勝の中日ドラゴンズをあと一歩のところまで追い詰めた東京ヤクルトスワローズ。けがによる戦線離脱が相次ぎ、最後は力尽きたが、レギュラーシーズンの132試合目まで首位を快走した今季の戦いぶりは、戦前の予想を覆した驚異的な内容だった。 中日とのCSの死闘も、野球ファンを唸らせた。
- 著者
- 小川 淳司
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1617, pp.60-63, 2011-11-21
「名選手、必ずしも名監督ならず」という格言がある。ところが、実績や人気がなければプロ野球の監督にはなかなか就任できないという日本球界の現実もある。それを思えば、小川淳司は従来の監督像からは懸け離れた存在と言える。 「選手としての実績がない分、最も一般の人に近い感覚を持っている」。
- 著者
- 角野 浩史 ウォリス サイモン 纐纈 佑衣 遠藤 俊祐 水上 知行 吉田 健太 小林 真大 平島 崇男 バージェス レイ バレンティン クリス
- 出版者
- 一般社団法人日本地球化学会
- 雑誌
- 日本地球化学会年会要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.64, 2017
<p>四国中央部・三波川変成帯に産する変泥質岩、エクロジャイト、蛇紋岩、かんらん岩のハロゲン・希ガス組成は一様に、深海底堆積物中の間隙水と非常によく似た組成を示す。同様の組成は島弧火山岩中のマントルかんらん岩捕獲岩や深海底蛇紋岩でも見られることから、沈み込み前に屈曲したプレートの断層沿いにプレート深部に侵入した間隙水がスラブマントルを蛇紋岩化する際に、ハロゲンと希ガスが組成を保ったまま蛇紋岩に捕獲されて沈み込み、水とともにウェッジマントルへと放出されている過程が示唆される。</p>
2 0 0 0 OA 極限状態における人間
- 著者
- 黒田 勲
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.6, pp.383-385, 1979-12-15 (Released:2018-03-31)
2 0 0 0 OA 高齢者のターミナルケアのあり方
- 著者
- 松下 哲
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.91-95, 2001-01-25 (Released:2009-11-24)
- 参考文献数
- 28
高齢者の終末医療では生命, 人間, 老化, 死に対する考え方が反映され, 実践される医療の質が問われる. 国民からみた現代医療は社会にとって大きい存在, 特異な亜文化, 高い統一性, イデオロギー性があり, 無益な治療つまり誤った技術の用い方が問われている. これは医学が客観性「もの」を追う科学の仲間入りをし, 進歩を遂げる条件として「こころ」を放棄したことに由来している. 故にこころの扱いが中心となる終末医療では問題が顕わとなる. 終末医療は文化全体と整合する道, こころを中心においた Art of Dying を探らなければならない. それは生, 老, 死に関する生命科学の進歩と生命観の発達を基とし, インフォームド・コンセントを中核とする緩和医療にほかならない. 天寿がんはこれらを具現する概念の一つであり, これを目標として Art of Dying が拡がる. 実践にあたっては高齢者にふさわしい理念から実際のケアに亘るガイドライン, 教育が求められる. 緩和医療の時期は不可逆的になったときから, また治療が尊厳を損ねるようになる時点からである. 高齢者は自ら医療やケアの改善を求める力がないことが多く, 家族も身近に死を経験するまではその良し悪しを判断しにくい. 医療やケアの情報を分かりやすく公開し, 緩和医療が高齢者と家族から選択されるよう推進する必要がある.
- 著者
- 井手 広康
- 出版者
- 情報処理学会 ; 1960-
- 雑誌
- 情報処理 (ISSN:04478053)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.5, pp.254-257, 2021-04-15
2020年10月,大学入試センターは,2024年度の大学入学共通テストに教科「情報」を新設する方針を示した.さらに同センターはこの翌月,「大学入学共通テストにおける「情報」試作問題(検討用イメージ)」を関連団体に通達した.本稿では,これまでの教科「情報」の変遷と,大学入学共通テスト「情報」試作問題の概要を記すとともに,情報担当の教員が試作問題に対してどのような想いを抱いているのかをまとめる.
2 0 0 0 OA 羞恥感情を引き起こす状況の構造 : 多変量解析を用いて
- 著者
- 成田 健一 寺崎 正治 新浜 邦夫 Kenichi Narita Masaharu Terasaki Kunio Niihama
- 雑誌
- 人文論究 (ISSN:02866773)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.73-92, 1990-06-15