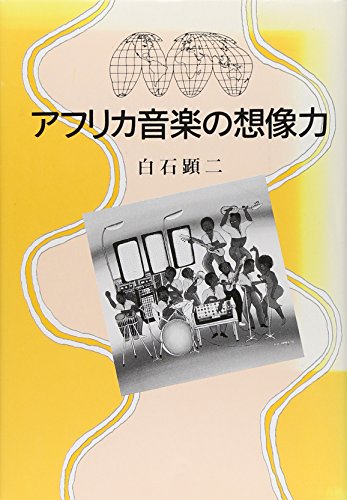1 0 0 0 OA ボルネオ熱帯山地林と低地林における降雨と渓流水の溶存物質濃度の特性
1 0 0 0 アフリカ音楽の想像力
- 著者
- 稲吉 直哉 白倉 祥晴
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.46 Suppl. No.1 (第53回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.H2-166_2, 2019 (Released:2019-08-20)
【はじめに】頸椎症性筋萎縮症(以下Keegan型頚椎症)は上位近位筋の筋力低下を主症候とし、感覚障がいがないか軽微なことが多い。Keegan型頚椎症は自然回復の報告も多いが、高齢になるほど、回復率も下がるとする報告や徒手筋力テスト(以下MMT)2以下では手術の方がよいという報告などがあるが、手術療法、保存療法のどちらが良いか一定の見解は示されていないことが現状である。また保存療法の報告はあるが、運動療法の報告は特に少ない。そこで今回、Keegan型頚椎症に対する運動療法により症状が改善されたので報告する。【症例紹介】84歳代男性。左利き。鍋の焦げを取るためスポンジで強く擦り、翌日より右肩痛と挙上困難感出現。2週間ほど様子を見たが、疼痛は緩和したが右肩挙上困難感が残存し、当院受診。手術の希望はなく、外来リハビリテーション開始した。X線、MRI所見では、C3/4、C4/5、C5/6、C6/7に椎間板の軽度膨隆を認めた。棘上筋の変性は認めたが連続性は保たれていた。神経内科診察により、他の運動ニューロン疾患は否定された。【介入方法】初期理学療法時、主訴は右肩挙上困難のみで疼痛・しびれ・感覚障がいの訴えはなかった。Shoulder36V.1.3:45点、MMT右肩屈曲1、肘屈曲4、ほかの筋群には著明な筋力低下なし。右肩関節可動域(以下ROM)屈曲Active10°、Passive160°、肘屈曲Active・Passiveともに制限なし。頚部のROMは左側屈・左回旋制限が認められた。右肩屈曲動作時には右肩甲帯の挙上が認められ、右僧帽筋上部線維、右肩甲挙筋に圧痛が認められた。また座位姿勢はHead Forward姿位であった。介入当初より右肩屈曲Passive ROM制限予防のため、右肩関節のROM-ex、僧帽筋上部線維、肩甲挙筋に対し、横断伸長法を実施した。右肩三角筋の萎縮を認めたため、三角筋に対し低周波療法(Inter Reha社)を実施した。低周波療法実施肢位は背臥位、redcord(Inter Reha社)を使用し、頸椎はNeutral position位になるよう、頸椎牽引を行い、右上肢は自重を免荷した。低周波が流れるタイミングで自動介助運動を行った。刺激強度は疼痛のなく三角筋の収縮が確認できる強度で5秒間通電し、5秒間休息を1セットとし、20分間実施した。また頚椎のHead Forward姿位改善のため、頚部深部屈筋群のエクササイズを行った。リハビリテーション介入5週目から徐々に右肩関節屈曲可動域Activeが徐々に改善が認められ、介入10週目で右肩関節屈曲可動域Active 90°まで回復。また右肩屈曲90°保持も可能となった。頚部のROMも側屈、回旋ともに左右差はほぼなくなった。この週より自動介助運動の肢位を背臥位から右肩上の側臥位へ変更し、三角筋の収縮が触知できるようになったので低周波療法から中周波療法へと変更した。介入13週目Shoulder36V.1.3 :116点、MMT右肩屈曲3、右肩ROM屈曲Active120°であった。【結論】乾は1)Keegan型頚椎症の予後予測では発症期間が6ヶ月未満、MMT3以上が予後良好であり、また、年齢も高齢になればなるほど予後不良となると報告している。齋藤2)は罹患期間が長く、筋萎縮が顕著であれば筋萎縮から手術により圧迫が解除されても筋が線維化し回復が望めない可能性があると報告した。そのため筋萎縮から線維化を防ぐため低周波・中周波療法を実施した。また、安藤3)は保存的治療・予防には頚椎の良い姿勢を保持することが重要と報告している。今回はHead Forward姿位改善のため、緊張筋である僧帽筋上部線維、肩甲挙筋に対し、筋緊張緩和を行い、頚部深部屈筋群の促通を実施し、良肢位保持へと誘導した。Keegan型頚椎症は筋萎縮から線維化防止と頚椎良肢位保持のため、電気療法と運動療法の併用は検討の余地があると考えられる。【参考文献】1)乾義弘 新原著レビュー:頚椎症性筋萎縮症に対する保存的および手術的治療の臨床成績とその予後予測因子 20122)齋藤貴徳 近位型頚椎症筋萎縮症 20163)安藤哲朗 頚椎症の診療 2012【倫理的配慮,説明と同意】本研究は、当院倫理委員会にて承認を得た。患者にはヘルシンキ宣言に基づいて文書と口頭にて意義、方法、不利益等について説明し同意を得て実施した。
- 著者
- 白鳥 浩
- 出版者
- NPO法人 日本シミュレーション&ゲーミング学会
- 雑誌
- シミュレーション&ゲーミング (ISSN:13451499)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.90-91, 2004-06-25 (Released:2020-09-01)
1 0 0 0 橈骨遠位端骨折手術後の安全な自動車運転再開に関する指標の確立
1 0 0 0 公開天文台白書
- 著者
- 日本公開天文台協会公開天文台白書編集委員会編
- 出版者
- 兵庫県立西はりま天文台公園, 2007.3-
- 巻号頁・発行日
- 2007
1 0 0 0 OA 救急集中治療における重症患者に対する栄養療法とNSTの活動
- 著者
- 白井 邦博
- 出版者
- 一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会
- 雑誌
- 日本静脈経腸栄養学会雑誌 (ISSN:21890161)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.4, pp.231-236, 2019 (Released:2019-11-20)
- 参考文献数
- 26
急性期医療を要する重症患者では、侵襲による過剰な炎症で代謝異化状態が亢進するため、まずは救命を目的に炎症を制御して呼吸循環動態を安定させる。その後は、急性期、回復期から退院後のquality of life(以下、QOLと略)向上を見据えた救急集中治療を継続的に行わなければならない。これに対して、栄養療法は救急集中治療の連鎖の一貫であり、急性期だけでなくQOLを改善させるための治療として認識する必要がある。さらに、ガイドラインやエビデンスの高い研究を活用して、各施設の実情にあったマニュアルやプロトコールを作成し、栄養サポートチーム(nutrition support team;以下、NSTと略)が遵守しながら適切な栄養療法を現場に提供することが重要である。
1 0 0 0 OA パーキンソン病患者における体幹前屈の姿勢異常の自覚および体幹前屈角度と前頭葉機能の関係
- 著者
- 三上 恭平 川崎 翼 白石 眞 加茂 力
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.2 (第51回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.1070, 2016 (Released:2016-04-28)
【はじめに,目的】パーキンソン病(PD)の体幹前屈(前屈)の姿勢異常(PA)は難治性で,病態背景も不明な点が多い。DohertyらはPDのPAの病態背景の一つに,姿勢の自覚に関わる固有感覚の統合異常を挙げているが,PAを呈するPD患者の姿勢の自覚についての報告は少ない。また近年PAには,前頭葉の機能低下との関連性も報告されている(Nocera JR, et al., 2010)。本研究では,1)前屈を呈するPD患者のPAの自覚の有無と修正の可否,2)前頭葉機能がPD患者の前屈と関係するかの2点を検討した。【方法】2014年6月から7月に当クリニックに来院したMini Mental State Examination(MMSE)24点以上のPD患者で,前屈の姿勢異常角度が10度以上の27名を対象とした(75.1±8.1歳。男性11名,女性16名)。前屈の自覚の評価は,立位で「前に曲がっていると感じるか」の問いに「感じる」を自覚あり,「感じない」を自覚なしとした。前屈の角度は静止立位および口頭で垂直位への修正を求めた修正立位の静止画を撮影しImage Jを用いて解析した。前頭葉機能評価にはFrontal Assessment Battery(FAB)を用い,川畑の分類に基づき12点をカットオフ値として低値群と高値群に分類した(川畑。2011)。PDの重症度分類にはHohen and Yahr(H-Y)Stageを用い,運動機能評価にはUnified Parkinson's diseases Rating Scale(UPDRS)PartIIIを用いた。統計解析は,前屈の自覚有り群,無し群およびFAB低値群と高値群の2群間における前屈角度,UPDRS Part III,H-Y Stage,MMSEの値の差を,対応のないt検定にかけて解析した。なお,統計分析の有意水準は全て5%とした。【結果】27例中17例が前屈を自覚し,自覚あり群(41.6±21.9度)では,自覚なし群(22.6±13度)より有意に前屈角度が大きかった(P=0.019)。自覚なし群の7例(70%)は,口頭指示による姿勢の修正が可能であった。FAB低値群は,高値群よりも体幹屈曲角度が有意に大きかった(P=0.04)。一方,FAB低値群と高値群の間でMMSE,H-Y Stage,UPDRS Part IIIに有意な違いはなかった。【結論】前屈の角度が高度であれば自覚はある。しかし,その角度が低い例では姿勢の修正が可能であるにも関わらず,前屈を自覚していないため修正できない。さらに体幹屈曲角度にはFABで示される前頭葉機能が一因として関わっている可能性があり,前屈姿勢の改善のためには,運動機能のみならず前頭葉機能を考慮したリハプログラムが必要である。
- 著者
- 白石 和也 藤江 剛 小平 秀一 田中 聡 川真田 桂 内山 敬介
- 出版者
- 社団法人 物理探査学会
- 雑誌
- 物理探査 (ISSN:09127984)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, pp.105-118, 2022 (Released:2022-12-28)
- 参考文献数
- 30
沿岸域の海底火山の活動性を評価するために,海底火山下の構造や物性を効果的に調査する地震探査法の確立を目的に,数値シミュレーションによる合成地震探査データを用いたフィージビリティスタディを行った。本研究では,海域と陸域を横断する測線長30 kmの調査を想定し,沿岸域にある海底火山の過去の活動痕跡あるいは現在の活動可能性を示唆する仮想的な構造を持つ深度10 kmまでの地質モデルを対象とした。このモデルでは,地殻内にマグマ溜りを模した3つの低速度体を異なる深度に設定し,その他には側方に連続的な明瞭な反射面が存在せず,一般的な反射法速度解析で地殻内の速度分布を決定するのは難しい構造とした。まず,作成した地質モデルに対して走時および弾性波伝播の数値モデリングを行い,地震探査で得られる初動走時と波形記録を合成した。そして,これらの合成地震探査データを用いて,初動走時トモグラフィと波形インバージョンによる段階的な解析により,低速度体を含む速度構造を推定した。その後,推定された速度モデルを用いてリバースタイムマイグレーションを適用し,反射波による構造イメージングを行った。また,発振点と受振点のレイアウトおよび低速度体の形状の違いについて比較実験を行った。数値データを用いた解析の結果,段階的なインバージョン解析により深度約6 kmまでの2つの低速度体を示唆する変化を含む全体的な速度構造を適切に捉え,深度領域の反射波イメージングによって3つの低速度体の形状を良好に描像することができた。速度構造の推定には探査深度と分解能について今後に改善の余地があるものの,一般的な反射法速度解析が難しい地質構造の場合には,波形インバージョンによる速度推定とリバースタイムマイグレーションによる反射波イメージングを組み合わせることで,地下構造を可視化するアプローチが効果的であることを示した。併せて,効果的な調査を計画するために,想定される地質モデルにおける最適な観測レイアウトや解析手法の適用性などについて,数値シミュレーションを用いたフィージビリティスタディにより事前検討する事の重要性も示された。
1 0 0 0 OA 高次脳機能障害者の医療と福祉における意思決定支援
- 著者
- 白山 靖彦 北村 美渚 伊賀上 舞 木戸 保秀
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.172-177, 2021-06-30 (Released:2022-06-30)
- 参考文献数
- 16
脳損傷により高次脳機能障害を呈した場合, 認知能力とともに, 意思決定能力も低下すると考えられている。意思決定能力とは, 自分の意思を伝えることができること, 関連する情報を理解していること, 選択した理由に合理性があることとされており, 医療同意能力や判断能力を包含する。しかし, 意思決定能力を定量・客観的に測定する指標は未だなく, 意思決定支援の定式化には及んでいない。したがって, 多職種による合意形成や, 質問方法の工夫といった支援者側のスキルが求められることになる。 本稿では, 高次脳機能障害者の医療と福祉における意思決定支援に関して, それぞれの立場におけるポイントを概説し, これまで行ってきた研究の一部を紹介する。
1 0 0 0 日本における上海土山湾工房作品の流布と影響に関する調査
土山湾は中国上海市徐家匯地区の村落である。1864年にイエズス会がそこに孤児院を設立し、職業訓練の工房を開設し、1950年代まで運営した。そこで制作された美術工芸品と印刷物は、幕末から昭和初期まで日本に輸入されて、博物館、記念館、修道院等に収蔵され、幅広く利用されている。本研究では、①日本に散在する土山湾の美術工芸品と刊行物に関する網羅的調査とデータベース化、②国内諸機関の書誌に対する補足情報の提供、③土山湾作品を手本とした幕末~明治初期の「プティジャン版」と布教用木版画の分析を通して、土山湾の作品が日本文化に与えた影響を検討し、日本現存の作品の保存と研究の推進に寄与したいと考える。
1 0 0 0 OA 放射線による遅延性染色体異常誘発効果はヒト6番染色体と8番染色体では異なる
- 著者
- 縄田 寿克 白石 一乗 松本 真里 押村 光雄 児玉 靖司
- 出版者
- 一般社団法人 日本放射線影響学会
- 雑誌
- 日本放射線影響学会大会講演要旨集 日本放射線影響学会第50回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.134, 2007 (Released:2007-10-20)
【緒言】 放射線が被曝した生存細胞の子孫に遅延性染色体異常を誘発することはよく知られている。そこで本研究は、被ばくした1本のヒト染色体を被ばくしていないマウス受容細胞に移入する手法を用いて、被ばく染色体が遅延性染色体異常誘発にどのような役割を果たすのかを明らかにすることを目的として行った。 【材料と方法】 遅延性染色体異常誘発に被ばく染色体が果たす役割を知るために、軟X線により4Gyを照射したヒト6番、及び8番染色体を被ばくしていないマウス不死化細胞に微小核融合法を用いて移入した。その後、微小核融合細胞における移入ヒト染色体の安定性を、ヒト染色体に特異的な蛍光DNAプローブを用いた蛍光着色法により解析した。 【結果と考察】 被ばくしていないヒト6番、及び8番染色体を移入した微小核融合細胞では、染色体移入後のヒト染色体の構造異常は全く見られなかった。このことは染色体移入過程で染色体構造が不安定化することはないことを示している。しかし、被ばくしていないヒト8番染色体を移入した5種の微小核融合細胞では、3種で8番染色体のコピー数が倍加していた。同様の変化は被ばくヒト8番染色体を移入した4種の微小核融合細胞のうち3種でも見られた。この結果は、ヒト8番染色体は数的変化を起こしやすいこと、さらに、放射線被ばくはこの変化に関与しないことを示唆している。一方、被ばくヒト6番染色体を移入した5種の微小核融合細胞では、4種において移入後に2~7種類の染色体異常が生じていた。これに対して、被ばくヒト8番染色体を移入した4種の微小核融合細胞では、移入後に2種類以上の染色体異常が生じていたのは1種のみであった。以上の結果は、被ばくヒト染色体が遅延性染色体異常誘発の引き金を担っていること、さらに、放射線による遅延性染色体異常誘発効果はヒト6番染色体と8番染色体では異なることを示唆している。
- 著者
- 近藤 隆子 白畑 知彦 須田 孝司 小川 睦美 横田 秀樹
- 出版者
- The Japan Society of English Language Education
- 雑誌
- 全国英語教育学会紀要 (ISSN:13448560)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.81-96, 2020-03-31 (Released:2021-04-01)
- 参考文献数
- 15
The present study investigates whether adult Japanese learners of English (JLEs) are able to use intransitive and transitive verbs in appropriate structures after a series of instructional sessions, and whether the effect of instruction can be observed with verbs which are not part of instruction. Second language learners have been reported to make errors concerning the structure of verbs. For instance, they tend to overpassivize some intransitive verbs (Hirakawa 1995, Zobl 1989) or use transitive verbs in the intransitive structure (Kondo 2014). In this study, we examine whether explicit instruction can be effective for JLEs to avoid the errors aforementioned, not only with verbs which are explained in instruction but also with those which are not. The results show that in general, the participants improved on their uses of intransitive and transitive verbs after receiving instruction, and interestingly the improvement was observed with both instructed and non-instructed verbs.
1 0 0 0 OA 神林長平論 : コミュニケーションと意識の表現
1 0 0 0 OA 社債流通市場における社債スプレッド変動要因の実証分析
- 著者
- 白須 洋子 米澤 康博
- 出版者
- 日本ファイナンス学会 MPTフォーラム
- 雑誌
- 現代ファイナンス (ISSN:24334464)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.101-127, 2008-09-30 (Released:2018-12-07)
- 参考文献数
- 67
- 被引用文献数
- 2
本稿は,1997年から2002年前半までのいわゆる金融逼迫時における国内社債流通利回りの対国債スプレッド(杜債スプレッド)変動を実証的に分析し,その変動要因を明らかにすることを目的としている.分析の結果,金融逼迫時等の状況下では,投資家は,より流動性のある社債又は国債へ,あるいは,より安全性の高い高格付け債に資金需要を逃避させる,いわゆるflight to liquidityあるいはflight to qualityと言われる現象が見受けられた.前者は流動性制約を有する投資家の流動性需要によって,後者は投資家の危険回避度の高まりによってそれぞれ説明できることがわかった.また両現象のうちflight to liquidityの方が強いことも明らかになった.流動性に関しては,これまでの分析はマーケット・マイクロストラクチャーの視点から見た,執行コストを分析の対象としたものであったが,本稿は投資家の流動性需要という価格に直接的に影響を与える要因を取り上げた点に特長があり,従来の実証分析とは大きく異なる.
1 0 0 0 OA 日本基礎心理学会第40回大会シンポジウム1 基礎心理学研究における深層学習の役割
1 0 0 0 長崎県沿岸に生息するスナメリの生活史に関する研究
1.分布・行動(1)大村湾当海域での発見例が極めて低いが、目視調査への協力者が増えた結果、湾内でスナメリが季節的に移動していることが伺がえるだけのデ-タの蓄積が出来た。即ち、冬期の湾奥にあたる南東部への集中と夏期における分散が伺えた。ただし発見数が極めて少ないため、正確に回遊を把握することはできなかった。(2)有明海・橘湾本海域では3年近いデ-タの蓄積から、各調査コ-ス毎に独特な季節変動が繰り返されていることが明らかになった。即ち、有明海奥部と橘湾との間を季節的に移動し、冬期には有明海奥部に集中する傾向がみられた。この移動は主に岸から2マイル以内を使って行なわれている。2.漁業との関連性本種は小型の魚類や軟体動物,甲殻類など多様な生物を餌としている。大村湾ではこれら餌となる生物の漁獲量が年々減少しており、発見数の減少と合わせて心配されている。有明海、橘湾ではさほどの減少は見られていない。また、餌生物への選択性に乏しく、、漁業との競合は少ない。3.生活史新生仔及び胎仔の状況から、本種の出生時期は秋から冬にかけてのかなり長い期間であることが推察された。冬期の集中行動と出生時期からこれらの間には深い関係があることが伺がわれた。雄は雌に比べて早く成熟する。今回の最高会の個体は雌で255才であった。4.資源量資源量を絞り込むことは出来なかったが、大村湾では数十から百といった危桟的な状態と考えられるし、他でも決して多くはない。
1 0 0 0 OA ミリ波帯無線LANシステムの標準化動向と要素技術
- 著者
- 滝波 浩二 白方 亨宗 入江 誠隆 高橋 和晃
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.100-106, 2016-09-01 (Released:2016-09-01)
- 参考文献数
- 13
1 0 0 0 OA HTLV-I関連細気管支・肺胞異常症 (HABA) の6症例
- 著者
- 木村 郁郎 坪田 輝彦 上田 暢夫 多田 慎也 吉本 静雄 十川 重次郎 白石 高昌 玉木 俊雄 植野 克巳 藤田 豊明 今城 健二 入江 正一郎 難波 次郎 福田 俊一
- 出版者
- The Japanese Respiratory Society
- 雑誌
- 日本胸部疾患学会雑誌 (ISSN:03011542)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.9, pp.1074-1081, 1989-09-25 (Released:2010-02-23)
- 参考文献数
- 9
びまん性汎細気管支炎 (DPB), 特発性間質性肺炎 (IIP) の中にATLを発症ないし抗ATLA抗体陽性を示すもののあることを見いだしたが, ATLの側からみればその肺病変の中に肺炎とか腫瘍細胞浸潤以外に細気管支肺胞領域に特異的な病態像を形成するものがあり, この病態をHTLV-I関連細気管支・肺胞異常症, HTLV-I associated bronchiolo-alveolar disorder (HABA) と称した. そして, これまでに見いだした細気管支型5例及び肺胞型1例の計6例の臨床的特徴について述べた. 本病態はHTLV-I感染後長年の間に形成されるものと考えられるが, DPB, IIPの成因についての示唆を与えるものと思われる.