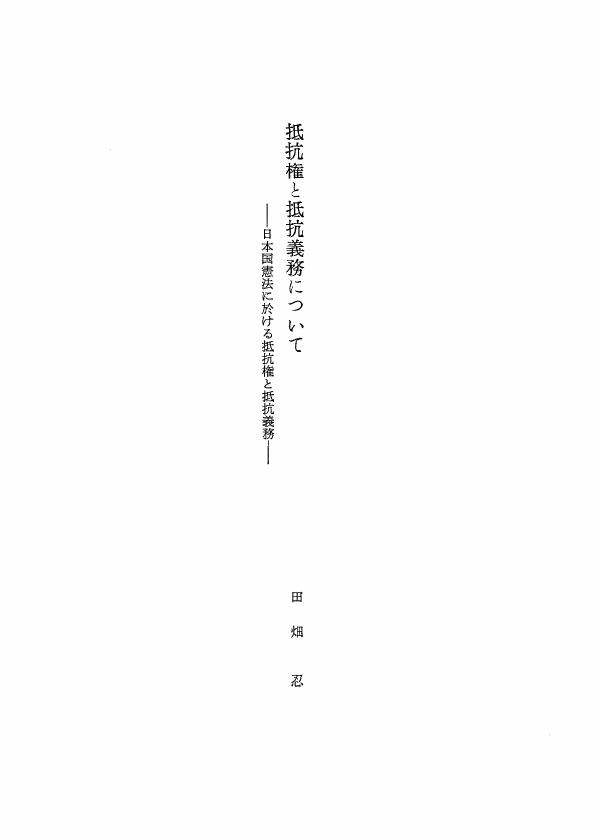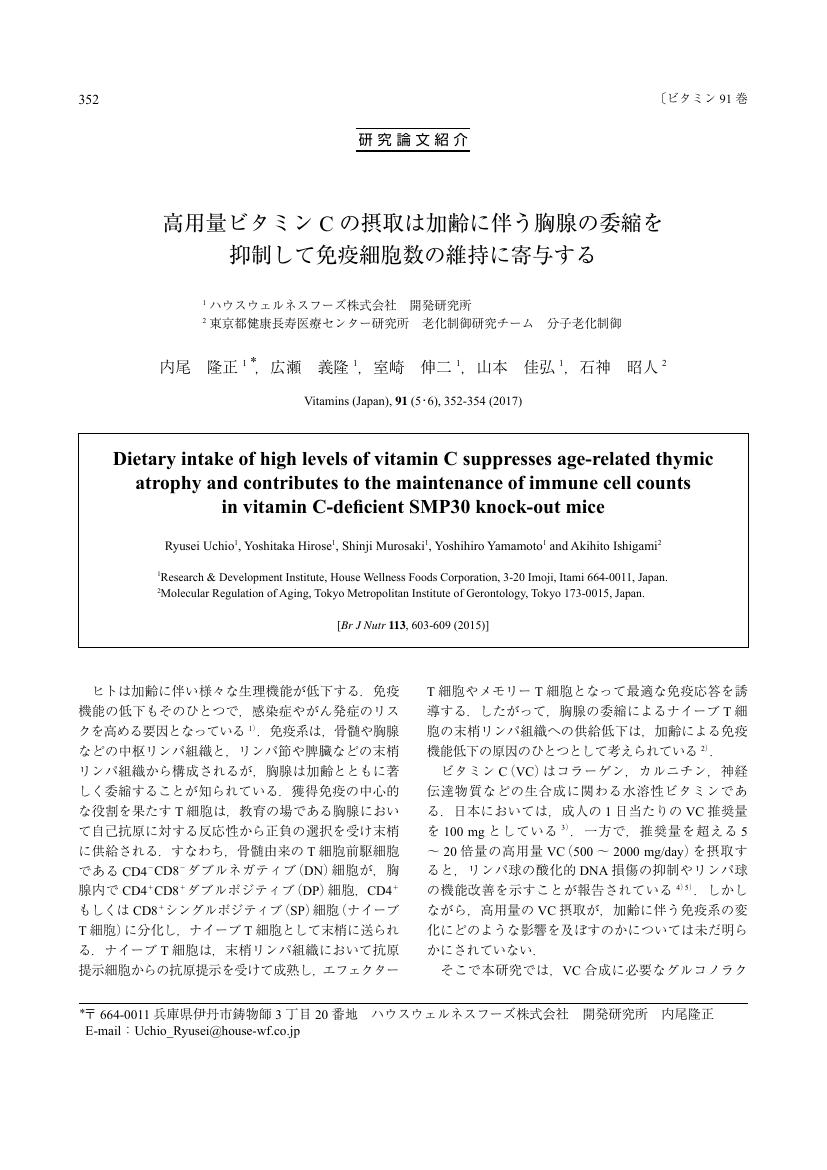17 0 0 0 OA 腸内細菌と自閉症スペクトラム障害
- 著者
- 黒川 駿哉 岸本 泰士郎 真田 健史 三村 將
- 出版者
- 日本生物学的精神医学会
- 雑誌
- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.55-59, 2019 (Released:2019-12-28)
- 参考文献数
- 21
腸内細菌叢とその代謝産物が,腸を介して脳に作用し,相互に影響し合うという腸内フローラ‐腸‐脳軸(microbiota‐gut‐brain axis)が注目されている。自閉症スペクトラム障害(autism spectrum disorder:ASD)は精神神経科領域において,microbiota‐gut‐brain axisについての報告が最も多い疾患の一つである。健常と比べてASDでは特定の菌種・構成パターンの違いや多様性の乱れ(dysbiosis)が報告されている一方で,このdysbiosisを復する目的で,腸内細菌叢移植(fecal microbiota transplantation:FMT)などの新しい試みについての報告も出てきている。本稿では,最新の腸内細菌叢の観察研究および介入研究について紹介し,治療応用や病態理解の可能性など今後の展望について述べる。
12 0 0 0 OA 土岐頼康と斯波義将ー尾張・三河からみた室町幕府ー
- 著者
- 松島 周一
- 出版者
- 愛知教育大学歴史学会
- 雑誌
- 歴史研究 (ISSN:02879948)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, pp.1-22, 2019-03-31
31 0 0 0 OA 抵抗権と抵抗義務について 日本国憲法に於ける抵抗権と抵抗義務
- 著者
- 田畑 忍
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1959, pp.67-89, 1960-09-25 (Released:2009-02-12)
- 参考文献数
- 23
10 0 0 0 OA リハビリテーション専門職の信念対立に対するマインドフルネストレーニングの効果
- 著者
- 古桧山 建吾 京極 真 織田 靖史
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.180-189, 2020-04-15 (Released:2020-04-15)
- 参考文献数
- 23
本研究の目的は,信念対立を経験したリハビリテーション専門職がマインドフルネストレーニングを実践することでたどる主観的体験の変化と,リハビリテーション専門職の信念対立に対してマインドフルネストレーニングがどのような影響を与えるかを明らかにすることである.対象者は,8週間のマインドフルネストレーニングを実践した.質的研究で対象者の主観的体験の変化,量的研究でマインドフルネストレーニングの効果を検証した.結果,対象者の信念対立の心理的側面は改善するが,信念対立そのものは改善しなかった.以上から,信念対立の問題には,マインドフルネストレーニングと信念対立解明アプローチを併せて対応する必要があると考える.
16 0 0 0 OA 生痕化石 Piscichnus waitemate―ジェット水流を用いた摂食行動の痕跡―
- 著者
- 小竹 信宏 奈良 正和
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, no.1, pp.I-II, 2002 (Released:2010-11-26)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 7 10
Piscichnus waitemata Gregory, 1991は白亜紀以降の海成層, なかでも浅海相に広く産する生痕化石である. かつて, この生痕化石は荷重痕やポットホールといった堆積構造の一つと考えられてきた. 現在では, 一部のエイ類やセイウチ類などが, 堆積物中に生息する底生動物を摂食した際に形成された摂食痕である可能性が指摘されている (Howard et al.,1977; Gregory,1991), 形成者の特異な摂食様式を反映し, 生痕化石内部には母岩を構成する粒子が再堆積した際に形成された級化構造や平行葉理が見られる. このような内部構造の特徴と円筒形状の形態とが相まって, 物理的堆積構造と混同される一因となった. この生痕化石が化石密集層内に形成されると, 化石の再配列や濃集が局所的に起こり, 通常の堆積メカニズムでは理解できない複雑なファブリックが見られるようになる. P.waitemata のサイズと形成メカニズムを考慮すると, 生痕形成に伴って大量の堆積物が短時間に撹拌され再堆積することは間違いない. この事実は, 堆積物表層部で起こる生物撹拌作用を考える際に, 一部の魚類や海生ほ乳類の摂食行動が決して無視できないことを示唆している.
62 0 0 0 IR 現代民俗の形成と批判 : 「成人式」問題をめぐる一考察 (宇都榮子教授 退職記念号)
- 著者
- 室井 康成
- 出版者
- 専修大学人間科学学会
- 雑誌
- 専修人間科学論集. 社会学篇 (ISSN:21863156)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.65-105, 2018-03
2000年以降、いわゆる「荒れる成人式」問題が顕在化している。一般に成人式は、多くの日本人が加齢の過程で経験する重要な人生儀礼の一種として理解されているため、その荒廃ぶりは現代の若者の未熟さを示すものとして、しばしば睥睨の対象となっている。それは成人式が、近代まで日本各地において、15歳前後の若者に対して行なわれてきた成人儀礼「元服」の現代版として捉えられることも一因だと思うが、実は両者に連続性はない。これまで現行の成人式は、敗戦直後に埼玉県蕨市で行なわれたものが全国に普及したとする説が有力であったが、本稿の調査を通じて、それがすでに戦前の名古屋市で行なわれていたことが明らかとなり、その開催趣旨や運営方式から、そこに元服的要素はなく、あくまでイベントとして開催されていたことを確認した。翻って成人式定着以前の類例を、各地の民俗事象を手掛かりに見てゆくと、何歳を成人と見なすかという基準は、ほぼ集落単位で取り決められており、全国一律の基準などなく、またその認定時期も個人の成熟度に応じて、かなりの柔軟性を持っていたことが明らかになった。この場合の成熟度とは、男子は「親の仕事を手伝う能力」、女子の場合は「結婚可能性」であり、いずれも個人差を前提としていた。だが、そうした柔軟性を駆逐したのが、明治期の徴兵制に起源をもつ「成人=20歳」という新基準であったが、これも全国民の間で共有されたと政府が認めたのは、戦後10年を経た頃であった。逆説的だが、「成人=20歳」という認識も、戦後の官製成人式の普及によって国民の間に浸透したのである。しかし、現在では新成人の約半数は就学者であり、しかもその段階で既婚である者も少ないであろう。前代に比べて現代の若者が幼く見えたとしても、それは仕方のないことである。法の規定とは別に、成人と見なす基準は時代や個人の境遇によって変わるということは、近代の民俗史が語るところだが、そうした様々な差異を無化して、無作為に人を一堂に集めるから荒れるのであり、そこに官製成人式の限界がある。とはいえ、多くの人が経験し、しかも70年以上の歴史をもつ行事であれば、それは十分に民俗学の対象である。通常、民俗学はその対象を「保護・顕彰」すべきものとして捉えるが、本稿では、現行の成人式が民俗的根拠を欠いた意義なきものであることを論じ、その廃止を提言する。
50 0 0 0 OA 保革イデオロギーの影響力低下と年齢
- 著者
- 竹中 佳彦
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.5-18, 2014 (Released:2018-02-02)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 2
若年層の政党の保革イデオロギーへの位置づけは高齢層と異なるという知見を踏まえ,(ア)イデオロギーの自己位置づけ(イ)争点態度の一貫性,(ウ)支持政党・投票政党とイデオロギーとの相関の年齢による違いを,JIGS有権者調査(2013年),JESⅣ調査(2010年)とJES調査(1983年)を用いて比較分析した。その結果,①同一コーホートが保守化してはいないが,若年層は,保革イデオロギーを認識しておらず,認識していた場合には自己を革新的と位置づけ,②若年層にも,争点の態度空間に一貫した基底的構造はあるが,その力は弱く,また保革イデオロギー次元でない場合もあり,③40歳代以下に,支持政党・投票政党と保革イデオロギーとの相関がない場合があった。このようにイデオロギーの自己位置づけと争点態度と投票政党との間の一貫性の喪失が,若年層ほど進んでいることを示した。
10 0 0 0 OA 虹彩色の異なる2群間における色の見えの差異
- 著者
- 庄山 茂子 川口 順子 栃原 裕
- 出版者
- 日本生理人類学会
- 雑誌
- 日本生理人類学会誌 (ISSN:13423215)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.111-117, 2007-05-25 (Released:2017-07-28)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2
To clarify the differences in the perception of color between two groups with different iris colors, we measured color discrimination ability by the 100 hue test under an illuminance of 500 or 30 lx in Caucassian females with blue-green irises and Mongoloid females with brown irises, and obtained the following results. The total deviation score at 30 lx did not significantly differ between the Caucasian and Mongoloid groups, but that at 500 lx was lower in the Mongoloid group, suggesting that color discrimination was easier at 500 lx in the Mongoloid group. In the Caucasian group, hue discrimination was more difficult in the region from green (G) to purplish blue (PB) compared with the Mongoloid group under an illuminance of 500 lx, and the spectral luminous efficiency decreased in the blue (B) region in the light condition. In both groups, color discrimination in the red (R) region was law at 30 lx, showing significant differences between 30 lx and 500 lx. In the Mongolian group, the discrimination ability in the blue (B) region was significantly lower at 30 lx than at 500 lx. Since color perception differed between the two groups with different iris colors, universal designs giving attention to differences in iris color are necessary.
34 0 0 0 OA 文系観・理系観の形成プロセスの解明―国立大学の学生を対象としてー
- 著者
- 岡本 紗知
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 科学教育研究 (ISSN:03864553)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.14-29, 2020 (Released:2020-04-11)
- 参考文献数
- 24
The purpose of this research is to determine how stereotypical views of the sciences and humanities are formed among university students. Thirty undergraduate or graduated students were semi-structurally interviewed, and the collected data were analyzed by the modified grounded-theory approach (M-GTA). The analysis revealed that, prior to the formation of stereotypical views, students first recognized their aptitudes for one of two categories: sciences or humanities. Once they established their aptitudes, they started to recognize those who were in the opposite category. When they encountered “ideal figures” in such categories, they unconsciously extracted some features and regarded them as common features shared among those in such categories. These common characteristics were further interpreted based on their own views and beliefs, which essentially led to forming stereotypical views. This study suggests that the stereotypical views of the sciences and humanities are not universal; they are gradually formed in parallel with students’ constant struggle to navigate themselves during countless decisions for academic and career planning.
10 0 0 0 IR 雉尾攷 : 日本書紀にみる赤気に関する一考察
- 著者
- 片岡 龍峰 山本 和明 藤原 康徳 塩見 こずえ 國分 亙彦 Ryuho KATAOKA Kazuaki YAMAMOTO Yasunori FUJIWARA Kozue SHIOMI Nobuo KOKUBUN
- 出版者
- 総合研究大学院大学文化科学研究科 / 葉山町(神奈川県)
- 雑誌
- 総研大文化科学研究 = Sokendai review of cultural and social studies (ISSN:1883096X)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.17-29, 2020-03
日本最古の天文現象の記録は、『日本書紀』巻二十二、推古二十八年十二月一日(西暦六二〇年十二月三十日)の條に記される「十二月庚寅朔、天有赤気。長一丈餘。形似雉尾」という一節である。「赤気」は、彗星の類と理解され、日本古典文学や歴史学などの研究では悪い兆候を示すもの、といった理解がなされてきた。その一方、地球物理学においては、オーロラと理解され、オーロラの最も早い事例としてこの『日本書紀』が位置づけられてきた経緯がある。今回の考察では、「赤気」だけではなく、文中の「雉尾」という言葉にも着目し、『日本書紀』諸本での記述を踏まえたうえで、扇形をした赤いオーロラが日本などの中緯度で観察されやすく、真夜中より前に見られ、かつ雉の尾に似た形状をし、「長一丈」に該当する角距離十度相当で見えるという最も構造が際立った形態であるということを、雉の生態など、鳥類学の研究も踏まえて明らかにした。文献学的な考察に加え、雉の生態や尾羽の特徴を理解する鳥類学、彗星に関する古天文学の知識も合わせて新たな考察を加えたことによって、『日本書紀』の編纂に当たった人々の記述に対する責任感や知性、私たち日本人のルーツとなった倭の人々の観察眼や感性を伺い知るうえで一定の視点を与えることに寄与しうるものである。The oldest record of an astronomical phenomenon in Japan was recorded in the Nihon-shoki as follows: "On December 30 in 620, a red sign appeared in heaven. The length was more than 1 jo (10 degrees). The shape was similar to a pheasant tail (Suiko-Tennou, 28)". The appearance of a red sign has been recognized as an expression of a bad omen in literature, while it has been interpreted as the northern lights in geophysics. First we examine the description of the pheasant tail in detail. We then introduce the latest scientific findings that the northern lights show a fan-shaped appearance with a red background when appearing over Japan. After showing that the fan-shape is similar to a pheasant tail, also pointing out the low possibility of comets, we conclude that the oldest record of the red sign is consistent with the appearance of the northern lights over Japan. We hope that this examination contributes to increasing awareness of the sensitivity of Japanese people 1400-years-ago who compared a beautiful behavior of birds with a magnificent and rare natural phenomenon.
- 巻号頁・発行日
- 1946
23 0 0 0 OA 高用量ビタミンCの摂取は加齢に伴う胸腺の委縮を 抑制して免疫細胞数の維持に寄与する
- 著者
- 内尾 隆正 広瀬 義隆 室崎 伸二 山本 佳弘 石神 昭人
- 出版者
- 公益社団法人 日本ビタミン学会
- 雑誌
- ビタミン (ISSN:0006386X)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.5.6, pp.352-354, 2017 (Released:2018-06-30)
28 0 0 0 自然勾配ブースティングを用いたニュース見出しの信頼度付きクリック率予測
11 0 0 0 OA Update on use of chloroquine/hydroxychloroquine to treat coronavirus disease 2019 (COVID-19)
- 著者
- Jianjun Gao Shasha Hu
- 出版者
- International Research and Cooperation Association for Bio & Socio-Sciences Advancement
- 雑誌
- BioScience Trends (ISSN:18817815)
- 巻号頁・発行日
- pp.2020.03072, (Released:2020-04-13)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 39
Drugs that are specifically efficacious against SARS-CoV-2 have yet to be established. Chloroquine and hydroxychloroquine have garnered considerable attention for their potential to treat coronavirus disease 2019 (COVID-19). Increasing evidence obtained from completed clinical studies indicates the prospects for chloroquine/hydroxychloroquine to treat COVID-19. More randomized control clinical studies are warranted to determine the feasibility of these two drugs in treating COVID-19.
- 著者
- ⻆谷 詩織 Shiori SUMIYA
- 出版者
- 上越教育大学
- 雑誌
- 上越教育大学研究紀要 = Bulletin of Joetsu University of Education (ISSN:09153162)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.301-309, 2020-03-31
13 0 0 0 (OS招待講演)信用・信頼・信託
- 著者
- 大屋 雄裕
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 2020年度 人工知能学会全国大会(第34回)
- 巻号頁・発行日
- 2020-04-01
26 0 0 0 OA 平安貴族社会における医療と呪術 : 医療人類学的研究の成果を手掛りとして
- 著者
- 繁田 信一
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.77-98, 1995-06-10 (Released:2017-07-18)
本稿の目的は、医療および呪術の平安貴族社会における治療手段としてのあり方、および、平安貴族の治療の場面における医療と呪術との関係を把握することにある。この目的のため、平安貴族の漢文日記(古記録)を主要史料として用いるが、考察にあたっては近年の医療人類学的研究の成果をも利用し、次に示す諸点について明らかにする。(1)平安貴族社会において、医療および呪術は一定の専門知識にもとづく技術として認識されていたのであり、また、(2)平安貴族は医療と呪術とをそれぞれ別個の技術体系に属するものとして認識していた。したがって、(3)平安貴族社会における治療手段は、医療と呪術とによる二元的なものだったのであるが、(4)医療と呪術とは相互に排除し合う関係にあったわけではなく、そのいずれもが各々の資格において有効な治療手段として認識されていた。また、(5)呪術は医療の有効性および安全性を保障・保証するものと見做されてもいたのであり(6)総合的に見るならば、平安貴族社会における医療と呪術との関係は相互補完的なものであった。
22 0 0 0 OA 尺度研究の必須事項(<特集>「行動療法研究」における研究報告に関するガイドライン)
- 著者
- 土屋 政雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.107-116, 2015-05-31 (Released:2019-04-06)
- 被引用文献数
- 12
質問票による測定指標についての尺度研究は、医療や心理学の分野をはじめ、認知・行動療法の研究においても広く行われてきた。しかし類似概念尺度の乱立や、尺度は開発されたものの科学的に明らかにすべき尺度特性が十分に検討されていないなどの問題がある。こうした現状を変えるため健康における測定の分野を中心にCOSMIN(COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments)チェックリストがさまざまな領域の研究者らの合意に基づき作成された。本稿では、COSMINチェックリストの概要を紹介するとともに、これに準拠し尺度研究において失敗しない研究計画を立てるため、特に重要な四つの留意事項((1)例数設計、(2)再検査信頼性・測定誤差の評価、(3)仮説の設定、(4)反応性・解釈可能性の評価)の解説と、その具体的な記載事例を紹介することを目的とする。
73 0 0 0 OA アメリカにおける政党の特質と予備選挙制度
- 著者
- 間柴泰治
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.648, 2005-01
18 0 0 0 OA 近世板本において併用された楷書体漢字と平仮名
- 著者
- 久田 行雄
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.101-86, 2019-08-01 (Released:2020-02-01)
現在、日本語の表記で使用される楷書体漢字平仮名交じり文という書記体は、近代以前においては一般的ではなく、活版印刷の導入を機に使用されるようになったと指摘されてきた。しかし、本稿の調査により、一八世紀初期に出版された医書に楷書体漢字平仮名交じり文の使用例が確認されること、この書記体は一八世紀中期には仏書へと広がり、一八世紀後期以降にさらに使用範囲が広がっていくことを明らかにした。楷書体漢字と平仮名が併用されるようになったのは、楷書体漢字との併用を許容する程に平仮名の役割が徐々に変化してきたからであろうと指摘した。このような表記意識の変化が、一八世紀を通して社会に広がっていったことを明らかにした。