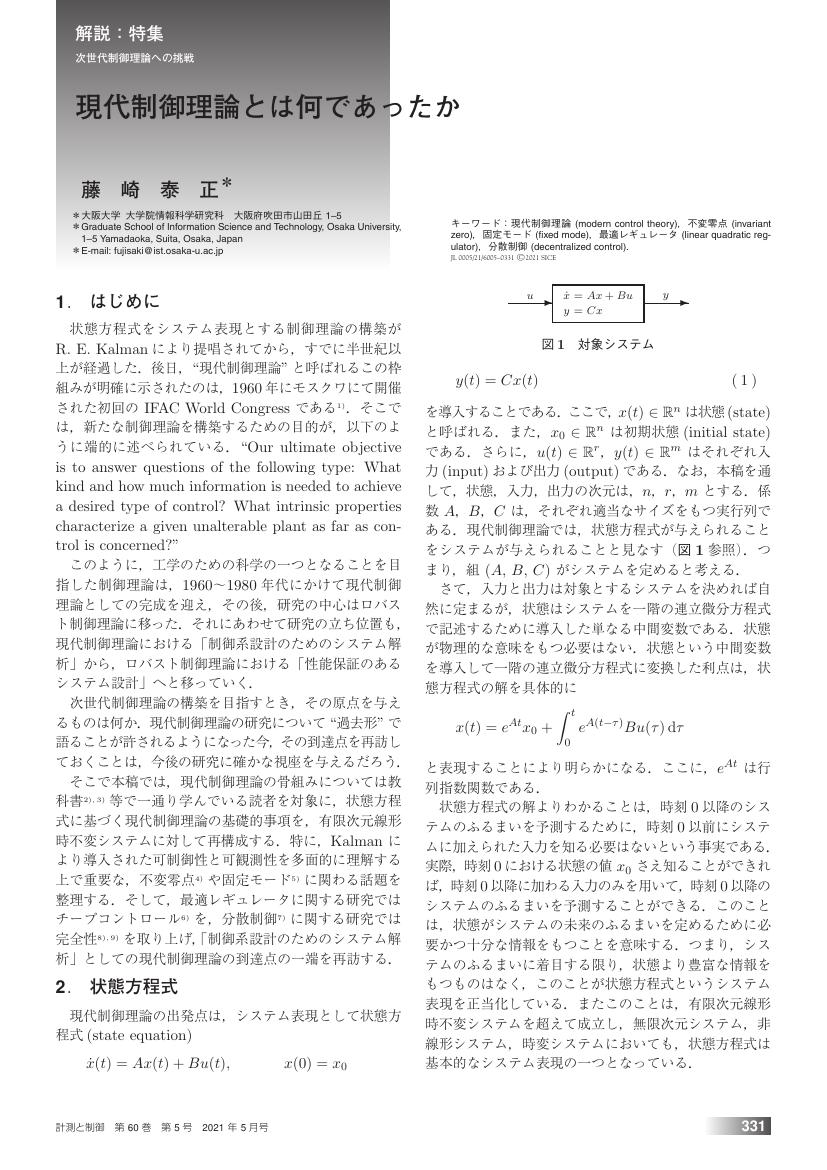9 0 0 0 OA ムネアカハラビロカマキリの非意図的導入事例―中国から輸入された竹箒に付着した卵鞘―
- 著者
- 櫻井 博 苅部 治紀 加賀 玲子
- 出版者
- 神奈川県立生命の星・地球博物館(旧神奈川県立博物館)
- 雑誌
- 神奈川県立博物館研究報告(自然科学) (ISSN:04531906)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, no.47, pp.67-71, 2018-02-28 (Released:2021-04-30)
近年国内に定着した侵略的外来種ムネアカハラビロカマキリHierodula sp. の導入経路は、これまで明らかにされていなかったが、筆者らは、今回本種のものと考えられる卵鞘を、市販の竹箒から確認し、それが正常に孵化すること、その形態・色彩が既知の本種幼虫のものと合致することを明らかにした。竹帚が導入経路の主要なものであれば、本種が通常の外来種の拡散パターンと異なり、同時多発的に各所で確認されたことの合理的な説明ができる。
9 0 0 0 OA 医薬分業と二つの政策目標—医薬分業の進展の要因—
- 著者
- 赤木 佳寿子
- 出版者
- 日本社会薬学会
- 雑誌
- 社会薬学 (ISSN:09110585)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.33-42, 2013-12-10 (Released:2015-06-26)
- 参考文献数
- 52
In this paper, I propose to look at the separation of prescription and dispensing in Japan(Iyakubungyo)from the point of view of social science and aim to clarify factors of promotion of Iyakubungyo. Today, the separation rate reached over 60%, and it shows Iyakubungyo comes into a common system. However the system has not been judged socially, because there is no paper about the social evaluation of Iyakubungyo while there are some papers about the factors of the satisfaction of patients. There are some investigations of how to promote Iyakubungyo, but no investigations of why. I will figure out factors of promotion of the separation of prescription and dispensing in Japan by verifying two policies, “the divorce between things and technique” and “proper use of pharmaceutical products”. A change of these policies makes the change of contents and rates of Iyakubungyo. By showing the possibility that the two policies were the factors of the development of Iyakubungyo, we can get a hint for finding the pharmacists’ function in social.
9 0 0 0 OA 地球大気の概算量(教育実践)
- 著者
- 竹内 智
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 大学の物理教育 (ISSN:1340993X)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.136-139, 2009-11-15 (Released:2018-12-09)
- 参考文献数
- 3
9 0 0 0 OA 調理用ガス器具から発生する有害物質の発生量
- 著者
- 小嶋 純
- 出版者
- 公益社団法人 日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.59-61, 2013-03-25 (Released:2013-04-27)
- 参考文献数
- 8
- 著者
- 藤井 宣彰
- 出版者
- 中国四国教育学会
- 雑誌
- 教育学研究ジャーナル (ISSN:13495836)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.1-10, 2011-03-22 (Released:2017-04-05)
- 参考文献数
- 34
The purpose of this research is to examine the effect of class size and small group learning on pupils' academic achievement by using Multilevel Models. Since 1950s to early 1990s, class sizes were reduced to 40 pupil classes. After the 1990s, instead of continuing to reduce class sizes, the Ministry of Education has adopted learning group systems to reduce the pupil-teacher ratio, for example, small group learning and Team-Teaching (TT). Do the class size and these new learning group systems have positive effect on the pupils' academic achievement? This is the theme of this research. Thirty-four elementary school principals and 843 pupils responded to the questionnaires and pupils took brief academic achievement tests for Japanese and Mathematics. This research focuses on the analysis on the effect of adopting teaching methods like small group learning on mathematic tests. The results like many former research findings suggest that small class size and small group learning have positive effect on pupils' academic achievement. To work small group learning effectively, it is necessary to arrange full-time teachers and to group pupils by the similar ability.
- 著者
- 深井 喜代子 大名門 裕子
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護研究学会
- 雑誌
- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.3_39-3_46, 1992-07-01 (Released:2016-03-31)
- 参考文献数
- 26
88名の健康な学生(男27名,女61名,18-37才)を被験者として,注射針刺入部としてよく選択されている三角筋,前肘,手背各部の皮膚痛覚閾値を,タングステン製(直径140μm)の刺激毛を用いて痛点分布密度を測定する方法で調べた。その結果,三つの皮膚領域とも,痛点分布密度(prick painとdull painの総数)は男性より女性の方が有意に大きかった(平均痛点数:男,7.6-11.0/4mm2,女,10.2-12.2/4mm2)。部位別では,手背部(男,7.6±4.7/4mm2,女,10.2±4.2/4mm2),三角筋部(男,9.1±5.0/4mm2,女,10.7±4.4/4mm2),前肘部(男,11.0±4.1/4mm2,女,12.1±3.3/4mm2)の順で痛点分布密度が小さかった。この傾向は注射針刺入時の鋭い痛みに相当するprick painのみの分布に着目しても同様であった。このような痛覚閾値の部位差,性差について考察した。本実験の結果から,看護者は,健康な青年層では,女性は男性より痛覚閾値が低いこと,そして手背部の閾値は比較的高いことを考察して注射や採血を行うべきであると結論した。
9 0 0 0 OA カウフマン博士夫妻と私〜賢いアセスメントからの学び
- 著者
- 石隈 利紀
- 出版者
- 日本K-ABCアセスメント学会
- 雑誌
- K-ABCアセスメント研究 (ISSN:21861609)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.1-15, 2021 (Released:2023-10-05)
9 0 0 0 OA メタバースの教科書 ─原理・基礎技術から産業応用まで─
- 著者
- 雨宮 智浩
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会
- 雑誌
- 日本バーチャルリアリティ学会誌 (ISSN:13426680)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.36-37, 2023-09-30 (Released:2023-10-18)
9 0 0 0 OA 親密な関係破綻後のストーカー的行為のリスク要因に関する尺度作成とその予測力
- 著者
- 金政 祐司 荒井 崇史 島田 貴仁 石田 仁 山本 功
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.89.17207, (Released:2018-05-25)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 3
This study aimed to reveal the risk factors for a person to perpetrate stalking-like behaviors following the end of a romantic relationship based on personality traits (attachment anxiety and narcissism), the characteristics of a romantic relationship before a breakup, and the emotions and thoughts of a person after a breakup. To develop two scales measuring the characteristics of a romantic relationship before a breakup and the emotions and thoughts of a person after a breakup, a web-based survey of 189 females and 165 males was conducted in Study 1. In Study 2, a national survey was conducted using two-stage stratified sampling; 106 females and 110 males who experienced the end of a romantic relationship during the past five years and did not initiate their most recent breakup were analyzed. The results of a multiple-group analysis revealed that both attachment anxiety and feelings that a partner was his/her “one and only” increased egoistic preoccupations after a breakup, and the egoistic preoccupations predicted the perpetration of stalking-like behaviors in both males and females.
9 0 0 0 OA トラブルとして記録される会話 : 新潮合評会に見る座談会の批評性
- 著者
- 酒井 浩介
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.12, pp.47-58, 2009-12-10 (Released:2017-08-01)
一九二〇年代の新潮合評会の佐藤春夫と久米正雄の会話の記録の不備を手掛りとして座談会と速記の関係に着目し、帝国議会議事速記録(一八九〇)から小林秀雄までを射程に座談会の批評的な意義を考察する。座談会とは会話を活字として現前させようという欲望によって生み出された言説のトラブルなのであり、それは書き言葉の無意識として現れ、言文一致という形で整除された近代文学にひびを入れることで批評性を獲得するのである。
9 0 0 0 OA 居合道の系譜と普及に関する一考察
- 著者
- 中井 憲治
- 出版者
- 仙台大学
- 雑誌
- 仙台大学紀要 = Bulletin of Sendai University (ISSN:03893073)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.53-71, 2020-09-30
- 著者
- Mei Yamagata Asako Miura
- 出版者
- The Japanese Group Dynamics Association
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- pp.si5-2, (Released:2022-11-09)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 2
Humans tend to distort past events, leading to a gap between experience and retrospective experience—the retrospective bias. This study clarified the characteristics of retrospective bias in the ongoing COVID-19 pandemic. Longitudinal data from 597 Japanese individuals were gathered during the COVID-19 pandemic from January 2020 to January 2021. Analysis revealed that cognition regarding COVID-19 one year ago was retrospectively underestimated. In addition, within-person variation among the responses of the 11 waves consistently showed a negative association with bias. These findings suggest that retrospective methods of describing long-lasting and fluctuating events will lead to inaccurate conclusions.
9 0 0 0 OA 初等トポス理論の射程 : 集合・圏・論理
9 0 0 0 OA <ポストp値時代>の統計学
統計的方法を学ぶことは,これまで,すなわち有意性検定を学ぶことでした。長期に渡りこの大前提はゆるぎなく盤石で,無条件に当たり前で,無意識的ですらありました。しかし,ときは移り,有意性検定やp値の時代的使命は終わりました。アメリカ統計学会ASAは,2016年3月7日に,p値の誤解や誤用に対処する6つの原則に関する声明をだしました (Wasserstein & Lazar, 2016)。この声明は「『ポストp < 0.05 時代』へ向けて研究方法の舵を切らせることを意図している」(R. Wasserstein (ASA News Releases, 2016)) ものだと言明されています。2016年現在,統計学における著名な学術雑誌バイオメトリカ (Biometrika) の過半数の論文が,ベイズ統計学を利用しています。多くの著名な学術雑誌も同様の傾向です。スパムメールをゴミ箱に捨て,日々,私たちの勉強・仕事を助けてくれるのは,ベイズ統計学を利用したメールフィルタです。ベイズ的画像処理によってデジタルリマスターされ,劇的に美しくよみがえった名作映画を私たちは日常的に楽しんでいます。ベイズ理論が様々な分野で爆発的に活用されています。ベイズ的アプローチなしには,もう統計学は語れません。 有意性検定にはどこに問題があったのでしょう。3点あげます。 Ⅰ.p値とは「帰無仮説が正しいと仮定したときに,手元のデータから計算した検定統計量が,今以上に甚だしい値をとる確率」です。この確率が小さい場合に「帰無仮説が正しくかつ確率的に起きにくいことが起きたと考えるのではなく,帰無仮説は間違っていた」と判定します。これが帰無仮説の棄却です。しかし帰無仮説は,偽であることが初めから明白です。それを無理に真と仮定することによって,検定の論理は複雑で抽象的になります。例えば2群の平均値の差の検定における帰無仮説は「2群の母平均が等しい (μ1=μ2)」というものです。しかし異なる2つの群の母平均が,小数点以下を正確に評価して,それでもなお等しいということは科学的にありえません。帰無仮説は偽であることが出発点から明らかであり,これから検討しようとすることが既に明らかであるような論理構成は自然な思考にはなじみません。p値は土台ありえないことを前提として導いた確率なので,確率なのに抽象的で実感が持てません。このことがp値の一番の弊害です。以上の諸事情を引きずり,「有意にならないからといって,差がないとは積極的にいえない」とか「有意になっても,nが大きい場合には意味のある差とは限らない」とか,いろいろな言い訳をしながら有意性検定をこれまで使用してきたのです。しかし,これらの問題点はベイズ的アプローチによって完全に解消されます。ベイズ的アプローチでは研究仮説が正しい確率を直接計算するからです。 Ⅱ.nを増加させるとp値は平均的にいくらでも0に近づきます。これはたいへん奇妙な性質です。nの増加にともなって,いずれは「棄却」という結果になることが,データを取る前に分かっているからです。有意性検定とは「帰無仮説が偽であるという結論の下で,棄却だったらnが大きかった,採択だったらnが小さかったということを判定する方法」と言い換えることすらできます。ナンセンスなのです。これでは何のために分析しているのか分かりません。nを増加させると,p値は平均的にいくらでも0に近づくのですから,BIGデータに対しては,あらゆる意味で有意性検定は無力です。どのデータを分析しても「高度に有意」という無情報な判定を返すのみです。そこで有意性検定ではnの制限をします。これを検定力分析の事前の分析といいます。事前の分析では有意になる確率と学術的な対象の性質から逆算してnを決めます。しかし検定力分析によるサンプルサイズnの制限・設計は纏足 と同じです。統計手法は,本来,データを分析するための手段ですから,たくさんのデータを歓迎すべきです。有意性検定の制度を守るために,それに合わせてnを制限・設計することは本末転倒です。ベイズ推論ではnが大きすぎるなどという事態は決して生じません。 Ⅲ.伝統的な統計学における平均値の差・分散の比・クロス表の適合などの初等的な統計量の標本分布を導くためには,理系学部の2年生程度の解析学の知識が必要になります。すこし複雑な統計量の標本分布を導くためには,統計学のために発達させた分布論という特別な数学が必要になります。それでも,どの統計量の標本分布でも求められるという訳ではなく,導出はとても複雑です。検定統計量の標本分布を導けないと,(教わる側にとっては)統計学が暗記科目になってしまいます。この検定統計量の確率分布は何々で,あちらの検定統計量の確率分布は何々で,のように,まるで歴史の年号のように,いろいろと覚えておかないと使えません。暗記科目なので,自分で工夫するという姿勢が育つはずもなく,紋切り型の形式的な使用に堕す傾向が生じます。でもベイズ統計学は違います。マルコフ連鎖モンテカルロ (MCMC) 法の本質は,数学Ⅱまでの微積分の知識で完全に理解することが可能です。標本分布の理論が必要とする数学と比較すると,それは極めて初等的です。生成量を定義すれば,直ちに事後分布が求まり,統計的推測が可能になります。文科系の心理学者にとっても,統計学は暗記科目ではなくなります。 学問の進歩を木の成長にたとえるならば,平行に成長した幾つかの枝は1本を残して冷酷に枯れ落ちる運命にあります。枯れ果て地面に落ちた定理・理論・知識は肥やしとなり,時代的使命を終えます。選ばれた1本の枝が幹になり,その学問は再構築されます。教授法が研究され,若い世代は労せず易々と古い世代を超えていく。そうでなくてはいけません。 統計学におけるベイズ的アプローチは,当初,高度なモデリング領域において急成長しました。有意性検定では,まったく太刀打ちできない領域だったからです。議論の余地なくベイズ的アプローチは勢力を拡大し,今やその地位はゆるぎない太い枝となりました。 しかし統計学の初歩の領域では少々事情が異なっています。有意性検定による手続き化が完成しており,いろいろと問題はあるけれども,ツールとして使えないわけではありません。なにより,現在,社会で活躍している人材は,教える側も含めて例外なく有意性検定と頻度論で統計教育を受けています。この世代のスイッチングコストは無視できないほどに大きいのです。このままでは有意性検定と頻度論から入門し,ベイズモデリングを中級から学ぶというねじれた統計教育が標準となりかねません。それでは若い世代が無駄な学習努力を強いられることとなります。教科教育学とか教授学習法と呼ばれるメタ学問の使命は,不必要な枝が自然に枯れ落ちるのを待つのではなく,枝ぶりを整え,適切な枝打ちをすることにあります。ではどうしたらいいのでしょう。どのみち枝打ちをするのなら,R.A.フィッシャー卿の手による偉大な「研究者のための統計的方法」にまで戻るべきです。「研究者のための統計的方法」の範囲とは,「データの記述」「正規分布の推測」「独立した2群の差の推測」「対応ある2群の差の推測」「実験計画法」「比率・クロス表の推測」です。これが統計学の入門的教材の初等的定番です。文 献Wasserstein, R. L. & Lazar, N. A. (2016). The ASA's statement on p-values: context, process, and purpose, The American Statistician, DOI:10.1080/00031305.2016.1154108ASA News Releases (2016). American Statistical Association releases statement on statistical significance and p-Values. (http://www.amstat.org/newsroom/pressreleases/P-ValueStatement.pdf)R.A.フィッシャー(著) 遠藤健児・鍋谷清治(訳) (1970). 研究者のための統計的方法 森北出版 (Fisher, R. A. (1925). Statistical Methods for Research Workers, Oliver and Boyd: Edinburgh.)1 纏足(てんそく)とは,幼児期から足に布を巻き,足が大きくならないようにして小さい靴を履けるようにした,かつて女性に対して行われていた非人道的風習です。靴は,本来,足を保護するための手段ですから,大きくなった足のサイズに靴を合わせるべきです。靴に合わせて足のサイズを制限・整形することは本末転倒であり,愚かな行為です。他の靴を履けばよいのです。
9 0 0 0 OA NHK「きょうの料理」における煮物調理の変遷調査
- 著者
- 須谷 和子 志垣 瞳 池内 ますみ 澤田 崇子 長尾 綾子 升井 洋至 三浦 さつき 水野 千恵 山下 英代 山本 由美
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.6, pp.416-426, 2015 (Released:2016-01-04)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
NHK「きょうの料理」に掲載された中から煮物レシピを抽出し,煮物に関する変遷を明らかにした。1960年度から15年間隔で収集した42冊を資料とした。料理総数3,373件のうち煮物は535件(15.9%)を占め,特に1975年度は和風煮物が74.8%であった。煮物で使われる主材料は野菜類がもっとも多く,だいこんはどの年代においても使用頻度が高かった。肉類では,牛肉・豚肉・鶏肉がよく使われ,年代で順位は変化した。 煮物のレシピは,食生活の変化とそれに伴った健康志向・簡便化志向を意識したものになっていた。
9 0 0 0 OA 現代制御理論とは何であったか
- 著者
- 藤崎 泰正
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.5, pp.331-338, 2021-05-10 (Released:2021-05-21)
- 参考文献数
- 17
9 0 0 0 OA 過去40万年間の関東平野の地形発達史 ―地殻変動と氷河性海水準変動の関わりを中心に―
- 著者
- 須貝 俊彦 松島(大上) 紘子 水野 清秀
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.6, pp.921-948, 2013-12-25 (Released:2014-01-16)
- 参考文献数
- 109
- 被引用文献数
- 18 19
The Kanto Plain, the hinterland of the Tokyo metropolitan area, is the largest plain in Japan and is characterized by marked marine and fluvial terrace levels that developed during Marine oxygen Isotope Stage (MIS) 5. Late Quaternary topographical changes to the plain have been controlled by concurrent tectonic activity and glacio-eustatic sea-level changes. The shoreline at the maximum transgression of MIS 11, 9, 7, 5 and 1 is reconstructed based on the distribution of marine sediments revealed by many geologic columnar sections and marine terrace surfaces. A comparison of the magnitudes of the last five full-interglacial transgressions above shows that magnitude decreased over the long term. This is due probably to changes in the tectonic regime in the Kanto basin, from subsidence to uplift along with the northward migration of the depositional center, probably associated with changes in the motion of the Philippine Sea Plate and the collision with the Izu peninsula. The marine transgression has also been controlled by fluvial processes, especially in the north-western part of the plain because of high sediment inputs from the Tone, Ara, and Watarase rivers. Aggradation coupled with regional uplift since MIS 5.4 limited the MIS 1 marine transgression within the incised valley formed during MIS 2. As a result, the Paleo Tokyo bay, which was connected directly with the Pacific Ocean, disappeared. Instead, a large shallow submarine area of about 10,000km2 emerged. The northern part of the present Tokyo bay is still subsiding and large volumes of water and sediments have been concentrated in the bay area during the Holocene. Such natural environmental conditions enable supplies of natural resources, such as fresh water, fertile soil, and flat land for the development of greater Tokyo.
- 著者
- Keiko Nakashima
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- National Diet Library newsletter (ISSN:13447238)
- 巻号頁・発行日
- no.200, 2015-06
9 0 0 0 OA 上代日本語の流音と動詞語幹末母音交替
- 著者
- 早田 輝洋
- 出版者
- The Linguistic Society of Japan
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, no.118, pp.5-27, 2000-12-25 (Released:2007-10-23)
- 参考文献数
- 13
上代日本語の二段活用動詞は終止・・連体・・已然・で語幹末母音が/u/と交替する.この交替は文献時代では既に文法化していた.しかし,文法化する以前の音韻的条件は何だったのであろうか.語幹末母音が/u/と交替するのは,乙類音節で終る語幹末母音の次に終止語尾/-u/,連体語尾|-ru|,已然語尾/-re/の来る時であるが,終止語尾/-u/の場合は母音の融合かも知れぬゆえ考察から外すと/-ru//-re/の前,即ち/-r/の前ということになる.しかし,受身接辞/-rare//-raje/の前では交替は起きない.日本語の歴史を通じて,その/r/の音はr的な音であること,その音が当面の母音交替に関係ないことを論じ,ついで奈良時代の東西方言の対応や服部仮説から連体接辞の祖・*rua,巳然接辞の祖・*rua-giを再構すると,当該の母音交替は後続音節*ruaの母音*uによる逆行同化を思わせるものとなることを示す.過去接辞/-isi//-isi-ka/の・態素構成にも示唆する所がある。