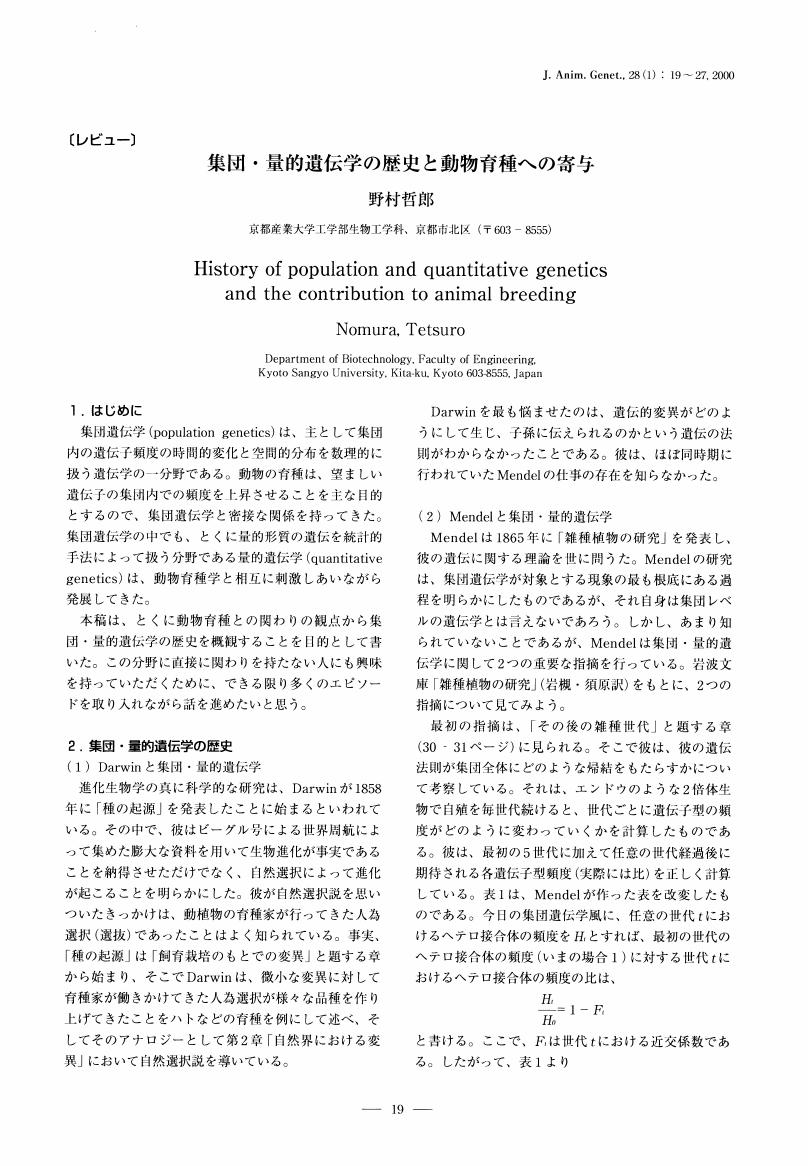- 著者
- Genya Kobayashi Shonosuke Sugasawa Hiromasa Tamae Takayuki Ozu
- 出版者
- International Research and Cooperation Association for Bio & Socio-Sciences Advancement
- 雑誌
- BioScience Trends (ISSN:18817815)
- 巻号頁・発行日
- pp.2020.03133, (Released:2020-05-28)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 30
Japan has observed a surge in the number of confirmed cases of the coronavirus disease (COVID-19) that has caused a serious impact on the society especially after the declaration of the state of emergency on April 7, 2020. This study analyzes the real time data from March 1 to April 22, 2020 by adopting a sophisticated statistical modeling based on the state space model combined with the well-known susceptible-infected-recovered (SIR) model. The model estimation and forecasting are conducted using the Bayesian methodology. The present study provides the parameter estimates of the unknown parameters that critically determine the epidemic process derived from the SIR model and prediction of the future transition of the infectious proportion including the size and timing of the epidemic peak with the prediction intervals that naturally accounts for the uncertainty. Even though the epidemic appears to be settling down during this intervention period, the prediction results under various scenarios using the data up to May 18 reveal that the temporary reduction in the infection rate would still result in a delayed the epidemic peak unless the long-term reproduction number is controlled.
3 0 0 0 OA 集団・量的遺伝学の歴史と動物育種への寄与
- 著者
- 野村 哲郎
- 出版者
- Japanese Society of Animal Breeding and Genetics
- 雑誌
- 動物遺伝育種研究 (ISSN:13459961)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.19-27, 2000-11-15 (Released:2010-03-18)
- 参考文献数
- 42
3 0 0 0 OA 初期地球における隕石衝突によるアミノ酸および核酸塩基の生成に関する研究
- 著者
- 古川 善博
- 出版者
- 一般社団法人日本地球化学会
- 雑誌
- 地球化学 (ISSN:03864073)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.1-9, 2016-03-25 (Released:2016-03-25)
- 参考文献数
- 60
- 被引用文献数
- 1
Emergence of life's building blocks on the prebiotic Earth should be the fundamental step to the origins of life. Geological evidences suggest that such organic compounds accumulated at some point in the time between 4.4 to 3.8 billion years ago. During this period, the flux of extraterrestrial objects was significantly higher than the subsequent periods. Such extraterrestrial objects might have provided substantial amounts of metallic iron to the surface of the Earth. Shock-recovery experiments simulating the impact-induced reactions of such iron-bearing objects suggest that hypervelocity oceanic impacts of meteorites form nucleobases and various amino acids as well as amines and carboxylic acids. High annual mass flux of such large objects suggests that the impact-induced formation was not negligible as a source of organic compounds on the early Earth. Further investigations on the impact-induced reactions and the nature of extraterrestrial objects would elucidate the fundamental step to the origin of life.
3 0 0 0 OA 道路交通信号
- 著者
- 河合 悟
- 出版者
- 一般社団法人 照明学会
- 雑誌
- 照明学会誌 (ISSN:00192341)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.3, pp.204-209, 1987-03-01 (Released:2011-07-19)
- 参考文献数
- 8
3 0 0 0 OA 肩甲下筋の効果的なストレッチング方法の検討
- 著者
- 清水 厳郎 長谷川 聡 本村 芳樹 梅原 潤 中村 雅俊 草野 拳 市橋 則明
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.2 (第51回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0363, 2016 (Released:2016-04-28)
【はじめに,目的】肩関節の運動において回旋筋腱板の担う役割は重要である。回旋筋腱板の中でも肩の拘縮や変形性肩関節症の症例においては,肩甲下筋の柔軟性が問題となると報告されている。肩甲下筋のストレッチ方法については下垂位での外旋や最大挙上位での外旋などが推奨されているが,これは運動学や解剖学的な知見を基にしたものである。Murakiらは唯一,肩甲下筋のストレッチについての定量的な検証を行い,肩甲下筋の下部線維は肩甲骨面挙上,屈曲,外転,水平外転位からの外旋によって有意に伸張されたと報告している。しかしこれは新鮮遺体を用いた研究であり,生体を用いて定量的に検証した報告はない。そこで本研究では,せん断波エラストグラフィー機能を用いて生体における効果的な肩甲下筋のストレッチ方法を明らかにすることを目的とした。【方法】対象は健常成人男性20名(平均年齢25.2±4.3歳)とし,対象筋は非利き手側の肩甲下筋とした。肩甲下筋の伸張の程度を示す弾性率の計測は超音波診断装置(SuperSonic Imagine社製)のせん断波エラストグラフィー機能を用い,肩甲下筋の停止部に設定した関心領域にて求めた。測定誤差を最小化できるように,測定箇所を小結節部に統一し,3回の計測の平均値を算出した(ICC[1,3]:0.97~0.99)。弾性率は伸張の程度を示す指標で,弾性率の変化は高値を示すほど筋が伸張されていることを意味する測定肢位は下垂位(rest),下垂位外旋位(1st-ER),伸展位(Ext),水平外転位(Hab),90°外転位からの外旋位(2nd-ER)の5肢位における最終域とした。さらに,ExtとHabに対しては肩甲骨固定と外旋の有無の影響を調べるために肩甲骨固定(固定)・固定最終域での固定解除(解除)と外旋の条件を追加した。統計学的検定は,restに対する1st-ER,Ext,Hab,2nd-ERにBonferroni法で補正したt検定を行い,有意差が出た肢位に対してBonferroniの多重比較検定を行った。さらに伸展,水平外転に対して最終域,固定,解除の3条件にBonferroniの多重比較検定を,外旋の有無にt検定を行い,有意水準は5%とした。【結果】5肢位それぞれの弾性率(平均±標準偏差,単位:kPa)はrestが64.7±9.1,1st-ERが84.9±21.4,Extが87.6±26.6,Habが95.0±35.6,2nd-ERが87.5±24.3であった。restに対し他の4肢位で弾性率が有意に高値を示し,多重比較の結果,それらの肢位間には有意な差は認めなかった。また,伸展,水平外転ともに固定は解除と比較して有意に高値を示したが,最終域と固定では有意な差を認めなかった。さらに,伸展・水平外転ともに外旋の有無で差を認めなかった。【結論】肩甲下筋のストレッチ方法としてこれまで報告されていた水平外転からの外旋や下垂位での外旋に加えて伸展や水平外転が効果的であり,さらに伸展と水平外転位においては肩甲骨を固定することでより小さい関節運動でストレッチ可能であることが示された。
3 0 0 0 OA 飛騨山脈の隆起と火成活動の時空的関連
- 著者
- 及川 輝樹
- 出版者
- Japan Association for Quaternary Research
- 雑誌
- 第四紀研究 (ISSN:04182642)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.141-156, 2003-06-01 (Released:2009-08-21)
- 参考文献数
- 108
- 被引用文献数
- 13 21
飛騨山脈の火成活動の消長と,山脈の隆起により生産された礫層の形成時期には,よい同時性が認められる.それは,2.5~1.5Ma(Stage I)と0.8~0Ma(Stage III)における火山活動の増大と周辺堆積盆への礫層の供給の時期であり,その間の1.5~0.8Ma(Stage II)には火山活動が低調で,周辺堆積盆における礫層の堆積が停止している.このことから,飛騨山脈は,激しい火成活動を伴いながら,3Ma以降に2度大きく隆起しているといえる.既知の広域テクトニクスの解析結果と隆起モデルから,各時期の隆起メカニズムを考察する.Stage Iでは伸張から中間応力場下での地殻へのマグマの濃集と地殻の厚化によるアイソスタティックな隆起が考えられる.一方,Stage IIIでは,この地域が圧縮場に変化し,マグマの熱によって弾性的厚さが薄くなった地殻が座屈変形し隆起したモデルが考えられる.このように飛騨山脈は,大規模なマグマの貫入・定置・熱の影響と,伸張から圧縮場への広域テクトニクスの変化とが合わさって形成された山脈といえる.
3 0 0 0 OA サルを用いたメタ記憶の神経生理学的研究に向けて
- 著者
- 田中 暁生 船橋 新太郎
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.91-105, 2007-12-20 (Released:2009-03-13)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 1
Metamemory refers to the knowledge about one's own memory capabilities and mnemonic strategies that support efficient learning and memory, and/or to the awareness and recognition about on-going mnemonic processes as well as what is stored in memory. Psychological studies established experimental methods to investigate the accuracy of human metamnemonic judgments and demonstrated that humans were capable of monitoring their own memory accurately. Recently, a number of neuropsychological as well as neuroimaging studies have indicated that the prefrontal cortex plays a crucial role in metamemory. Meanwhile there have been growing interests in exploring metacognitive abilities in animals. These lines of studies have developed new experimental paradigms suitable for systematically investigating the capability of animals' metamemory. In this article, we first briefly review previous studies on metamemory in humans and animals. Based on the findings from these studies, we then discuss strategies for examining neuronal substrates of metamemory in monkeys through neurophysiological approaches.
3 0 0 0 OA リピッドバブルと超音波によるセラノスティクスと遺伝子・核酸デリバリー
- 著者
- 髙橋 葉子 丸山 一雄 根岸 洋一
- 出版者
- 日本DDS学会
- 雑誌
- Drug Delivery System (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.116-123, 2019-03-25 (Released:2019-06-25)
- 参考文献数
- 27
遺伝子・核酸医薬が臨床応用されるうえで、標的組織および標的細胞へのデリバリー技術の開発は重要課題である。近年、物理エネルギーのなかでも超音波を利用したデリバリーシステムはその安全性の高さから注目されており、ナノバブルやマイクロバブルを併用することで、造影効果のみならず薬物・遺伝子・核酸デリバリー効果の増強の可能性が示されている。筆者らは、超音波造影ガスを封入したリピッドバブルを開発し、種々の疾患モデルマウスを用いて遺伝子・核酸デリバリーツールとしての有用性を評価してきた。本稿では、超音波による診断と治療を融合したシステム(セラノスティクス)構築に向けた現状について概説するとともに、筆者らが開発したリピッドバブルによる遺伝子・核酸デリバリー効果とその治療への応用を紹介する。
3 0 0 0 OA 竹林は植物の多様性が低いのか?
- 著者
- 鈴木 重雄
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 森林科学 (ISSN:09171908)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, pp.11-14, 2010-02-01 (Released:2017-07-07)
- 被引用文献数
- 4
3 0 0 0 OA Twitter 投稿データにみられる地域方言の分析
- 著者
- 峪口 有香子 桐村 喬
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2014年 人文地理学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.112-113, 2014 (Released:2020-06-13)
3 0 0 0 OA 蘚苔類に発生した白絹病(新称)
- 著者
- 森田 昭
- 出版者
- 九州病害虫研究会
- 雑誌
- 九州病害虫研究会報 (ISSN:03856410)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.25-30, 2013-11-29 (Released:2015-10-14)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1 1
2008年~2010年に長崎県大村市の山野,並びに庭園に生えているコスギゴケ,ハイゴケ,ツルチョウチンゴケ,フデゴケ,ヒメシノブゴケ,エゾスナゴケ,ホソバオキナゴケ,コムチゴケ,ジャゴケ,および島根県出雲市の庭園に植栽してあるセイタカスギゴケの10種の蘚苔類が坪枯れ状となって褐変枯死し,その上にナタネ種子大の褐色球形菌核を認めた。それらの褐変した部分からは白絹病菌様の糸状菌が分離され,その分離菌は馬鈴薯煎汁寒天培地上での生育適温,菌叢の色や形状,主軸菌糸幅,かすがい連結の有無などに関してギンゴケから分離された白絹病菌と一致した。これら蘚苔類からの分離菌は,すべて各宿主蘚苔類に対してギンゴケ白絹病菌と同様に病原性を示し,病徴の再現を認め,再分離も可能であった。以上の結果から,坪枯れ症状を呈した10種の蘚苔類から分離された糸状菌は白絹病菌(Sclerotium rolfsii Saccardo)と同定し,各宿主蘚苔類の白絹病(Southern blight)と呼称することを提唱する。
3 0 0 0 OA 「過去の職業」による老後の所得格差
- 著者
- 木村 好美
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.151-165, 2002-10-31 (Released:2009-02-10)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 1
本稿は、過去の主な職業による老後の所得格差について検討を行った。60歳以上の「過去に就業経験があり、現在無職」である男性サンプルについて、「過去の主な職業」と老後の所得の関連を年齢層ごとにみた結果、専門職・大企業ホワイトのすべての年齢層、中小企業ホワイトおよび大企業ブルー、自営業ホワイトの一部の年齢層において平均年間所得が300万円以上の高所得層が存在すること、自営業ブルー・農業はおしなべて低所得であることが確認され、職業的地位により、老後の所得が大きく異なることが明らかになった。さらにMDPREFを用いた分析では、専門職・大企業ホワイト・大企業ブルーが近くに位置づけられ、これに60-64歳における大企業ブルーの所得上昇、70-74歳以外では中小企業ホワイトよりも大企業ブルーの所得が高いという知見を併せると、ブルー・ホワイトという職種の差を超えた、中小企業に対する大企業の優位性が示唆されたと考えられる。
3 0 0 0 OA 半没水双胴形船舶について
- 著者
- 大島 正直
- 出版者
- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会
- 雑誌
- 日本舶用機関学会誌 (ISSN:03883051)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.5, pp.411-418, 1980 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 2
The Semi-Submerged Catamaran (SSC) has been expected as a new type of promising marine vehicle to break the various performance limitations imposed by the conventional monohull or the conventional catamaran vessel.This paper introduces the outline about the characteristics of SSC performance and the design conceptions on her propulsion system in addition to the outline of the commercial prototype of SSC ferry for 446 passengers, which had been completed for the first time in the world at the end of August, 1979 at Chiba Yard of Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd.
3 0 0 0 OA 4. 魚類の対光行動とその生理
- 著者
- 井上 実
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.8, pp.907-912, 1972-08-25 (Released:2008-02-29)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 3 5
3 0 0 0 OA 低自尊心者における下方螺旋過程についての検討(5)
- 著者
- 長谷川 孝治 浦 光博 礒部 智加衣
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第70回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.1PM025, 2006-11-03 (Released:2018-07-03)
3 0 0 0 OA ヒドロモルフォン注射剤から経口剤への換算についての検討
- 著者
- 大音 三枝子 薩摩 由香里 梅田 節子 新城 拓也 西本 哲郎 池末 裕明 室井 延之 橋田 亨
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.147-151, 2020 (Released:2020-06-11)
- 参考文献数
- 14
がん疼痛に対して,ヒドロモルフォン注射剤から投与を開始し鎮痛効果を評価した研究は少なく,注射剤と経口剤の換算比を検討した研究もほとんどない.そこで,中等度から高度のがん疼痛を有する患者において,ヒドロモルフォン注射剤から経口剤に変更する際の換算比の検討を目的とし,症例集積調査を行った.2018年7月から2019年12月に,ヒドロモルフォン注射剤から経口剤へ変更した入院がん患者を対象とし,1:5の換算比で変更した後の鎮痛効果と副作用の発現状況を調査した.対象患者6例のうち3例では適切な鎮痛効果が得られたが,1例で鎮痛効果が不十分で増量を要し,2例で有害事象の眠気が出現し減量を要した.この結果より,ヒドロモルフォン注射剤から経口剤に変更するときは,症例ごとに変更後の鎮痛効果と有害事象を慎重に観察し,投与量を調節する必要性が示唆された.
3 0 0 0 OA 教科書ができるまで
- 著者
- 田代 直幸
- 出版者
- 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- vol.116, no.2, pp.187-190, 2008 (Released:2008-12-27)
- 参考文献数
- 1
教科書の作成は,学習指導要領及び学習指導要領解説に基づいて行われる。学習指導要領は,目標,内容,内容の取扱いの3つの部分から構成され,扱う内容やその内容の扱い方(程度)が示されている。学習指導要領解説は,学習指導要領の趣旨や内容の取扱いなどをもう少し具体的に示したものである。教科書会社が作成した申請図書は,執筆されている内容の範囲や程度,学問上の正確性などの観点から,教科用図書検定調査審議会による審議によって意見が付される。これらの意見に対して適切に修正を加えることで,申請図書は,教科書として認められることとなる。
3 0 0 0 OA スニチニブ投与患者に発症した顎骨壊死の1例
- 著者
- 岩田 英治 古土井 春吾 鰐渕 聡 岸本 恵実 明石 昌也 古森 孝英
- 出版者
- 社団法人 日本口腔外科学会
- 雑誌
- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.2, pp.83-87, 2018-02-20 (Released:2018-04-20)
- 参考文献数
- 17
Osteonecrosis of the jaw is one of the problematic side effects observed during administration of angiogenesis inhibitors in patients receiving treatment for cancer. We report a case of osteonecrosis of the jaw in a patient receiving sunitinib. The patient was a 72-year-old man who was referred to our hospital because of exposed bone and contact pain of the tongue. After the clinical diagnosis of osteonecrosis of the jaw, observation and irrigation of the exposed bone were frequently performed. Four months later, the lesion healed. After 1 year, exposed bone was found in other sites ; however, it disappeared a month later. The present case suggests that the use of sunitinib can be associated with osteonecrosis of the jaw and indicates that invasive dental treatment and the status of the main disease should be considered when prescribing sunitinib, as is done when prescribing bisphosphonates or denosumab.
3 0 0 0 OA Picard の公式による第一種積分方程式の解の数値的構成法
- 著者
- 藤原 宏志
- 出版者
- 日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」
- 雑誌
- 理論応用力学講演会 講演論文集 第53回理論応用力学講演会 講演論文集
- 巻号頁・発行日
- pp.78, 2004 (Released:2004-03-25)
逆問題に現れる第一種積分方程式に対しては、そこに含まれる積分作用素の特異系を用いることで解を構成することができる。これは Picard の公式として知られる。しかし限られた積分核を除き、この特異系を具体的に得ることは理論的にも数値的にも困難であったため、従来、Picard の方法による解の構成は期待されなかった。本講演では、近年提唱された数値特異値分解を Picard の公式に適用することによる第一種積分方程式の数値解の構成を紹介する。
3 0 0 0 OA かご効果(<特集>化学における弱い相互作用)
- 著者
- 徳丸 克己
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学教育 (ISSN:24326542)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.270-273, 1980-06-20 (Released:2017-09-15)