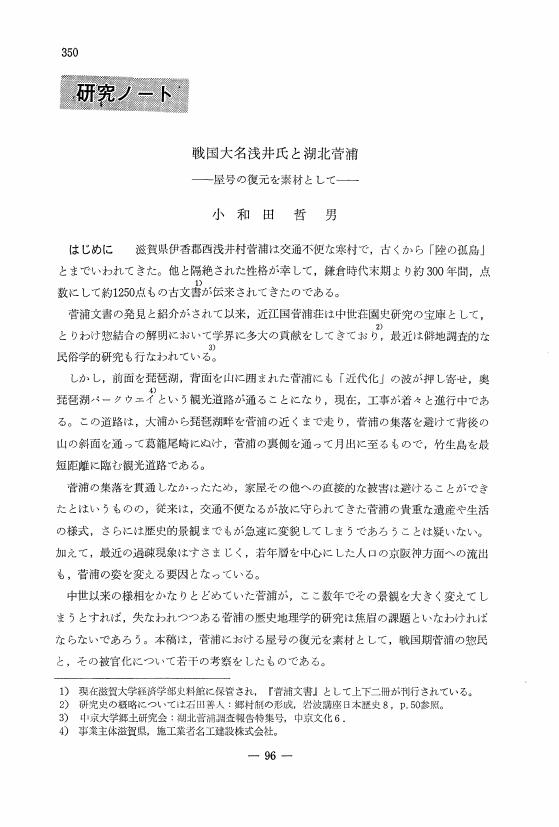2 0 0 0 OA 除草剤 glyphosate のエンドウ葉色素生合成に及ぼす影響
- 著者
- 本澤 彰一 松中 昭一
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.30-35, 1986-05-26 (Released:2009-12-17)
- 参考文献数
- 22
エンドウ葉リーフディスクを用いて, 除草剤 glyphosate の各色素生合成経路への阻害機構を調べた。1. 3種の芳香族アミノ酸は, 植物体内に取込まれタンパク質へと合成されたが, これらのアミノ酸3種の添加では, glyphosate の阻害からの完全な回復はなかった (Table 1 and Fig. 1)。2. 1つの色素生合成経路の前駆体化合物を添加しても glyphosate の薬害からの効果的な回復はなかった。しかし, 3種の芳香族アミノ酸, ホスホエノールピルビン酸及びδ-アミノレブリン酸の5種類全部を同時に添加した場合には, クロロフィル及びアントラキノンの減少の緩和及びシキミ酸蓄積の減少に効果的であった (Table 1 and 2)。3. カロチノイド生合成阻害を作用機構とする除草剤 methoxyphenone 処理によっては, この経路の末端部位の阻害によるフィトエン, フィトフルエン及びζ-カロチンの蓄積とβ-カロチンの減少が認められた。しかし, glyphosate 処理ではこれらの化合物の蓄積は認められず, 明条件下のみでβ-カロチンが減少した。したがって, glyphosate のカロチノイド生合成阻害は, その末端部位ではなく別の部位と考えられる (Table 3)。4. Glyphosate 処理により, 14C-アセチルCoAのクロロフィル, カロチン及びキサントフィルへの取込みが同程度阻害された (Fig. 2)。5. Glyphosate は, 5-エノールピルビルシキミ酸-3-リン酸シンターゼを阻害するのに加えて, 植物色素生合成経路の初期段階を阻害する可能性も考えられる。
2 0 0 0 OA 二酸化チタン複合材料の調製と殺菌システムへの適用
- 著者
- 田谷 正仁
- 出版者
- Brewing Society of Japan
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.8, pp.507-511, 2010 (Released:2016-01-25)
- 参考文献数
- 10
二酸化チタンの光励起により発生する活性酸素種は,種々の有機化合物を酸化分解し無機化することから,セルフクーリング機能のある環境浄化材料としての利用が期待されている。このような二酸化チタンの反応機構は,有機物の集合体ともいえる微生物やウイルスの滅菌や殺菌にも有効である。二酸化チタンによる有機物処理は,高い有機物含有環境には不向きで,低濃度で有機物(あるいは細胞)を含む系において効果を発揮する。この場合,標的とする反応物(細胞)を二酸化チタン粒子近くに引き寄せるような工夫が重要となる。ここでは,このような観点からの二酸化チタン複合材料の調製とその利用について,筆者らの取組みの一端を解説いただいた。
2 0 0 0 OA 尿路感染予防のための尿路カテーテル管理
- 著者
- 戸ヶ里 泰典 山田 正己 泉 キヨ子
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護研究学会
- 雑誌
- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.1_115-1_123, 2004-04-01 (Released:2016-03-31)
- 参考文献数
- 39
尿路カテーテル装着患者への尿路感染予防のための外尿道口周囲のケア(meatal care)は,様々な根拠に基づいた多種の方法で実施されていることが多い。そこで米国や英国のレビューやガイドライン,RCT研究等を概観し,尿路感染予防に効果的な外尿道口ケア方法を検討した。その結果,短期間(~7日)の留置に限る場合にはポビドンヨードによる消毒や石鹸洗浄の実施,抗生剤軟膏の塗布が細菌尿の出現に関連するという報告から,これらの実施を控えることが望ましいことがわかった。一方,中期間(7~30日)および長期間(1ヶ月以上)留置の場合,根拠とすべき研究は未だ報告されていない。すなわちEBNの観点より,尿路感染予防のための外尿道口ケアとは,通常の身体保清のみであるといえる。また今後,長期留置患者では感染防止に加え,顕性感染予防のためのケア方法の探究といった,視野を広げた研究が必要と考えられる。
2 0 0 0 OA 岐阜都市計画下水道事業の成立経緯に関する研究
- 著者
- 出村 嘉史
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.3, pp.297-304, 2018-10-25 (Released:2018-10-25)
- 参考文献数
- 52
- 被引用文献数
- 1
本研究は、日本で初めて全面的な分流式下水道を実現した市である岐阜市を対象に、建設されるまでの過程を追い複雑に絡み合う諸般の事情を整理して、都市計画下水道事業の計画の実態を明らかにし、その計画のパースペクティブを把握し、それがどのような立場と体制によって形成されてきたものであるのかを明らかにすることを目的とする。全国で下水道事業が発展段階にあった昭和初期に、岐阜市長松尾國松と技師安部源三郎は下流を含めた広い地域的な水収支を視野にいれた技術的な解を、既存の排水計画の徹底した研究と現状の測量を実施しながら見出していった。鍵は市内を通過して下流の広大な耕地を灌漑する忠節用水の改良事業であり、県と国によって進められたこの計画内容を共有しながらこれを含めて初めて実現する分流式下水道計画を同時に進め、全国においても最先端のシステムを実現させた。この下水道建設事業は、都市計画事業の枠を用いているものの、実態は高い技術の導入に導かれた基盤整備事業であった。しかし、その事業が持ち得た視野は、極めて地方計画的なものであったことが指摘できる。
2 0 0 0 OA PTにとって必要な法律知識
- 著者
- 水澤 亜紀子
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会宮城県理学療法士会
- 雑誌
- 理学療法の歩み (ISSN:09172688)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.2-5, 2009 (Released:2009-02-17)
理学療法士・作業療法士の業務に際しても最低限の法律知識が必要であり,特に患者等との紛争を念頭において,法律知識やその対処法等について述べる。
2 0 0 0 OA 抗NMDA受容体脳炎6例の臨床的検討
- 著者
- 堀野 朝子 塩見 正司 井上 岳司 温井 めぐみ 九鬼 一郎 岡崎 伸 川脇 壽 天羽 清子 外川 正生
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経学会
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:00290831)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.4, pp.275-280, 2014 (Released:2014-12-25)
- 参考文献数
- 15
【目的】小児の抗N-methyl-D-aspartic acid receptor脳炎 (以下抗NMDA受容体脳炎) 6例の臨床像と予後を検討する. 【方法】本脳炎の特徴的な臨床経過を有した症例を後方視的に検討した. 【結果】該当症例は男2例女4例, 年齢は13~16歳, 抗NMDA受容体抗体陰性例が1例含まれた. 女子全例で卵巣腫瘍を認め, 急性期以後の検出が3例, 増大例が1例存在した. 側頭葉病変を認めた1例で高次脳機能障害とてんかんが, 小脳病変を認めた1例で軽度知的障害の後遺症がみられた. 【結論】頭部MRIで異常を認めた2例は後遺症を有した. 腹部MRIによる卵巣腫瘍検索は, 脳炎治癒後最低4年以上は必要である.
2 0 0 0 OA 国立公園指定における伊勢志摩国立公園の特異性の背景と伊勢神宮の関係
- 著者
- 水内 佑輔 古谷 勝則
- 出版者
- 公益社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.5, pp.389-394, 2012 (Released:2013-08-09)
- 参考文献数
- 83
- 被引用文献数
- 1 4
Ise-Shima National Park is the only national park that was designated without a deliberation of the National Park Commission in 1946, right after World War II. The objective of this study is to clarify this exceptional case of Ise-Shima's designation as a national park, in relation to Ise Jingu (the Ise Grand Shrine), by exploring the background of its designation. The background can be roughly divided into two periods: during World War II, and right after the war. It has been confirmed that Ise Jingu imposed its influence in different ways in each period. The transportation network was well established due to Ise Jingu’s characteristics as a sacred place and for the purpose of shrine visits. This indirectly influenced the designation of the national park candidates in the Shima region. Soon after the war, Ise Jingu faced the threat of being dismantled. Walter Popham of GHQ and Ishigami Kashiro of the Ministry of Welfare recognized the value of Ise Jingu and proposed that they designate the shrine area of Ise Jingu as a national park. Re-establishment of the administrations of national parks was still in process; however, the necessity for speedy protection of Ise Jingu served as a key factor for the unusual designation. After the designation of Ise-Shima National Park, the demand for national park designations increased all over the country, and this was the impetus for national park administrations to fully resume their work.
2 0 0 0 OA 左利きの研究
- 著者
- 原田 富士子
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.205-212, 1960-08-15 (Released:2010-03-09)
- 参考文献数
- 5
2 0 0 0 OA 乾燥肌に対するグルコサミン塩酸塩の臨床効果
- 著者
- 梶本 修身 勝呂 栞 高橋 丈生
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.5, pp.335-343, 2001-05-15 (Released:2010-01-20)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
日頃,乾燥肌で肌荒れ傾向のある女性32名を対象に,グルコサミン塩酸塩(1500mg/day)のplaceboを対照とした6週間の二重盲検長期摂取試験を実施した.その結果,以下のことが明らかとなった.(1)医師による診察所見において,グルコサミン塩酸塩が,肌の乾燥や化粧のり,落屑を有意に改善させる働きのあることが示された.(2)肌の水分量測定において,グルコサミン塩酸塩が,水分量を増加させる働きのあることが示された.(3)肌の顕微鏡的3次元的皮膚表面解析によって,グルコサミン塩酸塩が,肌の滑らかさや鱗屑を改善させる働きのあることが示された.以上より,グルコサミン塩酸塩の長期摂取が,肌の保水や滑らかさを向上させる上で有効であることが示された.
2 0 0 0 OA 近世富士山における山小屋建築の諸相と山岳景観
- 著者
- 奥矢 恵 大場 修
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.756, pp.465-475, 2019 (Released:2019-02-28)
- 参考文献数
- 51
- 被引用文献数
- 1 4
From ancient times, mountains have been worshiped in Japan. Mt. Fuji is archetypal, and the huts that served its pilgrims can be regarded as the original form of current mountain huts. Since Mt. Fuji became a World Cultural Heritage site, its huts are required to be historically based. We examined and confirmed the establishment and form of Mt. Fuji's mountain huts, specifically, the stone huts on the Yoshida trail. They were built in the early Edo era and developed with the flourish of worship ascents by Fuji-ko societies. Then, we expanded our scope to the Omiya-Murayama, Suyama and Subashiri trails that were mainly used with the Yoshida trail since the Middle Ages. They have their own geographical and historical backgrounds. We examined historical materials and clarified the owners, location and form of the mountain huts (teahouses and stone huts) on each trail and the summit they serviced. We focused on these huts in relation to three areas on Mt. Fuji: Kusayama, Kiyama and Yakeyama. The huts were owned by Murayama Sanbo (three lodges for priests) on the Omiya-Murayama trail and by each village's oshi at the foot of Mt. Fuji on the other trails. Hyakusho managed and built the huts. On the summit, there were two temples surrounded by stone huts. Dainichido temple was managed by Murayama Sanbo and Yakushido temple by Subashiri villagers. Bids were taken for management of the stone huts in the latter. On each trail, the teahouses were in the Kusayama and Kiyama areas and the stone huts were in the Yakeyama area. On three trails excluding Yoshida, stations 1 to 9 were established to conduct mountain ascetic practices on Yakeyama. This suggests that Yakeyama was the most sacred and harshest environment, resulting in being referred to as the “Honzan” (main mountain of worship ascents). The huts were planned and built after natural disasters, such as the Hoei eruption and avalanches, or before Koshingoennen (a special year celebrated every 60 years) by the rulers, Murayama Sanbo and oshi. We found similarities of huts' location between the Omiya-Murayama and Suyama trails flourished till the early Edo era by Shugen-do, and the Subashiri and Yoshida trails flourished in the late Edo era by Fuji-ko. Depending on the trail, the teahouses had the same roofs as temples and shrines or houses in the village at the foot of Mt. Fuji. The Omiya-Murayama and Yoshida trails were managed by bo or oshi, a type of priest, and the Suyama and Subashiri trails were managed by oshi who belonged to the hyakusho class. The teahouses were made of the same materials and shapes used by the rulers' class or the villages they dominated. The scenery of the villages was continuously expanded to Kusayama and Kiyama. On the other hand, the stone huts in Yakeyama had the same form on all the trails. They had a wooden frame structure, hirairi, piled up cinders on the kiritsuma roof and around the walls and one or two entrances facing the trail. They came into sight on the boundary of Kiyama and Yakeyama, and their forms were unified like the mountain itself. Not only was the form of the stone huts unusual, but the way in which they came into being, with each owner locating and preparing suitable sites in three areas, made the stone huts a symbol of worship ascents on Mt. Fuji. In addition, about 8-16 stone huts on the summit that were used not as lodgings, but as teahouses, were lined with a tsumairi façade. It created a unique scene that was not seen on the trails.
2 0 0 0 OA 中房温泉の経営者による戦前期の山小屋建設とその立地計画
- 著者
- 梅干野 成央 堀田 真理子 土本 俊和
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.681, pp.2643-2650, 2012-11-30 (Released:2013-05-28)
- 参考文献数
- 35
This paper traces some links of the development process of the mountain huts through the example of the location planning of the mountain huts by the owners of the Nakabusa spa in the prewar period by analysing the Momose family's archives. The owners of the Nakabusa spa had construction plans for 15 mountain huts in the prewar period. This was done by using the local knowledge about the place which the mountain residents (i.e. huntsmen, etc.) had for the base of a mountaineering course around mountaineering stations.
2 0 0 0 OA 戦国大名浅井氏と湖北菅浦
- 著者
- 小和田 哲男
- 出版者
- The Human Geographical Society of Japan
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.350-360, 1970-06-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 27
2 0 0 0 OA 鉄道会社が経営する郊外遊園地の跡地利用に関する研究
- 著者
- 川崎 泰之
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.273-278, 2014-10-25 (Released:2014-10-25)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
本研究は日本において鉄道会社が主体的に行ってきた沿線開発事業の内、郊外の開発拠点として注力してきた遊園地に着目し、大手私鉄が経営していた郊外遊園地のうち閉園したものを対象として、その跡地利用について計画および実際の空間を調査し、都市計画公園・緑地の指定状況との関係性、鉄道や駅、周辺市街地との関係性、遊園地の景観資源との関係性について分析を行った。その結果、閉園前から都市計画公園に指定されていた事例は、高い割合で公園整備または公園的土地利用となっているが、閉園前も閉園後も都市計画公園に指定されていない事例は、公園整備面積が比較的小さく、そのことから都市計画公園・緑地制度が民間事業用地における公共的土地利用の担保性を持っていることがわかった。また鉄道や駅、周辺市街地との一体的整備により拠点性を高めている開発や、駅や鉄道との関係を重視した動線やゾーニングによる開発が多く見られた。景観資源については、自然環境に恵まれた立地特性を活かした事例が多く見られたが、歴史・文化資源については遊園地そのものを想起させる資源が残されている事例が少なく、郊外文化としての遊園地の記憶の継承が課題である。
2 0 0 0 OA 放射線皮膚炎に対する保湿クリームの効果
- 著者
- 齊藤 真江 林 克己
- 出版者
- 一般社団法人 日本がん看護学会
- 雑誌
- 日本がん看護学会誌 (ISSN:09146423)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.14-23, 2015 (Released:2016-11-25)
- 参考文献数
- 12
要 旨本研究の目的は,頭頸部の放射線治療で頻度の高い急性有害事象である放射線皮膚炎に対する,保湿クリーム(リモイス®バリア)の効果を明らかにし,看護支援に役立てることである.方法は,2011年1月~ 2013年9月に頭頸部に放射線治療を実施し(気管孔のある患者,および頸部全体が照射野に入らない喉頭がん以外の症例を除く),研究の同意が得られた患者33名を対象とした.封筒法(封筒に入れた複数のカードの中から患者自身が選択する方法)により保湿クリーム使用群と未使用群に分けた.保湿クリームは治療後と眠前に撫でるように塗布することを患者に指導し,照射時に自覚症状と他覚症状を観察した.皮膚障害の程度は,「症状なし」を「0」,「症状あり」を段階的に「1~6」に点数化し,照射ごとに加算した.さらに,保湿クリーム使用群16名と未使用群17名の皮膚障害の程度を比較し,統計的に分析した.その結果,保湿クリーム使用群は自覚症状,他覚症状ともに出現頻度が低く,出現時期が遅かった.また,両群の線量が進むごとに加算した皮膚障害の程度の点数を照射線量ごとに検定を行った結果,60Gy以上で有意差があった.さらに,保湿クリーム使用による皮膚炎の悪化は認めなかったことにより,放射線皮膚炎に対して保湿クリームは有効であることが分かった.保湿クリームは,放射線皮膚炎の進行を抑制する効果があり,皮膚炎による苦痛の軽減につながった.
2 0 0 0 OA 顔の大きさ知覚に及ぼす衛生マスク着用効果
- 著者
- 宮崎 由樹 伊藤 資浩 神山 龍一 柴田 彰 河原 純一郎
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第14回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.43, 2016 (Released:2016-10-17)
近年,衛生マスク (以下,マスク) は,風邪や花粉対策等の衛生用途以外にも使われる。例えば,若年女性の一部は,小顔に見せる為にマスクを利用することがある。本研究では,見た目の顔の大きさにマスクの着用が及ぼす効果を検証した。実験はマスク着用 (着用,非着用) と元々の見た目の顔の大きさ (小顔,中顔,大顔群) の2要因被験者内計画で実施した。被験者は,LCDに呈示された顔画像の見た目の顔の大きさを1 (小さい) から100 (大きい) の範囲で評定した。その結果,元々の見た目の顔の大きさに関わらず,マスク非着用画像に比べ,マスク着用画像の方が顔が小さく知覚されることが示された (マスク着用の効果量は小顔群に比べ,中顔・大顔群の方が大きかった)。この効果は,マスク着用で,顔の大きさ判断に用いられる視覚手がかり (咬筋部や下顎周りの皮膚厚等) が利用できなくなること,顔が遮蔽されたことによる錯視効果に基づくと考えられる。
2 0 0 0 OA 自己評価の規定要因とSELF-ESTEEMとの関係
- 著者
- 溝上 慎一
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.62-70, 1997-03-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1 1
Recently an idiographic approach into a nomothetic method has been the eyes of the world. Higgins, E. T. & Endo. Y. are quite famous for stressing the significance of this approach, though Higgins' approach is a little different from Endo's: the former is seen as an approach that a person represents idiographic points spontaneously while the latter is seen as an approach having a person select his own idiographic points in some items given by a researcher. The former is called “inner frame as an idiographic approach” and the latter is called “outer frame as an idiographic approach.” The purpose of this study is to examine the relationship between inner frame and outer frame as the base of factors regulating self-esteem or self-evaluation. At the results, both high-self-esteem group and low-self-esteem group can select many regulating factors through outer frame and are also easy to represent them through inner frame. Furthermore, regulating factors in ambivalent self-evaluations are also examined, and the relationship between inner frame and outer frame is eventually better clarified.
- 著者
- 島田 沢彦 中西 康博 木村 李花子 渡邉 文雄 渡辺 智 山本 裕基 伊藤 豊 大山 修一 ファドモ Aマロウ
- 出版者
- 日本沙漠学会
- 雑誌
- 沙漠研究 (ISSN:09176985)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.61-67, 2019-09-30 (Released:2019-10-24)
- 参考文献数
- 8
東京農業大学とジブチとの25年に渡る共同研究で培ってきた成果は,JST・JICA共同実施の地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)への課題「ジブチにおける広域緑化ポテンシャル評価に基づいた発展的・持続可能水資源管理技術確立に関する研究」の採択により評価され,2019年度から新たなフェーズとして社会実装へとつなげることとなった.本報では,これまでのジブチでの成果,今後5年間で展開される研究のビジョン,持続可能なパストラルアグロパストラル(農牧業)・システムの実装への課題および達成されるSDGsについて紹介した.
2 0 0 0 OA 両側前頭葉損傷に出現したforced gazing (強制凝視)について
- 著者
- 船山 道隆 前田 貴記 三村 將 加藤 元一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.40-48, 2009-03-31 (Released:2010-06-02)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1 1
両側前頭葉損傷後,強制的に人物とりわけ人の眼を中心に凝視ないしは注視 (forced gazing) を続ける2 症例を報告した。この2 例では,人が視界に入れば必ず凝視ないしは注視が誘発され,人が視界から消えるまで持続した。すなわち,この行動は,外部環境刺激に対して戸惑うことなく駆動され継続した。 forced gazing は,能動性がほとんどみられない患者に出現する,外部の環境刺激に対して視線が自動的に反応する被影響性が亢進した現象と考えられ,また前頭葉の損傷による抑制障害のため頭頂葉の機能が解放された結果,これらの行為/行動が出現したと考えた。本2 症例は前頭眼野を含む広範な両側前頭葉損傷であった。本2 症例に随伴した把握現象や道具の強迫的使用から両側前頭葉内側面損傷がforced gazing の責任病巣の中で最も重要と考えられ,前頭眼野も責任病巣の1 つと考えられた。
2 0 0 0 OA 低速域における乗り上がり脱線防止のための一提案
- 著者
- 永瀬 和彦 橋 弘矩
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 C編 (ISSN:03875024)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.744, pp.1938-1947, 2008-08-25 (Released:2011-03-04)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1 1
The friction coefficient μ on the contact point position between a wheel flange and a rail is said to seriously affect on the occurrence of the wheel-climb derailment. However, the method to quantitatively and exactly evaluate the μ has not suggested until to the present. The authors proposed a method to easily and exactly evaluate the value, and made it clear by an experiment, employing a 1/5 scale model track and model truck. The result obtained through the experiment indicates that the value on dry rails has a similarity with that of the adhesion coefficient, and that the dry rail on the main line keeps the value at high level. Using the μ value obtained by the studies, the risk of the wheel-climb derailment was evaluated. As the result of the evaluation, they found that higher μ value than the conventionally used one should be introduced for the risk evaluation of the derailment, and that very short term lateral force below 60 ms should be observed on the steep curvatures.
2 0 0 0 鉄道車両の構体設計に対する有限要素法の適用
- 著者
- 松井 信夫 江口 文夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会誌 (ISSN:24242675)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.713, pp.325-329, 1978-04-05 (Released:2017-06-21)