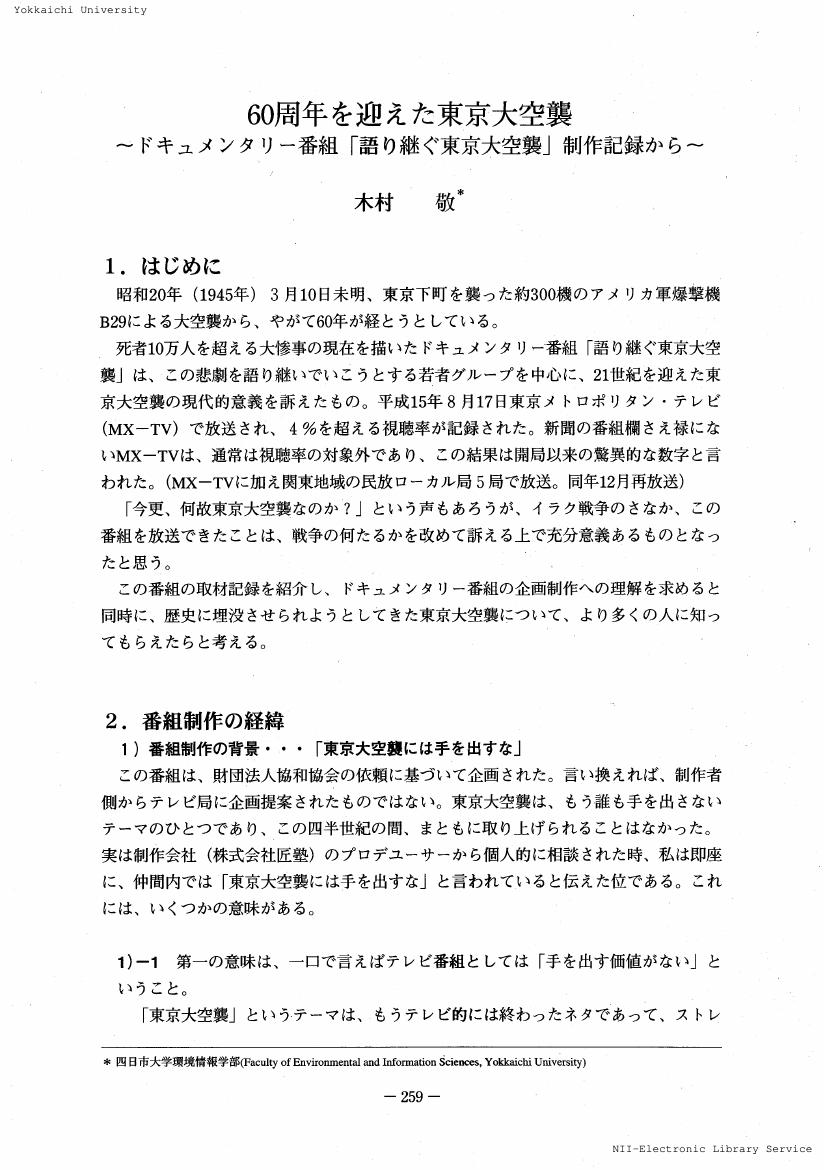4 0 0 0 OA 痛風患者におけるタイプA行動パターンの検討
- 著者
- 佐々木 絢子
- 出版者
- 桜美林大学
- 雑誌
- 桜美林論考. 自然科学・総合科学研究 (ISSN:21850712)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.57-74, 2018-03
4 0 0 0 OA 神経発達症をともなう子どもにおける書字のつまずきに関する研究動向
- 著者
- 加戸 陽子
- 出版者
- 関西大学人権問題研究室
- 雑誌
- 関西大学人権問題研究室紀要 (ISSN:09119507)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, pp.61-82, 2022-03-31
書字の問題は限局性学習症以外の神経発達症をともなう子どもにおいても指摘されている。そこで書字技能および各神経発達症における書字のつまずきに関する論文のレビューを行い、書字技能の発達過程と技能の諸側面に関連する認知・運動機能および、つまずきの特徴と背景要因についての研究動向を整理した。自閉スペクトラム症(ASD)では、部分に対する知覚・認知が優勢であるとする報告や、実行機能の状態、ASD症状および不注意症状の程度が文字の大きさや判読性のみならず書字速度や協調運動にも影響をおよぼすことが指摘されており注目された。注意欠如・多動症では、判読性の問題に関する指摘が多く、ワーキングメモリーや不注意症状との関連が示されている。また、発達性読み書き障害では書字困難の背景に視覚認知の問題の影響を指摘する報告が散見され、視覚認知に関するアセスメントによる確認が重要と考えられた。発達性協調運動症では書字のつまずきの背景に運動パターン形成の困難が推測されている。書字のつまずきの背景要因は各神経発達症によって異なり、併存症状がある場合にはこれらの要素が単独もしくは複合的に影響することも推測される。これらの報告は従来から特別支援教育で指摘されている、つまずきの特徴を明確化し、個に適した支援につなげることの重要性を裏付けるものと考えられる。
4 0 0 0 OA 中世聖徳太子伝と油日神社の縁起 : 聖徳太子の兵法伝受譚と武人としての太子像
- 著者
- 松本 真輔
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.6, pp.11-20, 2004-06-10 (Released:2017-08-01)
中世における聖徳太子信仰が、観音信仰と重なるものであったことは、かねてより指摘のあることである。そこには、「救世」の言葉にふさわしく、慈愛に満ちた太子のイメージを読みとることができる。しかし、中世における太子信仰は、観音信仰のみで語り尽くせるものではない。多種多様な形で展開していた中世太子信仰の世界においては、時として、戦争を仕掛ける凶暴な太子の姿も描かれていた。本稿では、中世太子伝における太子の兵法伝受説の展開を端緒として、武人としての太子像の形成について検討し、更に、こうした太子像の広がりを示す一例として、滋賀県甲賀郡にある油日神社の縁起を取り上げる。
4 0 0 0 OA ヒト口蓋咽頭筋の形態的・機能的意義を考える
- 著者
- 角田 佳折 守田 剛 馬場 麻人
- 出版者
- 四国歯学会
- 雑誌
- Journal of Oral Health and Biosciences (ISSN:21887888)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.19-25, 2022 (Released:2022-03-06)
- 参考文献数
- 25
The human palatopharyngeus is composed of two divisions: longitudinal and transverse. The longitudinal division originates from the velum, and descends in and along the palatopharyngeal arch to reach the thyroid cartilage and submucosa of the pharynx. It is the portion generally accepted as the palatopharyngeus in standard anatomy textbooks. The transverse division originates from the velum and runs transversely on the lateral to posterior wall of the fauces to reach the pharyngeal raphe. In velopharyngeal closure during swallowing, the lateral and posterior walls of the fauces, opposite to the elevated velum, swell inwards to form Passavant’s ridge, and the pharyngeal isthmus is therefore closed as if strangled. The transverse division occupies the position in which its contraction should produce a ridge and may accordingly be termed the palatopharyngeal sphincter. The transverse division corresponds to the transition muscle bundle (Tr) between the longitudinal division and the superior constrictor of the pharynx (SCP). It remains controversial as to whether the Tr should be regarded as an independent sphincter or as the rostral-most portion of the SCP. In contrast, our previous study clarified that the transverse division was distinct from the SCP, and its contraction may have produced Passavant’s ridge to increase the efficiency of velopharyngeal closure by pressing the salpingopharyngeal fold and musculus uvulae ridge against the elevated velum. In mammals with an intranarial larynx, three muscles radiate from the velum to the tongue, the larynx, and the pharyngeal wall: the palatoglossus, palatothyreoideus (pt), and palatopharyngeus (pp). The latter two collectively correspond to the muscle designated here as the palatopharyngeus and are considered responsible for maintaining the intranarial larynx as follows: the pt draws the larynx near the velum as a retractor while the pp holds the larynx in that position as a sphincter. In humans, however, the larynx is positioned low and is largely separate from the velum, and therefore the anatomical states of the two muscles change as follows: in the pt and lower portion of the pp, the site of insertion descends together with the larynx and the muscles become vertical to form the longitudinal division, whereas the upper portion of the pp, which is not as markedly affected by the descending larynx, retains its primitive position and original sphincter function to form the transverse division.
- 著者
- 大沢 真理
- 出版者
- 社会政策学会
- 雑誌
- 社会政策 (ISSN:18831850)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.74-85, 2014-03-31
- 被引用文献数
- 1
リーマン・ショックと東日本大震災は,日本の社会・経済の脆弱性を露わにした。とはいえ日本ではリーマン・ショックの10年前から,年間3万人以上が自殺する事態が続いていた。出生率も世界最低レベルに低迷し,相対的貧困率もOECD諸国でワーストクラスにあった。本稿は生活保障システム論にガバナンスという概念を導入し,また脆弱性のなかでも所得貧困に注目したい。所得貧困という指標の意義を考察したうえで,福祉国家の機能的等価策の効果とともに,所得移転が貧困を削減する度合いについて,国際比較する。また地域間所得格差にかんする研究成果に目を配る。結論的に,日本の税・社会保障制度はたんに機能不全というより逆機能していると主張する。しかもそこには,「男性稼ぎ主」世帯にたいしてその他の世帯が冷遇されるというジェンダー・バイアスがある。それは,多就業世帯が多数を占める農山漁村のような地域を冷遇するバイアスでもある。
4 0 0 0 OA 対米宣戦布告と日・タイ軍事協定問題
- 著者
- 佐藤 元英
- 出版者
- 中央大学政策文化総合研究所
- 雑誌
- 中央大学政策文化総合研究所年報 (ISSN:13442902)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.79-91, 2014-08-26
The main objective of this paper is to clarify the reason why the military convention between Japan and Thailand was made, and why the Japanese Government did not declare war against the American Government. From Kota Bharu, Japanese troops were to strike southward down the Malayan west coast to seize Singapore, gateway to the resources of the Netherlands East Indies, from the British Empire in Southeast Asia. the resources of the Netherlands East Indies. Japanese forces headed for Singapore needed to violate Thailand’s neutrality at Singora (Songkhla), a strategic port north of Kota Bharu on the Gulf of Siam, in the Kra Isthmus area of southern Thailand. The entire southern operation was premised on the violation of international law with respect to two major powers (the United States and Britain) and a minor but diplomatically active third power,Thailand. Fully aware of these operational imperatives, and uncertain if Thailand would enter the war on Japan’s side rather than Britain’s, Emperor Hirohito and Foreign Minister Togo removed from the imperial proclamation of war rescript the clause on respect for international law.
4 0 0 0 IR 出羽山北清原氏の系譜 : 吉彦氏の系譜も含めて
- 著者
- 野中 哲照 ノナカ テッショウ Nonaka Tessho
- 出版者
- 鹿児島国際大学国際文化学部
- 雑誌
- 国際文化学部論集 (ISSN:13459929)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.104-68, 2014-06
4 0 0 0 OA 計量分析の新展開
- 著者
- 村澤 昌崇 立石 慎治
- 出版者
- 日本高等教育学会
- 雑誌
- 高等教育研究 (ISSN:24342343)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.135-156, 2017-07-31 (Released:2019-05-13)
- 参考文献数
- 59
本稿では,高等教育関連の学会誌・機関誌に過去10年間に掲載された計量分析を用いた論文をレビューした.我々が分析の際に行ってしまう傾向がある各種の課題,すなわち必要最低限の情報の不記載や,分析の前提から外れた手法の適用,過剰な解釈等を確認しつつ,これらの課題を乗り越え望ましい分析結果を得るための,いくつかの対応策や新手法の有効性を分析事例とともに提案した.関連する議論として,筆者らの限界により詳細には取りあげなかった先進的手法への期待,論文の紙幅制限によって記載できない情報を共有する仕組みの重要性も併せて指摘した.最後に,高等教育研究における計量分析の質の向上と卓越性について,学会全体で取り組むべきことであることを述べた.
4 0 0 0 OA 原発性局所多汗症診療ガイドライン2023年改訂版
- 著者
- 原発性局所多汗症診療ガイドライン策定委員会 藤本 智子 横関 博雄 中里 良彦 室田 浩之 村山 直也 大嶋 雄一郎 吉岡 洋 宗次 太吉 羽白 誠
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.133, no.2, pp.157-188, 2023-02-20 (Released:2023-02-20)
- 参考文献数
- 231
4 0 0 0 OA 二分法的思考が社会的適応に及ぼす影響の研究
二分法的思考とはものごとを「白と黒」「善と悪」のように二項対立的に捉えようとする思考形態である。本研究では特に,二分法的思考と外在化問題に結びつきやすい心理指標との関連を通じて,二分法的思考の持つ意味や役割を明らかにすることを目的とする。第1に二分法的思考は誇大型の特権意識と強く結びついていた。第2に,外在化問題に結びつきやすいパーソナリティ特性であるダーク・トライアドは,二分法的思考と関連していた。第3に,二分法的思考は年齢にともなって直線的に低下していた。第4に,二分法的思考と攻撃性との間には正の関連が認められるが,その関連の大きさは若い年齢集団ほど大きいという効果が認められた。
4 0 0 0 OA 60周年を迎えた東京大空襲 : ドキュメンタリー番組「語り継ぐ東京大空襲」制作記録から
- 著者
- 木村 敬
- 出版者
- 四日市大学
- 雑誌
- 四日市大学環境情報論集 (ISSN:13444883)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.259-287, 2005-03-31 (Released:2019-12-01)
4 0 0 0 OA 災害による朝廷儀式記録の消失と高御座の再生 ――天明の大火後の即位礼を事例に――
- 著者
- 西村 慎太郎
- 出版者
- 国文学研究資料館
- 雑誌
- 国文学研究資料館紀要 = The Bulletin of National Institure of Japanese Literature Archival Studies (ISSN:18802249)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.1-33, 2016-03-14
本稿は、天明の大火によって近世朝廷において記録・調度品が焼失した後、どのように準備を進めるのかを検討し、文書・記録の管理の特徴を明らかにするものである。事例は天明の大火後、初めて開催された即位礼と即位礼の運営を担った甘露寺国長である。即位伝奏を務めた甘露寺国長のもとには多くの願・伺・届及び書付、または帳簿が提出された。それらは甘露寺家に集積され、コピーや目録としての複数の特徴的な留書が作成された。とりわけ、即位礼の際に天皇が即位を宣言するために登る高御座は重要な調度品だが、これも天明の大火によって焼失してしまい、甘露寺国長はその製作を進めようとする。しかし、即位伝奏である甘露寺家には過去の高御座製作費を把握する文書・記録が前任者から文書・記録が伝えられておらず、過去の即位礼に関与した地下官人の家の記録に依拠する必要があった。「疑似アーカイブズ(文書館)」と評価し得る地下官人の記録であったが、地下官人の記録の集積も不十分であったため、十全としたシステムではなかった。記録の集積が不十分であった理由は、過去の儀式の際に服忌によって家業が務められないという官司請負制の弊害であるが、このような動向が近世公家社会の文書管理の特質と位置づけられる。This paper investigates how to hold the ceremony of the court during Edo era after the court records were burned by TENMEI NO TAIKA (the big fire at Kyoto in 1788), elucidates the nature of the court’s records. This Case of case study is the first SOKUIREI (Japanese emperor’s ceremony) after TENMEI NO TAIKA. This person in charge of this ceremony was KANROZI KUNINAGA (he is aristocrats in Japan early modern times). A number of records have been submitted to KANROZI KUNINAGA. These records were arranged and listed by his vassals. However, KANROZI family doesn’t handed down the archives of the past SOKUIREI. It was necessary to refer the Archives of other nobles and they were not strong enough too. Because, the archives of the past SOKUIREI was not inherited in order to participated in the ceremony of the family of death. This paper points out that that is a feature of the records and archives in early modern Japanese imperial court.
4 0 0 0 OA 回路理論の講義体系に関する思索と実践 —論理的に厳密に,また実験も—
- 著者
- 大石 進一
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.4, pp.301-307, 2014-03-10 (Released:2014-04-01)
- 参考文献数
- 5
早稲田大学基幹理工学部に応用数理学科を設立して7年経過した.これは工学と数学を半分づつ学ぶ学科である.3年生に回路理論を工学系の中心的な必修科目として設置した.電気回路基礎から電子回路(アナログ電子回路もディジタル電子回路も含む)までを30回の90分講義で教える科目である.この科目を2012年度と2013年度の2年間担当した.講義の準備に当たって,回路理論を数学的な論理性を保って講義することができるかを考えた.講義開始前の数か月と講義開始後の8か月ぐらいの約1年間でこのことに対する思索(とそれに必要な歴史的な文献調査,外国の教科書の調査,現在の技術動向調査が含まれる)を巡らし,その結果をコロナ社から回路理論として出版した.結果的にこの本はマクスウェルの方程式を公理として仮定し,素子特性は数理モデルとして与えられていると考えて回路理論を数学的な論理性を保つように展開することを志した.教科書とするために,数学的道具立ては制限した部分が多く,また,原稿も半分程度に圧縮したが,回路理論の論理的展開のためにいろいろな講義展開法についての試行を行い,我が国の定石の講義法とかなり異なっている部分も多い.2年目には講義の前半は理論,後半は実験という形で講義を展開した.2年目は回路理論を論理的に捉えるだけでなく,実験により回路の実在をどう捉えるか考えさせた.これらの思索と実践について報告する.
4 0 0 0 性同一性障害の夫婦による嫡出子出生届をめぐる法律問題(下)
- 著者
- 梶村 太市
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- 法律時報 (ISSN:03873420)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.11, pp.70-77, 2012-10
4 0 0 0 OA 大阪中之島山崎ノ鼻「公園地」に関する一考察
- 著者
- 林 倫子 篠原 知史 大坪 舞
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D1(景観・デザイン) (ISSN:21856524)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.1, pp.21-36, 2017 (Released:2017-08-20)
- 参考文献数
- 64
- 被引用文献数
- 1 1
本研究では,大阪中之島公園の起源ともいえる山崎ノ鼻「公園地」に着目する.「この『公園地』は,豊國神社境内地造営と一体的に,大阪府によって計画・整備された門前の盛り場であった」という仮説を設定し,この仮説に関する3つの傍証,すなわち(1) 境内の隣接地に「公園地」が必要とされた理由,(2)両事業の主体・時期の重なり,(3) 開設直後の「公園地」施設とその利用実態,を示した.さらにこの「公園地」の制度上の位置づけや公園制度との関係についても考察した.「公園地」は公共の管理する盛り場であるという意味で最初期の公園と同じ場所であったが,近代土地制度上は道路施設の一部として位置づけられていたこと,西洋的公園観の広まりとともに「仮公園」との併存を経て,正式な公園に編入されたことを示した.
4 0 0 0 OA 技術の観点から見た日本のリプロダクティヴ・ライツ政策の問題点
- 著者
- 塚原 久美
- 出版者
- 日本医学哲学・倫理学会
- 雑誌
- 医学哲学 医学倫理 (ISSN:02896427)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.38-48, 2010-09-24 (Released:2018-02-01)
In this article, I would like to address the problems of the Japanese government's policy on reproductive rights from the viewpoint of development of reproductive control technologies. The problems were rooted in an old and unrefined abortion method spread in this country in spite of the international principle of reproductive health and rights. Reproductive Rights are the series of human rights relating to reproduction and reproductive health, which were explicitly recognized at the United Nations International Conference on Population and Development in 1994. These rights are key to women's dignity and gender equality, and articles of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, adopted in 1979 by the UN General Assembly, serve as a basis for these rights, as well as those of the UN declaration of Human Rights (1948) and several other International covenants for human rights. Reproductive rights were only possible after the development of abortion methods that assuage the tension between the pro-life position and women's rights. However, the Japanese government's continuing opposition to the advice of the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women to legalize abortion came about because of the fixation on the feto-centric and women-exclusive view of abortion. Such a policy should be replaced by a more humane, inclusive view of reproduction in order to improve reproductive healthcare and to eliminate discrimination against women in Japan.
4 0 0 0 OA いろは辞典 : 漢英対照
4 0 0 0 OA 過酸化脂質を還元消去する食材の探索と調理加工におけるその利用法の開発
調理や消化過程で生じる過酸化脂質は最小限に抑える必要がある。そこでネギ属野菜が有する過酸化脂質還元作用を利用することにより、過酸化脂質量低減化法を開発することを目的とした。万能ネギ、長ネギ、タマネギ、ニンニクのうちで長ネギの還元作用が最も強いことを明らかにした。食用油脂のトリアシルグリセロールヒドロペルオキシド(TG-OOH)を人工膵液で加水分解すると遊離脂肪酸ヒドロペルオキシ体(FFA-OOH)が産生したが、長ネギ試料はTG-OOHおよびFFA-OOHどちらとも還元作用を示さなかった。消化管ではネギの還元作用を発揮する活性本体が膵液により消化されて消失すると思われた。
- 著者
- 藤井 洋有 近藤 健
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.26-33, 2023-02-15 (Released:2023-02-15)
- 参考文献数
- 28
本研究の目的は終末期がん患者の在宅復帰の予測因子を検討し,リハの臨床で役立つ視点を提示することである.リハを実施した終末期がん患者102名を対象とし,基本属性,臨床データ,FIM,PPIを診療録より収集した.また,ロジスティック回帰分析で在宅復帰の因子を求め,カットオフ値を算出した.結果,PPIと主介護者以外の同居家族が因子として抽出され,PPIのカットオフ値は4であった.終末期がん患者の在宅復帰支援において,生命予後を踏まえてADLを予測し,リハ目標を設定する必要性を裏づける結果であった.また,PPIのカットオフ値と家族構成は,退院支援の方針を迅速に検討する際,有益な情報になり得ると考えた.