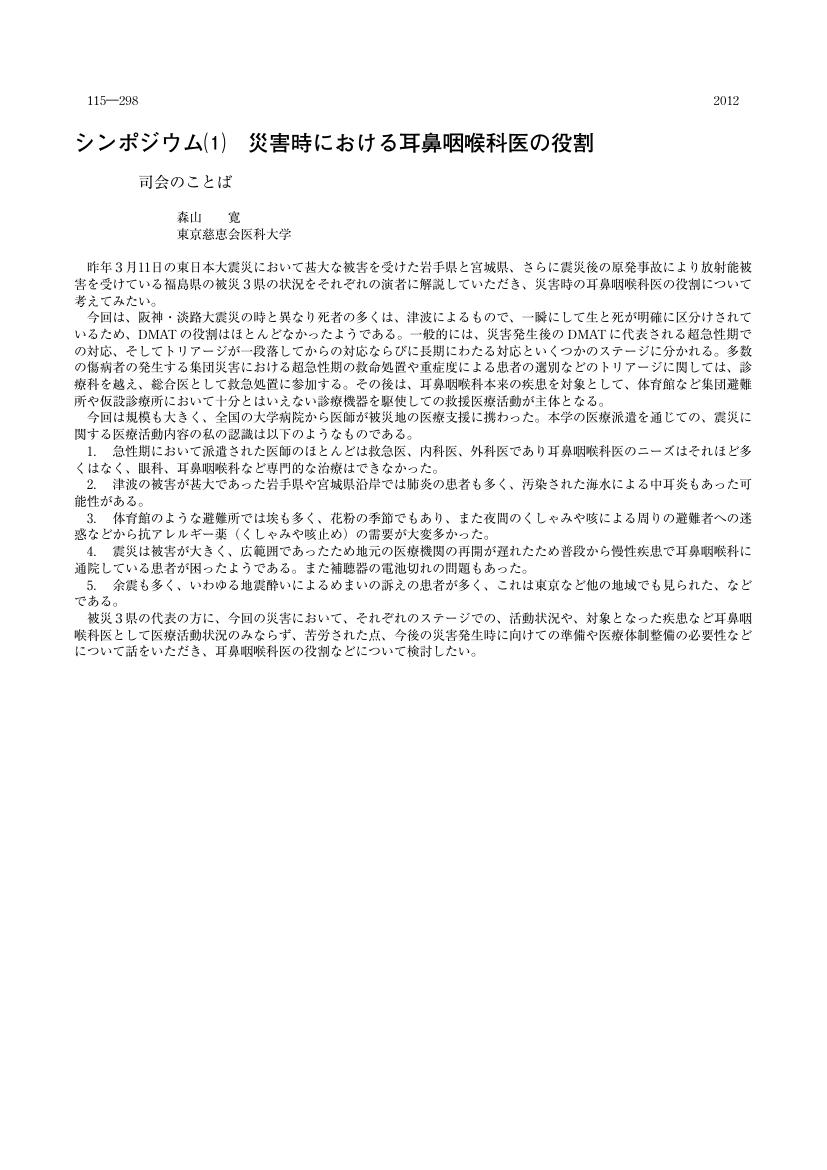133 0 0 0 OA ATA2015小児甲状腺結節・分化がんの治療ガイドラインについて
- 著者
- 山下 俊一
- 出版者
- 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会
- 雑誌
- 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 (ISSN:21869545)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.4, pp.274-279, 2015 (Released:2016-03-04)
- 参考文献数
- 8
米国甲状腺学会(ATA)が,小児甲状腺結節・分化がんの取扱いについて,診断の進め方と手術の選択方法,術後管理の詳細について405編におよぶ論文精査と専門家の意見を反映し,欧米の現時点でのコンセンサスを取り纏めた。既報の成人甲状腺がん治療ガイドラインと比較すると,発見された小児甲状腺がんの治療手順が中心であり,原則成人版と大差はない。すなわち,予後良好な小児甲状腺結節・分化がんの術前のリスク推定による治療選択ではなく,術中所見と術後リスクを考慮した術式(全摘中心)の議論と,術後フォローアップ時における血中サイログロブリン(Tg)濃度を,再発癌マーカーとし,全摘後も高リスクと評価される患者への放射性ヨウ素内用療法を推奨した管理ガイドラインとなっている。小児甲状腺がんの前向き調査がなく,自然経過を考慮した議論の余地もあり,現在実施されている福島県の約38.5万人を対象とする甲状腺超音波検査の今後が重要となる。
133 0 0 0 OA 生体網膜上の錐体比の測定
- 著者
- 山内 泰樹
- 出版者
- 日本眼光学学会
- 雑誌
- 視覚の科学 (ISSN:09168273)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.57-64, 2009 (Released:2019-11-08)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
色覚を司る視覚メカニズムのフロントエンドは異なる感度を有する3種類の錐体である。近年,非侵襲な方法により,これらの錐体の網膜上での存在比率を計測する技術が発達してきた。本稿では,それらの方法のうち,網膜像撮影方法と分光視感効率による推定方法について概説する。前者は,補償光学(adaptive optics)を用いて生体の網膜像を撮影する手法と,錐体の選択的な光反応特性を用いたものであり,後者は網膜電位法(ERG)により分光視感効率を求め,遺伝子解析により求めたL,M錐体のピーク感度を用いてこの分光視感効率を重みづけ,近似することにより推定する方法である。これらの方法により,L/M錐体比は被験者間で大きく異なることが示された。また全く異なる両者の結果が高い相関を有することから,両者とも有効な手法であることを示す。
133 0 0 0 OA 甲状腺がんと放射線障害
- 著者
- 大津留 晶 緑川 早苗 坂井 晃 志村 浩己 鈴木 悟
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.3, pp.593-599, 2015-03-10 (Released:2016-03-10)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
甲状腺は放射線に対して発がん感受性が高い臓器の1つと捉えられている.甲状腺がんの放射線発がんリスクは,被曝時年齢が若いほど高くなる.放射線は発がん因子の1つとしても,二次発がんという観点でも重要である.原爆被曝者の調査では,外部被曝による甲状腺がんリスク増加が示された.チェルノブイリ原発事故は,放射性ヨウ素の内部被曝が発がんの原因となった.いずれも100 mSv(ミリシーベルト)以上から徐々に有意となり,線量が高いほど罹患率が上昇する,線量依存性が見られている.東京電力福島第一原発事故後,小児甲状腺がんに対する不安が増大し,福島では大規模なスクリーニング調査が開始されている.本稿では,放射線と甲状腺がんについて,これまでの疫学調査と病理報告を概説し,放射線誘発甲状腺がんの分子機構の最前線に触れ,最後に小児甲状腺がんスクリーニングについての考え方についてまとめた.
- 著者
- KEIYA FUJIMORI HYO KYOZUKA SHUN YASUDA AYA GOTO SEIJI YASUMURA MISAO OTA AKIRA OHTSURU YASUHISA NOMURA KENICHI HATA KOUTA SUZUKI AKIHITO NAKAI MIEKO SATO SHIRO MATSUI KYOKO NAKANO MASAFUMI ABE FOR THE PREGNANCY AND BIRTH SURVEY GROUP OF THE FUKUSHIMA HEALTH MANAGEMENT SURVEY
- 出版者
- 福島医学会
- 雑誌
- FUKUSHIMA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE (ISSN:00162590)
- 巻号頁・発行日
- pp.2014-9, (Released:2014-07-15)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 8 47
Background: On 11 March 2011, the Great East Japan Earthquake followed by a powerful tsunami hit the Pacific Coast of Northeast Japan and damaged Tokyo Electric Power Company’s Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, causing a radiation hazard in Fukushima Prefecture. The objective of this report is to describe some results of a questionnaire-based pregnancy and birth survey conducted by the Radiation Medical Science Center for the Fukushima Health Management Survey.Materials and Methods: Questionnaires were sent to women who received maternal and child health handbooks from municipal officers in Fukushima Prefecture between 1 August 2010 and 31 July 2011, with the aim of reaching those who were pregnant at the time of the disaster. Mailing began 18 January 2012. Data were analyzed separately for six geographic areas in Fukushima Prefecture.Results: The total number of women meeting survey criteria was 15,972. The number of responses received to date is 9,298 (58.2%). Data from 8602 respondents were analyzed after excluding 634 invalid responses and 5 induced and 57 spontaneous abortions (less than 22 gestational weeks). The incidences of stillbirth (over 22 completed gestational weeks), preterm birth, low birth weight and congenital anomalies were 0.25%, 4.4%, 8.7% and 2.72%, respectively. These incidences are similar to recent averages elsewhere in Japan.Conclusion: Considering the pregnancy and birth survey data in aggregate, our disaster seemed to provoke no significant adverse outcomes over the whole of Fukushima prefecture. But post-disaster prenatal care and support intended for patients’ safety and security should be coupled with ongoing surveillance and rigorous data analysis.
132 0 0 0 OA 映像と音の同期―「動画先行の原則」の根拠と応用
- 著者
- 桑原 圭裕
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, pp.54-74, 2019-07-25 (Released:2019-11-19)
- 参考文献数
- 39
アニメーション制作の現場では、動画と音の同期に関して「動画は音より2フレーム前にすると仕上がりが良い」という「動画先行の原則」が語られてきた。たとえば映像と音楽の一体をテーマに 1929 年から 10 年間にわたって制作されたディズニーの短編アニメーション映画シリーズ「シリー・シンフォニー(The Silly Symphony)」の諸作品をコンピューターで解析すると、確かに時代がくだるにつれて動画を先行させるようになってきた事実を確認することができる。しかし、この動画先行の原則は、あくまで映像制作者たちの経験則に基づいており、その科学的な根拠はこれまで十分には解明されてこなかった。実写かアニメーションかを問わず映像制作の現場において、我々が映像と音を知覚する際に双方のずれを感ずるのは、3 フレーム以上、時間にしておよそ 0.1 秒以上といわれている。したがって、「動画先行の原則」について論じるためには、感覚刺激が脳に到達するまでの問題として知覚心理学の理論を援用する必要がある。本稿の目的は、このようなフレーム処理が一部の実制作の現場で採用されるようになった経緯の背景にある理論的根拠を提示するとともに、このように時間を先取りする手法が、アニメーションに限らず映像全般において、その芸術としてのダイナミズムをもたらしていることを、具体的な作例の分析を通して明らかにすることにある。
132 0 0 0 OA 「延喜式」に基づく古代乳製品蘇の再現実験とその保存性
- 著者
- 斎藤 瑠美子 勝田 啓子
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, pp.201-206, 1989-03-05 (Released:2010-03-10)
- 参考文献数
- 9
古代乳製品である蘇は製造されてから利用されるまでの期間, 少なくとも4ヵ月は保存可能な食品でなければならない. そこで蘇の製法の再現実験を試みるとともに保存性について検討するために水分活性に焦点をあて, 再現試料の妥当性を検討し, 次のような結果を得た。水分含量の異なる濃縮牛乳の水分含量と水分活性測定により等温吸着曲線と類似の曲線を得ることができた.この結果をもとに, 最も水分の少ない濃縮率 14 % のもの (S-14), エメンタールチーズの水分に近い濃縮率 18%のもの (S-18), その中間の濃縮率 16 % (S-16) を蘇の再現試料とし, 保存中の外観変化, 水分含量および水分活性の変化をビーカーを用いて検討した結果, S-16および S-18 は調製から 10 日目にカビの発生がみられ, 水分活性は 0.90 から 0.94 であった. S-14 は1カ月後もカビの発生はみられず, 水分活性は 0.80 以下を保ち続けていた. また水分含量も約 10 % と低い値を示した.一方, 素焼きの壼による保存では4ヵ月後には水分含量は 5.6 % と調製時より下降し, 水分活性は 0.65 と単分子層域の数値を示していた.したがって, 「延喜式」などの蘇の製法にもとついて保存性を重視し, 本実験のようにホルスタイン種の牛乳を用いて蘇の製法の再現を行った場合は, 牛乳を濃縮率 14 % まで加熱濃縮したもの, すなわち S-14 が古代乳製品蘇に最も類似したものであると考えられる.
- 著者
- 神田 れいみ 佐野 毅彦
- 出版者
- 日本スポーツ産業学会
- 雑誌
- スポーツ産業学研究 (ISSN:13430688)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.3_307-3_316, 2021 (Released:2021-07-24)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
Background: Due to the COVID-19 pandemic, the Japanese professional basketball's B. League postponed its regular season in late February 2020, which was then resumed in mid-March, before being suspended again only after one weekend. Eventually, the remaining regular season games (173 games in Division 1 and 117 games in Division 2) and all playoff games were cancelled. Purpose: This study mainly aimed to examine the professional basketball players' state of mental health after such unprecedented circumstances as the suspension and cancelation of league games in the middle of the season due to the pandemic of a communicable disease. Method: An electronic survey included members of the Japan Basketball Players Association in September 2020, which was 6 months after the season cancelation. The Japanese version of the K6 was used to assess players' mental health, and a K6 score ≥5 was defined as psychological distress. Results: There was a total of 108 eligible respondents. The ratio of K6≥5 (R5+) was 52% during the suspension period and 21% at 6 months after the cancelation. The R5+ was significantly higher in smaller teams than in bigger teams (odds ratio: 4.48, 95% confidence interval: 1.51-13.25). No relationship was found between R5+ and age, playing time, or the cumulative number of hometown infections. Conclusions: It was suggested that COVID-19 put half of the players at risk of psychological distress, namely, 30% acute and 20% chronic, and that the vulnerability of teams' business fundamentals affected players' mental health. Establishment of permanent counseling services for players' mental health care was recommended.
132 0 0 0 OA 災害時における耳鼻咽喉科医の役割
- 著者
- 司会: 森山 寛 シンポジスト: 大森 孝一 川瀬 哲明 佐藤 宏昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.115, no.4, pp.298-304, 2012 (Released:2012-07-03)
131 0 0 0 OA 二人の悪魔と多数の宇宙 : 量子コンピュータの起源
- 著者
- 古田 彩
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.8, pp.512-519, 2004-08-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 30
131 0 0 0 OA スギ・ヒノキ苗の成長に与える土壌水分と窒素の影響
- 著者
- 長倉 淳子 重永 英年 赤間 亮夫 高橋 正通
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本林学会大会発表データベース 第114回 日本林学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.443, 2003 (Released:2003-03-31)
スギとヒノキは日本の主要な造林樹種であり、スギは沢沿い、ヒノキは斜面中腹に植林するのが良い、とされてきた。このことは、スギは水要求度が高く、ヒノキは比較的乾燥に耐えるという樹種特性と、斜面上の水分傾度に基づいていると考えられる。しかし林地の斜面上には、水以外にも環境傾度が存在する。植物の生育に大きく影響を及ぼす窒素条件も斜面位置によって異なることが知られている。そこで本研究では、土壌水分と窒素がスギとヒノキの成長に及ぼす影響を明らかにするため、水分と窒素をそれぞれコントロールして苗木の育成試験を行った。森林総合研究所内苗畑において発芽させたスギ、ヒノキ当年生実生苗を、発芽から約1ヶ月後に赤玉土 (pH(H2O)=5.3)を培地とした1万分の1アールワグネルポットに一本ずつ移植した。約2ヶ月の予備栽培後、ポットを6群に分け、3つの窒素条件と2つの土壌水分条件(湿潤、乾燥)とを組み合わせた6つの処理を約3ヶ月行った(n=10)。窒素条件は培養液の窒素濃度を0.5、2、8mM(0.5N、2N、8N)と変えることによって設定した。窒素源には硝酸アンモニウムを用いた。水分条件は灌水間隔を変えることによって設定した。湿潤条件ではおよそ2日に一回の頻度で灌水し、育成期間中、最も乾燥した日で土壌含水比がθ=0.36(-0.005MPa)程度であった。一方乾燥条件ではθ=0.30(-0.06MPa)程度に乾燥した時点で培養液を灌水した。育成試験は自然光型育成温室で行い、温度25/20℃は、湿度は70/80%とした。育成期間中は経時的に主軸の伸長成長を測定した。処理開始から約7週間後に各処理半数の個体(n=5)について掘り取りを行い、その約5週間後に残りの個体も掘り取った。1回目の掘り取り後の約5週間は、各個体について蒸散量を重量法によって測定した。掘り取った個体は部位別の乾重、根元直径、苗高を測定した。各部位は粉砕して分析試料とした。これらの結果を用いて、個体乾重、R/S比(地下部乾重/地上部乾重)、育成期間後半の水利用効率(蒸散量あたりの乾物生産量)等を算出した。葉と根の窒素含有率をNCアナライザによって測定した。スギの乾物生産は窒素処理濃度の増加に伴って増加したが、水分条件による違いは有意でなかった。しかし、伸長成長は乾燥によって抑制された。一方、ヒノキの乾物生産は処理の影響は有意でなかった。ヒノキは伸長成長についても処理間差は明らかでなかった。スギ・ヒノキ共に乾燥処理によって相対的に根への乾物分配が増え、R/S比が増加した。R/S比は、両樹種とも乾燥処理内では窒素処理濃度が低いほど高かったが、湿潤処理内では窒素条件による違いはみられなかった。スギの水利用効率は、水分条件には影響されなかったが、窒素処理濃度の増加に伴って増加した。ヒノキの水利用効率は水分条件や窒素条件に対する一定の傾向がみられなかった。葉の窒素含有率は、両樹種とも窒素処理濃度の増加に伴って増加し、水分条件の影響は受けなかった。根の窒素含有率は両樹種とも窒素処理濃度の増加に伴って増加し、湿潤処理でやや高い傾向がみられた。スギは乾燥によって伸長成長が低下し、窒素処理濃度の減少によって乾物生産、水利用効率も減少した。一方、ヒノキは水分条件や窒素条件による伸長成長、乾物生産への影響は小さかった。これらのことから、スギはヒノキに比べ、窒素、水分条件に対する感受性が高いと考えられる。斜面下部に比べ、窒素や水分の少ない斜面上部における成長低下はヒノキよりもスギで大きいことが示唆された。
131 0 0 0 OA マッサージ後に発症した成人環軸椎回旋位固定の1例 ―慢性例&保存治療例―
- 著者
- 泉 貞有 上森 知彦 今村 寿宏 平塚 徳彦 加治 浩三 松延 知哉 河野 勤 鬼塚 俊宏 畑中 均 神宮司 誠也 岩本 幸英
- 出版者
- 西日本整形・災害外科学会
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.53-56, 2018-03-25 (Released:2018-05-21)
- 参考文献数
- 5
マッサージ後に発症した成人環軸椎回旋位固定(成人AARF)の1例を経験したので報告する.症例は37歳女性,喘息・アトピーの既往歴あり.初診時,後頚部痛を認めたが斜頚は存在せず,Xp・MRI精査するも有意な病変は無かった.初診後,整骨院で2日間,後頚部の愛護的マッサージを受けた.翌朝から斜頚を自覚し改善せず.2ヶ月後,斜頚を主訴に再診.Xp・CTにてFielding分類type 1のAARFを認めた.AARF以外は身体所見・臨床検査データ等も正常だった.入院後,頚椎持続介達牽引を施行.斜頚出現3ヶ月後,鎮静下に徒手整復を行った.オルソカラー固定するも1日で再脱臼した為,再整復しHalo vest固定を8週間施行した.現在,整復後2年が経過するもAARFの再発は認めない.成人AARFは非常に稀で,マッサージ後の発症例は報告がない.また,整復までに3ヶ月を要した慢性例であったが保存治療が可能であった.
131 0 0 0 OA VI.慢性血栓塞栓性肺高血圧症
- 著者
- 佐藤 徹
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.2, pp.234-242, 2018-02-10 (Released:2019-02-10)
- 参考文献数
- 10
慢性血栓塞栓性肺高血圧症(chronic thromboembolic pulmonary hypertension:CTEPH)は,血栓/塞栓が肺動脈の亜区域枝付近より中枢に形成され,器質化して狭窄,閉塞を起こし,肺高血圧を来たす疾患である.第4群の肺高血圧症に分類され,最も予後良好で症状等の著明な改善が得られる.急性肺塞栓症の既往があって本疾患へ発展する場合と,慢性のPHとして見つかり,鑑別診断でCTEPHと診断される症例がある.現在では,画像診断の進歩によって,ほとんどの症例が適切に確定診断される.治療法としては,1990年代後半から2010年頃までは手術療法が主体であった.2010年頃以降,バルーン肺動脈形成術(balloon pulmonary angioplasty:BPA)が日本で発展し,ほぼ同様の効果が得られるようになった.数年前には内服薬のリオシグアトが開発され,前2者には劣るが一定の効果が得られるようになった.
131 0 0 0 OA 医学生における喫煙状況と学業成績の関係
- 著者
- 川根 博司 松島 敏春
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.6, pp.379-383, 1998-12-25 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
1996年度および1997年度に, 当大学の第5学年医学生における喫煙状況と学業成績の関係を調査した.喫煙状況の調査方法としては, 呼吸器内科に臨床実習のため回ってきた際に, 各班ごとに1人ひとりの喫煙習慣について聞き取りを行った.学業成績は第5学年までストレートに進級してきたか, 1回でも留年したことがあるかで評価した.1996年度, 1997年度の男子学生の喫煙率は, ストレート組でそれぞれ48.9%, 39.1%であるのに対して, 留年組では80.6%, 65.4%と有意に高かった.女子学生においても, 1996年度, 1997年度の喫煙率はストレート組がそれぞれ8.7%, 9.1%なのに, 留年組は25.0%, 37.5%と高率を示した.喫煙状況が学業成績に関係することが示唆される.わが国において, 医学生に対するアンチスモーキング教育をもっと積極的に進めていく必要がある.
130 0 0 0 OA 「国際養子縁組に関する子の保護及び協力に関する条約」案の作成に携わって
- 著者
- 鳥居 淳子
- 出版者
- 国際女性の地位協会
- 雑誌
- 国際女性 (ISSN:0916393X)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.8, pp.131-134, 1994-11-30 (Released:2010-09-09)
130 0 0 0 OA わが国の集中治療室は適正利用されているのか
- 著者
- 内野 滋彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.141-144, 2010-04-01 (Released:2010-10-30)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 3 5
130 0 0 0 OA アメリカ合衆国においてワクチン接種が拒否される理由
- 著者
- 加藤 穣
- 出版者
- 日本医学哲学・倫理学会
- 雑誌
- 医学哲学 医学倫理 (ISSN:02896427)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.41-51, 2015-09-30 (Released:2018-02-01)
The objective of this paper is to discuss the reasons that some individuals in the United States refuse to be vaccinated, focusing on those reasons usually described as "conscientious." This paper discusses current compulsory vaccination practices and the most common categories of reasons objectors in the United States give for refusing vaccinations (on medical, religious, or philosophical grounds, the latter two of which are often described as conscientious reasons). Possible ways to handle refusals are examined from the perspectives of the three categories of refusals mentioned above, the particularities of vaccination within biomedical ethics, and public health ethics discussions. Although refusals based on divergent perceptions of risk are commonly classified as refusals for philosophical (personal) reasons, objectors in this category are trying to present medical reasons, which do not convince experts. Even if experts try to persuade the public by presenting scientific evidence, there remain fundamental difficulties in convincing objectors. Refusals for religious reasons are to a certain extent established historically, but few major religious groups nowadays explicitly refuse vaccinations per se. Refusals in this category are not necessarily plainly "religious." Certain refusals on religious grounds, including those based on repugnance for the use of components derived from aborted fetuses, can be avoided by technological advances in the medical field. Refusals based on philosophical reasons should be handled in more sensitive, individualized ways than they are now. The inquiry ventured in this paper is important for Japanese society in that it deals with general questions surrounding the contradictions between the autonomy principle, which is paramount in biomedical ethics, and the compulsory schema of public health policy, and asks whether and how the different qualities or characters of decisions regarding health care and public health should be translated into practice.
- 著者
- Yutaro Akiyama Takeshi Inagaki Shinichiro Morioka Eiji Kusano Norio Ohmagari
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- pp.1682-23, (Released:2023-04-21)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 2
A Japanese man experienced three episodes of hypovolemic shock and was diagnosed with systemic capillary leak syndrome (SCLS). He developed SCLS exacerbation 2 days after receiving a second dose of the Pfizer-BioNTech BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine, 1 year after the third episode. After fluid therapy and albumin administration, we initiated terbutaline and theophylline prophylaxis for SCLS. A literature review revealed that SCLS attacks often occur 1-2 days after the second COVID-19 vaccination. Patients with a history of SCLS should avoid COVID-19 vaccination and be carefully monitored for 1-2 days if they receive the vaccine.
130 0 0 0 OA 利根川水系片品川流域の地形発達史
- 著者
- 竹本 弘幸
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.11, pp.783-804, 1998-11-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 2
片品川流域に発達する河岸段丘についてテフラ層序に基づき調査し,堆積物の分析を通じて火山活動の影響を明らかにした.片品川流域に発達する河岸段丘は,更新世中期の砥山面(To), 15~10万年前の沼田面(Nu),11~10万年前の追貝原面(Ok),6万年前の伊閑面(Ik),5万年前の平出面(Hi),3~1.5万年前の貝野瀬1~皿面(Ka-1~皿);1.3~1万年前の低位面(L)に分類される.砥山面(To),追貝原面(Ok)は,更新世中期に赤城山の火山活動によって多量の砂礫が供給された結果,形成された堆積段丘面群である沼田画(Nu)は,赤城山の活動によって形成された堆積段丘面で,約20万年前から最終間氷期を経て約10万年前まで存続した水域(古沼田湖)に形成されたと考えられる.古沼田湖の堆積物である沼田湖成層の層厚は最大約60mに及び,上流側では沼田礫層に層相変化する.沼田礫層は礫径が大きく,礫種構成において赤城山起源の礫が卓越する.これに対して,伊閑礫層以降には赤城山起源の礫の混入率が徐々に減少し,貝野瀬I礫層以降には30%以下となる.この傾向は赤城山の火山活動と調和的である.伊閑面は,最大層厚35mの砂礫からなる堆積段丘面である.本面の形成には,断ある程度火山活動の影響も認められるが,中部日本などに広く認められる気候性の堆積段丘面と同様の成因が想定される.粒径や礫種構成から判断して,現河床への赤城山の影響はほとんど認められない.
130 0 0 0 OA 『斉民要術』に基づいた東アジアの古代乳製品の再現と同定
- 著者
- 平田 昌弘 米田 佑子 有賀 秀子 内田 健治 元島 英雅 花田 正明 河合 正人
- 出版者
- 日本酪農科学会
- 雑誌
- ミルクサイエンス (ISSN:13430289)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.9-22, 2010 (Released:2014-03-15)
- 参考文献数
- 27
The reproduction and identification of ancient dairy products in East Asia were conducted based on “SEIMINYOUJYUTU” which is the order ancient document available in East Asia and contains detailed explanation about milk processing, and then the spread pathway of these milk processing techniques into East Asia was discussed in this paper. As the results of reproduction and identification experiments, RAKU was identified as sour milk, KANRAKU could not be identified, ROKURAKU was identified as unmatured type cheese such as KHOROOT of Mongolian pastoralists and KURUT of Turki pastoralists, and SO was identified as butter and butter oil. Since some imprecise descriptions were found in SEIMINYOUJYUTU through the reproduction experiment, it was considered that Kashikyou, the author of SEIMINYOUJYUTU, was the just editor to use various texts which were gathered from different ethnic origins on milk processing and did not conduct processing milk products by themselves. The milk processing such as sour milk (RAKU) making from raw milk, butter (SO) making from sour milk (RAKU) by churning, butter oil (SO) making from butter by heating are wide spread techniques and still used among the current pastoralists in West Asia, South Asia, Central Asia and Inner Mongolia. As the comparison with components in milk products and the milk processing techniques of pastoralists in the Asian continent, it was concluded that the milk processing techniques adopted in SEIMINYOUJYUTU were mainly influenced from the pastoralists in North Asia and/or Central Asia.