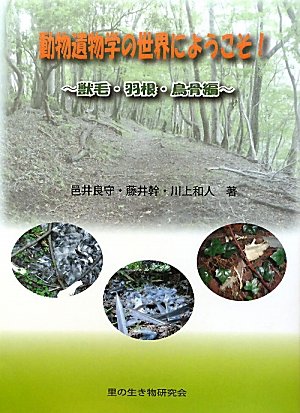- 著者
- 五三 裕太 福島 秀哉
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.3, pp.22-00025, 2023 (Released:2023-03-20)
- 参考文献数
- 37
本稿は,河川管理と地域再生の連携推進に向けた計画概念「河川文化アプローチ」の実践課題に対応するため,日本の「かわまちづくり」施策における河川管理施設の計画検討プロセスの特徴を明らかにすることを目的とし,河川利用推進を図る護岸改修が計画された肱川かわまちづくり第1期計画での整備内容の議論の特徴を分析した.研究の結果,肱川かわまちづくりの関係者の特徴を示し,協議会・ワークショップを通じた整備内容の検討経緯と各関係者の意見の関係を明らかにした.以上から,日本の「かわまちづくり」における計画検討初期段階での河川利用の状況に詳しい主体の参画,および地域住民の河川に対する関心が高いタイミングでの計画検討の展開の重要性を示し,「河川文化アプローチ」の実践展開で留意すべき関係者の特徴と地域特性を指摘した.
- 著者
- 中村 敏 久保 雅義
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 日本デザイン学会 第69回研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.110, 2022 (Released:2022-08-30)
第3セクターのいすみ鉄道は、乗客、沿線地域の人々、行政などステークホルダーの価値を高めることを使命としています。観光客誘致のために、沿線住民、行政、ステークホルダーの価値を高めることを使命としています。地域の魅力を豊かな価値に変え、提供することにより、公共交通事業から公共交流事業へ転換しています。例えば、地元の支援者に菜種の種を配り、春に花が咲くように種を蒔いたり、線路に飾り付けをしたりしています。これは「菜の花が咲く鉄道」として全国に知られ、多くの鉄道ファンや観光客を集めています。本稿ではこれらの取り組みについて調査しました。
2 0 0 0 OA あんな本・こんな本 : ボランティアによる新着案内・資料案内 No.88
- 著者
- 国立女性教育会館情報ボランティア
- 巻号頁・発行日
- 2023-03-03
2 0 0 0 OA シリア戦争とロシアの世界政策
- 著者
- 松里 公孝
- 出版者
- 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター
- 雑誌
- スラヴ研究 (ISSN:05626579)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, pp.71-105, 2021-09-08
The military interventions led by the United States and its allies in Iraq (2008), Libya (2011), and Syria (indirectly since 2011), despite their promised purposes, produced failed states and nurseries of jihadism. This dismantled the moral legitimacy of the unipolar world. Bitter lessons procured from the Libyan crisis made Russia and China veto any resolution authorizing the West’s and Gulf States’ possible military intervention in Syria at the UN Security Council. In 2012-2014, Russia’s police and security organs intentionally allowed domestic Islamists to emigrate to Syria to become jihadist fighters for the sake of domestic security on the eve of the Sochi Olympic Games. Fearing their return to Russia and the former Soviet territories after the expected seizure of Damascus by the radical Islamists, President Vladimir Putin decided (perhaps in early August 2015) to conduct air strikes on their military facilities in Syria. The essay critically examines widespread interpretations attributing Russia’s participation in the Syrian War to Putin’s domestic populism, Russian leaders’ desire to protect the Bashar Assad regime, and their attempts to overcome Russia’s diplomatic isolation after its annexation of Crimea. The main purpose of Russia’s military intervention was to change the decision making procedure of the unipolar world. Russia’s Middle East policy was benefited from its developed Middle Eastern studies inherited from the Soviet Union, whereas in the United States “Arabists” have traditionally been alienated from policy-making vis-à-vis the Near East and North Africa. Based on area specialists’ expertise, Russian policy-makers do not primordialize confessional confrontations in the Middle East, which facilitated Russia’s brokering roles between conflicting local parties. Michael Kofman calls Russia’s decision-makings on the Syrian and Middle Eastern problems a lean strategy, which, in my view, well echoed the “hedging diplomacy” pursued by Middle Eastern countries. The collaboration between Russia and the US since the beginning of Russia’s military intervention in Syria in September 2015 could not continue due to US domestic politics in 2016. Instead, the radical Islamists’ evacuation from Aleppo to Idlib was implemented by the collaboration of Russia, Turkey, and Iran. In 2017, this tri-polar collaboration developed into the Astana Process managing de-escalation zones in Idlib, East Ghouta, and North Homs, while the collaboration of the US, Russia, and Jordan in Southern Syria generated the Amman Process to control the South de-escalation zone. In 2018, three de-escalation zones, except for that of Idlib, practically functioned as mechanisms to allow radical Islamists to evacuate from there to Idlib, as a result of which these territories returned to government control. The Russian MFA is skeptical of the Astana Process and is concerned about the practical shelving of Syria’s political transition, determined by the UN Security Council Resolution No. 2254 (December 2015). For the MFA, a “multi-central dualism” privileging the participants in the Yalta-Potsdam Declarations, not just a multipolar world, should follow the declining unipolar world. Thus, dual diplomacies between the Russian MFA and military emerged, which has barely been coordinated by the hyper centralizing presidential authorities.
2 0 0 0 OA 法解釈における立法者意思の位置づけ : 裁判所と学説の協働に向けた基盤整備の試み
- 著者
- 山下 慎一 Yamashita Shin'ichi
- 出版者
- 福岡大学研究推進部
- 雑誌
- 福岡大学法学論叢 = Fukuoka University Review of Law (ISSN:04298411)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.963-999, 2021-12
2 0 0 0 近代西欧における遠隔作用概念の思想史・文化史的研究
平成24年度は、昨年度に続いて放射線の概念史・文化史的研究を行なった。とくにロシア生まれの生物学者グールヴィチ(1874-1954)とオーストリア生まれの精神分析家・社会思想家ライヒ(1897-1957)の生体放射概念についての論考「生体放射の歴史」を『生物学史研究』に寄稿した。ライヒのいわゆるオルゴンエネルギー説については平成23年度以来の調査を継続し、新たな成果は「宗教と精神療法研究会」(吉永進一・舞鶴高専准教授主催)で報告した。この研究会では神秘思想、宗教思想の研究者との交流により、<科学と神秘>という本研究課題のなかでも重要な位置を占める問題系についての議論が深まった。また、平成24年度は西欧の遠隔作用概念についての概念史的背景をなす「不可秤量流体」についての調査・分析をおこなった。その西欧的文脈についての調査から派生した近代日本における不可秤量流体概念の歴史を、さきのグールヴィチ/ライヒの生体放射概念と比較しつつ、明治期の医師・明石博高(1839-1910)と昭和初期の霊術家・松本道別(1872-1942)を主要な対象として研究した。その成果は「人体、電気、放射能―明石博高と松本道別にみる不可秤量流体の概念」として『近代日本研究』に投稿され、査読を経て掲載された。この論考は単に明石と松本の思想を紹介・分析するにとどまらず、不可秤量流体概念を通じた19世紀~20世紀初頭の目・欧・米の比較科学文化史、さらに<近代日本科学>、すなわち<近代における><日本で><科学をいとなむ>とはそもそもいかなる歴史的現象なのかを問う議論を含む長大な論考となった。研究最終年度としていくつかのテーマが調査・分析のなかばで残ったが、他方で、当初、西欧近代をその射程としていた当研究は、日本近代の史料をもコーパスとすることで、より重層的・多面的なものへと拡大した。
2 0 0 0 OA 二つのアイアース像
- 著者
- 木曽 明子
- 出版者
- 京都大学西洋古典研究会
- 雑誌
- 西洋古典論集 (ISSN:02897113)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.1-13, 1991-12-20
この論文は国立情報学研究所の学術雑誌公開支援事業により電子化されました。
2 0 0 0 動物遺物学の世界にようこそ! : 獣毛・羽根・鳥骨編
- 著者
- 邑井良守 藤井幹 川上和人著
- 出版者
- 築地書館(発売)
- 巻号頁・発行日
- 2011
2 0 0 0 人骨および人骨付着昆虫遺体からみた古墳時代モガリの研究
まず、記紀にあらわれるモガリは期間に長短があること、また、古墳主体部の墓墳周辺の存在する柱穴が「殯屋」であるこという見解が一部で定説扱いされていることを確認した。このうち、古墳主体部周辺の柱穴については、柱穴が墓墳に切られた例もあり、墓墳内に石棺を囲んで掘られた例もあることから、造墓前や埋葬前の「結界」である場合があると考えた。この他にも、古墳築造時の作業用の覆い屋であるとの指摘もあることから、少なくとも「殯屋」は否定されることが明らかになった。次に、松山市葉佐池古墳1号石室出土人骨付着のハエ蛹を実態顕微鏡下で観察した。その結果、ハエの種はニクバエ属とヒメクロバエ属のものであることが明らかとなった。この両者のハエの生態が、前者は死後すぐに死体にたかり産卵する一般的なハエであるのに対して、後者は死体が腐敗した後にたかり産卵する種であることから、葉佐池古墳1号石室出土人骨は、死後少なくとも1週間前後は、ハエが活動するような明かりのある場所に置かれており、埋葬されていなかったことが明らかとなった。また、えびの市島内地下式横穴墓において、埋葬後腹部に発生したガスによって骨盤腔外に排出された便が検出されたことから、ガスが腹腔内に充満する期間、おそらくは2〜3週間の間にはモガリを終えて埋葬されたことがうかがえた。以上から、古墳時代のモガリは、古墳上で行われたものではなく、1週間前後以上で2〜3週間以内の間行われるのが通常であった可能性が高く、香川県宮ヶ尾古墳線刻壁画のような小屋状の施設が、これらの所見に最もふさわしい「殯屋」のあり方であると考えられる。また、記紀に記載されたモガリ期間の長さは、死者の階層の高さに基づく墳墓築造と葬送儀礼の長さを反映したものと考えられる。
2 0 0 0 OA 遺伝学から見たモチ性穀類の起源:モチの文化誌とモチの遺伝子
2 0 0 0 OA 差分進化に基づくアーム型倒立振子の非線形準最適レギュレータ設計と実機実験による検証
- 著者
- 吉崎 亮介 川田 昌克 伊藤 稔
- 出版者
- 一般社団法人 システム制御情報学会
- 雑誌
- システム制御情報学会論文誌 (ISSN:13425668)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.41-49, 2015-02-15 (Released:2015-05-15)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 3 3
The arm-driven inverted pendulum is an unstable and nonlinear system. Therefore, the feedback controller designed by the linear control theory cannot be stabilized in the wide range. This paper discusses a nonlinear control design based on the optimal regulator problem. However, it is difficult to get the analysis solution for this problem. In this paper, DE (Differential Evolution) and PSO (Particle Swarm Optimization) methods are used to get an approximate solution. In addition to the first order feedback gain designed by the linear optimal regulator, we design the higher order gain. Finally, the validity of our nonlinear controller designed by DE is verified through some experiments.
2 0 0 0 OA 中国人民武装警察部隊に関する研究ー武警部隊と解放軍の関係と将来像一
2 0 0 0 OA リファンピシンとの相互作用でステロイド効果の減弱が認められたSLEの1例
- 著者
- 伊東 秀夫 藤平 隆司 原田 進 城戸 優光 加治木 章 中島 康秀 黒岩 昭夫
- 出版者
- THE JAPANESE SOCIETY FOR TB AND NTM
- 雑誌
- 結核 (ISSN:00229776)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.303-308, 1984-04-15 (Released:2011-05-24)
- 参考文献数
- 5
Accelerated inactivation of corticosteroids following rifampicin therapy has beenrecognized. We observed nonresponsiveness to prednisolone treatment during rifampicinadministration in a case of systemic lupus erythematosus with diffuse alveolitis andconcomitant apical tuberculosis.A 51 year-old woman complained in September 1980, of polyarthralgia and butterflyerythema of the face. From typical clinical manifestations and positive serological tests, systemic lupus erythematosus was diagnosed and treatment with prednisolone was startedat a local hospital. To prevent exacerbation of old apical tuberculosis, isoniazid 0.2 gdaily was also administered. Good response was obtained for an initial few months butdyspnea, diffuse pulmonary infiltrates appeared following prednisolone decrement.She was transfered to our hospital in August 1981. On admission, she had a few skinulcers in bilateral hands and pigmentations over the surface of shoulder, elbow and knee.Velcro rales were audible over the lung base. No lymphadenopathy was detected.Laboratory examination revealed positive RA test, antinuclear and anti-DNA antibody. Thyroid test and microsome test were also positive, but LE test, RNP antibody, SMantibody were negative. C4, CH50 were normal but C3 was decreased. Chest X-Prevealed diffuse reticular shadows in bilateral middle and lower lung field and nodularconsolidation in right apical region. Although tubercle bacilli was negative in sputum, exacerbation of tuberculosis were suspected radiologically. Histological specimen obtained by transbronchial lung biopsy from the left lung showed mild interstitial thickening of alveoli with mononuclear cell infiltration.Prednisolone was increased from daily dose of 5mg to 80mg and 450mg of rifampicin, 1, 000mg of ethambutol were added, but no response was obtained. In December 1981, prednisolone was altered to equivalent dose of betamethasone but minimal improvementwas observed.After quitting rifampicin on January 1982, dramatic improvement in symptoms, laboratory data and chest roentgenogram was achieved. Although pharmacokineticstudies were not performed, we feel that the circumstantial evidence suggests strongly toincreased metabolism of prednisolone by rifampicin-induced microsomal enzymes.
2 0 0 0 IR 「伝統」の多義性 -イタリア・サルデーニヤ島の音楽文化を例に-
- 著者
- 金光 真理子
- 出版者
- 横浜国立大学
- 雑誌
- 横浜国立大学教育人間科学部紀要. II, 人文科学 (ISSN:1344462X)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.13-22, 2010-02
2 0 0 0 OA リベラル期におけるウィーン市政の発展
- 著者
- 山之内 克子
- 出版者
- 東欧史研究会
- 雑誌
- 東欧史研究 (ISSN:03866904)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.76-96, 1991 (Released:2018-12-01)
- 著者
- 三重野 由加
- 出版者
- 教育出版センタ-
- 雑誌
- 解釈 (ISSN:04496361)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.10, pp.5-13, 1997-10
2 0 0 0 OA 鳥類における協同繁殖様式の多様性
- 著者
- 江口 和洋
- 出版者
- The Ornithological Society of Japan
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.1-22, 2005 (Released:2007-09-28)
- 参考文献数
- 132
- 被引用文献数
- 2 1
長期個体群動態研究の拡大と遺伝学的血縁解析手法の導入により,鳥類の協同繁殖の研究はこの30年間ほどで大きく発展し,多くの研究成果が発表されている.現在,協同繁殖が知られている鳥類は350種(全鳥類の3.9%)を超える.協同繁殖の起源と維持に関わる生態的要因と系統の問題,様式の多様性,手伝い行動の利益の問題を中心に最近の研究成果を紹介し,これからの研究を展望した.協同繁殖種は特定の分類群に特によく出現する.種間比較研究は,生活史は協同繁殖が出現する素因となり,生態的要因はそのような分類群内での協同繁殖の出現を促進することを示唆する.一方,系統学的研究は,協同繁殖は祖先的であり,系統学的歴史が協同繁殖の起源や維持を説明する確かな手段であると示唆している.協同繁殖種の配偶様式,群れ内メンバー間の血縁関係,ヘルパーの手伝い行動などのあり方は,従来考えられていたよりも多様であることが明らかになりつつある.群れメンバーはそれぞれ異なる利益を得ていると考えられている.非血縁ヘルパーが以前考えられていたよりも多く,非繁殖ヘルパーは普遍的ではない.ヘルパーの手伝い行動は群れ内で一様ではない.ヘルパーの存在,手伝い行動そのものが繁殖成功の向上に結びつかない例も少なくない.これらの事実は,手伝い行動における直接的利益の重要性を示唆している.ヘルパーが繁殖し,直接的利益を得ていることも稀ではない.これからの研究に不可欠なものは,長期間の個体群動態研究と遺伝学的手法を用いた性判定や血縁判定である.国外の協同繁殖種と近縁な非協同繁殖種の研究も重要である.
- 著者
- Takayuki Yamada Susumu Ohwada
- 出版者
- The Kitakanto Medical Society
- 雑誌
- 北関東医学 (ISSN:13432826)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.1, pp.87-89, 2022-02-01 (Released:2022-03-18)
- 参考文献数
- 8
Axillary lymphadenopathy is a local reaction to mRNA COVID-19 vaccination. A 19-year-old healthy woman presented with a mass in the axilla diagnosed by ultrasonography as a result of COVID-19 vaccine-induced hyperreactive lymphadenopathy. After two weeks, ultrasonography revealed that the lymph node had shrunk and that the blood flow signal in the hilum had disappeared. This case describes the typical course of isolated unilateral axillary lymphadenopathy after BNT162b2 COVID-19 vaccination. Short-term ultrasound is sufficient for monitoring unilateral axillary lymphadenopathy following recent COVID-19 vaccination, avoiding unnecessary radiation injury and axillary lymph node biopsies.
- 著者
- 水上 雅晴
- 出版者
- 中央大学文学部
- 雑誌
- 文学部紀要 哲学 (ISSN:05296803)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, pp.41-73, 2021-03-10
- 著者
- 高岡 健 岡田 俊 小坂 浩隆 野間 俊一 森岡 由起子 吉川 徹
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.628-664, 2016-08-01 (Released:2017-05-17)
- 参考文献数
- 3