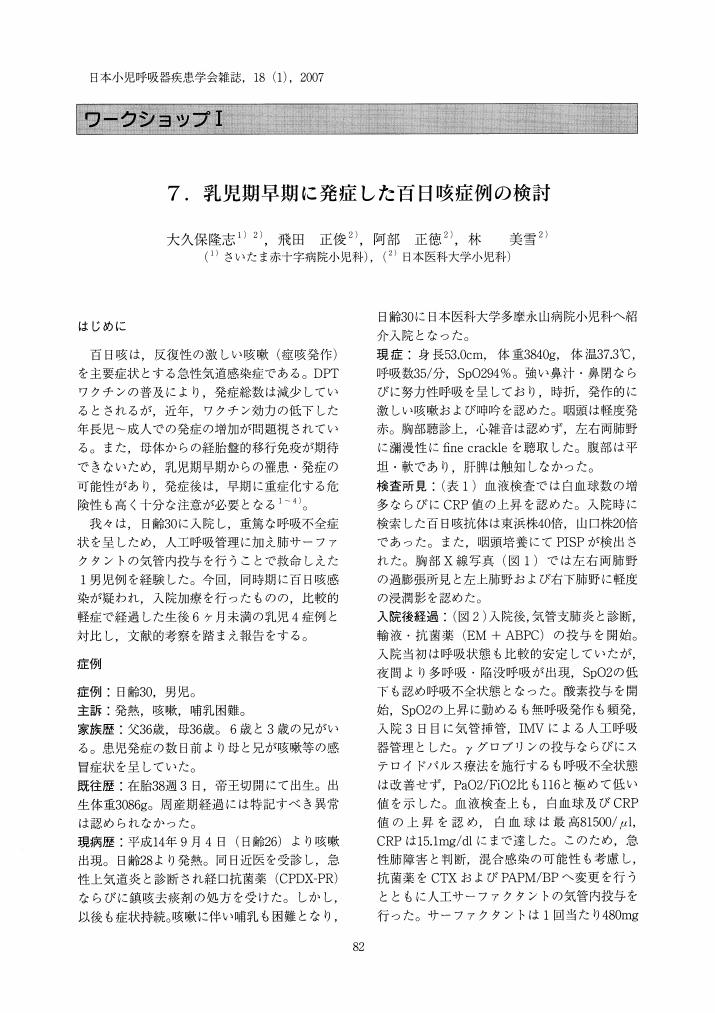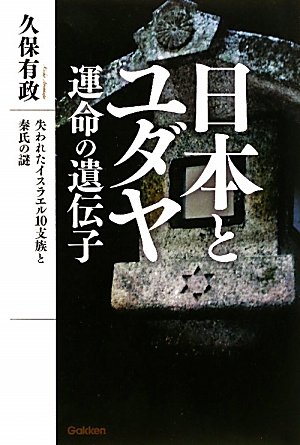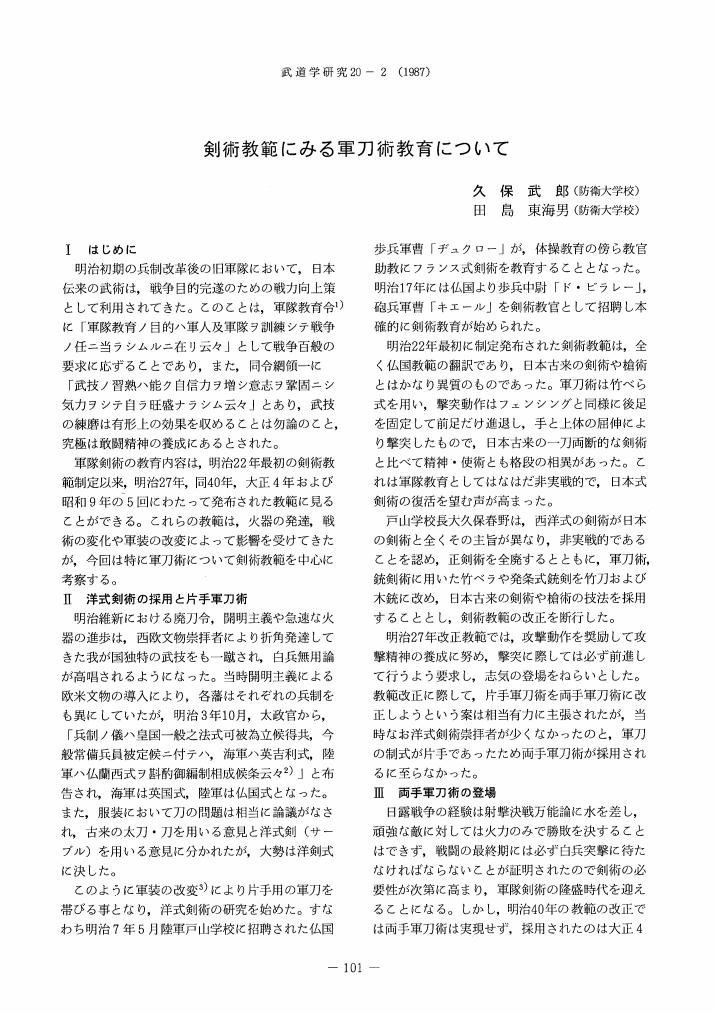6 0 0 0 OA 真性半陰陽の1例
- 著者
- 佐々木 秀平 久保 隆 大堀 勉
- 出版者
- 泌尿器科紀要刊行会
- 雑誌
- 泌尿器科紀要 (ISSN:00181994)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.115-120, 1975-02
A six-year-old person reared as a girl came to us with enlargement of the clitoris. Various examinations revealed true hermaphroditism with karyotype of 46XX, positive sex chromation, ovotestis on the right side and ovary on the left. The ovotestis was surgically removed and the clitoris was amputated.
6 0 0 0 老いと<ことば>:ブログ・テキストから測る老化
- 著者
- 荒牧 英治 久保 圭 四方 朱子
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 研究報告情報基礎とアクセス技術(IFAT)
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, no.23, pp.1-6, 2014-07-25
言語能力は人生における経験の結晶であり,加齢によって損なわれることがないとされる.しかし,その一方で,文法能力など,一部の能力の加齢による低下が示されることもある.このように,老化と言語能力の関係については不明な点が多い.この原因は,次の 2 つによるところが大きい.まず,研究対象である高齢者から大規模なデータを得るのが困難であること.次に,言語はさまざまな能力の総体であり,調査ごとに測っている言語能力が異なることである.そこで,本研究では,Web 上の文章を利用する.まず,50 代から 80 代の高齢者や小中学生,第二言語習得者,認知症患者のブログや作文を集めた.また,測定に関しては,語彙に関するものや構文に関するものなど,さまざまな指標を用いた.この結果,高齢者は,使う言葉の種類が減る可能性があること,さらに,難易度の高い言葉から使用頻度が減ることが明らかになった.この知見を応用することによって,老化や認知症の早期発見の可能性があり,今後の応用が期待される.Preceding study claims that one's language abilities develop over long period of time and improve with age. On the other hand, some study reports that some parts of language abilities, such as grammatical ability, show some decrease in elder people. Since one's language ability is often shown as the aggregation of multiple human abilities, it is difficult to solely extract his/her language ability out of his/her written texts. This study, thus, analyzes texts by using multiple linguistic measures. The corpora cover school students (children attending primary to junior high school, age 6 to 15 years old), elders (age 50 to over 80 years old), Japanese as the Second Language learners, and a dementia patient (Alzheimer type). As a result, this study shows that the lexical richness decreases, and difficult vocabularies tend to be especially lost from elders. This study also displays the possibility of detecting dementia in its early stage.
6 0 0 0 OA 「不安障害」から「不安症」への病名変更案について
- 著者
- 清水 栄司 佐々木 司 鈴木 伸一 端詰 勝敬 山中 学 貝谷 久宣 久保木 富房
- 出版者
- 日本不安障害学会
- 雑誌
- 不安障害研究 (ISSN:18835619)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.116-121, 2014-03-31 (Released:2014-05-02)
- 被引用文献数
- 1
日本不安障害学会では,日本精神神経学会精神科用語検討委員会(日本精神神経学会,日本うつ病学会,日本精神科診断学会と連携した,精神科病名検討連絡会)からの依頼を受け,不安障害病名検討ワーキング・グループを組織し,DSM-5のドラフトから,不安障害に関連したカテゴリーの翻訳病名(案)を作成いたしました。ご存知のように,厚生労働省は,地域医療の基本方針となる医療計画に盛り込むべき疾病として指定してきた,がん,脳卒中,急性心筋梗塞,糖尿病の四大疾病に,新たに精神疾患を加えて「五大疾病」とする方針を決め,多くの都道府県で2013年度以降の医療計画に反映される予定です。精神疾患に関しては,「統合失調症」や「認知症」のように,common diseasesとして,人口に膾炙するような,馴染みやすい新病名への変更が行われてきております。うつ病も,「大うつ病性障害」という病名ではなく,「うつ病」という言葉で,社会に広く認知されております。そこで,DSM-5への変更を機に,従来の「不安障害」という旧病名を,「不安症」という新名称に変更したいと考えております。従来診断名である,「不安神経症」から,「神経」をとって,「不安症」となって短縮されているので,一般に馴染みやすいと考えます。ただし,日本精神神経学会での移行期間を考え,カッコ書きで,旧病名を併記する病名変更「不安症(不安障害)」とすることを検討しております。そのほかにもDSM-5になって変更追加された病名もあるため,翻訳病名(案)(PDFファイル)を作成しました。翻訳病名(案)については,今後も,日本精神神経学会精神科用語検討委員会の中での話し合いが進められていく予定です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
6 0 0 0 OA 「家族の多様化」論再考
- 著者
- 久保田 裕之
- 出版者
- 日本家族社会学会
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.78-90, 2009-04-30 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 3 2 2
「家族の多様化」論の前提となる,家族に関する選択可能性の増大という認識は,家族が依然として選択不可能な部分において個人の生存・生活を保障している点からみれば一面的である。法・制度に規定された家族規範は,現代においても,婚姻をモデルとした性的親密性・血縁者のケア・居住における生活の共同というニーズの束として複合的に定義されており,個人の主観的な家族定義もまた,この家族概念をレトリカルに参照せざるを得ない。さらに,貧弱な家族外福祉を背景として,主観的家族定義における親密性の重点化により,親密性と生存・生活の乖離が生じることが現代の「家族の危機」の一因となっている。そこで,政策単位としても分析単位としても複合的な家族概念を分節化し,従来の家族の枠組みを超えて議論していくことが重要である。家族概念を分節化することで,家族概念の単なる拡張を超えて,家族研究の対象と意義を拡大することができる。
6 0 0 0 OA 蘭学資料研究会発足の思い出
- 著者
- 大久保利謙
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 参考書誌研究 (ISSN:18849997)
- 巻号頁・発行日
- no.38, 1990-09-29
6 0 0 0 年賀状分析による拡大パーソナルネットワークの研究
1.本研究の目的は,年賀状をデータベースとして事例調査を実施し,拡大パーソナルネットワーク(親しい人びとだけでなく知人とのネットワークを含むもの)を捉えること,また標本調査を実施し,親しい人びとのみに限定されたネットワークの内部構造を捉えることの二つである。平成11年度〜平成12年度にかけて事例調査と標本調査を実施し,その成果を報告書にまとめている。2.事例調査は,3地点でそれぞれ異なる研究課題のもとに実施された。三鷹市では,コミュニティ・センター運営委員を対象者として,地域社会への関与の様相と拡大パーソナルネットワークとの連関を捉えることに,福岡市では,中央区と西区の高齢者を対象者としてライフコースに伴う拡大パーソナルネットワークの変容過程を捉えることに課題がおかれ,かなりの達成をみた。徳島市では住民運動のリーダーを対象者として署名集めの資源としてのネットワークの動員過程を明らかにすることとし,多くの興味深い知見をえることができた。3.平成11年度に実施したプリテストの結果から,回答者の挙げる親しい人5名の相互関係を問う質問項目において,個別面接調査と郵送調査とで,回答の精度に差がみられないことが明らかとなった。そこで平成12年度は,東京都市区全域から8市区をランダムに抽出し,対象者総計2000名に対する郵送調査を実施した。8市区は,文京区・品川区・大田区・世田谷区・八王子市・青梅市・東村山市・多摩市であり,各市区の人口比にしたがって2000名を配分した。有効回収票は656票(回収率33.2%)であった。データクリーング後,集計解析を実施し,ネットワーク構造を規定する要因群の析出,地位達成とネットワーク構造との関連などをテーマとして報告書を作成した。報告書のI部はこの成果が,II部は事例調査の成果が載せられている。
- 著者
- 釜﨑 大志郎 大田尾 浩 八谷 瑞紀 久保 温子 大川 裕行 藤原 和彦 坂本 飛鳥 下木原 俊 韓 侊熙 丸田 道雄 田平 隆行
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年療法学会
- 雑誌
- 日本老年療法学会誌 (ISSN:2436908X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.1-8, 2023-01-06 (Released:2023-01-07)
- 参考文献数
- 31
【目的】本研究の目的は,プレフレイルからロバストへの改善に関連する基本チェックリスト(kihon checklist: KCL)の各領域の特徴を検討することとした。【方法】対象は,半年に1回の体力測定会に参加した地域在住中高年者とした。改訂日本版cardiovascular health study基準(改訂版J-CHS)でプレフレイルの有無を評価し,半年後に同様の評価を行った。ベースラインから半年後にプレフレイルからロバストに改善した群と変化がなかった非改善群の2群に分けた。また,KCLで生活に関連する機能の評価を行った。改善群と非改善群を従属変数,KCLの各領域の点数を独立変数とした2項ロジスティック回帰分析を行った。また,有意な関連を示したKCLの下位項目に回答した割合を比較し,特徴を検討した。【結果】分析対象者は,地域在住中高年者60名(71.9±7.8歳)であった。2項ロジスティック回帰分析の結果,プレフレイルからロバストへの改善の有無にはKCLの社会的孤立(OR: 0.04, 95%CI: 0.00-0.74, p=0.031)が関連することが明らかになった。また,ロバストに改善した群は,社会的孤立の中でも週に1回以上外出している者が有意に多かった。【結論】プレフレイルの地域在住中高年者へ外出を促すことで,ロバストへ改善する可能性が示唆された。
5 0 0 0 OA 細菌(群)の日本語名称に関する考察と提案
5 0 0 0 OA 乳児期早期に発症した百日咳症例の検討
- 著者
- 大久保 隆志 飛田 正俊 阿部 正徳 林 美雪
- 出版者
- 日本小児呼吸器疾患学会
- 雑誌
- 日本小児呼吸器疾患学会雑誌 (ISSN:09183876)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.82-87, 2007-06-30 (Released:2011-01-25)
- 参考文献数
- 11
- 著者
- 久保有政著
- 出版者
- 学研マーケティング (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2011
5 0 0 0 OA 灌漑用ため池におけるオオクチバス・ブルーギルの下流域への拡散
- 著者
- 藤本 泰文 久保田 龍二 進東 健太郎 高橋 清孝
- 出版者
- 応用生態工学会
- 雑誌
- 応用生態工学 (ISSN:13443755)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.213-219, 2012 (Released:2013-04-24)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 7 3
オオクチバスとブルーギルは,日本各地に移殖された外来魚で,ため池はその主要な生息場所となっている.本研究では,オオクチバスおよびブルーギルのため池からの用排水路を通じた移出状況を調査した.私たちは宮城県北部に位置する照越ため池の用水路と排水路に,ため池から流出した魚類を捕獲するトラップを設置した.4 月下旬から 7 月下旬の調査期間中,これらの外来魚は用水路と排水路の両方から何回も流出しており,その流出のタイミングは,それぞれの水路の通水期間に限られていた.体長 125 mm の成魚のブルーギルも流出していた.ため池の魚類生息数を池干しによって調査した結果,ため池に生息する外来魚のうち,オオクチバスは 4. 0%,ブルーギルは 7. 1%が流出していたことが示された.外来魚の流出は繰り返し生じ,生息個体数の数%が流出していたことから,外来魚の流出は稀な現象ではなく一般的な現象である可能性が高い.この結果は,ため池が下流域への外来魚供給源となっていることを示す.周辺地域への被害拡大を防ぐためにも,ため池の外来魚の駆除は重要だと言える.
5 0 0 0 OA 東京の台地と低地
- 著者
- 久保 純子
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- Geographical review of Japan, Series B (ISSN:02896001)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.73-87, 1990-06-30 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 6 5
東京首部の地形は更新世の台地と完新世の低地とからなっている。台地は最終間氷期の海底面と最終氷期の河成面に由来し,その表面は後期更新世を通じて富士火山・箱根火山などにより供給された風成テフラに覆われている。台地には台地上に水源をもつ開析谷が分布する。これらの谷のなかには,台地表面の離水時に現われた名残川に由来し,その起源が最終氷期まで遡るものがある。 低地は最終氷期末に形成された谷が後氷期海進を受け,日本有数の大河である利根川水系により形成されたもので,厚い軟弱地盤を形成する。完新世後期の東京低地の形成過程は,従来ほとんど行なわれなかった考古歴史資料と微地形分布との関係の検討により明らかにされるであろう。17世紀以降になると,河道の改修,海岸部の埋め立て等の人工改変が大規模に行なわるようになった。 東京の台地と低地の地形には,変動帯の特色としての関東造盆地運動や火山活動に加え,ユースタティックな海水準変動の影響があらわれている。そして近年は人類による改変が最も大きなファクターとなっている。
- 著者
- 井畑 真太朗 山口 智 光藤 尚 小内 愛 堀部 豪 久保 亜抄子 山元 敏正
- 出版者
- 一般社団法人 日本頭痛学会
- 雑誌
- 日本頭痛学会誌 (ISSN:13456547)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.600-603, 2023 (Released:2023-04-20)
- 参考文献数
- 15
症例 : 47歳,女性.主訴 : 頭痛.現病歴 : X-1年1月当院脳神経内科を受診,同年5月よりエレヌマブの臨床試験に参加.X年5月臨床試験終了後より片頭痛の日数が増加したため,X年12月鍼外来紹介受診.片頭痛予防と頸肩部の筋緊張緩和を目的に頸肩部に位置する経穴に週1回鍼治療を実施.評価は頭痛ダイアリーを用いた.鍼治療前には1ヵ月の片頭痛日数14日,エレトリプタン服薬数14錠であったが,鍼治療3ヵ月後の片頭痛日数4日,エレトリプタン5錠に減少.鍼治療はcalcitonin gene-related peptide (CGRP) 関連製剤使用後に増加した片頭痛日数とトリプタン服薬数を減少させる可能性がある.
5 0 0 0 OA 剣術教範にみる軍刀術教育について
5 0 0 0 OA 尿中薬物簡易スクリーニングキット2製品の比較検討
- 著者
- 杉村 朋子 原 健二 久保 真一 西田 武司 弓削 理絵 石倉 宏恭
- 出版者
- 一般社団法人 日本救急医学会
- 雑誌
- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.12, pp.842-850, 2012-12-15 (Released:2013-01-17)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 2 4
尿試料からの簡易薬物スクリーニング検査を実施している3次救命救急センターや高度救命救急センターでは,これまでTriage DOA(シスメックス社)が使用されてきた。2010年11月にはこれに加えて,尿検査キットINSTANT-VIEW M-I(TFB社)が国内販売となった。そこで当施設において薬物分析結果に基づいた両キットの比較検討を行った。対象は2010年12月28日から2011年8月30日までの約8か月間で,救急初療時に検査が必要と判断し,採尿可能であった症例を対象とした。Triage DOAおよびINSTANT-VIEW M-Iの検査を施行し,1項目でも陽性を認めた45症例に対し,当大学法医学教室でガスクロマトグラフ質量分析装置(Gas Chromatograph Mass Spectrometer,以下GC/MS)および液体クロマトグラフ質量分析装置(Liquid Chromatography - tandem Mass Spectrometry,以下LC/MS/MS)を用いた薬物分析を実施した。比較検討の結果,INSTANT-VIEW M-Iの方が操作は簡便で所要時間も短時間であった。しかし,結果の判定はTriage DOAの方が簡単であった。薬物検査の性能に関しては,感度はINSTANT-VIEW M-Iが高く,特異度はTriage DOAが高い傾向にあった。両キットで三環系抗うつ薬とベンゾジアゼピン系の偽陽性率が高く,数例で偽陰性も認めた。簡易スクリーニング検査には偽陽性(偽陰性)があるということを理解したうえで用いることが重要である。
- 著者
- 矢久保 修嗣 並木 隆雄 伊藤 美千穂 星野 卓之 奥見 裕邦 天野 陽介 津田 篤太郎 東郷 俊宏 山口 孝二郎 和辻 直
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.167-174, 2019 (Released:2019-12-20)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
国際疾病分類(ICD)は疾病,傷害及び死因の統計を国際比較するため世界保健機関(WHO)から勧告される統計分類である。この国際疾病分類第11改訂(ICD-11)のimplementation version が2018年6月18日に全世界に向けてリリースされた。これに伝統医学分類が新たに加えられた。ICD の概要を示すとともにICD-11の改訂の過程やICD-11伝統医学分類の課題をまとめる。ICD-11は2019年5月の世界保健総会で採択される。我が国がICD-11を導入し,実際の発効までには,翻訳作業や周知期間なども必要であるためまだ猶予が必要となるが,国内で漢方医学の診断用語も分類のひとつとして使用できることが期待される。このICD-11伝統医学分類を活用することにより,漢方医学を含む伝統医学の有用性などが示されることも期待され,ICD に伝統医学が加わる意義は大きいものと考えられる。
5 0 0 0 OA 買物意識尺度の開発:公募型Web調査における妥当性検証
- 著者
- 大久保 暢俊 鷹阪 龍太 山田 一成
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.76-84, 2021-12-25 (Released:2021-12-25)
- 参考文献数
- 20
The purpose of this study is to develop a Japanese version of the Shopping Consciousness Scale (SCS) and to examine its construct validity. Factor analyses of data by 520 nonprobability online panels in a Web survey (in 2016) confirmed a hypothesized two-factor structure (the hedonic and utilitarian), and each subscale showed high internal consistency. Correlation analyses of data by 568 nonprobability online panels in a Web survey (in 2018) confirmed high test-retest reliability for each subscale. Furthermore, the correlations of each subscale with other measures (window shopping and frugality) provided support for the construct validity of each subscale. In many cases, these relationships were not affected by variables such as gender, household income, and discretionary income. In addition, we examined sociodemographics and personality predictors for each subscale. These factors were not as strongly related to these predictors as expected. Finally, the implications of these findings and the usefulness of SCS for online consumer behavior research are discussed.
5 0 0 0 OA 頂点捕食者が存在する生態系から見る北海道へオオカミ再導入の可能性
- 著者
- 大久保 響 吉村 珠美 山内 大樹 星野 仏方
- 出版者
- 酪農学園大学
- 雑誌
- 酪農学園大学紀要. 自然科学編 (ISSN:21870500)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.25-39, 2022-10
On northern Japanʼs Hokkaido Island, wolves (Canis lupus) have been extinct for 100 years. As a result, the sika deer (Cervus nippon) population has increased in recent years, causing damage to agriculture and to the forestry and fisheries industries and leading to an increase in train and automobile traffic accidents. On the other hand, wolves live in Mongolia where stock-farming is the main livelihood. Yet nomadic livestock herders have coexisted with wolves for centuries. The main reason for this successful coexistence in the Mongolian steppes can be attributed to the nomadsʼ understanding of wolf ecology. This understanding has led to the development of ways for humans and apex predators to interact with one another in this ecosystem. We also discovered that livestock damage caused by wolves in Mongolia is minimal because there is sufficient prey (e.g., red deer) and because the wolves and their prey do not live in proximity to humans. We note there has never been a documented attack by a wolf on a human in Mongolia. Our investigation of the habitat of wolves in Hustai National Park (HNP) in Mongolia gave us a base of information to assess the challenges that might occur if wolves are reintroduced into Hokkaido. Based on our habitat assessment of the island, we were able to estimate the carrying capacity of wolves on Hokkaido. We concluded that Hokkaido Island can successfully support approximately 1300 wolves with a prey base of up to 100,000 sika deer.
5 0 0 0 OA 民間企業によるイネ育種への挑戦と今後の課題
5 0 0 0 OA 低炭水化物食の理解と実践 〜栄養指導のためのナラティブ・レビュー〜
- 著者
- 深津 章子 宮本 佳代子 諸澤 美里 大久保 研之 池本 真二
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養士会
- 雑誌
- 日本栄養士会雑誌 (ISSN:00136492)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.12, pp.673-681, 2022 (Released:2022-12-01)
- 参考文献数
- 53
低炭水化物食への注目が続く中、その効果と安全性を担保する栄養指導の実践方法は、十分に確立されていない。本ナラティブ・レビューは、低炭水化物食に関する研究結果を見る要点を整理するとともに、低炭水化物食の功罪を概論した上で栄養指導の方法論を提言する。低炭水化物食の研究で用いられる食事の炭水化物量には幅があり、比較対照には種々の食事が用いられる。また、対象者の脱落や食事の遵守度の低下は食事療法の評価を難しくする。低炭水化物食の体重減少や糖尿病管理への効果は、長期的には低脂質食等他の食事に比べて差異は見られない。低炭水化物食は高脂質、高たんぱく質、食塩過多になりやすく、動脈硬化性疾患の危険性が懸念される。食生活に取り入れやすい利点を生かすためには、炭水化物の摂取量を示した上で、植物性たんぱく質や多価不飽和脂肪酸を炭水化物の代替としたり、減塩したりする等の丁寧な指導が不可欠である。