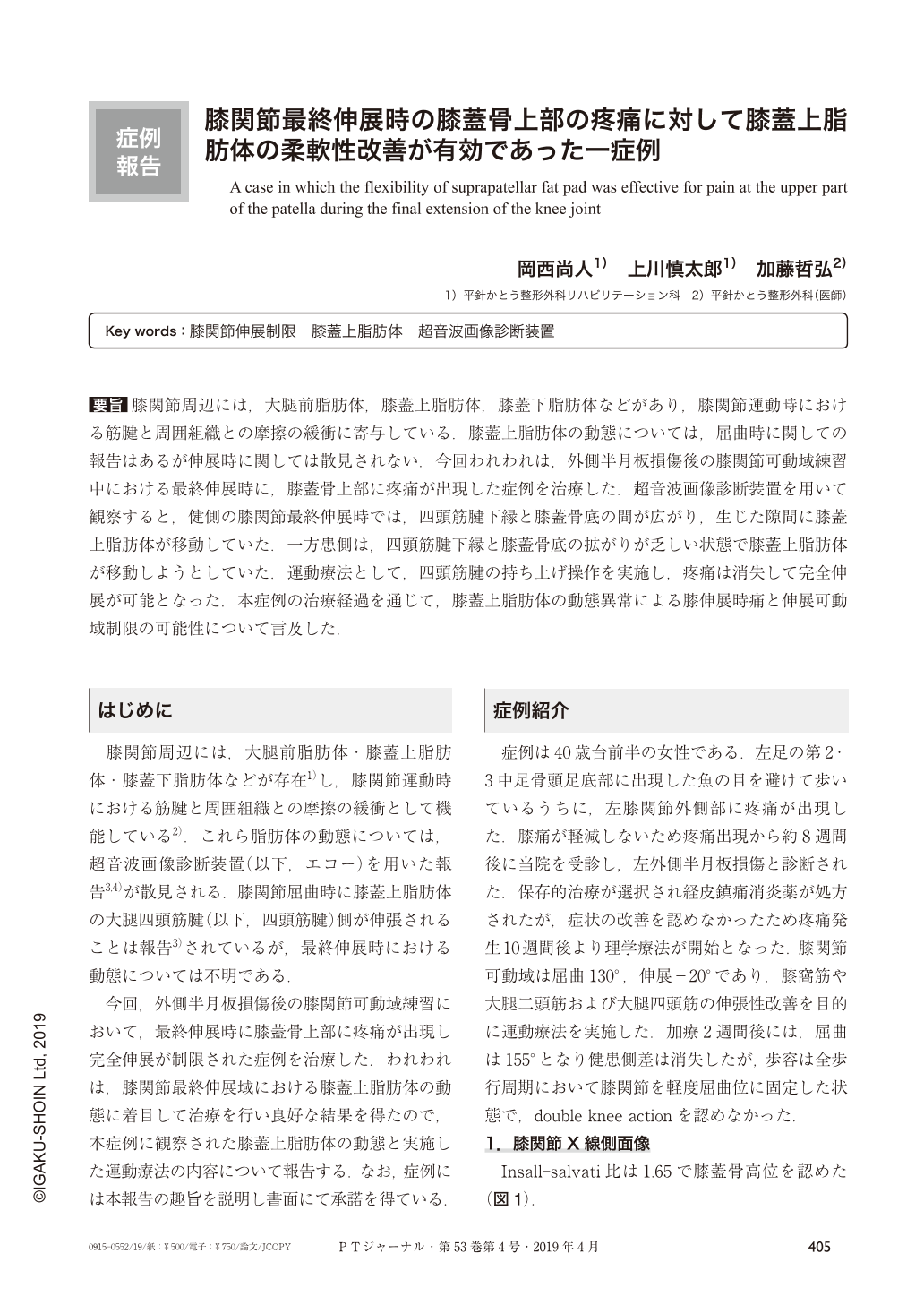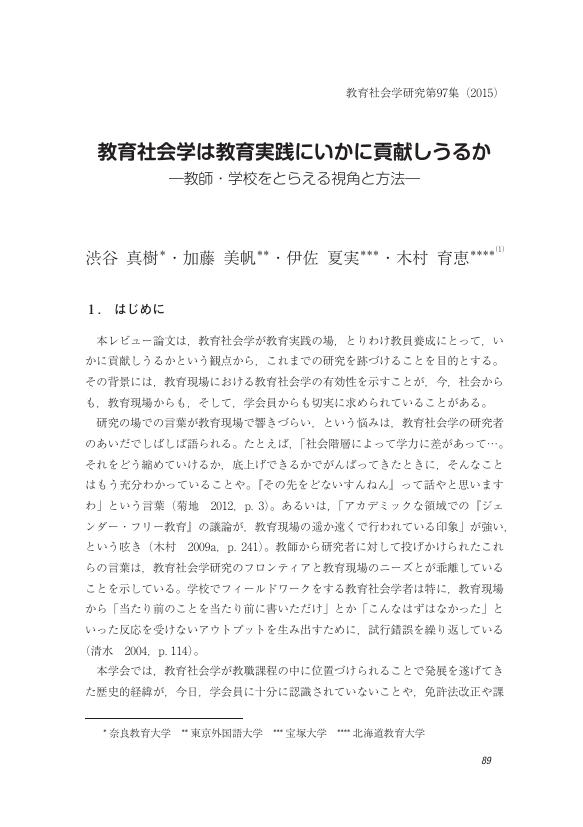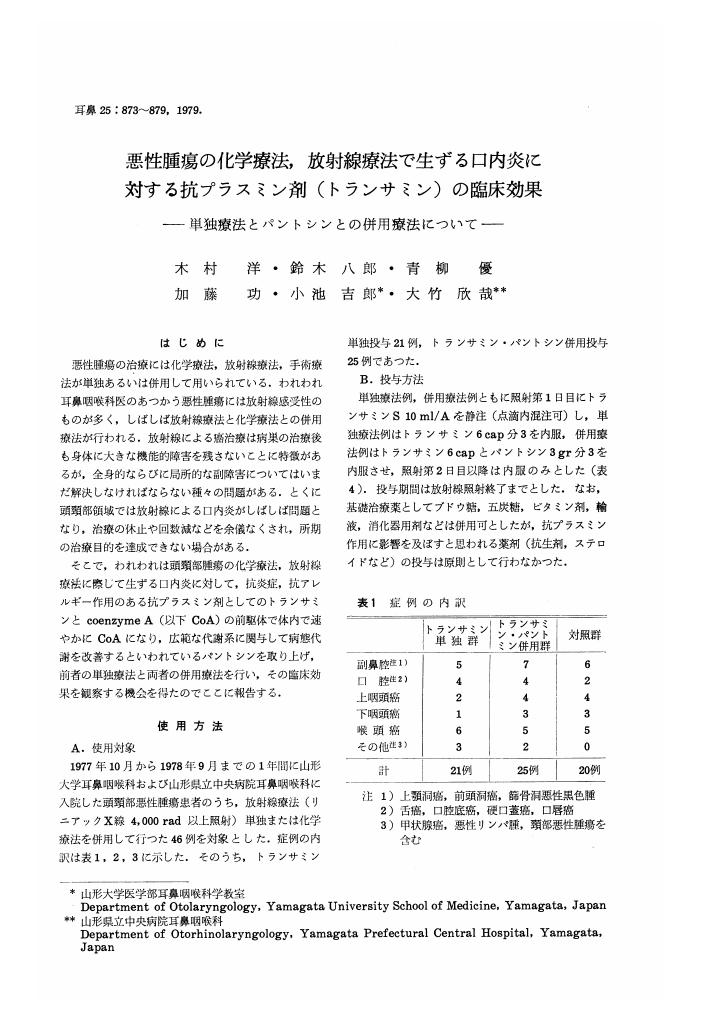- 著者
- 月本 一郎 塙 嘉之 高久 史麿 浅野 茂隆 上田 一博 土田 昌宏 佐藤 武幸 大平 睦郎 星 順隆 西平 浩一 中畑 龍俊 今宿 晋作 秋山 祐一 櫻井 實 宮崎 澄雄 堺 薫 内海 治郎 黒梅 恭芳 古川 利温 山本 圭子 関根 勇夫 麦島 秀雄 矢田 純一 中沢 真平 小出 亮 加藤 俊一 金子 隆 松山 秀介 堀部 敬三 小西 省三郎 多和 昭雄 筒井 孟 高上 洋一 田坂 英子 植田 浩司
- 出版者
- 一般社団法人 日本血液学会
- 雑誌
- 臨床血液 (ISSN:04851439)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.10, pp.1647-1655, 1990 (Released:2009-03-12)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 3
Recombinant human granulocyte colony-stimulating factor (rG-CSF), produced by Chinese hamster ovary cells, was administered in 69 chemotherapy-induced neutropenic pediatric patients (pts) with malignant tumors. Each pt received two cycles of the same chemotherapy and had neutropenia with absolute neutrophil counts (ANC) <500/μl in the first cycle. Initiating 72 hours after termination of chemotherapy in the second cycle, rG-CSF (2 μg/kg/day) was given subcutaneously or intravenously to each pt for 10 days. rG-CSF significantly increased ANC at nadir; 72±14 vs. 206±40/μl (data in the first cycle vs. data in the second cycle, respectively), and reduced the period of neutropenia with ANC<500/μl; 9.7±0.6 vs. 5.1±0.6 days, and the period for restoration to ANC≥1,000/μl after initiation of chemotherapy; 25.5±0.6 vs. 17.5±0.9 days. rG-CSF did not affect other components of peripheral blood. The number of days with fever ≥38°C was significantly reduced by rG-CSF treatment. Neck pain and lumbago were observed in one pt, polakysuria in one pt, and elevation of the serum levels of LDH and uric acid in one pt, however these were mild to moderate, transient, and resolved without any specific treatment. We concluded that rG-CSF was effective in neutropenia induced by intensive chemotherapy for malignant tumors without any serious side effects.
要旨 膝関節周辺には,大腿前脂肪体,膝蓋上脂肪体,膝蓋下脂肪体などがあり,膝関節運動時における筋腱と周囲組織との摩擦の緩衝に寄与している.膝蓋上脂肪体の動態については,屈曲時に関しての報告はあるが伸展時に関しては散見されない.今回われわれは,外側半月板損傷後の膝関節可動域練習中における最終伸展時に,膝蓋骨上部に疼痛が出現した症例を治療した.超音波画像診断装置を用いて観察すると,健側の膝関節最終伸展時では,四頭筋腱下縁と膝蓋骨底の間が広がり,生じた隙間に膝蓋上脂肪体が移動していた.一方患側は,四頭筋腱下縁と膝蓋骨底の拡がりが乏しい状態で膝蓋上脂肪体が移動しようとしていた.運動療法として,四頭筋腱の持ち上げ操作を実施し,疼痛は消失して完全伸展が可能となった.本症例の治療経過を通じて,膝蓋上脂肪体の動態異常による膝伸展時痛と伸展可動域制限の可能性について言及した.
1 0 0 0 OA 乾燥性皮膚疾患に対するスクワランの有用性, 皮膚刺激性および保湿性についての検討
- 著者
- 谷井 司 加藤 順子 八代 典子 新藤 季佐 幸野 健 濱田 稔夫 山口 武津雄
- 出版者
- Meeting of Osaka Dermatological Association
- 雑誌
- 皮膚 (ISSN:00181390)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.155-163, 1991 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
乾燥性皮膚疾患に対するスクワランの有用性, 皮膚刺激性, 保湿性について検討した。貼布試験は73例全例陰性であった。使用試験では乾皮症, 手湿疹に有用で, 炎症を伴わないアトピー性皮膚炎にも有効であったが, 炎症を伴っている場合には慎重に使用することが望ましいと思われた。症状別では皮膚の乾燥に特に有効であった。この理由としては, 保湿能の検討より角層水分の貯留作用によるものと思われた。以上よりスクワランは, 適切に使用すれば安全性が高く, ベタつくという不快感がほとんどなく, 使用感も良好で, 乾燥性皮膚疾息の治療に有用と思われた。
1 0 0 0 OA 戦後型公企業制度の誕生 ──政府系金融機関の名称と制度設計──
- 著者
- 加藤 龍蘭 Ryura Kato
- 雑誌
- 国際基督教大学学報. II-B, 社会科学ジャーナル = The Journal of Social Science
- 巻号頁・発行日
- no.65, pp.27-52, 2008-03-31
- 著者
- 加藤 有希子
- 出版者
- 三田哲學會
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:05632099)
- 巻号頁・発行日
- vol.132, pp.281-307, 2014-03
Daily life interests, such as the desire for health and happiness, have been excluded from major avant-garde art since the 18th century. As Peter Bürger properly stated, if art is identified with daily life practices, the sanctity of art would be spoiled; however, if art completely avoids life's interests, art can be suffocating. After World War II, some movements in deconstructing art—the 1960s counterculture, Art Therapy beginning in the mid-1940s and actually flourishing from the 1990s onwards, and De-Art in the 2000s led by Kumakura Takaaki—have tried to fuse art and life, although their attempts have not always been successful. In a sense, such a synthesis of art and life is one of the main themes of post-War art history.As one pioneer in avant-gardes, Neo-Impressionists have tried to synthesize art and life. This article focuses on Neo-Impressionism in the late 19th century. Having detailed the fact that Neo-Impressionists practiced color therapy, homeopathy, and hydro therapy, the study clarifies that their hygienic practices were firmly related to their theory of painting. Themetizing the concept of "equilibrium"and the divergent character of color as a medium, I reveal how the Neo-Impressionists were exceptionally able to integrate art and life.特集 : 論集 美学・芸術学 : 美・芸術・感性をめぐる知のスパイラル(旋回)
1 0 0 0 IR 大学生の心理学観の構造-2-心理学者との比較
- 著者
- 東 正訓 橋本 尚子 加藤 徹 藤本 忠明
- 出版者
- 追手門学院大学文学部
- 雑誌
- 追手門学院大学文学部紀要 (ISSN:03898695)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.p1-13, 1994
1 0 0 0 OA 責任追及性に基づく認証のレベル
- 著者
- 菅 知之 米倉 昭利 加藤 寛之
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP)
- 巻号頁・発行日
- vol.2001, no.57(2001-EIP-012), pp.15-19, 2001-06-01
ネット社会の発展は目覚しく、今後の可能性に大きな期待がかけられているが、一方ではハッカーや成りすまし等の不安要素も抱えている。非対面・非書面が特徴のネット社会は無責任社会になる潜在的な可能性を秘めているが、無責任社会には善良な市民は入ってこなくなり健全な発展は望めないので、責任追及性の確保が今後の発展のキーポイントである。ネット社会での活動は電子データとして記録されるため、ばらばらに存在する個人情報が容易に収集することができ、その結果として起こり得るプライバシー侵害はネット社会の発展阻害要因となる。責任追及性とプライバシー保護とのバランスこそがネット社会の発展の鍵であり、そのためにはリアル社会との接点を確保して責任追及性を備えた匿名性の導入が有名である。
1 0 0 0 OA 教育社会学は教育実践にいかに貢献しうるか
1 0 0 0 OA 自然災害と関連分野におけるレジリエンス,脆弱性の定義について
- 著者
- 塩崎 由人 加藤 孝明
- 出版者
- 東京大学生産技術研究所
- 雑誌
- 生産研究 (ISSN:0037105X)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.643-646, 2012-07-01 (Released:2013-02-23)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2
近年,気候変動や自然災害等の環境変化に関して,「レジリエンス」,「脆弱性」という用語が頻繁に使われている.これらの用語は環境変化に対するシステムの変化や挙動を表す概念であるが,その定義が多様であるため混乱をまねく恐れがある.本論では,英語圏の自然災害などの学術分野において発達してきたこれらの概念について,その発達の経緯と多様な定義の整理を行った.そして,「曝露」や「感応性」など,レジリエンス,脆弱性の概念に関する要素によって,環境変化に対するシステムの変化や挙動を説明できることを示した.[本要旨はPDFには含まれない]
1 0 0 0 OA 先天性難聴者による青年期以降の人工内耳装用における音楽聴取
- 著者
- 大金 さや香 原島 恒夫 小渕 千絵 佐藤 友貴 城間 将江 野口 佳裕 榎本 千江子 加藤 秀敏 加我 君孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本聴覚医学会
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.5, pp.508, 2019-10-30 (Released:2019-11-28)
1 0 0 0 OA 仙腸関節の加齢性変化について
- 著者
- 西 啓太 鶴崎 俊哉 弦本 敏行 加藤 克知
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.41 Suppl. No.2 (第49回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0835, 2014 (Released:2014-05-09)
【はじめに,目的】臨床場面において,腰痛などの骨盤帯領域の機能障害は,腰椎・骨盤・股関節などの複数領域の機能障害が複雑に組み合わさっている場合が多い。そのため,近年では腰椎・骨盤・股関節を複合体としてとらえ,総合的に評価治療を行うことが重要と考えられている。諸家の報告では,Hip-spine syndromeのように股関節と腰椎の機能障害に関連性があるという報告は多いが,仙腸関節と他関節の機能障害の関連性を報告している研究は殆どみられない。そこで今回,腸骨耳状面の年齢推定法を仙腸関節の加齢性変化を示す指標として用い,他関節の加齢性変化との関係を調べた。本研究の目的は,仙腸関節の加齢性変化が股関節などの他関節と関連性があるのかを明らかにすることである。【方法】死亡時年齢が記録されている男性晒骨100体(平均年齢56.5歳:19-83歳)の左右腸骨耳状面(200側)を肉眼で観察し,Buckberryら及びIgarashiらによる年齢推定法に準じて関節面の年齢推定を行った。2法から得られた推定年齢値の平均をその個体における仙腸関節の『関節年齢』とし,実年齢と関節年齢から年齢校正値を算出した。次に,関節年齢と年齢校正値の差を,腸骨耳状面の加齢性変化の程度を表す『Gap』と定義した。他関節の加齢性変化の指標として,同一の骨標本を使用したTsurumoto(2013)らの先行研究から股関節(200側)と膝関節(102側)の関節周囲骨棘指数のデータを引用した。さらに,耳状面形態に個体によって多様性がみられたため,耳状面の『くびれ率』を定義し測定を行った。これは,耳状面の長腕と短腕の関節面の最後方を直線で結び,この直線と耳状面の前下縁と後上縁の最長距離を測定し,後上縁までの距離から前下縁までの距離を除した値のことである。2つの年齢推定法の妥当性を検討するために,実年齢との相関性を調査した。また,くびれ率と年齢,耳状面Gap,股関節骨棘指数との関連を検討した。さらに,耳状面形態が関節の加齢性変化に及ぼす影響を考慮し,くびれ率の大きさが仙腸関節と股関節の加齢性変化の関連性を検討した。統計学的分析はMicrosoft Excel 2010の分析ツールを用いて行った。有意水準は5%とした。【倫理的配慮,説明と同意】本研究で用いた骨標本は,長崎大学医学部生の解剖実習のために同意を得て献体されたご遺体から取り出した標本である。本研究では骨標本に直接手を加えず,肉眼観察を行うために使用したため,倫理的な問題はない。【結果】2つの年齢推定法ともに,実年齢との間に高い正の相関がみられた。2法の平均推定年齢も実年齢との高い正の相関を示した。耳状面Gapと股関節骨棘指数との間には中等度の正の相関を示し,膝関節との間には弱い正の相関を示した。くびれ率に関しては,耳状面Gapおよび股関節骨棘指数との間に相関はみられなかった。さらに,くびれ率の分布の90%領域中の個体群において,耳状面Gapと股関節骨棘指数の間にr=0.40の相関を示した。くびれ率の大きさで仙腸関節と股関節の加齢性変化の関連性をみたところ,くびれ率が小さいほど仙腸関節と股関節の加齢性変化の相関が強くなる傾向がみられた。【考察】Vleemingらは骨盤帯の関節安定戦略に異常をきたした場合,仙腸関節に破綻をきたし,退行変性を進行させてしまう可能性があると述べている。本研究で行った腸骨耳状面の加齢性変化の評価より,仙腸関節における安定機構の変化が他の関節に影響を及ぼす可能性があることが示唆された。本研究結果より,仙腸関節と股関節の加齢性変化の間に相関がみられた。腰痛患者に見られる骨盤帯のアライメント不良や諸筋の活動変化により,関節にストレスが加わり,その加齢性変化が進行する可能性があると考えられる。本研究からは,股関節と仙腸関節のどちらが原因で加齢性変化が生じるのかは知ることが出来ないが,腰椎・骨盤・股関節のアライメント異常などによる安定戦略の変化により,股関節と仙腸関節の両方に加齢性変化が生じる可能性が示唆された。また,仙腸関節面のくびれ率が小さいほど仙腸関節と股関節の加齢性変化の相関が強くなる傾向がみられた。このことより,仙腸関節の形状がHip-spine syndromeのような腰椎・骨盤・股関節領域の複合的な病態の生じやすさに影響を及ぼしている可能性があることが示唆された。【理学療法学研究としての意義】本研究結果は,骨盤とその周囲の運動器疾患に対する考察を助けるデータとなり,さらに,腰椎・骨盤・股関節領域における運動器疾患の予防を行う上でも有用なデータになると考える。
1 0 0 0 OA Acute autonomic neuropathy と思われる1例
- 著者
- 安田 武司 伊藤 多美子 横井 喜久代 毛利 篤子 安藤 恒三郎 加藤 友義 杢野 謙次
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経学会
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:00290831)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.3, pp.218-223, 1984 (Released:2011-08-10)
- 参考文献数
- 12
腹痛, 発熱を主訴として発症し, 対光反射, 輻輳反射の消失, 瞳孔の散大, 深部反射の消失, 筋力低下などの神経学的所見を認めるとともに, 皮膚乾燥, 涙液分泌低下, 尿失禁, 便秘, 食道アカラジアなどの自律神経系, 特に副交感神経系の広範な障害をきたした7歳女児例を報告した.経過中, 間質性肺炎, 両側気胸, ADH分泌異常症候群 (SIADH) を合併したが, ステロイドホルモンの投与により改善傾向を示し, 約1年後には, ほぼ完全な寛解状態となった.本例は, 髄液の蛋白細胞解離, 末梢運動神経障害を認め, ギランバレー症候群を合併していると考えられるが, 自律神経症状が前景を呈しており, acuteautonomic neuropathyと考えられた
- 著者
- 浅井 明倫 杉浦 健之 藤掛 数馬 加藤 利奈 太田 晴子 祖父江 和哉
- 出版者
- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会
- 雑誌
- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)
- 巻号頁・発行日
- pp.18-0044, (Released:2019-12-20)
- 参考文献数
- 5
- 著者
- 加藤 和歳
- 出版者
- 記録管理学会
- 雑誌
- レコード・マネジメント : 記録管理学会誌 = Records management : journal of the Records Management Society of Japan (ISSN:09154787)
- 巻号頁・発行日
- no.77, pp.27-53, 2019-12
1 0 0 0 OA 垂直的骨量の不足した上顎骨に矯正治療を用いてインプラント体埋入を行った2症例
- 著者
- 勝沼 孝臣 渡沼 敏夫 加藤 義治 関 啓介 金子 貴広 村上 洋 清水 礼子 久野 敏行
- 出版者
- 公益社団法人 日本口腔インプラント学会
- 雑誌
- 日本口腔インプラント学会誌 (ISSN:09146695)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.168-174, 2015-06-30 (Released:2015-08-01)
- 参考文献数
- 13
The first requirement of implant treatment is to obtain sufficient bone quantity in the implant placement area. We have developed a method to obtain new bone and bone apposition nonsurgically using minor tooth movement (MTM) before insertion of implants. Here, we report two cases treated using this approach that both had satisfactory outcomes. Case 1 was a 46-year-old woman with insufficient vertical bone quantity in the area where the maxillary right first molar was lost. There was some distance between the root apex of the second premolar and maxillary sinus. In this case, the maxillary second premolar was distally moved to the area of tooth loss using MTM. The period of orthodontic treatment was 13 months. An implant was inserted in the original area in which the second premolar had been present. The superstructure was then placed on the implant. Four years have passed since this treatment and the outcome is satisfactory. Case 2 was a 29-year-old man with insufficient vertical bone quantity in the area where the maxillary right first molar had existed. The root apex of the second premolar touched the maxillary sinus. The maxillary second premolar was distally moved using MTM. The period of orthodontic treatment was 10 months. An implant was inserted into the newly made space and the superstructure was placed on the implant. Metamorphosis was observed in the remodeled bone wall of the maxillary sinus attached to the distal part of the moved maxillary second premolar. After three years and two months, the outcome is favorable. These two cases show that the MTM approach makes it possible to obtain new bone and bone apposition and to insert an implant in the newly made space in the original bone.
1 0 0 0 OA 対談 日本語をどのように〈うたう〉か
- 著者
- 林 光 米川 敏子 加藤 富美子 澤田 篤子
- 出版者
- 日本音楽教育学会
- 雑誌
- 音楽教育実践ジャーナル (ISSN:18809901)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.6-17, 2010 (Released:2017-05-30)
- 著者
- 打田 佑人 小池 春樹 小栗 卓也 加藤 秀紀 湯浅 浩之 三竹 重久
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.5, pp.339-344, 2015 (Released:2015-05-30)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 3 3
53歳男性.頭痛と発熱が10日間遷延後,尿閉が出現し,髄液異常をみとめたため,髄膜炎・尿閉症候群と診断.入院後,血清IgM抗サイトメガロウィルス抗体陽性が判明し,ガンシクロビル点滴治療を施行したところ,髄膜炎症状は軽快した.一方で,尿閉は改善せず,高度で多彩な自律神経症状が重畳した.自律神経機能検査では節前線維の障害を示唆する所見を呈し,末梢神経伝導検査ではF波の出現率の低下をみとめた.免疫療法を試みたところ,とくにステロイド治療が奏効した.抗ガングリオシド抗体の中でIgM抗GM1抗体およびIgM抗GM2抗体が陽性であり,Guillain-Barré症候群との異同を考える上で貴重な症例と考えられた.
1 0 0 0 飛騨高山の憑きもの俗信牛蒡種
■発症・由来・伝承 牛蒡種の牛蒡とは植物のゴボウで,牛蒡種をゴンボダネと読む。牛薄種を端的に言えば,「牛蒡種筋と呼ばれる家系があって,その筋の者に憎悪や羨望などの感情を持たれると,牛蒡種の生霊が憑いて精神異常を来す」とされる憑きもの俗信である。牛蒡種は憑かせる人・憑くもの・憑かれる人の構造が明確で,憑依体が狐つきなどの動物ではなく,生霊である点が特徴である。岐阜県飛騨地方(この中心が高山市)にほぼ特有の迷信であるが,飛騨周辺の地方にも若干存在する。 牛蒡種の発症・由来・伝承といった民俗学的側面については須田の研究3)を紹介しておく。牛蒡種俗信の所在地は飛騨山脈の岐阜県側登山口に一致する。人の生霊が憑くという思想が生じたのは平安時代であり,この時代は山岳宗教の修験者が競って深山幽谷に入り,厳しい修練をし,修験道が隆盛を極めた時代でもある。穂高,槍岳,双六岳,笠岳,乗鞍などの峻嶮高峰のそびえる飛騨山脈のふもとは修験者の格好の修業の場であったに違いない。飛騨地方における中世の神社仏閣の調査によれば,山岳宗教である天台宗と真言宗の寺院,および修験道と関連する白山神社は,飛騨山脈を源とするいくつかの川の流域に数多く存在している。この修験者の宗教的なまじないや祈祷によって,その地域の住民が強い情動体験を受け,祈祷性精神病に類似した特異な精神状態を惹起させられたことは想像に難くない。これを体験した地域の住民は,修験者に対し,畏怖,尊敬,嫌悪などの複雑で無気味な感情を抱き,特異な力を持つ人たちと感じるようになった。そして,修験者が村落に定着した場合,彼らの子孫は特異な力を持ったその筋の者とされ,牛蒡種筋の家系が成立したものと思われる。俗信の発症はおおむね平安時代であろうと推定される。この俗信は飛騨地方の地理文化的条件(四方を山で囲まれ,閉鎖的な部落が多いということのほかに,例えば,上宝村は今なお原始宗教の影響が残り,民俗学的研究の宝庫とされる風土)と,飛騨人の迷信を信じやすい性格傾向(例えば,1966年の出生率が丙午迷信によって全国平均より大幅に減少)などがあって今日まで伝承された。なお,牛蒡種の名称は修験者同士の呼称である「御坊」に由来し,それが植物の牛蒡(その種は人によく付着し,付着したら除去しにくい特性を持つ)に付会されて牛蒡種になった説が最も説得力がある。
1 0 0 0 OA 現代政治学におけるメタ理論の必要性―批判的実在論が問いかけるもの―
- 著者
- 加藤 雅俊
- 出版者
- 横浜法学会
- 雑誌
- 横浜法学 (ISSN:21881766)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.97-145, 2017-12-25