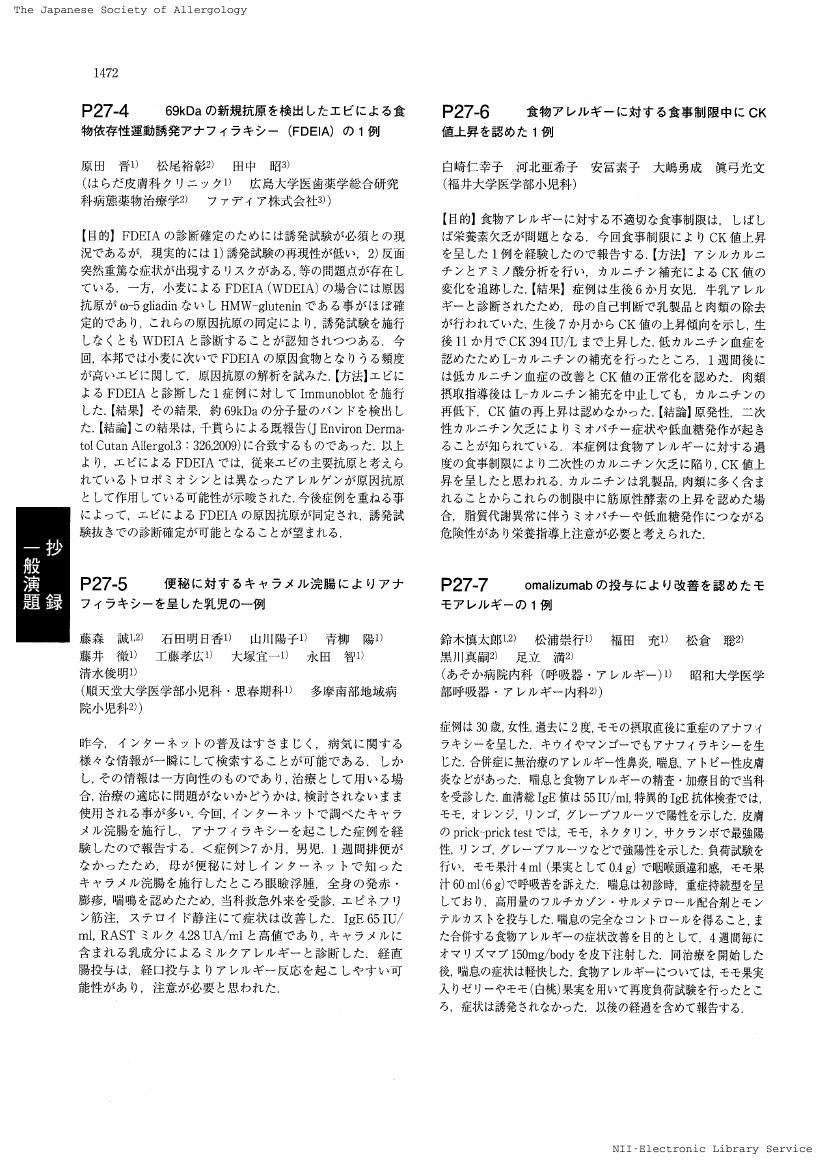264 0 0 0 OA インフルエンザ脳症の最新の治療
- 著者
- 新島 新一
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経学会
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:00290831)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3, pp.160, 2015 (Released:2015-11-20)
264 0 0 0 OA 日本の医学界におけるジェンダー平等について
- 著者
- 安川 康介 野村 恭子
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.275-283, 2014-08-25 (Released:2016-05-16)
- 参考文献数
- 66
- 被引用文献数
- 3
近年, 女性医師の勤務継続支援に関しては活発に議論されるようになってきたが,ジェンダー平等へ向けたより包括的な議論は不十分である.本稿では,日本の医学界におけるジェンダー不平等をめぐる現況について概観し,ジェンダー平等に向けた課題について考察する.医学界のジェンダー不平等の主な原因として,性役割分業を前提とした医師の長時間・不規則な勤務体制,女性医師の家庭と仕事の二重負担,女性に対する固定観念・偏見・差別等があげられる.女性であることが,医師として不利にならない労働環境を構築するために,ジェンダー平等へ向けた取組みが必要である.
264 0 0 0 OA 諸外国における国家研究公正システム(3) 各国における研究不正の特徴と国家研究公正システム構築の論点
- 著者
- 松澤 孝明
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.12, pp.852-870, 2014-03-01 (Released:2014-03-01)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1
わが国における研究不正の低減に向けた検討に資するため,すでに2回にわたり諸外国の国家研究公正システム(NRIS)の特徴とその背景を比較・分析した。今回は最終報告として,各国における研究不正の定義や情報公開の考え方を整理するとともに,各国の研究公正当局が取り扱う研究不正事案の年平均件数を推定した。また,不正の特徴を比較・分析した。最後に,3回の報告全体を通じた考察を行った。わが国の研究不正の特徴は,欧米先進国と共通性があるが,一方で,アジア諸国の特徴との類似性も一部に見られた。各国のNRIS構築の取り組みには,わが国にふさわしいNRISを構築していくうえで参考になるものが多い。
263 0 0 0 OA 駄洒落の面白さにおける要因の分析
- 著者
- 谷津 元樹 荒木 健治
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 第32回ファジィシステムシンポジウム
- 巻号頁・発行日
- pp.237-242, 2016 (Released:2019-03-15)
263 0 0 0 OA 新潟平野部に多発する胆嚢がんの原因について
- 著者
- 山本 正治
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.6, pp.795-803, 1996-03-30 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 15
Geographical distribution of standardized mortality ratio (SMR) for biliary tract cancer (BTC) showed a characteristic clustering pattern; high in the northeastern regions and low in the southwestern regions of Japan. Among the 47 prefectures (corresponding to counties in the U. S.) with high SMRs, Niigata Prefecture has been the highest in both sexes for the last two decades. It was found that the cities, towns and villages in Niigata where the mortalities from BTC were high were correspondent with rice producing areas.In addition, it was revealed that the sources of tap water in the cities with high SMRs in Niigata were commonly big rivers, whereas in those with low SMRs they were either reservoirs located in the mountains, underground water or small river originating from the mountains. Based on these findings, the contamination of tap water by agricultural chemicals form paddy fields was suspected as a cause of the high mortality from BTC. Among several chemicals examined, diphenylether herbicide, chlornitrofen (CNP) and its derivative (CNP-amino) were detected high in tap water in the cities with higher SMRs and they seem to be related to the occurrence of BTC, particularly of female gallbladder cancer.
262 0 0 0 OA 瀬田貞二訳『指輪物語』における地名の訳し分け ――中つ国・イングランド・日本――
- 著者
- 川野 芽生
- 出版者
- 日本比較文学会
- 雑誌
- 比較文学 (ISSN:04408039)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.22-36, 2017-03-31 (Released:2020-04-01)
The Japanese translation of The Lord of the Rings by Seta Teiji is criticized to be too ‘Japanesque' and incoherent as to his choice of word used to translate the place-names in the text. He has translated some place-names by sense, but others phonetically. However, this incoherence and Japanization is deliberate. Tolkien, the author of The Lord of the Rings, has set a strict rule about nomenclature in the text. He has used multiple languages to name places in the Middle-earth, his invented world. This multilingualism shows the variety of peoples living in the world. He has written a guide to the names in this novel for the use of translators of this novel and has said in it that names consisted of present-day English vocabulary should be translated into the language of translation according to their meaning and the others should be left unchanged. The apparent incoherency of Seta's translation has come from his following this rule. In addition, he has distinguished names to be translated word-forword from names to be modified to give them an appearance of actual Japanese names. He has translated nonliterally the tongue of Hobbits, through whose eyes the events are reported, thus making readers feel that they are familiar, while Common Speech has been translated literally. Though Hobbiton in the Middle-earth can be identified with England, Tolkien gives greater importance to the universality of his imaginary world than to the Englishness of it. Seta's Japanization of the world is a response to Tolkien's choice.
- 著者
- Harumi Okuyama Yoichi Fujii Atsushi Ikemoto
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Journal of Health Science (ISSN:13449702)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.157-177, 2000-06-01 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 183
- 被引用文献数
- 16 27
Classic lipid nutrition for the prevention of chronic, elderly-onset diseases was apparently established before 1960, assuming that hypercholesterolemia is the major risk factor and that raising the polyunsaturated/saturated (P/S) ratio of dietary fatty acids is hypocholesterolemic. However, the hypocholesterolemic effect of linoleic acid (LA) was found to be transient. Furthermore, hypercholesterolemia itself is unlikely to be a serious risk factor for diseases in the elderly because serum cholesterol level is positively correlated with longevity. Instead, a high n-6/n-3 ratio of dietary fatty acids was found to increase thrombotic tendency, decrease peripheral blood flow and lead to persistent inflammation, which was proposed to be the major risk factor for atherosclerosis and related diseases. Based on animal experiments and epidemiological studies, we recommend a reduction in the intake of LA from a current value of >6 en% to half, and a reduced n-6/n-3 ratio from the current value of >4 to 2. Simply decreasing LA intake would produce the recommended n-6 and n-3 fatty acid balance in Japan due to the typical Japanese diet, but both decreasing the intake of LA and increasing that of n-3 fatty acids, particularly eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), is necessary in Western industrialized countries for the effective prevention of atherosclerosis and related diseases, as well as of apoplexy, allergic hyper-reactivity and cancers typical in Western populations.
262 0 0 0 OA 世界日本学によるトリレンマ緩解論
- 著者
- 沢 恒雄
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第30回全国大会(2016)
- 巻号頁・発行日
- pp.1D35, 2016 (Released:2018-07-30)
261 0 0 0 OA 罰なき社会
- 著者
- B.F スキナー
- 出版者
- 一般社団法人 日本行動分析学会
- 雑誌
- 行動分析学研究 (ISSN:09138013)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.87-106, 1991-03-31 (Released:2017-06-28)
- 著者
- 村田 真
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.13-20, 2012 (Released:2012-04-01)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 5 1
EPUB3は,HTMLとCSSなどのWeb技術に基づいた電子書籍フォーマットである。EPUB3は国際化されており,その1つとして日本語組版を扱うことができる。縦書き等の機能は,まずW3CにおいてCSS Writing ModesとCSS Textを作成し,次にIDPFにおいてこれらをもとにEPUB3を作成することによって導入された。この標準化経験に基づいて,国際的標準化において日本が陥りやすい落とし穴を指摘し,成功するアプローチを示唆する。
258 0 0 0 OA 太陽光発電システム火災と消防活動における安全対策
- 著者
- 田村 裕之
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.6, pp.438-444, 2014-12-15 (Released:2016-07-30)
- 参考文献数
- 2
太陽光発電システムの普及が急速に拡大している.しかし,火災事例や消防活動事例を調べると,太陽光発電システムからの出火や消火活動中の消防隊員の感電などが起こっており,火災や感電の面で安全対策が不十分なことが分った.そこで,太陽光発電システムが設置されている建物での出火危険性や消防活動時の危険性について,太陽光発電システムの構造や火災事例から課題を見出し,火災実験や発電実験を行った.その結果,火炎からの光でも発電すること,モジュールの一部が脱落しても発電を継続すること,モジュール表面の強化ガラスが熱によりフロートガラスに戻ること,人体に危険を及ぼす感電が起こりうること,などが分かった.これらを基に安全な消防活動を行うための対策をまとめた.
258 0 0 0 OA 鰹節原料カツオの交番電流処理による脱脂について
- 著者
- 鈴木 康策
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.7-8, pp.435-437, 1957-11-25 (Released:2008-02-29)
- 参考文献数
- 2
In obtaining skipjack having so little body oil as to be suitable for making good “Katsuobushi” thereof, we cannot still to-day but rely on the natural coming of such material. If we had, therefore, any proper means of removing excessive oil from the fish, we would be able to remove also the limitation arising from the seasonal overgrowth of skipjack oil. Carrying out a few experiments on a small scale, the author has ascertained that very satisfactory results can be achieved by applying an alternating current to the material interposed intimately between the electrodes kept in running water. The results are summarized as follows. 1. The higher the voltage, the less oil remains in the meat after the treatment by an electric device shown schematically in Fig. 2. 2. Ampere of the electric current is not of consequence for the effective removal of the body oil. The best range of available voltage is 170-200 V., while too high voltages cause the meat to crack. 3. Continuous refreshment of water surrounding the meat as shown in Fig. 2 is essential to avoiding large and fruitless consumption of electric energy.
257 0 0 0 OA 鉄道車両が求める軽量金属の材料特性
- 著者
- 水田 明能 木村 敏宣
- 出版者
- 公益社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- まてりあ (ISSN:13402625)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.5, pp.392-395, 2004-05-20 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 2 3
257 0 0 0 OA 食品中のフッ素含有量に関する研究
- 著者
- 副島 隆
- 出版者
- Japanese Society for Oral Health
- 雑誌
- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.342-353, 1994-07-30 (Released:2010-10-27)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 2
う蝕予防のためのフッ化物の応用に際して使用すべき適正量の検討には, あらかじめ通常の生活の中でのフッ素摂取量を把握しておくことは意義がある。本研究では, 福岡市で日常的に入手できる14食品類の65食品目を測定の対象とした。食品試料中のフッ素含有量は, 前処理に乾式灰化法と微量拡散法, 測定法をイオン電極法でそれぞれ8回の繰り返し測定を行った。その結果, 測定値の範囲は, 穀類0.19~6.04μg/g, 種実類0.13μg/g, 芋類0.01~0.02μg/g, 豆類0.42~41.75μg/g, 果実類n. d. ~0.02μg/g, 野菜類n. d. ~0.94μg/g, 茸類0.01~0.75μg/g, 海草類0.06~0.58μg/g, 飲料類0.17~2.99μg/g, 魚介類n. d. ~2.87μg/g, 肉類0.04~0.21μg/g, 卵類n. d., 乳類0.35~1.52μg/gであった。これらの結果を基にして, 平成3年度の国民栄養調査にある食品群別摂取量を利用して成人1日あたりの食品からのフッ素摂取量を推定したところ, 全国平均は1.44mgおよび北九州ブロックは1.42mgであった。
256 0 0 0 OA ウクライナ危機をめぐる国際関係
256 0 0 0 OA ジェンダー・フリー・バッシングとその影響
- 著者
- 江原 由美子
- 出版者
- 関東社会学会
- 雑誌
- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.20, pp.13-24, 2007-07-31 (Released:2010-04-21)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1 2
The subject of this paper is to consider the influence of Gender Free Bashing (GFB) on present-day Japanese society. GFB means that there are certain political groups which oppose a gender-equal policy in Japan. Those who advocate GFB think that people who use words such as ‘gender’ or ‘gender-free’ are extremists who deny the existence of natural sex difference and family. Past researches has shown that GFB had influenced many young men who had supported nationalistic view. In this paper, I try to show the influence of GFB from the viewpoint of various people in connection with GFB. And I also try to show that the main aim of GFB is to achieve a invisible change in gender-equal policy through a supply of voluntary alignment of a member of administrative occupation.
255 0 0 0 OA 胃瘻バッシングの結果、起きたこと
- 著者
- 西口 幸雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会
- 雑誌
- 日本静脈経腸栄養学会雑誌 (ISSN:21890161)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.6, pp.1225-1228, 2016 (Released:2016-12-20)
- 参考文献数
- 2
PEGは口から食べられない人にとって、きわめて安全で効率の良いエネルギー投与ルートである。PEGが「無駄な長生き」「国民医療費の無駄使い」のシンボルとして社会的にバッシングを受けてからというもの、PEG造設件数は減少した。いわゆる「PEGバッシング」があってから、どのようなことが起こっているのであろうか。代わって経鼻胃管や PICCの件数が増えている。PEG造設件数の減少は診療報酬の改定による造設手技料の減少によるところも大きい。また、在宅においては経腸栄養管理よりも経静脈栄養管理したほうが診療報酬が高いことも一因である。PEGが必要なひとに PEGができない現状であれば、非常に不幸である。PEGバッシングによって、PEGのエンドユーザーには無用の精神的な苦痛を与えていることは、ゆゆしい問題である。これを打破するには、社会に対する PEGの啓蒙と医師に対する栄養療法の教育が必要である。
254 0 0 0 寿司職人に生じたアワビによる接触蕁麻疹症候群の1例
- 著者
- 木村 友香 加藤 敦子
- 出版者
- 一般社団法人 日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会
- 雑誌
- 日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会雑誌 (ISSN:18820123)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.158-164, 2017-04-30 (Released:2017-06-30)
- 参考文献数
- 25
22歳, 男性。初診の2年前に寿司屋に就職し, 生の魚介類を扱うようになった。1ヵ月前に生のアワビ, クルマエビとアカエビを調理中に手に瘙痒感を伴う発赤が生じ, その後全身の瘙痒感, 呼吸困難感を訴え救急搬送された。その後も仕事を継続し, アワビとクルマエビを調理した際には, 時折手の瘙痒感や咳嗽を自覚する。アワビとクルマエビはいつも同時に扱うという。精査目的に当科初診した。血液検査ではアサリ, カキとホタテの特異的IgEがクラス2であった。プリックテストを施行し, 生のアワビで強陽性, 加熱したアワビ, 生のクルマエビ, 生のタコで陽性であった。アワビのプリックテスト中, 軽度の呼吸困難感が出現したが, 5分ほどで自然に軽快した。また, 生と加熱したアカエビを含むほかの各種魚介は陰性であった。タコは接触しても摂取しても症状は生じない。以上より, 生のクルマエビに対する接触蕁麻疹を合併したアワビによる接触蕁麻疹症候群と診断した。
- 著者
- 林 三千雄 中井 依砂子 藤原 広子 幸福 知己 北尾 善信 時松 一成 荒川 創一
- 出版者
- 一般社団法人 日本環境感染学会
- 雑誌
- 日本環境感染学会誌 (ISSN:1882532X)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.5, pp.317-324, 2015 (Released:2015-12-05)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 3 7
2007年1月から2012年12月までに当院血液内科病棟の入院患者より分離されたmetallo–β-lactamase (MBL)産生緑膿菌24株について細菌学的,遺伝子学的解析を施行すると共に,その患者背景を調査した.POT法を用いた遺伝子タイピングでは24株すべてが同一株と判定された.患者リスク因子では抗緑膿菌活性のある抗菌薬使用が21例,末梢静脈カテーテル留置が20例,過去一年以内のクリーンルーム入室歴が18例であった.器具の洗浄消毒方法の見直し,手指衛生や抗菌薬適正使用の徹底などを実施したが血液内科病棟における新規発生は減少しなかった.環境培養の結果などから伝播ルートとして温水洗浄便座を疑い,同便座ノズルの培養を行ったところMBL産生緑膿菌保菌者が使用した便座ノズルの27.2%から同菌が検出された.2013年1月,温水洗浄便座の使用を停止したところ新規のMBL産生緑膿菌検出数は減少した.その後,同便座の使用を再開したところ再び増加したため,2014年1月以降使用を停止した.血液内科病棟への入院1000 patints-daysあたりの新規MBL産生緑膿菌検出数をMBL産生緑膿菌感染率とすると,温水洗浄便座使用時は0.535,中止中は0.120であった(p=0.0038).血液内科病棟における温水洗浄便座の使用はMBL産生緑膿菌院内伝播の一因となり得ると考えられた.