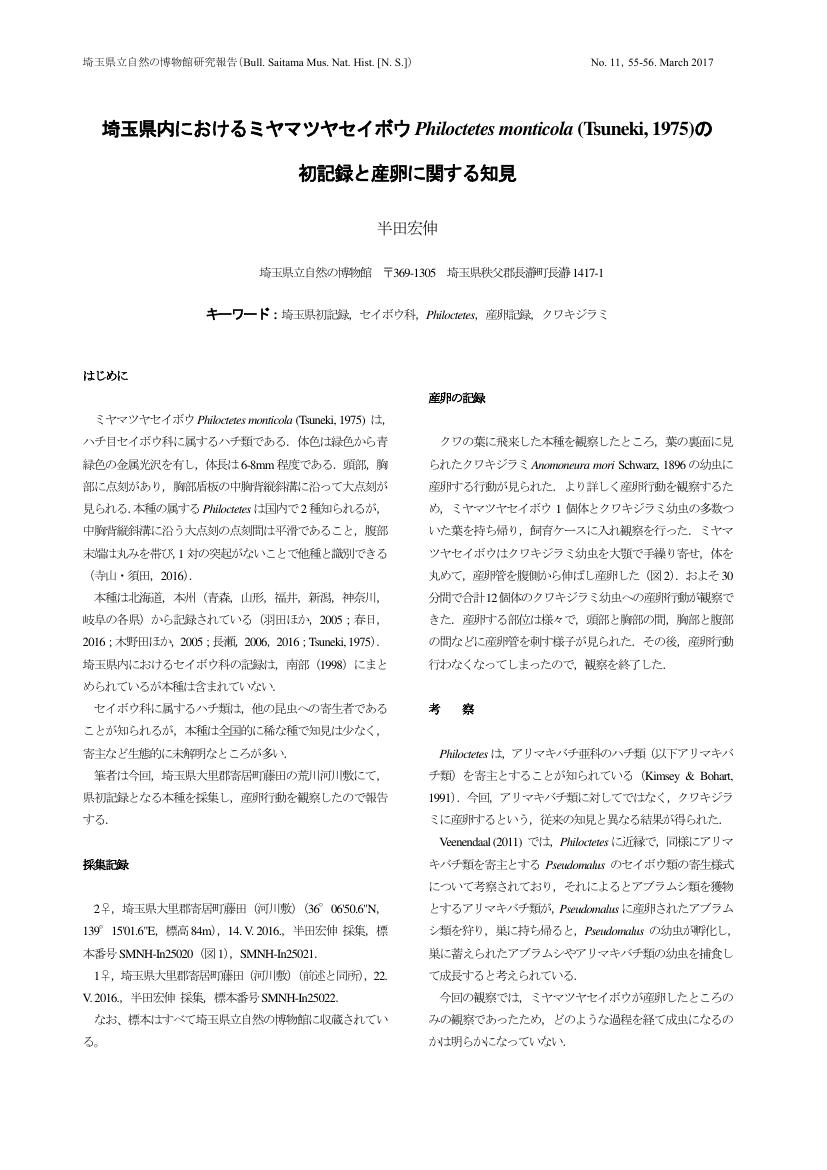26 0 0 0 OA 若手研究者の雇用環境の変化とハラスメント問題
- 著者
- 戒能 民江 鈴木 華子 原田 悦子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.322-342, 2016 (Released:2016-08-12)
26 0 0 0 OA ウェステルマン肺吸虫症の姉妹例
- 著者
- 鹿児島 崇 山﨑 善隆 坂口 幸治 久保 惠嗣 杉山 広 齊藤 博
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, no.4, pp.975-977, 2014-04-10 (Released:2015-04-10)
- 参考文献数
- 6
ウェステルマン肺吸虫はモクズガニやサワガニを生食することでヒトに感染する.今回,姉妹の感染例を経験した.両名ともプラジカンテルの投与で軽快した.国内で販売されている淡水産のカニの肺吸虫感染率は決して低くなく,加熱なしで淡水産カニを喫食する際には十分な注意が必要と考えられる.また本例はいずれも外国人であり外国人診療においては食習慣の違いによる感染症にも留意する必要があると考えられた.
- 著者
- 半田 宏伸
- 出版者
- 埼玉県立自然の博物館
- 雑誌
- 埼玉県立自然の博物館研究報告 (ISSN:18818528)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.55-56, 2017 (Released:2020-04-21)
26 0 0 0 OA キーボードの人間工学的設計
- 著者
- 中迫 勝
- 出版者
- Japan Ergonomics Society
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.53-61, 1986-04-15 (Released:2010-03-11)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
26 0 0 0 OA 必須アミノ酸, 非必須アミノ酸 その二つを分けるもの
- 著者
- 小田 裕昭
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会
- 雑誌
- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.137-149, 2007-06-10 (Released:2009-01-30)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 2 5
必須アミノ酸, 非必須アミノ酸という命名法の問題点は古くから指摘されてきたが, 特に非必須アミノ酸の定義には曖昧さもあり, 厳密にすればするほど複雑になってしまう。必須アミノ酸の必須性は, 主にその炭素骨格に依存しているが, 必須アミノ酸を生体内で合成するには長いステップを必要とするため, 進化の過程でその合成系が失われたと推測される。原核生物, 植物, 菌類は, すべてのアミノ酸合成能をもっているため必須アミノ酸をもっていない。一方, ヒトを含むすべての動物から原生生物の細胞性粘菌は必須アミノ酸をもち, その必須アミノ酸はほとんど同じである。原生生物の進化のあるときに10種ほどのアミノ酸合成能が一斉に失われたようである。ゲノム情報からもこのことが裏付けられる。原生生物の進化過程の限られた時期に複数のアミノ酸合成能を欠落させた原因は不明である。
26 0 0 0 OA モルモットに経口摂取させたビタミンC, L-システイン, ビタミンEの併用による色素沈着抑制効果
- 著者
- 藤原 葉子 秋元 浩二 二宮 伸二 坂口 靖江 脊山 洋右
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会
- 雑誌
- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.221-228, 2003-08-10 (Released:2009-12-10)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 3 3
ビタミンC (アスコルビン酸), L-システインおよびビタミンE (コハク酸d-α-トコフェロール) の併用による色素沈着抑制効果を, 褐色モルモットに経口摂取して検討した。背部を除毛後, 紫外線 (UV-B) を照射した褐色モルモットの皮膚色はメラニン色素の沈着によりL*値 (明度) が低下したが, ビタミンC単独摂取ではL*値の上昇傾向を示し, ビタミンCとL-システインの併用またはビタミンC, L-システインとビタミンEを併用することにより, 紫外線照射によるL*値の低下はいずれも有意に抑制された。紫外線照射部の表皮ではDOPA反応陽性のメラノサイト数が増加したが, ビタミンCとL-システインの併用またはビタミンC, L-システインとビタミンEの併用では, 対照群に比べて有意に減少した。L*値の低下抑制効果およびDOPA反応陽性メラノサイト数増加の抑制効果の程度は, いずれも (ビタミンC+L-システイン+ビタミンE群)>(ビタミンC+L-システイン群)>ビタミンC群であった。以上の結果から, ビタミンやシステインを組み合わせることによって, 経口摂取によってもUV照射によるメラニンの沈着を抑制できることがわかった。
- 著者
- 渡辺 匠 櫻井 良祐 綿村 英一郎 唐沢 かおり
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.53-56, 2014-07-30 (Released:2014-08-26)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 2 1
This research developed a reliable and valid Japanese version of the Free Will and Determinism Plus Scale (FAD+) to measure people's belief in free will. Study 1 developed a Japanese version of the FAD+ using questionnaire data from 203 undergraduates. Study 2 tested the reliability and validity of the Japanese FAD+ in a sample of 362 adults. The results provide evidence that the translated scale has the same factor structure as the original scale. In addition, free will beliefs were associated with locus of control, sense of trust, and belief in a just world, indicating high validity of the scale.
- 著者
- Jeffrey C. Raber Sytze Elzinga Charles Kaplan
- 出版者
- 日本毒性学会
- 雑誌
- The Journal of Toxicological Sciences (ISSN:03881350)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.6, pp.797-803, 2015-12-01 (Released:2015-11-10)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 6 141
Cannabis concentrates are gaining rapid popularity in the California medical cannabis market. These extracts are increasingly being consumed via a new inhalation method called ‘dabbing’. The act of consuming one dose is colloquially referred to as “doing a dab”. This paper investigates cannabinoid transfer efficiency, chemical composition and contamination of concentrated cannabis extracts used for dabbing. The studied concentrates represent material available in the California medical cannabis market. Fifty seven (57) concentrate samples were screened for cannabinoid content and the presence of residual solvents or pesticides. Considerable residual solvent and pesticide contamination were found in these concentrates. Over 80% of the concentrate samples were contaminated in some form. THC max concentrations ranged from 23.7% to 75.9% with the exception of one outlier containing 2.7% THC and 47.7% CBD. Up to 40% of the theoretically available THC could be captured in the vapor stream of a dab during inhalation experiments. Dabbing offers immediate physiological relief to patients in need but may also be more prone to abuse by recreational users seeking a more rapid and intense physiological effect.
26 0 0 0 OA 宮城県で確認されたドジョウ(クレードA)(コイ目ドジョウ科) 雄個体の遺伝的・形態的特徴
- 著者
- 旗 薫 小池 花苗 丹野 夕輝 中島 淳
- 出版者
- 公益財団法人 宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団
- 雑誌
- 伊豆沼・内沼研究報告 (ISSN:18819559)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.15-32, 2020 (Released:2020-08-20)
- 参考文献数
- 26
宮城県で採集されたクレードA に属すると思われるドジョウについて,ミトコンドリアDNA 調節領域による遺伝的特徴と,体型や骨質盤による形態的特徴を調査した.宮城県産クレードA はキタドジョウと同定された下北半島産クレードA と同じ遺伝的集団内の異なる分集団に属すること,眼径や第2 口髭長の体長比は下北半島産クレードA が示す値に近いが,骨質盤の形態は明瞭に異なることなどが明らかとなった.このことから,宮城県産クレードA はキタドジョウとは形態的に区別できる未知の在来集団,もしくは人為的に導入されたドジョウとの交雑集団である可能性が考えられた.
26 0 0 0 OA 還元性気体に注目した深海底環境生態系に関する地球化学的研究
- 著者
- 川口 慎介
- 出版者
- 一般社団法人日本地球化学会
- 雑誌
- 地球化学 (ISSN:03864073)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.79-97, 2015-06-25 (Released:2015-06-25)
- 参考文献数
- 175
- 被引用文献数
- 1
I am very honored to receive Young Scientist Award 2012 from Geochemical Society of Japan. This article overviews advance of continuous flow-isotope ratio mass spectrometry and novel isotopic tracers and then shows achievement and perspective of geochemical studies for deep-sea hydrothermal system. I regard molecular hydrogen and methane as key molecules to discuss limit of biosphere on the Earth and habitability of other planets and moons. This article propounds possibilities of geo-engineering activities and geochemical cell biology.
26 0 0 0 OA 堰堤建設による渓流の環境変化が水生昆虫に与える影響
- 著者
- 國分 美華子 田中 夏子 榮 結以 掛谷 亮太 野澤 佳司 村津 匠 瀧澤 英紀 小坂 泉 阿部 和時
- 出版者
- 日本緑化工学会
- 雑誌
- 日本緑化工学会誌 (ISSN:09167439)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.271-274, 2015 (Released:2016-04-19)
- 参考文献数
- 5
治山・砂防堰堤(以下,堰堤)は,渓流生態系に影響を及ぼすと考えられる。本研究では,水生昆虫に焦点をあて,堰堤建設による渓流環境の変化が水生昆虫の生息状況にどのような影響を与えるか検討した。調査は,神奈川県西丹沢地区の中川支流の白石沢上流で行った。堰堤直上流部の土砂堆積域(以下,堰堤土砂堆積域),堰堤の直下流域及び付近に堰堤が建設されていない自然渓流域にて水生昆虫の採集を行った。データ解析の結果,総個体数は堰堤土砂堆積域で最も多く,総種数は自然渓流域で最も多かった。このことから,堰堤建設による渓流の安定化・単調化は,水生昆虫の生息場所を減少させ種の多様性を低下させていると考えられた。
26 0 0 0 OA ポイントと値引きはどちらが得か?:ポイントに関するメンタル・アカウンティング理論の検証
- 著者
- 中川 宏道
- 出版者
- 行動経済学会
- 雑誌
- 行動経済学 (ISSN:21853568)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.16-29, 2015 (Released:2015-11-30)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 2
小売業での買物において,ポイント付与と値引きとでは,どちらが消費者にとって得と感じられるのであろうか.本研究では,少額のポイントは心理的な貯蓄勘定に計上され,多額のポイントは当座勘定に計上されるというポイントに関するメンタル・アカウンティング理論の仮説を提示し,スーパーマーケットおよび家電量販店におけるアンケート実験によって検証をおこなった.スーパーマーケットでの実験結果から,値引率・ポイント付与率が低い水準においては,値引きよりも同額相当のポイント付与の知覚価値の方が高いことが明らかになった.低いベネフィット水準におけるセールス・プロモーション手段としては,値引きよりもポイント提供の方が有効であることが本研究の結果から示唆される.
26 0 0 0 OA 『アンサングシンデレラ』ドラマ化に際して
- 著者
- 富野 浩充
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬剤学会
- 雑誌
- 薬剤学 (ISSN:03727629)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.1, pp.53-55, 2021 (Released:2021-01-01)
- 参考文献数
- 2
26 0 0 0 OA 自律ロボットからの働きかけと感性
- 著者
- 石原 恵子 原田 実穂 石原 茂和
- 出版者
- 日本感性工学会
- 雑誌
- 感性工学研究論文集 (ISSN:13461958)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.4, pp.709-716, 2008-06-30 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 10
Autonomous robots, which are becoming more widespread in Japanese homes and workplaces, perform such diverse functions as cleaning, or security patrolling. As people need to accept and understand these robots with which they may be in contact for extended periods, we studied Kansei in relation to the movements of robots. We observed the behavior of the people who participated in “a simulated workplace with robots experiment.”We developed six small simple robots of similar appearance but exhibited different behaviors in terms of their approaches to people; the combination of three types of movement and two types of wagging of the stick on the back. Each robot was evaluated on autonomism, Kansei, and affectiveness, anthropomorphism, safety and durability. According to the last evaluation after the session in three successive days, we concluded that approaching a person was interpreted as “cleverness”and wagging a “tail”as “charm.”The wag alone did not promote attachment but alleviated the aggression of the autonomous robot.
26 0 0 0 OA パーキンソン病患者の慢性疼痛について
- 著者
- 湯浅 龍彦 米谷 富美子 角田 博 西澤 舜一
- 出版者
- 一般社団法人 国立医療学会
- 雑誌
- 医療 (ISSN:00211699)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.7, pp.381-385, 2008-07-20 (Released:2011-10-07)
- 参考文献数
- 14
パーキンソン病にともなう慢性疼痛の実態を知る目的で, 千葉県パーキンソン病友の会会員にアンケート調査を実施した.108件の有効回答中, 3カ月以上続く慢性疼痛を有す者は69名(64%)であった. 自覚症状は, 腰痛が最多であり, 肩こり, 関節痛, 手足のしびれ, 手足の痛みなどがそれに続いた. 痛みの性状は, 鈍痛や締め付けなどが90件, びりびりや電撃痛などが46件であった. 痛みの強さでは, きわめて強い痛みを9名(8%)が訴え, 痛みのために不眠になる者が約半数にみられた. 線維性筋痛症の診断基準とされる11カ所以上の圧痛点を有す者は3名(2.7%)であった. 6割の患者では抗パーキンソン薬で痛みが軽快した.今後, パーキンソン病の慢性疼痛の要因を明らかにし, それぞれの原因に沿った治療法の確立が望まれる.
26 0 0 0 OA インフルエンザの時・空間的流行モデル
- 著者
- 中谷 友樹
- 出版者
- The Human Geographical Society of Japan
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.254-273, 1994-06-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 90
- 被引用文献数
- 1 1
A mathematical model is built for influenza or other similar disease epidemics in a multi-region setting. The model is an extended type of chain-binomial model applied to a large population (Cliff et al., 1981), taking into account interregional infection by interregional contacts of people. If the magnitude of the contact is presented by simple distance-decay spatial interaction or the most primitive gravity model, a conventional gravity-type epidemic model (Murray and Cliff, 1977; Thomas, 1988) is deduced.Given the number of infectives and susceptibles, the chain-binomial model predicts the number of infectives in the next period with binomial probability distribution. Available data are, however, weekly cases per reporting clinic in each prefecture reported by the surveillance project, characterized by continuous variation; the data could be a surrogate index for rates of infection. The author modified the model to use rates of infectives and susceptibles, and used a normal approximation of binomial distribution. With the maximum-likelihood method, this model can be calibrated. The specification of the model is as follows:Li(Yi, t=0, …, Yi, t=T|β°i, δi)=Πt1/√2πVar[Yi, t+1]·exp{-1/2Var[Yi, t+1](Yi, t+1-E[Yi, t+1])}, E[Yi, t+1]=β°i/MiXi, tΣjmijYj, t, Var[Yi, t+1]=β°i/MiXi, tΣjmijYj, t(1-β°i/MiΣjmijYj, t), Xi, t=δi-Σis=0Yi, s, where Mi=Σjmij; Li denotes the likelihood of the model for region i; Xi, t denotes the estimated rate of susceptibles in region i at week t; Yi, t denotes the reported rate of infectives in region i at time t; mij denotes the size of interregional contact with the people in regions j for the people in region i; β°i denotes the infection parameter in region i; δi denotes the parameter concerned with the rate of initial susceptibles in region i.The model posits that the average number of people who come into contact with a susceptible in prefecture i is a constant, and that the average rate of infectives of the people is ΣjmijYj, t/Mi. The probability of a susceptible in region i infected at time t is, therefore, β°iΣjmijYj, t/Mi.This model was applied to a weekly incidence of influenza in each prefecture, from the 41st week, 1988, to the 15th week, 1989, Japan, letting the size of interregional passenger flow Tij correspond to mij as follows: mij=Tij+Tji (i≠j), mii=Tii.Goodness-of-fits (Table 1) of one-week-ahead forecasts were almost satisfactory except for prefectures whose epidemic curves were bi-modal (e.g., Hokkaido) or whose transition speed between epidemic breakout and peak was too high (e.g., Yamagata). The latter might be explained by a cluster of group infection (e.g., school classes) in an earlier phase of the epidemic (see Fig. 4).
26 0 0 0 OA ゲーム情報学:コンピューター将棋を超えて
- 著者
- 松原 仁
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.89-95, 2016-05-01 (Released:2016-05-01)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2
ゲーム情報学はゲームを対象とした情報処理の研究分野である。チェスがゲーム情報学の中心のゲームであったが,チェスでコンピューターが世界チャンピオンに勝った後は将棋が注目されていた。将棋はまだ世界チャンピオンに勝ってはいないが,対戦すれば勝つ可能性が高いレベルに達した。囲碁はチェスや将棋と比べて場合の数がはるかに大きいのでまだ世界チャンピオンを倒すまで10年はかかるとみられていたが,深層学習(ディープラーニング)の利用によってすでにトップのプロ棋士に勝ち越すまでになった。今後は「人狼」など不完全情報ゲームがゲーム情報学のテーマになっていくであろう。
26 0 0 0 OA パリテ法から十年 : 経過と現状
- 著者
- 西尾 治子
- 出版者
- 日本フランス語教育学会
- 雑誌
- Revue japonaise de didactique du français (ISSN:18805930)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.76-85, 2010-12-05 (Released:2017-10-14)
La loi sur la parite a joue un role primordial dans l'histoire du feminisme ainsi que l'histoire constitutionnelle en ce sens qu'elle a ete promulguee pour la premiere fois au monde en 2000, conformement au principe d'egalite, apres la revision de la Constitution de la Republique francaise. Quelles sont les raisons qui ont rendu la parite necessaire ? La presente etude a pour but de faire la lumiere la genese de la parite, son evolution et son etat actuel. Elle examine, en premier lieu, la genese de la parite, ensuite les differences entre d'une part le quota et le systeme americain d'action affirmative, d'autre part la parite dont le debat jadis centre sur la theorie dichotomique a divise les feministes francais en deux camps : l'universalisme et le differentialisme. Enfin, elle etudie les problemes concrets auxquels est confrontee actuellement la prite.
26 0 0 0 OA 肩甲骨位置が胸郭の運動性に与える影響
- 著者
- 根本 伸洋 大橋 夏美 湖東 聡 松永 勇紀 角本 貴彦 柿崎 藤秦
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.34 Suppl. No.2 (第42回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.A1258, 2007 (Released:2007-05-09)
【目的】胸郭の運動性は、呼吸において重要であるが、身体全体に対して0.479の質量比を持つ体幹の約半分を占める部分である為、歩行などの身体運動にも影響すると考える。実際の臨床においても、胸郭全体の運動性低下や、運動性の左右差が生じている患者では、それに見合った呼吸や身体運動しか出来ないことが観察される。また、そのような患者に対して、胸郭と接する肩甲骨位置を修正することで、運動性や左右差の改善を図ることができ、良好な呼吸や身体運動を獲得できることを経験する。そこで今回は、肩甲骨内外転位置が胸郭の運動性に与える影響を検討したので、ここに報告する。【方法】対象は、本研究の内容を十分に説明し同意を得た健常成人8名とし、各条件での坐位姿勢をゼブリス社製3D-Motion Analysis CMS20Sを用いて測定した。測定した姿勢は、1)安静坐位姿勢、2)安静坐位から胸郭を右側へ並進移動させた坐位姿勢(以下、右変位姿勢)、3)右肩甲骨を外転誘導しての右変位姿勢、4)右肩甲骨を内転誘導しての右変位姿勢とした。なお、右変位姿勢は、骨盤帯が動かない範囲で胸郭を並進移動させ、肩甲骨位置の誘導は、右上肢を内旋位にすることで肩甲骨外転位置へ誘導し、右上肢を外旋位にすることで肩甲骨内転位置へ誘導した。また、測定の順番は、最初に安静坐位を測定した後は、無作為の順で各右変位姿勢を測定した。測定したランドマークは、両PSIS、両ASIS、両腸骨稜、Th1棘突起、Th11棘突起、胸骨頸切痕、剣状突起、第11肋骨先端とし、最も突出した部分または最も陥没した部分に十分注意を払いマーキングした。検討項目は、各ランドマークの空間座標から、1)胸骨頸切痕と第11肋骨先端の距離(以下、胸郭距離)、2)Th11棘突起と剣状突起を結ぶ線とTh11と第11肋骨先端を結ぶ線が水平面上でなす角(以下、肋骨角度)を左右で求め、対応のあるt検定を用いて、それぞれ危険率5%未満を有意とした。【結果】胸郭距離は、肩甲骨の誘導がない右変位姿勢と比較し、肩甲骨外転位での右変位姿勢で、変位させた側の右胸郭距離が有意に増大した。また、肋骨角度の左右差の平均は、肩甲骨内転位での右変位姿勢、右変位姿勢、外転位での右変位姿勢の順に増大し、それぞれ安静坐位と比較し有意に増大していた。【考察】胸郭距離、肋骨角度の左右差が肩甲骨内転位で増大していた結果から、胸郭の運動性が増大したと考えた。これは、肩甲骨外転位では肩甲骨が胸郭側方に位置する為に、胸郭側方の運動性を妨げるが、肩甲骨内転位にすると肩甲骨は胸郭後方に移動し、胸郭側方の運動を妨げない為であると考えた。今回の結果から、肩甲骨の位置を考慮することで、胸郭の運動性を引き出し、呼吸や身体運動の改善に繋げられる可能性が考えられた。
- 著者
- 土居 秀幸 高橋 まゆみ
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.241-247, 2010-07-31 (Released:2017-04-21)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
地球温暖化による気温上昇の影響は、広く生態系に拡がりつつあり、フェノロジー(生物季節)のタイミングにもその影響が波及しつつある。近年、今まで蓄積されてきた長期データを使用した研究により、地球温暖化が植物・動物のフェノロジーのタイミングに、大きな影響を与えていることが明らかとなってきた。しかし今までの研究では、ある場所でのフェノロジーの温暖化への反応を検討している場合が多く、そのマクロ的な傾向について検討した研究例は未だに少ない。気象庁では、1953年から現在まで全国102ヵ所の観測所で、のべ120種以上の植物・動物種についてその開花・発芽・落葉・初見日・初鳴日などのフェノロジーを記録している。全国102ヵ所という広範囲で長期に観測されたフェノロジーデータを用いれば、フェノロジーの温暖化への反応をマクロエコロジーの視点から考えることが可能である。そこで本稿では、気象庁・生物季節データセットを用いたマクロスケールおけるフェノロジーと気候変動の関係についての研究、特にフェノロジーの温度反応性の緯度クラインと、温度反応性への遺伝的多様性の影響について紹介する。まとめとして、今後のマクロスケールでのフェノロジー研究の意義と方向性について述べる。