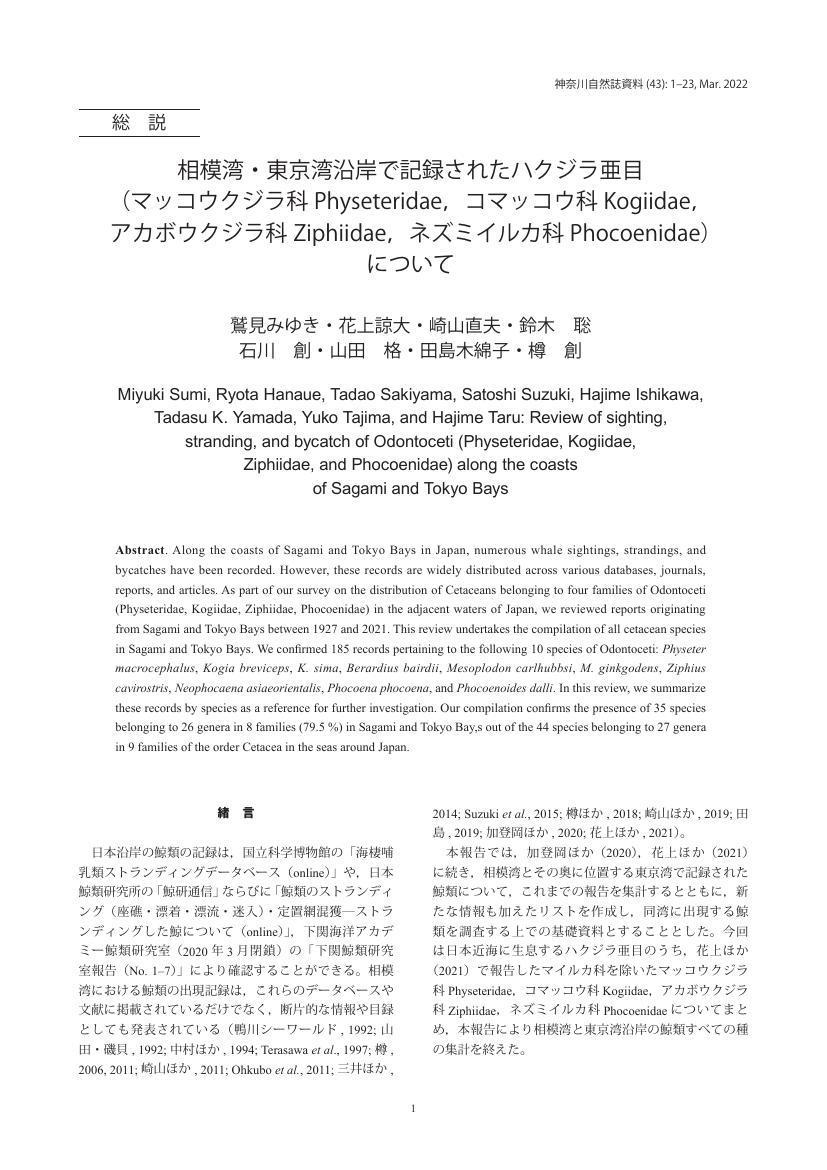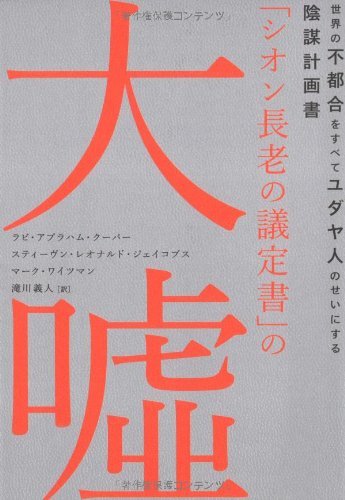3 0 0 0 OA 牧羊犬制御のモデル化
- 著者
- 東 俊一 田淵 絢子 杉江 俊治
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.12, pp.882-888, 2012 (Released:2013-01-23)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 2 5
This paper develops a mathematical model of a sheepdog control strategy, in order to clarify a principle for controlling autonomously (and randomly) moving multiple agents. First, by observing real behaviors of a sheepfold and a sheepdog, we extract their essential properties as a multi-agent system. Based on this, difference equations are constructed for the sheep and sheepdog. It is verified by numerical simulations that the proposed model captures their qualitative behaviors.
3 0 0 0 OA ウェブサイト上における日・米・英・台の学生相談機関の情報発信
- 著者
- 伊藤 直樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.1, pp.79-85, 2017 (Released:2017-04-25)
- 参考文献数
- 25
This study aimed to compare information provided on student counseling center websites of universities and colleges in Japan, the United States, the United Kingdom, and Taiwan. A survey was conducted on websites of 315 centers in Japan, 282 centers in the United States, 70 centers in the United Kingdom and 61 centers in Taiwan. Trends in the provision of information on websites in each country were analyzed and compared for the rate and quantity of information published. Results of multiple correspondence analyses indicated two basic dimensions of information that could effectively distinguish information provided in the four countries. These were provision of necessary information and provision of information for use of individual counseling or support of community. Finally, issues related to websites in student counseling centers of Japanese universities and colleges are discussed.
3 0 0 0 OA 私の手術教育 ―初心者指導の経験から―
- 著者
- 堤 一生
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中の外科学会
- 雑誌
- 脳卒中の外科 (ISSN:09145508)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.5, pp.361-363, 2007 (Released:2008-08-26)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 16 7
Recently, better direct surgery for cerebrovascular disease has come to be required, while less invasive treatment (gamma knife and intravascular surgery) has played an alternative role. To improve the quality of surgery, one of the most important issues is the surgical education of young neurosurgeons. They must learn traditional surgical skills and achieve more sophisticated techniques than those of their seniors. In this paper, I present my experience and discuss the education of neurosurgeons. My teaching method was based on suturing training with 10-0 nylon using a microscope and hands-on practice under my supervision. This training was useful to improve dexterity and maneuverability with a limited number of clinical cases. The hands-on practice of microsurgery was inevitable to learn surgical skills and judgment. Moreover, the experience of real surgery was an incentive to train harder. My residents trained in suturing for 1 to 3 years with a total of 10,000 to 20,000 stitches each. During the same period, they operated on 150-250 cases, including aneurysmal clipping (20-50 cases), STA-MCA anastomosis (5-20) and carotid endarterectomy (5-30). Surgical complication was 1-2% of all, although the time of surgery was prolonged in the early stage. Differences of resident's grades at the start of training were not related to the results. Satisfactory results were not achieved in less than 2 years. In my subjective judgment, the result of education depended on the individual passion for surgery, the continuous training and a positive attitude about learning from others. Even young neurosurgeons should be given a chance to perform microsurgery if they continue the training. Under a senior's supervision, the results of surgery can be acceptable. Early experience and education may be promising for improving microsurgery for cerebrovascular disease.
3 0 0 0 IR 昭和維新運動 : 大本教・出口王仁三郎を中心に (宇都榮子教授 退職記念号)
- 著者
- 徐 玄九
- 出版者
- 専修大学人間科学学会
- 雑誌
- 専修人間科学論集. 社会学篇 (ISSN:21863156)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.53-64, 2018-03
明治末期から大正期を経て昭和初期にかけて、いわゆる「第二維新」を掲げる多くの運動が展開された。日本のファシズム化の過程で結成された多くの国家主義団体は、ほとんど大衆的組織基盤をもっておらず、しかも、組織機構を整備していなかった。ごく少数の幹部が勇ましいスローガンを掲げていたに過ぎず、経済的基盤も弱かった。しかし、大本教および出口王仁三郎の思想と運動は、これまでのテロやクーデターに頼った右翼や青年将校に比べて、大衆組織力、社会への影響力という点で、群を抜いていた。そして、大本教および出口王仁三郎の運動を「天皇制ファシズム」を推し進める他の団体、青年将校らと比較した場合、決定的に違う点は、テロやクーデターのような暴力的手段に訴える盲目的な行動主義とは一線を画し、「大衆的な基盤」に基づいて、あくまでも「無血」の「第二維新」を目指したことである。出口王仁三郎が追求したのは「民衆の力を結集すること」による社会変革であったのである。
3 0 0 0 OA 1.慢性咳嗽の病態,鑑別診断と治療―咳喘息を中心に―
- 著者
- 新実 彰男
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.9, pp.1565-1577, 2016-09-10 (Released:2017-09-10)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1 1
3 0 0 0 IR 留まる人々の「自由」 : 文化発信の拠点としてのハンセン病療養所
- 著者
- 有薗 真代
- 出版者
- 京都大学人文科学研究所人文学国際研究センター
- 雑誌
- コンタクト・ゾーン = Contact zone
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.196-221, 2012-03-31
3 0 0 0 OA 法令工学の実践 国民年金法の述語論理による記述と検証
- 著者
- 片山 卓也
- 出版者
- JAIST Press
- 巻号頁・発行日
- pp.1-146, 2021-12
国民年金法のような行政サービスに関する法令は,その内容は明確であり,文章上の見かけの複雑さの割には論理的深度は深くない.したがって,形式的手法によってその内容を記述することにより,可読性が高く,機械的なテストや分析が可能な法令記述が得られる可能性が高い.また,このような法令は我々の社会の制度的基盤であり,その法令実働化IT システムが我々の社会生活を 支えていることを考えると,法令に対する形式的技術の確立は重要である. 本書は,このような立場から行政サービスに関する法令を意図した通りに正しく作る上で,法令の形式的記述と自動検証技術の可能性を,国民年金法の基本的条文の述語論理による記述と定理自動証明器(SMT ソルバー)Z3Py による検証事例に基づいて述べたものである.近年の定理証明技術の進歩や計算機システムの高性能化により,このような技術は十分に実用化可能であるというのが本書の結論である.法令の度重なる改正に対応するため法令実働化ITシステムの内部構造劣化が進み,保守の困難性が社会的な問題となっているが,本書で述べる技術はこの問題に対する有力な解決法になると思われる. 本書は2部から構成されている. 第I部はこのような新しい法令作成方法論の原理的可能性を示すために書かれた,日本ソフトウェア科学会誌「コンピュータソフトウェア」36巻3号(2019)に掲載された論文をそのままの形で転載したものである. 被保険者の資格,年金の支給期間及び支払期月,併給の調整に関する3 つの典型的条文を通して,論理式化の方法やその構造化の方法等を示すと同時に,検証に必要なテストデータとしての年金原簿の扱いなどについて述べている.また,条文の誤りの定理証明システムによる検証例について述べている. 第II部は,第I部で述べた内容を事例の面から補強するために,そこで紹介した方法を国民年金法のより多くの条文へ適用した結果を詳細かつ具体的に述べたものであり,このような手法を広く実践する際の助けとなることを目的としたものである. 各条文ごとに,(1)条文の文章,(2)論理式記述,(3)検証スクリプトと検証結果,(4)それらの内容に関するメモを付加した.論理式記述は,パターン表現を用いてなるべく簡潔になるように心懸けたが,このようなパターンの定義などを基本用語定義集として纏めた.検証においてはテストデータとしての年金原簿が必要であるが,各条文の検証に必要な複数の年金原簿も纏めて収録した.最後に,日付けを抽象データとして扱った検証事例,実際の暦による日付け記述,論理式記述に基づく年金システムシミュレーターの構成の概略などを収録した.
3 0 0 0 IR 里親への心理的支援 -アタッチメント理論に基づく支援を中心に-
- 著者
- 瀬地山 葉矢
- 出版者
- 日本福祉大学子ども発達学部
- 雑誌
- 日本福祉大学子ども発達学論集 = THE JOURNAL OF CHILD DEVELOPMENT (ISSN:24352802)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.1-9, 2022-01-31
本稿では,里親養育における里親の支援ニーズと実際の支援方法について,既存の調査と先行研究に基づいて整理をした.支援方法のなかでも,とりわけアタッチメント理論に基づく子どもと親子関係の理解,および親子関係支援プログラムについて取り上げ,検討を行った.その結果,現場の特徴を踏まえたうえで,アタッチメント理論を適切に活用することにより,里子の行動を理解する手がかりが得られる可能性があること,また親子関係支援プログラムでは,子どもの行動やその対応方法について,ファシリテーターによるアタッチメントの視点に基づいた助言が,子どもの変化や里親のサポートにつながることが示唆された.さらにファシリテーターは,それ以外にも,里親の安全感・安心感を高め,視点の変換を養育者にもたらすことが示唆された.
3 0 0 0 OA リスク選好の男女間比較:日本,タイでのサーチ実験を用いた分析
- 著者
- 三浦 貴弘 犬飼 佳吾 Pacharasut S. San S. Thanee C. 佐々木 勝
- 出版者
- 行動経済学会
- 雑誌
- 行動経済学 (ISSN:21853568)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.106-109, 2017 (Released:2017-06-01)
- 参考文献数
- 5
本研究では,アンケートを用いたリスク選好の測定の代替案の1つとして,実験室におけるサーチ実験を行い,観測された被験者のサーチ行動からリスクに対する選好の程度を測定した.その結果を用いて,性別間でリスク回避度に違いがみられるのかを日本,タイの被験者を用いて比較分析を行った.本研究から得られた結果として,日本では男女間でリスク選好に違いは見られなかったが,その一方でタイではリスク選好は女性のほうが統計的に有意にリスク愛好的であることが明らかになった.また,アンケートの結果から測定したリスク選好は日本,タイどちらの国でも有意な違いはみられなかった.この結果から,求職行動に関連するリスク選好の男女差は文化によって異なることが示唆される.
3 0 0 0 OA 天才ハッカー 萩野純一郎博士を悼む-IPv6時代は彼によって開かれた-
3 0 0 0 OA 徐福学序説 : ロマンの昇華を求めて
3 0 0 0 OA シラカバ花粉感作例における口腔アレルギー症候群を起こす原因食物のクラスタリング
- 著者
- 山本 哲夫 朝倉 光司 白崎 英明 氷見 徹夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.111, no.8, pp.588-593, 2008 (Released:2009-10-01)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 3 5
【目的】シラカバ花粉にアレルギーを有する患者は, 交差反応性のために, リンゴなどの果物や野菜を食べる時の口腔や咽頭の過敏症をしばしば訴える. こういった現象は現在では時に随伴する全身症状とともに, 口腔アレルギー症候群 (OAS) と呼ばれて注目されており, IgEを介したアレルギーと考えられている. われわれは問診にて伴いやすいOASの原因食物の関係について調べ, 食物を分類した. 【方法】対象は, 1995年から8年間に札幌市南区にある耳鼻咽喉科診療所を受診, シラカバ花粉に対するIgEが陽性で, 問診にてOASの既往を有する272例 (15歳から65歳) である. OASの診断は問診により, 様々な食物を食べた後のOASのエピソードの有無を尋ねた. OASを引き起こすことの多い, 14種の食物 (リンゴ, モモ, サクランボ, ナシ, プラム, イチゴ, キウイ, メロン, カキ, ブドウ, スイカ, トマト, マンゴーとバナナ) について, クラスター分析を用いて, OASを伴いやすい食物の分類を行い, 次にカッパ統計量を用いて, 個々の食物間の伴いやすさを確認した. 【結果】14種のOASの原因食物は2種のクラスターに分類された. 1つはバラ科の果物であり, もう1つはバラ科以外の食物である. バラ科の果物 (リンゴからイチゴ) は互いに関連していた. メロンとスイカは伴いやすかった. メロンとキウイはバラ科の果物とは関連は少なかった. バラ科以外の食物 (キウイからバナナ) は互いに関連しており, 伴う場合があった.
3 0 0 0 OA 住宅における換気量の簡易予測法
- 著者
- 趙 雲 荏原 幸久 吉野 博
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.512, pp.39-44, 1998-10-30 (Released:2017-02-02)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 2 2
Ventilation calculation is important for prediction of heating/cooling load and indoor air quality in residential buildings. In past several decades, many simulation programs are developed for building research and design, but they generally need many input data and complicated modeling. A simplified and accurate prediction method is essential for speedy and convenient ventilation calculation during building design and performance evaluation. In this paper, thousands of ventilation cases are calculated by COMIS ventilation simulation program for a single room house. Using simulated results and ventilation theory, a simplified model and chart for ventilation rate is proposed in consideration of building air-tightness, type of ventilation system and climatic condition. By comparison of COMIS program and the simplified method, it can be found that there is a good agreement with relative error of less than 5 %. In addition, this simplified method is used for a study on building air-tightness level of a solar house having a forced supply ventilation system of heated outdoor air by solar collectors.
3 0 0 0 OA 唐王朝の官僚制と北衙禁軍 -唐前半期を中心に-
- 著者
- 林 美希
- 出版者
- 早稲田大学多元文化学会
- 雑誌
- 多元文化 (ISSN:21867674)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.二三五-二二二, 2018-02-28
3 0 0 0 OA 向精神薬の作用機序:神経細胞新生との関係
- 著者
- 氏原 久充
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.123, no.5, pp.319-328, 2004 (Released:2004-04-27)
- 参考文献数
- 60
- 被引用文献数
- 1 1
近年新しい精神科治療薬が次々と登場し精神障害の薬物療法は革新の時期を迎えている様に思われる.さらに,成熟後の脳であっても神経組織は再生可能であり,実際に神経細胞の新陳代謝が日常的に起こっているらしいという認識ができつつある.ここ数年間で蓄積された成熟個体での神経細胞新生の知見によって精神障害の治療戦略そのものが変化せざるを得なくなってきているのである.これらの知見は,精神障害の発生メカニズムの理解にまで影響を与えるだろう.すなわち抗うつ薬·気分安定薬·精神病治療薬さらに電撃けいれん療法の作用機序が神経栄養因子や抗アポトーシス分子の誘導,あるいはアポトーシス促進分子の阻害という形で整理されつつある.臨床実践の場で神経細胞新生·神経細胞保護仮説を支持する知見が蓄積していくことで,新しい薬理作用の理解が深まり,より合理的で効果的な精神障害の治療法が確立されることが望まれている.ここでは,急速に進歩している抗精神病薬等の新しい薬理学の理解について総説した.
- 著者
- ラビ・アブラハム・クーパー スティーヴン・レオナルド・ジェイコブス マーク・ワイツマン著 滝川義人訳
- 出版者
- 徳間書店
- 巻号頁・発行日
- 2008
3 0 0 0 OA 自治体監査の外部委託及び共同化に関する現状と課題
- 著者
- 丸山 恭司
- 出版者
- 日本監査研究学会
- 雑誌
- 現代監査 (ISSN:18832377)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, no.28, pp.57-68, 2018-03-31 (Released:2019-08-17)
- 参考文献数
- 8
自治体では不正経理が忘れた頃に発覚し,監査の実効性が問われてきた。自治体監査の実効性向上の一方策として監査業務の外部委託や共同化がある。わが国の都道府県,政令指定都市および中核市に対して監査組織の実態,外部委託および共同化の現状についてアンケート調査をした。監査組織については,民間企業の内部監査部門に比較して同等の人数が監査委員事務局に配属されていた。だが,監査実務経験年数が3年未満の監査担当職員が多く,会計や監査に係る専門的資格の保有者が少ないことが明らかとなった。外部委託については,公共工事の工事監査を外部委託する事例は,多数確認されたものの,会計専門職や監査法人に財務に関する監査業務を委託する事例は少なかった。共同化については,ほとんどの自治体で検討すらなされていないことが明らかとなった。自治体の会計基準や監査基準を民間企業に適用されている会計基準や監査基準に近づけるなどの環境整備,国からの財政的・技術的な支援が重要となる。
3 0 0 0 OA 企業組織における管理監督者と組合リーダーによるリーダーシップの効果
- 著者
- 高口 央 坂田 桐子 黒川 正流
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.83-97, 2005 (Released:2006-02-18)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1
本研究では,企業組織において調査を実施し,職場集団内の2名のリーダーによるリーダーシップ機能の分担を吟味するとともに,リーダーが複数存在することと,所属従業員のモラール,帰属意識,およびストレスとの関連を検討した。日常業務に関わる複雑さの認知,集団サイズ,また支社の部署数を状況の複雑性として取り上げた。各集団の2人のリーダーのうち,1人は職制上の管理者(係長,もしくは班長),もう1人は各部署に一名配置されている組合委員とした。有効回答者数8,758名のうち,管理職,組合委員,および出向者を除外した788部署の5,670名(男性4,793名,女性805名,不明72名)を分析対象とした。分担の形態を吟味した結果,管理監督者のみが統合型であるよりも管理監督者と組合委員の2人がともに統合型である部署が多く存在することが確認できた。効果性について,2名がともに統合型である部署が,管理監督者のみが統合型である単独統合型と同等以上の成果を得ていることが示唆された。加えて,状況の複雑性が高い場合に,複数リーダーの有効性が示された。