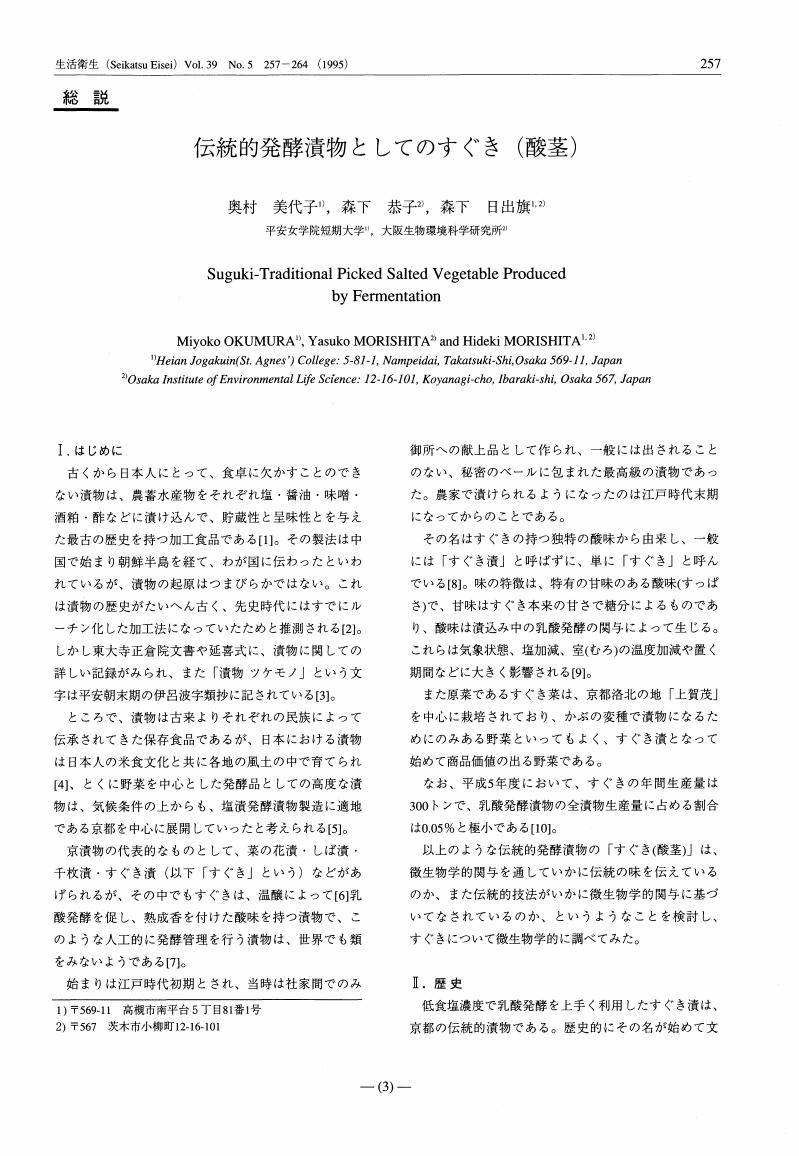3 0 0 0 OA 伝統的発酵漬物としてのすぐき (酸茎)
- 著者
- 奥村 美代子 森下 恭子 森下 日出旗
- 出版者
- Osaka Urban Living and Health Association
- 雑誌
- 生活衛生 (ISSN:05824176)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.5, pp.257-263, 1995-09-30 (Released:2010-03-11)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA 男性用性的欲求尺度(SDS-M)の作成と信頼性・妥当性の検討
- 著者
- 田口 真二 桐生 正幸 伊藤 可奈子 池田 稔 平 伸二
- 出版者
- 日本犯罪心理学会
- 雑誌
- 犯罪心理学研究 (ISSN:00177547)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.1-13, 2007 (Released:2018-06-30)
- 参考文献数
- 27
A projective questionnaire for measuring male sexual desire was developed. In Study 1, the original Sexual Desire Scale for Males (SDS-M) was developed by referring to information on sexual activities on the Internet, as well as to prior studies on sexual offenders and their victims. The original SDS-M requested participants to judge whether they agreed or disagreed with sentences regarding various sexual behaviors and objects of sexual desire. SDS-M did not inquire about the frequency of sexual activities or the strength of sexual desire. The original SDS-M was administered to 140 males. The factor analysis of their responses revealed that the SDS-M had a 5-factor structure: daily sexual desire, h omo-hetero sexual desire, penis oriented sexual desire, intercourse oriented sexual desire and abnormal sexual desire. Cronback's alpha indicated satisfactory internal consistency and reliability. Study 2, investigated the stability and the validity of the SDS-M. It was administrated to 274 males, and based on the results of confirmatory factor analysis using Structural Equation Modeling, the SDS-M was divided into two subscales: a general sexual desire subscale consisting of the four factors with the exception of the Abnormal factor, and an Abnormal sexual desire subscale. The goodness of fit index of each subscale indicated satisfactory factor validity. Moreover, the SDS-M had reasonable test-retest reliability and satisfactory correlations with the Sexual Attitudes Scale and the Beck Depression Inventory.
3 0 0 0 IR 御霊信仰の成立と展開: 平安京都市神への視角
- 著者
- 井上 満郎
- 出版者
- 奈良大学
- 雑誌
- 奈良大学紀要 (ISSN:03892204)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.187-201, 1976-12
御霊,即ち,何らかの記念的な行動の足跡を残して死去した人に対する信仰は,古代に発生してより以来,はるかのちの近代社会においても存在している.その事例は極めて多く,既往の研究においてもふれられているのでここでは取りあげない.本稿で扱かうのは,古代においてこの御霊に対する人々の崇敬がいつ発生し,どのように定着・展開していったかということである.
- 著者
- 大原 ゆい
- 出版者
- 大谷大学真宗総合研究所
- 雑誌
- 大谷大学真宗総合研究所研究紀要 = ANNUAL MEMOIRS OF THE OTANI UNIVERSITY SHIN BUDDHIST COMPREHENSIVE RESEARCH INSTITUTE (ISSN:13432753)
- 巻号頁・発行日
- no.36, pp.17-29, 2019-03-29
3 0 0 0 OA 間欠的運動における強度の違いがサッカー選手の認知機能に及ぼす影響
- 著者
- 松竹 貴大 夏原 隆之
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- pp.22084, (Released:2023-02-09)
- 著者
- 根津 雅彦 鈴木 達彦 平崎 能郎 並木 隆雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.4, pp.420-451, 2021 (Released:2023-03-03)
- 参考文献数
- 80
スペイン風邪の際に漢方治療が多くの命を救ったことはよく知られる。古来よりインフルエンザを初めとした急性ウイルス性呼吸器感染症は傷寒などと呼ばれてきたが,本邦ではその治療にあたり,『傷寒論』『小品方』『太平恵民和剤局方』『万病回春』などから多くの処方が取り入れられてきた。江戸期には漢方治療は本邦独自の発展を遂げるものの,医療及び経済的な格差のため,その恩恵を受けた庶民は少数派であった。さらに傷寒治療のキードラッグである麻黄には,古来よりトクサ属植物と混同されるなど品質面に大きな問題を抱え,その薬効が過小評価されてきた可能性があることは,今後も留意すべきものと思われる。新型インフルエンザ・コロナウイルスパンデミックにも,漢方の有効性が期待されている。しかしその力を十分に引き出すには,十分なレベルの知識のもと方剤を適正に使用することの重要性が,今回歴史を振り返ったことにより再認識させられた。
3 0 0 0 OA 学生の所属大学・学部の特性からみたスポーツライフ実態と課題
- 著者
- 望月 拓実 柴田 紘希 横山 剛士 川崎 登志喜 中路 恭平
- 出版者
- 日本体育・スポーツ経営学会
- 雑誌
- 体育・スポーツ経営学研究 (ISSN:24323462)
- 巻号頁・発行日
- pp.370001, (Released:2023-03-02)
- 参考文献数
- 30
Due to the increasing enrolment in universities and their role as a hub for lifelong participation in sports, the improvement of the sports life of university students is now positioned as an important issue. A review of previous studies on the sports life of university students identified the following issues: the existence of a quarter of Non-exercisers, half of those who are members of an athletic club exercise six or more days a week, and half of those who are members of a circle use off-campus facilities and bear the financial and time costs. However, no studies have examined these issues according to the characteristics of the university or department to which the students belong. Therefore, the purposes of this study were to examine the sports life of students according to the characteristics of their universities and faculties, and to clarify the details of their actual conditions and issues.A questionnaire survey was conducted at 41 universities across the country, asking questions about current exercise frequency, barriers to exercise, current exercise status, and venues and costs of activity. The participants were categorized by athletic environment into “Members of an athletic club”, “Members of a circle”, “Other exercisers” and “Non-exercisers”. Further analysis was conducted based on three characteristics: the “Establisher”, “University size”, and “Faculty”.As a result of the analysis, the following four points were identified as the actual conditions and issues in the sports life of university students.1: Non-exercisers are most common among students at large universities, public universities, and general faculties.2: There was a high frequency of physical education and sports department activities at medium and small universities.3: Circle students at large universities and private universities do not have access to on-campus facilities, and the cost of their activities is high.4: Students at small universities, public universities and general faculties feel that they do not have the opportunity to exercise.
3 0 0 0 OA 国学者長野義言の基礎的研究
3 0 0 0 IR 地域共生社会と自立した地域づくり
- 著者
- 須賀 由紀子
- 出版者
- 実践女子大学
- 雑誌
- 実践女子大学生活科学部紀要 = Bulletin of Jissen Women's University Faculty of Human Life Sciences (ISSN:24336645)
- 巻号頁・発行日
- no.57, pp.79-89, 2020-03-09
少子高齢化・人口減少社会の到来の中で、我が国が目指すべき社会モデルとして「地域共生社会」が掲げられ、どのように地域の施策を進めていけばよいのかが問われている。この問題に対して、地域福祉から得られる知見は何かを問いとして、「ケアリングコミュニティ」に関しての検討を行った。その結果、福祉教育および地域の居場所の必要性、「社会包摂」の概念の必要性、相互実現的自立観の必要性が視点として得られた。総合考察として、ケアリングコミュニティを作っていくには、これら3 つの必要性を実現していくことが不可欠で、中でも、「地域の居場所」を数多く地域の中で作りだし有機的に結ぶことが、ケアリングコミュニティの現実化に希求されること、そして、多様な「地域の居場所」との関わりは、個人の自立生活を高める上でも必要であり、これからの自立した地域社会づくりともなることを示した。
3 0 0 0 OA 大学政策に対する世論の構造と形成
本研究は、高等教育政策の世論の構造と形成機能を萌芽的に解明することにあり、全省庁の政策案件のパブリック・コメントデータベースをe-GOVを基に作成した上で、文科省に考察対象を絞り、局別のパブリック・コメントの構造を明らかにした。局により案件数や公募タイプ別の案件分布が異なり、意見数についても公募タイプの相違を超えて、局別の特性の存在が析出された。他方で、意見の反映状況は、行政手続法に基づく案件に限定されてしまい、意見のまとめ方も定型的なフォーマットが存在しておらず、マクロの量的な分析から得られる知見に一定の意義はあるものの、意見反映までを見据えた考察には限界があることも、改めて明らかとなった。
3 0 0 0 IR 津軽信政の修史事業と「東日流記」の成立--岩見文庫本と高屋家旧蔵本の比較研究
- 著者
- 工藤 大輔
- 出版者
- 弘前大学國史研究会
- 雑誌
- 弘前大学国史研究 (ISSN:02874318)
- 巻号頁・発行日
- no.126, pp.27-35, 2009-03
- 著者
- 園山 繁樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.55-66, 2008-09-30 (Released:2019-04-06)
学校に関連する場面で複数の嫌悪的体験をしたことを契機に登校拒否を示した小学2年生女児1名を対象に、母親を不安拮抗刺激とした段階的再登校法を中心とした介入を行い、その効果を検討した。本児の場合、登校拒否の契機として、友人の転校、不審者との接触、雨中での重い荷物を持っての下校など複数の嫌悪的体験が推測された。具体的な介入としては、母親面接、母親が付き添っての登下校と段階的な授業参加、授業参加記録表の活用、小学校の不登校検討委員会との協議などを行った。その結果、約1年間の介入によって、本児一人での登下校および全授業参加が可能となり、登校拒否行動はみられなくなった。4年間のフォローアップにおいても特別な問題はなく、病欠も含め欠席は1日もなかった。複数の嫌悪的体験が契機となった登校拒否について、持続的な不安反応に留意した段階的な再登校支援の必要性が示唆された。
3 0 0 0 OA 聴覚障害利用者からみた電話リレーサービスに関する調査研究
- 著者
- 中野 聡子 新海 晃 二神 麗子 金澤 貴之 NAKANO Satoko SHINKAI Akira FUTAGAMI Reiko KANAZAWA Takayuki
- 出版者
- 群馬大学共同教育学部
- 雑誌
- 群馬大学共同教育学部紀要. 人文・社会科学編 (ISSN:27581136)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, pp.187-206, 2023-01-27
- 著者
- 伊藤 雄 松本 尚 ⼭⼝ 聖太 ⽯⽥ 知也 末永 直樹 ⼤泉 尚美
- 出版者
- 一般社団法人 日本運動器理学療法学会
- 雑誌
- 運動器理学療法学 (ISSN:24368075)
- 巻号頁・発行日
- pp.202105, (Released:2022-07-08)
- 参考文献数
- 35
【⽬的】鏡視下腱板修復術(以下,ARCR)後に装具固定中に退院することが再断裂率,健側・患側肩関節機能に与える影響を調査すること。【⽅法】ARCR 術後の65 歳以上の⼥性91 名を装着固定中に⾃宅退院した退院群48 名,装具除去まで⼊院を継続した⼊院群43 名に分類し,術前および術後各時期における肩関節可動域,等尺性筋⼒,肩機能スコア,再断裂率を健側,患側共に⽐較検討した。【結果】再断裂率および術後3 ヵ⽉の他動屈曲,外転,2nd 外旋可動域を除いた肩関節可動域において術前,術後各時期で両群間に有意差を認めず,術後6,12 ヵ⽉時の肩・肘関節筋⼒,肩機能スコアにおいて退院群で有意に良好であった。【結論】安全なADL,セルフエクササイズ実施⽅法を指導して装具固定中に退院することは,再断裂,関節可動域制限のリスクを増加することなく,良好な肩関節機能を得ることができる可能性が⽰された。
3 0 0 0 OA 英米の俗信(1)
- 著者
- 小泉 直
- 出版者
- 愛知教育大学
- 雑誌
- 愛知教育大学研究報告. 人文・社会科学編 (ISSN:18845177)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, pp.43-50, 2012-03-01
3 0 0 0 OA 石川啄木 : 短歌にみる生と死の表現
Takuboku Ishikawa was a poetic genius during the Meiji Era. He showed outstanding intelligence from childhood. He displayed talent as a poet in his teenage years and moved to Tokyo, intending to become a novelist. In this, however, he did not succeed and experienced a serious setback. During this time of living in poverty, however, he produced his revolutionary collection of poems, included in A Handful of Sand. Yet, at the young age of 27, he died of tuberculosis. In this article, Takuboku Ishikawa’s life will be reviewed, focusing on how his psychological conflicts developed. The author also discusses how these conflicts influenced Ishikawa’s works through an examination of his diaries and tanka.The results of this study show that Ishikawa did not write tanka for his own personal benefit. For him, tanka were reflections of his subconscious self, a type of creative regression. In his tanka, he honestly wrote about his existence. That is, the tanka are an “egotistic” expression of himself as a special person, and his feelings of anger and rebellion that he was not esteemed by the world. Through his tanka, Ishikawa was able to face his weak and ugly sides for the first time.During the period when Ishikawa was unable to write novels, there were many references to death in his work. However to him, death may have held the meaning of an escape from reality. For Ishikawa, illness and death were almost the same as sleep. The action of sleeping could be considered an extreme escape from reality. However, after Ishikawa abandoned novels, he came to face reality; he gradually became grounded to the real world through critique, and he began to seriously confront the circumstances of his life. However, in the middle of this transition, he died of an illness.
3 0 0 0 OA マルコフスイッチングモデルのマクロ経済・ファイナンスへの応用
- 著者
- 沖本 竜義
- 出版者
- 一般社団法人 日本統計学会
- 雑誌
- 日本統計学会誌 (ISSN:03895602)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.137-157, 2014-09-26 (Released:2015-04-30)
- 参考文献数
- 51
- 被引用文献数
- 1
経済やファイナンスデータの中には,景気循環や政策の変更などに応じて,挙動が大きく変化しているようなデータが少なくない.本稿では,そのようなデータを分析するための強力なツールのひとつであるマルコフスイッチングモデルを概観する.具体的には,モデルを簡単に紹介した後,マルコフスイッチングモデルの重要な要素であるマルコフ連鎖について述べ,具体例を用いて解釈の仕方を説明する.続いて,マルコフスイッチングモデルの統計的推測問題について触れ,最後に,マクロ経済やファイナンスへの応用例を紹介する.
3 0 0 0 古代の秘儀と場の記憶 : ペルーの古代文明と遺跡
- 著者
- 木村 はるみ 小林 夕希
- 出版者
- 山梨大学教育人間科学部
- 雑誌
- 山梨大学教育人間科学部紀要 (ISSN:18825923)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.20, pp.136-148, 2011
3 0 0 0 OA スポーツファンのライバル観とその認知理由 : Bリーグ・クラブのサポーターを対象として
- 著者
- 内田 好治 舟橋 弘晃 澤井 和彦 間野 義之
- 出版者
- Japan Society of Sports Industry
- 雑誌
- スポーツ産業学研究 (ISSN:13430688)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.2_195-2_206, 2020 (Released:2020-04-20)
- 参考文献数
- 27
Opposing clubs involve not only sports competitors but also economic partners that are likely to influence fan behavior. Therefore, it is important to understand rivalry in team sports to ensure the financial viability of the leagues and teams. However, much of the study on rivalry in sports has focused either on professional or high-level men’s collegiate team sports in the US. The research in this study explored the perceptual rivalry of a Japanese professional sport club’s supporters against other clubs and the reasons for the rivalry. Data were collected via an email survey of the official fan club members of Alvark Tokyo, a Japanese professional basketball team in the B.League (N=377). Respondents were asked to rank up to five of the biggest rival clubs in the B.League first division and assess their subjective intensity of rivalry on a 100-point direct rating scale (RP). Next, they were asked to answer the reasons for their rivalry perception, based on 17 rivalry element items. The intensity of the rivalry against each club was calculated as the average value of the RP. A Kruskal-Wallis test was used to assess the differences in the reasons why each club was recognized as the biggest rival. The Chiba Jets was selected as the biggest rival team (RP=84.0), followed by the Tochigi Brex (RP=82.1), the Ryukyu Golden Kings (RP=61.2), the Kawasaki Brave Thunders (RP=56.0), the Seahorses Mikawa (RP=27.4), and the Sunrockers Shibuya (RP=16.9). The Kruskal-Wallis test indicated that the reasons for supporters’ perception of rivalry differed significantly across the six clubs. The empirical results suggested that the rivalry against other clubs may be amplified by the overlapping of conditions such as comparable competitiveness, geographical proximity, and historical relationships. Some practical implications are provided.
- 著者
- 小柳津 和博 野々山 貴
- 出版者
- 日本リハビリテイション心理学会
- 雑誌
- リハビリテイション心理学研究 (ISSN:03895599)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.51-63, 2022-11-30 (Released:2023-02-20)
- 参考文献数
- 25
近年,各地でインクルーシブ保育の実践が進められているが,子ども同士の関わり合いを促す保育者の専門性を一般化することは難しいとされてきた。本研究では,インクルーシブ保育において子ども同士の関わり合いを成立させるために必要となる保育者の専門性について,実際の保育場面を分析することで明らかにすることを目的とした。対象となる施設で,重症心身障害児と他児が関わり合う場面をエピソードとして取り出し,重要語句を選定した。重要語句から保育者の専門性に関わる概念を抽出した。分析の結果,インクルーシブ保育に必要な保育者の専門性として8項目の説明概念が抽出され,これらは創造力として4種類に構成された。このことから,インクルーシブ保育において子ども同士の関わり合いを促す保育者の専門性に,4種類の創造力があると考察した。