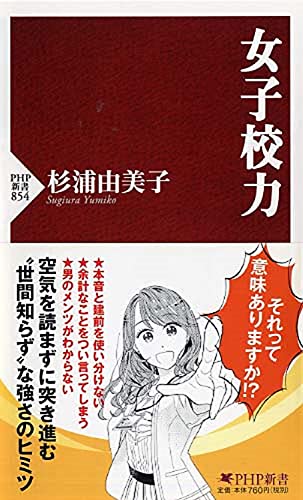1 0 0 0 IR 教職課程で教育心理学を学ぶ意味--教員採用試験問題とその対策から考える
- 著者
- 杉浦 健
- 出版者
- 近畿大学教職教育部
- 雑誌
- 近畿大学教育論叢 (ISSN:18809006)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.43-57, 2012-03
1 0 0 0 IR 大学キャンパスにおける環境保全活動と連携した実践教育とテキスト作成
- 著者
- 日野 貴文 窪田 千穂 杉浦 晃介 金子 正美
- 出版者
- 酪農学園大学
- 雑誌
- 酪農学園大学紀要. 自然科学編 (ISSN:0388001X)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.119-126, 2014-04-20
- 著者
- 佐藤 德 杉浦 義典
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.6, pp.605-611, 2014
- 被引用文献数
- 7
Previous studies showed that incidental feelings of disgust could make moral judgments more severe. In the present study, we investigated whether individual differences in mindfulness modulated automatic transference of disgust into moral judgment. Undergraduates were divided into high- and low-mindfulness groups based on the mean score on each subscale of the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ). Participants were asked to write about a disgusting experience or an emotionally neutral experience, and then to evaluate moral (impersonal vs. high-conflict personal) and non-moral scenarios. The results showed that the disgust induction made moral judgments more severe for the low "acting with awareness" participants, whereas it did not influence the moral judgments of the high "acting with awareness" participants irrespective of type of moral dilemma. The other facets of the FFMQ did not modulate the effect of disgust on moral judgment. These findings suggest that being present prevents automatic transference of disgust into moral judgment even when prepotent emotions elicited by the thought of killing one person to save several others and utilitarian reasoning conflict.
1 0 0 0 ノンストップのための条件
- 著者
- 杉浦 和史
- 雑誌
- あたらしい眼科 = Journal of the eye (ISSN:09101810)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.6, pp.811-812, 2012-06-30
1 0 0 0 復刊不死鳥 : 杉浦翠子戦中戦後歌誌
1 0 0 0 トムとジェリーの本 : なかよくけんかしな
- 著者
- 菅也寸志 杉浦邦一編
- 出版者
- SCM
- 巻号頁・発行日
- 1990
- 著者
- 三科 正樹 杉浦 彰彦
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. RCS, 無線通信システム
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.530, pp.7-14, 1997-02-20
本研究では、普遍同期方式の微弱電波スペクトル拡散通信方式を用いて、混信の少ない空きTVチャネル帯域の有効利用を検討する。ここでは、放送波中のカラーバースト信号を用いた普遍同期方式を提案し、試作装置により2チャネル帯域を用いた双方向通信を実現する。初めにCATV等の有線系を想定して実験を行い、つぎに無線系において室内電波通信について評価を行う。試作装置を用いて微弱電波データ通信を評価した結果、基準信号送信方式と比較した場合で、約12dB妨害余裕度が向上した。
1 0 0 0 中心地理論のナチ・ドイツ国土計画への応用に関する研究
1.ナチ・ドイツの国土計画に中心地理論が応用されていく最大の契機は、国土調査全国共同体研究所長のMeyer(ベルリン大学)の中心地理論への注目であったが、学位論文提出後のChristallerは、フライブルク大学のMetzらの急進的民族主義(volkisch)地理学者たちとつながりを持つようになり、それも媒介として、ナチ・ドイツの国土計画に参画していった。2.人口の不均等分布の解消のみならず、原料・食糧の効率的な調達・供給も目ざしていたナチ・ドイツの国土計画論では、国土全域の階層的編成が求められていたので、中心地に加え、開拓集落、工業集落をも構成要素とするChristallerの集落システム論(1938年のアムステルダムIGCで発表)は、その要請に答えうるものであった。3.1939年9月のポーランド占領後、東方占領地の集落再編計画に中心地理論は応用されようとしたが、ポーランド語文献によれば、それに先立ち、1937年にはポーランドと国境を接するシュレージェン地方において、防衛上の観点から、中心地網の整備案が、国土調査全国共同体研究所の命を受けたブレスラウ大学の地理学者たちによって作成されていた事実が判明した。4.関連文献の引用分析だけからは、中心地理論の他の学問分野の集落配置プランへの影響を厳密に捉えることができないので、他の学問分野の関連文献を詳細に読み込む必要がある。5.ナチ・ドイツに受容された中心地理論が、1939年以降、占領地ポーランドで実際に応用されていく過程については、Christallerの1940年代の論文等を検討することで解明されるであろう。
1 0 0 0 OA 卵黄血管遺残によるイレウスの1例
- 著者
- 木村 昌弘 小林 俊三 田中 宏紀 江口 武史 工藤 淳三 杉浦 弘典 杉戸 伸好
- 出版者
- 一般社団法人日本消化器外科学会
- 雑誌
- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.9, pp.1729-1732, 2000-09-01
- 被引用文献数
- 2
症例は64歳の男性.腹痛を主訴に近医を受診し, 腹痛が増強, 嘔吐も出現したため当院緊急入院.来院時腹部は平坦, 軟であったが全体に圧痛を認めた.腹部単純X線, 小腸造影にて絞扼性イレウスを疑い開腹術を施行した.術中所見は, 回盲弁より約5cmの回腸に狭窄を認め, 狭窄した回腸の腸間膜前葉および後葉にそれぞれ索状物が存在した.索状物の切除により狭窄は解除された.病理検査で, 索状物内の脂肪織に動静脈を認め, 卵黄動静脈の遺残によるmesodiverticular bandと診断した.左右の卵黄血管の遺残によるイレウスの本邦報告例は今回検索した範囲では本症例を含めて2例のみで, 極めてまれと考えられた.
- 著者
- 原 耕平 河野 茂 門田 淳一 朝野 和典 平潟 洋一 前崎 繁文 中富 昌夫 浅井 貞宏 水兼 隆介 奥野 一裕 福島 喜代康 伊藤 直美 井上 祐一 小池 隆夫 大西 勝憲 大道 光秀 山田 玄 平賀 洋明 渡辺 彰 貫和 敏博 武内 健一 新妻 一直 柳瀬 賢次 友池 仁暢 中村 秀範 加藤 修一 佐田 誠 池田 英樹 板坂 美代子 荒川 正昭 和田 光一 原口 通比古 星野 重幸 五十嵐 謙一 嶋津 芳典 近 幸吉 瀬賀 弘行 関根 理 鈴木 康稔 青木 信樹 滝沢 敬夫 兼村 俊範 竹村 尚志 長尾 光修 濱島 吉男 坂本 芳雄 坂田 憲史 豊田 丈夫 大角 光彦 小林 宏行 河合 伸 酒寄 享 杉浦 宏詩 押谷 浩 島田 馨 佐野 靖之 荒井 康男 北條 貴子 小川 忠平 柴 孝也 吉田 正樹 岡田 和久 佐藤 哲夫 古田島 太 林 泉 宍戸 春美 松本 文夫 桜井 磐 小田切 繁樹 鈴木 周雄 綿貫 祐司 高橋 健一 吉池 保博 山本 俊幸 鈴木 幹三 下方 薫 川端 原 長谷川 好規 齋藤 英彦 酒井 秀造 西脇 敬祐 山本 雅史 小笠原 智彦 岩田 全充 斉藤 博 三木 文雄 成田 亘啓 三笠 桂一 二木 芳人 河端 聡 松島 敏春 副島 林造 澤江 義郎 高木 宏治 大泉 耕太郎 木下 正治 光武 良幸 川原 正士 竹田 圭介 永正 毅 宇都宮 嘉明 秋山 盛登司 真崎 宏則 渡辺 浩 那須 勝 橋本 敦郎 後藤 純 河野 宏 松倉 茂 平谷 一人 松本 亮 斎藤 厚 健山 正男 新里 敬 伊志嶺 朝彦 上地 博之 比嘉 太 仲本 敦 我謝 道弘 中島 光好
- 雑誌
- 日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy (ISSN:13407007)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.11, pp.901-922, 1997-11-25
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 19
1 0 0 0 OA 国際関係論における内発性・土着性・自立性の基礎的研究
- 著者
- 初瀬 龍平 野田 岳人 池尾 靖志 堀 芳枝 戸田 真紀子 市川 ひろみ 宮脇 昇 妹尾 哲志 清水 耕介 柄谷 利恵子 杉浦 功一 松田 哲 豊下 楢彦 杉木 明子 菅 英輝 和田 賢治 森田 豊子 中村 友一 山口 治男 土佐 弘之 佐藤 史郎 上野 友也 岸野 浩一 宮下 豊
- 出版者
- 京都女子大学
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2012-04-01
本研究の目的は、戦後日本における国際関係論の誕生と発展を、内発性・土着性・自立性の視点から、先達の業績の精査を通じて、検証することにあった。研究成果の一部は、すでに内外の学会や公開講座などで報告しているが、その全体は、『日本における国際関係論の先達 -現代へのメッセージ-(仮)』(ナカニシヤ出版、2016年)として集大成、公開する準備を進めている。本書は、国際政治学(国際政治学、政治外交史)、国際関係論(権力政治を超える志向、平和研究、内発的発展論、地域研究)、新しい挑戦(地域研究の萌芽、新たな課題)に分けた先達の業績の個別検証と、全体を見通す座談会とで構成されている。
1 0 0 0 OA 室温付近の固相反応によるセリア-ジルコニア固溶体の合成
- 著者
- 須田 明彦 神取 利男 右京 良雄 曽布川 英夫 杉浦 正洽
- 出版者
- 公益社団法人日本セラミックス協会
- 雑誌
- 日本セラミックス協会学術論文誌 : Nippon Seramikkusu Kyokai gakujutsu ronbunshi (ISSN:18821022)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, no.1257, pp.473-477, 2000-05-01
- 被引用文献数
- 9 19
The surprisingly low temperature (〜323 K) synthesis of the ceria-zirconia solid solution upon milling ceria powder with zirconia mill and zirconia balls (in ethanol and/or water) was studied. Solid solutions up to 60 mol%ZrO_2 were obtained, whose formation was proved to result from solid phase reaction between ceria and zirconia powders, enhanced by contact stress (either shear or compressive one). Furthermore, the occurrence of large plastic deformation, breaking and mutual combining was found on the ceria powder before and after solid solution. The grain size of ceria-zirconia solid solution was ≨20 nm, which would cause on easy rearrangement of low diffusion atoms of cerium and zirconium to form the solid solution at such a low temperature. In addition, the possible existence of a solid solution for which the migration of the constituents is much faster (or the stability of the solid at the composition is much higher) than that of other composition, was suggested around 50 mol%CeO_2-50 mol%ZrO_2.
1 0 0 0 OA 左肝管から発生した真の癌肉腫の1切除例
- 著者
- 木内 亮太 杉浦 禎一 岡村 行泰 水野 隆史 金本 秀行 前平 博充 絹笠 祐介 坂東 悦郎 寺島 雅典 上坂 克彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器外科学会
- 雑誌
- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.34-41, 2014-01-01 (Released:2014-01-21)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1 3
症例は75歳の男性で,検診の採血で肝機能異常を指摘され,前医で左肝管原発の肝門部胆管癌と診断されたため,当院紹介受診となった.造影CTでは,左肝管から左右肝管合流部にかけて造影効果を伴う壁肥厚と,左葉の肝内胆管の拡張を認めた.内視鏡的逆行性胆管造影では,左右肝管合流部に陰影欠損を認めた.肝門部胆管癌と術前診断し,肝左葉・尾状葉切除,肝外胆管切除再建術を施行した.切除標本では,左肝管から左右肝管合流部に発育する21 mm大の乳頭状腫瘍を認めた.組織学的には,一部扁平上皮癌成分を伴う腺癌成分と,紡錘形細胞の増殖および骨形成を認める肉腫成分が混在していた.免疫組織学的に,肉腫領域は上皮系マーカーであるAE1/AE3が陰性,間葉系マーカーであるvimentinが陽性であった.以上より,左肝管原発の真の癌肉腫と診断した.術後1年経過した現在,無再発生存中である.
1 0 0 0 OA 新潟県の大輪ギクに発生したキクわい化ウイロイドによる病害
- 著者
- 杉浦 広幸 花田 薫
- 出版者
- 園芸学会
- 雑誌
- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.432-438, 1998-05-15
- 被引用文献数
- 4 13
新潟県で特定の大輪ギク品種に発生した特異的な生育障害, すなわち草丈のわい化, 開花の1∿2週間の遅延, 花型の丁字型化などを起こすCSVdの性質を調査した.'ミスルトー'を用いた生物検定, およびRNAのポリアクリルアミドゲル電気泳動による解析の結果, 本症がCSVdによるものであると確定した.発病株から発生した冬至芽からのCSVdの無病化は, 2品種中1品種で認められ50∿61%の冬至芽が無病徴であった.汁液接種によるCSVdの伝染性については品種間差があり, 調査した10品種中, 5品種はCSVd抵抗性であった.土壌伝染性は認められなかった.塩基配列を解析した結果, 2か所でイギリス型と異なっていたが, 塩基数は同じであった.
- 著者
- 杉浦 俊彦 横沢 正幸
- 出版者
- 園芸学会
- 雑誌
- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.1, pp.72-78, 2004-01-15
- 被引用文献数
- 14 44
リンゴおよびウンシュウミカンの栽培環境に対する地球温暖化の影響を年平均気温の変動から推定した.果樹栽培に有利な年平均気温として解析対象とした温度域はリンゴでは6〜14℃およびこれよりやや狭い7〜13℃,ウンシュウミカンでは15〜18℃である.将来の気候の予測データとしては「気候変化メッシュデータ(日本)」を用い,約10×10 km単位のメッシュで解析を行った.その結果,リンゴ,ウンシュウミカンとも栽培に有利な温度帯は年次を追うごとに北上することが予想された.リンゴでは,2060年代には東北中部の平野部までが現在よりも栽培しにくい気候となる可能性が示唆され,東北北部の平野部など現在のリンゴ主力産地の多くが,暖地リンゴの産地と同等の気温になる,一方,北海道はほとんどの地域で栽培しやすくなる可能性が示唆された.ウンシュウミカンでも2060年代には現在の主力産地の多くが現在よりも栽培しにくい気候となる可能性が示唆されるとともに西南暖地の内陸部,日本海および南東北の沿岸部など現在,栽培に不向きな地域で栽培が可能になることが予想された.以上のように地球温暖化は今世紀半ばまでにわが国のリンゴおよびウンシュウミカンの栽培環境を大きく変化させる規模のものである可能性が示された.
- 著者
- 時実 象一 杉浦 友哉
- 出版者
- 情報知識学会
- 雑誌
- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.86-92, 2010-05-15 (Released:2010-07-10)
Web 上のホームページを収集して保存・公開する Web アーカイブは最近注目を集めている。米国の Internet Archive の Wayback Machine はこの分野のパイオニアで、1996 年からわが国を含め世界の Web ページを収集して公開している。ここに収集されているわが国の数機関のホームページを経年的に比較調査し、それら機関の情報発信の状況を分析した。
1 0 0 0 OA 胆管小細胞癌の1切除例
- 著者
- 山田 英貴 金井 道夫 中村 從之 大場 泰洋 濱口 桂 小松 俊一郎 鷲津 潤爾 桐山 真典 矢野 孝 杉浦 浩
- 出版者
- 一般社団法人日本消化器外科学会
- 雑誌
- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.51-56, 2004-01-01
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 7
症例は80歳の男性.2001年10月24日から食欲不振と尿濃染を自覚し,近医を受診.CTで肝内胆管の拡張と総胆管内の腫瘤像を認め,当院へ紹介.ERCP,MRCP,PTBDチューブからの胆管造影で中部胆管に境界明瞭な乳頭状の腫瘍を認め,PTCS直視下生検で低分化腺癌と診断.以上より中部胆管の乳頭型胆管癌と診断し胆管切除術・リンパ節郭清を行った.病理組織学的には核/細胞比が高い小型の細胞がシート状,充実性に増殖する腫瘍であり,chromogranin A染色陽性で,small cell carcinoma (pure type)と診断した.術後合併症なく,第19病日に退院したが,術後9か月目の2002年9月,肝転移のため再発死亡した.胆管小細胞癌の報告例は欧米などの報告を含め11例と極めてまれである.しかし,術前の画像診断で乳頭型の胆管癌を認め,生検で低分化腺癌を認めた場合には本症を考慮する必要があると思われた.
1 0 0 0 OA 占領期外国語教育政策の審議過程について : 教育刷新委員会第11特別委員会会議録を中心に
- 著者
- 杉浦 隆
- 出版者
- 大阪樟蔭女子大学
- 雑誌
- 大阪樟蔭女子大学研究紀要 (ISSN:21860459)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.103-114, 2013-01-31
占領期における様々な改革の中で教育改革は最も大きいものの一つである。この改革にはCIEと教育刷新委員会が大きな役割を果たした。その中で「文化問題」を扱った、第11特別委員会の会議録を通して、戦後の外国語教育政策に関する議論を概観し、いくつかの問題提起を行う。