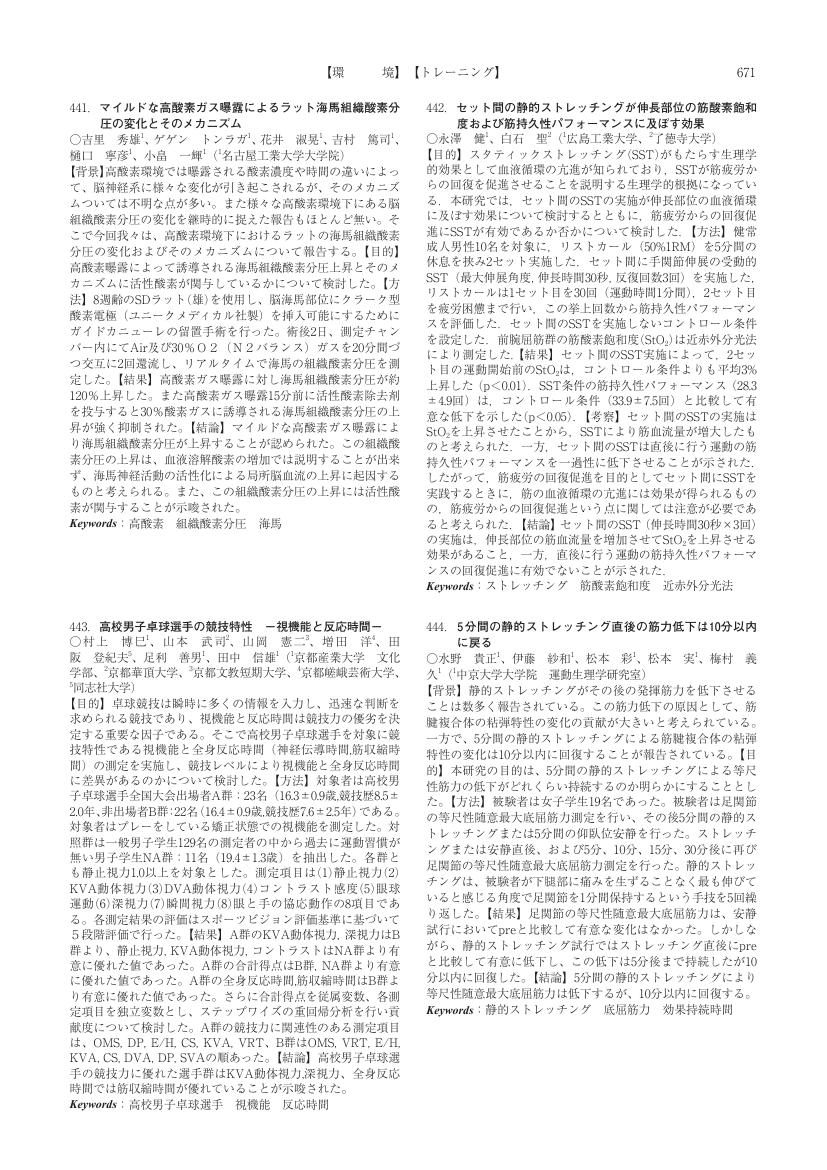2 0 0 0 OA 採録される論文の書き方 ——誌上チュートリアル——
- 著者
- 瀬田 和久 桑原 千幸 仲林 清
- 出版者
- 教育システム情報学会
- 雑誌
- 教育システム情報学会誌 (ISSN:13414135)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.82-93, 2021-04-01 (Released:2021-04-01)
- 参考文献数
- 16
This tutorial explains principles of writing papers for transactions of JSiSE. In this paper, we first roughly classify the research conducted in the research field of information and systems in education, introduce the paper categories of JSiSE, and explain the guidelines for selecting the paper category. Then, we will introduce principles for clarifying research questions, which are important points for papers to be accepted, and introduce concrete examples of research questions by picking up from practical papers that have been accepted. In addition, by introducing the editorial board’s underlying philosophy of reviewing papers in more detail, we hope authors utilize it for writing papers.
2 0 0 0 OA 人はなぜ化粧をするのか
- 著者
- 鈴森 正幸
- 出版者
- 日本香粧品学会
- 雑誌
- 日本香粧品学会誌 (ISSN:18802532)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.27-35, 2018-03-31 (Released:2019-03-31)
- 参考文献数
- 19
Why people wear make-up is a fundamental and wide-ranging question. Make-up and skin care have evolved over the course of time through the influence of society and culture. Having undergone many changes, the term “make-up” has become a word that encompasses numerous meanings and concepts. In an attempt to answer the question why people wear make-up, this paper first analyzes what constitutes make-up from the viewpoint of make-up activities and the meaning of make-up, then it traces the changes in what comprises make-up in Japanese cosmetic culture. Lastly it examines modern make-up from three perspectives: the allure of women’s appearance, the effects of make-up, and the interpretation of beauty culture.
2 0 0 0 OA カント「教育論」の人間観 特にルソーとの関連において
- 著者
- 原田 茂
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1965, no.12, pp.15-27, 1965 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 23
“Nature” is the central concept in the education of the Enlightenment and the task of education is to foster the nature with which man is endowed according as children grow up. Here is seen a strong trust of the nature of man, while Kant, who draws a strict line between the empirical world of phenomena and the transcendental world of ideas, takes a different standpoint from that of the Enlightenment. In Kantian philosophy the pure forms of reason and pure laws of will are enthroned with the result that the task of education is not to develop natural endowments but to discipline them through education and lead them into the transcendental world. Man, a personality provided with reason and autonomous will, is an existence which stands on a completely different level from that on which other animals crawl, and it is incumbent on man to realize this dignity of his personality. On the other hand, however, Kant is strongly influenced by Rousseau as far as his view of education is concerned, and his belief in the goodness of human natnre forms the keynote of his view of education. Moreover, his concept of human liberty and equality are to be clearly traced back to Rousseau. The present writer tries to consider Kant's view of education as the consequence of his philosophy and at the same time in reference to Rousseau.
2 0 0 0 OA 公州丹芝里横穴墓群発掘調査概要
- 著者
- 池 ミン周
- 出版者
- 一般社団法人 日本考古学協会
- 雑誌
- 日本考古学 (ISSN:13408488)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.19, pp.115-127, 2005-05-20 (Released:2009-02-16)
朝鮮半島の公州丹芝里横穴墓遺跡では,23基の横穴墓が群集して発見された。残存状態が非常に良好で構造が明確であり,副葬遺物と被葬者の人骨などが完全に残っている。これは朝鮮半島の横穴墓の構造的特徴と築造時期はもちろん,日本考古学界でこれまで模索されてきた日本列島の横穴墓の起源問題をはじめとする古代韓日関係研究に画期的な資料となる。横穴墓の築造時期は副葬された土器類の型式的特徴を通して大まかな年代幅を把握することができるが,蓋杯や三足器などの遺物型式をみると,横穴墓はおよそ百済熊津期前半(5世紀後半)にわたって造営されたものと把握される。一方,公州丹芝里横穴墓の構造的特徴は日本列島の初期横穴墓である福岡県行橋市竹並・大分県上ノ原などの北部九州一円に集中して分布している横穴墓と類似する。その時期は5世紀後半~6世紀前半頃とされており,今まで知られる日本列島の横穴墓の中では朝鮮半島系遺物が副葬される例が少なくない。このような事実はこれまでベールに包まれていた日本列島の横穴墓の起源問題を解明することができる極めて重要な資料となり,今回の丹芝里横穴墓群の存在とともに,横穴墓の百済地域起源の可能性を積極的に検討する契機となるものである。
2 0 0 0 OA 日本建築学会鉄筋コンクリート造建築物の耐久設計施工指針 (案) ・同解説の概要
- 著者
- 桝田 佳寛 野口 貴文 兼松 学
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学 (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.11-18, 2005-02-01 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 6
2004年3月, 日本建築学会「鉄筋コンクリート造建築物の耐久設計施工指針 (案) ・同解説」が発刊された。本指針は, 建築学会の材料施工分野において初めて性能設計に具体的に踏み込み, 今後の材料施工分野の雛型となるべく性能指向型の指針として提案したものである。具体的には, 性能規定としての耐久性能の整理と理論体系の構築を行い, 「性能検証型一般設計法」および「標準仕様選択型設計法」, 「性能検証型特別設計法」の3つの設計ルートから成る耐久設計の枠組みを提案した。また, 構造体および部材の限界状態の設定方法を性能論的な観点からまとめ, 鉄筋, コンクリート, 仕上材など各材料の限界状態との関係から定義した点で意義深い。
2 0 0 0 OA トレーニング
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.6, pp.671-684, 2012 (Released:2012-12-28)
- 著者
- 山本 (前田) 万里 永井 寛 江間 かおり 神田 えみ 岡田 典久 安江 正明
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.12, pp.584-593, 2005 (Released:2007-04-13)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 8 9
A double-blind clinical study was carried out on subjects with Japanese cedar pollinosis for the evaluation of the effects and safety of ‘Benifuuki’ green tea, which contains epigallocatechin-3-O-(3-O-methyl)-gallate (O-methylated catechin), and a combination of ‘Benifuuki’ green tea and ginger extract, with ‘Yabukita’ green tea as a placebo. First, the effect of the combination of ‘Benifuuki’ green tea and various vegetable extracts on cytokine production inhibition was investigated using mast cells ; the simultaneous use of ‘Benifuuki’ green tea and ginger extract was found to suppress cytokine (TNF-α or MIPI-α) production to a remarkable extent. Subjects were given 1.5 g of ‘Benifuuki’ green tea, ‘Benifuuki’ green tea containing 30 mg of ginger extract, or ‘Yabukita’ green tea with water twice every day for 13 weeks. As cedar pollen scattering increased, the severity of pollinosis symptoms among the groups was observed to increase in the following order : placebo group>’Benifuuki’ group>’Benifuuki’ and ginger group. Eleven weeks after the beginning of treatment, during the most severe cedar pollen scattering period, symptoms of runny nose and itchy eyes were significantly relieved among the ‘Benifuuki’ group compared with the placebo group (p<0.05). In the ‘Benifuuki’ and ginger group, runny nose, itchy eyes and nose symptom scores were significantly reduced at the eleventh week, and nasal congestion, sore throat and nose symptom medication scores were significantly reduced at the thirteenth week compared with the placebo group. Among all test groups, hematological examination, general biochemical examination, determination of total IgG, CMV antibody titer, and serum iron content, and interviews throughout the intake period found no changes related to clinical problems. These results suggest that intake of ‘Benifuuki’ green tea over one month is useful in reducing some of the symptoms of Japanese cedar pollinosis, and did not affect normal immune response in subjects with Japanese cedar-pollinosis. It was also found that the addition of ginger extract enhanced the effect of ‘Benifuuki’ green tea.
2 0 0 0 OA 親密な関係における特別観が当事者たちの協調的・非協調的志向性に及ぼす影響
- 著者
- 相馬 敏彦 浦 光博
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.1-16, 2009 (Released:2009-08-25)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 2 1 2
本研究では,親密な関係における特別観が関係の相手に対する行動にどのような影響を及ぼすのかを検討した。大学生474名を対象とする調査研究を行った。親密な関係での特別観は関係内での協調的な志向性を高め,他方非協調的な志向性を抑制することが示された。さらに,特別観が協調的・非協調的志向性に及ぼす影響は,相互依存諸変数(代替肢の質,満足度,投資量,コミットメント)が志向性に及ぼす影響と独立したものであることも示された。これらの結果より,親密な関係に対して強い特別観をもつ者は非協調的な行動がとれないことが示唆された。親密な関係における特別観がその当事者に不適応を生じさせる可能性について議論した。
2 0 0 0 OA 「国語科」の壊し方について ―― 国語・教科書と文学・作品 ――
- 著者
- 須貝 千里
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.21-36, 2015-04-10 (Released:2020-05-26)
① 本報告は、田中実氏とともに立ち上げ、おおよそ二五年余り取り組んできた「文学研究と国語教育研究(実践)の相互乗り入れ」という〈事業〉の一環としてなされる。② 問題を本大会・文学研究の部のテーマである「教科書と文学」に焦点化するならば、このテーマは「国語・教科書と文学・作品」というように把握し直されなければならない。このことによって、与えられたテーマの「問題提起」を掘り起こすことができるからである。とすると、包含する課題は次のようになる。「国語」と「文学」、「教科書」と「作品」、「国語」と「教科書」、「文学」と「作品」、「国語」と「日本語」、「教える本」と「学ぶ本」、「物語」と「小説」、「作品」と「テクスト」などなど、「古文」と「漢文」、「古文・漢文」と「現代文」、「散文」と「韻文」もあるか。さらに課題は細分化できるが、本報告ではそれらを網羅的に論ずる時間は与えられていない。大森荘蔵は「生活上の真偽の分類」を「世界観上の真偽の分類」としてとらえ直し、世界観の転換という課題を提起したが、私はここから浮上してくる問題との関わりで、「国語・教科書と文学・作品」について、総括的に問題提起したい。この提起は、「歴史教科書問題」よりも「国語教科書問題」の方がより根源的問題であることを明らかにしていくはずである。③ 本報告は、「国語科」の壊し方について、文学作品の教材価値とともに論ずる。そのことによって、「国語科」からの文学作品の排除、あるいは戦略的撤退論に対して、「国語科」に文学作品が居座り続けることの居心地の悪さ、この立場に立って「国語科」の壊し方とそのための諸課題を提起することになる。この提起は、ポストモダン思想の台頭によって解体されてしまった「読むこと」の根拠の再構築を〈原文〉の〈影〉の働きに着目することによって図り、〈近代の物語文学〉と〈近代小説〉の違いを明らかにし、〈主体〉の構築という課題に挑むことによって、文学研究と国語教育研究(実践)の新たな地平を切りひらくことを目指しているのである。なお、「文学研究と国語教育研究(実践)の相互乗り入れ」という〈事業〉自体が居座り続けることの居心地の悪さを前提にしている。
2 0 0 0 OA エキゾチックアニマルの生物学 (X)
- 著者
- 深瀬 徹
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.6, pp.368-371, 2006-06-20 (Released:2011-06-17)
- 参考文献数
- 5
2 0 0 0 OA 足趾が動的姿勢制御に果たす役割に関する研究
- 著者
- 加辺 憲人 黒澤 和生 西田 裕介 岸田 あゆみ 小林 聖美 田中 淑子 牧迫 飛雄馬 増田 幸泰 渡辺 観世子
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.199-204, 2002 (Released:2002-08-21)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 30 20
本研究の目的は,健常若年男性を対象に,水平面・垂直面での足趾が動的姿勢制御能に果たす役割と足趾把持筋力との関係を明らかにすることである。母趾,第2~5趾,全趾をそれぞれ免荷する足底板および足趾を免荷しない足底板を4種類作成し,前方Functional Reach時の足圧中心移動距離を測定した。また,垂直面における動的姿勢制御能の指標として,しゃがみ・立ちあがり動作時の重心動揺を測定した。その結果,水平面・垂直面ともに,母趾は偏位した体重心を支持する「支持作用」,第2~5趾は偏位した体重心を中心に戻す「中心に戻す作用」があり,水平面・垂直面での動的姿勢制御能において母趾・第2~5趾の役割を示唆する結果となった。足趾把持筋力は握力測定用の握力計を足趾用に改良し,母趾と第2~5趾とを分けて測定した。動的姿勢制御能と足趾把持筋力との関係を分析した結果,足趾把持筋力が動揺面積を減少させることも示唆され,足趾把持筋力の強弱が垂直面での動的姿勢制御能に関与し,足趾把持筋力強化により転倒の危険性を減少させる可能性があると考えられる。
- 著者
- 石橋 達也 形部 裕昭 早川 隆洋 太田 敬之 古川 安志 西 理宏 古田 浩人 赤水 尚史
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.9, pp.675-680, 2015-09-30 (Released:2015-09-30)
- 参考文献数
- 14
症例は46歳,女性.32歳よりうつ病で近医に通院中であった.35歳より2型糖尿病で治療を開始された.メトホルミン500 mg/日およびインスリン(1日70単位)による治療でHbA1c5.4 %であった.来院当日,自殺目的でリスプロ2100単位,グラルギン900単位を注射し,1時間後に救急搬送となった.遷延性低血糖に対応するため入院とし,食事および経口と経静脈でブドウ糖の投与を行った.来院時の血清インスリン濃度(IRI)が31975 μU/ml,6時間で20903 μU/ml,9時間で9370 μU/mlと低下,注射後141時間でブドウ糖投与を要しなくなった.持続血糖モニタリングでは血糖値の変化はブドウ糖投与による上昇と低下を繰り返し,急峻な鋸歯状波形を呈していた.IRIの経過は低血糖からの回復時期を予測する目安となり,血糖降下作用が続く期間では頻回の血糖測定が必要であると考えられた.
2 0 0 0 OA Three New Species of the Family Eosentomidae (Protura) from the Nasu Imperial Villa, Central Japan
- 著者
- Osami Nakamura
- 出版者
- The Japanese Society of Systematic Zoology
- 雑誌
- Species Diversity (ISSN:13421670)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.111-125, 2021-04-06 (Released:2021-04-06)
- 参考文献数
- 18
Three new proturan species, Eosentomon villare sp. nov., Pseudanisentomon nasuense sp. nov., and P. villaticum sp. nov., collected from the Nasu Imperial Villa, Tochigi Prefecture, central Japan are described. Eosentomon villare sp. nov. is characterized by the absence of foretarsal sensillum b′1, a long empodium on the hind tarsus, four pairs of anterior setae on abdominal tergite VII (A1, 2, 4, and 5), two anterior and seven posterior setae on sternite VIII, and six setae on sternites IX–X. Both P. nasuense sp. nov. and P. villaticum sp. nov. also lack foretarsal sensillum b′1. Pseudanisentomon nasuense sp. nov. has long empodia on the middle and hind tarsus and five pairs of anterior setae on abdominal tergite IV. Pseudanisentomon villaticum sp. nov. is distinguished from its congeners by the number of anterior setae on abdominal tergite VII (three pairs: A2, 4, and 5), the absence of foretarsal sensillum c′ and seta x, and rudimentary setae 1 and 2 on tergite XI. In addition to descriptions of these new species, an updated key to species of Pseudanisentomon Zhang and Yin, 1984 is provided.
- 著者
- Alexandr N. Mironov Toshihiko Fujita
- 出版者
- The Japanese Society of Systematic Zoology
- 雑誌
- Species Diversity (ISSN:13421670)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.101-110, 2021-03-22 (Released:2021-03-22)
- 参考文献数
- 31
Hirsutocrinus duplex, a new genus and new species of the Bathycrinidae, collected from Okinawa, Japan at a depth of 596–606 m, is described. The main diagnostic characters of the new genus are the presence of side plates in pinnules and of knobby processes on Brs 1–2. Knobby processes on secundibrachials are found for the first time. Monachocrinus A. H. Clark, 1913 shares side plates with Hirsutocrinus. It differs from the new genus in having knobby processes on IBrs 1, parallel ridges on the articular surface of knobby processes, proximal and distal arm pattern a b+c d+e f, saccules, in lacking knobby processes on IBrs 2 and Brs 1–2, pinnule on every second Br, x-shaped tube-feet plates, needle-like spines on external surface of IBrs and Brs. The cover and side plates are similar to each other in Monachocrinus, and quite different in Hirsutocrinus. Hirsutocrinus duplex is the shallowest species in the abyssal family Bathycrinidae usually known from 1100 to 9735 m. Other than H. duplex, only three among 25 nominal bathycrinid species are known from depths less than 1000 m.
2 0 0 0 OA 国家賠償法2条の瑕疵判例より見た社会基盤施設の安全性と技術者の責任
- 著者
- 本城 勇介 諸岡 博史
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集F (ISSN:18806074)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.1-13, 2010 (Released:2010-01-20)
- 参考文献数
- 18
社会基盤施設に関連した事故に関する判例などが報道されると,工学で考えられている設計問題の枠組みと,法律で規定されている枠組みに差があることを感じることがある.本研究はこのような法律の考え方と,設計の考え方の関係を明確にし,社会基盤施設に求められる安全性や技術者の責任を明らかにすることを目的とする.判例を検討していると,瑕疵に関する考え方も,徐々に安全性が相対的なものであるという認識に変化していると思われる.判例は依然通説である「客観説」をとっているが,その判断にあたり,予見可能性,回避可能性など技術的見識を加え,結果の重大性や構造物の重要性などを多面的に勘案するようになってきていると思われる.
2 0 0 0 OA 地域在住高齢者における応用歩行予備能の有用性と生活機能との関連
- 著者
- 橋立 博幸 内山 靖
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.367-374, 2007 (Released:2007-06-18)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 7 10
目的 本研究では,地域在住高齢者における応用歩行の予備能の定量的な評価指標を開発し,その有用性と日常生活活動(ADL)や生活範囲を含んだ生活機能との関連性を検討することを目的とした.方法 対象は地域在住高齢者107人(平均年齢72.6±5.0)とした.歩行機能検査としてTimed"Up and Go"Test(TUG),10m歩行時間,6分間歩行距離(6MD),Physiological Cost Index(PCI),Rating of Perceived Exertion(RPE)を実施した.また,日常生活活動の指標として老研式活動能力指標(TMIG-IC)を調査した.TUGは至適速度(TUGcom),最大速度(TUGmax)にて計測し,TUGmaxに対するTUGcomとTUGmaxの差の割合(TUG-R)を応用歩行の予備能の指標とした.結果 TUG-Rは級内相関係数ICC(1, 2)=0.82と高い再現性を示した.TUG-Rは6MD, PCI, RPEと有意な関連を示し,歩行の持久性および安楽性を反映していると考えられた.TUG-RはTMIG-IC手段的自立に障害のある高齢者では有意に低下しており,高い移動機能を要するADLへの関連性が示唆された.ロジスティック回帰分析の結果,屋外活動の遂行にはTUG-Rが有意に関連した.結論 応用歩行の予備能を示すTUG-Rは,指標の再現性が高く,歩行の持久性,および生活範囲等の生活機能と密接に関連する高齢者において重要な臨床指標であると考えられた.
2 0 0 0 OA 氷床コアに記録された気候•環境変動
- 著者
- 本山 秀明
- 出版者
- 日本エアロゾル学会
- 雑誌
- エアロゾル研究 (ISSN:09122834)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.247-255, 2010 (Released:2010-10-20)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
The accumulation rate, aerosol flux, and air temperature fluctuation can be determined from the study of ice cores drilled through ice sheets and glaciers. The aerosol which gives climate and environmental information is accumulated on the surface of ice sheet. In order to elucidate the climate and environmental changes, it is necessary to find the changes in concentration, composition, and isotope ratio of impurities in accumulated particles after the deposition on the snow surface. This study revealed that the global climate and environmental changes have occurred on various time scales in the past million years. The characteristics of aerosol particles deposited on the Antarctic ice sheet are investigated. Furthermore, the history of solar activity and associated geomagnetic fields is clarified by analyzing the cosmogenic nuclides in ice cores. An interdisciplinary study on ice cores is also carried out to elucidate the evolution mechanisms of microorganisms in the ice cores.
- 著者
- 高橋 和孝 篠原 秀典 吉田 拓矢 浅井 武
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- pp.20076, (Released:2021-04-06)
2 0 0 0 OA 月経周期による血液出血凝固系検査の変動について
- 著者
- 伊藤 宗元 大黒 久子 篠田 孝司 佐藤 桃子 渡部 健次
- 出版者
- 一般社団法人 国立医療学会
- 雑誌
- 医療 (ISSN:00211699)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.6, pp.764-770, 1969 (Released:2011-10-19)
- 参考文献数
- 10
We observed alteration of the behavior of coagulation factors during menstrual cycle by examination of nine kinds of test every week upon 12 healthy single females. At the same time we examined 5 healthy males in same way as a cotrast.The items of test are platelet count, bleeding time, coagulation time, capillary fragility (negative pressure), clot retraction, prothrombin time, recalcification time, partial thromboplastin time and serum fibrinogen.We obtained the following results;After period, there are definite increase of platelet count, prolongation of bleeding time, slight prolongation of recalcification time and prothrombin time. During period, coagulation time is shortened slightly and clot retraction became stable as 40∼50%. There is temporal decrease of capillary resistence after period, partial thromboplastin time much prolonged in one to two weeks after period. Serum fibrinogen increased slightly after period.The alteration of the behavior of coagulation factors during menstmal cycle are supposed to be affected by the age, marriage, delivery, amount of bleeding at period and length of menstrual cycle, because of which we should interpret results in consideration of the alteration during menstrual cycle in laboratory study.
- 著者
- Yuto SANO Kanae SEKI Kenjirou MIYOSHI Toshikazu SAKAI Tsuyoshi KADOSAWA Kazuya MATSUDA
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.20-0518, (Released:2021-04-05)
- 被引用文献数
- 2
Mediastinal masses in dogs were diagnosed as basaloid carcinoma associated with multiple thymic cysts (MTCs). The masses were composed of MTCs and proliferating intracystic neoplastic basaloid cells, which immunohistochemically diffusely expressed p63 and cytokeratin 19. A gradual transition from the basal cell layers lining the cysts walls to the neoplastic cells was seen, and it was indicated that the neoplastic cells had originated from the basal cell layers of the cysts. To the best of our knowledge, this is the first report of basaloid carcinoma occurring in the mediastinal cavity in dogs. Although these tumors were demonstrated to be rare origins, basaloid carcinoma should be included in the differential diagnoses for canine mediastinal tumors.