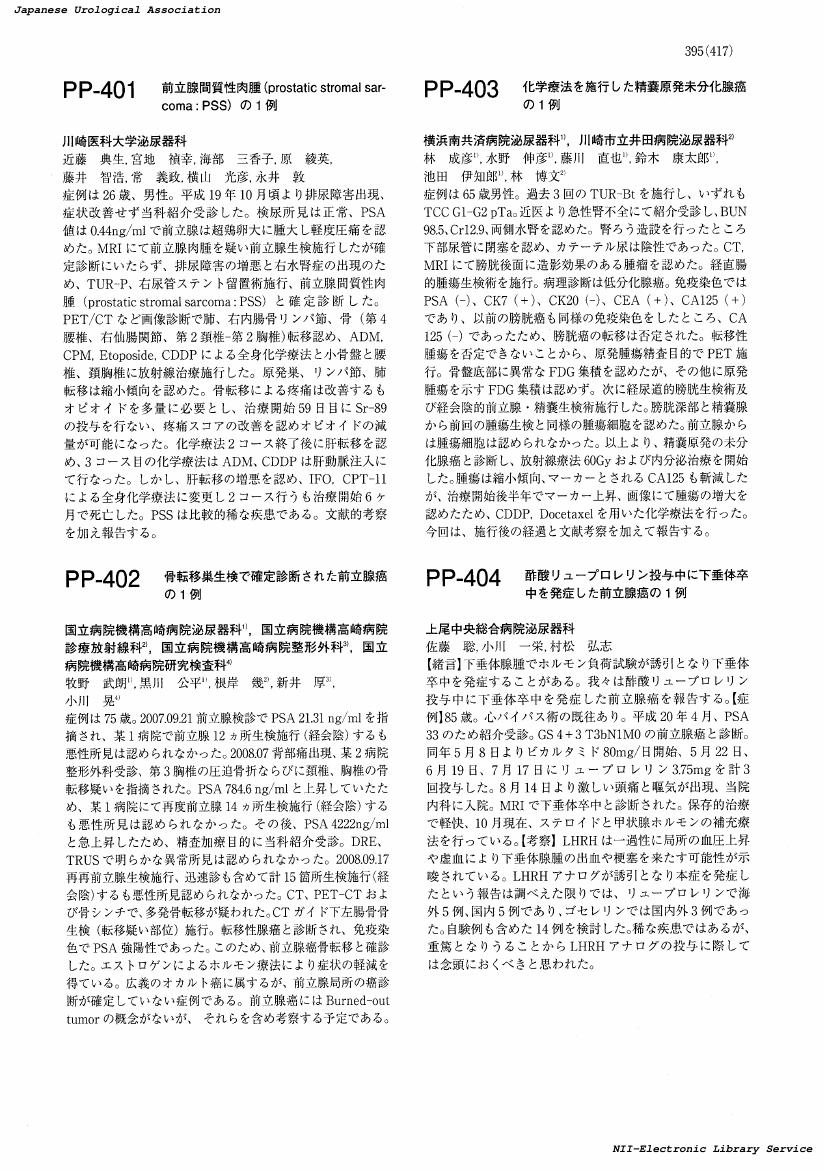30 0 0 0 OA 帰化植物ナルトサワギクの学名
29 0 0 0 OA Twitterにおける意見の多数派認知とパーソナルネットワークの同質性が発言に与える影響
- 著者
- 小川 祐樹 山本 仁志 宮田 加久子
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.5, pp.483-492, 2014-09-01 (Released:2014-08-27)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 3
The purpose of this paper is to test the Spiral of Silence theory in Internet society. Even today Noelle-Neumann's Spiral of Silence Theory is an important topic on the formation of public opinion. In the Spiral of Silence Theory up to now, the willingness to speak out has been handled as a dependent variable. However, there is significant bias in the question as to what extent the willingness to speak out actually influences the number of times a person speaks out. In addition, snowball sampling has been used, even in regard to the distribution of opinions of persons close to an individual. Accuracy increases because the attitudes of direct close users can be studied; however, only a small portion of close users can be studied. One defect of this approach is that it is actually quite costly. We use as a dependent variable the actual number of `tweets' on Twitter rather than willingness to speak out. In addition, for the attitude of close users, we used machine learning to estimate the attitudes of persons the users came in contact with, and we quantified homogeneity. We used and combined social investigations and behavior log analysis. With these, we were able to adopt simultaneously the following to a model: 1) individuals' internal situations, which can only be clarified by a questionnaire. 2) the actual quantity of behavior and the structure of communication networks, which can only be clarified through analysis of behavior logs. In the result, we found that a person's perception that their opinion in the majority and estimated homogeneity had a positive effect on the number of times a person spoke out. Our results suggest that the spiral of silence in regard to actual speaking out on Twitter.
29 0 0 0 離婚後の親子関係の制度構築の多角的研究
離婚後の親子のありかたをめぐって国民的な議論が巻き起っている。日本において離婚後の共同親権の研究や調査は、社会学の分野ではほぼ皆無であり、規範的な法学論議にとどまっている。法がどのように社会を構築し、どのような制度によって支えられているかという問題として検討されていない。本研究では、離婚後の「子どもへの権利(責任)」の「所有」、「ケア」や「子どもの福祉」といった概念を問い直し、「保護複合体」の形成のありかたを分析し、ポスト「近代家族」において制度構築が可能なのかを検討する。その際にこれまで外国で積み重ねられてきた共同親権や共同監護をめぐる議論や調査を参考とし、調査を複合的に検討する。
28 0 0 0 OA 自治医科大学における学生寮教育と今回の新型コロナウイルス感染症対策 : 全寮制下での対応と課題
- 著者
- 小川 莉奈 山西 良典 辻野 雄大 吉田 光男
- 雑誌
- エンタテインメントコンピューティングシンポジウム2022論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, pp.11-18, 2022-08-25
ソーシャルメディア上には多くのイラストが能動的エンタテイメントとして投稿されており,様々な画風を分析する上での貴重なデータとして扱うことができる可能性がある.しかしながら,ソーシャルメディア上で投稿された画像は構造化されておらず,画像データベースとしてそのまま用いることはできない.本稿では,整理されていない画像集合を整理する作業を 2 つのゲームに分けることで,楽しく整理する手法を提案する.データセットを構築するための「検定ゲーム」と作成したデータセットにアノテーションを加えるための「パーティゲーム」の 2 つに分けた.整理されていない画像集合とし#ghibliredrawのタグを用いた描き変えイラスト画像を対象とした.
27 0 0 0 OA 「アイヌ教育制度」の廃止 : 「旧土人児童教育規程」廃止と1937年「北海道旧土人保護法」改正
- 著者
- 小川 正人
- 出版者
- 北海道大學教育學部 = THE FACULTY OF EDUCATION HOKKAIDO UNIVERSITY
- 雑誌
- 北海道大學教育學部紀要 (ISSN:04410637)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, pp.37-79, 1993-06
27 0 0 0 OA 「つなぐ技術(人・モノ・社会)2」特集号刊行にあたって
- 著者
- 小川 剛史 小俣 昌樹 宇都木 契
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会
- 雑誌
- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.1, 2020 (Released:2020-03-31)
26 0 0 0 OA うつ病患者における栄養学的異常
- 著者
- 功刀 浩 古賀 賀恵 小川 眞太郎
- 出版者
- 日本生物学的精神医学会
- 雑誌
- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.54-58, 2015 (Released:2017-02-16)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
海外では,うつ病患者において肥満,脂質異常,n-3 系多価不飽和脂肪酸,ビタミン B12 や葉酸,鉄,亜鉛などにおける栄養学的異常が発症や再発のリスクと関連するという報告が増えている。しかし,わが国におけるエビデンスは今のところ乏しい。特に精神科受診患者を対象とした研究はほとんどない。そこでわれわれは,うつ病患者と健常者における栄養素・食生活について調査し,予備的結果を得た。末梢血を採取し,アミノ酸・脂肪酸・ビタミン濃度等について詳細に測定した。食生活調査は食事歴法質問紙を使用した。うつ病群は健常者群と比較して肥満,脂質異常が多かった。脂肪酸では,エイコサペンタエン酸やドコサヘキサエン酸濃度について両群間で有意差は見られなかった。ビタミンでは葉酸が低値を示す者がうつ病群に有意に多かった。アミノ酸では,うつ病群で血漿トリプトファン値が有意に低下していた。鉄や亜鉛などのミネラルの血清中濃度に関しては,欠乏を示す者は患者と健常者の両群に高頻度でみられたが,両群の間で有意差は見られなかった。嗜好品では,うつ病患者は緑茶を飲む頻度が低い傾向がみられた。以上から,海外での先行研究と必ずしも一致しないものの,日本のうつ病患者においても栄養学的問題が多数みられることが明らかになり,うつ病患者に対する栄養学的アプローチの重要性が明らかになった。
- 著者
- 佐藤 聡 小川 一栄 村松 弘志
- 出版者
- 一般社団法人 日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科学会雑誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, no.2, pp.417, 2009-02-20 (Released:2017-04-08)
26 0 0 0 OA 放射線治療に伴う腸炎・口内炎に対する半夏瀉心湯有効例とその検討
- 著者
- 永井 愛子 小川 恵子 三浦 淳也 小林 健
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.108-114, 2014 (Released:2014-10-17)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 1 1
放射線治療装置や技術の発展にも関わらず有害事象である腸炎や口内炎は存在する。半夏瀉心湯は腸炎や口内炎に対する効果が報告されている。放射線による腸炎や口内炎に対する半夏瀉心湯の有効例を経験したので報告する。腸炎3例,口内炎5例の計8例に対して症状出現後1-35日に半夏瀉心湯7.5g/日または18錠/日(適宜漸減)を投与した。腸炎と口内炎の重症度は内服前後でCommon Terminology Criteria for Adverse Events と Numerical Rating Scale で評価した。口内炎5例中,改善,不変,増悪は各々3例,1例,1例,腸炎3例中では各々2例,1例,0例であり,増悪はなかった。放射線治療中の腸炎や口内炎などの早期有害事象を制御することは患者の負担軽減のみならず腫瘍制御率改善にもつながる。今後より多くの患者に対するランダム化比較試験の報告が望まれる。
- 著者
- 田口 裕起 鈴木 久貴 小川 耕作 白井 暁彦
- 出版者
- 一般社団法人映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.10, pp.9-11, 2014-02-25
本研究ではHMDのセンサフュージョンをそのまま利用し,普及しているコンテンツ開発環境であるUnity3Dにおける首の動きを利用したジェスチャ入力の認識方法を提案する.最も基本的な方法として,絶対的な回転角度によって「肯定」,「否定」,「疑問」の3つのジェスチャを認識する.
25 0 0 0 OA 地下比抵抗構造から推定される草津白根火山のマグマ熱水系
- 著者
- 松永 康生 神田 径 高倉 伸一 小山 崇夫 齋藤 全史郎 小川 康雄 関 香織 鈴木 惇史1 4 木下 雄介 木下 貴裕
- 出版者
- 日本地球惑星科学連合
- 雑誌
- JpGU-AGU Joint Meeting 2017
- 巻号頁・発行日
- 2017-03-10
草津白根山は群馬県と長野県の県境に位置する標高2000mを越える活火山であり、その山頂部は2つの主要な火砕丘で構成されている。そのうち、北部に位置する白根山では、火口湖である湯釜を中心に活発な活動が観測されていることから、これまで地球化学的研究を中心に様々な研究が行われてきた。一方で、白根山の2kmほど南に位置する本白根山では、歴史時代に火山活動が観測されていないこともあり、幾つかの地質学的な研究を除いてほとんど研究されておらず、地下構造や火山熱水系については不明な点が多い。たとえば、本白根山の山麓には草津温泉、万代鉱温泉、万座温泉など湧出量が豊富な温泉が分布し、それらの放熱量は湯釜周辺からのものを大きく上回ることが知られているが、熱の供給源の位置については未だに不明である。また、本白根山は1500年前にマグマ噴火が起こったことが最近の地質学的研究で明らかにされたものの、マグマ溜まりの状態・位置についてはほとんど分かっていない。本白根山における噴火の発生可能性を議論する上でも、本白根山周辺のマグマ熱水系を解明することは重要である。そこで本研究では、白根山南麓を含む本白根山周辺の23点において広帯域MT観測を行い、地下比抵抗構造の推定を試みた。MT法は電磁気探査手法の一つであり、地下のメルトや熱水など高導電物質に敏感であるため、マグマ溜まりや熱水系の観測に適している。MT法データの3次元解析によって得られた最終モデルから、白根山から本白根山の地下1-3kmにかけて低比抵抗体が広がっていることがわかった。この上部に火山性地震の震源が分布することから、この低比抵抗体は流体に富んだ領域であり、ここから流体が浅部へと上昇し、地震を引き起こしていると考えられる。先行研究において、山麓温泉(草津温泉、万代鉱温泉、万座温泉)は、高温火山ガスと天水が混合してできた初生的な温泉水が、分別過程を経ずに湧出したものであると解釈されていること、この低比抵抗体の他に目立った火山性流体の存在領域が見られなかったことから、本研究ではこれを山麓温泉の流体供給源と考え、以下のようなモデルを提案する。(1)低比抵抗体の下深くには何らかの熱源が存在し、上部に熱と流体を供給する。(2)熱の供給を受けた低比抵抗体内の流体は山頂下へと上昇し、火山性地震を発生させる。(3)流体の一部は断層に沿って本白根山の東斜面へと上昇し、表層に変質領域を形成する。(4)この流体と天水が混同してできた温泉水は東斜面の溶岩中を流れ下り、万代鉱温泉、草津温泉として湧出する。一方、本白根山の直下では、マグマの存在を示すような特徴的な低比抵抗体は解析されなかった。しかし、現状では深部構造を詳細に議論できるほど測定・解析精度が十分ではないので、今回の解析結果からは火山直下にマグマ溜まりが存在しないと結論づけることはできない。今後、マグマ熱水系の推定精度を向上させるため、追加の観測やシミュレーションを実施していきたい。
24 0 0 0 OA 音楽幻聴 (楽音性耳鳴) に関する臨床的検討
- 著者
- 御子柴 卓弥 新田 清一 中山 梨絵 鈴木 大介 坂本 耕二 島貫 茉莉江 岡田 峻史 藤田 航 鈴木 法臣 大石 直樹 小川 郁
- 出版者
- 一般社団法人 日本聴覚医学会
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.4, pp.315-325, 2019-08-30 (Released:2019-09-12)
- 参考文献数
- 18
要旨: 音楽幻聴は, 外部からの音刺激がないのに歌や旋律が自然に聞こえる現象であり, 耳鳴患者の中にも稀に存在する。2011年1月から2018年10月までに当科を受診した耳鳴患者のうち, 音楽幻聴を訴えた23例の臨床像を検討した。このうち11例に対し耳鳴について詳細に説明した上で補聴器による音響療法を行い, 治療効果を検討した。音楽幻聴症例は, 高齢者・女性に多く1例を除く全例で感音難聴を認めた。全例で病識が保たれており, 精神神経科疾患の合併を認めなかった。治療後に Tinnitus Handicap Inventory の合計値, 耳鳴の自覚的大きさ・苦痛の Visual Analogue Scale は有意に改善した。本検討から, 精神神経科疾患の合併がなく難聴が主病因の音楽幻聴に対し耳鳴の説明と補聴器による音響療法が有効な治療である可能性が示唆され, 耳鼻咽喉科医が中心となり診療に携わることが望ましいと考えられた。
24 0 0 0 OA 昆虫学DX-デジタルデバイスによる昆虫形態図の作成法
- 著者
- 駒形 森 小川 浩太
- 出版者
- 一般社団法人 日本昆虫学会
- 雑誌
- 昆蟲.ニューシリーズ (ISSN:13438794)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.128-143, 2022-09-25 (Released:2022-09-29)
- 参考文献数
- 3
As part of promoting digital transformation (DX) in the field of entomology, we present a method for drawing morphological illustrations of insects using digital devices. The method presented here uses an iPad, Apple pencil, and ibis Paint. The combination of the iPad and Apple pencil is superior in imitating the sensation of drawing with a pen on paper, and the use of the ibis Paint is advantageous in almost all the functions required to create scientific illustrations.For figures used in scientific papers, the recommended canvas size of the ibis Paint is 2400×3200 pixels with a resolution of 600 dpi. The following steps are recommended for the ibis Paint: first, in the “Settings” set “Use Pressure Sensitivity” and “Palm Rejection” to on, “Quick Eyedropper” to off, and “Stabilizer” to the maximum value of 10 for ease of use. Next, set the following five brushes to Custom Brush: Pencil #1, Dip Pen (Hard), Dashed Line, Outline (Fade), and Felt Tip Pen (Soft).The layer function is utilized in the drawing process. The drafting procedure differs depending on whether the tracing or grid method is used. In the tracing method, the photograph to be traced is imported and set on the bottom layer. After adjusting the position, angle, and transparency of the photo, create a new layer for the draft and use “Pencil #1” to write the draft. For the grid method, start “Filter” mode and use the filter “Table (Size)” to create a grid. After placing the grid layer on the bottom layer, create a new layer for drafting and write a draft using “Pencil #1”.For inking (final drawing), use “Dip Pen (Hard)” to draw the outline first, and then add details in sequence. Use “Dashed Line” for structures hidden behind, “Outline (Fade)” for soft hairs, and “Felt Tip Pen (Soft)” for dots. Using different layers for different purposes, such as shadows, three-dimensional expressions, and hairs, makes revising later easier. Screen tones can be used to fill in arbitrary areas with slash or cross lines.The method presented here can easily applied to simulate traditional drawing techniques.Thus, it can be adopted by different users, from senior researchers who already have established techniques to students who intend to learn scientific drawing. However, this method is still in its infancy, and it is necessary to continue to develop improved methods. Therefore, sharing the practical usage of digital devices with the entire entomological community is also essential.
24 0 0 0 OA 唾液を用いたストレス評価 ―採取及び測定手順と各唾液中物質の特徴―
- 著者
- 井澤 修平 城月 健太郎 菅谷 渚 小川 奈美子 鈴木 克彦 野村 忍
- 出版者
- 日本補完代替医療学会
- 雑誌
- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.3, pp.91-101, 2007 (Released:2007-10-19)
- 参考文献数
- 78
- 被引用文献数
- 42 34
近年,疾病予防などの観点からストレスの評価法に注目が集まっている.本稿では唾液を用いたストレス評価について概説した.人の唾液には様々なストレス関連物質が存在することがわかっており,非侵襲的なストレス評価法として利用できる可能性が考えられる.唾液採取,検体の取り扱い,測定などの基本的事項を紹介し,唾液より測定可能な 7 つの物質(コルチゾール,デヒドロエピアンドロステロン,テストステロン,クロモグラニン A,3-メトキシ-4-ハイドロキシフェニルグリコール,α アミラーゼ,分泌型免疫グロブリン A)の各種ストレスとの関連や使用の際の留意点を概観した.最後に目的や状況に応じた唾液によるストレス評価の方法や今後の課題について述べた.
23 0 0 0 OA 終末期がん患者の呼吸困難に対する送風の有効性についてのケースシリーズ研究
- 著者
- 角甲 純 關本 翌子 小川 朝生 宮下 光令
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.147-152, 2015 (Released:2015-03-05)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 3
【目的】呼吸困難に対する扇風機を用いて顔へ送風する支援は臨床ではよく行われているが,終末期がん患者に対する科学的なエビデンスは明らかではない.本研究では,終末期がん患者の呼吸困難に対する支援の有効性を後方視的に検討した.【方法】2013年7月~2014年1月に,当院の緩和ケア病棟に入院している終末期がん患者のうち,呼吸困難に対して扇風機を用いた支援を受けた9名の患者を分析の対象とした.効果の評価には,支援の実施前後で収集されていた呼吸困難VAS値の変化を用いた.【結果】扇風機を用いた支援実施前の呼吸困難VAS値は40.2±11.8,実施後VAS値は15.6±14.9で,実施前後で有意に減少していた(P=0.004).【考察】扇風機を用いた支援は,終末期がん患者の呼吸困難に対して効果がある可能性がある.今後は,介入研究を行い,前向きに有効性を検証していく必要がある.
22 0 0 0 OA COVID-19 罹患後症状・Long COVID における神経症状
- 著者
- 中嶋 秀人 原 誠 石原 正樹 小川 克彦
- 出版者
- 日本大学医学会
- 雑誌
- 日大医学雑誌 (ISSN:00290424)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.4, pp.197-204, 2022-08-01 (Released:2022-09-27)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 1
COVID-19 罹患後症状・Long COVID は,これまで新型コロナ後遺症,新型コロナウイルス (SARS- CoV-2) 急性感染後症候群とも呼ばれ,COVID-19 罹患後に感染性は消失したにもかかわらず,急性期から持続する症状や経過途中から新たに生じて持続する症状全般を指す.代表的な症状として,①全身症状:疲労感・倦怠感,関節痛,筋肉痛,②呼吸器症状:咳,喀痰,息切れ,胸痛,③精神・神経症状:記憶障害,集中力低下,不眠・睡眠障害,頭痛,抑うつ,筋力低下,④その他:嗅覚障害,味覚障害,脱毛,動悸,下痢,腹痛があげられる.LongCOVID の病態機序として,急性期からの遷延症状,肺機能低下がもたらす全身症状,集中治療後症候群などの複合的要因によるものが考えられ,神経症状としては中枢神経へのウイルス感染による神経障害,全身炎症に伴う中枢神経への炎症の波及,COVID-19 に誘導された自己抗体による神経障害などが想定されるが不明点が多い.Long COVID の症状は多岐であり,多分野におけるアプローチ・フォローアップが必要と考えられる.
- 著者
- 今井 信也 小川 俊夫 赤羽 学 今村 知明
- 出版者
- 一般社団法人 日本医療情報学会
- 雑誌
- 医療情報学 (ISSN:02898055)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.141-149, 2014 (Released:2016-04-20)
- 参考文献数
- 12
磁気共鳴画像装置(MRI)は今日の画像診断において欠かすことのできない検査機器であるが,その採算性についてはMRIの性能や利用頻度,また周辺地域の導入状況に影響されると考えられる.そこで本稿では平成23年度に一般病院で稼働しているMRIの一台あたり年間収支差を年間費用と収入より試算し,MRI導入の採算性を性能別,病床規模別,都道府県別に分析を行った.MRIの年間収支差は,1.5テスラ以上では病床規模別,都道府県別においてばらつきはあるものの,ほぼすべて黒字であったが,1.5テスラ未満ではほぼすべて赤字であった.MRI導入による採算性の要因としては,病床規模での各種加算の取得割合の違いや,地域でのMRI一台あたりの人口および医師数が大きく関係していた.病院経営の視点から,高性能なMRIは病床規模や地域性に関わらず導入を検討できうる医療機器であると考えるが,採算面だけでなく臨床的な必要性や間接的な収支を考慮するべきである.