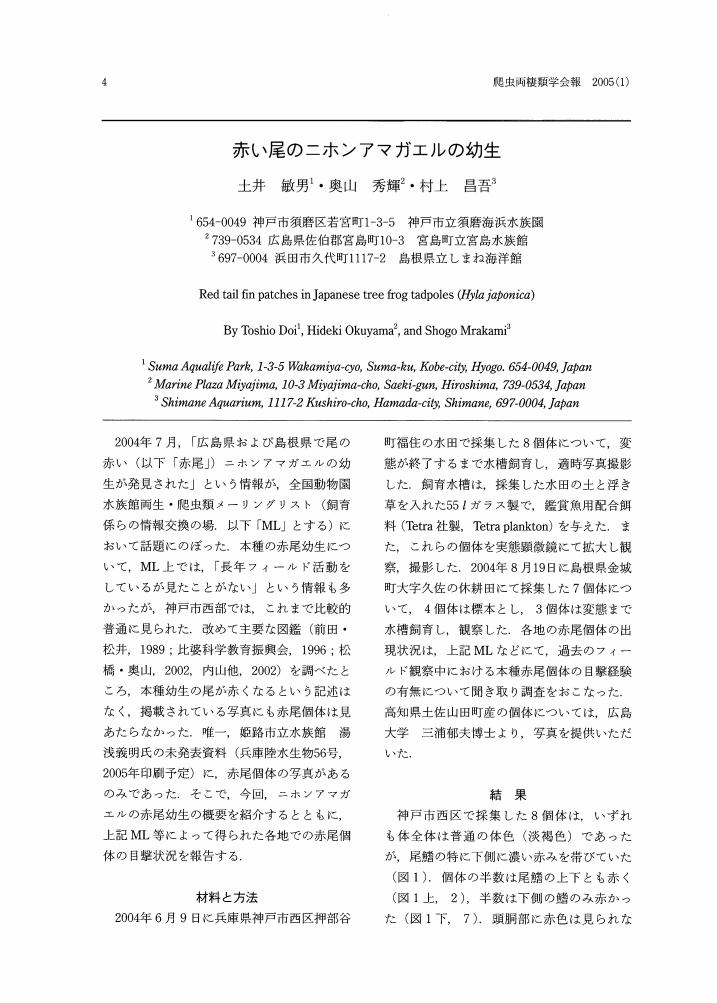5 0 0 0 OA 色環境の及ぼす心身への影響 -色刺激と皮膚血流量の変化-
- 著者
- 猪下 光 内海 滉
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護研究学会
- 雑誌
- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.4_17-4_23, 1992-09-01 (Released:2016-03-31)
- 参考文献数
- 26
1) 裸眼への光刺激の人体に与える影響を色覚正常な健康成人女性15名の皮表における微小循環血流量の変化にて観察した2) 光刺激の強度を,黄色光刺激の100ルクスの場合と,同じく600ルクスの場合とで比較すると,前者は後者に比して,その変動は大であった。3) 色彩別光刺激による血流変化量は,刺激となる光の波長に関係し,赤・黄・緑・青の順であった。4) 顕在性不安尺度(MAS)を用いて不安のレベルより観察すると,同一色彩,同一強度による光刺激の負荷においても血流変化量は異なり,高不安群は低不安群に比して,緑を除き大なる変動を示していた。
5 0 0 0 OA 熊リハパワーライス®は脳卒中回復期の栄養状態や機能的予後を改善する
- 著者
- 嶋津 さゆり 吉村 芳弘 上野 いずみ 工藤 舞 白石 愛 備瀬 隆広 長野 文彦 濱田 雄仁
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会
- 雑誌
- 学会誌JSPEN (ISSN:24344966)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.3, pp.149-156, 2019 (Released:2020-02-05)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 6
【目的】脳卒中回復期における熊リハパワーライス®の臨床効果の検討.【対象と方法】2015年から2016年に連続入院した脳卒中回復期患者204人を対象とした後向きコホート研究.物性や分量,味や匂いを損なわず,軟飯に中鎖脂肪酸とたんぱく質を混ぜ込んだ熊リハパワーライス®を用い食事管理を行った患者群と,通常の食事管理を行った患者群の単変量解析,意識状態,嚥下レベル,栄養状態,日常生活自立度(FIM運動)等,12項目の傾向スコアでマッチングした2群間の検討と退院時FIM運動を従属変数とした多変量解析を行った.【結果】対象者は204人(平均年齢73.6歳,男性109人,女性95人),脳梗塞127人,脳出血62人,くも膜下出血15人.マッチング後(両群とも38人)では,熊リハパワーライス®摂取群は非摂取群と比較して多くのエネルギーを摂取し,体重と骨格筋量が増加,退院時の常食摂取の割合が高く,FIM運動が高かった(全てp<0.05).多重回帰分析では,熊リハパワーライス®摂取は退院時FIM運動に独立して関連していた(β=.169, p=0.02).【考察】熊リハパワーライス®は脳卒中回復期における栄養改善,身体機能改善に有効である.
5 0 0 0 日本グループ・ダイナミックス学会第69回大会発表論文集
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.Supplement, pp.63-S1, 2023 (Released:2023-08-29)
5 0 0 0 OA 石灰沈着性頸長筋腱炎の8例
- 著者
- 大塚 雄一郎 茶薗 英明 鈴木 誉 大熊 雄介 櫻井 利興 花澤 豊行 岡本 美孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.116, no.11, pp.1200-1207, 2013-11-20 (Released:2014-01-16)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1 5
石灰沈着性頸長筋腱炎の8例を経験した. いずれも頸部痛, 頸部可動制限, 嚥下痛を主訴に来院した. 診断と鑑別にはCT, MRIが有用であり, CTで頸長筋腱の石灰沈着を認めた. また造影CTでは咽後膿瘍においてみられる造影効果 (ring enhance) を認めなかった. MRIでは頸長筋が腫大しT2強調画像で高信号を呈した. これらの画像検査で咽後膿瘍, 化膿性脊椎炎を否定した上で7例を入院加療, 1例を外来加療とした.本疾患は特別な治療は不要とされるが, 症状が強いため咽後膿瘍, 化膿性脊椎炎が否定しきれず抗生剤を投与することが多い. 今回の8例でも全例で抗生剤が投与されていた. 本疾患は周知されておらず, 加療中に本疾患と診断された症例は4例だけであり, 残りの4例は咽頭後間隙炎, 咽後膿瘍の疑いの診断で加療されていた.
5 0 0 0 OA タイムカプセルに保存した9年前の「思い出」の記憶と変容
- 著者
- 新垣 紀子 北端 美紀 松岡 裕人 高田 敏弘 折戸 朗子 加藤 ゆうこ 都築 幸恵 大和田 龍夫
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.15-28, 2014-03-01 (Released:2015-02-02)
- 参考文献数
- 26
How should we save our personal memories? Many people keep diaries and take pictures for that purpose. In this study, we kept things of personal significance in a time capsule for 9 years and examined whether personal memories could be saved in a time capsule and how they might possibly change over time. We held a workshop in 2003 when participants put something that they had possessed which had personal significance at that time of their life. They were interviewed to explain what kinds of significance these possessions had for them, and these interview sessions were recorded. Nine years after the initial workshop, the participants came together again. Before the time capsule was opened, they were asked to recall what they had put in the time capsule and to describe in what ways their possession in the time capsule had been significant to them. By comparing the contents of the participants’ responses between 2003 and 2012, it was found that a great deal of the contents have been changed from 2003 to 2012. Implications were discussed as regards to the significance of objects themselves and the narratives that go with the objects in preserving personal memories.
5 0 0 0 OA サポーターカルチャーズ研究序説
- 著者
- 清水 諭
- 出版者
- 日本スポーツ社会学会
- 雑誌
- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.24-35,131, 2001-03-21 (Released:2011-05-30)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 4 1
本論文の目的は、この国のサポーターカルチャーズ研究に向けてのパースペクティヴを導き出すことである。まず、英国で行われてきたフーリガニズム研究について、レスター学派、テイラーの研究を批判的にレヴユーしている。そして、1990年代におけるフーリガンの変容をふまえたポピュラーカルチャーズ研究として、ジュリアノッティとレッドヘッドの研究を検討している。本論文では、これらの研究を基盤にしながらも、この国におけるサポーターの現実との往復運動によって研究を進めていくことが重要だと考える。浦和レッズサポーターへのフィールドワークによれば、表象とその記憶に加えて、「男らしさ」、「浦和の場所性」、そして「抵抗の契機」といった要素がそれぞれの歴史的堆積をふまえながら複雑に絡み合って、重層決定されていることがわかる。サポーターのさまざまなポピュラーカルチャーズの要素をふまえながら、その日常で瞬間瞬間にさまざまな要素が紡ぎ合わさって構成される現実を読み解くことが必要である。
5 0 0 0 OA 後漢末荊州学派の研究
- 著者
- 野沢 達昌
- 出版者
- 立正大学文学部
- 雑誌
- 立正大学文学部論叢 (ISSN:0485215X)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.139-161, 1972-02-05
5 0 0 0 OA 昆虫の飛行メカニズム(流体力学的視点から)
- 著者
- 河内 啓二
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.5, pp.279-284, 1999-09-25 (Released:2000-04-12)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 4 7
Flight mechanism of insect is different from that of our familiar system of aircraft, machinery, or bird. Recent studies quantitatively indicated that many features of insect flight mechanism, such as thin airfoil, high beating frequency, or continuous beating motion, well conform to the fluiddynamic condition given to the insect.
5 0 0 0 OA 90年前の超高層RC造
- 著者
- 加藤 博人
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学 (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.7, pp.595, 2015 (Released:2016-07-01)
5 0 0 0 OA 罰金刑の目的と量定
- 著者
- 永田 憲史
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.206-219, 2008-02-10 (Released:2020-11-05)
5 0 0 0 OA 組織における制度と文化 社会心理学の視点から
- 著者
- 村本 由紀子
- 出版者
- 一般社団法人 日本産業保健法学会
- 雑誌
- 産業保健法学会誌 (ISSN:27582566)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.25-29, 2022-07-10 (Released:2023-02-22)
- 参考文献数
- 20
組織が新たなルールや制度を導入したとき、従業員がその新制度に即応し、活用することは必ずしも容易ではない。従業員の心理や行動は、明示的な制度よりも目に見えない職場の文化に規定されがちであり、文化には、環境が変わっても容易には変化しがたいという特質が備わっているためである。特に留意すべきは、旧態依然とした文化が「多元的無知」によって維持されている場合である。本稿では、多元的無知に関する社会心理学の研究例を紹介しながら、組織における制度と文化の関係について考察する。
5 0 0 0 OA ピアニストの身体運動制御 : 音楽演奏科学の提案
- 著者
- 古屋 晋一
- 出版者
- 一般社団法人 システム制御情報学会
- 雑誌
- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.10, pp.419-425, 2009-10-15 (Released:2017-04-15)
- 参考文献数
- 28
5 0 0 0 OA 明治時代東北地方におけるニホンオオカミの駆除
- 著者
- 中沢 智恵子
- 出版者
- 「野生生物と社会」学会
- 雑誌
- 野生生物保護 (ISSN:13418777)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.19-38, 2010-03-01 (Released:2017-09-20)
- 参考文献数
- 41
The causes of the extinction of the Japanese wolf (Canis lupus hodophilax), once found in three-Honshu, Shikoku, and Kyushu-of the four Japanese large islands, were documented by surveying official documents of northeastern Honshu from the Meiji era (1868-1912). The results showed many instances of nuisance killings of the animals, motivated by attacks on free-ranging livestock by the animals. The extirpation policies and their implemental measures were planned and authorized by the prefectural administrations of Aomori, Iwate, Iwai (then occupying parts of both present-day Iwate and Miyagi Prefectures), and Miyagi. In Aomori Prefecture, the police killed wolves. In Iwai Prefecture, the police commanded hunters to conduct the nuisance killings. The government of Iwate Prefecture enacted a bounty system in 1875, and 201 wolves were killed in 6 years. The government of Miyagi Prefecture followed it in 1877. In Fukushima Prefecture, local people conducted nuisance killings. Besides, the documents showed that fur, meat, and other parts of wolves were traded and used in northeastern Honshu. Thus, it can be concluded that the nuisance killings and hunting of wolves in the late 19th century contributed to the extinction of these animals in northeastern Honshu.
5 0 0 0 OA 大都市圏における移民の住宅市場への編入過程に関する研究
- 著者
- 金 希相
- 出版者
- Japan Association for Urban Sociology
- 雑誌
- 日本都市社会学会年報 (ISSN:13414585)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, no.40, pp.93-108, 2022-09-05 (Released:2023-09-16)
- 参考文献数
- 26
This paper examines how immigrants in metropolitan areas are assimilated into the local housing market. Most work on racial/ethnic disparities in homeownership draw from two different frameworks, spatial assimilation model and place stratification model, both of which were developed in the United States based on the relationship between social and spatial mobility. In Japan, however, it is said that immigrants move up the stratification ladder through homeownership rather than through migration, such as that to a higherquality location like the suburbs. Building on this perspective, this paper explores various factors that account for the ethnic inequality in homeownership and advances migration studies in Japan by dividing housing tenure into four categories–high– and low-quality owner–occupied, high– and low-quality rental–and presents alternative frameworks about housing trajectories, housing assimilation model, and stratified housing model. Analysis of anonymized census data for 2000 and 2010 indicates that the socioeconomic and life-cycle characteristics are associated with homeownership, showing a similar pattern of housing consumption between Japanese and immigrant group. However, for immigrant group, the education level does not account for the probability of attaining low-quality owner-occupied housing, presumably due to the low transfer of human capital in dual labor market in Japan. Marital status also has a large effect on homeownership, while the impact of intermarriage on homeownership attainment varies by head of household's nationality and housing tenure, revealing that an intermarriage premium in the housing market is higher for intermarried families with a native head of household. These findings suggest that there is indeed a homeownership hierarchy in Japan that are partly attributable to institutional barriers in housing and mortgage markets, although immigrants tend to be moderately assimilated into the housing market.
5 0 0 0 OA 放射性物質で汚染された港内海底土を封じ込める新しい被覆土と施工方法
- 著者
- 秋本 哲平 熊谷 隆宏 福田 守芳 古川園 健朗
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集B3(海洋開発) (ISSN:21854688)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.I_288-I_293, 2017 (Released:2017-08-22)
- 参考文献数
- 6
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴って発生した津波により,福島第一原子力発電所は大きな被害を受け,高濃度の放射性物質を含む汚染水が漏洩した影響等により,港湾内海底土から放射性物質が検出された.放射性物質を含む海底土が巻き上がり,港湾外へ拡散することが懸念されたため,固化処理土による海底土被覆を行った.2012年度に第1期工事として72,600m2を被覆し,2014年度から第2期工事として,180,600m2を被覆した.第2期工事では,波浪条件が厳しい港口部を含んでいたことから,被覆土には早期強度が求められたため,砂質土を主材とする固化処理土を選定した.砂質土を主材とする固化処理土の課題であった水中打設時の材料分離は,特殊添加剤や打設治具を開発することで解決し,港湾内全域を被覆することができた.
5 0 0 0 OA 前庭・平衡機能と重力適応
- 著者
- 野村 泰之
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.17-22, 2010 (Released:2016-04-15)
- 参考文献数
- 38
新たな宇宙開発時代にともなって低重力環境など異重力環境への対応が必要な時代となってきた.有史以来,地球上の1G環境で過ごしてきた人類にとって,異重力環境での平衡機能は未知な部分が多い.1G環境でのヒトの平衡バランスは,入力としての3系統への情報が,中枢前庭と高次脳での制御を経て合目的に全身に出力されることで維持されている.しかし異重力環境に突入して内耳前庭への入力情報が変化すると,入出力系統の統合混乱をきたして多様な平衡障害を生じ,宇宙酔いなども生じる.そこで異重力環境への適応をいかに速やかにこなし,平衡障害や空間識失調に陥らずに身体活動のパフォーマンスを保つかが鍵となり,それはひいては地上での平衡障害疾患治療へのフィードバックへもつながることになる.ここでは地上と低重力環境における平衡機能の差異を中心に述べる.
- 著者
- 岡本 拓司
- 出版者
- 教育思想史学会
- 雑誌
- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.42, 2022-09-17 (Released:2023-09-17)
5 0 0 0 OA 「フィンランド症候群」からの連想
- 著者
- 川口 典男
- 出版者
- 信州医学会
- 雑誌
- 信州医学雑誌 (ISSN:00373826)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.61-62, 2005-04-10 (Released:2016-04-22)