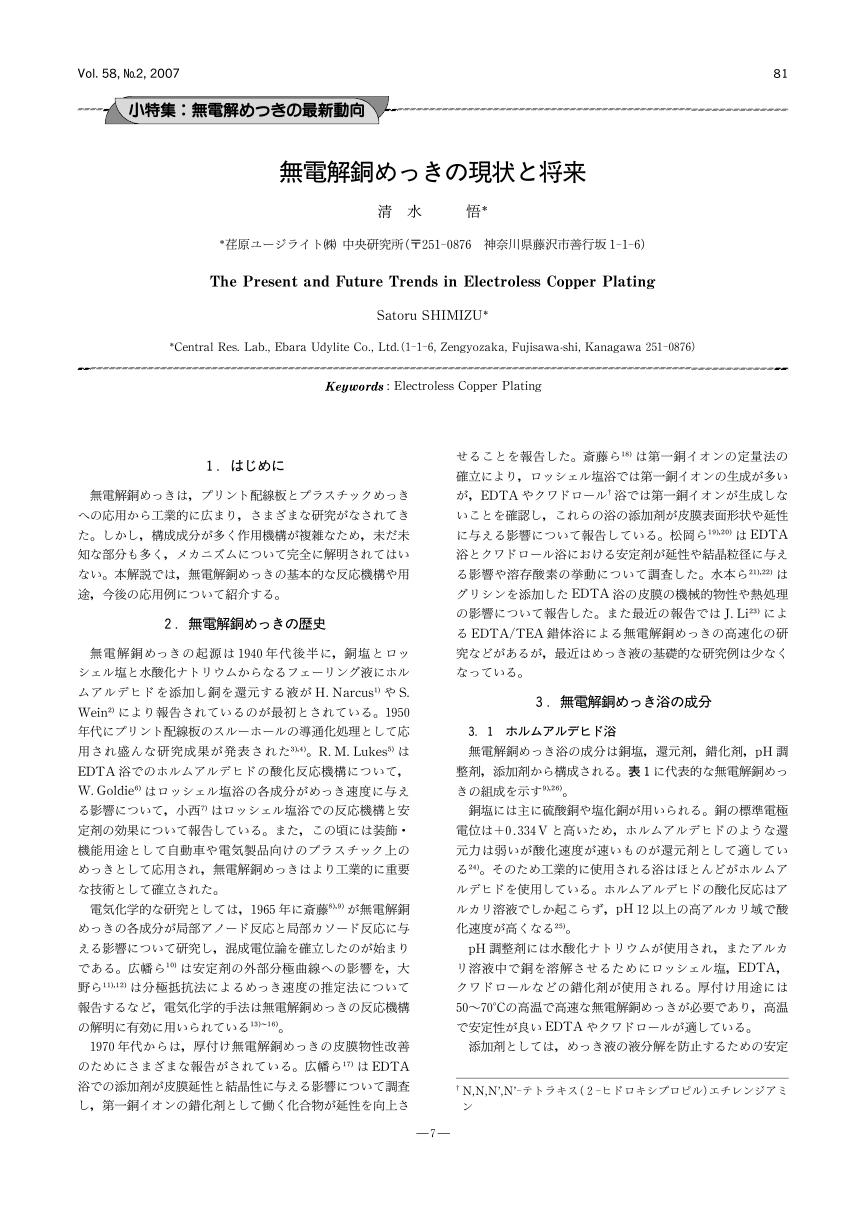3 0 0 0 S 式ベースC言語における変形規則による言語拡張機構
- 著者
- 平石 拓 李 暁? 八杉 昌宏 馬谷 誠二 湯淺 太一
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌プログラミング(PRO) (ISSN:18827802)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.40-56, 2005-01-15
- 被引用文献数
- 2
現在,実用的システムの開発にC 言語は欠かせないが,細粒度マルチスレッド機能などを追加するためにC 言語を拡張するのはそれほど容易ではない.言語拡張の実現方式としては,C コンパイラに手を加えるもの以外に,拡張C プログラムを変換し,C コードを生成する方式もある.後者の方式では,最初にプログラムを抽象構文木(AST)に変換し,拡張に必要な解析や変形などを行った後,C コード生成を行うことが多い.AST のデータ構造には従来,構造体,オブジェクト指向言語のオブジェクト,直和型のデータなどが用いられているが,本研究では,AST をS 式で表現し,それをそのままプログラムとして用いることを提案する.このため,S 式ベースの構文を持つC 言語,SC 言語を設計した.SC 言語では新しいコンストラクトの追加が容易であり,また,S 式は,変換時に便利な動的変数も備えたCommon Lisp 言語を使って簡単に入出力や解析や変形ができるため,言語拡張のrapid prototyping が可能となる.ただし,Common Lisp 言語ではパターンマッチングを直接書くことができないので,本研究では,backquote マクロの記法をパターン部にも用いた変形規則の表記も提案する.このようなSC 言語は他の高水準言語の中間言語として用いることも可能である.本論文では,実際にSC 言語に細粒度マルチスレッド機能を追加した例も示す.The C language is often indispensable for developing practical systems, but it is not so easy to extend the C language by adding a new feature such as fine-grained multithreading. We can implement language extension by modifying a C compiler, but sometimes we can do it by translating an extended C program into C code. In the latter method, we usually convert the source program to an Abstract Syntax Tree (AST), apply analysis or transformation necessary for the extension, and then generate C code. Structures, objects (in object-oriented languages), or variants are traditionally used as the data structure for an AST. In this research, we propose a new scheme where an AST is represented by an S-expression and such an S-expression is also used as (a part of) a program. For this purpose we have designed the SC language, the C language with S-expression-based syntax. This scheme allows rapid prototyping of language extension because (1) adding new constructs to the SC language is easy, (2) S-expressions can easily be read/printed, analyzed, and transformed in the Common Lisp language, which features dynamic variables useful for translation. Since pattern matching cannot be described directly in Common Lisp, we also propose denoting transformation rules with patterns using the backquote-macro notation. Such an SC language can also be used as an intermediate language for other high-level programming languages. This paper also shows a practical example where fine-grained multithreading features are added to the SC language.
3 0 0 0 都市の熱環境形成における水面・緑地の効果に関する総合的調査研究
夏期の都市熱環境における水面・緑地の効果に関し、実測調査を主とした総合的な研究を行い、以下のような成果を得た。1.海風の冷却効果に関して、風向・風速と気温の3地点同時の長期観測を実施した。陸風から海風への変化により、気温上昇の緩和あるいは気温の低下が認められ、海岸からの距離によって異なるが、平均的に3℃程度に達する。2.河川上と街路上における熱環境の比較実測を行った。河川は風の通り道としての役割を果しており、その水面温度も舗道面温度などに比較して最大30℃程度低い。その結果、海風時の河川上の気温は街路上のそれに比較して低く、その気温差は海岸からの距離により異なるが、最大4℃に達する。3.満水時と排水時における大きな池とその周辺の熱環境の分布を実測した。池の内部と周囲には低温域が形成されており、その外周200〜400mまでの市街に対し0.5℃程度の気温低下をもたらしている。その冷却効果は池の風上側よりは風下側により広く及んでいる。4.公園緑地内外の熱環境の分布を実測した。公園緑地内はその周辺市街に比べて最大3.5℃低温である。また公園緑地内の大小に依らず、緑被率、緑葉率に対する形態係数が大きくなれば、そこでの気温は低下する傾向にある。5.地表面の粗度による風速垂直分布および地表面温度分布を境界条件として、LESとk-ε2方程式モデルを用いて2次元の市街地風の数値シミュレ-ションを行い、市街地の熱環境を数値シミュレ-ションにより予測できる可能性を示した。6.建物の形状や配置を考慮した地表面熱収支の一次元モデルを作成し、都市の大気境界層に関する数値シミュレ-ションを行い、接地層の気温の垂直分布について実測値とよく一致する結果を得た。建物高さ、人工廃熱、水面・緑地の面積率などに関してパラメ-タ解析を行い、都市の熱環境の定量的な予測を行った。
3 0 0 0 OA 食肉のマリネに関する研究 : 筋原繊維蛋白質の分解を中心として
- 著者
- 妻鹿 絢子 藤木 澄子 細見 博子
- 出版者
- 一般社団法人日本調理科学会
- 雑誌
- 調理科学 (ISSN:09105360)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.197-202, 1980-10-30
- 被引用文献数
- 2
1.市販牛角切り肉を1.5%酢酸溶液に5℃で40時間浸漬するマリネ処理により,官能的にも物理的測定からも肉がやわらかくなることが認められた。同時にマリネ処理肉のpHは4.5付近を示し,肉重量が増加した。2.同様のマリネ処理により,筋原繊維蛋白質中の分子量220,000daltonのミオシンが,150,000daltonfragmentすなわちHMMへと分解した。この時のミオシン分解率は肉中心部で22.3%,肉表層部で44.5%を示し,牛肉ホモジネートをp4.0に調整し,5℃で40時間インキュベートしたモデル実験におけるミオシン分解率46.9%にほぼ一致した。3。肉ホモジネートをpH4.0でインキュベートした場合,水溶性蛋白質が分解し,低分子窒素化合物が増加することが認められた。角切り肉をマリネ処理した場合には,蛋白質の分解により生成した比較的高分子の窒素化合物は肉中に保存され,低分子の窒素化合物は浸漬液中に溶出した。おわりに本研究を行うにあたり終始ご懇篤なる御指導御校閲を賜わりましたお茶の水女子大学荒川信彦教授に厚く御礼を申し上げます。
3 0 0 0 IR 機関リポジトリとオープンアクセス雑誌 : オープンアクセスの理念は実現しているか?
- 著者
- 佐藤 翔 逸村 裕
- 出版者
- 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 = The journal of Information Science and Technology Association (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.4, pp.144-150, 2010-04-01
- 被引用文献数
- 1
機関リポジトリ(IR)とオープンアクセス(OA)雑誌はBudapest Open Access Initiative(BOAI)を背景に普及してきた。本稿では両者の現状をBOAIの理念と持続可能性の観点から検討する。現在のIRとOA雑誌は, BOAIが挙げる3つの障壁のうち法の壁や技術の壁への対応に問題がある。持続可能性については継続的なコンテンツ収集のために,IRでは研究活動の中に埋め込まれること,OA雑誌では質を維持しながら多くの論文を掲載することが重要となる。また,BOAIは「研究の加速」などをOAの実現の目的としているが,IRとOA雑誌にはこれを損なう危険性もある。
3 0 0 0 OA 歴史地震・津波記録の理工学的手法による検証と発生機構の推定の研究
およそ100年ごとの間隔で発生していることが、歴史記録から判明している東海地震・.海地震、三陸沖の巨大地震、およびそれらに誘発されたと考えられる内陸直下の地震について、歴史記録の収集、現地調査、および理工学的考察を経て、発生機構にいたる研究を推進した。海溝型巨大地震として1707年宝永地震、1854年安政東海・.海地震、および古代に発生した869年貞観三陸地震などを検討した。内陸直下の地震としては1596年文禄豊後地震、1828年文政越後三条地震、1812年文化神奈川地震、1855年安政江戸地震などを研究した。
3 0 0 0 IR 松江のハーン(一) : 『盆踊り』と『神々の国の首都』
- 著者
- 牧野 陽子
- 出版者
- 成城大学
- 雑誌
- 成城大學經濟研究 (ISSN:03874753)
- 巻号頁・発行日
- no.107, pp.89-119, 1989-12
3 0 0 0 OA 無電解銅めっきの現状と将来
- 著者
- 清水 悟
- 出版者
- 一般社団法人 表面技術協会
- 雑誌
- 表面技術 (ISSN:09151869)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.81, 2007 (Released:2007-10-19)
- 参考文献数
- 68
- 被引用文献数
- 7 11
- 著者
- 山本 詩子 伊藤 充代
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 助産雑誌 (ISSN:13478168)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.6, pp.542-545, 2010-06
3 0 0 0 OA 新製品開発戦略の「戦略化」プロセスにおける管理会計の役割に関する実践論的研究
・引き続き,被差別部落出身者,ハンセン病病歴者およびその家族,トランスジェンダー,レズビアン,中国帰国者といったインビジブル・マイノリティの聞き取り調査を重ねた。さらに,ハンセン病療養所をフィールドワークし,当事者との関係の構築を図ってきた。・蘭由岐子『病の経験を聞き取る』(2004年)以降,社会学の文脈では,ハンセン病病歴者の姿が隔離政策の「被害者」としてのみ描かれることが批判され,彼ら/彼女らの「生活者」としての姿をとらえるべきだという主張がなされてきた。しかしながら,ともするとそれは,被害を訴える病歴者と,国に感謝する病歴者とを,対立的に位置づけることにつながった。「隔離政策の被害を訴える」語りと,「国に感謝する」語りが,じつは,両方とも隔離政策の力によって生み出されていること。同様に,園内での堕胎について,「意志に反して堕胎させられた」という語りと,「みずから進んで堕胎した」という語りがあるが,これも,両方とも,優性政策の力の強さを示すものであることを,語りの分析によって示した。・群馬県にある国立ハンセン病療養所・栗生楽泉園の入所者自治会が中心となって作成される『栗生楽泉園入所者証言集』編集委員会の一員として,8月から原稿作成作業に専心してきた。これには,ぜんぶで51人の入所者の証言,および,家族や園の元職員らの証言が掲載される予定である。入所者の平均寿命が80歳を超えた現在,これだけの数の当事者の語りを記録できることは,今後はそうそうないことであり,貴重な歴史的資料をつくる営みに参画できた。わたしも編者のひとりであるこの証言集は,2009年夏は出版予定である。
- 著者
- 山下 俊一
- 出版者
- 医歯薬出版
- 雑誌
- 医学のあゆみ (ISSN:00392359)
- 巻号頁・発行日
- vol.172, no.11, pp.p712-713, 1995-03-18
3 0 0 0 OA 「キャラ化」して「笑い」を操る若い世代
- 著者
- 西村 敬子 西村 友希 丸山 浩徳
- 出版者
- 愛知教育大学実践総合センター
- 雑誌
- 愛知教育大学教育実践総合センタ-紀要 (ISSN:13442597)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.169-177, 2010-02
今,日本は急速にキャラ化しているといわれ,私たちの周りには様々なキャラクターグッズがあふれている。子どもたちにとってキャラクターは欠かすことのできないものとなっている。この子どもたちを取りまく生活の中で,肥満や偏食など,食に関する問題が多く発生している。そこで,子どもが自ら健康で自分の体に合わせた食生活について学ぶ手助けをするために食育キャラクター「食まるファイブ」を誕生させた。本研究ではこの「キャラクター」及び「キャラ」という言葉の定義を調べた。さらに子どもたちが楽しく食について学ぶことができるように食育キャラクター「食まるファイブ」のキャラを立て「食まるファイブ」グッズ作製を行った。
本研究は、日本の民謡を題材に、地方文化において伝統芸能の「保存」活動が行われる際の「伝統」の表象や地域文化の表象のありよう、その地域アイデンティティ意識との関わりについて考察しようとするものである。当初は、現地における文献調査や聞き取り調査を通じて、その表象のあり方にみられる「中央」と「地方」との温度差を浮き彫りにしてゆく計画であったが、途中からは、そのようなあり方を生み出す媒介としてメディア、観光、文化運動などの要因が大きな役割を果たしていることが認識されるにいたったため、それら諸要因の絡み合いから生じる様々な力学のありようや、それらが芸能の伝承や保存に関わるプロセスやメカニズムを解明することに焦点が移行した。そのため、民謡だけでなく幅広い対象をとりあげてレコード・メディアや観光産業の関与のあり方を捉える一方で、民謡に関してはそれを応用した形でいくつかの問題をトピック的にとりあげて考えてゆくという形をとることになった。とりわけ、当初「国民文化」として位置づけられていた民謡が「地方文化」として捉えられるようになる上で、昭和戦前期の「旅行ブーム」が大きな役割を果たしたこと、他方で、民謡を「国民文化」の基礎にすえる考え方が戦後にも引き継がれ、それがレクリエーション運動やうたごえ運動などの文化運動と結びついて機能しており、それが今日とは異なる民謡の「保存」や「伝承」のあり方を生み出していたことなどを明らかにしえた。なお、現在まだ未定稿の状態にあるいくつかの論考を完成させた上で、本研究の成果は本年中には単行本として公刊される見通しである。
3 0 0 0 OA 裁判員制度と犯罪被害者参加制度の新設下での死刑存廃論の倫理学的研究
- 著者
- 平田 俊博
- 出版者
- 国立大学法人山形大学
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2008
現代の日本において、どのようにして死刑制度について国民的合意が可能か、をカント倫理学に立脚して市民レベルで究明した。そのために、生者と死者の相関関係の3様態に基づく近代倫理の3区分という新機軸の構想を導入することによって、殺人行為の3領域を明らかにした。つまり、行為者に定位する功利主義的な近代法、行為とその動機に定位するカントの義務倫理、行為の結果に定位する前近代の宗教倫理である。
3 0 0 0 日本語ディベートにおける「わかりやすさ」に関する考察
- 著者
- 松本 茂
- 出版者
- 日本コミュニケーション学会
- 雑誌
- Speech communication education (ISSN:13470663)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.29-41, 1999
3 0 0 0 知識創出を目指した集合知再構成手法の提案
- 著者
- 川戸祐介 松村 敦 宇陀 則彦
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告情報学基礎(FI) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.109, pp.1-6, 2007-11-08
本研究は複数の関連する集合知の情報を再構成することで,単体の集合知の利用ではできなかった新しい知識創出を目指した.まず,ソーシャルブックマーク,百科事典作成,Q&A サイトの各集合知を利用する場合の問題点を指摘した.次に,複数の集合知を組み合わせ,これらの問題を解決可能な,回答の補完,百科事典の項目に対する意見付与,意味的な類似キーワードの付与の3例を示した.これらを実現するための,集合知の再構成手法を検討し,プロトタイプシステムの実装を行った.In this research we propose a new reconstruction method that intends to create a combination of knowledge from collective intelligence. At first, we examined some problems on use of single collective intelligence. To solve these problems, we put multiple collective intelligence together and reconstruct. We report this method and the prototype system.
3 0 0 0 OA 急性期医療の看護場面における実践知の記述的研究
本研究では各大学における教育目標、教育方針、アドミッションポリシーと中等教育の多様性の適合度を明らかにしたいと考え、入学者受入方針等に関する調査を行うとともに、AO入試の実施状況、オープンキャンパスにおける高校生に対する情報提供の現状と課題、専門高校および総合学科高校出身者の大学受入の現状、ならびに入学者の志望動機等に関するアンケート調査などを実施した。また、専門高校、総合学科高校、SSHと高大接続、総合的な学習と高大接続などの高校での学びの多様化と大学入試について研究会を開催し、話し合った。モデル化も行う予定であったが、この数年でAO入試実施大学が急激に増加し、そのアドミッションポリシーも新たに独白性を持ったものが増えており、今後さらに増加すると予想されるため、静的なモデルではあまり意味がないと考え現状分析を行った。今後、時代の変化に応じた新しい入試や大学進学を扱う、環境適応能力を表現できる動的なモデルを考える必要があると思う。アドミッションポリシー、入学試験や合格者への調査は本研究のメンバーによって大変精力的に行われ、大きな成果があったと考えている。一方、入学後ある程度の時間を経た学生や大学側の満足度のような指標の調査はあまり広く実施できなかった。複数の大学で共通のアンケート調査を実施して卒業研究評価を試み、幸い九州大学と筑波大学の2大学で実施した結果を平成18年度の入研協で報告できることとなったが、このような共同研究は大学間の調整の困難さだけでなく、アドミッションセンターと学部や学科との間の調整がかなり困難であるらしいことも分かった。海外調査はSARSの影響で平成16年度以降に行った。欧州の調査は行えなかったが本研究メンバーが他の研究費で行ったフィンランド等の調査結果について本研究のミーティングで知ることができた。本研究では米国、オーストラリア、中国、台湾の調査を行い、各国で入試の多様化が進んでいることが分かった。「理科離れ」について、理科教育を熱心に行っている教員や学芸員、SSHの教員との研究会を開催してAO入試との関連について話し合った。総合的な学習で理科が好きになる、総合的な学習の時間を減らして理科の時間を増やすべき、などの意見があった。しかし、私見であるが、実践されている授業内容に大きな違いは無いように思われ、また、理科離れは科学振興という社会の要請と生徒や学生の個人の幸福が結びついていないというところにも問題があると思われた。さらなる研究が必要である。本研究の成果は、平成15、16年度中間報告書とシンポジウム論文集ならびに成果報告書の4部に収録した。