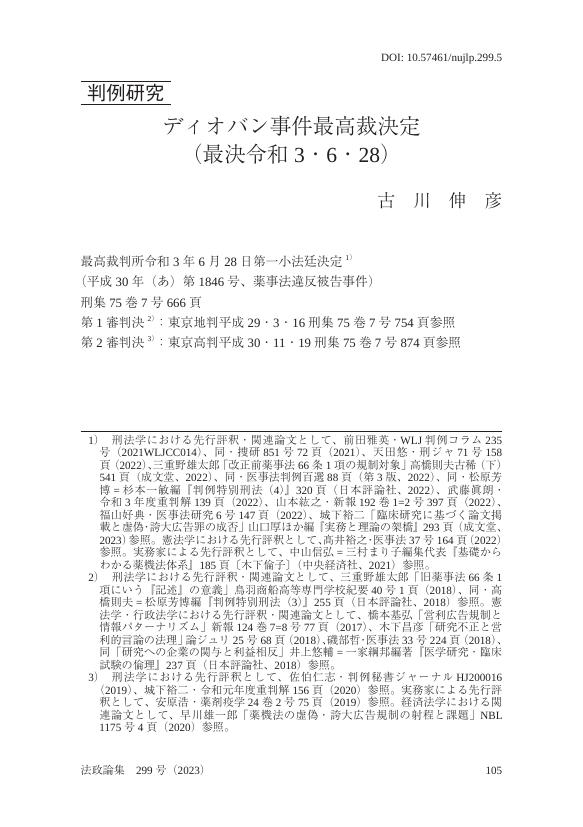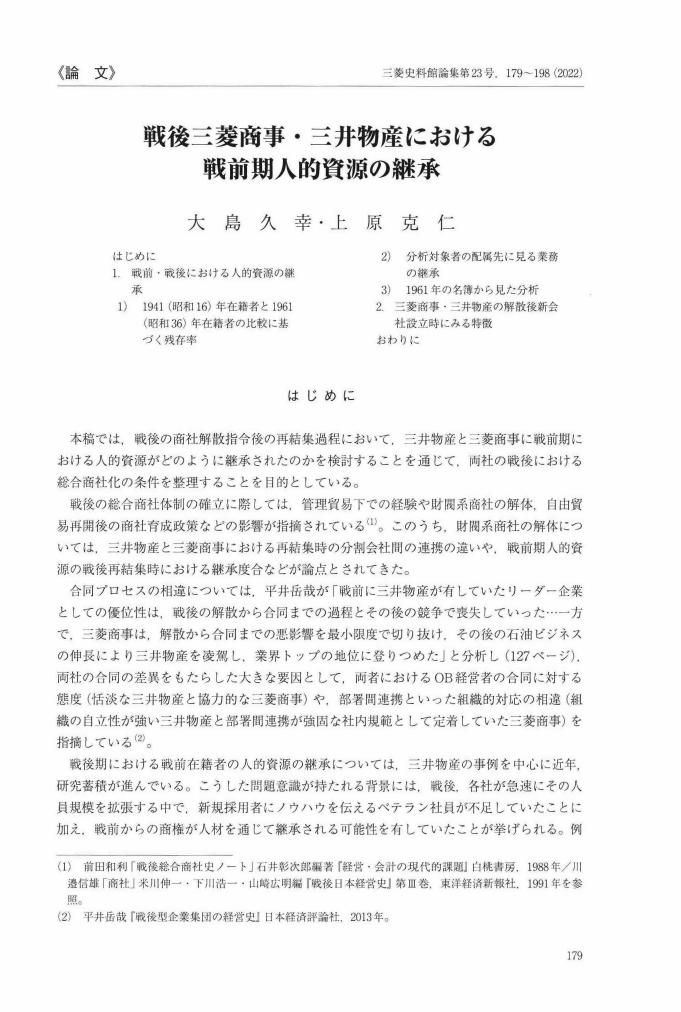6 0 0 0 OA ディオバン事件最高裁決定(最決令和3・6・28)
- 出版者
- 東海国立大学機構 名古屋大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 名古屋大学法政論集 (ISSN:04395905)
- 巻号頁・発行日
- vol.299, pp.nujlp.299.5, 2023 (Released:2023-09-28)
6 0 0 0 OA 原資産価格過程不要な敵対的Deep Hedging
- 著者
- 平野 正徳 南 賢太郎 今城 健太郎
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023, no.FIN-030, pp.51-57, 2023-03-04 (Released:2023-03-04)
深層学習と価格時系列シミュレーションを用いてオプションのヘッジ戦略を学習するDeep Hedgingは,取引手数料などを考慮に入れたより現実的な取引戦略を立てることができるため,近年脚光を浴びている.しかしながら,その学習において活用される原資産価格のシミュレーターは,Heston過程などの特定の価格過程を使用することが多い.そこで,本研究においては,特定の価格過程を用いることなく,Deep Hedgingの取引戦略の学習を可能にする手法を提案する.提案手法では,架空の任意の価格過程を生成する生成器とDeep Hedgingが敵対的に学習を行う.提案手法を用いた場合,一切の価格時系列を与えることなく,通常のDeep Hedgingとほぼ同等の性能のヘッジを行えることを示した.
6 0 0 0 OA 4.医薬品の毒性評価の考え方
- 著者
- 小野寺 博志
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床薬理学会
- 雑誌
- 臨床薬理 (ISSN:03881601)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.4, pp.147-152, 2010 (Released:2010-10-08)
- 参考文献数
- 18
Drugs have to be evaluated from a different viewpoint from other toxic substances such as natural toxins, environment substances and chemicals. Toxicological evaluations are also important to clarify the benefits and risks of pharmaceuticals to humans. Many of the toxicology studies are conducted according to guidelines. The type and timing of toxicology studies have been harmonized internationally. Recently, the ICH guidelines have been revised in light of technological advances and reduction of animal usage in accordance with the 3R (reduce/refine/replace) principle. The results of toxicology studies must always be evaluated based on extrapolation to humans. The goal of regulatory science is to predict a risk based on the latest information and evaluate safety. Even if the toxicological findings are similar, the toxicological acceptability assessment is not always the same. It is important that the toxicology for pharmaceutical products is evaluated on a case-by-case basis.
6 0 0 0 OA 看護職・リハビリテーション職の多職種連携態度に影響を及ぼす対人葛藤解決方略の検討
- 著者
- 深澤 彩 高田 幸子 近藤 健 金 始映 李 範爽
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.5, pp.614-621, 2023-10-15 (Released:2023-10-15)
- 参考文献数
- 34
急性期と回復期病棟に勤務する看護職とリハビリテーション職の計94名を対象に,対人葛藤解決方略が多職種連携態度に及ぼす影響を調査した.多職種連携態度は修正版Attitudes toward Health Care Teams Scale,対人葛藤解決方略はRahim Organizational Conflict Inventory-Ⅱを用いて評価した.結果,統合解決と妥協の方略は多職種連携態度に正の影響を及ぼした.双方が受け入れられる解決策を見つける統合解決の視点と行き詰まりを打破するために中間点を提案する妥協の視点は,多職種連携態度に前向きな影響を及ぼすことが示唆された.
6 0 0 0 OA 近現代日本における食肉文化 食肉・居場・部落をめぐるオーラルヒストリー
- 著者
- 桜井 厚
- 出版者
- 日本オーラル・ヒストリー学会
- 雑誌
- 日本オーラル・ヒストリー研究 (ISSN:18823033)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.27-41, 2019-09-30 (Released:2020-12-24)
- 参考文献数
- 15
6 0 0 0 OA テレビ番組における「いじめ」描写が子供の「いじめ」行為に与える影響に関する研究
- 著者
- 佐々木 輝美 武藤 栄一
- 出版者
- 日本教育メディア学会
- 雑誌
- 放送教育研究 (ISSN:03863204)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.57-70, 1987-05-31 (Released:2017-07-18)
While the problem of "ijime (bullying)" has become serious among pupils, few scholars have paid attention to this problem until recently. Among the studies done by scholars, most of them are fact-finding surveys and are not enough to explain why pupils bully others. Pupils' ijime behavior is sometimes very violent and such behavior is often portrayed on TV programs. Thus, it is possible to consider the issue from the view point of TV violence. Many researchers have undertaken studies of TV violence in western countries. Several theories on the mechanics of how television violence affects the viewer have been raised. One such theory, supported by past research, deals with the effects of modeling as well as of desensitization. The objective of this study is to examine the effects of "ijime" TV programs on children within the framework of observational learning theory and desensitization theory. The following three hypotheses will form the basis for this study. 1) Pupils exposed to "ijime" TV programs tend to bully others. 2) Pupils learn ways of bullying more through TV than any other medium. 3) Pupils exposed to "ijime" TV programs are more desensitized to bullying behavior by others. A survey was conducted in order to test the above hypotheses. The subjects were 977 (male 497, female 480) junior high-school students. The questionnaire included the following headings: 1) sex 2) programs frequently watched 3) experiences of bullying behavior 4) media through which students learn this bullying behavior 5) degree of desensitization to real bullying (students were asked how they would react if they happened to see real bullying by others) The first hypothesis was proved as a result of a chi square analysis of the obtained data; while the others were not. By discussing these results, the following were suggested. 1) In measuring desensitization, our questionnaire did not seem to be sensitive enough, and this reminds us of the basic problem of difficulty in measuring attitude. 2) In the process of learning bullying behavior, personal media as well as mass media seem to function as sources of acquiring bullying methods. This suggests that it would be necessary to clarify the interaction of these two types of media. 3) Pupils exposed to " ijime" TV programs tend to bully others and this suggests the necessity to control the portrayal of bullying behavior on TV.
6 0 0 0 OA 日本語より英語の呼称が頻出した 超皮質性運動失語の一例
- 著者
- 畑中 美穂 島守 勇気 古村 梨絵 柴内 一夫 紺野 広
- 出版者
- 紀要編集小委員会
- 雑誌
- 八戸赤十字病院紀要 = Acta Medica HACHINOHE Institutio Hospitalis Crucis Ruberae (ISSN:09198121)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.23-28, 2015-03-26
6 0 0 0 OA 動物の共感 - 比較認知科学からのアプローチ -
- 著者
- 渡辺 茂
- 出版者
- 認知神経科学会
- 雑誌
- 認知神経科学 (ISSN:13444298)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.89-95, 2011 (Released:2017-04-12)
共感は社会的認知の基礎的な機能であると考えられる。他者の情動とそれによって 惹起された自己の情動状態によって共感は4 つに分類できる。他者の不快が自分の不快にな る場合を負の共感、他者の快が自分の快になる場合を正の共感、他者の快が自分の不快にな る場合を逆共感、そして他者の快が自分の不快になる場合は慣習的にSchadenfreude と言わ れる。主としてマウスの研究から動物での共感を調べると負の共感、正の共感、逆共感は一 定に見られるもののSchadenfreude は認められない。Schadenfreude はかなり複雑な長期持続 的社会において形成された情動の形態であると考えられる。
6 0 0 0 OA 急性期から行う脳卒中重度片麻痺例に対する歩行トレーニング(第二部)
- 著者
- 阿部 浩明 辻本 直秀 大鹿 糠徹 関 崇志 駒木 絢可 大橋 信義 神 将文 高島 悠次 門脇 敬 大崎 恵美
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会宮城県理学療法士会
- 雑誌
- 理学療法の歩み (ISSN:09172688)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.11-20, 2017 (Released:2017-04-11)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 9
これまでの脳卒中例に対する理学療法技術は十分な科学的効果検証を行われずに継承されてきたものが少なくなかったかもしれない。脳卒中例に対する理学療法は主観的な評価が中心であったり,経験のみに基づいて構築されたりしていくべきものではなく,有効と思われる治療は検証を経た上でその有効性を示していくべきであろう。 前号に引き続き,我々がこれまで取り組んできた急性期の脳卒中重度片麻痺例に対する歩行トレーニングの実際と装具に関わる臨床および学術活動について紹介する。
6 0 0 0 OA 日本語の方言研究と一般言語学
- 著者
- 窪薗 晴夫
- 出版者
- The Linguistic Society of Japan
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.148, pp.1-31, 2015 (Released:2016-05-17)
- 参考文献数
- 69
- 被引用文献数
- 1
この論文では,日本語の音声データ,とりわけ語アクセントに関連するデータをもとに,一般言語学が日本語(方言)の研究にどのような新しい知見をもたらすか,逆に日本語方言の実証的,理論的研究が一般言語学や他の言語の研究にどのような洞察を与えるか考察する。具体的な例として「音節量」の現象を取り上げ,この概念を日本語の分析に導入することにより,さまざまな日本語の諸言語が一般化できること,また,そのようにして得られた日本語の分析が一般言語学,音韻理論の研究に大きく寄与できる可能性を秘めていることを指摘する。論文の後半では日本語諸方言のアクセント体系・現象を取り上げ,この言語が「アクセントの宝庫」と言えるほど多様なアクセント体系を有していること,そしてその分析が言語の多様性について重要な示唆を与えることを指摘する。
6 0 0 0 OA 松原武生先生を偲んで (追悼)
- 著者
- 米沢 富美子
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.4, pp.292, 2015-04-05 (Released:2019-08-21)
6 0 0 0 OA 近世の権力者の邸宅における催能の場についての考察
- 著者
- 丸山 奈巳
- 出版者
- 建築史学会
- 雑誌
- 建築史学 (ISSN:02892839)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, pp.2-36, 2018 (Released:2019-10-30)
6 0 0 0 OA 戦後三菱商事・三井物産における戦前期人的資源の継承
- 著者
- 大島 久幸 上原 克仁
- 出版者
- 公益財団法人 三菱経済研究所
- 雑誌
- 三菱史料館論集 (ISSN:13453076)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, no.23, pp.179-198, 2022-03-20 (Released:2023-07-27)
6 0 0 0 OA 三菱商事における学歴と昇進
- 著者
- 大島 久幸 中林 真幸
- 出版者
- 公益財団法人 三菱経済研究所
- 雑誌
- 三菱史料館論集 (ISSN:13453076)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, no.22, pp.1-18, 2021-03-20 (Released:2023-07-27)
6 0 0 0 OA 急性期から行う脳卒中重度片麻痺例に対する歩行トレーニング
- 著者
- 阿部 浩明 大鹿 糠徹 辻本 直秀 関 崇志 駒木 絢可 大橋 信義 神 将文 高島 悠次 門脇 敬 大崎 恵美
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会宮城県理学療法士会
- 雑誌
- 理学療法の歩み (ISSN:09172688)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.17-27, 2016 (Released:2016-04-21)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 11
これまでの脳卒中者に対する理学療法技術は十分な科学的効果検証を行われずに継承されてきたものが少なくなかったかもしれない。脳卒中者に対する理学療法の治療指針を示す脳卒中理学療法診療ガイドラインにはエビデンスに基づき推奨される治療が記載されている。しかし、実際の理学療法の臨床では多様な意見があり、必ずしもガイドラインが有効に用いられてはいない感がある。脳卒中の理学療法は主観的な評価が中心であったり、経験のみに基づいて構築されたりしていくべきものではなく、有効と思われる治療は検証を経た上でその有効性を示していくべきであろう。 ここでは我々がこれまで取り組んできた急性期の脳卒中重度片麻痺例に対する歩行トレーニングの実際について概説し、装具に関わる臨床および学術活動について次号に渡って紹介したい。
6 0 0 0 現代日本文学はなぜビデオゲームを志向するのか?
- 著者
- 大西 永昭
- 出版者
- 松江工業高等専門学校
- 雑誌
- 若手研究
- 巻号頁・発行日
- 2023-04-01
新規メディアの登場とともに更新されてきた我々人間の認識や感性が文学にどのように影響してきたのかを、世界でも有数のビデオゲーム大国である日本の現代文学を題材として考察を行い、ゲーム的な感性が現代人にいかに根付いているかを明らかにする。
6 0 0 0 OA アルコール飲料摂取後の呼気に含まれる臭気成分の同定
- 著者
- 根来 宏明
- 出版者
- Brewing Society of Japan
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.111, no.11, pp.694-700, 2016 (Released:2018-08-06)
- 参考文献数
- 9
酒臭い息で帰宅して家族に顔をしかめられる,多くの人が身に覚えがあるのではないだろうか。飲酒後の呼気のにおいは,お酒を敬遠する要因の一つかもしれない。著者らは,GC-olfactometry/MSを用いて呼気の「酒臭さ」に関わるにおい成分を同定し,さらに,お酒の種類やタイプの間でもその成分に違いがあることを明らかにした。今後,「酒臭くならない」お酒の開発などにもつながっていきそうな,興味深い研究である。
6 0 0 0 OA セロトニントランスポーター遺伝子のSアレルを有する日本人の生理人類学的特徴
本研究は日本人集団におけるセロトニントランスポーター遺伝子多型(5-HTTLPR)と社会的集団維持に関わる生理心理反応の関連を明らかにすることを目的とし、人物画像の呈示実験における生理反応、性格特性との関連を検討した。その結果ss型は、人物画像により大きな注意反応を示し、lアレル及びオキシトシンレセプター遺伝子多型のAアレルを持つ被験者は、Buss-Perry攻撃性質問紙の「言語的攻撃」「敵意」「短気」得点が有意に高かった。従って社会的集団維持に寄与すると考えられる生理反応や一部の性格特性が5-HTTLPR 遺伝子多型に影響を受けることが示唆された。
6 0 0 0 OA 図書館におけるゲームを用いた取組事例
- 著者
- 高倉 暁大
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.8, pp.350-356, 2021-08-01 (Released:2021-08-01)
全米図書館協会(ALA)の取り組みに始まり,全世界の図書館では様々なゲームを提供するようになってきた。近年,日本でも公共図書館を中心にゲームを活用した企画が数多く開催されている。賑わい創出,資料の利用促進,コミュニティの確立など様々な目的の元に行われ,効果を上げている一方,騒音問題,ゲーム知識や技術のある司書が必要というハードルの高さなど,課題も多く見られる。本稿では,図書館でのゲーム企画事例を紹介し,その目的や狙い,効果などを述べる。