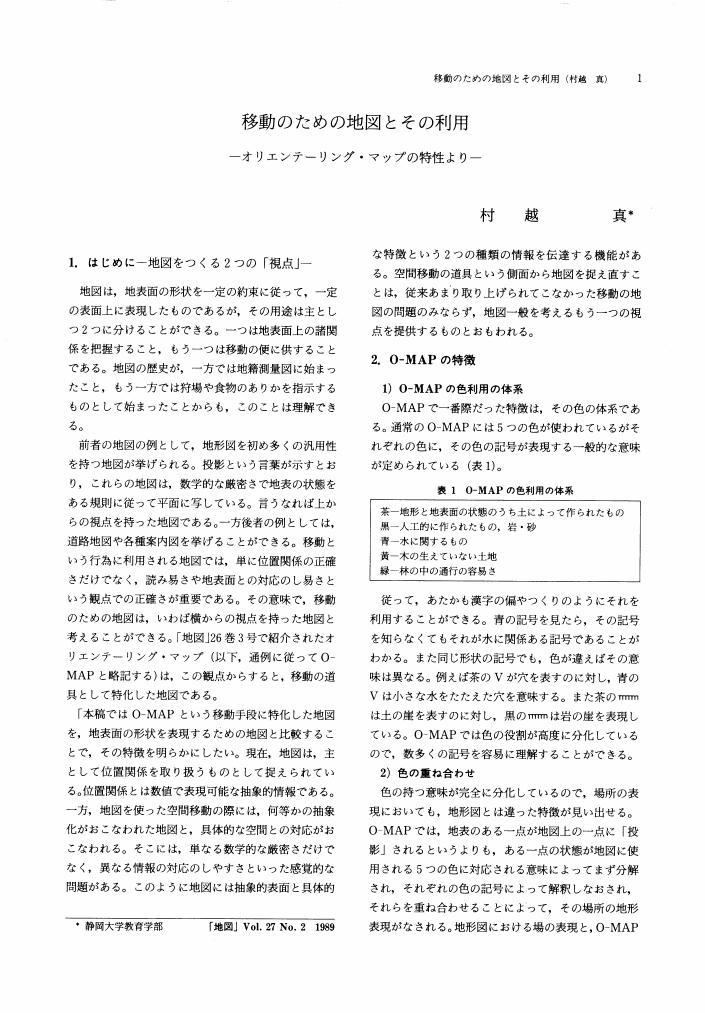3 0 0 0 OA 昭和の3大台風時の瀬戸内海,伊勢湾,東京湾における波高分布の再現
- 著者
- 山口 正隆 畑田 佳男 野中 浩一 大福 学 日野 幹雄
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集B2(海岸工学) (ISSN:18842399)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.I_131-I_135, 2011 (Released:2011-11-09)
- 参考文献数
- 5
Shallow water wave hindcastings are conducted in the Seto Inland Sea, Ise Bay and Tokyo Bay for each of the so-called 3 giant typhoons in the Showa Era (Muroto Typhoon in 1934, Makurazaki Typhoon in 1945 and Isewan Typhoon in 1959). The computations follow the spatial distribution of time-dependent wave height and maximum value. The sea wind distributions given as the driving forces are estimated using a method which transforms the land-based measurement wind data into the wind data at sea or coastal stations and applies a spatial interpolation technique to the data. The main conclusion is that any of the typhoons may have generated the largest wave height over the past 90 years in the sea area of the typhoon path.
3 0 0 0 OA 書店をめぐる現在(<特集>当世"書店"気質)
- 著者
- 柴野 京子
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.8, pp.310-314, 2013-08-01 (Released:2017-04-18)
- 参考文献数
- 20
ここ10年ほどの間に,日本の新刊書店数は7割程度まで減少した。とくに著しいのは個人経営の小規模書店の閉店だが,郊外化や都市部への大型出店をすすめてきたチェーン書店や大書店もまた,ブックオフやアマゾンなど,既存の枠組みの外からもたらされた環境の変化に直面している。ここではそれらの状況を概観したうえで,インターネット書店のデザインが現実の書店にもたらした影響や,バーチャルとの対比で新たに発見される「リアル」書店のありようなどについて,代表的な事例を用いながら,実験的に言及していく。
3 0 0 0 OA スギ花粉症舌下免疫療法の治療2年目における症状改善の増強効果
- 著者
- 湯田 厚司 小川 由起子 鈴木 祐輔 有方 雅彦 神前 英明 清水 猛史 太田 伸男
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, no.1, pp.44-51, 2017-01-20 (Released:2017-02-10)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 4
舌下免疫の最初の数年間の効果は治療年数により高まるとされる. スギ花粉舌下免疫の同一患者での症状を, ともに中等度飛散であった2015年 (花粉総数2,509個/cm2) と2016年 (同3,505個/cm2) の2年間で検討した. 【方法】発売初年に開始した舌下免疫132例 (41.8±17.5歳, 男女比75: 57) と対照に初期療法56例 (44.9±13.5歳, 同25: 31) を選択した. 2015年と2016年の両方のスギ花粉飛散ピーク時に, 1) 症状スコアと症状薬物スコア, 2) Visual analog scale, 3) 日本アレルギー性鼻炎標準 QOL 調査票 (JRQLQ No1) で調査した. 主目的に舌下免疫療法2年目に効果が増強するか, 副次目的に舌下免疫と初期療法の比較とした. 【結果】推定周辺平均ですべてに治療方法と年度に交互作用はなく, くしゃみ, 鼻汁, 鼻閉, 眼のかゆみなどの眼鼻症状において, 初期療法には2年での差はなく, 舌下免疫療法の多くで2年目は1年目より有意に良かった. 全般症状の項目も同様であった. QOL (quality of life) は, 舌下免疫の17項目中2項目のみで有意に2年目が良かった. また, ほとんどの項目で舌下免疫は初期療法より有意に効果的であった. 【結論】初期療法を対照にした中等度飛散の2年の比較で, 舌下免疫の治療効果は治療1年目より2年目で高まっていたと考えられる.
- 著者
- 中村 智美 石倉 宏恭 中野 貴文 仲村 佳彦 神村 英利
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.589-596, 2018-08-31 (Released:2018-09-01)
- 参考文献数
- 12
播種性血管内凝固症候群(DIC)治療薬の遺伝子組み換えヒト可溶性トロンボモジュリン(rTM)の急性腎障害(AKI)患者への至適用量を検討した。rTM を1日1回380U/kgまたは130U/kgで投与したDIC合併AKI患者129例を対象とし,持続的血液濾過透析(CHDF)の有無およびrTMの投与量別に,有効性・安全性を評価した。DIC離脱率は,CHDFを施行しなかった患者群ではrTMの用量による違いはなかったが,CHDF施行群では380U/kg群のほうが高い傾向であった(p=0.050)。出血率はCHDFの有無およびrTMの用量間で差はなかった。以上より,AKI合併DIC患者にはrTM 130U/kgと380U/kgで有効性,安全性に差はないものの,CHDF施行時には380U/kg投与によりDIC離脱の可能性が高まることが示唆された。
- 著者
- Tomohiro Murase Kosuke Oiwa Akio Nozawa
- 出版者
- The Institute of Electrical Engineers of Japan
- 雑誌
- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)
- 巻号頁・発行日
- vol.138, no.9, pp.1148-1153, 2018-09-01 (Released:2018-09-01)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 4
In automated driving at Level 3, drivers constantly need to allocate attention to the driving environment to react immediately to a take-over request. However, the amount of attention of drivers to the driving environment has not been quantified. The objective of this study was a quantitative evaluation of the amount of attention to the driving environment, and the psychophysiological state of the driver, during automated driving at Level 3. Attention and driver state at Level 3 were evaluated using ERP and psychophysiological indices respectively with compared to Level 2. The dual task method was used, in which twelve subjects performed driving tasks (Level 2 and Level 3) on a driving simulation system while in parallel performing an auditory oddball task. The data showed that the amount of attention to the driving environment at Level 3 decreased in comparison to Level 2, as indirectly measured by a 19.2% increase in attention to the auditory oddball task. Sympathetic nervous system activity during Level 3 automated driving decreased as compared to Level 2. In the psychological state, comfortable feeling and arousal level decreased at Level 3.
3 0 0 0 OA 市販されている魚卵の脂肪酸組成とその特徴について
- 著者
- 原馬 明子 勝間田 祥帆 手代木 栞 守口 徹
- 出版者
- 日本脂質栄養学会
- 雑誌
- 脂質栄養学 (ISSN:13434594)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.225-230, 2017 (Released:2017-09-20)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
The consumption of seafood in Japan has continued to decline, and consumption of meat is increasing. One reason for this is that it takes time to cook fish. Therefore, we focused on fish roe that require little cooking time, and examined whether they can be used as a food source of n-3 fatty acids. We selected salmon (sujiko and ikura), herring, cod, flounder, flying fish, and smelt roe, and measured their eicosapentaenoic acid (EPA) content, docosahexaenoic acid (DHA) content and n-6/n-3 ratio by fatty acid analysis. In addition, cooked cod, flounder, and smelt roe were analyzed. The amounts of EPA and DHA in each fish roe were in the order salmon roe 1 (sujiko)> smelt roe ≒ salmon roe 2 (ikura)> cod roe ≒ flounder roe > herring roe > flying fish roe. There was no difference in the amount of EPA, DHA, and fatty acid composition between raw and cooked roe. All fish roe contained only traces of n-6 fatty acid, and the n-6/n-3 ratio was as low as 1 or less. Our results showed that EPA and DHA can be easily acquired from fish roe, particularly salmon roe. Moreover, the EPA and DHA content of fish roe was not decreased by cooking, so they are suitable as a food source of n-3 fatty acids.
3 0 0 0 OA 一般的信頼のマルチレベル規定構造の変化
- 著者
- 大崎 裕子 坂野 達郎
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.20-38, 2016 (Released:2016-08-06)
- 参考文献数
- 26
ソーシャル・キャピタル研究において,制度信頼とアソシエーション参加は一般的信頼の主要規定因とされるが,どちらがより有力な規定因であるかについては見解が一致していない.本稿の目的は,Inglehart and Welzelが論じる社会の価値体系の変化を考慮することで,対立的に論じられてきた2要因の一般的信頼に対する効果について統合的に論じることである.データに世界価値観調査と欧州価値観調査をもちい,価値変化により分類される前工業社会,工業社会,ポスト工業社会の3つの国家グループに対して,個人,国レベルにおける2要因の一般的信頼規定力をマルチレベル分析により検討した.その際,価値変化が2要因の内的構造に与える影響も考慮し,3社会のマルチレベル因子構造の比較も行った.マルチレベル分析の結果,個人,国レベルともに,(1)前工業社会では一般的信頼に対する2要因の規定力はほぼ同等であるのに対し,工業社会ではアソシエーション参加と比べ制度信頼が強い規定力を示した.(2)ポスト工業社会では工業社会と同様の傾向が維持されたが,制度信頼については秩序維持制度への信頼と政治制度への信頼の両方の効果が示された.これらの結果から,工業化による世俗的・合理的価値の高まりにより制度信頼の一般的信頼規定力が増大し,その規定効果はポスト工業化による自己表現価値の高まりによって多様化することが示唆された.
3 0 0 0 OA 古景観の復原における3次元景観情報を用いた地理的想像の喚起
- 著者
- 早川 裕弌 安芸 早穂子 辻 誠一郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.236-250, 2018 (Released:2018-05-31)
- 参考文献数
- 41
現象を空間的に拡張して想像する「地理的想像」を喚起し,地理的思考を促すことは,地理学のアウトリーチにおいて必要なアプローチのひとつである.本研究では,特に3次元地理空間情報を用いた空間的現象の可視化の手法を,縄文時代の集落生態系を対象とした古景観の復原に適用し,その効果的な活用について検討する.まず,小型無人航空機を用いた現景観の3次元空間情報を取得し,古景観の復原のためのデータ解析を行う.次に,オンラインシステムを用いた古景観の3次元的な表示と,博物館における展示としての提供を行い,その効果を検証する.ここで,地理学,考古学,第四紀学的な研究成果の統合だけでなく,芸術分野における表現手法との融合的表現を試みることにより,さまざまな閲覧者の時空間的な地理的想像を補うかたちで,復原された古景観の直感的理解を促す効果が示された.これは,地理的思考の普及にも発展的に貢献できることが期待される.
3 0 0 0 OA 高校初年次生と大学生の説明文理解に及ぼす標識化効果の境界条件
- 著者
- 山本 博樹 織田 涼 島田 英昭
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.3, pp.240-250, 2018 (Released:2018-08-28)
- 参考文献数
- 24
We examined the hypothesis that the effect of signaling on students' prose comprehension is significant only when structure strategies are deficient during production. Participants included first-year high school students (N = 120, mean age 16.0) and university students (N = 120, mean age 20.8). Students' tendencies to use structure strategies were evaluated and classified as lower-structure (LS) or upper-structure (US) strategy using the median (23 high school students and 25 university students). Participants performed sentence arrangement, recall, and reconstruction tasks. Each task consisted of expository sentences with or without signaling. The results indicated the following: (a) Signaling facilitated structure identification in organizational processes in the US strategy group of high school students, which improved their prose comprehension, whereas no effects were evident in the LS strategy group. (b) An identical effect was seen in the LS strategy group of university students, whereas it was not observed in the US strategy group. These results support our hypothesis. The boundary conditions for the effect of signaling on students' prose comprehension are discussed from the perspective of the production deficiency in structure strategy.
- 著者
- 西川 徹
- 出版者
- 日本生物学的精神医学会
- 雑誌
- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.131-134, 2014 (Released:2017-02-16)
本シンポジウムでは,4 名のケタミンによる抗うつ効果の研究者が,最近得た成果について講演した。初めに,世界で初めてうつ病患者の治療に低用量のケタミンを導入した,Yale大学精神科の Krystal 教授が単独で投与した低用量ケタミンの抗うつ作用について最新の知見を報告した。次に,札幌鈴木病院の岡本主任医長が国立精神・神経医療センターで行った,難治性うつ病への修正電気療法において,麻酔にケタミンを使用する方が通常の propofol を投与するより優れていることを示した。3 番目の,浜松ホトニクスの塚田 PET センター長は,サルにおける PET 脳画像解析を進め,低用量のケタミンが NMDA 型グルタミン酸受容体遮断薬としてだけでなく,セロトニン取り込み阻害薬としても作用することを明らかにした。最後に,ミシガン大学の Domino 教授が抗うつ効果と基礎研究がもたらした謎のいくつかを説明する,ケタミンの多様な神経薬理学的メカニズムを展望した。
3 0 0 0 OA 牛のモロヘイヤ (Corchorus olitorius L.) 種子中毒
- 著者
- 濱口 芳浩 平井 良夫 谷山 敦 合澤 正哲
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.8, pp.407-410, 1998-08-20 (Released:2011-06-17)
- 参考文献数
- 8
実のついたモロヘイヤを黒毛和種繁殖母牛に給与したところ, 食欲不振, 下痢などの症状を呈して2日後に3頭が死亡し, 剖検では心外膜下の点状出血ならびに心内膜下出血が認あられた. 病理組織学的には心内膜に著明な出血, 脾臓に出血およびヘモジデリン沈着, 肝臓にうっ血が認あられた. モロヘイヤの実および死亡牛心臓の塩基性抽出液 (Stas-Otto法) から薄層クロマトグラフ法でストロファンチジンが検出され, モロヘイヤの実のエタノール抽出液を腹腔内投与されたマウス3匹中2匹が死亡した.
3 0 0 0 OA 熱中症死亡数と気象条件
- 著者
- 中井 誠一
- 出版者
- 日本生気象学会
- 雑誌
- 日本生気象学会雑誌 (ISSN:03891313)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.4, pp.169-177, 1993-12-01 (Released:2010-10-13)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 10
日本における1970年から1990年までの熱中症死亡数と気象条件の関係を検討した.熱中症死亡数は21年間で1, 450件であり, 年平均にすると69件 (26件から155件の範囲) であった.熱中症死亡数1, 450件のうち65歳以上の年齢の占める割合は41.4%, 25歳から64歳までは37.2%であった.東京および大阪管区気象台の資料から熱帯夜 (日最低温度が25℃以上の日) 真夏日 (日最高温度が30℃以上の日) の日数を調査した.その結果年間熱中症死亡数と熱帯夜および真夏日の年間発生数との間に有意な相関関係が認められた.
- 著者
- Tomohiro Nishimura Wittaya Tawong Hiroshi Sakanari Takuji Ikegami Keita Uehara Daiki Inokuchi Masatoshi Nakamura Takuya Yoshioka Shota Abe Haruo Yamaguchi Masao Adachi
- 出版者
- The Plankton Society of Japan, The Japanese Association of Benthology
- 雑誌
- Plankton and Benthos Research (ISSN:18808247)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.46-58, 2018-05-30 (Released:2018-05-24)
- 参考文献数
- 68
- 被引用文献数
- 13
Ciguatera fish poisoning (CFP) is caused by toxins originating from an epiphytic/benthic dinoflagellate of the genus Gambierdiscus. In Japan, CFP cases have been increasingly reported not only in subtropical areas but also in temperate areas. It is therefore important to study Gambierdiscus cell occurrences, cell densities, and population dynamics to address CFP outbreaks in Japan. This study assessed the densities in Japanese shallow waters (0.1–3 m depths) and revealed that the densities were lower than those in tropical and subtropical areas worldwide. In the shallow waters of Tosa Bay, a Japanese temperate area, population dynamics of Gambierdiscus cells were assessed monthly between 2007 and 2013. Gambierdiscus did not show substrate preferences for macroalgal species. The cell densities in the area ranged from 0 to 232.2 cells g−1 wet weight algae. The average cell densities in spring, summer, autumn, and winter were 0.1±0.4, 0.9±2.6, 4.0±20.6, and 0.4±1.4 cells g−1 wet weight algae, respectively. The cell densities in summer and autumn were not significantly different (p>0.05), whereas those in summer and autumn were significantly higher than those in spring and winter (p<0.01). A significant positive correlation between cell densities and sea surface temperatures (SSTs) was observed (rs=0.21, p<0.001), while a significant negative correlation between cell densities and salinity was recognized (rs=−0.18, p<0.001). These results suggest that cell densities of Gambierdiscus in Japanese temperate shallow waters increase in summer and autumn when the SST is high and salinity is moderately low.
3 0 0 0 OA 経営学者の立ち位置は?
- 著者
- 立本 博文
- 出版者
- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター
- 雑誌
- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)
- 巻号頁・発行日
- pp.0180618a, (Released:2018-06-19)
- 参考文献数
- 1
3 0 0 0 OA 「見せ物の場所」から「生きられる空間」へ
- 著者
- 李 小妹
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2008年 人文地理学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.501, 2008 (Released:2008-12-25)
本研究は,中国・シンセンにある「錦繍中華」,「中国民俗文化村」と「世界之窓」という三つのテーマパークにおいて,新しい都市空間がいかなる過程で作りあげられているのかについて考察する。これらのテーマパークは,中国国内で初めて作られた同類の観光施設として,中国の文化観光開発事業をリードし,経済開発の産物と見本であると同時に政治文化の発信地でもある。テーマパークがもつこのような経済的,政治文化的特性は,シンセンの都市空間のそれを反映している。そのうえ,市場経済化とグローバル化の中で成長したシンセンは,グローバル時代における中国都市の都市空間の変容と,都市空間を生きる人々とのかかわりのダイナミックな変容実態を,他のどの都市よりも先見的に,よりよく反映している。本研究において,これらのテーマパークの建設経緯,展示内容および展示手法について検討し,「見せ物の場所」と「生きられる空間」といった二つの視座から,開発側である中国政府と華僑資本家および「ユーザー」である観光客や少数民族の若い労働者による「空間の生産」がいかなるものかを明らかにした。 まず,「見せ物の場所」としてこれらのテーマパークは,中国および世界の歴史文化といった大きなテーマの下で,「社会主義的国民国家」と「市場経済の発展ぶりおよび生活の向上」を見せ,経済発展を正当化する手段であると同時に,愛国主義教育といったような政治宣伝の場でもある。 また,アンリ・ルフェーブルの「表象の空間」とエドワード・ソジャの「第三空間」の概念を用いて,これらのテーマパークが「見せ物の場所」であると同時に「生きられる空間」でもあると確認した。具体的に三つの場面を挙げながら論じる。場面_丸1_:「錦繍中華」において,観光客であるシンセン住民がテーマパークを自らの所有物でもあるように他の町から来た観光客に紹介する時の,彼らの表情や振る舞い型や使った言葉と話す口調から,彼らがこの空間に付与された意味を自分たちの住民としてのシンセン・アイデンティティとも言うべき主体性の発揮が見られる;場面_丸2_:「中国民俗文化村」に百人以上の少数民族の若者が働いている。彼らはテーマパークのすぐ近くにある社員寮に住み,テーマパークを中心に生活している。テーマパークの中での活動と言えば,観客にパフォーマンスしたり民族文化を紹介したりするような労働だけでなく,売店やレストランで自ら消費者になって見せる身から見る身に変身するのである。こうした「生産」と「消費」の間に移行する身体は,見せ物の場所を生きられる空間へと変えている。場面_丸3_:「世界之窓」で80歳の闇ガイドに出会った。彼は「75歳以上の老人が入場無料」という規則で毎日テーマパークに来ている。目的は観光ではなく,観光客にテーマパークを案内することで案内費を稼いでいるのだ。彼のようなテーマパークに雇われていないガイドをここにおいて「闇ガイド」と名付け,彼らによって「世界之窓」という空間が一種の抵抗空間として生産されている。つまり,シンセンのテーマパークは,観光客や少数民族の若者や闇ガイドのおじいさんのような住民や「ユーザー」の空間であって,彼らの諸活動によって抵抗の空間,または「生きられる空間」に練り上げられている。 国民国家のアイデンティティと民族文化は,常に変化しており,確立される必要性に迫られている。従って,それらが空間と時間の枠組みのなかで再生産され,再確認されるプロセスは,わたしたちの周りに絶えず展開されている。万里の長城が5000年の中国歴史文化を象徴するように,シンセンは経済発展がもたらした現代性を象徴する。シンセンの都市空間は,いわばひとつのテーマパークのような存在であって,そのテーマというのが,「グローバル化」であり,中国の改革開放の成功(「社会主義体制」と「市場経済様式」との接合)である。中国が社会主義の政治体制と資本の自由化との間に,その矛盾と戦いながら自らの発展の道を探りつつあると同様に,中国の人びとは,矛盾に満ちた都市に放り出された身をもって,都市を自分たちの需要に合わせながら作り変えている。こうした表象され,実践され生きられる空間には経済発展に巻き込まれている社会的諸主体間の関係性が生き生きと作られ,また現されてもいる。わたしたちが今日及び近未来の中国の都市空間と中国社会を理解するのに,こうした関係性としての空間を第三空間的想像力で考察することはきわめて有意義であろう。
3 0 0 0 OA 移動のための地図とその利用
- 著者
- 村越 真
- 出版者
- Japan Cartographers Association
- 雑誌
- 地図 (ISSN:00094897)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.1-8, 1989-06-30 (Released:2011-07-19)
- 参考文献数
- 13
3 0 0 0 OA 漢方薬内服により発症した腸間膜静脈硬化症の臨床経過
- 著者
- 大津 健聖 松井 敏幸 西村 拓 平井 郁仁 池田 圭祐 岩下 明徳 頼岡 誠 畠山 定宗 帆足 俊男 古賀 有希 櫻井 俊弘 宮岡 正喜
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.111, no.1, pp.61-68, 2014 (Released:2014-01-05)
- 参考文献数
- 26
(背景)腸間膜静脈硬化症(以下MP)は比較的まれな大腸疾患である.その原因として,近年漢方薬との関連が注目されている.(対象と方法)本検討では,自験例と報告例を合わせた42例を対象に,MPと漢方薬の関連を検討した.(結果)自験例の約9割の症例に漢方薬内服歴を認めた.特に,加味逍遥散と黄連解毒湯が多数例で内服されていた.生薬成分では,大部分の症例が山梔子を含む漢方薬を内服していた.(考察)MP症例の多くは漢方薬の内服歴があり,MP発症後も漢方薬の継続内服により症状増悪をきたした症例が存在し,同じ漢方薬の長期内服を行った夫婦にMPを発症したことから,漢方薬成分山梔子がMP発症に強く関与すると推測した.
3 0 0 0 OA 教学IR,ラーニング・アナリティクス,教育工学
- 著者
- 松田 岳士 渡辺 雄貴
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.199-208, 2018-01-31 (Released:2018-02-05)
- 参考文献数
- 35
本稿では,教育工学を媒介として,教学IR(Institutional Research)とラーニング・アナリティクスの関係を整理すると同時に,教育工学の立場からみると教学IR とはどのような研究・実践の分野で,どのような知見をもたらしているのか検討してから,ラーニング・アナリティクスが教育工学とどのように関わっているのかについて考察した.結果的に,教育工学研究は,教育の諸課題を工学的アプローチで解決しようとするがゆえに,教学IR とラーニング・アナリティクスの両者と重複する研究対象・分析手法等を含んでおり,両者と知見を共有する意義がみとめられた.また,教育工学側も研究対象を広げ,新たな学際性の形成領域として両者との連携を積極的に図ることが期待される.
3 0 0 0 OA 酒造の理論と實際 (四)
- 著者
- 小穴 富司雄
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.11, pp.41-42, 1930-11-15 (Released:2011-11-04)
3 0 0 0 OA 基礎系教員と実務家教員の連携による実務実習事前学習の試みとその評価
- 著者
- 清水 忠 西村 奏咲 安田 恵 村上 雅裕 橋本 佳奈 大野 雅子 桂木 聡子 上田 昌宏 天野 学
- 出版者
- 日本薬学教育学会
- 雑誌
- 薬学教育 (ISSN:24324124)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.2018-014, 2018 (Released:2018-08-24)
- 参考文献数
- 7
薬学実務実習終了生を対象としたアンケート調査によれば,大半の学生は実習中に基礎薬学の知識を活用する機会は少なかったと感じていることが報告されている.その要因として,教員が基礎薬学は臨床現場でどのように役に立つかを具体的に説明できていないことが指摘されている.しかし,臨床現場での問題は基礎薬学が問題解決に有用となることもある.そのため,基礎系教員と臨床系教員が連携し基礎薬学の臨床現場での有用性を理解させ,それが可能であることを示すことが必要であると考えた.そこで,実務実習事前学習において有機化学を専門とする基礎系教員と実務家教員が連携した医薬品の配合変化に関する実習を実施し,終了後にアンケートを行った.この結果,受講生の90%以上が基礎薬学の内容が臨床の問題を解決するのに有用であることを意識できた.すなわち,基礎薬学が臨床現場でどのように役に立つかを意識させる実習を提供できたと考えられる.