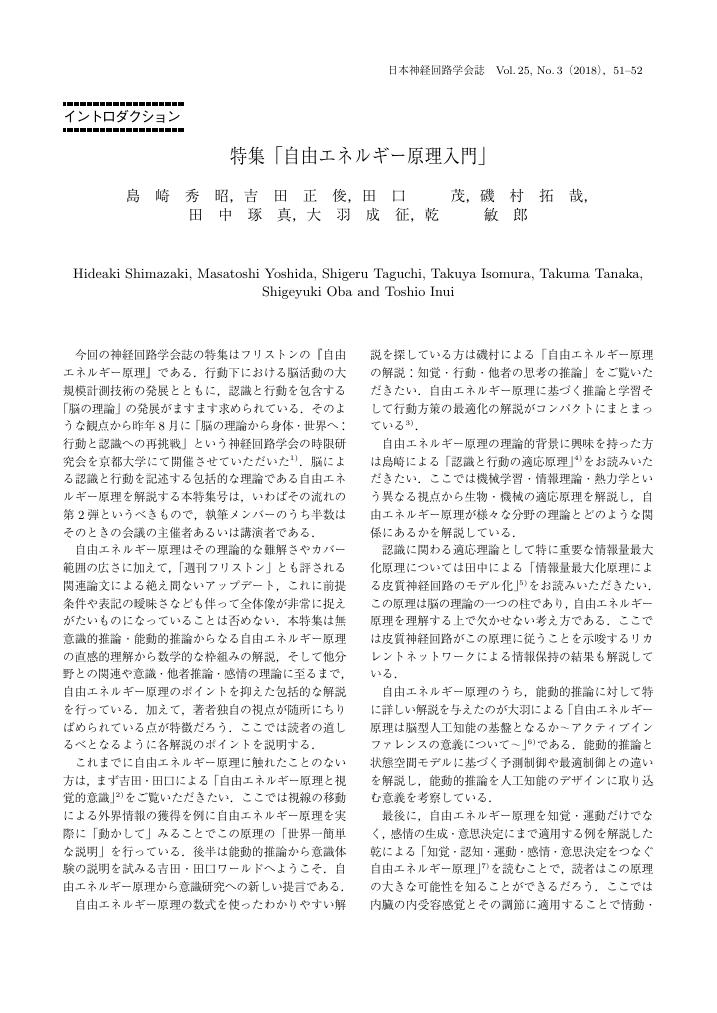2797 0 0 0 OA 政権交代の比較研究と民主政治の可能性に関する考察
- 著者
- 山口 二郎 杉田 敦 遠藤 乾 空井 護 吉田 徹 渡辺 将人 木宮 正史 川島 真 遠藤 誠治 高安 健将 村上 信一郎 宮本 太郎 小川 有美 中北 浩爾 水野 和夫
- 出版者
- 法政大学
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2012-04-01
20世紀後半に民主主義国で確立された二大政党制、二極的政党システムにおける政権交代というモデルは、1980年代の新保守主義的政治、1990年代後半の中道左派の復活までは、順調に作動し、民意の吸収と政策転換という効果をもたらした。しかし、2000年代に入って、経済のグローバル化の一層の進展と、雇用の不安定化や格差の拡大は政治的安定の基盤をなした経済的安定を侵食した。その結果、政権交代に対する国民の期待が低下し、ポピュリズムが現れた。こうした危機を打開するためには、従来の左右を超えた政党再編が必要とされている。
2788 0 0 0 OA 排便時に便器中から発見 されたミミズについて
- 著者
- 吉田 菜穂子 野村 慧 美田 敏宏 島野 智之
- 出版者
- 日本土壌動物学会
- 雑誌
- Edaphologia (ISSN:03891445)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.29, 2020 (Released:2021-12-28)
443 0 0 0 OA キノコと放射性セシウム
- 著者
- 村松 康行 吉田 聡
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.7, pp.450-463, 1997-07-15 (Released:2010-07-21)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 6 13
366 0 0 0 日本/朝鮮・中国東北からみた『満洲』の記憶と痕跡~輻輳する民族・階級・ジェンダー
まず、2年目の研究実績として、最大の成果といえるのは、初年度の成果をふまえて、2017年8月に本格的に中国東北へのフィールドワーク調査(長春、延辺、ハルピン、8泊9日)を実施したことだった。とくに延辺では、現地の研究者2名の全面的な協力によって、3日間にわたって日本人入植地と朝鮮人入植地をフィールドワーク調査することによって、両者の違いを現地で直接に経験しただけでなく、現地で当時を知る複数の経験者にインタビューすることができた。また、現地研究者との研究交流と写真論文集出版に向けた協力体制を深めることができた。なお、フィールドワーク調査の事前準備として、同年7月に中国東北への朝鮮人移民に関する専門研究者を招いて開いた公開研究会をもって認識を深め、さらに同年8月にはハルピンと万宝山事件の歴史と現在に関する研究分担者による内部研究会を開き、問題意識を共有した。また、フィールドワーク調査後の同年10月には、成果を共有するための記録集の作成と公開フォーラムを開催した。次に、2018年1月には、第3課題「『満洲』の社会と文化」を主題に関連して、中国から「満洲」文学の専門研究者を招き国際カンファレンスを開催するとともに、非公式の集まりを含めて、「満洲」に関する文学・文化の視点、現在のデジタル資料の利用方法などの研究交流を行った。さらに、この主題に関連して、同年3月に「満洲」のキリスト教史の専門研究者を招いて公開研究会を行い、「満洲」の宗教と欧米人という側面からテーマを深めた。以上のように、所定の計画通りに目標を達成することができた。
348 0 0 0 OA ヨーグルトの過剰摂取が原因と考えられた感染性心内膜炎に伴う破裂感染性脳動脈瘤の1例
- 著者
- 寺尾 和一 吉田 光宏 相見 有理 石田 衛 濱﨑 一 水谷 尚史 中西 浩隆 中林 規容
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.5, pp.426-431, 2023 (Released:2023-09-25)
- 参考文献数
- 11
生来健康な34歳男性.発熱にて精査中,頭痛を主訴に左脳出血を発症し,精査加療目的に入院した.血液培養からLactobacillus rhamnosusが同定され,心臓超音波検査にて大動脈弁に疣贅を指摘されたため,感染性心内膜炎と診断された.本患者は1日推奨量の10倍以上のヨーグルト摂取を行っており,これが侵入門戸と推定された.抗生物質による加療を開始していたにもかかわらず,右脳出血を続発した.血腫内に脳動脈瘤が認められ,保存加療中に脳動脈瘤が経時的に増大したため,感染性動脈瘤と診断し,開頭脳動脈瘤切除術を施行した.発症から33日後に大動脈弁置換術が施行され,その後リハビリテーション目的に転院した.ヨーグルト製品の過剰摂取によるLactobacillus菌血症は,少ないながらも報告があり,本症例のように感染性心内膜炎を発症し,細菌性脳動脈瘤の形成,破裂に至る可能性も考慮すべきである.
322 0 0 0 OA 日本におけるニホンウナギの保全と持続的利用に向けた取り組みの現状と今後の課題
- 著者
- 海部 健三 水産庁 環境省自然環境局野生生物課 望岡 典隆 パルシステム生活協同組合連合会 山岡 未季 黒田 啓行 吉田 丈人
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.43-57, 2018 (Released:2018-04-06)
- 参考文献数
- 47
古来より人間は、ニホンウナギから多様な生態系サービスを享受してきたが、国内漁獲量は1961年の約3,400トンをピークに、2015年の70トンまで大きく減少し、2013年には環境省が、2014年には国際自然保護連合(IUCN)が、本種を絶滅危惧IB類およびEndangeredに区分した。本稿は、今後の研究や活動の方向性を議論するための情報を提供することを目的として、現在我が国で行われているニホンウナギの保全と持続的利用に向けた取り組みと課題を整理した。水産庁は、放流と河川生息環境の改善、国内外の資源管理、生態・資源に関する調査の強化等を進めている。環境省は、2ヵ年に渡る現地調査を行なったうえで、2017年3月に「ニホンウナギの生息地保全の考え方」を公表した。民間企業でも、一個体をより大きく育てることで消費される個体数を減少させるとともに、持続的利用を目指す調査研究や取り組みに対して寄付を行う活動が始まっている。しかし、web検索を利用して国内の保全と持続的利用を目指す取り組みを整理すると、その多くは漁業法に基づく放流や漁業調整規則、シンポジウムなどを通じた情報共有であり、生息環境の保全や回復を目的とした実質的な取り組み件数は限られていた。漁業管理を通じた資源管理を考えた場合、本種の資源評価に利用可能なデータは限られており、現時点ではMSY(最大持続生産量)の推定は難しい。満足な資源評価が得られるまでは、現状に合わせて、限られた情報に基づいた漁獲制御ルールを用いるなど、適切な評価や管理の手法を選択することが重要である。本種の生息場所として重要な淡水生態系は劣化が著しく、その保全と回復はニホンウナギに限らず他の生物にとっても重要である。ニホンウナギは水域生態系のアンブレラ種など指標種としての特徴を備えている可能性があり、生態系を活用した防災減災(Eco-DRR)の促進など、水辺の生物多様性の保全と回復を推進する役割が期待される。
307 0 0 0 OA 心理学的研究における重回帰分析の適用に関わる諸問題
- 著者
- 吉田 寿夫 村井 潤一郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.92.19226, (Released:2021-05-31)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 5
Although multiple regression analysis is a frequently used method for multivariate analysis in psychological research, it has been used inappropriately or incorrectly in most studies. To resolve these problems effectively, we investigated and summarized the issues related to the use of multiple regression analysis found in papers published in The Japanese Journal of Psychology and discussed the issues in detail. We argue that researchers should not use multiple regression analysis for simplistic reasons, such as “because there are several independent variables” or “because some relationships between independent variables or between independent and control variables are supposed.” We further argue the importance of carefully considering whether the purpose of the study is to explain or to predict and what kind of causal relationships exist between variables.
275 0 0 0 OA 導尿目的で利用したネギによる膀胱尿道異物の1例 尿道カテーテルの歴史的考察
- 著者
- 吉永 敦史 吉田 宗一郎 中込 一彰 後藤 修一
- 出版者
- 一般社団法人 日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科学会雑誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.5, pp.710-712, 2007-07-20 (Released:2010-07-23)
- 参考文献数
- 15
症例は62歳, 男性. 1998年交通事故によりC3-4レベルの頚髄損傷となり両上下肢麻痺, 膀胱直腸障害が出現したが, 手術とリハビリテーションによって現在では歩行可能となっている. また排尿状態については術後尿閉がみられたが, 次第に改善し自排尿可能となっていたとのことであった. 2001年排尿障害を自覚し, 尿の排出ができなくなったため自己導尿目的にネギを尿道に挿入したが抜去できなくなったため当科受診となった. 鉗子による異物の除去はできず, 経尿道的に異物の除去を行った. 尿道カテーテルの歴史について調べてみると, 金属製のものや自験例のようなねぎなどが用いられていた時代もあった.
181 0 0 0 OA <特集論文>最大・最悪の公害としての原発災害
- 著者
- 吉田 文和
- 出版者
- 北海道大学大学院経済学研究科地域経済経営ネットワーク研究センター
- 雑誌
- 地域経済経営ネットワーク研究センター年報 (ISSN:21869359)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.51-74, 2012-03-30
2011 年3 月11 日に発生した福島第1原子力発電所が引き起こした原発災害を,公害論からみることによって,この問題を原因論と被害論を基礎として責任論,対策論,費用論,救済論,代替政策論から分析し,問題の広がりと解決の方向性と時間軸,課題を整理し,展望を見出すことができることを具体的に示した。
174 0 0 0 OA 中高年女性における河内音頭が身体へ及ぼす影響
- 著者
- 三村 寛一 清水 一二三 吉田 智美 塩野 祐也 檀上 弘晃 上田 真也
- 出版者
- 大阪教育大学
- 雑誌
- 大阪教育大学紀要. IV, 教育科学 (ISSN:03893472)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.45-52, 2006-02-28
本研究は,K市在住の河内音頭愛好家である女性51名を対象に,河内音頭が中高年女性の身体にどのような影響を及ぼすかについて検討することを目的とした。その結果,河内音頭中の心拍数および運動強度は,中程度のレベルでほぼ一定であった。また,年齢と体脂肪率が上がるに伴い心拍数および運動強度は低い値を示した。以上の結果より,河内音頭は運動者の特性に応じた運動強度で運動ができ,その運動強度から中高齢者にとって安全な運動であり,健康づくりの運動プログラムとして効果的な運動であることが示唆された。
138 0 0 0 OA 陰茎絞扼症の1例
120 0 0 0 OA 特集「自由エネルギー原理入門」
105 0 0 0 OA モンゴル人の農耕
- 著者
- 吉田 順一
- 出版者
- Society of Inner Asian Studies
- 雑誌
- 内陸アジア史研究 (ISSN:09118993)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.1-26, 2016-03-31 (Released:2017-05-26)
This paper presents a study on crop farming agriculture of the Mongol nomads in the Mongolian highlands. The paper essentially concludes that both the nomadic Mongols of Eastern Inner Mongolia and the Khalkha Mongol nomads, who widely inhabit the central and northern parts of the Mongolian highlands, have been sharing a number of common features since the Mongol Empire, demonstrating particularly strong connection to millet – such as prefixing the Mongolian word for "millet" with the predicate "Mongol", referring to "millet" with the single word "Mongol", and predominantly cultivating millet. They also use the same cultivation method that does not interfere with their nomadic lifestyle and consists in sowing seeds after the rainy season in early summer just before leaving for summer pastures (with no irrigation or random irrigation) and harvesting on their return from the pastures before autumn frosts set in (in Eastern Inner Mongolia this traditional type of farming is called "namuγ tariy-a"). This method differs from the one adopted in the Western Mongolian highlands inhabited mostly by Oirat nomads who learned crop farming from the Bukharans and mainly cultivate cereals with substantial irrigation.
102 0 0 0 OA 高等学校理科「地学基礎」「地学」開設率の都道府県ごとの違いとその要因
- 著者
- 吉田 幸平 高木 秀雄
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.3, pp.337-354, 2020-06-25 (Released:2020-07-11)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1
Science subjects at Japanese high schools are divided into physics, chemistry, biology, and Earth science. The numbers of credits set are two for basic subjects and four for advanced subjects. With a change of courses based on new guidelines enforced by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan (MEXT) in 2012, the Earth science field has classes in Basic Earth Science and Advanced Earth Science. The percentage of high school students who take Earth science classes is estimated from the number of textbooks adopted by MEXT (26% for Basic Earth Science and 1.2-0.9% for Advanced Earth Science), but the percentages of high schools that offer Earth science classes in each prefecture have not been reported. Therefore, the proportion of high schools that offer Basic Earth Science and Advanced Earth Science classes are estimated based on a survey of more than 5,000 high schools in Japan. Data for the survey were collected from the curriculum listed on each high-school homepage and from a questionnaire distributed using the Google mail system. Survey results indicate that 43.7% of high schools nationwide offer Basic Earth Science, and only 8.8% of high schools offer Advanced Earth Science. In addition, the proportion of high schools offering Earth science classes varies depending on the prefecture. The highest proportion of high schools offering Basic Earth Science is 71% (Okinawa) and the lowest is only 4% (Miyazaki). The top prefectural percentage for Advanced Earth Science is 48%, but nine prefectures have no high schools offering Advanced Earth Science. The proportion of high schools offering Earth science correlates with the number of Earth science teachers employed over the past 40 years in each prefecture. However, some prefectures have records only for the total number of science teachers; therefore, the numbers of teachers hired specifically to teach Earth science are not known in these cases. The percentages of high schools offering Earth science classes are higher in prefectures for which only the total number of science teachers is known. A draft is provided on promoting Earth science education at high schools comparing differences among prefectures in the percentages of high schools offering Earth science classes. Based on our results, to promote high school geoscience education, support should be provided through workshops on Earth science education, so that science teachers other than full-time Earth science teachers can recognize the importance of Earth science and teach Basic Earth Science.
97 0 0 0 OA 児童・生徒の教師認知がいじめの加害傾向に及ぼす影響
- 著者
- 大西 彩子 黒川 雅幸 吉田 俊和
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.324-335, 2009 (Released:2012-02-29)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 11 12
本研究の目的は, 児童・生徒が教師の日常的な指導態度をどのように捉えているのかということ(教師認知)が, 学級のいじめに否定的な集団規範と, いじめに対する罪悪感の予期を媒介して, 児童・生徒のいじめ加害傾向に与える影響を明らかにすることである。547名(小学生240名, 中学生307名)の児童・生徒を対象に, 教師認知, 学級のいじめに否定的な集団規範, いじめに対する罪悪感予期, いじめ加害傾向を質問紙調査で測定し, 共分散構造分析による仮説モデルの検討を行った。主な結果は以下の通りであった。(1) 学級のいじめに否定的な集団規範といじめに対する罪悪感の予期は, 制裁的いじめ加害傾向と異質性排除・享楽的いじめ加害傾向に負の影響を与えていた。(2) 受容・親近・自信・客観の教師認知は, 学級のいじめに否定的な集団規範といじめに対する罪悪感の予期に正の影響を与えていた。(3) 怖さの教師認知と学級のいじめに否定的な集団規範は, いじめに対する罪悪感に正の影響を与えていた。(4)罰の教師認知は, 制裁的いじめ加害傾向と異質性排除・享楽的いじめ加害傾向に正の影響を与えていた。本研究によって, 教師の受容・親近・自信・客観といった態度が, 学級のいじめに否定的な集団規範といじめに対する罪悪感の予期を媒介して, 児童・生徒の加害傾向を抑制する効果があることが示唆され, いじめを防止する上で教師の果たす役割の重要性が明らかになった。
91 0 0 0 OA 千葉県柏市の東京大学柏キャンパスにおける放射能汚染の実態と芝生の除染試験
- 著者
- 福田 健二 朽名 夏麿 鬼頭 秀一 山路 永司 斎藤 馨 小貫 元治 鯉渕 幸生 三谷 啓志 吉田 善章 神保 克明 松尾 泰範 末吉 和人
- 出版者
- 日本芝草学会
- 雑誌
- 芝草研究 (ISSN:02858800)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.20-30, 2013-10-31 (Released:2021-04-22)
- 参考文献数
- 9
福島第一原発事故による放射能汚染のホットスポットとなっている千葉県柏市に位置する東京大学柏キャンパス内の緑地において, 汚染実態調査を行うとともに芝生の除染試験を行った。2011年8〜10月に測定したキャンパス内の地上1mの空間線量率はほぼ0.3〜0.6μSv/hの範囲にあり, 芝生や森林の面積当たりの放射性セシウム汚染量は39〜137kBq/m2であった。芝生地の放射性セシウムは表層0〜1cmの土壌粒子に最も多く含まれ (35〜107kBq/m2), 芝の植物体およびサッチに含まれる量に比べてはるかに多かった。除染方法として, リールモアとロータリーモアを用いた芝刈りとサッチの吸引 (A方式) と, ソッドカッターによる芝生の剥ぎ取り (B方式) とを行い比較した結果, A方式による空間線量率の低下はわずかであったのに対し, B方式では約0.4〜0.6μSv/hだった地上5cmの空間線量率が0.11〜0.21μSv/hまで低下した。このことから, 千葉県東葛地域の芝生地の除染には, ソッドカッターを用いた芝の剥ぎ取りが最も簡単かつ有効な手段であると考えられた。一方, 雨どいからの飛沫が降り注ぐ約5m2の範囲において, 表層2cmで100kBq/kg, 深さ4〜6cmで10kBq/kg以上の土壌汚染がみられ, 深さ6cmまでの表土の入れ替えを行っても地上5cmで0.5μSv/h前後までしか低下しなかった。
87 0 0 0 OA 内生的貨幣供給論と信用創造(<特集>現代の貨幣・信用論争)
- 著者
- 吉田 暁
- 出版者
- 経済理論学会
- 雑誌
- 季刊経済理論 (ISSN:18825184)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.15-25, 2008-07-20 (Released:2017-04-25)
I have advocated the endogeneity of money supply following the views of M. Nishikawa and J. Itakura as well as those of N. Kalldor and B. J. Moor. As Moor appropriately wrote, "Currently the standard paradigm, especially in the United States, treats the central bank as determining the money base and thence the money stock. / Modern monetary theory has inherited an approach to money that was more appropriate in a world where money was a commodity, usually gold or silver, without fully recognizing the fundamental differences between commodity and credit money." These views, however, have not been widely accepted, especially among Japanese Marxian economists. Some of them have criticized the endogenous money supply theory. This article is a counter-criticism of some most criticizing arguments, mainly those of professor H. Noda and professor T. Itoh Marxian economists quite often express their views based on what Marx said, especially in "The Capital". Marx introduced capitalistic money through the logical developments of the value form, and said that gold would become the main material of money due to its physical characteristics. Then, it is not strange that their views on credit money are based on gold. They have regarded that the gold convertibility is the essence of credit money. They do not attach greater importance to the causes of issuance or withdrawal of credit money, that is, the connection between the supply of credit and the supply of money. In the modern world gold as money does not exist. But they tacitly regard fiat money as a replacement of gold, in other word, exogenous money. Another point I stressed in this article is that those who are severely critical to the endogenous money supply theory misunderstand Marx's logical way of writing. In "The Capital" vol. 1 and 2, there are no credit systems, no credit money. There is only commodity money (gold) introduced at the money theory (vol. 1). At the reproduction charts (vol. 2), his premise is each capitalist has a certain amount of money which is needed for the purchase of materials and the payment of wages etc. Credit system and credit money are the problems of vol. 3, and unfortunately Marx could not complete the credit theory. But some of those who criticize the endogenous money supply theory quote from vol. 1 or 2 where, actually, only commodity money (gold) exists. I also stressed that Phillips-type credit creation theory (multiplier theory)is not valid, especially in the world of credit money. Revival of Macleod or Hahn=Schumpeter type theory is very important. Today's monetary policies of major central banks are not money supply control, but money market interest rates control that affects the public demand of funds. The starting points of the credit creation are loans of banks to firms and household by crediting to their deposit accounts. At this point banks do not need surplus money. Monies are created by the action of banks, that is Macleod-type credit creation. When the cash demand increases, central banks should accommodate. If a central bank worries about the level of the economic expansion and the increase of prices, it can affect demand of funds and then affect prices by interest rates control policy. Today's monetary policies of major central banks are money market interest rates control. Lastly, I stressed the importance of the independence of central banks. Some people might question that the central bank independence is against the democratic procedures of policy determination. But, in my opinion, there is a big difference between the monetary policy and other policies of the governments. While monetary policies are executed through financial transactions in the market, other governmental policies are executed as an exercise of administrative powers.
86 0 0 0 OA 尺度の作成・使用と妥当性の検討
- 著者
- 吉田 寿夫 石井 秀宗 南風原 朝和
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.213-217, 2012 (Released:2013-01-16)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 12 11