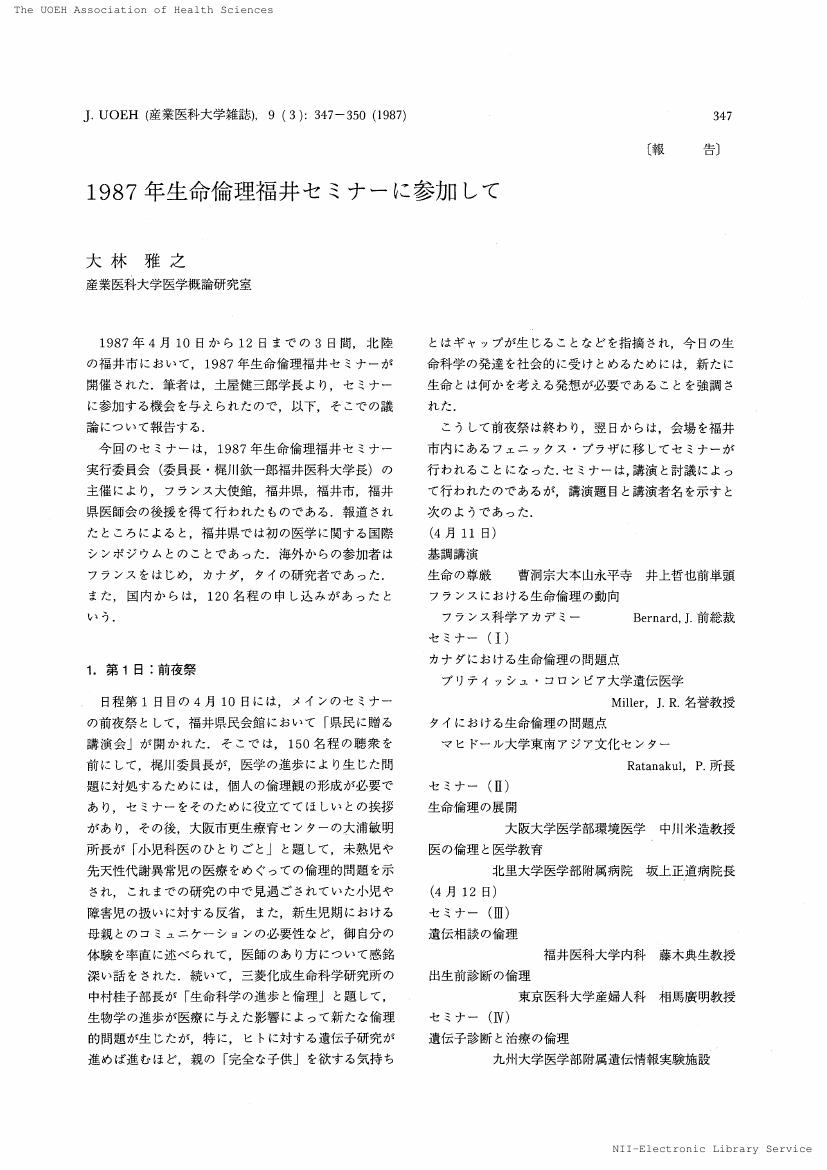3 0 0 0 IR 古典古代の奴隷医師 (シンポジウム 古代地中海世界における病・癒し・祈り)
- 著者
- 小林 雅夫
- 出版者
- 早稲田大学地中海研究所
- 雑誌
- 地中海研究所紀要 (ISSN:13482076)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.45-54, 2008-03
3 0 0 0 OA 親の養育態度が大学生の過剰適応に及ぼす影響――性差の視点から
- 著者
- 任 玉洁 林 雅子
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.23-26, 2020-05-07 (Released:2020-05-07)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2
The purpose of this study was to examine the effect of parental bonding instrument (PBI) on over-adaptation in adolescence from the viewpoint of gender difference. The participants were 299 university students (male=125; female=174). The results showed that the level of mother’s loving on the PBI positively predicted boys’ and girls’ external aspect (EA) of over-adaptation, but negatively predicted girls’ internal aspect (IA) of over-adaptation. The level of mother’s overprotectiveness on the PBI was found to positively predict both EA and IA in adolescence. The level of father’s overprotectiveness on the PBI was positively associated with IA in boys; however, it was not significantly correlated with IA in girls.
- 著者
- 林 雅清
- 出版者
- 白帝社
- 雑誌
- 中国語研究 (ISSN:03886956)
- 巻号頁・発行日
- no.46, pp.39-58, 2004-10
3 0 0 0 OA キーボードのキーピッチが操作性に及ぼす影響
- 著者
- 小林 雅幸
- 出版者
- Japan Ergonomics Society
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.Supplement, pp.448-449, 1992-05-31 (Released:2010-03-11)
3 0 0 0 OA 鼻前庭扁平上皮癌に対する小線源治療主体の放射線治療
- 著者
- 小林 雅夫 兼平 千裕 加藤 孝邦 青柳 裕
- 出版者
- Japan Society for Head and Neck Cancer
- 雑誌
- 頭頸部腫瘍 (ISSN:09114335)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.159-165, 2003-03-25 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
鼻前庭扁平上皮癌5例に小線源治療主体の放射線治療を施行した。鼻前庭に限局した3例には外部照射40Gy後に鼻腔内へ1cm径, 2cm長のアプリケータを挿入し, 18-20Gy/4frの高線量率腔内照射 (1例ではさらにAuグレインによる組織内照射を追加) を行った。鼻唇溝皮膚に浸潤した2例には外部照射50-60Gy後に30-40Gy/3-4日の低線量率組織内照射を施行した。1年2ケ月で他癌死 (肺癌) した1例を除くと全例 (7年8ケ月, 7年2ケ月, 2年6ケ月, 4ケ月) とも無病生存であった。重篤な晩期有害事象は認めなかった。T1-2N0鼻前庭扁平上皮癌に対しては, 小線源治療を主体とした放射線治療で高い局所制御率が得られ, 美容の面でも優れていた。鼻前庭に限局した病変には組織内照射と比べてより侵襲が少なく, 外来で治療可能な高線量率腔内照射が適していると思われた。
3 0 0 0 OA 高等教育グランドデザイン策定のための基礎的調査分析
- 著者
- 金子 元久 矢野 眞和 小林 雅之 藤村 正司 小方 直幸 山本 清 濱中 淳子 阿曽沼 明裕 矢野 眞和 小林 雅之 濱中 淳子 小方 直幸 濱中 義隆 大多和 直樹 阿曽沼 明裕 両角 亜希子 佐藤 香 島 一則 橋本 鉱市 苑 復傑 藤墳 智一 藤原 正司 伊藤 彰浩 米澤 彰純 浦田 広朗 加藤 毅 吉川 裕美子 中村 高康 山本 清
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 学術創成研究費
- 巻号頁・発行日
- 2005
本研究は、1)日本の高等教育についての基礎的なデータを大規模調査によって蓄積し、その分析をおこない、2)それをもとに各国の高等教育との比較分析を行うとともに、3)その基礎にたって、日本の高等教育の課題を明らかにすること、を目的とした。とくに大規模調査については、(1)高校生調査(高校3年生4000人を、その後5年間にわたり追跡)、(2)大学生調査(127大学、約4万8千人の大学生について学習行動を調査)、(3)社会人調査(9千事業所、2万5千人に大学教育の経験、評価を調査)、(4)大学教員調査(回答者数約5千人)、(5)大学職員調査(回答者数、約6千人)、を行い、それをデータベース化した。
2 0 0 0 OA 環境化学物質の脳発達への影響:培養シナプス形成系と遺伝子発現解析による評価
子どもの脳の発達障害の一因として、環境化学物質の影響が懸念されている。本研究では、リスク評価が不十分な農薬ネオニコチノイドの低用量長期曝露の影響を、発達期のラット小脳神経細胞培養を用い、遺伝子発現の変化から発達神経毒性を調べた。ニコチン、ネオニコチノイド2種を低濃度で2週間曝露した小脳培養のmRNAをDNAマイクロアレイで解析し統計処理した結果、複数の遺伝子で1.5倍以上の有意な発現変動を確認した。3種の処理で共通に変動した遺伝子には、シナプス形成に重要なカルシウムチャネルやG蛋白質共役受容体などが含まれており、ネオニコチノイドはニコチン同様に子どもの脳発達に悪影響を及ぼす可能性が確認された。
2 0 0 0 OA 火星衛星探査計画MMXにおける観測性とΔVコストを考慮したDeimosフライバイ軌道計画
2 0 0 0 OA 経済格差と教育格差の長期的因果関係の解明:親子の追跡データによる分析と国際比較
- 著者
- 赤林 英夫 妹尾 渉 敷島 千鶴 星野 崇宏 野崎 華世 湯川 志保 中村 亮介 直井 道生 佐野 晋平 山下 絢 田村 輝之 繁桝 算男 小林 雅之 大垣 昌夫 稲葉 昭英 竹ノ下 弘久 藤澤 啓子
- 出版者
- 慶應義塾大学
- 雑誌
- 基盤研究(S)
- 巻号頁・発行日
- 2016-05-31
本研究では、経済格差と教育格差の因果関係に関するエビデンスを発見するために、親子を対象とした質の高い長期データ基盤を構築し、実証研究と実験研究を実施した。さらに、経済格差と教育格差に関する国際比較研究を実施した。具体的には、テスト理論により等化された学力データを活用し、学力格差と経済格差の相関の国際比較、親の価値観が子どもの非認知能力に与える影響の日米比較の実験研究、子ども手当が親の教育支出や子どもの学力に与える影響に関する因果分析等を実施した。
2 0 0 0 OA 選抜・配分装置としての学校 労働市場の内部化との関連で
- 著者
- 小林 雅之
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.51-62,en214, 1981-09-12 (Released:2011-03-18)
In 1970s a lot of critical works on the Human rCapital Theory which has been a theoretical framework of the economics of education have been raised in the U.S.A. Among them, the Segmented Labor Market Theory, especially the Internal Labor Market Theory and the Screening Device Hypothesis seem to be very suggestive from a view point of the sociology of education. This paper aims at reviewing these new views and acquiring implications about school education systems.The Internal Labor Market Theory insists as follows: There are barriers to entry in the internal labor markets. Employment of workers is restricted to entry jobs and they are promoted internally. They acquire their vocational skills not by school education but by On the Job Training (OJT). By acquiring these skills they are promoted to the higher rank jobs. If these skills are enterprise-specific, employers must bear the training costs. To minimize the hiring and training costs, employers prefer to promote workers internally rather than hire them from outside the enterprises. The more skills are enterprise-specific, the more the labor markets are internalized.The Screening Device Hypothesis insists as follows: Education does not contribute to raising productivity, but serves as a means to sorting people for jobs. Employers do not have enough information about work performances of workers. So they use education as an indirect proxy measure of workers' abilities.In the internal markets, the more skills are enterprise-specific and training needs long time, the more employers use education as a Screening Device and become indifferent to vocational skills acquired by school education and skills are acquired by OJT. Thus in the internal labor market school education is used as a Screening Device and the transmission function of vocational skills by school systems is weakened. Moreover, some economists declare that school education develops personalities which are correspondent to hierarchical work relations in enterprises.Japanese labor markets characterized by a life-time employment system seems to be well explained by the Internal Labor Market Theory. In the internal labor markets the utilities of vocational knowledge and skills acquired by school education are denied. Some empirical research evidences support this conclusion.
- 著者
- 五十嵐 里菜 馬場 悠太 平林 雅和 伊從 慶太 大隅 尊史
- 出版者
- 日本獣医皮膚科学会
- 雑誌
- 獣医臨床皮膚科 (ISSN:13476416)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.153-156, 2019 (Released:2019-09-20)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
ブリティッシュ・ショートヘアー,4歳4ヶ月齢,未去勢雄が両外耳道および耳介周囲に多発性の黒〜灰色,ドーム状の隆起性病変を呈した。病理組織学的検査によって,Feline ceruminous cystomatosisと診断された。自宅での点耳治療が困難であったため,病院での耳洗浄および1%フロルフェニコール,1%テルビナフィン,0.1%ベタメタゾン酢酸エステル配合の点耳ゲル剤による治療を計3回実施したところ,約3ヶ月以内に病変の著しい退縮を認め,最終投与の約6ヶ月後に至るまで再発を認めなかった。
2 0 0 0 OA 「小さな死」と「孤独」
In this paper I will clarify the relationship between the meaning of “Solitude” as a way of life, and the meaning of “Little Deaths” which were discussed by Kazuko Watanabe, a Catholic sister. Watanabe defined “Solitude” as the original way of human existence, and as a positive concept. She showed that “Little Deaths” were experienced when living with a consciousness of death, and when living honestly. Furthermore, living honestly means facing oneself and living honestly in “Solitude,” which is seen as the original way of life for human beings. In other words, she seemed to say that the original way of human existence is to accumulate experiences of “Little Deaths” through “Solitude” and honesty.
2 0 0 0 OA 超好熱菌由来の新規DNAポリメラーゼの発見とその産業利用
- 著者
- 北林 雅夫 小松原 秀介 今中 忠行
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.12, pp.866-871, 2015-11-20 (Released:2016-11-20)
- 参考文献数
- 8
2 0 0 0 OA マムシ咬傷67例の検討
- 著者
- 吉峯 宗大 瀬山 厚司 菅 淳 村上 雅憲 林 雅規 井上 隆 松並 展輝 守田 知明
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.4, pp.468-474, 2019 (Released:2019-12-28)
- 参考文献数
- 13
マムシ咬傷の治療に関するガイドラインは存在せず,臨床現場においては治療方針に迷うことが少なくないと推測される。そこで,当院で2007年から2016年までの10年間に経験した67例を用いて治療内容や予後について検討した。男女比は35:32,年齢は16歳から86歳(平均68歳)で,60歳以上が79%を占めていた。受傷時期は7月から9月に56例(84%)が集中し,受傷場所は田畑が28例,自宅が26例と多く,受傷部位は全て四肢であった。49例にマムシの目撃があり,目撃のない症例では臨床症状から診断した。受傷直後から著明な血小板減少を呈し重症化した「血小板減少型」の1例を除いた66例について検討した。全例に入院加療が行なわれ,平均入院日数は6.8日であった。腫脹範囲が大きい症例ほど入院日数が有意に長かった。3例が腎機能障害を合併し,そのうち1例が死亡した。腫脹がピ―クに達するのは平均21.8時間後,CPK値が最大となるのは平均2.6日目であり,初診時に軽症であっても数日間の経過観察は必要であると考えられた。マムシ抗毒素は28例に投与されたが,投与の有無では入院日数に差を認めなかった。しかし,より重症の症例にマムシ抗毒素が投与されていること,腎機能障害を合併した3例の中,死亡した1例を含む2例にはマムシ抗毒素が投与されていなかったことから,重症例にはマムシ抗毒素の投与が必要であると考えている。また当院で経験した非常に稀な「血小板減少型」の1例についても報告する。
2 0 0 0 OA 大学生の無気力に対する縦断研究――スチューデント・アパシー的な無気力の特徴に着目して
- 著者
- 林 雅子
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.39-51, 2022-07-06 (Released:2022-07-06)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
本研究は,無気力への感情に着目し,縦断調査から一般学生におけるスチューデント・アパシー的な無気力の実態を検討した。3回の調査に参加した大学生121名が,意欲低下領域尺度,無気力感尺度,心のゆとり感尺度を含めた質問紙に回答した。条件付き潜在曲線モデルに基づく解析を行い,初回測定時の学業意欲低下から切片と傾きへの影響を検討した。切片では,心の充足・開放性と対他的ゆとりに負の影響があり,切迫・疲労感には影響がなかった。傾きでは,心の充足・開放性と切迫・疲労感どちらも学業意欲低下からの影響がなかった。つまり,学業への意欲低下は心のゆとりを減少させるが,ネガティブな感情は伴わないことが示された。ただし,意欲の低下はその後の心のゆとりの増減に影響しないことも明らかになり,スチューデント・アパシー的な無気力の特徴が見出された。今後,大学生の無気力に対して上記の特徴を踏まえた支援を検討すべきであろう。
2 0 0 0 OA 最近の原子力動向:第3世代炉が本格化 露中台頭の中,SMR開発に注目
- 著者
- 小林 雅治
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.9, pp.650-655, 2019 (Released:2020-04-02)
昨年,中国で三門原子力発電所1,2号機と海陽1,2号機,さらに台山1号機が相次いで発電開始し,中国は原子力発電規模で日本を抜き,世界3位に躍り出た。これらの原子炉は米国ウエスチングハウス(WH)製AP1000と仏フラマトム製EPRで,他国に先駆けての発電開始となった。いずれも所謂「第3世代炉」と呼ばれるもので,同炉の本格化時代に入ったとも言える。近年の原子力発電所の建設・輸出では,ロシアと中国の台頭が著しい。一昔前に原子力開発を先導してきた米英加は最近,2020年代半ば以降の商用展開を目指して,小型モジュール炉(SMR)の開発を熱心に進めている。本稿では,これらの動きを概括的に紹介する。
2 0 0 0 OA 病院薬剤師と保険薬局薬剤師を対象とした臨床試験に関する意識および知識調査
- 著者
- 岡澤 香津子 若林 雅人 松岡 慶樹 佐々木 伸一 水越 裕樹 竹原 恵美子
- 出版者
- 一般社団法人日本医薬品情報学会
- 雑誌
- 医薬品情報学 (ISSN:13451464)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.83-89, 2013 (Released:2013-09-05)
- 参考文献数
- 15
Objective: The present study investigated awareness and knowledge about clinical trials among pharmacists working in the Nagano Hokushin area as well as their contribution to the enlightenment of clinical trial.Methods: A questionnaire survey of clinical trials was conducted to evaluate levels of interest, impressions, sources of information, and knowledge among hospital and community pharmacists.Results: We received responses from 77 hospital and 67 community pharmacists. The levels of interest in clinical trials were not significantly different between hospital and community pharmacists. About impressions, hospital pharmacists thought that clinical trials were “a new development.” Contrarily, community pharmacists thought that clinical trials were “a field that they were seldom concerned with.” About sources of information, hospital pharmacists found that “study meetings” were the most informative. More community pharmacists than hospital pharmacists chose “general reports, for example, newspapers and televisions” as a source of information, and similarly more community pharmacists indicated that they had “few opportunities for obtaining information about clinical trials.” About knowledge, the percentage of correct answers about clinical trials between hospital and community pharmacists was not significantly different. A higher percentage of community pharmacists than hospital pharmacists answered unknown.Conclusion: Hospital and community pharmacists had different impressions and knowledge about clinical trials probably because of differences in sources of information and its access. Henceforth, study meetings involving educational material about clinical trials should be held for discussing fundamental knowledge about the methods and structure of clinical trials and for discussing case studies wherein patients consult pharmacists about clinical trials.
2 0 0 0 OA 1987年生命倫理福井セミナーに参加して
- 著者
- 大林 雅之
- 出版者
- 学校法人 産業医科大学
- 雑誌
- Journal of UOEH (ISSN:0387821X)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.347-350, 1987-09-01 (Released:2017-04-11)
2 0 0 0 高等教育機関の新設・統廃合に関する比較社会学的研究
本年度は、4年制大学と短期大学の入学定員割れおよび統廃合の要因を分析するための理論作りおよび実証データの作成・分析を行った。さらに、大学・短大の設置者である学校法人の新設統廃合の分析も行った。そのために以下の3種類のデータ・ベースを作成した。第1に、各大学に関して昭和61年度の定員充足率、社会的評価(偏差値等)、構成員の特性(研究状況、年齢分布、学歴等)、就職状況などの属性的情報を収集した。第2に、昭和24年度以降新設統廃合された大学および短大の学部別の入学定員数と在籍者数を調べた。第3に、昭和25年以降の学校法人の許可と廃止の状況について調べた。さらに、以上の数量的情報を補うため、各大学の学校案内の収集や関係者へのインタビュー調査を行なった。その結果、以下の新たな知見が得られた。1.定員割れしている大学は27校ある。2.定員割れの要因を、経営戦略、内部組織特性、外部環境特性の3つの観点から検討した結果、地方所在で小規模で偏差値ランクが低いという傾向がみられた。3.さらに、伝統的な女子教育を支えた学部で定員割れが目立っている。4.廃止となった45校の短大の平均存続年数は、14.2年であった。国立私立別では、それぞれ26.7年、17.4年、12.7年で私立の短大が設置されてから最も早く廃止される比率が高い。5.昭和50年当時の学校数で廃校数を割った廃校率をみると、短大のそれは2.9%で、幼稚園の4.2%、小学校の4.9%、中学校の4.5%、高等学校の5.9%についで高い値となっている。しかし、大学の廃校率は0.2%で、相対的にみてかなりひくい。6.高等教育への参入以前、それらの学校法人の約8割は各種学校や高等学校などなんらかの学校経営していた。これは特に短期大学に参入した学校法人に著しい。
2 0 0 0 OA 果実食性になった食肉目パームシベットの採食生態
- 著者
- 中林 雅 ハミッド・アブドゥル アハマッド 幸島 司郎
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 Supplement 第29回日本霊長類学会・日本哺乳類学会2013年度合同大会
- 巻号頁・発行日
- pp.116, 2013 (Released:2014-02-14)
本大会では,マレーシア・ボルネオ島に生息する食肉目ジャコウネコ科パームシベットの採食生態について発表を行う.【背景と目的】パームシベットは,発達した犬歯,裂肉歯,短い消化器官等,食肉目に共通する形質を有しながら,果実が食物の 70%以上を占める果実食傾向が強い食肉目である.パームシベットは,消化を阻害する大きな種子を飲み込み,果実を十分に消化しないまま排泄する等,食肉目特有の形態が果実の利用を不利にしているように見え,長い進化史において果実食に適応してきた果実食者とは異なる採食戦略を採ることが考えられる.そこで,パームシベットの採食戦略を明らかにするために,以下の観察を行った.さらに,パームシベットが選択する果実の特徴を明らかにするために,果実中の化学物質の分析を行った.【方法】2012年 12月から 2013年にかけて,結実木で,パームシベットを含む果実食者の採食行動を観察した.観察項目は,結実木を訪れた種,結実木での滞在時間(分),採食時間(秒),果実選択時間(秒)である.また,同一結実木内において,パームシベットが選択した果実と,標準果実の化学物質の組成を,高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を用いて分析し,比較した.【結果と考察】結実木での観察の結果,パームシベット 2種(Paradoxurus hermaphroditus, Arctogalidia trivirgata)の他にサイチョウ(Anthracoceros albirostris)とカニクイザル(Macaca fascicularis)が観察された.パームシベットは,結実木での滞在時間,採食時間,果実選択時間すべてにおいて他の 2種よりも長かった.このことは,パームシベットが利用可能な果実は限定されていることを示唆している.また,パームシベットによって選択された果実は,標準果実よりもグルコース量が有意に多かった.その他の化学物質についても分析を進め,得られた結果を基に考察を行う.