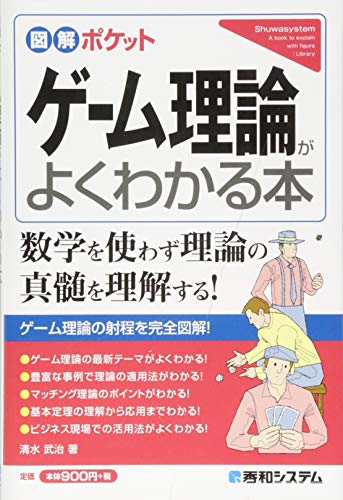1 0 0 0 ゲーム理論がよくわかる本
1 0 0 0 OA 幼少年期の一輪車乗りの活動とその環境の実態
- 著者
- 古賀 範雄 清水 聖子 吉田 梢 Koga Norio Shimizu Satoko yoshida Kozue
- 出版者
- 中村学園大学発達支援センター
- 雑誌
- 中村学園大学発達支援センター研究紀要 = Bulletin of Nakamura Gakuen developmental support center (ISSN:18849857)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.85-87, 2017-03
- 著者
- 渡辺 祥子 清水 幹博 山田 寿郎
- 出版者
- 北海道大学水産学部
- 雑誌
- 北海道大學水産學部研究彙報 (ISSN:00183458)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.7-18, 1978-03
1 0 0 0 OA 勾配ブースティング回帰木を用いた製造業流体シミュレーションの高速化手法
- 著者
- 小川 雄太郎 清水 琢也 横井 俊昭
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第33回全国大会(2019)
- 巻号頁・発行日
- pp.3Q3J1304, 2019 (Released:2019-06-01)
流体シミュレーションは製造業などの製品設計フェイズで重要となるCAE (Computer Aided Engineering) のひとつである. より最適な設計を実現するうえで流体シミュレーションの計算時間短縮は重要な課題のひとつであり, 近年は機械学習を使用した高速化手法の試みが盛んになりつつある. 本研究では流体シミュレーション手法のひとつMPS法 (Moving Particle Semi-implicit) に着目し, MPS法の一部を機械学習モデルに置き換え高速化する手法を提案する. 具体的にはナビエ・ストークス方程式の圧力勾配項を求める際に, MPS法では陰解法形式になっている圧力計算部分を, 10種類の特徴量からなる入力と勾配ブースティング回帰木による回帰モデルに代替し, 流体シミュレーションを高速化する. 最後に提案手法の定性的挙動を流体シミュレーションのトイプロブレムであるダム崩壊問題の数値計算で確認し, 提案手法の結果が従来手法と同様の挙動を示すことを示す.
1 0 0 0 OA 化学療法時にインスリン治療を必要とする糖尿病患者のケアシステムの導入
- 著者
- 清水 雅代
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病教育・看護学会
- 雑誌
- 日本糖尿病教育・看護学会誌 (ISSN:13428497)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.1-6, 2018 (Released:2018-05-22)
- 参考文献数
- 5
糖尿病合併がん患者は,化学療法時に使用するステロイド剤により血糖コントロールが悪化すると,感染や治療効果が半減するなどの問題から,糖尿病診療医と腫瘍治療医が連携して安全に化学療法を実施することの必要性が指摘されている.当院においても安全に化学療法を受けられることを目的に,化学療法をうける糖尿病合併がん患者の血糖管理基準を明確に示し,化学療法の指示を出す診療科と内分泌代謝科が連携してインスリン治療を必要とする糖尿病合併がん患者が安全に外来化学療法へ移行できるケアシステムを検討し導入した結果,安全な化学療法の推進につながることが示唆された.
1 0 0 0 OA 多様な音楽における認識法の違いをどう伝えるか
- 著者
- 清水 美穂子
- 出版者
- 光琳
- 雑誌
- 食品工業 (ISSN:05598990)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.5, pp.46-50, 2013-03-15
1 0 0 0 OA 中国瀋陽市における高齢介護必要者とその介護者の現状調査―介護負担感を中心として―
- 著者
- 馮 巧蓮 堀口 逸子 清水 隆司 羊 利敏 丸井 英二
- 出版者
- The Japanese Society of Health and Human Ecology
- 雑誌
- 民族衛生 (ISSN:03689395)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.1, pp.3-13, 2007-01-31 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1
To date, there have been only few studies which investigated the situation of care for the elderly and caregiver burden in China. We performed a structural interview with 172 frail elderly and their caregivers, in pairs, in Shenyang City, China, after explaining the purpose of our study and obtaining consent. The interview was comprised of the Chinese version of the Zarit Caregiver Burden Inter view (ZBI) questionnaire, Activities of Daily Living (ADL) questionnaire and questions on the char acteristics of the elderly and his/her caregiver. Responses from 150 elderly-caregiver pairs (87%), sufficient for analysis, were collected. Caregivers with high burden were defined as those who scored 51 points or more out of 88 points (66l or higher) on the ZBI. There were significant differences in ADL of frail elderly, caregiver's age, average number of hours of caregiving per day and elderly-caregiver relationship between caregivers with and without high burden from x 2 analysis. Using a multi variate logistic regression, we found that caregiver burden was associated with ADL of frail elderly, caregiver's age and elderly-caregiver relationship. The results of this study showed that ADL of frail elderly, caregiver's age, average daily hours of care provided and relationship between elderly and their caregivers affect burden among caregivers in China.
1 0 0 0 OA 韓国の李明博政権と6月地方選挙 : 金萬欽(韓国政治アカデミー院長)
- 著者
- 清水 敏行
- 出版者
- 札幌学院大学総合研究所
- 雑誌
- 札幌学院法学 = Sapporo Gakuin law review (ISSN:09100121)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.55-77, 2010-12
翻訳
1 0 0 0 OA SAR画像を用いた2017年九州北部豪雨における被害溜池の抽出
- 著者
- 小室 隆 赤松 良久 山口 皓平 プトゥ エディ ヤスティカ 清水 則一 二瓶 泰雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.271-287, 2019 (Released:2019-07-03)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 2
平成29年7月5日に発生した九州北部豪雨により,福岡県朝倉市に点在する溜池では決壊や一部決壊が生じた.それらの溜池を対象に災害後に国土地理院によって撮影された空中写真から15箇所の溜池を選び,現地調査を行った.また陸域観測技術衛星2号「だいち2号」(ALOS-2)に搭載されているLバンド合成開口レーダ(PALSAR-2)により観測された災害前後の地表面データを用いて,土砂堆積などにより地表面に変化が生じた溜池の抽出を行った.調査対象とした溜池のうち,5ヶ所の溜池で決壊・一部決壊を確認した.決壊・一部決壊が生じていた溜池以外では,決壊までは到達していないものの,溜池上流部において土砂の流入・堆積を確認した.PALSAR-2によって得られた地表面データを解析したところ,5,000 m2以上の面積の大きい溜池では土砂や流木の堆積による変化を捉えることが出来た.一方,山間地域に築造された小さな溜池では,周囲の斜面勾配による画像の歪みの影響により,必ずしも明確に抽出することができないことが明らかとなった.
1 0 0 0 OA 黒ニンニク含有サプリメント摂取による肝機能保護作用
- 著者
- 河崎 祐樹 八木(田村) 香奈子 後藤 純平 清水 邦義 大貫 宏一郎
- 出版者
- Japan Society of Nutrition and Food Science
- 雑誌
- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.3, pp.109-115, 2017 (Released:2017-06-23)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 2
目的: 健常な日本人が黒ニンニク含有サプリメントを摂取することによる肝機能への有効性を検証すること。試験デザイン: プラセボ対照・二重盲検・ランダム化比較試験。方法: 40名をランダムに2群に割付, 黒ニンニクまたはプラセボを12週間, 摂取させた。摂取前, 6週間後, 12週間後に血液検査 (肝機能, 腎機能, 血糖, 脂質) , 身体測定などを行った。結果: 12週間後の変化量において, 肝機能マーカーであるアラニンアミノトランスフェラーゼ (ALT) は黒ニンニク群のほうが有意に小さい値を示し (p=0.049) , アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (AST) も黒ニンニク群のほうが小さい傾向を示した (p=0.099) 。結論: 黒ニンニクを12週間摂取することで, 健常日本人に対して肝機能保護作用を示すことが示唆された。本試験はUMINへ登録されている (UMIN000024771) 。
- 著者
- 矢澤 智博 安倍 徳寿 清水 祐紀
- 出版者
- 一般社団法人 日本創傷外科学会
- 雑誌
- 創傷 (ISSN:1884880X)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.3, pp.128-132, 2016 (Released:2016-07-01)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA 科学技術に関する意識調査 - 2001年 2~3月調査 -
- 著者
- 岡本 信司 丹羽 冨士雄 清水 欽也 杉万 俊夫 第2調査研究グループ
- 出版者
- 科学技術政策研究所
- 雑誌
- NISTEP REPORT
- 巻号頁・発行日
- vol.072,
1 0 0 0 OA 会計倫理に対する事件史的アプローチ-不正会計の歴史的分析-
1 0 0 0 OA 農夫症の研究
- 著者
- 松島 松翠 寺島 重信 磯村 孝二 市川 英彦 横山 孝子 大柴 弘子 井出 秀郷 萩原 篤 清水 博昭 白岩 智恵子
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.135-144, 1969-03-01 (Released:2011-02-17)
長野県南佐久郡八千穂村の三部落から, 40才代及び50才代の男女113名を選び, 2年間にわたって農夫症々候群を中心に追跡調査を行なった。そのうち4回全部検診及び調査のできた81例について, 次のような結果を得た。1) 労働時間は男に比べて女に多く, かつ逆に睡眠時間は女の万に短かい, とくに40才代にかいて著明である。あきらかに女の万が過労状態であるといえる。また疲労の自覚症状や一般的健康状況, 検査結果, 有病率なども一般に女の万に悪い。即ち女の万が健康障害が多い。2) 農夫症総点数は, 一般に40才代より50才代が, 又, 男より女に多く, 農繁期に増加している。最近2年間の経過では, 男女とも増加しているが, 女の万が増加率が高い。3) 農夫症総点数は, 耕地面積 (一人当り) の多いほど, また乳卵摂取量の少ないほど高い。4) 農夫症総点数は, 疲労の自覚症状 (とくに身体的症状)、有病率と著明に相関している。また諸検査結果 (血圧, 血液, 肝機能等), 心電図, 胃レ線, 腰部レ線結果による異常と若干の相関が認められる。5) 以上の点から, 農夫症は慢性疲労状態, 不健康状態, 疾病状態を表わす一つの健康示標であるといえる。これを減らしていくためには, 農家の生活及び農業全般の根本的な改善がなされなければならない。
1 0 0 0 OA 転移性肝腫瘍と鑑別が困難であった肝副葉の1切除例
- 著者
- 清水 誠一 福田 三郎 有田 道典 先本 秀人 江藤 高陽 高橋 信 西田 俊博
- 出版者
- 日本臨床外科学会
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.8, pp.2090-2095, 2010 (Released:2011-02-25)
- 参考文献数
- 12
腎癌術後に肝転移再発と鑑別困難であった,肝副葉の1例を経験した.症例は59歳,男性.平成16年,右腎癌に対して手術施行されたが,術前のComputed tomography(CT)では肝腫瘤は認めていなかった.腎癌術後6カ月のCTで肝左葉に1cm大の腫瘤を認め,その後増大傾向を認めた.Dynamic CTでも造影効果を認めたため,転移性肝腫瘍を疑った.手術を施行したところ,肝外側区域から被膜を介して肝外に伸びる母指頭大の腫瘤を認め,切除した.摘出標本では,被膜内に門脈,動脈,胆管を認め,腫瘤は正常肝組織であり肝副葉と診断された.肝副葉は手術時などに偶然発見されることが多いが,本症例は術前に転移性肝腫瘍と鑑別困難な症例であったため,文献的考察を加えて報告した.
- 著者
- 清水 慶子
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.3, pp.367-383, 2009-03-31 (Released:2010-06-17)
- 参考文献数
- 121
- 被引用文献数
- 2 1
Noninvasive methods for the measurement of estrone conjugates (E1C), pregnanediol-3-glucronide (PdG), testosterone (T), follicle stimulating hormone (FSH), monkey chorionic gonadotropin (mCG) and cortisol in excreta of non-human primates were described. In the series of studies, results suggest that 1) urinary and fecal steroid metabolites accurately reflected the same ovarian or testicular events as observed in plasma steroid profiles in captive Japanese macaques, time lags associated with fecal measurements were one day after appearance in urine; 2) these noninvasive methods were applicable to wild and free-ranging animals for determining reproductive status; 3) hormonal changes during menstrual cycles and pregnancy could be analyzed by measurement of FSH, CG and steroid metabolites in the excreta in captive great apes and macaques; and 4) hormone-behavior relationships of macaques in their natural habitats and social setting could be analyzed. In these studies, we confirmed an association between maternal rejection and excreted estrogen, but not excreted progesterone, for Japanese macaques. We also reported that significantly higher levels of fecal cortisol were observed in high-ranking male Japanese macaques. 5) A reliable non- instrumented enzyme-linked immunosorbent assay for detection of early pregnancy in macaques was established.These results suggest that the noninvasive methods for monitoring characteristics of excreted hormones provide a stress-free approach to the accurate evaluation of reproductive status in primates. These methods provide the opportunities for the study of hormone-behavior interactions in not only captive but also wild and free-ranging animal species.
1 0 0 0 OA DHA含量が異なるワムシを摂餌したブリ仔稚魚のアルテミア摂餌期におけるDHA要求
- 著者
- 竹内 俊郎 石崎 靖朗 渡邉 武 今泉 圭之輔 清水 健
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.2, pp.270-275, 1998-03-15 (Released:2008-02-29)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 16 16
A feeding experiment was conducted to examine the effect of different docosahexaenoic acid (DHA) content in rotifers on the DHA requirement of larval yellowtail Seriola quinqueradiata during Artemia feeding stages. Rotifers enriched with freeze-dried shark eggs (HR) or Nannochloropsis (LR) having different levels of DHA were given to larvae for 23 days. Each lot of larvae was then divided into three groups, and each group was fed Artemia containing different levels of DHA; 0%, 1.6% and 2.6%, respectively, for 16 days.Both survival and vitality of larvae during Artemia feeding stages were affected by the DHA levels in rotifers at the start of feeding. It was found that as DHA content in rotifers increased, the DHA requirement of larvae during Artemia feeding stages decreased from 2.6 to 1.6%. When larvae were fed rotifers containing 1.3% DHA followed by Artemia containing 1.6% or 2.6% DHA, healthy larvae were obtained. The survival and vitality of larvae fed on rotifers having a low level of DHA improved by feeding them with Artemia containing 2.6% DHA.The results indicate that the DHA content in rotifers influences the DHA requirement of larval yellowtail during the Artemia feeding stages.
1 0 0 0 二十世紀初頭日本の民主主義
- 著者
- 清水 靖久
- 出版者
- 日本政治学会
- 雑誌
- 日本政治學會年報政治學 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.207-231, 1995
1 0 0 0 IR 永久革命としての民主主義
- 著者
- 清水 靖久
- 出版者
- 九州大学大学院地球社会統合科学府
- 雑誌
- 地球社会統合科学 (ISSN:21894043)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.1-20, 2017-12-10
Maruyama Masao (1914 - 1996) famously expressed his political thought by "democracy as permanent revolution" in the addition to the third part of his book Thought and Behavior in Modern Japanese Politics(enlarged edition, 1964). Also, Maruyama made his "bet on the sham of postwar democracy" in the postscript of the same book. This article traces his thought of democracy during the postwar period and considers his idea of democracy as permanent revolution. After the end of World War II, Maruyama worried about democracy for more than a half year partly due to his skepticism about its contradictions. With the announcement of the drafted constitution in March 1946 , he converted to the principle of the sovereignty of the people, and wrote about the so-called democratic revolution of Japan. Since 1949 he was committed to the movement of the democratic camp, pursuing democratization of Japanese society and protesting against the conservative and reactionary forces. Around 1960 he talked about the paradox of democracy, for the government of the people was not natural as Rousseau thought. Shortly after the rise of the Anti-Anpo movement, he wrote in his notebook that not socialism, but democracy deserved the name of "permanent revolution" because of the paradox of the government of the people. Democracy had been the protest concept against the orthodox concept for Maruyama until 1960 . In 1964 , when he professed democracy as "permanent revolution," he kept such literary radicals in his mind as Tanigawa Gan, Yoshimoto Takaaki and their epigones. His idea of democracy as "permanent revolution" was to routinize the revolution as the process of everyday movement. Since then, he had never mentioned "democracy as permanent revolution" before the late 1980 s. Exceptionally, he disputed with students about "permanent revolution" of Trotsky at the University of Tokyo Struggles in 1969 .