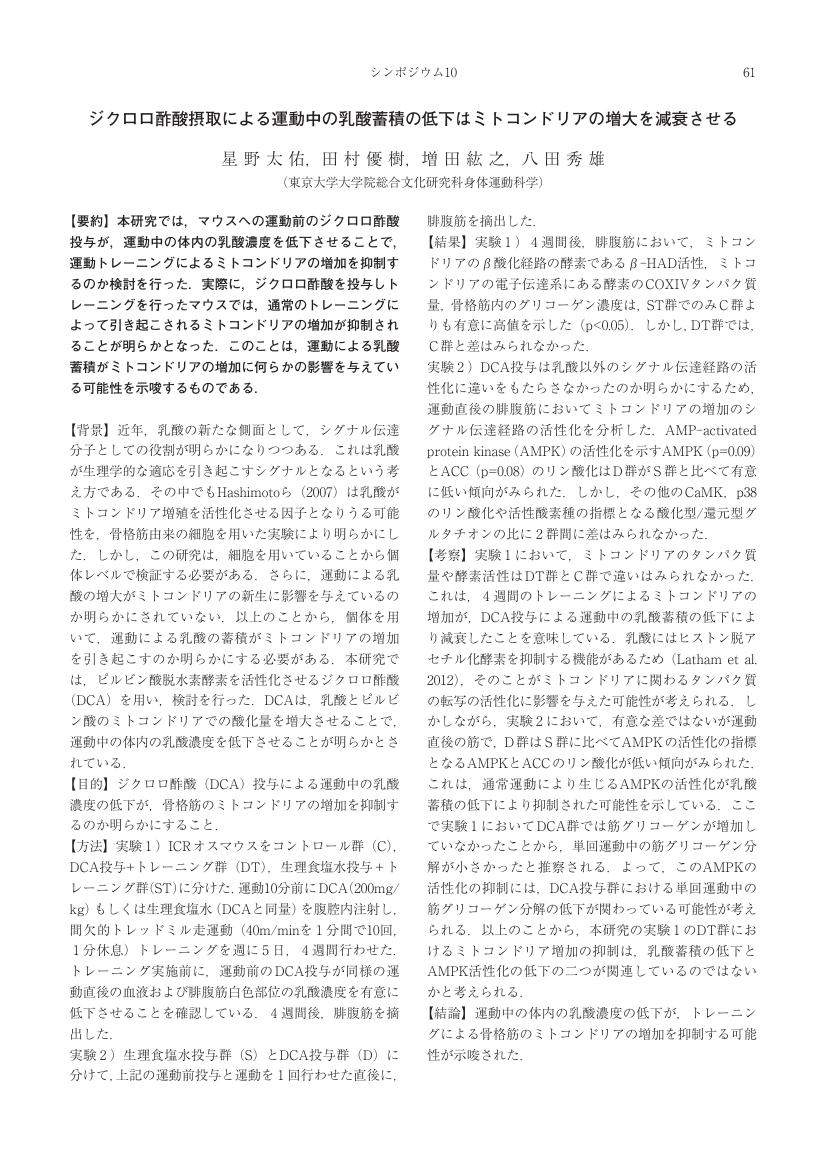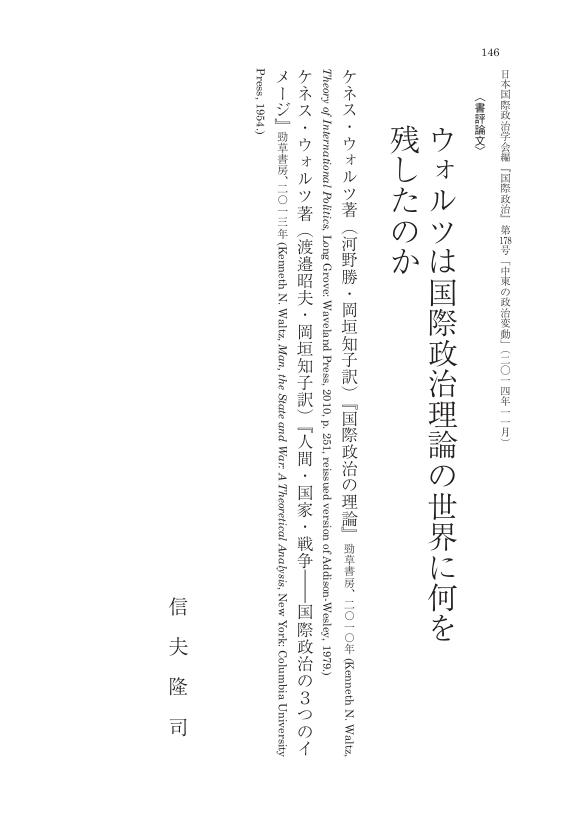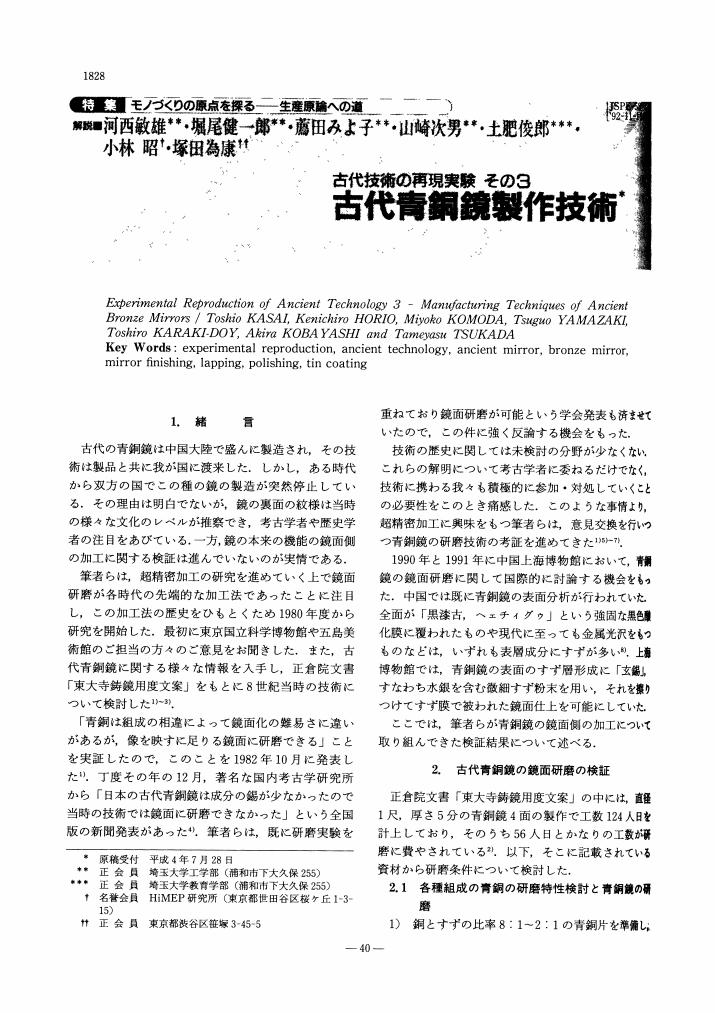3 0 0 0 OA 調理と機能水
- 著者
- 堀田 国元
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.4, pp.275-278, 2010 (Released:2014-10-03)
- 参考文献数
- 17
3 0 0 0 OA 2.パニック障害治療用バーチャルリアリティ
- 著者
- 河合 隆史 李 在麟
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.8, pp.1086-1091, 2007-08-01 (Released:2009-12-21)
- 参考文献数
- 17
3 0 0 0 OA 原子力発電所における安全文化醸成活動の実効性向上に関わる研究
- 著者
- 山本 晃弘 関村 直人
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会和文論文誌 (ISSN:13472879)
- 巻号頁・発行日
- pp.J16.002, (Released:2017-06-27)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 1
The enhancement of safety culture is an issue for both plant operators and regulators working in fields related to the safety management of nuclear power plants. Plant operators have been collecting safety culture data through a broad range of tools and methods such as observations, interviews and other surveys. However, many issues remain regarding the effectiveness of safety culture activity. A new regulatory authority was established in 2012 after the Fukushima Dai-ichi accident to enforce nuclear safety regulations but its activity is still weak in terms of monitoring the performance of plant operators’ safety culture. In order to promote and strengthen safety culture, plant operators need to collect detailed event information, even when events do not directly affect plant safety, and accumulate information related to human, organizational and technical factors through dialogue among the parties responsible for coping with events. Both operators and regulators should all be working in the same direction to assess information that will help their periodic reviews, and the involvement of local government is a key to enhancing their safety culture.
3 0 0 0 OA ジクロロ酢酸摂取による運動中の乳酸蓄積の低下はミトコンドリアの増大を減衰させる
- 著者
- 星野 太佑 田村 優樹 増田 紘之 八田 秀雄
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.61, 2014 (Released:2014-01-24)
- 著者
- Shouma Ishikawa Atsushi Sawamoto Satoshi Okuyama Mitsunari Nakajima
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.550-556, 2021-04-01 (Released:2021-04-01)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 3
We previously reported a screening method for caloric restriction mimetics (CRM), a group of plant-derived compounds capable of inducing good health and longevity. In the present study, we explored the possibility of using this method to screen CRM drugs for drug repositioning. The method, T-cell activation-inhibitory assay, is based on inductive logic. Most of CRM such as resveratrol have been reported to suppress T-cell activation and have anti-inflammatory functions. Here, we assessed the activity of 12 antiallergic drugs through T-cell activation-inhibitory assay and selected four that showed the lowest IC50 values—ibudilast (IC50 0.97 µM), azelastine (IC50 7.2 µM), epinastine (IC50 16 µM), and amlexanox (IC50 33 µM)—for further investigation. Because azelastine showed high cytotoxicity, we selected only the remaining three drugs to study their biological functions. We found that all the three drugs suppressed the expression of interleukin (IL)-6, an inflammatory cytokine, in lipopolysaccharide-treated macrophage cells, with ibudilast being the strongest suppressor. Ibudilast also suppressed the secretion of another inflammatory cytokine, tumor necrosis factor (TNF)-α, and the expression of an inflammatory enzyme, cyclooxygenase-2, in the cells. These results suggest that T-cell activation-inhibitory assay can be used to screen potential CRM drugs having anti-inflammatory functions for the purpose of drug repositioning.
3 0 0 0 OA ウォルツは国際政治理論の世界に何を残したのか
- 著者
- 信夫 隆司
- 出版者
- 一般財団法人 日本国際政治学会
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, no.178, pp.178_146-178_155, 2014-11-10 (Released:2015-11-30)
- 参考文献数
- 27
3 0 0 0 OA 健常高齢者における神経心理学検査の測定値 ―年齢・教育年数の影響―
- 著者
- 原田 浩美 能登谷 晶子 中西 雅夫 藤原 奈佳子 井上 克己
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.16-24, 2006 (Released:2007-04-01)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 8 9 2
われわれは,健常高齢者における神経心理学検査の測定値を求めるために,65 ~ 85 歳の 92 名の対象に神経心理学検査を実施し,成績と年齢,教育年数との関連を調べた。年齢および教育年数によって階層化した各群別成績を求め,群間比較を行うことにより測定値の有用性を示した。 かなひろいテスト (無意味綴り,物語) とTrail Making Test (part A,part B) の成績は年齢,教育年数の双方ともと有意に関連した。300 語呼称検査の成績は年齢と有意に関連した。 Mini-Mental State Examination,N 式精神機能検査—物語再生項目 (直後再生,遅延再生) ,Rey-Osterrieth 複雑図形検査 (模写,直後再生) は,年齢と教育年数の双方に影響されなかった。本研究で検討した神経心理学検査成績の解釈をするとき,年齢と教育年数の影響を考慮に入れる必要があることがわかった。
3 0 0 0 OA 主観的幸福度のセルフレコーディング手法の開発
- 著者
- 佐伯 政男 前野 隆司
- 出版者
- 行動経済学会
- 雑誌
- 行動経済学 (ISSN:21853568)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.146-152, 2010 (Released:2011-04-26)
- 参考文献数
- 17
幸福度を継続的に自己管理するための手法として,カレンダー·マーキング法を開発した.カレンダー·マーキング法は,一日の終わりにその一日を振り返り,主観的な評定を行う手法である.すなわち,評定の結果,その日がよい日であったら「◯」,悪い日であったら「×」,どちらでもない日であったら「△」をカレンダーの日付欄に記録する.心理学部の学部生を対象に,10週間,手法の実施を行った.実施後に測定したThe Satisfaction with life Scale (SWLS)では,手法の実施群と対照群のSWLSに統計的に有意差は見られなかった.SWLSと各被験者の各記号の総数との相関係数は,◯,△,×,それぞれ,0.506,-0.439,-0.237であった.分析の結果,よい日にも悪い日にも△を付ける傾向が見られた.◯を増やし△と×を減らすことによって幸福度を向上させうることが示唆された.また,被験者間,被験者内で各記号の報告には変動性が見られたことから,本手法で得られた結果は,主観的幸福度の測定手法として利用されうることを示した.
- 著者
- Daisuke Shimada Atsushi C. Suzuki Megumu Tsujimoto Satoshi Imura Keiichi Kakui
- 出版者
- The Japanese Society of Systematic Zoology
- 雑誌
- Species Diversity (ISSN:13421670)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.49-63, 2021-03-22 (Released:2021-03-22)
- 参考文献数
- 81
- 被引用文献数
- 4
Two new species of free-living marine nematodes, Odontophora odontophoroides sp. nov. and Parabathylaimus jare sp. nov., are described from the coastal sand of Langhovde, Lützow-Holm Bay, Dronning Maud Land, Antarctica. Odontophora odontophoroides sp. nov. is the only species in Odontophora Bütschli, 1874 that has bicuspidate odontia. Odontophora odontophoroides sp. nov. is similar to species in Odontophoroides Boucher and Helléouët, 1977 and Synodontium Cobb, 1920 in having bicuspidate odontia, but differs in having a didelphic reproductive system in females. Parabathylaimus jare sp. nov. differs from congeners in the unjointed inner labial and cephalic sensilla, the outer labial sensilla three-jointed in males and two-jointed in females, the position of the amphids, the shorter spicules, and the conical tail without long subterminal setae. Modified generic diagnoses and keys to species are included for Odontophora and Parabathylaimus De Coninck and Schuurmans Stekhoven, 1933. A new combination, Parabathylaimus arthropappus (Wieser and Hopper, 1967) comb. nov., is established.
- 著者
- MARIA KOWALSKA
- 出版者
- Journal of Radiation Research Editorial Committee
- 雑誌
- Journal of Radiation Research (ISSN:04493060)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.4, pp.385-394, 1985-12-15 (Released:2006-06-16)
- 参考文献数
- 15
Three generations of rats were long-term exposed to HTO in drinking water at activity of 37.0 kBq/ml or to food containing OBT at activity of 48.1 kBq/g. The rats consumed tritiated water and tritiated food ad libitum. In the experiment the F1 and F2 generation of rats were exposed continuously from conception to the 21-st or 120-th day of age and rats of F3 generation during 22 days of their intrauterine life. It was found that the amount of tritium incorporated into the major rat brain phospholipids and gangliosides after administration of tritiated food was higher than after administration of tritiated water. Tritium activity in all studied phospholipids and gangliosides was the highest in 21-day-old rats exposed during both-pregnancy and lactation.
3 0 0 0 OA Finding of talc– and kyanite–bearing amphibolite from the Paleoproterozoic Usagaran Belt, Tanzania
- 著者
- Keiko MORI Tatsuki TSUJIMORI Nelson BONIFACE
- 出版者
- Japan Association of Mineralogical Sciences
- 雑誌
- Journal of Mineralogical and Petrological Sciences (ISSN:13456296)
- 巻号頁・発行日
- vol.113, no.6, pp.316-321, 2018 (Released:2018-12-29)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 1 6
We report a newly discovered assemblage of talc–kyanite in an amphibolite from the Isimani Suite of the Paleoproterozoic Usagaran Belt, central Tanzania. The amphibolite is characterized by the mineral assemblage of clinoamphibole, kyanite, talc with minor rutile, quartz, dolomite, and rare barite. The high Fe3+/(Fe3+ + Fe2+) ratio (0.48–0.80) of clinoamphibole and the presence of sulfate (barite) indicate a very–high oxidation state during metamorphism. P–T pseudosection modelling predicts that the studied talc– and kyanite–bearing amphibolites formed at high–pressure conditions (P > 1.0 GPa). Moreover, the modelling suggests formation of talc + kyanite + clinoamphibole at a highly oxidizing condition with CO2 fluid. This talc–kyanite association provides an index of high–pressure metamorphism of the Usagaran Belt and marks the oldest record of the talc–kyanite association in regional metamorphism in the Earth’s history.
- 著者
- 顧 抱一
- 出版者
- The Japanese Association of Administrative Science
- 雑誌
- 経営行動科学 (ISSN:09145206)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.117-137, 2015 (Released:2016-05-10)
- 参考文献数
- 68
- 被引用文献数
- 1
The purpose of this paper is to investigates predictors for subjective and objective phenomena of withdrawal behaviors, e.g. absenteeism, turnover intention etc. As the most important predictor, this research takes psychological capital, and as other predictors it takes leadership and stress. The data were collected from Chinese 300 employees of an apparel maker in China. Psychological capital, leadership, and stress affected turnover intention and absenteeism. Stress mediated the relationship between psychological capital and absenteeism. Stress also mediated the relationship between psychological capital and turnover intention. Implications of this study's findings were discussed.
3 0 0 0 OA 健康長寿のための音声の維持
- 著者
- 平野 滋 杉山 庸一郎 金子 真美 椋代 茂之
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.124, no.1, pp.11-13, 2021-01-20 (Released:2021-02-01)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
声帯は50歳ごろより萎縮が始まり, 声の減弱化, 嗄声を呈するようになる. 声帯の粘膜および筋肉の萎縮によるが, 声の劣化は活力の低下, 生活圏の制限, 社会的地位への脅威など高齢者における生活および仕事環境を脅かすことにもなり, またひいては誤嚥による健康被害にも繋がる. 声が掠れてきたら要注意であり, 予防による声帯の維持が重要である. 声帯の維持のために, 1. 声帯の保湿, 2. 喉頭の慢性炎症の予防, 3. 適度な発声, 4. 活性酸素の抑制を勧めている. 声帯の保湿には1日1.5L 以上の水分摂取が世界的に推奨されている. 喉頭の慢性炎症予防のためには禁煙, 胃酸逆流やアレルギー性炎症のコントロールが重要である. 歌手は声帯の寿命が長いといわれるが, 近年の臨床研究で一定のエビデンスが示された. 適切な発声を継続することが声帯維持に重要である. また, 活性酸素は加齢とともに増加し, 組織障害性を発揮する. 声帯も例外ではなく, 加齢や声帯酷使により声帯粘膜内の活性酸素が増加すること, また抗酸化剤の投与によりこれを予防し, 声帯の維持に有効なことを示した. 声帯の萎縮が生じてしまった場合, 呼気と共鳴を最適化する適切な音声治療によりある程度の改善が期待できる. 塩基性線維芽細胞増殖因子は, 萎縮した声帯粘膜内のヒアルロン酸産生を促進することで, 声帯の再生を促すことが可能である. かつては「年だから仕方ない」とされた声帯萎縮であるが, 健康長寿のために予防と治療が重要である.
3 0 0 0 OA 社会政策における互酬性の批判的検討
- 著者
- 平野 寛弥
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.239-255, 2012-09-30 (Released:2013-11-22)
- 参考文献数
- 33
本稿は, 社会政策における互酬性の変遷をその構造に着目して比較分析することにより, それぞれの互酬性の異同を明らかにするとともに, 新しい互酬性として提案されたTony Fitzpatrickの「多様な互酬性」がもつ社会構想としての可能性を検討するものである.第2次世界大戦後に成立した福祉国家体制が変容していくなかで, 社会政策における互酬性もまた変遷を遂げてきた. とりわけ現在支配的な言説となっている「福祉契約主義」においては, 権利に伴う義務の重要性が強調され, 権利を制約しようとする傾向が強まっている. これに対して「福祉契約主義」の対抗言説として提唱された新たな互酬性の1つである「多様な互酬性」は, 無条件な義務を前提としつつも, 権利に伴う義務の要求を逆手に取り, 義務の履行条件として無条件な権利の要求の正当性を主張する戦略であることが明らかとなった.この「多様な互酬性」からは, 無条件での基礎的生活保障の提供や「ヴァルネラブルな人々」に対する公正な保護, 多様な義務の選択可能性など, 現在直面している社会問題に対する新たな対応策への示唆を引き出すことができる. これらの内容は, 「多様な互酬性」が社会政策における配分原理という位置づけをはるかに超えて, ラディカルな社会変革の可能性を秘めた1つの社会構想ともいえる射程を有していることを示している.
3 0 0 0 OA 古代技術の再現実験その3
3 0 0 0 OA 世界における除草剤の歴史:その誕生・発達・変遷
- 著者
- 伊藤 操子
- 出版者
- 特定非営利活動法人 緑地雑草科学研究所
- 雑誌
- 草と緑 (ISSN:21858977)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.3-11, 2016 (Released:2017-05-31)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
除草剤の存在は世界の食糧生産を支える上で不可欠だが,生活圏の雑草問題である衛生被害の回避,環境保全,インフラ保護にとっても重要である.しかし,未だに除草剤への拒否反応がはびこる日本の現状に鑑み,今日あるような除草剤がなぜ生まれ,科学・技術としてどう発達し,現在どういう段階にあるのか,世界の流れを振り返る.化学物質で雑草を撲滅するという発想は19世紀中頃から始まり,手取りや機械で防除できない多年草に大量の無機物質の投与が試みられた.一方,本格的な除草剤の発展は,1940年代初頭の選択的有機除草剤2,4-Dから始まった.これは世界の雑草防除自体のありようを一変させた画期的出来事である.その後1080年代にかけて,作物―雑草間の選択性の追求,新規作用点の開発,低処理薬量・低残留性,新規剤型の開発等が世界的に進展し,効果,作物や環境に対する安全性において優れた多くの除草剤が生まれた.しかし,その後徐々に縮小されて今日に至っている.理由は,除草剤のマーケットが成熟し,既剤を上回るものを開発しにくい,安全性試験へのコストの増大,グルホサート抵抗性遺伝子組換え作物の普及で,対抗できるインセンテイブが低下したなどである.化学的防除の著しい発展は,他方で,雑草防除実施者が創意工夫の意思の喪失,簡単に成果が期待できるという思い込みを生んだ.その最も顕著なしっぺ返しは,未だに止むことのない世界的な除草剤抵抗性雑草の増加である.
3 0 0 0 OA 日本における研究データ管理教材の開発経緯
- 著者
- 西薗 由依 尾城 孝一 古川 雅子 南山 泰之
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.4, pp.187-193, 2021-04-01 (Released:2021-04-01)
研究データ管理(RDM)は,オープンサイエンスにおける研究データ共有や公開を支える重要なプロセスとして位置づけられる。機関リポジトリ推進委員会,及びその後継となるオープンアクセスリポジトリ推進協会は,国内でRDMを推進するための方策として,2015年から研究支援者向けのRDM教材開発に取り組んできた。本稿では,開発した2つの教材「RDMトレーニングツール」及び「研究データ管理サービスの設計と実践」の開発経緯について紹介する。また,開発した教材の活用事例として,国立情報学研究所と共同で作成した動画教材についても触れる。
3 0 0 0 OA LSSのダイナミクス, モデリングおよび低次元化
- 著者
- 狼 嘉彰 木田 隆 山口 功
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.10, pp.845-854, 1987-10-10 (Released:2009-11-26)
- 参考文献数
- 30
3 0 0 0 OA 2.出血傾向へのアプローチ
- 著者
- 加藤 淳
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.7, pp.1562-1568, 2009 (Released:2012-08-02)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 4
出血傾向は血小板・血管壁,凝固・線溶系,または両方の異常により生じるが,迅速な診断,対応が必要である.スクリーニング検査としては,血小板数,プロトロンビン時間,活性化部分トロンボプラスチン時間でほぼ十分であるが,これらに異常がない場合は出血時間,XIII因子,α2-プラスミンインヒビター,プラスミノゲンアクチベーターインヒビター-1活性,またDICが疑われる場合はフィブリノゲン,FDPを測定する.
3 0 0 0 OA 組織内での個人の自由
- 著者
- 蔡 芢錫
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織科学 (ISSN:02869713)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.28-45, 2012-09-20 (Released:2013-10-01)
- 参考文献数
- 132
本論文は,個人が自らの自由な選択で雇用契約を結び「個人」から「従業員」へと身分が変わる時,個人が享受する自由にどのような変化が生じるのかに注目する.具体的には,現代の自由観念の中心にある「消極的自由」と「積極的自由」との枠組みの下で,組織内で個人の自由はどのような歴史を経験してきたのか,なぜ組織で働く人々は自由を叫ばないのか,組織内で個人の自由はどのように議論・研究されてきたのか,組織内で個人の自由を拡大するためには何が必要なのかに焦点を当てる.