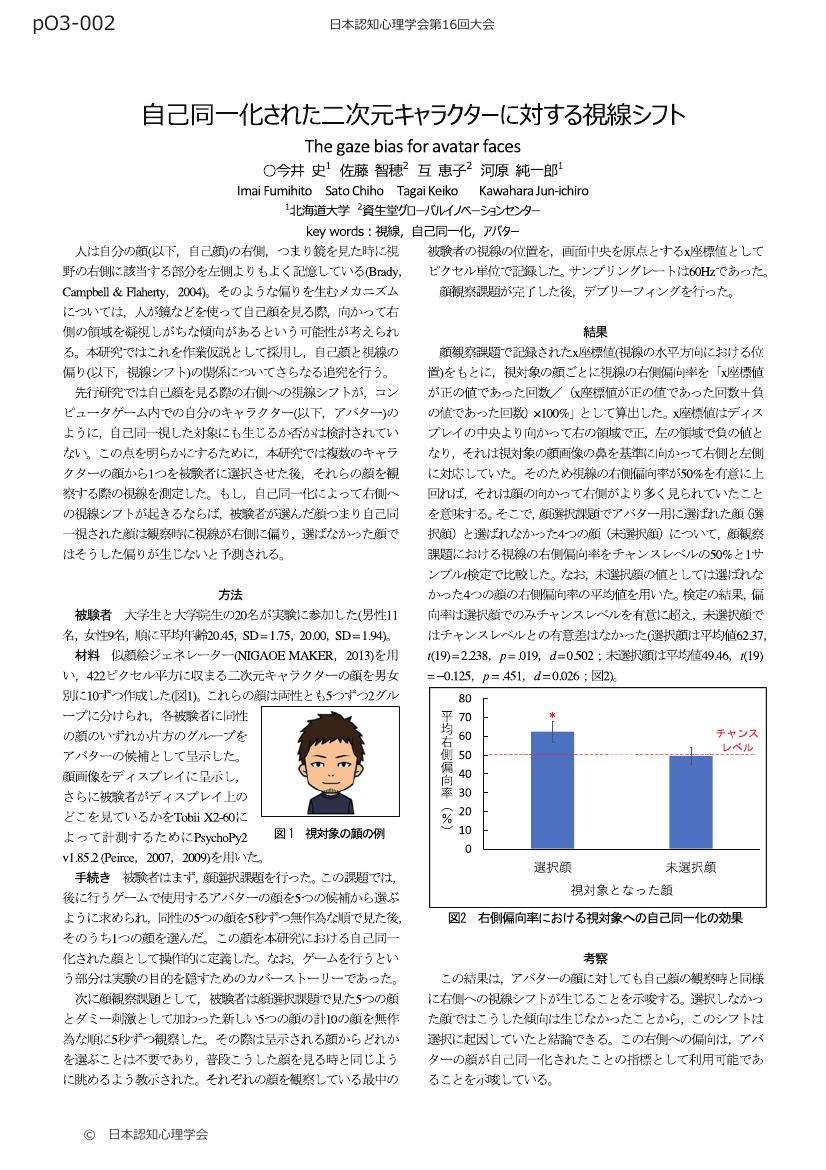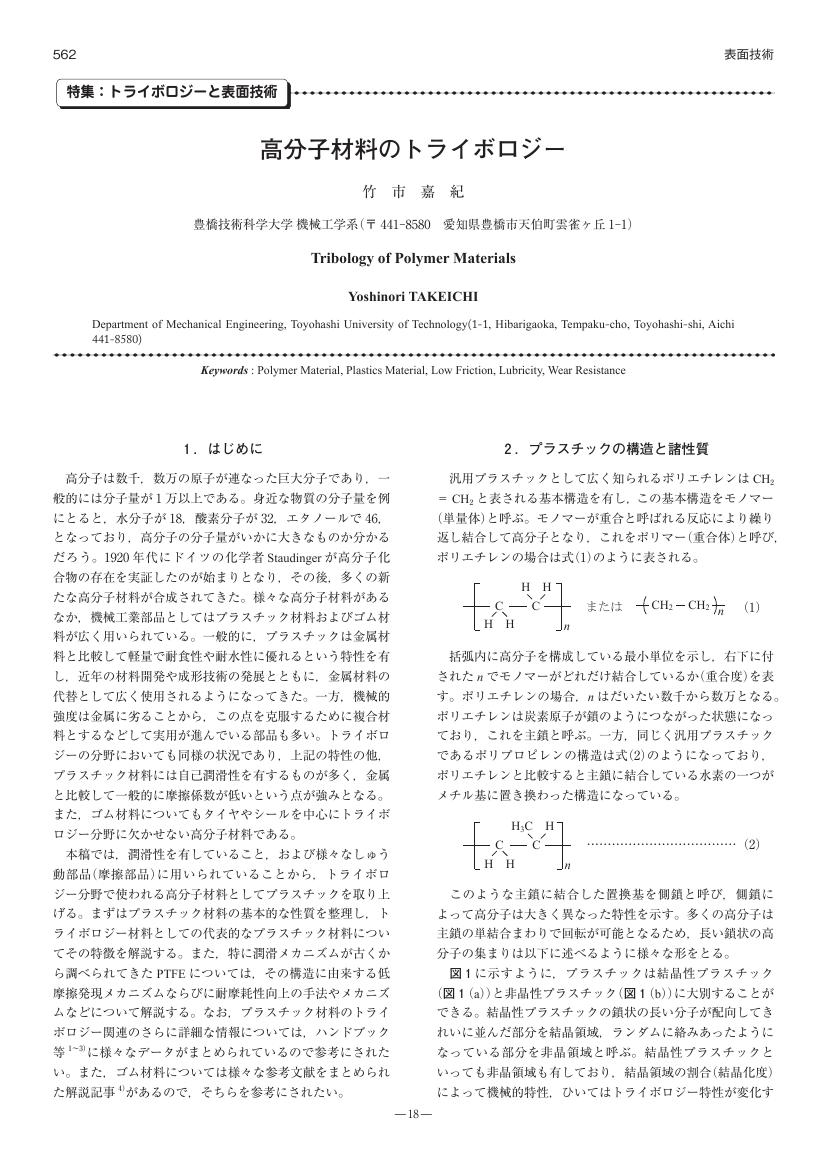3 0 0 0 OA 次亜ハロゲン酸塩による酸化
- 著者
- 小方 芳郎 木村 眞
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.7, pp.581-594, 1979-07-01 (Released:2009-11-13)
- 参考文献数
- 85
- 被引用文献数
- 3 8
Metal hypohalites (e. g. NaOCl) can be used not only for selective oxidation and halogenation of organic compounds, but also for oxidative removal of pollutants such as aromatic compounds and surfactants, especially nitrogen compounds which results in the eutrophication of sees and lakes.The present article reviews the properties and oxidative preparation, reactions of hydrocarbons (aliphatic and aromatic), alcohols, aldehydes, ketones, ethers, carboxylic acids, ammonia, amines, amides (including urea), and sulfur compounds (including sulfonic acids) with the hypohalites. On UV irradiation hypohalites delivers atomic oxygen and HO·which are highly active oxidants, thus initiate a chain reaction by abstracting hydrogen atom, and can be used for removal of pollutants. The review emphasizes the mechanisms for hypohalite oxidation and photo-oxidation of compounds polluting waste water.
3 0 0 0 OA 我が国への三大バルク貨物輸送船の大型化に向けた考察
- 著者
- 赤倉 康寛 瀬間 基広
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D (ISSN:18806058)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.369-382, 2010 (Released:2010-08-20)
- 参考文献数
- 28
中国・インド等の旺盛な資源需要を背景に,石炭,鉄鉱石,穀物等のドライバルク貨物を輸送するバルクキャリアの大型化が,急激に進展している.我が国産業の国際競争力の維持・強化や,より安定した食糧原料の供給のためには,この大型化動向に対する我が国港湾の対応方策を,十分に検討しておく必要がある.一方,ドライバルク貨物輸送は,特定荷主のための不定期輸送であり,その情報は非常に限られている.以上の状況を踏まえ,本研究は,バルクキャリアの大型化動向の分析,我が国港湾施設の輸送船大型化に対する制約状況の把握,大型化による輸送コスト削減効果の算定により,我が国への三大バルク貨物輸送船の大型化に向けた方策について考察したものである.
- 著者
- 杉下 守弘 朝田 隆
- 出版者
- 認知神経科学会
- 雑誌
- 認知神経科学 (ISSN:13444298)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.87-90, 2009 (Released:2010-03-10)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 3
高齢者用うつ尺度短縮版(GDS)の日本版(GDS-S-J)を作成した。作成に際して、質問項目が現在の日本文化からみて妥当であるか否かを検討した。また、聞いて分かりやすい訳語を使用した。さらに、各項目の日本文が長くならないように配慮した。このように、文化的および言語学的妥当性を高めてあるので、実際に用いることができると考えられる。英語版から翻訳された心理検査では文化的妥当性と言語学的妥当性を考慮する必要があるが、同時に英語版との等価性にも配慮する必要がある。これによって英語版のデータと日本語版のデータを比較しやすくなるからである。
3 0 0 0 OA Bertolotti症候群に対し横突起切除術を施行した2例
- 著者
- 赤瀬 広弥 吉岩 豊三 宮崎 正志 野谷 尚樹 石原 俊信 津村 弘
- 出版者
- 西日本整形・災害外科学会
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.362-366, 2017-03-25 (Released:2017-05-01)
- 参考文献数
- 10
【はじめに】Bertolotti症候群は1917年にBertolottiが提言した最尾側腰椎の肥大した横突起と仙骨間に関節を形成し,腰痛を生じる症候群である.今回,Bertolotti症候群に対し横突起切除術を施行した2例を経験したので報告する.【症例】28歳女性と64歳女性.いずれも保存的治療に抵抗性の腰痛があり,単純X線,CTでは片側性に横突起と仙骨翼での関節形成が見られた.両症例とも横突起直上より侵入し,横突起切除術を施行した.1例目では,横突起基部から関節突起間部にかけての視認性が不良であり,横突起基部の切除に難渋した.2例目では顕微鏡を使用し,L5神経根に対して,より愛護的に施行し得た.いずれも術後,症状改善を認めた.【考察】手術的治療には横突起切除術と固定術があり,いずれも良好な成績が報告されている.われわれの症例では,横突起切除術を施行し,症状の改善を認めた.横突起基部の切除には,L5神経根が近接するため慎重を要するが,愛護的な処置のために顕微鏡が有用であった.
3 0 0 0 OA カーボンマイクロコイル (CMC) の開発とその応用
- 著者
- 陳 秀琴 元島 栖二
- 出版者
- THE CARBON SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- 炭素 (ISSN:03715345)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.230, pp.338-344, 2007-11-15 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 2 1
Carbon micro-coils (CMCs) with 3D-helical/spiral structures and coil diameters of orders were obtained by the metalcatalyzed pyrolysis of acetylene at 700-800°C. In this review, the preparation process, morphology, microstructure, properties, and some applications of CMCs are introduced and their future prospect is discussed. The as-grown CMCs have almost amorphous structure, but were graphitized by high temperature heat treatment with full preservation of the coiling morphology. The CMCs could effectively generate inductive electromotive force, inductive current and thus Joul's heat under the application of microwaves. The CMCs/elastic polymer composite elements showed high tactile/proximity sensing properties which are comparable to that of human skin. The CMCs are a possible candidate for electromagnetic wave absorbers, remote heating materials, visualization elements of microwaves, tactile/proximity sensor elements, micro-antenna, chiral catalysts, bio-activators or bio-deactivators, energy converters, etc.
3 0 0 0 OA 墨書土器村落祭祀論序説
- 著者
- 高島 英之
- 出版者
- 一般社団法人 日本考古学協会
- 雑誌
- 日本考古学 (ISSN:13408488)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.9, pp.53-70, 2000-05-15 (Released:2009-02-16)
- 参考文献数
- 20
集落遺跡出土の墨書・刻書土器は,村落の内部における祭祀・儀礼等の行為に伴って使用されたものである。土器に墨書する行為は,日常什器とは異なるという非日常の標識を施すことであり,祭祀用に用いる土器を日常什器と区別し,疫神・祟り神・悪霊・鬼等を含んだ意味においての「神仏」に属する器であることを明記したものであると言える。墨書土器は,集落全体,もしくは集落内の1単位集団内,或いはより狭く単位集団内におけるところの1住居単位内といった非常に限定された空間・人的関係の中における祭祀や儀礼行為に伴って使用されたものであり,記された文字の有する意味は,おそらくそれぞれの限定された空間や集団内において共通する祭儀方式の中でのみ通用するものであり,個々が多様な時間的・空間的広がりの中で機能したと考えられる。文字を呪術的なものとして受容したところに,古代の在地社会の特質があるわけであり,祭具として東国を中心とする在地社会に浸透していったと見られるのである。
3 0 0 0 OA 応永期における渡唐天神説話の展開
- 著者
- 芳澤 元
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, no.10, pp.1675-1696, 2011-10-20 (Released:2017-12-01)
When taking up the question of the essential character of Japanese Buddhism during the Muromachi Period, it is necessary to investigate its influence on the era's cultural phenomena. For example, in the recent research dealing with Muromachi culture, focus has been placed on the period's Oei 応永 Era (1394-1428), which amends conventional Kitayama vs. Higashiyama view of the period's cultural history; however, when turning to the subject of the cultural influence of Zen Buddhism, the discussion has not developed beyond the classic study by Tamamura Takeji, which concentrates on the unique character of Shogun Ashikaga Yoshimochi. The cause of the problems that have now arisen is that the research taking up 1) obscure source materials related to the Gozan 五山 Zen temples and 2) the social aspects of Zen Buddism has not yet dealt with the Oei Era. This situation is mainly the responsibility of the historical research done on Buddhism in general and Zen in particular that ignores the aspect of culture. The present article discusses the Tale of Totou Tenjin 渡唐天神, a Buddhist story about Sugawara-no-Michizane (later diefied as Tenjin, the patron of scholarship and the literary arts) appearing in a dream of a Zen monk who advises him to journey to Tang China to learn the art of Zen meditation from his master Fojian 仏鑑, in relation to poetic picture scrolls and the renga 連歌 genre of Japanese poetry. It was during the Oei Era that such aspects of the tale appearing in the latter half of the 14th century as the dream about Michizane and Tenjin folk beliefs, as well as the activities of Zen monks studying abroad in China writing poetry about such subjects as the literati of Jiangnan (Jiangnan renwen 江南文人) and the legend of Tobiume 飛梅, a legendary plum tree planted by Michizane at the Dazaifu Tenjin shrine (Kyushu), all began to be edited as illustrated versions. The author argues that despite the vast research literature dealing with the Tale of Totou Tenjin, no definitive work has yet to appear on the meaning of and historical background to its popularity during the Oei Era. Next, the author takes up records of Ouchi Morimi, the governor of Suo and Nagato Province (Yamaguchi) and home of the Matsuzaki Tenjin shrine, presenting a pictorial image of Totou Tenjin to Shogun Yoshimochi while residing in Kyoto and excerpts from literary works on the subject of the image, in order to show Morimi's conversion to Tenjin beliefs while in Kyushu and the process by which Morimi traveled to Kyoto after Yoshimochi the suceeded to the head of the House of Ashikaga and received the Shogun's favor. From that time on, what led to the further development of the Tale were 1) Yoshimochi and Morimi's adoration of Tenjin and the participation of the shogun and Gozan Zen monks in Tenjin-related Buddhist ceremonies sponsored by Morimi, which would end with renga poetry writing and 2) Koun Myogi, aristocrat, Zen monk and literatus serving the shogun, who was also deeply interested in the Tale of Totou Tenjin, instructing Gozan Zen monks in the literary arts. The world of the Gozan temples and provincial governors participating in the promotion of the literary arts and the appreciation of the fine arts was formed under the auspices of cooperative personal relationships developed between the capital and the provinces during the Oei Era; and it was this world in which the Tale of Totou Tenjin became the main theme in a wide range of artwork. The image of Totou Tenjin is characterized not only by elements limited exclusively to the events and social structure specific to the Oei Era, but also by more fluid elements easily articulated with themes unrelated to Zen Buddhism. This dual character enabled the Tale to develop while gradually drifting away from its original Zen context, and it could not have continued on past the Muromachi cultural scence into the late premodern period merely on(View PDF for the rest of the abstract.)
- 著者
- Kazutaka Aonuma Hiro Yamasaki Masato Nakamura Takashi Matsumoto Morimasa Takayama Kenji Ando Kenzo Hirao Masahiko Goya Yoshihiro Morino Kentaro Hayashida Kengo Kusano Yutaka Gomi Michael L. Main Takahiro Uchida Shigeru Saito
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-20-0196, (Released:2020-06-26)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 15
Background:The SALUTE trial was a prospective, multicenter, single-arm trial to confirm the safety and efficacy of the WATCHMAN left atrial appendage closure (LAAC) device for stroke prevention in patients with nonvalvular atrial fibrillation (NVAF) in Japan.Methods and Results:A total of 54 subjects (including 12 roll-in subjects) with a WATCHMAN implant procedure were followed in 10 investigational centers. Follow-up visits were performed up to 2 years post-implant. The baseline CHA2DS2-VASc score was 3.6±1.6 and the baseline HAS-BLED score was 3.0±1.1. All 42 subjects in the intention to treat (ITT) cohort underwent successful implantation of the LAAC device without any serious complications, achieving the prespecified performance goal. The effective LAAC rate was maintained at 100% from 45 days to 12 months post-implant, achieving the prespecified performance goal. During follow-up, 1 subject died of heart failure, and 3 had ischemic strokes, but there were no cases of hemorrhagic stroke or systemic embolism. All events were adjudicated as unrelated to the WATCHMAN device/procedure by the independent Clinical Events Committee. All 3 ischemic strokes were classified as nondisabling based on no change in the modified Rankin scale score.Conclusions:Final results of the SALUTE trial demonstrated that the WATCHMAN LAAC device is an effective and safe alternative nonpharmacological therapy for stroke risk reduction in Japanese NVAF patients who are not optimal candidates for lifelong anticoagulation. (Trial Registration: clinicaltrials.gov Identifier NCT 03033134)
3 0 0 0 OA 社会ネットワークと社会空間からみた住民の定着過程
- 著者
- 原 真志
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.10, pp.701-722, 1994-10-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 2
都市化した住宅地域で,旧村落時代からの祭り運営が残る大阪府堺市百舌鳥梅北町5丁を対象地域に,自治会加入全世帯についての自治会関連組織に関する行動の分析,および個人単位での社会ネットワーク・社会空間の分析を行ない,地域社会特性と住民の定着の相互関係について考察した.年齢別,性別に分化した自治会関連組織は年齢の両端に位置する子供会・老人会が空間的には限定的であるが幅広い世帯属性を包摂しているのに対し,中間の青年団・秋月会はその逆である.この重層的包摂構造が住民の定着に影響を与えており,早くから社会空間を認知し組織に参加することで自治会全域という地域社会スケールでの定着がうながされる「地域社会型定着過程」と,若い間は組織に参加せず隣組およびその周辺という近隣スケールでの定着がまず進行し,後に社会空間を認知し定着範囲が広がる「近隣型定着過程」という2つの定着過程が生じていると考えられる.
3 0 0 0 OA 学習者主体からことばの市民へ
- 著者
- 細川 英雄
- 出版者
- 言語文化教育研究学会:ALCE
- 雑誌
- 言語文化教育研究 (ISSN:21889600)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.58, 2017 (Released:2018-06-05)
本稿では,人間の学としての言語文化教育学の歴史的な展開として,学習者主体からことばの市民への教育理念の変容を論じた。いわゆるコミュニケーション能力育成が目的化されてきた1970年代から80年代以降,90年代後半から打ち出された言語文化教育の思想は,これまでの言語教育の範疇を超え,ことばと文化の教育を人間科学として捉えようとする,言語教育上のポリティクスだったといえよう。1995年の「学習者主体」提案から20年,教育技術方法主義と文化本質主義に陥った日本語教育を捉えなおすための,自己・他者・社会をつなぐ理論的な枠組みとして,言語能力向上の先に存在する,人間形成の課題としての「ことばの市民」という教育概念の意味とその位置づけを提案し,その社会変革理念がどのように具体的な活動実践と結びついていくかという課題を,言語文化教育学のポリティクスとその実践の方向性として示した。
3 0 0 0 OA インタラクティブなプロジェクションマッピングの実現
- 著者
- 橋本 直己 櫻井 淳一
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.J60-J63, 2013 (Released:2013-01-25)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
We propose an interactive projection mapping that provides ultra-realistic effects by mixing realistic and diverse visual effects with the users interactions. To achieve high quality and real-time generation of the visual effects, we create pre-rendered movies with layered architecture including the target itself, its background, and additional effects. Based on the user's interactions estimated with a depth camera, the movies are superimposed for various visual patterns in real time. These movies are projected on a real space by using common 3D projection mapping techniques, and it feels like the resultant projection is part of the real world. In this research, we implemented a wall breaking game by throwing a virtual and an actual ball at a real wall.
3 0 0 0 OA 漢方薬と心身医学的アプローチが有効であったvulvodyniaの1例
- 著者
- 塚本 路子 村上 正人 松野 俊夫 塚本 克彦 縄田 昌子
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.4, pp.347-351, 2018 (Released:2018-05-01)
- 参考文献数
- 13
女性患者が日常生活に支障をきたしていても羞恥心のために医療機関を受診しづらい症状の一つに外陰部痛がある. 外陰部痛の中でも特に器質的疾患が認められないvulvodyniaは治療に難渋することが多い. 今回われわれは, 漢方薬内服と心理療法が有効であったvulvodyniaの症例を経験した. そこでvulvodyniaの病態と治療について, 漢方医学および西洋医学の視点から心身医学的に考察した. 本症例は, 漢方医学的には腎虚と瘀血の所見がみられ, 八味地黄丸と桂枝茯苓丸が有効であった. Vulvodyniaは西洋医学的には外陰部の血流障害や筋肉の攣縮としてとらえられ, 治療薬として抗うつ薬や抗けいれん薬などが用いられる. またvulvodyniaには今回の症例のように心理療法を含む心身医学的なアプローチも大切である.
3 0 0 0 OA 未知なる可能性ケタス®
- 著者
- 宇野 隆司
- 出版者
- 一般社団法人 国立医療学会
- 雑誌
- 医療 (ISSN:00211699)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.7, pp.407-408, 2008-07-20 (Released:2011-10-07)
3 0 0 0 OA カテコラミン製剤のシリンジ交換に関する研究動向
- 著者
- 斉藤 沙織 城丸 瑞恵
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.4, pp.551-556, 2013-08-31 (Released:2013-10-15)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
カテコラミン製剤のシリンジ交換は,循環動態に影響を及ぼすことがあり,緊張度の高い手技でありながらもスムーズに行う必要があるため,適切な交換方法についての検討が必要と考える。その基礎資料とするため,本稿ではシリンジ交換に関する研究動向を明らかにした。医学中央雑誌を用いて,「シリンジポンプ」「カテコラミン」をキーワードとし,解説を除外した原著論文15 件を対象として内容を分析した。結果は,【医療機器の特性】,【シリンジ交換方法】に大きく分類され,さらに【シリンジ交換方法】は,「シリンジ交換手技」と「シリンジ交換方法の比較検証」に分類された。これらの結果からシリンジ交換方法について,現在まで推奨される方法はいくつかあるが,一般的に標準化されるまで至っていないことが明らかになった。
3 0 0 0 OA 自己同一化された二次元キャラクターに対する視線シフト
3 0 0 0 OA [B43] 『人事興信録』データからの親族ネットワークの可視化
- 著者
- 佐野 智也 増田 知子
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.2, pp.195-198, 2020 (Released:2020-04-25)
- 参考文献数
- 3
「日本研究のための歴史情報」プロジェクトでは、様々な資料のテキストデータ化に取り組み、研究に利用している。本報告では、テキスト処理とその結果の活用事例の一つとして、『人事興信録』の人的ネットワークの可視化について報告する。『人事興信録』は、家族・親戚情報が詳細に記載されている点に大きな特徴があり、これを利用することで、実親子関係やより広い姻戚関係の情報を得ることができる。可視化のための前提作業として、テキストデータからの親の氏名の抽出処理や、採録者との同定処理について紹介する。特に、採録者の同定処理は、他の人事情報資料を扱う際の参考になるものと考えられる。このようなテキスト処理を経て描かれたネットワーク図は、『人事興信録』原典だけでは容易にわからない人的関係性を可視化しており、実際の事例を用いてその有効性を示す。
3 0 0 0 OA サプリメントに関する若年女性向け啓発リーフレット開発の試み
- 著者
- 佐藤 陽子 小林 悦子 千葉 剛 梅垣 敬三
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.5, pp.113-122, 2019-10-01 (Released:2019-11-01)
- 参考文献数
- 26
【目的】サプリメントの不適切な利用や健康被害が懸念されている。そこで,若年女性にサプリメントに関する正しい知識を普及するため,実態調査結果を踏まえた啓発リーフレットを作成し,その有用性を検討する。【方法】2015年10月~11月に女子大学・短期大学生230名を対象にサプリメントに対するイメージ,サプリメント利用状況,性格特性,食物摂取頻度について調査した。サプリメントに対するイメージをクラスタ分析にて分類し,得られたクラスタと有意な関連が認められた項目を主として用い,サプリメントに対するイメージを推測するYes/Noチャートを作成後,Yes/Noチャートを活用した啓発リーフレットを開発した。さらに2017年11月に女子短期大学生190名を対象に,啓発リーフレットのユーザビリティ調査を実施した。【結果】サプリメントに対するイメージは3つのクラスタに分類でき,作成したYes/Noチャートにて,この分類のおおよその推測が可能であった。また,啓発リーフレットによる情報提供は,女子短期大学生のサプリメントについての基本事項の認識を変化させることができた。【結論】本研究にて開発したリーフレットは,対象の女性に興味を持って見てもらえ,認識の変化にも寄与できたことから,サプリメントに対する正しい知識の普及に活用できる可能性が示唆された。
- 著者
- SHIBATA Kiyotaka LEHMANN Ralph
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- pp.2020-032, (Released:2020-04-02)
- 被引用文献数
- 2
Ozone loss pathways and their rates in the ozone quasi-biennial oscillation (QBO) simulated by a chemistry-climate model of the Meteorological Research Institute of Japan are evaluated by using an objective pathway analysis program (PAP). The analyzed chemical system contains catalytic cycles due to NOx, HOx, ClOx, Ox, and BrOx. PAP quantified the rates of all significant catalytic ozone loss cycles, and evaluated the partitioning among these cycles. The QBO amplitude of the sum of all cycles amounts to about 4 and 14 % of the annual mean of the total ozone loss rate at 10 and 20 hPa, respectively. The contribution of catalytic cycles to the QBO of the ozone loss rate is found to be as follows: NOx cycles contribute the largest fraction (50-85 %) of the QBO amplitude of the total ozone loss rate; HOx cycles are the second-largest (20-30 %) below 30 hPa and the third-largest (about 10 %) above 20 hPa; Ox cycles rank third (5-20 %) below 30 hPa and second (about 20 %) above 20 hPa; ClOx cycles rank fourth (5-10 %); and BrOx cycles are almost negligible. The relative contribution of the NOx and Ox cycles to the QBO amplitude of ozone loss differs by up to 10 and 20 %, respectively, from their contribution to the annual-mean ozone loss rate. The ozone QBO at 20 hPa is mainly driven by ozone transport, which then affects the ozone loss rate. In contrast, the ozone QBO at 10 hPa is driven chemically mainly by NOx and the temperature dependence of [O]/[O3], which results from the temperature dependence of the reaction O + O2 + M → O3 + M. In addition, the ozone QBO at 10 hPa is influenced by the overhead ozone column, which affects [O]/[O3] (through ozone photolysis) and the ozone production rate (through oxygen photolysis).
3 0 0 0 OA 共通語アクセントの成因分析
- 著者
- 佐藤 大和
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.11, pp.775-784, 1993-11-01 (Released:2017-06-02)
- 参考文献数
- 13
共通語アクセントの統計的分析結果を報告する。「日本語アクセント」辞典に収録されている約6万語に、語の構造を示す境界記号を付し、計算機に入力して、単語長別、語種別(和語、漢語、外来語等)、及び語構造別にアクセント型を集計した。従来より、語尾から3番目のモーラに核を置くアクセント型(逆3型)が頻度の高い型であることが知られていたが、こうした逆3型などの中高型アクセントは、語の複合によって生じていることを語構造とアクセントの分析結果から明らかにする。また、日本語の基本語彙を構成する4モーラ以下の語に関して、語種別に頻度の高いアクセント型を示し、短い語から長い複合語に至るアクセント型の変遷を考察する。
3 0 0 0 OA 高分子材料のトライボロジー
- 著者
- 竹市 嘉紀
- 出版者
- 一般社団法人 表面技術協会
- 雑誌
- 表面技術 (ISSN:09151869)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.12, pp.562-567, 2014-12-01 (Released:2015-12-01)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 3