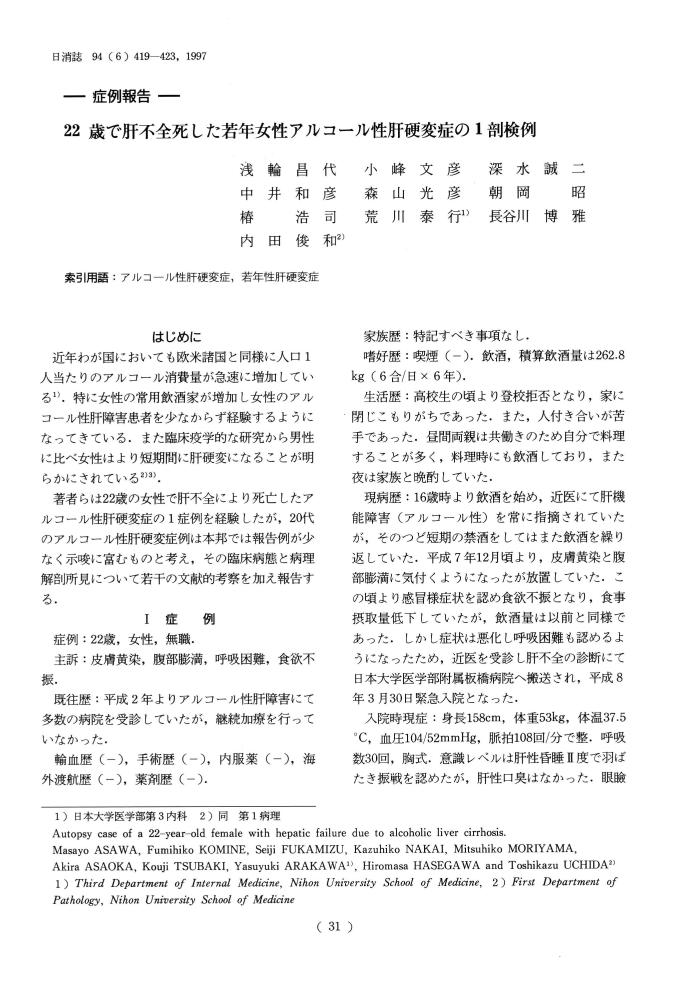- 著者
- 今井 聖
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.141-161, 2021-07-07 (Released:2023-04-08)
- 参考文献数
- 14
「学校の管理下の災害」に対する補償・救済のために,日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度がある。児童・生徒が死亡した場合に,この災害共済給付制度にもとづいて遺族に支給されるのが死亡見舞金という給付金である。 本稿では,〈子ども〉の自殺に対する死亡見舞金の給付はいかになされてきたのか,また,その制度はいかに変化してきたのかを問う。これらの点を問うことで,〈子ども〉の自殺をめぐる補償・救済の論理を検討し,〈子ども〉の自殺と学校の関係についての社会の認識を考察することが目的である。 分析部では,「社会問題の構築主義」の立場から,制度の運用に関わる以下の変化を明らかにする。第1に,1970年代後期,〈小学生〉による学校での自殺事件を契機に,「学校の管理下の災害」としての〈子ども〉の自殺が成立したこと。第2に,〈中学生〉の「いじめ自殺」事件を契機に,「学校の管理下の災害」としての自殺の範囲が拡大したこと。第3に,〈高校生〉の自殺に意志を想定する規定が争点化した結果,〈高校生〉による「故意」による自殺でも例外的に補償・救済の範囲に含まれる場合が見られるようになったことである。 以上の分析知見をもとに,〈子ども〉の自殺をめぐる社会の認識に変化が見られたこと,またそれが〈子ども〉の自殺という社会事象の「学校問題」化の具体的過程であることを論じる。
4 0 0 0 OA 脳卒中患者の治療用装具はありえるか
4 0 0 0 OA 授業秩序はどのように組織されるのか ―児童間の発話管理に着目して―
- 著者
- 松浦 加奈子
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, pp.219-239, 2015-05-29 (Released:2016-07-19)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1 2
本稿の目的は,授業秩序がどのように組織されるのかということを教師による児童間の発話管理という観点から明らかにすることである。本稿ではこれらの目的に対して,授業場面の教師-児童間の実際の活動を記録した映像データを用いて会話分析を行っていく。 本稿は授業秩序を維持するための教師の振る舞いに着目している点において,教師ストラテジー研究と問題関心を共有している。しかし教師ストラテジー研究では想定されてこなかった1対1と1対多のディメンジョンの並存状況を検討している。そして,会話分析を用いて,そこで生じている相互行為の特徴を再記述することで学級の成員が協調して振舞うようになる規則を理解可能な形で見出していく。 分析の中心となるのは,児童の発話に教師が応答することで,児童によって日常会話の順番交替の規則が志向され,授業における課題の組織化が困難になる場面である。その結果,授業進行が停滞し,授業の秩序が動揺していくことになる。それを克服するために,授業場面に適切な「形式」で応答できる者を次の話者として選択し,質問を開始することで,IRE 連鎖を3ターンで完了させ,授業秩序を組織していくのである。
4 0 0 0 公共財供給の新たなモデル構築をめざして : 理論と実験
公共財の存在する経済においては公共財の提供するサービスにただ乗りをする主体が発生するため,パレート効率な配分を達成するのは容易でない.ところが,1977年にグロブズとレッジャードは,彼らのデザインしたメカニズムにおけるナッシュ均衡配分がパレート効率になることを示した.この研究は経済学における70年代の最も輝かしい成果のひとつであった.この後,グロブズ=レッジャード・メカニズムよりも性能のよいメカニズムが数多く開発された.グロブズ=レッジャード以降の研究においては,各主体がメカニズムに参加することを暗黙のうちに仮定していた.しかし,たとえば地球温暖化防止京都議定書のように,議定書には署名はしても批准はしない(メカニズムそのものは認めてもそれには参加しない),という国々が出現している.この問題は地球温暖化防止や平和という国際公共財供給などの国際条約における共通の問題である.我々は,上述のメカニズムに参加するかどうかも戦略変数にとりいれ,理論モデルの構築を行ってきた.残念ながら,すべての主体が参加するようなメカニズムをデザインすることは不可能であるという基本的な不可能性定理を証明している.このことを検証するために実験室にてさまざまな実験を実施した.日本における実験では,参加をせずにフリーライドをする主体を参加者がパニッシュするという行為を通じて,自分の利得が下がるのにも関わらず,ほぼすべての主体が参加するということを観察している.一方,アメリカにおける実験では,進化論的に安定的な均衡という理論の予測どおりに被験者が行動している.この極端に異なる実験結果の分析は今後の課題となろう.
4 0 0 0 OA 遅発性肺損傷を呈した塩素ガス吸入2症例の検討
- 著者
- 山元 良 藤島 清太郎 上野 浩一 宮木 大 栗原 智宏 堀 進悟 相川 直樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本救急医学会
- 雑誌
- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.7, pp.390-396, 2009-07-15 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1 1
塩素ガスへ暴露すると上気道粘膜の刺激症状や急性肺損傷acute lung injury(ALI)などの呼吸器系障害が生じるが,ALI発症までには数時間以上を要するという報告が散見されている。今回我々は,塩素ガス吸入後に遅発性のALIを発症した 2 症例を経験したので報告し,ALI発症までの時間と症状出現から増悪までに要する時間について検討した。症例 1 は26歳の女性で,自殺目的で 3 種類の洗剤を混合し,発生した塩素ガスを吸入した。来院時無症状であったが,受傷10時間後に低酸素血症が出現し,胸部X線撮影・胸部CTで両側肺の浸潤影が出現した。ALIの診断でsivelestat sodium hydrateを投与し,受傷 6 日目に軽快退院した。症例 2 は64歳の男性で,塩素含有化学物質を誤って混合し,発生した塩素ガスを吸入した。来院時より上気道症状や低酸素血症を認めたが,受傷35時間後に病態が増悪し,胸部CTでのスリガラス状陰影の出現を認め,ALIと診断した。ステロイドを経口投与し,PaO2/FIO2 ratioは改善した。本 2 症例の経過と,塩素ガス暴露による症例報告や動物実験の報告から検討すると,症状の出現までに10時間程度の時間を要し,受傷後48時間程度で病態が最も増悪することが予測された。以上より,塩素ガスに暴露した患者では,来院時無症状であったとしても10時間程度の経過観察を行い,有症状の患者に対しては48時間程度の慎重な経過観察が必要と考えられた。
4 0 0 0 OA PM2.5の健康影響と環境基準
- 著者
- 上田 佳代 新田 裕史
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3, pp.253-258, 2011-03-01 (Released:2017-03-18)
4 0 0 0 OA オランダにおける2001年税制改革 ―ボックス課税と給付付き税額控除の導入背景
- 著者
- 島村 玲雄
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.191-210, 2013 (Released:2021-10-26)
- 参考文献数
- 25
オランダにおける2001年税制改革では,3つの所得分類に課税するボックス課税と社会保険料から減免可能な給付付き税額控除を導入した。ボックス3にみなし課税が導入されたことで資本所得の分離課税化が改革の中心として捉えられてきた。しかし,この改革が成立過程においてどのように正当化され成立したのかについては,論じられてこなかった。本稿では,同改革がどのように議論されたのかを政治過程分析から明らかにし,どのような租税制度として結実したのかを制度分析から明らかにすることを試みた。その結果,同改革は労働者に対する租税負担の軽減策こそが改革の主要な課題であり,所得階層ごとへの配慮だけでなく,同時に租税制度の内在的な問題をも克服しようとしたものであることを明らかにする。
4 0 0 0 OA 22歳で肝不全死した若年女性アルコール性肝硬変症の1剖検例
- 著者
- 浅輪 昌代 小峰 文彦 深水 誠二 中井 和彦 森山 光彦 朝岡 昭 椿 浩司 荒川 泰行 長谷川 博雅 内田 俊和
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.6, pp.419-423, 1997-06-05 (Released:2008-02-26)
- 参考文献数
- 13
4 0 0 0 OA 中国からみた日米関係 : 「話語権」概念による一視角
- 著者
- 鎌田文彦
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 日米関係をめぐる動向と展望 : 総合調査報告書
- 巻号頁・発行日
- 2013-08
4 0 0 0 OA ベ平連と女たち ――結成期の長崎ベ平連を中心に――
- 著者
- 港 那央
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.47-61, 2022-10-14 (Released:2023-10-13)
- 参考文献数
- 29
「ベトナムに平和を!」市民連合(以下、ベ平連1 )は、1965年のアメリカによる北ベトナム爆撃に対する抗議運動が世界的興隆を見せるなかで、同年4月に日本で誕生したベトナム反戦市民運動体である(油井 2019、2, 95-105頁)。ベ平連は「個人原理」と呼ばれる方針により、個人の自発性を尊重し、運動内部にはピラミッド型組織に見られるような上下関係をつくらなかった。非暴力を原則とし、会員制度や幹部を設けず、誰でもベ平連を名乗り運動を始めることができた(小熊2009b、312頁 ; 平井 2020、85-86頁 ; 吉川 2011、64-68頁)。以上の運動スタイルが一因となり、最初に結成された東京のベ平連が1974年に解散するまでに、日本各地で数百ものベ平連が誕生した。これらは地域ベ平連と呼ばれる。本稿は、地域ベ平連の一つである、1968年1月末に長崎県長崎市で結成された長崎ベ平連に焦点を当て、長崎ベ平連結成期の中心人物の語りを通して、その人物の運動参加経緯を明らかにしながら、運動のジェンダー化過程を分析することを目的とする。本論に入る前に、先行研究を以下の三点から検討し本稿の課題を示したい。まず、平井一臣(2005)は、それまで主に明らかにされてきたのは東京のベ平連の運動であるため、資料収集やインタビュー調査を行い、地域特性に留意しながら、各地の地域ベ平連の動向を検討したうえで、ベ平連の運動全体を再検討する必要があることを主張した。先行研究の地域的偏向の背景には、語り、記録し、保存し/されえた手記や回顧録が東京のベ平連の「知識人」によるものが多かったことがある。次に、松井隆志(2016)は、東京のベ平連の中心メンバーはほぼ男性であり「そこに時代の限界もあった」(12頁)と注釈にて言及した。つまり、従来のベ平連研究は「東京」の「知識人」の語りを中心に評価してきたと同時に、「男性」の語りを中心とした分析だったのである。これを踏まえて先行する地域ベ平連研究を見ると、黒川伊織(2015)・平井(2005)はそれぞれベ平連こうべ、金沢ベ平連の運動内部でセクシズム告発の動きがあったことに注目している。しかし、両者は各地域ベ平連が向き合う課題の変容・展開を示す複数の例のうちの一つとして挙げているため、告発の経緯や、運動においてセクシズムがなぜ、いかに稼働していたのかを詳細には明らかにしていない。最後に、阿部小涼(2020)は、東京のベ平連のデモの常連でもあった新宿ベ平連の古屋能子が残したさまざまなテクストから、特に「八月沖縄闘争」をめぐって「ベ平連」の運動内外から向けられるセクシズムに抵抗し、記録に残されないと思われる女性たちの闘争を自らが記録しようとも努めた古屋の姿を掘り起こした。「ベ平連」に参加した女性論客や書き手は一定数いたにもかかわらず、その省察が十分になされていないことを指摘し、それらをジェンダー・トラブルとして再読することの重要性を提起したのである。まさに古屋が記録しようと努めたような、そもそも記録されることのなかった無名の女性の闘争、自ら書き残すことのできなかった、あるいは聞き手の不在により語りえなかった無名の女性の思想や行動が、オーラル・ヒストリーの蓄積をともなう地域ベ平連研究によって掘り起こされる可能性を示唆している。本稿は、これらの先行研究では十分に明らかにされてこなかった「地域」「無名性」「女性」に着目し、長崎ベ平連結成期の中心的人物であったK.T. のオーラル・ヒストリーを中心に運動におけるジェンダー化された運動当事者と記録の問題に焦点を当てる。長崎ベ平連結成期の資料は極めて少なく2、特にK.T. が運動に中心的に関わったことを示すもの3 は、警察による尾行や複数回にわたる実家への訪問などといった嫌がらせを受けてK.T. が資料の保存を断念した4 ため、ほとんど残されていない。資料分析はオーラル・ヒストリーに大きく限定されるものの、運動参加当事者・周辺の運動参加当事者へのインタビュー調査5 の実施と、結成期の長崎ベ平連に関わる周辺組織・人びとの記録や報道の分析を行いながら、運動や記録にジェンダーがどのように働きかけたのかを検討したい。
- 著者
- 加納 遥香
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.17-31, 2022-10-15 (Released:2023-10-15)
1954 年のジュネーブ協定によりベトナムは南北に分断された。北部を支配領域とする社会主義体制下のベトナム民主共和国(以下、ベトナム)では、ベトナム労働党が厳重な思想統制を敷く一方で、自国の文化に創出に積極的に取り組んだ。16 世紀末イタリアに起源を持つオペラに関する事業として、文化省は国立のオペラ団であるベトナム交響・合唱・音楽舞踊劇場を設立し、外国のオペラ作品を上演した。さらにベトナムの作曲家ドー・ニュアン Đoች Nhuận(1922–1991)がオペラの形式的特徴に基づいて創作した《コー・サオ Cô Sao》は、ベトナムで初めての「音楽劇 nhạc kịch」として 1965 年に初演された。 本稿では、当時の政策文書、新聞・雑誌記事、楽譜を用いて、1954 年から 1965 年にかけて展開されたオペラに関連する政策、活動、言論を読み解く。それにより、ソ連やフランスといったオペラ大国と密接な関係を持つベトナムが、外来の芸術であるオペラにどのように向き合ったのかという問いに取り組む。ベトナムの対外関係と国際社会に対する対外意識に着目して、ベトナムの音楽家たちのオペラに対する思想や姿勢を照らしだし、同国の国家建設におけるオペラの機能を明らかにする。 ベトナムの政府や音楽家たちは、植民地時代の遺産としてのオペラ劇場や西洋音楽に関する知識、技術、人材を継承し、社会主義諸国の積極的な協力の下でオペラを受容することで、オペラに関する制度を構築し、ベトナムらしさに満ちた自国の作品と共産主義者の方針に沿う新しい言説を創出した。国家建設において、オペラはベトナムが国際舞台にあがるための手段であった。さらにそこで、「音楽劇」という概念を用いることで、冷戦構造の中で、まさにベトナムを舞台として熱戦が始まるこの時期に、ベトナムはヨーロッパ、ソ連、中国などを眼差しながら主体的な国家を構想していた。
4 0 0 0 OA 関与度推定システムを活用したポジティブ作業に根ざした実践の臨床有用性 ─事例報告─
- 著者
- 後藤 一樹 野口 卓也
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.5, pp.678-686, 2023-10-15 (Released:2023-10-15)
- 参考文献数
- 17
本実践の目的は,ポジティブ作業への関与状態を5段階評価できる関与度推定システム(以下,推定システム)を活用したポジティブ作業に根ざした実践(Positive Occupation-Based Practice;以下,POBP)の有用性を検討することであった.方法は,精神障害者2名のクライエントを対象に,推定システムを適用したPOBPを3ヵ月間実施した.介入は,推定システムの結果から推奨されるポジティブ作業を参考にPOBPを展開した.その結果,2事例はポジティブ感情の向上や精神状態の安定に肯定的な影響を示した.これより,本実践は推定システムをPOBPに適用できることを例証できたと考えられる.
本稿では,2014年春から2015年春にかけて自然言語処理の研究者らによって行われたProject Next NLPというプロジェクトを紹介する.本プロジェクトではエラー分析を通じて自然言語処理技術の方向性を考える目的で,ボランティアベースで100名を超える研究者が参加して行われた.自然言語処理で重要な基礎技術,要素技術,応用技術について18個の技術に分け,それぞれの研究している研究者を集い,協調的にそれぞれの分野の技術の分析を行った.分析の方法は各グループに委ねたところ,さまざまな方法での分析が行われ,エラー分析の方法論の研究という側面も持っている.本プロジェクトの紹介により,自然言語処理以外の情報処理分野に対して,エラー分析を通した研究やグループによるエラー分析の重要性が伝わると存外の喜びである.
4 0 0 0 OA 死ぬ権利と死ぬ義務 : 日本、欧米の医療者・生命倫理学者の意識
- 著者
- 小西 恵美子 デービス アンJ
- 出版者
- 日本生命倫理学会
- 雑誌
- 生命倫理 (ISSN:13434063)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.84-91, 2000-09-13 (Released:2017-04-27)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 4
「死ぬ権利」とは、終末期の患者が、さらなる治療を拒否して死を早めることを自らの意思で決定できる権利をさす。「死ぬ義務」とは、終末期の患者や老人は、家族の負担や医療コスト等の社会的要因から、延命のための治療は拒否して死を早める義務があると感じることである。日本、欧米の生命倫理に関心をもつ看護婦、医師および生命倫理学者それぞれ121名、64名を対象に、この二つの概念に対する意識を調査した。結果、死ぬ権利は欧米は全員、日本も大多数が支持した。死ぬ義務については、欧米の支持率は高かったが、日本は支持しない人のほうが多かった。自由記述からしばしば出現したテーマは、「自己決定」、「命の意味」、「公正」、「患者と家族との愛」である。それらの意味の両群の相違点と類似点を探索し、終末医療の問題をかかえる日本と欧米が相互に学ぶ必要を示唆した。
- 著者
- 町田 匠人 真野 洋介
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.1310-1317, 2020-10-25 (Released:2020-10-25)
- 参考文献数
- 14
本研究では新宗教に根ざした都市として天理を取り上げ、天理の都市の誕生から現在までの一連の中心市街地の変容を明らかにすることを目的としている。信者数や宗教施設の建設数など定量的な天理教の教勢の変化は、第二次世界大戦やオウム真理教地下鉄サリン事件などの出来事を境に3つの時期に区分されるが、天理の中心市街地の変容もそれらの時期区分毎に特性が異なるため、本研究では天理の都市の誕生から戦前までを第一期 : 「信者過多期」、戦後から1980年頃までを第二期 : 「都市発展期」、1990年頃から現在までを第三期 : 「教勢衰退期」と定義して、教勢の変化と新宗教都市の変容との関係性を考察している。また、統計資料や地図等の定量的な分析に加えて、商店街歩行者、商店主、宿泊施設経営者等様々な主体に対するヒアリング調査を行うことで、宗教都市の変容を多視点から考察している。結果として、天理の中心市街地は天理教の教勢に牽引されて発展し、天理教の信者も非信者も利用する都市へと発達したことが明らかになった。また近年では天理教の教勢の衰退に伴って宗教に依存するだけの産業は衰退傾向にあることも明らかとなった。
4 0 0 0 OA 韓国語ソウル方言のイントネーション(<特集>諸言語のイントネーション)
- 著者
- 閔 光準
- 出版者
- 日本音声学会
- 雑誌
- 音声研究 (ISSN:13428675)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.16-27, 2007-08-30 (Released:2017-08-31)
This paper presents an overview of the characteristics of intonation in Seoul Korean. After briefly reviewing previous studies on Korean accent and intonation, it describes the intonational characteristics of Seoul Korean with respect to intonational structure, accentual phrase, intonational phrase, declination, focus, syntactic structure, the relationship between accentual phrasing and their related phonological alternation, paralinguistic information and prosodic aspects of dialogue. This paper also introduces K-ToBI, a prosodic transcription convention for Seoul Korean. Finally, it identifies the intonation problems Japanese learners of Korean frequently have difficulty mastering.
4 0 0 0 OA ニューシートピア計画 : 300m実海域実験概要報告
- 著者
- 金田英彦
- 出版者
- 海洋科学技術センター
- 雑誌
- JAMSTEC
- 巻号頁・発行日
- vol.1(1)(創刊), 1989-01-01
4 0 0 0 OA 本州西部における中大型哺乳類3種の堅果類選択性とタンニン収斂性の関係
- 著者
- 大森 鑑能 細井 栄嗣
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.239-247, 2021 (Released:2021-08-26)
- 参考文献数
- 38
ブナ科堅果類は様々な野生動物の秋冬季の重要な食物資源であることが知られているが,被食防止物質としてタンニンを含んでいる.タンニンによる収斂性を測定し,その強さが異なるコナラ属のコナラ(Quercus serrata),クヌギ(Q. acutissima),アラカシ(Q. glauca)及びシイ属のツブラジイ(Castanopsis cuspidata)の4種を用いて,野生の哺乳類を対象にカフェテリア試験を行った.その結果,データ数が少なく断片的であるものの,タヌキ(Nyctereutes procyonoides)は収斂性の比較的強いコナラ属堅果よりも収斂性の弱いツブラジイの採食時間が有意に長かった.タンニンに対して唾液タンパク質などの生理学的な対応策を持つ堅果類消費者も報告されているため,タヌキをはじめとした中大型哺乳類に関しても,生理学的な研究を展開することが望まれる.
4 0 0 0 OA ジョン・カサヴェテス『フェイシズ』論 : 顔,身体,空間
- 著者
- 堅田 諒
- 出版者
- 北海道大学文学研究科
- 雑誌
- 研究論集 (ISSN:13470132)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.141-155, 2018-12-26
本稿ではジョン・カサヴェテス『フェイシズ』(Faces,1968)の作品分析をおこなった。従来の研究では,作家の伝記的事実ばかりが強調され,個々の画面に基づいた「ショット」や「カメラの運動性」の分析はなおざりにされてきた。したがって本稿では画面から出発し,作品のもつ豊饒さに接近したい。第1章では,本作の最も支配的なショット形態である「顔のクロースアップ」の機能と効果を分析した。カサヴェテスの顔=クロースアップは,物質性や触覚性,カメラの機械的な運動性が発露する場であり,とりわけ観客の能動的な見る意志を刺激する。第2章では,身体に目をむけた。『フェイシズ』における顔は,雄弁に何かを語ろうとするものの(たとえば人物の感情),結局何も語らないものであり,一方,身体はその寡黙さゆえに,図らずも主題があらわれる地点となる。「中年と若者」「中年の欲望」などの主題と身体はかかわる。第3章では,空間とコミュニケーションの観点から,顔/身体それぞれを考察した。一階と二階はそれぞれ異なる性質をもち,とくに一階では身体が後景においやられ,反対に顔が前景化することを明確にした。第4章では,映画ラストシーンの階段という中間的な狭間の空間と身体の関係を分析した。この特異な空間に座るリチャードとマリアを分析することにより,映画のいくつかの諸相,空間や時間性の混淆が生じることを明らかにした。階段というカサヴェテス的トポスでは,両極性が混在し,とりわけ身体において過去と未来の時制が呼びよせられ,同時的共存を果たしている,というのが本稿の論旨である。
4 0 0 0 OA 保存期慢性腎臓病患者における筋力値および健常者平均値との比較
- 著者
- 音部 雄平 平木 幸治 堀田 千晴 井澤 和大 櫻田 勉 柴垣 有吾 木村 健二郎
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.6, pp.401-407, 2017 (Released:2017-12-20)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 6
【目的】保存期CKD 患者は腎機能低下に伴い筋力も低下しているが,健常者と比較しどの程度低下しているかは明らかでない。保存期CKD 患者の筋力年齢予測比を明らかにする。【方法】保存期CKD 患者291 例を対象に筋力(握力,膝伸展筋力)を測定し,健常者平均値から筋力年齢予測比を算出した。さらに男女別,年代別の筋力値の比較を行った。【結果】CKD ステージG3a,3b,4,5 の順に,握力年齢予測比は84.4%,85.5%,78.6%,72.3%,膝伸展筋力年齢予測比は104.6%,95.9%,88.3%,84.2% であった。男女別,年代別の筋力値は,高齢女性で低下が顕著であった。【結論】CKD ステージG4,5 の保存期CKD 患者において,握力は健常者平均値の70 ~80%,膝伸展筋力は85 ~90% 程度の低下を示す可能性が示唆された。