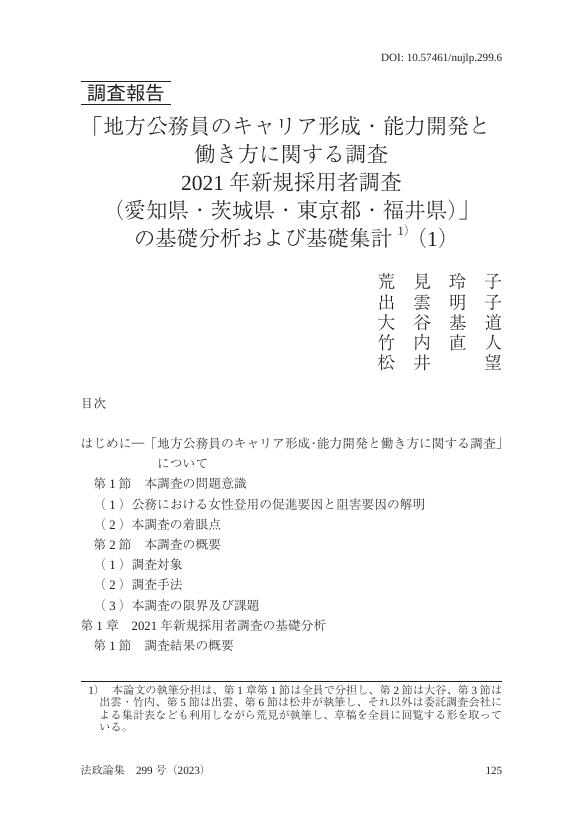- 著者
- 永田 大輔
- 出版者
- 日本メディア学会
- 雑誌
- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, pp.137-155, 2016-01-31 (Released:2017-10-06)
- 参考文献数
- 10
This paper discusses the Video Tape Recorder (VTR) spread process in the 1960s and 1970s. Previous studies on videos have mainly focused on two aspects: (1) sexual media and (2) leisure communities' unique consumption. This paper examines how functions such as slow motion, which were usually used by the leisure communities only were prepared in the first process of family spread. This paper researches the industry paper Video Journal in the period 1968-1978. This industrial magazine has a different focus than that of leisure magazines. This magazine discusses multiple markets in the spread process. This paper will examine each market's demands, according to the industry magazine. From the 1960s to the 1970s the video market was supported by an educational demand. Video was a revolutionary media in audio-visual education. Education has diverse functional needs and feedback regarding these needs can reach the market through study groups. These unique functional demands of leisure groups later spread to family use. In the mid -1970s, Video Journal was conscious of the family market, but its development in this market had been late. First, this may be due to a lack of good content on video. But the true reason is the cost of video recording. Thus, the market could not identify families' needs for a long time, and could not predict the time of family spread. Furthermore, educational needs continued and their demand is left. Both family and educational needs continued and their demand is left. Both family and educational needs did not utilize video functions such as slow motion, which were only used by leisure groups.
- 著者
- 満薗 勇
- 出版者
- 政治経済学・経済史学会
- 雑誌
- 歴史と経済 (ISSN:13479660)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.11-20, 2015-04-30 (Released:2017-08-30)
The theme of this symposium (What Is the Middle Class?) emphasizes the importance of lifestyle and values rather than occupation and income level as the defining components of the middle class. As is well known, the increase in the number of people who regarded themselves as middle class during the period of rapid economic growth after World War II gave birth to the so-called 'all-middle class society' in Japan. It has been shown that their middle-class consciousness derived from a lifestyle and values focused on consumption. This paper therefore focuses on the history of consumption and elucidates the following points. It was in the 1920s-30s that a middle-class model was formed based on consumption levels and patterns rather than on the social prestige or culture associated with occupation and type of employment. Although this model was certainly influenced by that of the USA, its consumption patterns revealed certain Japanese characteristics. For example, Japanese consumers preferred small-scale mom-and-pop retail stores rather than large-scale stores such as GMS. As a result, the commercial sector was able to sustain many self-employed households and to expand business opportunities during rapid growth and thereby to allow the acquisition of sufficient income to meet middle-class consumption levels. Moreover, this model was inextricably linked to the norm of the 'modern family' as a consumption unit. Traditional families changed drastically in these years, for example in the reduced number of children in a household. They willingly accepted birth control and family planning in order to build an affuluent life. At the same time, many married females engaged not only in reproductive activity but in productive activity as well to acquire money sufficient for the middle-class levels of consumption, so that the male-breadwinner family did not in fact become the majority. These women were not entirely happy because they could not take time for housework, child-rearing and leisure. The 'all-middle class society' focused on consumption entailed various conflicts between time and money. From the comparative perspective of this symposium, this type of 'all-middle class society' based on consumption was not formed in contemporary China or India because of differences in historical conditions. Income inequality and family structures give rise to large variations in the consumption levels and patterns in these countries. It is important to take the historical particularity of Japan's 'all-middle class society' into account when considering the Comparison between Developed and Emerging Countries.
4 0 0 0 OA 抗真菌剤の長期使用は歯垢量を減少させる
- 著者
- 木村 陽介 山本 共夫 草塩 英治 前田 伸子
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF ORAL THERAPEUTICS AND PHARMACOLOGY
- 雑誌
- 歯科薬物療法 (ISSN:02881012)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.9-14, 2017 (Released:2017-04-20)
- 参考文献数
- 18
Changes in the amount and physical properties of dental plaques were investigated in the oral cavity in which the oral fungal population was maintained at a low level by the long-term use of an antifungal agent as a mouthwash. For the antifungal agent used as a mouthwash, amphotericin B (AMPH-B), which specifically acts on fungi without influencing bacteria and is unlikely to be absorbed from the oral cavity or gastrointestinal mucosa, was selected. For the index of the fungal level in the oral cavity, Candida indigenous to the oral cavity was selected. We paid attention to time-course changes in the Candida count and the amount of dental plaques and its physical properties observed by palpation using a dental probe and macroscopically.The long-term use of the AMPH-B-containing mouthwash for 4 months or longer reduced the oral Candida count with time, confirming that the count can be maintained at a low level by continued use of the mouthwash. In addition, dental plaques macroscopically decreased as the Candida count decreased, and the physical properties the dental plaques also changed. Although the quantitative and qualitative influences of fungi in the oral cavity on dental plaques have not been investigated, it was clarified that long-term gargling with AMPH-B reduced the oral fungal level, which may have quantitatively and qualitatively changed dental plaques, i.e., microorganisms constituting the indigenous microbial flora in the oral cavity.Dental plaques show latent pathogenicity. In addition to the fact that causative microorganisms of the 2 major oral diseases, dental caries and periodontal disease, are present in dental plaques, the causative microorganisms of aspiration pneumonia, which is a major issue in the elderly, are also present. Thus, reduction of the amount of dental plaques may be beneficial for the health of the oral cavity as well as the whole body.
4 0 0 0 OA 北海道のアイヌ語地名における頻用語
- 著者
- 佐藤 典彦
- 出版者
- Japan Cartographers Association
- 雑誌
- 地図 (ISSN:00094897)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.11-20, 1977-03-31 (Released:2011-07-19)
- 参考文献数
- 14
- 著者
- 林 真範 太田 郁
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.188-195, 2019 (Released:2019-06-20)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 4
【目的】屋内歩行自立が予測される脳卒中片麻痺患者の歩行自立までの期間を予測すること,および交差妥当性を検証し臨床応用が可能か検証すること。【方法】対象は脳卒中片麻痺患者60 名。回復期リハビリテーション病棟入棟時の評価項目を用い,病棟歩行自立までの期間を目的変数とする重回帰分析を行った。得られた重回帰式を用い,入棟時期が独立した脳卒中片麻痺患者19 名で歩行自立までの予測日数と実測日数の有意差を確認し,交差妥当性を検証した。【結果】重回帰式の説明変数として下肢12 段階片麻痺回復グレード,Motor Functional Independence Measure が採択された。入棟時期が独立した集団を用いて予測日数と実測日数を比較した結果,有意差を認めず高い相関を示したことから,当該病院の対象においての交差妥当性が支持された。【結論】当該病院における歩行自立までの重回帰式の構築と臨床応用は可能であることが示唆された。
4 0 0 0 OA カシワモチ,チマキ等の食物に利用する植物(葉)の記録
- 出版者
- 兵庫県立人と自然の博物館
- 雑誌
- 人と自然 (ISSN:09181725)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.127-150, 2007 (Released:2019-03-03)
日本の食生活全集編集委員会(1984 ~ 1992e)などの文献および聞き取り調査によって,大正末期から 昭和初期における植物の葉を包装用材料,食器あるいは調理時の下敷きなどに利用するカシワモチやチマキ などの食物の地域名,利用植物名,材料などの調査を行った.その結果,青森県から沖縄県に至る45 都府 県よりカシワモチ,チマキなどに関する512 の情報を得ることができた.これらの情報を一覧表としてま とめ,伝統的食文化の保存,継続,復活のための基礎資料として報告した.
4 0 0 0 OA 次号特集に向けて
- 著者
- 寿楽 浩太
- 出版者
- 科学技術社会論学会
- 雑誌
- 科学技術社会論研究 (ISSN:13475843)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.103-106, 2015-03-10 (Released:2023-09-11)
4 0 0 0 OA 小児頻用医薬品に関する医薬品添付文書における記載状況の調査
- 著者
- 荒牧 英治 若宮 翔子 岩尾 友秀 川上 庶子 中江 睦美 松本 妙子 友廣 公子 栗山 猛
- 出版者
- 一般社団法人 日本医療情報学会
- 雑誌
- 医療情報学 (ISSN:02898055)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.6, pp.337-348, 2018 (Released:2020-02-28)
- 参考文献数
- 8
急速な医療のIT化と共に,様々な医療情報や医薬品情報が電子化されつつある.しかし,医薬品の適正使用に欠かせない添付文書については表記が統一されているか等の質に関して,これまで体系的な調査は実施されていない.そこでわれわれは,小児領域に着目し,添付文書に小児に関する情報がどのような形で記載されているかを調査した.その結果,小児に対する用法・用量の情報が記載されている割合は添付文書全件の13.5%,小児頻用医薬品についても49.2%にとどまっていることが分かった.特に,詳細な小児区分である低出生体重児や新生児に関しての記述が少ないことが判明した.さらに,添付文書の記述方法についても,年齢区分や安全性,記載場所に曖昧性が存在し,小児医療の現場での医薬品適正使用の障壁となっている可能性が高い.本研究により,今後は添付文書の表現のゆれや曖昧性をなくす等の添付文書自体の質の向上も必要であると考えられる.
4 0 0 0 OA 場所と物語
- 著者
- 土居 浩
- 出版者
- The Human Geographical Society of Japan
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.398-407, 1996-08-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 1 1
4 0 0 0 OA 言説の歴史社会学における権力問題
- 著者
- 赤川 学
- 出版者
- 関東社会学会
- 雑誌
- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, no.15, pp.16-29, 2002-06-01 (Released:2010-04-21)
- 参考文献数
- 15
Do we need the concept of “power” in doing historical sociology of discourse? Three years ago, I described the formation and transformation of discursive space of sexuality, especially masturbation, in modern Japan. While some have analyzed this using the concept of “discursive power” toward children and women, I argue here that such explainations are inadequte by analyzing the transformation of discourse on female masturbation and virginity.
4 0 0 0 OA Beneficial Biological Effects of Miso with Reference to Radiation Injury, Cancer and Hypertension
- 著者
- Hiromitsu WATANABE
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF TOXICOLOGIC PATHOLOGY
- 雑誌
- Journal of Toxicologic Pathology (ISSN:09149198)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.91-103, 2013 (Released:2013-07-18)
- 参考文献数
- 101
- 被引用文献数
- 6 24
This review describes effects of miso with reference to prevention of radiation injury, cancer and hypertension with a twin focus on epidemiological and experimental evidence. Miso with a longer fermentation time increased crypt survival against radiation injury in mice. When evaluating different types of miso provided by different areas in Japan, miso fermented for a longer period increased the number of surviving crypts, and 180 days of fermentation was the most significant. Dietary administration of 180-day fermented miso inhibits the development of azoxymethane (AOM)-induced aberrant crypt foci (ACF) and rat colon cancers in F344 rats. Miso was also effective in suppression of lung tumors, breast tumors in rats and liver tumors in mice. The incidence of gastric tumors of groups of rats given NaCl was higher than those of the groups given miso fermented for longer periods. Moreover, the systolic blood pressure of the Dahl male rat on 2.3% NaCl was significantly increased but that of the SD rat was not. However, the blood pressures of the rats on a diet of miso or commercial control diet (MF) did not increase. Even though miso contains 2.3% NaCl, their blood pressures were as stable as those of rats fed commercial diet containing 0.3% salt. So we considered that sodium in miso might behave differently compared with NaCl alone. These biological effects might be caused by longer fermentation periods.
4 0 0 0 OA 大阪大学医学部学士編入学制度30年の総括
- 著者
- 清原 達也 渡部 健二 野口 眞三郎 青笹 克之
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.259-264, 2005-08-25 (Released:2011-02-07)
- 参考文献数
- 6
今年度で30年目を迎える大阪大学医学部学士編入学制度の成果を総括するために, 学士編入学者のプロフィールと卒後進路について分析を行った. 現在までに通算で453名が入学している. 受験者はバブル期に一時減少したがバブルの崩壊とともに増加した. 入学者のうち男性が93%を占め, 入学時の年齢は30歳未満が82%で24-26歳にピークがあった. 出身大学は国立大学が96%を占めた. 学歴は学士が57%, 修士が36%, 博士が7%. 理科系の専攻が84%であった. 卒後進路としては, 一般学生との比較で学士編入学者の方が基礎医学系に進む割合が高かった. また, 学士編入学者は一般学生と比べて教授や病院長などの管理職を務めている率が高かったが, その一方で開業率も高かった. 卒後20年目以上では, 学士編入学者の勤務先は大学関係が14%で病院関係が44%. 9.6%は教授で7%は病院長, 開業医は27%であった. 以上より大阪大学医学部の学士編入学制度は理科系出身で目的意識が明確で有能な人材を集めて指導的立場にある卒業生を輩出しているとの結果が得られた.
4 0 0 0 OA アメリカのビッグラボでブチ抜くためには。
- 著者
- 中村 斐有
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- MEDCHEM NEWS (ISSN:24328618)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.8-12, 2021-02-01 (Released:2021-05-01)
- 参考文献数
- 1
2018年のサッカーロシアWカップでは日本代表の登録メンバー23人の内、15人が欧州クラブから選出された。2010年の南アフリカWカップでは海外組が4人であったことから考えても、これは驚異的な躍進である。一方、伝統的に化学の強豪国である日本では、古くから博士号取得後またはPh.D.取得を目的に海外の研究機関で働くことが珍しくない。これから海外で留学生活を送られる方もおられるだろう。目的はさまざまだと思うが、重要なのは、サッカー界がそうであるように自分の市場価値を上げてステップアップすること、延いては日本社会そのものの市場価値を上げることではないだろうか。
4 0 0 0 OA 当院におけるデルタ株およびオミクロン株流行期毎の COVID-19 入院症例の特徴
- 著者
- 中山 大 藤原 学 中山 晴夫 中山 文枝 渡邉 聡子 石井 敦
- 出版者
- 一般社団法人 日本病院総合診療医学会
- 雑誌
- 日本病院総合診療医学会雑誌 (ISSN:21858136)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.1-4, 2023-01-31 (Released:2023-05-31)
- 著者
- 清水 基之 田中 英夫 高橋 佑紀 古賀 義孝 瀧口 俊一 大木元 繁 稲葉 静代 松岡 裕之 宮島 有果 高木 剛 入江 ふじこ 伴場 啓人 吉見 富洋 鈴木 智之 荒木 勇雄 白井 千香 松本 小百合 柴田 敏之 永井 仁美 藤田 利枝 緒方 剛
- 出版者
- 国立保健医療科学院
- 雑誌
- 保健医療科学 (ISSN:13476459)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.3, pp.271-277, 2023-08-31 (Released:2023-09-21)
- 参考文献数
- 22
目的:日本の新型コロナウイルス第6波オミクロン株陽性者の致命率を算出し,これを第5波デルタ株陽性者と比較する.方法:2022年1月に7県3中核市3保健所で新型コロナウイルス感染症と診断され届出られた40歳以上の21,821人を,当時の国内での変異型流行状況からオミクロン株陽性者とみなし,対象者とした.死亡事実の把握は,感染症法に基づく死亡届によるpassive follow up法を用いた.2021年8月~9月にCOVID-19と診断された16,320人を当時の国内での変異株流行状況からデルタ株陽性者とみなし,同じ方法で算出した致命率と比較した.結果:オミクロン株陽性者の30日致命率は,40歳代0.026%(95%信頼区間:0.00%~0.061%),50歳代0.021%(0.00%~0.061%),60歳代0.14%(0.00%~0.27%),70歳代0.74%(0.37%~1.12%),80歳代2.77%(1.84%~3.70%),90歳代以上5.18%(3.38%~6.99%)であった.デルタ株陽性者の致命率との年齢階級別比は,0.21,0.079,0.18,0.36,0.49,0.59となり,40歳代から80歳代のオミクロン株陽性者の30日致命率は,デルタ株陽性者のそれに比べて有意に低かった.また,2020年の40歳以上の総人口を基準人口とした両株の陽性者における年齢調整致命率比は0.42(95%信頼区間:0.40-0.45)と,オミクロン株陽性者の致命率が有意に低値を示した.結論:日本の50歳以上90歳未満のCOVID-19第6波オミクロン株陽性者の致命率は,第5波デルタ株陽性者に比べて有意に低値であった.
- 出版者
- 東海国立大学機構 名古屋大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 名古屋大学法政論集 (ISSN:04395905)
- 巻号頁・発行日
- vol.299, pp.nujlp.299.6, 2023 (Released:2023-09-28)
4 0 0 0 OA 高校選択における相対的リスク回避仮説と学歴下降回避仮説の検証
- 著者
- 藤原 翔
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, pp.29-49, 2012-11-30 (Released:2014-02-11)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 7 3
現代日本の高校階層構造は,社会経済的背景と高校選択との関係を明確にしてきたといえる。このような実態を背景として,本稿ではなぜ高校選択の社会経済的格差が生成・維持されるのかについて,Richard Breen and John H. Goldthorpe(1997)の合理的行為理論に基づく相対的リスク回避仮説と吉川徹(2006)の学歴下降回避仮説に注目した。そして,2002年に行われた高校生とその母親に対する社会調査データ(N=545)を用いて,その妥当性を検証した。分析の結果,経済的資源や中学3年時の成績をコントロールしても,親の職業や学歴は高校ランクに対して直接影響を与えていること,また,中学3年時の成績が高校ランクに対して与える影響は,親の職業や学歴によって異なることが明らかになった。加えて,高校タイプ別の職業達成・教育達成の見込みから予測されるパターンにしたがって,親の職業や学歴が高校タイプの選択に影響を与えていることが示された。以上の分析結果から,高校選択の社会経済的格差を説明する上での,相対的リスク回避仮説と学歴下降回避仮説の妥当性が示された。
4 0 0 0 OA 歩行障害のリハビリテーション治療―装具―
- 著者
- 大畑 光司
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.9, pp.735-739, 2018-09-18 (Released:2018-10-29)
- 参考文献数
- 16
脳卒中後片麻痺に伴う歩行障害は日常生活に影響を与える重要な因子の1つである.リハビリテーション治療によって歩行能力を改善させるために,適切な下肢装具の選定とその使用は必要不可欠な因子であるといえる.短下肢装具の一般特性としては,足関節運動(立脚期の最大背屈角度と遊脚期の下垂足の改善)および立脚期の膝関節運動(荷重応答期の膝屈曲角度の増加)の変化による歩行機能の改善が指摘されているが,その変化の程度は継手や装具の形状に影響を受ける.また,現時点では長期的な使用による効果は明確ではなく,治療効果を確立するためにはさらなる検討が必要である.
4 0 0 0 OA ホップの品種改良
- 著者
- 森 義忠
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.6, pp.423-428, 1983-06-15 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 17
ホップの品種改良をすすめるとき, まずビールにとって望ましいホップとは如何なるものかということを考慮しなくてはならない。本稿はホップ以外の酒類原料の品種改良を実施するうえでも示唆される点が多い。
4 0 0 0 OA <特集論文>『今昔物語集』に登場する犬
- 著者
- 永藤 美緒
- 出版者
- 法政大学国文学会
- 雑誌
- 日本文學誌要 (ISSN:02877872)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.42-53, 1998-03-24