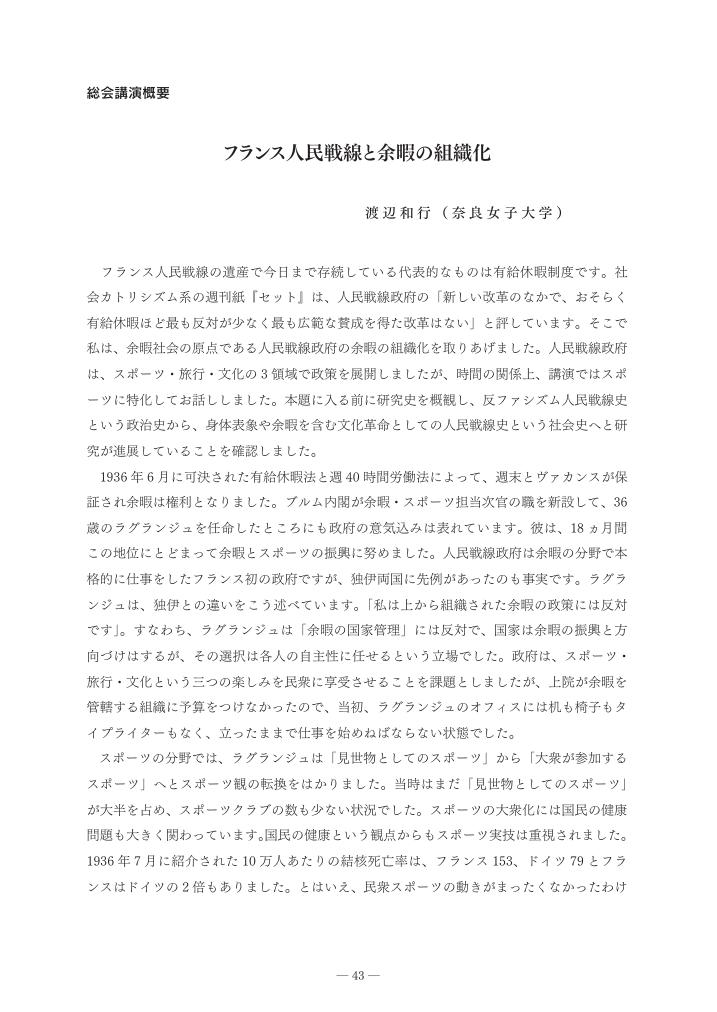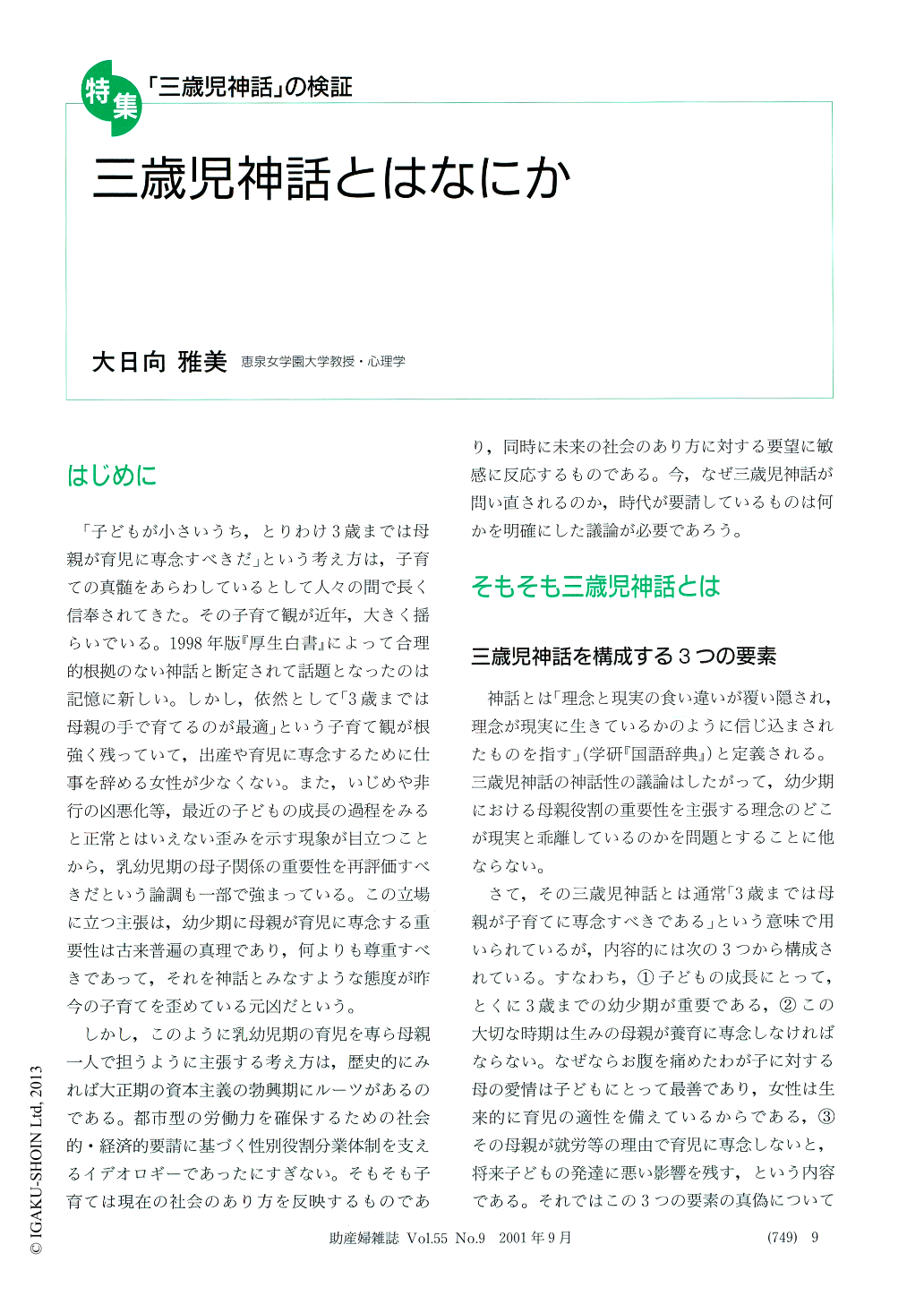4 0 0 0 OA 学会誌50年の記録
- 著者
- 学会誌委員会編集担当委員
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.153, pp.71-80, 2012 (Released:2017-02-17)
本稿では,学会誌の50年を5期に分けて振り返り,その変遷について整理した。 まず,創刊から1972年までの10年間は「日本語教育」という学問を模索した時期と言える。第2期(~1988年ごろ)は,「教育」自体に焦点を当てた研究が多く取り上げられ,「日本語」分野でも現場から出発した具体的な研究が増えた。第3期(~1997年ごろ)には,「心理」や「社会」分野の研究が出始め,「教育」分野の研究は,実践研究が増えた一方,枠組み自体も広がりを見せた。第4期には,更に,関連周辺領域とも結びつき,急速に学際化が進んだ。2004年ごろから現在に至る第5期には,「教育」の研究に,単に問題点の発見に留まらない質の高さが追求されるようになった。また,日本語教育が複合的な領域をまたぐ研究を必要とすることもますます明らかになってきた。今後の研究は,この深化と学際化,双方の面から取り組んでいく必要があると言えよう。
4 0 0 0 OA 総会講演概要 フランス人民戦線と余暇の組織化
- 著者
- 渡辺 和行
- 出版者
- 日仏歴史学会
- 雑誌
- 日仏歴史学会会報 (ISSN:24344184)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.43-45, 2014 (Released:2020-04-02)
- 著者
- 宮原 悠太 敷地 恭子 古谷 裕美 阿座上 匠 原田 美紀 水野 秀一 中村 準二
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
- 雑誌
- 医学検査 (ISSN:09158669)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.331-336, 2014-05-25 (Released:2014-07-10)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
MRSAのバンコマイシン(VCM)MIC測定結果が2 μg/mlの場合,臨床においてVCM治療の失敗する可能性があることが知られている.VCM MIC測定結果は測定方法によって異なることが知られており,マイクロスキャンPos Combo 3.1Jパネル(シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス社)を用いた場合,プロンプト法と基準濁度法の菌液調整方法によって測定結果が異なると報告されている.本研究ではプロンプト法と基準濁度法のVCM感受性測定結果の感度の違いを検討することを目的とした.当院で検出されたS. aureus 91株を対象として,CLSI推奨微量液体希釈法に準拠するドライプレート‘栄研’(栄研化学)の測定結果を基準とし,両法のVCM MIC測定結果を比較した.結果,ドライプレート法を基準とした一致率はプロンプト法が40.7%に対し,基準濁度法は81.3%であった.プロンプト法は基準濁度法よりも高値になる傾向が見られ,VCM MICは基準濁度法を用いて測定したほうが良かった.
4 0 0 0 OA 公共危険犯の現代的意義
- 著者
- 星 周一郎
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.194-207, 2009-02-25 (Released:2020-11-05)
4 0 0 0 OA 学校登山が生徒の自己効力感に及ぼす影響
- 著者
- 大賀 淳子 庄子 和夫 島田 凉子
- 出版者
- 日本心身健康科学会
- 雑誌
- 心身健康科学 (ISSN:18826881)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.77-89, 2018 (Released:2018-11-01)
- 参考文献数
- 51
本研究は,生徒の自己効力感への学校登山の影響について明らかにすることを目的とした.長野県の山への登山を行った2つの中学と2つの高校の生徒(登山参加者531人,登山をしなかった対照群73人)を対象として,登山前,後,1ヶ月後(登山をしなかった対照群では相当時)における自己効力感の測定を行った.また,登山を行った生徒には登山後に,Banduraの4つの情報源,波多野らの5つの条件,および登山での体験に関する質問紙調査を行った.その結果,登山に参加した生徒の自己効力感は登山後に有意に上昇し,1ヶ月後まで保たれていた.これに対して,対照群の自己効力感に変化はみられなかった.また,登山前の自己効力感が低かった生徒のほうが登山による自己効力感の上昇が大きかった.登山における自己効力感の変化への関連要因は「山の自然の印象」,Banduraの「代理的経験」,および波多野らの「他者との暖かいやりとり」であった.したがって,学校登山においては,山の自然に心を動かされることに加えて,友人の頑張る姿から刺激を受けたり,友人との暖かなやりとりを通じて,生徒の自己効力感が上昇すると考えられた.
4 0 0 0 OA 性教育指導観の理解を目指した授業の学習効果 ―ジグソー法を用いて―
- 著者
- 郡司 菜津美
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.67-86, 2022-03-30 (Released:2022-03-30)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 3
本研究では,ジグソー法を用いた性教育指導観の理解を目指した授業の学習効果を検討することを目的とし,2018年,2019年の7月,首都圏A私立大学の2ヶ年分の受講者282名を対象に,授業の前後で質問紙調査を実施した。性教育指導観の変化を検討するため,(1)「性」に対するイメージ,(2)性教育をする理由,(3)性教育による児童生徒の具体的な変化についてKH Coderを用いて分析した。その結果,授業の前後で質問紙に記述された語(恥ずかしい,違い,知識,大人,性など)の共起関係が変わった,つまり同じ単語が異なる文脈の中で用いられるようになった。このことから,学生らに性や性教育に対する捉え方に変化が起こり,学習者から指導者へと認識の変化があったと推察された。また,ジグソー法で課題に取り組む協働の過程の中で,学生は主体的に他者と対話することで学習したと推測できた。つまり,文献の内容をグループのメンバーが個々に理解したというより,対話によってグループでの共同理解に努めたということになる。ジグソー法によって性に関しての学びを頭の中に主知的に構築するのではなく,他者との対話の中でパフォーマティブに意味を構築していたことが推測された。
- 著者
- 尼崎 光洋 森 和代
- 出版者
- 一般社団法人 日本健康心理学会
- 雑誌
- 健康心理学研究 (ISSN:09173323)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.9-21, 2012-03-10 (Released:2013-09-06)
- 参考文献数
- 62
- 被引用文献数
- 2 3
Application of the Health Action Process Approach (HAPA) to condom use behavior in university students was investigated. University students (n = 230: 80 males and 150 females, Mean age 20.39 years, SD = 1.60) completed a questionnaire that inquired about demographic variables, including gender, marital status, sexual history, percentage of condom use, and planning for condom use, as well as social‒cognitive variables that included risk perception, outcome expectancies, preventive behavioral intentions, and action self-efficacy. Structural Equation Modeling with Amos 5 and the Maximum Likelihood estimation method was used to test HAPA. Results indicated that the model fit indices satisfied statistical requirements (GFI = .96, AGFI = .84, CFI = .95, RMSEA = .14). Each pass in HAPA was found to have a positive influence on each variable, whereas risk perception had a nonsignificant effect on intention. These results indicate that HAPA is a valid model for explaining condom use behavior among university students.
4 0 0 0 OA 大学生の性感染症予防に対する意識とコンドームの使用との関係 意識尺度の開発と予測性の検討
- 著者
- 尼崎 光洋 清水 安夫
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.5, pp.306-317, 2008 (Released:2014-07-01)
- 参考文献数
- 54
目的 本研究の目的は,性行動が活発化する青年期の大学生を対象に,性感染症予防を意図した心理・行動科学的な尺度の開発を行うことである。尺度の構成概念として,性感染症予防に効果的であるコンドームの使用に対する意識に着目し,性感染症の感染リスク行動および予防行動という二つの観点から尺度の構成概念の検討を行った。また,開発された尺度によるコンドーム使用行動の予測性について検討を行った。方法 質問紙法による 2 回の調査を実施した。第 1 回目は,2006年 1 月に大学生362人(男180人,女182人)を対象に実施し,第 2 回目は,2007年 1 月に大学生248人(男121人,女127人)を対象に実施した。なお,今回の研究では,異性間の性交による性感染症予防に対する意識を検討するため,異性愛者を分析対象とした。 尺度開発のために,探索的因子分析,ステップワイズ因子分析,検証的因子分析を実施した。また,抽出された各因子に対して,信頼性係数(Cronbach's α)を算出した。さらに,開発された尺度の予測性の検討を行うために,ロジスティック回帰分析による検討を行った。結果 1) 大学生の性感染症予防行動に関する意識尺度(STDASUS)について,探索的因子分析の結果,4 因子(各 5 項目)が抽出され,計20項目構成となった。2) 抽出された項目の精査を行うために,ステップワイズ因子分析を行った結果,4 因子(各 4 項目)の計16項目の尺度が開発された。各因子の α 係数は0.759~0.879であった。3) 構成概念を検証するために,探索的因子分析を実施した調査対象者とは異なる対象者に対して,4 因子16項目の尺度を用いて検証的因子分析を実施した。その結果,尺度全体の適合度を表す指標は,GFI=0.916, AGFI=0.883, CFI=0.948, RMSEA=0.057を示した。4) 最近の性交時のコンドームの使用状況を従属変数,大学生の性感染症予防行動に関する意識尺度を独立変数としたロジスティック回帰分析の結果,統計的に有意な偏回帰係数(β=0.154, P<0.001)が認められた。結論 本研究の結果,4 因子16項目による「大学生の性感染症予防行動に関する意識尺度」が開発された。尺度の信頼性および構成概念妥当性は,十分な適合値を示した。また,本尺度による近時点におけるコンドームの使用の有無の予測性が示唆され,今後のリスク行動および予防行動のアセスメントの可能性が推察された。
4 0 0 0 OA コンドーム購入および使用に関する行動の変容ステージと羞恥感情との関連
- 著者
- 樋口 匡貴 中村 菜々子
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.3, pp.234-239, 2010 (Released:2010-11-05)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 2
This research focused on (a) embarrassment at the time of condom purchase or use, and (b) stages of change (Prochaska & DiClemente, 1983) as psychological factors related to the use of condoms. A written questionnaire was completed by 376 university students. For condom purchases, ANOVAs revealed that scores for “intent of behavior” increased as participants moved from the “precontemplation” stage to the “action” stage. The scores for embarrassment, and many factors of embarrassment, were lower in the “action” stage than in the other stages. However, the patterns of condom use scores were unclear. These results indicate that with regard to condom purchases, persons who are in the “preparation” or earlier stages (i.e., persons who are not purchasing condoms) are particularly susceptible to embarrassment.
4 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1915年04月08日, 1915-04-08
4 0 0 0 OA アルコールを中心として, 栄養障害(ビタミン B1 欠乏症等アルコール関連)
- 著者
- 鈴木 貴浩
- 出版者
- 日本大学医学会
- 雑誌
- 日大医学雑誌 (ISSN:00290424)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.5, pp.309-312, 2018-10-01 (Released:2018-12-01)
- 参考文献数
- 6
Nutritional deficiencies are not uncommon. Therefore, we must understand whether nutritional deficiencies can cause cognitive disorder. Wernicke-Korsakoff encephalopathy (WKE), which occurs as a result of thiamine deficiency, pellagra due to nicotinic acid deficiency, malignant anemia, which occurs as a result of vitamin B12 deficiency, and diabetic coma due to hypoglycemia, can all lead to cognitive disorder. We must treat these disorders at the appropriate time, in order to prevent the cognitive disorder from becoming chronic. In this article, we consider WKE. WKE is a metabolic disease that is treatable, when diagnosed in the early stage. In the general setting, it is difficult to diagnose WKE appropriately. Therefore, we must determine whether this nutrition deficiency can contribute to the development of this treatable cognitive disorder.
4 0 0 0 OA 特許法の先使用権に関する一考察 (2) : 制度趣旨に鑑みた要件論の展開
- 著者
- 田村 善之
- 出版者
- 北海道大学情報法政策学研究センター
- 雑誌
- 知的財産法政策学研究 (ISSN:18802982)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.129-142, 2019-10
4 0 0 0 OA 親鸞聖人における「いのり」の概念-その使用例の考察-
- 著者
- 大谷 光淳
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.517-519, 2005-03-20 (Released:2010-03-09)
4 0 0 0 OA 定期接種化を見据えたおたふくかぜワクチンの安全性について
- 著者
- 中野 貴司
- 出版者
- 日本小児耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 小児耳鼻咽喉科 (ISSN:09195858)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.277-283, 2020 (Released:2021-03-31)
- 参考文献数
- 13
おたふくかぜはムンプスウイルスによる全身感染症であり,無菌性髄膜炎や難聴をはじめとして合併症の多い疾患である。したがって予防することが望ましく,おたふくかぜワクチンは広く接種を促進してゆくことが大切と考えられる。かつてのMMRワクチンによる教訓も踏まえて,定期接種化に向けては弱毒生ワクチンの副反応リスクの評価が必要であり,現在も議論が継続されている。これまでに得られたエビデンスや審議の経緯,呈示された論点を考慮すると,以下の3点が重要と考えられる。①早期からの予防と高い接種率につながり,かつ副反応のリスクが低いと考えられる1歳での初回接種を推奨する。②無菌性髄膜炎の発症頻度に影響をおよぼす因子についての検討は継続する。③重篤な副反応の監視とリスクコミュニケーションに力を注ぐ。
- 著者
- Masaharu Akao Hiroshi Inoue Takeshi Yamashita Hirotsugu Atarashi Takanori Ikeda Yukihiro Koretsune Ken Okumura Shinya Suzuki Hiroyuki Tsutsui Kazunori Toyoda Atsushi Hirayama Masahiro Yasaka Takenori Yamaguchi Satoshi Teramukai Tetsuya Kimura Yoshiyuki Morishima Atsushi Takita Wataru Shimizu
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-23-0143, (Released:2023-07-21)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
Background: This sub-analysis of the ANAFIE Registry, a prospective, observational study of >30,000 Japanese non-valvular atrial fibrillation (NVAF) patients aged ≥75 years, assessed the prevalence of direct oral anticoagulant (DOAC) under-dose prevalence, identified the factors of under-dose prescriptions, and examined the relationship between DOAC dose and clinical outcomes.Methods and Results: Patients, divided into 5 groups by DOAC dose (standard, over-, reduced, under-, and off-label), were analyzed for background factors, cumulative incidences, and clinical outcome risk. Endpoints were stroke/systemic embolic events (SEE), major bleeding, and all-cause death during the 2-year follow-up. Of 18,497 patients taking DOACs, 20.7%, 3.8%, 51.6%, 19.6%, and 4.3%, were prescribed standard, over-, reduced, under-, and off-label doses. Factors associated with under-dose use were female sex, age ≥85 years, reduced creatinine clearance, history of major bleeding, polypharmacy, antiplatelet agents, heart failure, dementia, and no history of catheter ablation or cerebrovascular disease. After confounder adjustment, under-dose vs. standard dose was not associated with the incidence of stroke/SEE or major bleeding but was associated with a higher mortality rate. Patients receiving an off-label dose showed similar tendencies to those receiving an under-dose; that is, they showed the highest mortality rates for stroke/SEE, major bleeding, and all-cause death.Conclusions: Inappropriate low DOAC doses (under- or off-label dose) were not associated with stroke/SEE or major bleeding but were associated with all-cause death.
4 0 0 0 OA 東京市立小学校鉄筋コンクリート造校舎の外部意匠
- 著者
- 藤岡 洋保
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会論文報告集 (ISSN:03871185)
- 巻号頁・発行日
- vol.300, pp.115-123, 1981-02-28 (Released:2017-08-22)
This paper shows the changes of the exterior design of Tokyo municipal elementary school buildings built of reinforced concrete and points out that pursuit of clarity, rather than that of rationalism, is shown in the simple exterior design after 1931 which is characterized by whitish smooth surface with only rectangular windows.
4 0 0 0 OA ピアノ演奏における離鍵速度の重要性と特性に関する考察
- 著者
- 大島 千佳 西本 一志 阿部 明典
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.5, pp.1546-1557, 2006-05-15
以前より演奏表現に関しての研究が行われ,最近ではコンピュータに自動的に人間らしい演奏をさせる研究が行われている.これらの研究では,主に各音の音量や音長をもとに演奏表現を議論してきた.しかし,音楽演奏では「音の切れ方」も表現の一要素として重要である.ピアノ演奏の場合,音の切れ方は「離鍵速度(下におりた鍵盤が元の位置に戻る速さ)」によって表現され,Musical Instrument Digital Interface(MIDI)では,“Note off velocity” として数値的に示される.したがって本論文では,音楽情報科学分野における演奏分析や演奏生成の研究に利用可能な,知識表現を求めるための基礎的な段階として,ピアノの演奏表現における離鍵速度の重要性を示した.まず,音響スペクトログラムと聴取による評価実験により,離鍵速度の変化が演奏表現に影響を与えることが分かった.次に,演奏データを分析したところ,ところどころで際立って離鍵速度が遅い箇所があり,これらの箇所は楽譜上の情報と関係していることが示唆された.さらに度数分布を求めて打鍵速度の特性と比較することで,離鍵速度に示される奏者の知識表現を求めるには,離鍵速度が際立って遅い箇所や速い箇所に注目する必要があることが示された.
- 著者
- 大西 まどか 小田 浩一
- 出版者
- 一般社団法人 照明学会
- 雑誌
- 照明学会誌 (ISSN:00192341)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.10, pp.474-483, 2017-10-01 (Released:2017-12-01)
- 参考文献数
- 36
This study aims to explain as quantitatively as possible the readability of Japanese characters in terms of certain elements in the multi-dimensional, and rather qualitative, space of font design. Based on a review of previous studies, two main dimensions have been selected as the most influential on readability ; the relative character size in the bounding box, which we call style, and the stroke width, which we call weight (when discussed in a categorical way). The Gothic fonts were chosen as the target because they are well known to be the most legible. Behavioral evaluations of readability were conducted instead of subjective judgments. In accordance with the reading acuity measurement MNREAD-J, short and easy-to-read sentences were presented to participants, and the time required to read them aloud was recorded along with any reading errors ; this provided three readability indices. Sentences were rendered in one of 12 different fonts consisting of four kinds of style-Old, Standard, Modern, and UD-times three weight levels-Light, Regular, and Bold. Findings for the style suggest that the enlargement of relative size represents a tradeoff with narrowed inter-letter spacing. This means that good legibility of single letter design may not result in good readability of letters in sentences. However, the weight had a notable effect especially in small sizes. Two readability indices were predicted relatively well by participants’ acuity and stroke width. The effect of stroke width had a ceiling between 10 and 15 % of the letter size.
4 0 0 0 三歳児神話とはなにか
- 著者
- 大日向 雅美
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 助産婦雑誌 (ISSN:00471836)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.9, pp.749-753, 2001-09-25
はじめに 「子どもが小さいうち,とりわけ3歳までは母親が育児に専念すべきだ」という考え方は,子育ての真髄をあらわしているとして人々の間で長く信奉されてきた。その子育て観が近年,大きく揺らいでいる。1998年版『厚生白書』によって合理的根拠のない神話と断定されて話題となったのは記憶に新しい。しかし,依然として「3歳までは母親の手で育てるのが最適」という子育て観が根強く残っていて,出産や育児に専念するために仕事を辞める女性が少なくない。また,いじめや非行の凶悪化等,最近の子どもの成長の過程をみると正常とはいえない歪みを示す現象が目立つことから,乳幼児期の母子関係の重要性を再評価すべきだという論調も一部で強まっている。この立場に立つ主張は,幼少期に母親が育児に専念する重要性は古来普遍の真理であり,何よりも尊重すべきであって,それを神話とみなすような態度が昨今の子育てを歪めている元凶だという。 しかし,このように乳幼児期の育児を専ら母親一人で担うように主張する考え方は,歴史的にみれば大正期の資本主義の勃興期にルーツがあるのである。都市型の労働力を確保するための社会的・経済的要請に基づく性別役割分業体制を支えるイデオロギーであったにすぎない。そもそも子育ては現在の社会のあり方を反映するものであり,同時に未来の社会のあり方に対する要望に敏感に反応するものである。今,なぜ三歳児神話が問い直されるのか,時代が要請しているものは何かを明確にした議論が必要であろう。
4 0 0 0 OA アリストテレスの幾何学観
- 著者
- 田中 裕
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.91-106, 1982-11-13 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 29