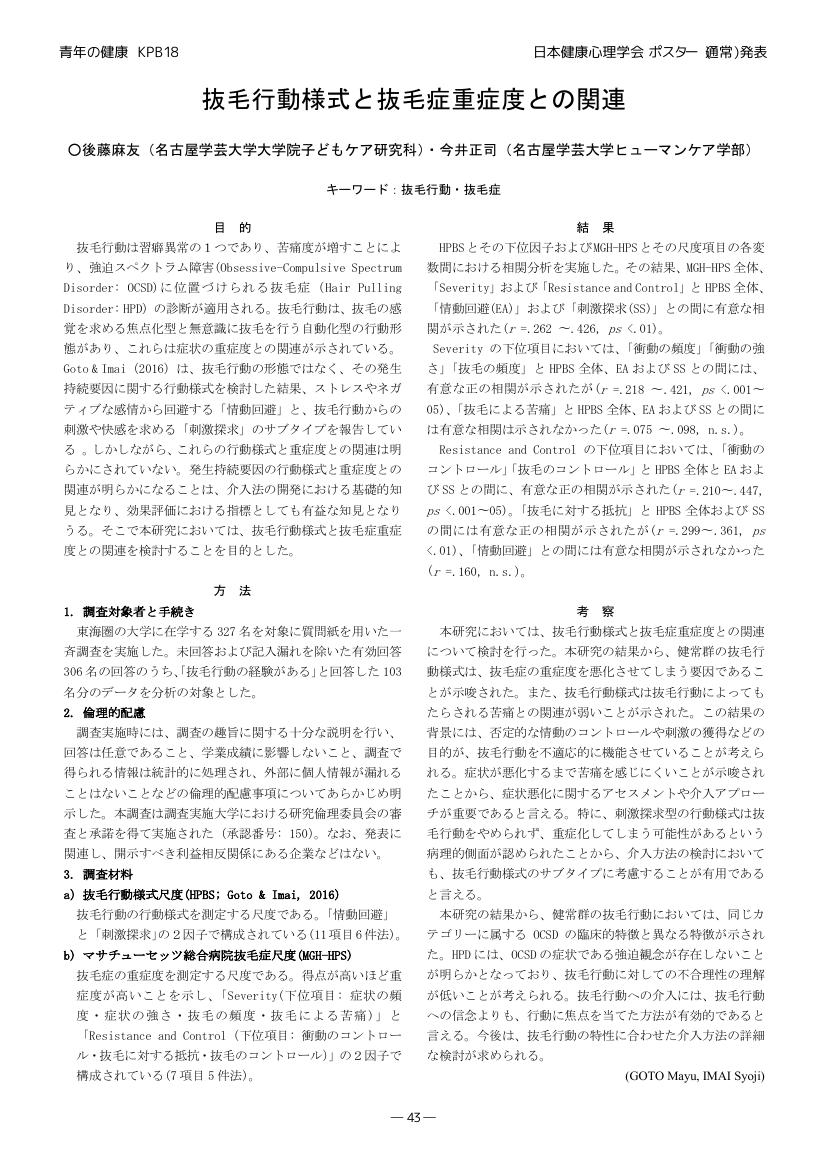2 0 0 0 OA 介護における人的サービスとリスクマネジメント―心の危機管理からの一考察―
- 著者
- 菅原 好秀
- 出版者
- 日本リスクマネジメント学会
- 雑誌
- 危険と管理 (ISSN:09110992)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.160-172, 2014 (Released:2019-12-23)
2 0 0 0 OA ファイナンシャル・リテラシー尺度開発の現状と課題
- 著者
- 神谷 哲司
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.6, pp.651-668, 2017 (Released:2017-02-25)
- 参考文献数
- 155
- 被引用文献数
- 5 5
This paper examines the definitions and measurement scales for financial literacy presented in previous studies in order to develop a new financial literacy scale. The early definition of financial literacy basically meant “financial knowledge,” but the latest definition has been extended to include or refer to consumers’ financial behaviours, consumers’ interactions with their social and economic environments, and the effect of cognitive biases on consumers’ financial behaviours. On the other hand, conventional measurement scales for financial literacy are generally composed of declarative knowledge questions and numerical ability tests concerning personal finance. This paper addresses the fact that previous financial literacy scales have been based on the traditional concept of “Homo economicus”. We suggest that it is necessary to develop a new financial literacy scale that is comprised of critical thinking disposition such as “awareness for logical thinking” or “evidence-based judgment.”
2 0 0 0 OA 鉄門海の思想:『亀鏡志』の分析を中心に
- 著者
- 中村 安宏 鹿野 朱里
- 出版者
- 岩手大学人文社会科学部
- 雑誌
- Artes Liberales = アルテスリベラレス (ISSN:03854183)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, pp.13-31, 2022-06-30
2 0 0 0 OA 日本企業における業績管理の変化と変容 10年分の実態調査データに基づく分析と考察
- 著者
- 桝谷 奎太 岩澤 佳太 吉田 栄介
- 出版者
- 公益財団法人 牧誠財団
- 雑誌
- メルコ管理会計研究 (ISSN:18827225)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.3-20, 2022 (Released:2023-03-07)
- 参考文献数
- 39
本研究の目的は,日本企業における業績管理実践と効果の変化に加え,その背後にある考え方に関する変容の有無や内容,要因について探究することにある。本研究の特徴は,10年分の実態調査データに基づく経時的な分析の実施,得られたデータの深掘り,他の実態調査を参照した統合的解釈にある。分析の結果,2009年から2019年の10年間での業績管理の変化は,資本効率性や貸借対照表を重視した管理への変革というよりも,伝統的な損益計算書中心の管理を計数管理の強化により漸進的に改善するものである可能性や,中長期的な企業価値の向上というよりも短期的な財務業績の向上を目指したものである可能性が示唆された。一部の企業群における変容の兆候も示唆されたが,平均的な調査対象企業においては,業績管理の革新的な変容というよりも,従来の実践の延長線上での漸進的な改善に留まっている可能性がある。本研究は,仮説導出的研究と位置付けられ,実態の説明と将来の研究課題の析出に役立つ。
2 0 0 0 OA 二一世紀に自由民主主義体制は生き残れるか ――正統性の移行と再配置される暴力――
- 著者
- 山崎 望
- 出版者
- 一般財団法人 日本国際政治学会
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, no.194, pp.194_14-194_28, 2018-12-25 (Released:2019-05-16)
- 参考文献数
- 28
The liberal democratic regime, which survived confrontation with the fascist and communist regimes, has spread throughout the world, but with the loss of its enemies, it has acquired the problem of creation of legitimacy and effectiveness by oneself. The crisis of the liberal democratic regime, which is unable cope with this, has been pointed out.In this paper, noting the various countries where the liberal democratic regime has been consolidated, we discuss the transition of legitimacy and the concomitant repositioning of violence through the reconsideration of the various discourses of political theory that point out the transition of legitimacy, an element of the political regime.First, we examine the discourses that have noted the transition of legitimacy in the liberal democratic regime. Specifically, we focus on the articulation of the legitimacy of liberalism and democracy; examine the discourses of 1) the undoing of democracy by neo-liberalism (W. Brown), 2) the crisis of liberalism due to populism, also referred to as the shadow of democracy (J.-W. Müller), and 3) the suspension of liberal democracy due to rules in the state of exception (G. Agamben); and discuss the transition from liberal democracy to another type of legitimacy.Next, we examine discourses that point out the transition of the legitimacy of the sovereign or national state system (international political system), which is a prerequisite of liberal democratic regime. Specifically, focusing on the articulation of the legitimacy of sovereignty and nationalism, we examine the 1) disruption of sovereignty due to racism (M. Wieviorka), 2) ruin of nationalism due to cosmopolitanism (U. Beck), and 3) transformation of legitimacy due to the formation of a new form of polity, ‘Empire’ (M. Hart & A. Negri), and discuss the transition from sovereignty and nationalism to another type of legitimacy.In addition, we discuss the transition of legitimacy based on the articulation of various discourses by dividing them into the three levels of national political regime, international political system, and the level of the intersection of international politics and national politics. Finally, we sketch the repositioning of violence associated with the “triple transition” of legitimacy and discuss the challenges that confront it.
2 0 0 0 OA 食品の窒素-たん白質換算係数について
- 著者
- 堀 光代 青山 頼孝
- 出版者
- The Japanese Society of Nutrition and Dietetics
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.6, pp.297-306, 1991 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 71
- 被引用文献数
- 1 1
2 0 0 0 OA 高速バス運行の機能的変容と高速バスストップ(BS)の設置と使用に関する俯瞰的分析
- 著者
- 家田 仁 岩森 一貴
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.5, pp.I_719-I_730, 2019 (Released:2019-12-26)
- 参考文献数
- 13
高速道路ネットワークが約1万kmにまで拡張され,高速バス輸送は今や年間1億人の輸送人員を担う重要な交通手段となっている.特に新幹線を持たない地域においては短距離から中長距離輸送まで,公共旅客輸送の主役の地位を占めるに到っている.この研究では,高速バス輸送における最も重要なインフラ施設ともいえる高速バスストップ(BS)に着目し,まず創始期の高速バス導入の意図とその後の変容経緯を歴史的に振り返り,それを踏まえてBSの設置タイプ別の整備状況と使用状況を調査し,その特性について交通学的見地から分析して一定の合理性を確認するとともに,地域的偏差特性に着目した考察を通じて,BSの整備と使用に関わる地域政治的もしくは意思決定論的性質の内在性を示唆したものである.
2 0 0 0 OA 戦時体制下の相模原都市建設区画整理事業の成立と展開
- 著者
- 中島 将弘 秋本 福雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画報告集 (ISSN:24364460)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.4, pp.102-105, 2005-04-05 (Released:2022-09-01)
- 参考文献数
- 13
相模原都市建設区画整理事業は新興工業都市建設事業の一つとして実施された。新興工業都市は、戦時体制下に、軍施設を中心とした地方発展、空襲による被害の緩和を目的に、全国に23ヶ所建設された。新興工業都市は、旧都市計画法第13条の公共団体による土地区画整理事業によって建設され、相模原の施行面積は、1,594haと全国最大である。本研究の目的は、相模原都市建設区画整理事業の、①事業計画案の特徴、②事業の進捗と成果を、神奈川県立公文書館に残された神奈川都市計画地方委員会の資料に基き、明らかにすることである。
2 0 0 0 OA 里山の猛禽を支える栽培体系とその地理的差異の解明:農業と生物多様性両立を目指して
本研究では、里山の生物多様性を広域にわたり保全する方策として、里山の象徴種猛禽サシバの生息地保全に農地の栽培体系がどう貢献しているか、気候帯の違う複数地域での解明を目的とした。その結果、サシバ分布北限にあたる北東北では、田植え時期は温暖な関東よりわずかに遅い程度で、サシバはため池の多い農地で繁殖していること、カエル類はため池周辺で高密度に分布していることが明らかになった。サシバ分布南西部にあたる九州中北部では二毛作が盛んで田植え時期が関東より1か月遅く、主な餌生物のカエル類がほとんど生息していなかった。そして、バッタ類の生息する草地がサシバの重要な生息地として機能していることが明らかになった。
- 著者
- 杉村 美佳
- 出版者
- 教育史学会
- 雑誌
- 日本の教育史学 (ISSN:03868982)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.6-22, 2001-10-01 (Released:2017-06-01)
2 0 0 0 IR 祭礼を飾るもの--1つ物の成立と伝播
- 著者
- 福原 敏男
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- no.45, pp.p257-325, 1992-12
- 被引用文献数
- 1
一つ物と称する稚児や人形がお渡りする祭礼がある。従来民俗学ではこれをヨリマシ(憑坐・依坐)・ヨリシロ(憑代・依代)と解釈してきた。それに対して、本稿では近畿・九州地方の事例を中心に検討することによって一つ物を再考する。一つ物は平安末期に畿内の祭礼において、馬長(童)が田楽・王の舞・獅子舞・十列・巫女神楽・相撲・競馬・流鏑馬という当時の典型的な祭礼芸能の構成に組み入れられることによって成立した。その成立の場は、宇治・春日・祇園・稲荷・今宮・日吉などの祭にある。一つ物は中世に畿内の祭礼・法会芸能から各地へ、天台―日吉社系の神事芸能構成の一つとして、あるいは八幡社放生会系の神事芸能構成の一つとして伝播した。各地に土着した一つ物は、中世祭祀組織や宮座が解体・変質すると多くのものは消えていった。一つ物はもともと若者や大人も勤め、その生命は意外性や目立つ趣向にあった。しかし、一つ物は祭という同一の形が繰り返される行為のなかで、芸もなくマンネリ化がすすみ多くのものは飽きられて消えていった。そのなかで、稚児や人形が動員されることによってのみ愛でられ命脈を保ち得た。一つ物は元来神賑であったので行列に参加する宗教的意味は希薄で、近代になって民俗学者により憑坐と解釈された。一つ物の本質が、本来の俗(渡り物の一種)から聖(神霊の憑坐)へと解釈されていき現在の定説となっている。一つ物はその発生の平安期の祭礼において、すでに神輿とともに登場している。神学的にいうなら神は神輿にのって御旅所にお渡りするのに、何故別に憑坐に神を憑らせなくてはならないのだろうか。「一つ物」の「一つ」は、数詞とともに一番という順序の意味もあり、一番最初にお渡りをする、一番目立つ、という二つの意味があるのではないか。一つ物の本質は、渡り物・神幸・神のみゆき(お渡り)・渡御・行列(パレード)における風流なのである。In some festivals, a child or doll called "Hitotsumono" passes in the procession. In folklore, this has been conventionally interpreted as Yorimashi or Yorishiro (an image into which the divine spirit enters). As against this, this paper reviews the Hitotsumono by investigating examples mainly in the Kinki and Kyûshû Districts. The Hitotsumono came into being in the late Heian Period in the festivals of the Kinai Region, when a horse driver (a child) was brought into the framework of then typical festival entertainments, such as Dengaku (ritual music and dancing performed in Shinto shrines and Buddhist temples), O-no-mai (King's Dance), Shishimai (ritual lion dance), Seinoo (Court dance performed at the Kasuga shrine), Mikokagura (shrine maidens' music and dancing), Sumô (wrestling), Kurabeuma (horse racing), and Yabusame (horseback archery). The Hitotsumono appeared in the festivals of shrines at Uji, Kasuga, Gion, Inari, Imamiya, and Hie. The Hitotsumono spread from these festivals in the Kinai Region in the early Middle Ages, to various parts of the country, as one of the entertainments for divine service connected with the Tendai-sect and Hie-Shrine, or as one of the entertainments for divine service connected with the Hachiman-Shrine Hôjôe (Buddhist ceremony in which captured animals and fish are released to fields, mountains, ponds or marshes). Many of the Hitotsumono, which became established in various areas, disappeared when the framework of the festivals of the Middle Ages and the Miyaza (local organizations for festivals) were dissolved, or changed in quality. The Hitotsumono was, originally, performed also by young people and adults, and its existence depended on unexpectedness and eye-catching ideas. However, in the repetition of the same acts in festivals, the Hitotsumono became stereotyped with no special art, and most of them lost popularity and disappeared. Only Hitotsumono which brought a child or a doll into the performance remained in existence. The Hitotsumono was originally a medium, so its participation in a parade had no religious meaning. In the Modern Age, folklorists came to consider it as an image into which the divine spirit enters. The interpretation of the essence of the Hitotsumono shifted from that of its original secular existence (a type of performance in the parade) to a sacred one (an image into which the divine spirit enters); the latter is the commonly accepted opinion at the present. The Hitotsumono already existed in festivals in the Heian Period, together with Mikoshi (portable shrines). From the theological viewpoint, the question is why a god should have to rest on a separate image, though the god passes to Otabisho (the resting place) by a portable shrine? "Hitotsu" of the Hitotsumono is not a cardinal number, but an ordinal number. It seems to have two meanings; the Hitotsumono passes by first, and it is the most conspicuous. The essence of the Hitotsumono is the elegance of the procession, the divine presence, the divine visit, or passage, or parade.
- 著者
- 狩谷 尚志
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.14-27, 2020
<p>本研究は,1940~1950年代にかけて「社会保障制度審議会」を構成した政策主体(アクター)の「自立」言説を再検討することによって,生活保護制度へ「自立」が制度化された背景に,以下の三つの言説上の潮流が存在したことを明らかにした.第一に,労働市場で活動を行い経済的な自助を達成している状態を「自立」と定義する立場.第二に,労働市場もしくは民間社会福祉施設にて,何らかの活動を行っている状態を「自立」としたうえで,個人をそのような場所へと統合する必要を主張した立場.第三に,個人が日常生活を営むうえで必要な所得を備え,特定の施設外での活動を行うことができる自由を有した状態を「自立」と定義した立場である.このような言説分析を踏まえ,「自立」概念の両義性を指摘した.また,各アクターの認識に基づく「自立」概念の歴史的発展と,それらアクターの相互関係による福祉政策の形成という二つの仮説を提示した.</p>
- 著者
- 加藤 一郎
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 教育学部紀要 = Annual Report of The Faculty of Education (ISSN:03882144)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.71-86, 2000-12-01
Unu el la ortodoksaj historiistoj pri la Holokaŭsto, D. Lipstadt en sia verko "Denying Holocaust" severe kritikis la anglan historiiston, D. Irving, kiel "la defendanton de Adolf Hitler" kaj "la neanton de la Holokaŭsto". Kontraŭ tio, D. Irving akuzis ŝin kaj la eldonejon "Penguin books LTD" pro la malhonorado. Tamen, tiu proceso ne restis la personara malhonorada proceso, sed iĝis la tribunalo de la Holokaŭsto, ĉar la diputitaj temoj en la proceso havis rilatojn kun ĉefe la Holokaŭsto, precipe, la koncentrejo de Auschwitz kaj "gasaj ĉambroj". Unu el la gravaj disputitaj temoj estis "la arkitekture criminalaj postsignoj", kiuj pruvas, ke la koncentrejo de Auschwitz estis la eksterma centro uzinta "hommortigajn gasajn ĉambrojn". Bazante sin sur diversaj studoj de "la Holokaŭstaj Revizionistoj", D. Irving konkrete kritikis "la criminalaj postsignoj" prezentitajn de R. J.van Pelt.
2 0 0 0 OA 代数曲線の基本群に関するGrothendieck予想
- 著者
- 中村 博昭 玉川 安騎男 望月 新一
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.113-129, 1998-04-28 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 45
2 0 0 0 IR 祭りのなごり -富山県高岡市C村の獅子舞調査5-
- 著者
- 西島 千尋
- 出版者
- 日本福祉大学福祉社会開発研究所
- 雑誌
- 現代と文化 : 日本福祉大学研究紀要 = Journal of Culture in our Time (ISSN:13451758)
- 巻号頁・発行日
- no.139, pp.21-36, 2019-03-31
本エッセイは,「天狗がつくられる村:富山県高岡市C 村の獅子舞調査」(『現代と文化』第131 号,2015 年),「女がみた男の世界:富山県高岡市C 村の獅子舞調査2」(『現代と文化』第133 号,2016 年),「天狗のきもち,獅子のきもち:富山県高岡市C 村の獅子舞調査3」(『現代と文化』第135 号,2017 年),「祭りのおわり:富山県高岡市C 村の獅子舞調査4」(『現代と文化』第137 号,2018 年)の続編である.2015 年のエッセイでは「天狗をつくる」というC 村の表現を手がかりに獅子舞を含む村の行事へのコミットが自明視されていたことに,2016 年のエッセイでは青年団という組織の限界に,2017 年のエッセイでは獅子舞の学習過程におけるあいまいさに,2018 年のエッセイでは人手不足により休止を迎えたC 村の獅子舞をテーマとした. 本エッセイでは,全国一と言われる富山県の獅子舞状況の変化を把握し,C 村の獅子舞休止の相対的な位置づけを試みる.
- 著者
- 村尾 忠廣
- 出版者
- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.255-259, 2000-07-20 (Released:2010-06-22)
- 参考文献数
- 7
1960年代以降, 音痴に関するおびただしい数の研究論文が発表されてきているが, 日本では90年代に入ってカラオケとの関係で急速に関心が寄せられるようになった.しかし, 欧米におけるこれまでの科学的な先行研究が踏まえられていない.本報告では, まず, 音痴の概念, 現状, 原因, 治療法の4点について先行研究を外観し, その上で, コンピュータを使った視覚フィードバックによる診断と治療法 (SINGAD, VSG) について述べる.
2 0 0 0 IR 日本の雇用,社会システムにおける性差別及び人権について
- 著者
- バックリー 節子
- 出版者
- 国際基督教大学
- 雑誌
- 国際基督教大学学報. I-A 教育研究 = Educational Studies (ISSN:04523318)
- 巻号頁・発行日
- no.62, pp.79-85, 2020-03-31
現在,日本は生活水準向上のため,高度な知識,スキルを必要とする知識基盤,実力主義社会である。 一方,日本では少子高齢化が急速に進み,雇用不足の撤回,高年齢者介護福祉が必須とされる。しかし, 男性中心の雇用,社会システムおいて,女性差別は深刻な問題である。1985 年の雇用機会均等法施行以 来,政府は雇用,社会システムにおける男女平等に全力を尽くしているが,教育の機会均等にもかかわ らず,日本の雇用,社会システムは依然として,男女不平等である。本稿は,まず雇用,社会システム における女性差別問題を明確にする。次に,政府がどのように女性差別問題に取り組んでいるかを探索 する。さらに,心理学的,社会学的立場から,日本女性の社会進出への可能性を探索する。本稿は特殊 文化を持つ日本社会における女性差別問題を論理的に提起し,女性の社会進出を社会の公生及び人権レ ベルで捉えることにおいて,有意義であろう。 Today Japan is a knowledge-based and performance-based society where demonstrating advanced knowledge, information, and skills are critical to success. Meanwhile, Japan is facing a sharp declining of the birthrate as well as societal aging, a combination which causes a labor shortage. In spite of the equal opportunity for education for all in Japan, the labor and social system stressing Japanese traditional gender roles certainly reveals gender inequality. Consequently, labor shortage and gender inequality in the labor and social system is a critical issue. The question is how to change a distorted gender perspective and take action for equity and human rights. Since the Equal Opportunity Law was enacted in 1985, the Japanese government has been striving to attain gender equality in the labor and social system. This paper will 1) clarify the gender issues in the labor and social system; 2) examine the government measures to attain gender equality in Japan; and 3) examine gender equality for equity and human rights from a psycho-sociological perspective. Advanced knowledge, information, and skills are needed to enhance equity in the labor and social system. Furthermore, there is a need for empowering the relationship between men and women that may help them to build a gender-equal society. Without a change of men's consciousness about gender equality, there is no solution. This approach could benefit educators to find ways to attain gender equality and to empower the relationship between men and women in the labor and social system, which could result in attaining human rights in Japan.
2 0 0 0 OA 抜毛行動様式と抜毛症重症度との関連
- 著者
- 後藤 麻友 今井 正司
- 出版者
- 一般社団法人 日本健康心理学会
- 雑誌
- 日本健康心理学会大会発表論文集 31 (ISSN:21898812)
- 巻号頁・発行日
- pp.P43, 2018 (Released:2018-08-14)
2 0 0 0 成龍の初期作品における父子関係の転倒と自作自演の視線
- 著者
- 雑賀 広海
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.4-28, 2018
 本論文は、成龍が主演デビューしてから初監督作品『笑拳怪招』(1979) を手掛けるまでの1970年代香港映画に着目する。成龍に関する先行研究は、監督と主演を兼任する、いわゆる自作自演という点については十分に論じていない。本論文は、『笑拳怪招』を中心とする議論を通して、監督と俳優の関係、または作品内における父と子の関係がどのように描かれているか考察する。<br> 1980年代に黄金期を迎えるまでの香港映画産業では、監督と俳優の間には厳格な封建的関係が結ばれていた。しかし、1970年代の李小龍の登場から独立プロダクションのブームを経て、監督と俳優の父子関係は崩壊していく。それを象徴するのが羅維と成龍の関係性である。だが、『笑拳怪招』に見るのは父子関係の崩壊だけではなく、監督と俳優の間にある境界の曖昧化でもある。この曖昧化は黄金期を特徴づけるものであり、したがって、本作は1970年代末の転換を象徴する重要な作品であるという結論に至った。