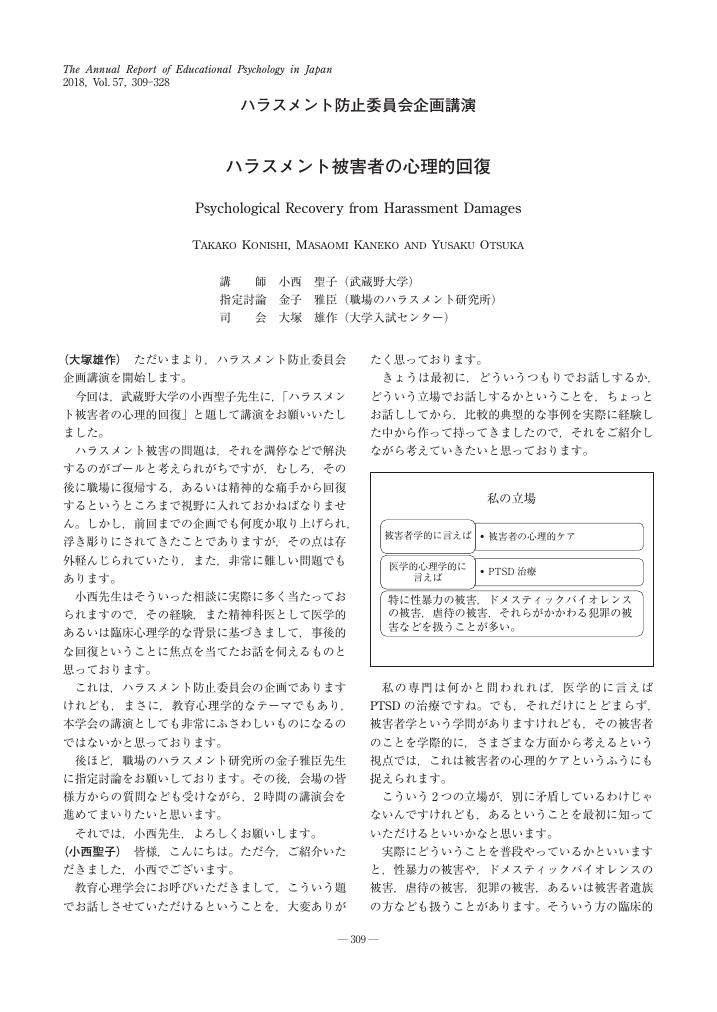57 0 0 0 OA ハラスメント被害者の心理的回復
- 著者
- 小西 聖子 金子 雅臣 大塚 雄作
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.309-328, 2018-03-30 (Released:2018-09-14)
57 0 0 0 OA 新型コロナワクチンと流言・デマの拡散 接種への影響を探る
- 著者
- 福長 秀彦
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.1, pp.2-23, 2022 (Released:2022-02-20)
本稿は、新型コロナワクチンをめぐる流言やデマが、20~40代の人びとの間でどのように拡散し、接種の意思決定にどの程度の影響を及ぼしているのかをインターネット調査によって明らかにしたものである。調査結果は以下の通り。 ■何らかの流言・デマを「見聞きしたことがある」という人が全体の71%に上った。 流言・デマの中で、最も多くの人が見聞きしたのは「接種すると不妊になる」だった。 ■流言・デマを見聞きして「信じた」人が5%、「半信半疑だった」人が42%いた。流言・デマのうち、信じたり、半信半疑だったりした人が最も多かったのは「治験が終わっていないので安全性が確認されていない」だった。この流言を見聞きした人のうち60%が信じたり、半信半疑になったりした。 ■流言・デマを見聞きして、20%の人が家族や他人に「伝えた」。伝えた理由で一番多かったのは「デマかどうかに関係なく、話題として伝えた」で、二番目が「不安な気持ちを共有したかったから」だった。 ■流言・デマを見聞きして、接種を「やめようと思った」人が7%、「見合わせようと思った」人が28%いた。接種を躊躇したのはどのような流言・デマを見聞きしたからかを尋ねたところ「治験が終わっていないので安全性が確認されていない」が最も多かった。 ■流言・デマを見聞きして、いったんは接種を躊躇した人びとが接種する気になったのは、多くの場合「感染への不安」や「同調圧力」によるもので、流言・デマの否定情報による効果は限定的であった。
57 0 0 0 OA 第二回:離散フーリエ変換
- 著者
- 矢田部 浩平
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.5, pp.331-338, 2021-05-01 (Released:2021-06-01)
57 0 0 0 OA 医療現場の行動経済学:意思決定のバイアスとナッジ
- 著者
- 佐々木 周作 大竹 文雄
- 出版者
- 行動経済学会
- 雑誌
- 行動経済学 (ISSN:21853568)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.110-120, 2019-02-15 (Released:2019-02-15)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 1
本稿では,これまでに,医療・健康分野でどのような行動経済学研究の成果が蓄積されてきたかを整理する.本分野の研究は,患者を対象に,以下二つの分類で進められてきた.一つは,患者の意思決定上の行動経済学的な特性が積極的な医療・健康行動を取りやすくしたり,逆に,阻害したりしていることを明らかにする実証・実験研究である.具体的には,リスク回避的な人ほど積極的な医療・健康行動を取りやすいこと,一方で,時間割引率の大きい人・現在バイアスの強い人ほど取りにくいことがさまざまな医療・健康分野で観察されている.もう一つは,患者の行動経済学的な特性を逆に利用して,積極的な医療・健康行動を促進しようとする,ナッジの介入研究であり,実際に,ナッジが患者の行動変容を促すことが,多くの研究で報告されている.さらに,近年の研究動向として,医療者を対象にした行動経済学研究を紹介するとともに,長期的かつ安定的に効果を発揮するナッジの開発の必要性について議論する.
- 著者
- 清水 孜 広鰭 律子 野村 泰子 栗飯原 景昭 宮木 高明
- 出版者
- National Institute of Infectious Diseases, Japanese Journal of Infectious Diseases Editorial Committee
- 雑誌
- Japanese Journal of Medical Science and Biology (ISSN:00215112)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.5, pp.271-279, 1971 (Released:2010-03-19)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1 3
In order to prove sodium toxicity of MSG, baby chicks known to be the most susceptible one to sodium chloride were chosen as the experimental animal. Almost isotonic solution of MSG, NaCl or monopotassium glutamate was given ad libitum as the sole source of drinking water. Two-day old chickens given MSG died of gout within a few days and showed higher mortality and lesions severer than those given physiological saline, while none died nor was weakened among those receiving monopotassium glutamate. Very rapid development of kidney lesions and a large amount of urate deposits were the two main features resulting from MSG ingestion, and primary histological changes were tubular degeneration and tophi obstruction in collecting ducts. Even at half concentration, MSG ingestion caused lobar atrophy in the kidney and some died of gout. Besides sodium toxicity, glutamate counterpart is suspected of contributing to uric acid synthesis.
57 0 0 0 OA 福島第一原子力発電所事故後の食品中のストロンチウム90濃度実態の調査
- 著者
- 鍋師 裕美 堤 智昭 植草 義徳 蜂須賀 暁子 松田 りえ子 手島 玲子
- 出版者
- Japanese Society for Food Hygiene and Safety
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.133-143, 2015-08-25 (Released:2015-09-03)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 13 19
平成23年3月に発生した福島第一原子力発電所事故(以下,原発事故)によって環境中に放出された放射性核種の1つである放射性ストロンチウム(90Sr)の食品中濃度の実態を調査した.その結果,セシウム(Cs)134および137がともに検出され,原発事故の影響を受けているとされた放射性Cs陽性試料(主に福島第一原子力発電所から50 ~250 km離れた地域で採取)では,40試料中25試料で90Srが検出された.一方,134Csが検出下限値未満であり,原発事故の影響を受けていないとされる放射性Cs陰性試料においても,13試料中8試料で90Srが検出された.今回の調査における放射性Cs陽性試料の90Sr濃度は,放射性Cs陰性試料の90Sr濃度や原発事故前に実施されていた環境放射能調査で示されている90Sr濃度範囲を大きく超えることはなかった.本研究の結果からは,放射性Cs陽性試料の90Sr濃度は過去のフォールアウトなどの影響と明確に区別ができない濃度であり,原発事故に伴う放射性Cs陽性試料の90Sr濃度の明らかな上昇は確認できなかった.
57 0 0 0 OA 骨格筋電気刺激の実施頻度の違いが下肢の筋力トレーニングに与える影響
- 著者
- 小泉 美緒 奥村 将之 玉木 彰
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.44 Suppl. No.2 (第52回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0770, 2017 (Released:2017-04-24)
【はじめに,目的】呼吸リハビリテーションにおける下肢の筋力トレーニングのエビデンスレベルは最も高いGrade Aに位置づけられている。しかし,呼吸器疾患患者では呼吸困難感などにより筋力トレーニングに必要な高強度負荷をかけられないという問題がある。そこで近年,骨格筋電気刺激(以下,EMS)が注目されている。これまでにEMSの生理学的効果に着目した先行研究は散見されるが,その効果が現れる実施頻度に関する報告は少ない。そこで本研究では,EMSの異なる実施頻度が下肢の筋厚,筋力,運動耐容能に与える効果を検証し,その効果の差を比較検証することを目的とした。【方法】対象は健常成人男女25名(男性9名・女性16名,年齢:20.3±1.2歳,身長:164.5±7.5cm,体重:56.6±8.2kg)とし,EMS非実施群(Control群)と,EMS実施群を週3日実施群(週3群),週5日実施群(週5群)に無作為に分類した。EMS実施群はベルト電極式骨格筋電気刺激装置を用い,非監視下にて1日1回20分の電気刺激を6週間継続して実施した。強度は対象者の耐えうる最大強度とし,毎回指定の用紙に強度を記入してもらうよう指示した。尚,全ての対象者は6週間のうち最初と最後の1週間の活動量をモニタリングし,日常生活における活動量を統一した。EMS介入前には,超音波診断装置を用い大腿部と下腿部筋厚,等尺性膝関節伸展筋力(膝伸展筋力)及び筋疲労率,体組成などを測定し,さらに運動耐容能として心肺運動負荷試験(CPX)を実施し,6週間後も同様の評価を行った。また,CPXと膝伸展筋力の測定日は別日とした。統計処理は各群のEMS実施前後における各測定値の差を対応のあるt検定で,3群間における各測定値の変化量の差を一元配置分散分析および多重比較にて分析した。さらに,大腿部筋厚と膝伸展筋力の関係をPearsonの相関係数を用いて分析した。有意水準は5%とした。【結果】EMS実施後の大腿部,下腿部筋厚は実施前より週3群,週5群で有意に高値を示した(p<0.05)。また,各群における筋厚の変化量はControl群と比較して週3群,週5群で有意に高値を示し(p<0.05),週3群と週5群間には有意差が認められなかった。EMS実施後の膝伸展筋力は週3群と週5群で有意に高値を示し(p<0.05),膝伸展筋力の変化量はControl群と比較して週3群と週5群で有意に高値を示した(p<0.05)。EMS実施後のpeak Wattと右脚筋肉量は週5群のみ有意に高値を示した(p<0.05)。さらに,大腿部筋厚と膝伸展筋力との間には有意な相関関係が認められた。【結論】6週間のEMSの実施により週3群では筋厚,膝伸展筋力に有意な増加が認められ,その変化量は週5群と比較しても統計学的に有意な差は認めなかった。このことから,EMSは週3日という実施頻度でも十分に下肢の筋力トレーニングとしての効果が得られることが示唆された。
57 0 0 0 OA 量子計算で出来ること・出来ないこと
- 著者
- 森前 智行
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.2, pp.98-101, 2019-02-05 (Released:2019-08-01)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
話題量子計算で出来ること・出来ないこと
57 0 0 0 OA アメリカ外交の規範的性格-自然的自由主義と工学的世界観-
- 著者
- 中山 俊宏
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, no.143, pp.12-27,L6, 2005-11-29 (Released:2010-09-01)
- 参考文献数
- 53
Since it first appeared, Louis Hartz's The Liberal Tradition in America (1955) has had a major impact on the interpretation of American political thought and America's understanding of itself. His aim was to study the logical consequences of naturalized liberalism in the United States and show that ‘ideological consensus’ rather than ‘absence of ideology’ is what defines the uniqueness of America. This essay attempts to apply the concept of ‘natural liberalism’ in understanding the ‘normative character’ of U. S. foreign policy.Hartz has argued that since the United States lacks a feudal past, liberalism is perceived as a natural phenomenon. However, precisely because liberalism is seen in this light, it could sometimes become fixed and dogmatic. The belief that the ultimate moral question of the regime is settled comes from this dogmatic reception of liberalism. Hartz argues that as a result of ethics being taken for granted, all problems emerge as ‘problems of technique.’ He further argues that when the U. S. is simply solving problems on the basis of a submerged and absolute liberal faith, it can depart from liberalism with a kind of ‘inventive freedom’ which others cannot duplicate. This tendency, when applied to international relations, tends to bring about an attitude of mechanically applying its own cultural pattern to the rest of the world. The result is double-edged; the U. S. can become a norm builder as well as a norm destroyer.Hartz argues that interactions with the rest of the world will mitigate the dogmatic nature of naturalized liberalism and will force the United States to realize the relative nature of American exceptionalism. However, contrary to Hartz's expectations, the resulting tendency of the United States' contact with the outside world has been to further reinforce American exceptionalism and strengthen the sense of missionary liberalism.This essay will explore the foreign policy implications of natural liberalism and how these reinforce American exceptionalism. It will show that the United States will act as a norm builder when it can comfortably project its self-image to international relations. This was the tendency immediately after World War II when the United States successfully created the normbased post-war world order. However, the recent tendency has been to act unilaterally, in some cases even neglecting the international norms that the United States itself has played a major role in establishing. This attitude, sometimes referred to as ‘deinstitutionalization of the Wilsonian project, ’ has widened the gap between the United States and the rest of the world. Two domestic trends, namely the increasing religiosity and the conservative turn in U. S. politics has accelerated the widening of the gap. The U. S.' image of itself as a norm builder and the fact that the world no longer sees it so will continue to pose difficult questions for the U. S. and the world.
57 0 0 0 OA 「障がい者」表記が身体障害者に対する態度に及ぼす効果 —接触経験との関連から—
- 著者
- 栗田 季佳 楠見 孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.129-139, 2010 (Released:2012-03-27)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 7 1
本研究では, 近年用いられるようになった「障がい者」表記に注目し, ひらがな及び漢字の表記形態が身体障害者に対する態度に及ぼす影響について, 接触経験との関連から検討することを目的とした。身体障害者に対する態度については, イメージと交流態度の2つの態度次元に着目した。SD法及び交流態度尺度を用いて, 大学生・大学院生348名を対象に調査を行った。その結果, 身体障害者イメージは身体障害学生との交流に対する当惑感を媒介として身体障害学生と交友関係を持つことや自己主張することに対する抵抗感に影響を与えることが示された。そして, ひらがな表記は接触経験者が持つ身体障害者に対する「尊敬」に関わるポジティブなイメージを促進させるが, 接触経験の無い者が持つ尊敬イメージや, 身体障害学生との交流に対する態度の改善には直接影響を及ぼすほどの効果を持たないことがわかった。身体障害学生との交流の改善には「社会的不利」「尊敬」「同情」を検討することが重要であることが本研究から示唆された。特に, 身体障害者に対する「尊敬」のイメージの上昇は, 接触経験の有無にかかわらず, 交流態度の改善に影響を与えることが考えられる。
57 0 0 0 OA 『兵庫北関入舩納帳』の一考察 ―問丸を中心にして―
- 著者
- 徳仁 親王
- 出版者
- 日本学術会議協力学術研究団体 交通史学会
- 雑誌
- 交通史研究 (ISSN:09137300)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.30-55, 1982 (Released:2017-10-02)
57 0 0 0 OA 光アレルギーの発症機序と対策
- 著者
- 戸倉 新樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.5, pp.1006-1012, 2007 (Released:2012-08-02)
- 参考文献数
- 14
光アレルギー機序で発症する疾患には,1)光接触皮膚炎,2)薬剤性光線過敏症,3)日光蕁麻疹,4)慢性光線性皮膚炎(CAD)がある.光接触皮膚炎,薬剤性光線過敏症は抗原となる光感受性物質が明らかであり,その他は明確でない疾患となる.光接触皮膚炎は,抗原が皮膚に塗られて,紫外線が当たって発症し,薬剤性光線過敏症は抗原が薬剤という形で経口投与されて,紫外線が当たって発症する.光接触皮膚炎の原因には,ケトプロフェン,スプロフェンやサンスクリーン薬がある.診断は光貼布試験が決め手となる.薬剤性光線過敏症の原因には,ニューキノロン,ピロキシカム,降圧利尿薬,チリソロール,メチクランをはじめとして多くの薬剤がある.日光蕁麻疹は日光照射により膨疹が生ずる疾患である.CADは,外因性光抗原を原因としない自己免疫性光線過敏症と呼ぶべき疾患で,時にHIV陽性者,ATL患者に発症する.
- 著者
- Masahiro Yano Tomoaki Morioka Yuka Natsuki Keyaki Sasaki Yoshinori Kakutani Akinobu Ochi Yuko Yamazaki Tetsuo Shoji Masanori Emoto
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- pp.9004-21, (Released:2022-02-08)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2 38
During the ongoing coronavirus disease 2019 (Covid-19) pandemic, it is critical to ensure the safety of Covid-19 vaccines. We herein report a 51-year-old Japanese woman who developed acute-onset type 1 diabetes with diabetic ketoacidosis six weeks after receiving the first dose of a Covid-19 mRNA vaccine. Laboratory tests indicated exhaustion of endogenous insulin secretion, a positive result for insulin autoantibody, and latent thyroid autoimmunity. Human leukocyte antigen typing was homozygous for DRB1*09:01-DQB1*03:03 haplotypes. This case suggests that Covid-19 vaccination can induce type 1 diabetes in some individuals with a genetic predisposition.
57 0 0 0 OA 強化学習を用いた依存症の計算論的精神医学研究
- 著者
- 加藤 郁佳 下村 寛治 森田 賢治
- 出版者
- 日本神経回路学会
- 雑誌
- 日本神経回路学会誌 (ISSN:1340766X)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.52-64, 2022-06-05 (Released:2022-07-05)
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 1
本稿では,強化学習を用いた依存症の計算論的精神医学研究について紹介を行う.依存症は,物質の摂取や高揚感を伴う行為などを繰り返し行った結果,それらの刺激を求める耐えがたい欲求や,得られないことによる不快な精神的・身体的症状を生じ,様々な損害を引き起こしてもやめられない状態に陥る重大な精神疾患である.この疾患の理解と治療法開発のために,臨床研究による病態の解明やマウスなどを用いたモデル動物によるメカニズムの解明が進められているが,本稿ではそれらの知見を元にして数理モデルを構築する研究アプローチを取り上げる.まずは導入として筆頭著者らが開発した計算論的精神医学研究データベースの使用例を示しつつ,主眼である依存症研究においてどのような数理モデルが多く用いられてきたのかについて分析する.その後,最もよく研究されている強化学習を用いた依存症の行動的特徴に関する具体的な研究の流れを紹介する.最後に,筆者らが最近提案した,非物質への依存(ギャンブル・ゲームなど)にも適用可能な計算論モデルの一例として,successor representation(SR)と呼ばれる状態表現を用いた依存症の計算論モデルを紹介する.今回紹介する研究は強化学習過程における状態表現に着目しており,不十分な状態表現を用いることで適応的でない報酬獲得行動につながるという観点を提示し,物質/非物質に共通する依存のメカニズムの解明などに寄与することが期待される.
57 0 0 0 OA アニメ作品の集約的なデータ整備における課題
- 著者
- 大坪 英之
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.20-24, 2022-02-01 (Released:2022-03-22)
- 参考文献数
- 14
現在日本においてアニメ作品は日々大量に制作されていることは異論がないが、しかし、どのような作品が公開されたり、過去にどのようなパッケージが販売されていたのかは十分に明らかではない。また、それら作品制作/製作に関わったスタッフ等については、公開されている情報の中でも内容の信憑性が保証されたものは限られている。現在公開されている情報のうち、どこまでが信用できるのか、それはなにに依拠しているのか、現在進行形で対処している事はなにか、問題解消を阻む障壁はなにかについて明らかにする。
- 著者
- 安宅 和人 チェン ドミニク 山口 高平 山本 勲
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.12, pp.865-881, 2018-03-01 (Released:2018-03-01)
人工知能に関して第一線で活躍している4人をパネリストに招いて,トークセッションを開催した。セッションのテーマは「AIとは何か」「AIによって人間の仕事はどう変化するのか」「これから身に付けたい能力」「若者への提言」などである。パネリストの発言はAIの真実やAIの現状を知り,AIとの付き合い方を考える大きな手がかりとなる。
57 0 0 0 小笠原諸島における撹乱の歴史と外来生物が鳥類に与える影響
- 著者
- 川上 和人
- 出版者
- 日本鳥学会
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.237-262, 2019-10-25 (Released:2019-11-13)
- 参考文献数
- 149
- 被引用文献数
- 2 7
小笠原諸島は太平洋の北西部に位置する亜熱帯の海洋島である.小笠原の生態系は現在進行中の進化の過程を保存するとともに高い固有種率を示しており,2011年にユネスコの世界自然遺産に登録された.しかし,1830年から始まった近代の入植により,森林伐採や侵略的外来種の移入などが生じ,在来生物相は大きな影響を受けている.小笠原では2種の外来種を含む20種の陸鳥と21種の海鳥の繁殖が記録されている.このうち7種の固有種・亜種が絶滅し,5種の繁殖集団が諸島から消滅している.絶滅の原因は,主に生息地の消失,乱獲,侵略的外来種の影響と考えられるが,特に外来哺乳類の影響が大きいと考えられる.小笠原諸島にはこれまでに10種の外来哺乳類が野生化しているが,このうちヤギ,イエネコ,クマネズミ,ドブネズミ,ハツカネズミが現存し,その生態系への影響の大きさから駆除事業が行われている.ヤギは旺盛な植食者であり,移入先ではしばしば森林の草原化,裸地化を促し,土壌流出を生じさせる.小笠原諸島では特に聟島列島でその影響が大きい.また,ヤギが歩き回ることで海鳥の営巣が撹乱される.ヤギは過去に20島に移入されたが,父島以外の島では根絶されており,海鳥の分布拡大が見られる.鳥類の捕食者となるネコは8島に移入され,現在は有人島4島に生残する.父島では山域のネコの排除が進み,アカガシラカラスバトColumba janthina nitensが増加している.ネズミは小笠原諸島のほとんどの島に侵入しており,無人島では駆除事業が進められている.根絶に成功した島では鳥類相の回復も見られるが,再侵入や残存個体の増加が生じている島も多い.外来哺乳類の駆除後には,想定外の生態系の変化も見られている.ヤギ根絶後には抑制されていた外来植物の増加が生じている.ネコ排除後にはネズミが増加している可能性がある.ネズミの駆除後は,これを食物としていたノスリButeo buteo toyoshimaiの繁殖成功の低下が見られている.複数の外来種が定着している生態系では,特定の外来種を排除することは必ずしも在来生態系の回復につながらない.このような影響を緩和するためには,種間相互作用を把握し外来種排除が他種に及ぼす影響を予測しなければ,保全のための事業がかえって生態系保全上の障害になりかねない.このため,外来種駆除を行う場合は複数のシナリオを想定し,生態系変化モニタリングに基づいて次のシナリオを選択し順応的に対処を進めていく必要がある.
- 著者
- 石垣 智也 尾川 達也 宮下 敏紀 平田 康介 岸田 和也 知花 朝恒 篠宮 健 市川 雄基 竹村 真樹 松本 大輔
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- pp.11957, (Released:2021-02-10)
- 参考文献数
- 24
【目的】在宅環境での2 ステップテストの信頼性と妥当性の検討を行い,歩行自立の基準値を見出すこと。【方法】訪問リハビリテーション利用者を対象とした横断調査のデータベース(10 施設226 名)から,目的別にデータを抽出した(信頼性98 名,妥当性117 名,基準値209 名)。調査項目は基本情報と膝伸展筋力,歩行能力として2 ステップテストによる2 ステップ値や歩行自立度などとした。歩行手段と距離により屋内杖歩行から屋外独歩800 m 以上と12 種の歩行自立条件を設定し,各自立を判別するカットオフ値を検討した。【結果】2 ステップテストの検者内信頼性は良好であり,固定誤差は認めないが比例誤差が示された。2 ステップ値は膝伸展筋力より歩行能力との相関係数が高く,歩行自立条件に応じた段階的なカットオフ値が設定できた。【結論】2 ステップテストは在宅環境でも信頼性と妥当性があり,歩行自立に対する基準値を有する歩行能力評価である。
57 0 0 0 OA 学会事務センターの破綻とその後(<特集>20周年記念)
- 著者
- 小柳 義夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用数理学会
- 雑誌
- 応用数理 (ISSN:24321982)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.3-5, 2011-03-25 (Released:2017-04-08)
57 0 0 0 「県外の人に伝えたいこと」に見た福島の誇り
- 著者
- 服部 美咲
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.5, pp.299_1, 2022 (Released:2022-05-10)