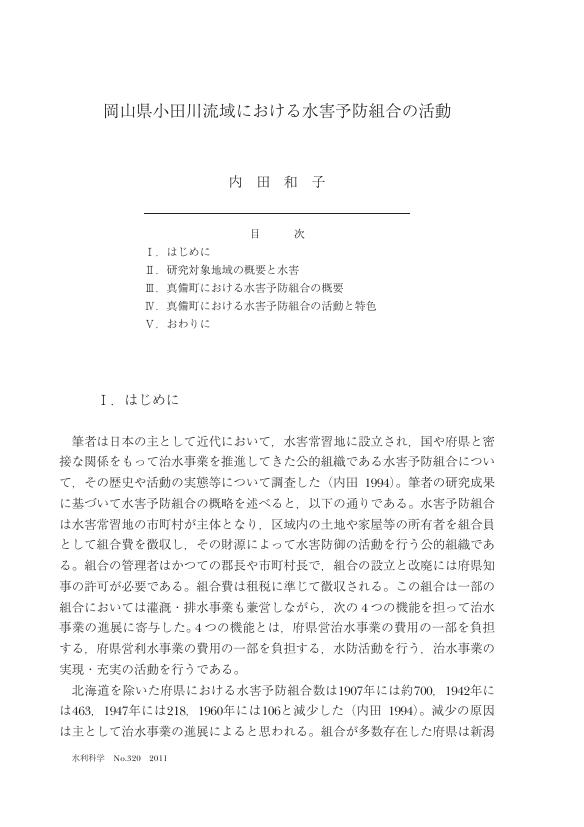164 0 0 0 OA Comparison of the Filter Efficiency of Medical Nonwoven Fabrics against Three Different Microbe Aerosols
- 著者
- NORIKO SHIMASAKI AKIRA OKAUE RITSUKO KIKUNO KATSUAKI SHINOHARA
- 出版者
- The Society for Antibacterial and Antifungal Agents, Japan
- 雑誌
- Biocontrol Science (ISSN:13424815)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.61-69, 2018 (Released:2018-06-16)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 6 12
Exact evaluation of the performance of surgical masks and biohazard protective clothing materials against pathogens is important because it can provide helpful information that healthcare workers can use to select suitable materials to reduce infection risk. Currently, to evaluate the protective performance of nonwoven fabrics used in surgical masks against viral aerosols, a non-standardized test method using phi-X174 phage aerosols is widely performed because actual respiratory viruses pose an infection risk during testing and the phage is a safe virus to humans. This method of using a phage is simply modified from a standard method for evaluation of filter performance against bacterial aerosols using Staphylococcus aureus, which is larger than virus particles. However, it is necessary to perform such evaluations based on the size of the actual pathogen particles. Thus, we developed a new method that can be performed safely using inactivated viral particles and can quantitate the influenza virus in aerosols by antigen-capture ELISA (Shimasaki et al., 2016a) . In this study, we used three different microbial aerosols of phi-X174 phage, influenza virus, and S. aureus and tested the filter efficiency by capturing microbial aerosols for two medical nonwoven fabrics. We compared the filter efficiency against each airborne microbe to analyze the dependency of filter efficiency on the microbial particle size. Our results showed that against the three types of spherical microbe particles, the filter efficiencies against influenza virus particles were the lowest and those against phi-X174 phages were the highest for both types of nonwoven fabrics. The experimental results mostly corresponded with theoretical calculations. We conclude that the filter efficiency test using the phi-X174 phage aerosol may overestimate the protective performance of nonwoven fabrics with filter structure compared to that against real pathogens such as the influenza virus.
164 0 0 0 OA 長野県上田市の中部中新統伊勢山層から産出したポリメリクチュス属魚類化石
- 著者
- 鈴木 秀史
- 出版者
- 地学団体研究会
- 雑誌
- 地球科学 (ISSN:03666611)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.3, pp.129-139, 2022-07-25 (Released:2022-09-02)
- 参考文献数
- 59
長野県の北部フォッサマグナ別所層に相当する上田市北部の中部中新統伊勢山層からミズウオ類の頭部の化石が発見された.口蓋骨歯の特徴に基づいて化石標本と現生同類との比較・検討を行った結果,化石はヒメ目ミズウオ亜目( Aulopiformes, Alepisauroidei)に属するポリメリクチュス科ポリメリクチュス属の一種であることが判明した.同属魚類化石の報告は国内では約 50年ぶりで世界では 5例目となる.今回の発見によりポリメリクチュス属は 15.1~13.1 Ma(Langhian)か,あるいは 15.1~12.6 Ma(Langhian~ Serravalian)までほぼ連続的に生存していたことが示唆される.他の産出層準の堆積環境とも比較すると同属は深海から浅海にかけての移動域をもつ中深層遊泳性か,あるいは,浅海性である可能性が考えられる.ポリメリクチュス属は日本近海では少なくとも 15.1~12.6 Ma(Langhian~ Serravalian)の暖流影響下の深海域に広く点在し,前期中新世の内山期には北部フォッサマグナの南方で南に開いていた古太平洋の深海域にも生息していた.古太平洋には現在と類似する太平洋型の魚類群集が存在し,ポリメリクチュス属はそのメンバーの一員だった.前~中期中新世の内村期になると,当時陸だった北部フォッサマグナ地域は急激に沈降し,太平洋と日本海をつなぐ中部漸深海帯以深の連絡水道が形成され,古太平洋からポリメリクチュス属や深海性魚類が表層暖流や低層水とともに徐々に北上してきた.上田地域は深海水道の中央にあたり,そこでポリメリクチュス属を含む魚類は新たな生息域を獲得し,他の暖流系浅海性魚類とともに太平洋型の魚類群集を形成していった.
164 0 0 0 OA アウトカムを見直す1
- 著者
- 大生 定義
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.6, pp.1247-1248, 2007 (Released:2012-08-02)
- 参考文献数
- 7
164 0 0 0 OA 規程を中心にしてみる我が国の鉄道保線の歴史
- 著者
- 田中 鉄二 樋口 輝久 馬場 俊介
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D2(土木史) (ISSN:21856532)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.38-48, 2011 (Released:2011-10-20)
- 参考文献数
- 64
- 被引用文献数
- 1 3
日々軌道を検査し,線路に発生する様々な異常を整備することが保線作業であり,保線なしで安全で快適な鉄道運転は成り立たない.輸送量の増加,速度の向上,使用機械及び材料の変化,さらには,鉄道事故や戦争の影響によって保線は変化し続けてきた.そこで本論文では,保線を行う際の規範となり,鉄道創業時から制定され続けている“規程”に着目し,鉄道創業時から国鉄の分割民営化後までの鉄道保線の変遷を明らかにしようとする.対象とした組織は,官設鉄道,国有鉄道そしてJRで,民営鉄道は除いている.まず,規程についての概略を述べた上で,保線に影響を与えた重要な出来事について整理し,作業,材料(レール,枕木,道床,分岐器)に区分して,その変遷を明らかにした.
164 0 0 0 OA 計測的特徴からみた西日本古墳人頭蓋形質の地理的勾配
- 著者
- 土肥 直美 田中 良之
- 出版者
- The Anthropological Society of Nippon
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.3, pp.325-343, 1987 (Released:2008-02-26)
- 参考文献数
- 64
- 被引用文献数
- 2 3
周知のように,北部九州地方は,金関の"渡来混血説"によって,弥生時代の開始期に朝鮮半島からの移住があったとされる地域である(金関,1976).この金関の説に従うならば,北部九州は,弥生時代における渡来遺伝子の影響が最も強かった地域と考えられる.そして,これらを支持する成果も,人類学•考古学双方から得られつつある(池田,1982;埴原,1984;山口,1982;永井,1985;尾本,1978;小田,1986;下条,1986;田中,1986).したがって,古墳人形質の地理的変異は,弥生時代以来の混血による遺伝子拡散の過程とみることができよう.我々はこれらの成果を踏まえた上で,さらに,北部九州を中心とする渡来遺伝子の動き,すなわち,より詳細な渡来の実態について形質人類学的立場からのアプローチを試みた.資料は,主として九州大学所蔵の古墳人頭蓋であるが,既報告のデータもできるだけ収集し,併せて使用した.計測はマルチンの計測法(Martin & Saller,1957)および顔面平坦度(山口,1973)について行い,地理的変異をみるために主成分分析を適用した.また,北部九州からの拡散過程をみるために,渡来的形質の分布パターンと北部九州からの距離との関係を, single step migration モデル(Hiorns & Har-rison,1977)との対比において考察した.結果は,マルチンの計測値•顔面平坦度ともに,北部九州における渡来遺伝子の強い影響を支持した.特に,マルチンの計測値については,第1主成分のスコアと筑前から各群までの距離の関係から,北部九州を中心とする渡来的形質の地理勾配が再確認された.この地理勾配には明らかな方向性が認められたが,筑前を起点として描くカーブはルートによって異なる.すなわち,1)筑後•肥前および豊後を経て南九州に至るルートは,急激な fa11-off curve を描く.これは,弥生人において金隈から大友を経て西北九州へと至るカーブと同様である.2)北豊前から南豊前•豊後を経て南九州に至るルートは,緩やかな fal1-off curve を描く.これらに対して,3)北豊前•西瀬戸内を経て中部瀬戸内に至るルートは直線をなし,山陰を経て近畿へと至るルートは不規則な線を描く.また,金隈を起点として,佐賀東部•土井ケ浜•古浦とつないだ線も不規則である.1)2)は,ともに fall-off curveを描くものの,その傾斜は大きく異なる.両ルートは,基本的に,前者が山間部•海浜部を経由するのに対して,後者は平野部を通る点に大きな相違点がある.さらに,3)のルートは single step migration モデルのようなランダムな拡散では説明できないパターンであり,渡来系遺伝子の高い移動性を示したものと考えられる.これらの分布パターンは,古墳時代における政治的•文化的関係をそのまま反映したものではない.したがって,これらは,むしろ渡来人および混血を経たその子孫が,北部九州を起点として,婚姻や移住によって,農耕に適した土地へと拡散していった過程を示すものと考えられる.
164 0 0 0 OA 日本人第三大臼歯中に蓄積された放射性核種および微量元素に関する研究
- 著者
- 樋出 守世 井上 一彦 今井 奨 山本 実
- 出版者
- 一般社団法人 日本口腔衛生学会
- 雑誌
- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.206-213, 1991-04-30 (Released:2010-10-27)
- 参考文献数
- 31
1. Japanese third molars were divided into sample groups based on the donor's year of birth, and 90Sr level in each sample group of 10 teeth was determined to compare it with the previously reported data obtained from sample groups of 28 teeth.2. Trace and detection-limit amounts of 90Sr were detected in the teeth from donors born in 1929-1931. The 90Sr level increased in the teeth from donors born in 1935, and reached a peak value of 66.9-72.8mBq/g Ca in the teeth from donors born in 1953. It decreased afer 1954 and reached 25.5mBq/g Ca in the teeth from donors born in 1970.3. Compared with previous data using 28 teeth as a sample group, good accordance was observed in period showing detection-limit level of 90Sr, tendency of increase thereafter, peak period, radioactivity at peak period, tendency of decrease after 1953 and radioactivity after peak period.4. These results clearly indicate that a small sample, that is, 10 teeth, is sufficient for the examination of annual change in the 90Sr level.
163 0 0 0 OA 被害者非難と加害者の非人間化――2種類の公正世界信念との関連――
- 著者
- 村山 綾 三浦 麻子
- 出版者
- The Japanese Psychological Association
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.86.13069, (Released:2015-01-15)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 2 5
This study defined Belief in Just World (BJW) multidimensionally and investigated the effects of Belief in Immanent Justice (BIJ) and Belief in Ultimate Justice (BUJ) on victim derogation and draconian punishment of perpetrators. Study 1 tested the validity of the multidimensional structure of BJW and demonstrated relationships between BJW and other psychological variables. In Study 2, we measured the reactions to the victim and perpetrator in an injury case reported in a news article, and evaluated the relationships of these reactions to BIJ and BUJ. The results revealed that BIJ was associated with a preference in draconian punishment of the perpetrator, while BUJ was associated with dissociation from the victim (a type of victim derogation). In addition, as hypothesized, we found that dehumanization of the perpetrator partially mediated the relationship between BIJ and victim derogation. We discussed relationships between the two types of BJW and just-world maintenance strategies in the situation where a victim and a perpetrator are both recognized.
163 0 0 0 OA 松尾芭蕉の歩行能力の検証 : 『曾良旅日記』の分析を中心として
- 著者
- 谷釜 尋徳
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- pp.21013, (Released:2021-08-13)
162 0 0 0 OA 江戸時代の体罰観・研究序説
- 著者
- 江森 一郎
- 出版者
- 教育史学会
- 雑誌
- 日本の教育史学 (ISSN:03868982)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.4-24, 1984-09-19 (Released:2017-06-01)
162 0 0 0 OA 玄米浸漬時の乳酸菌添加効果
- 著者
- 熊谷 武久 瀬野 公子 渡辺 紀之
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.3, pp.179-184, 2006-03-15 (Released:2007-03-09)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2 1
乳酸菌添加液に玄米を浸漬することによる乳酸菌の付着性を検討した.(1)米及び米加工品より分離したL. casei subsp. casei 327を乳酸菌スターターとして,コシヒカリ,ミルキークイーン及びこしいぶきの玄米を用い,玄米浸漬液にスターターを添加して37℃,17時間発酵することにより,乳酸菌の増殖が浸漬液及び玄米で見られた.16SrRNA遺伝子塩基配列により当該菌が増殖したことを確認した.(2)発酵処理した玄米のpHはおおよそ6であり,炊飯後の米飯の食味に影響を及ぼさなかった.(3)発酵温度の低下により発酵処理玄米のLactobacillus数が低下し,玄米と浸漬液の配合比及びスターター量の変化では,大きな影響はなかった.(4)乳酸菌を添加しない区では,乳酸菌以外の菌数が増加し,Enterobacteriaceaeが主要な菌であった.(5)5菌種,7菌株の乳酸菌,全てで発酵液及び発酵処理玄米のLactobacillus数の増加が見られ,L. acidophilus JCM1132Tのみ生育が悪く,L. casei subsp. casei 327が最も増殖効果が高かった.
- 著者
- 巖城 隆 佐田 直也 長谷川 英男 松尾 加代子 中野 隆文 古島 拓哉
- 出版者
- 日本野生動物医学会
- 雑誌
- 日本野生動物医学会誌 (ISSN:13426133)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.4, pp.129-134, 2020-12-24 (Released:2021-02-24)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1 2
2011年から2019年に西日本各地で捕獲された4種のヘビ類(シマヘビ,アオダイショウ,ヤマカガシ,ニホンマムシ)の口腔から吸虫を採取した。これらは形態観察と分子遺伝子解析によりOchetosoma kansenseと同定した。この種は北アメリカのヘビ類への寄生が以前から知られているが,日本に生息するヘビ類での確認は初であり,今回の結果は新宿主・新分布報告となる。
162 0 0 0 OA ライフル射撃音による急性音響性難聴の臨床的検討
- 著者
- 中屋 宗雄 森田 一郎 奥野 秀次 武田 広誠 堀内 正敏
- 出版者
- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.1, pp.22-28, 2002-01-20 (Released:2010-10-22)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1 2
目的: ライフル射撃音による急性音響性難聴の聴力像と治療効果に対する臨床的検討を行った.対象と方法: ライフル射撃音による急性音響性難聴と診断され入院加療を行った53例, 74耳とした. 治療方法別 (ステロイド大量漸減療法群23耳とステロイド大量漸減療法+PGE1群51耳) と受傷から治療開始までの期間別 (受傷から治療開始まで7日以内の群42耳と8日以降の群32耳) に対する治療効果と聴力改善 (dB) についてretrospectiveに検討した. また, 各周波数別に治療前後の聴力改善 (dB) を比較検討した.結果: 全症例の治癒率19%, 回復率66%であった. ステロイド大量漸減療法群では治癒率17%, 回復率78%, ステロイド大量漸減療法+PGE1群では治癒率24%, 回復率63%であり, 両者の群で治療効果に有意差を認めなかった. 受傷から7日以内に治療を開始した群では治癒率21%, 回復率78%, 受傷から8日目以降に治療を開始した群では治癒率16%, 回復率50%であり, 受傷から7日以内に治療を開始した群の方が有意に治療効果は高かった. 入院時の聴力像はさまざまな型を示したが, 2kHz以上の周波数において聴力障害を認める高音障害群が50耳と多く, 中でも高音急墜型が20耳と最も多かった. また, 治療前後における各周波数別の聴力改善 (dB) において, 500Hz, 1kHzの聴力改善 (dB) は8kHzの聴力改善 (dB) よりも有意に大きかった.結論: 今回の検討で, 受傷後早期に治療を行った症例の治療効果が高かったことが示された. また, 高音部より中音部での聴力障害は回復しやすいと考えられた.
162 0 0 0 OA 兵庫県内花崗岩地域を主とする河川水および飲料水中ウラン濃度
- 著者
- 礒村 公郎 杉山 英男
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.10, pp.626-634, 1999-10-15 (Released:2011-03-10)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2 1 2
兵庫県下の河川水および水道水のウラン濃度を調べた。県内大部分の地域で河川水のウラン濃度は検出限界0.02μg/kg以下であったが, 六甲山周辺および淡路島北部でウラン濃度の高い河川水が認められ, さらにウラン濃度とフッ素濃度には有意な相関が認められた。ウラン濃度の高い河川の分布する地域は六甲花崗岩および領家花崗岩の分布する地域と一致した。河川水のウラン濃度の高い原因は六甲花崗岩および領家花崗岩の地下水によると推定された。水道水の摂取に伴うウランによる年実効線量当量は, 過去には最高で1.5μSv/年 (1996年神戸市兵庫区) と推定されたが, その後ウラン濃度は減少し, 1997年12月以降は厚生省の指針値 (0.002mg/L) の半分以下で, 年実効線量当量は0.3μSv/年以下で推移している。
162 0 0 0 OA 努力の成果か運の結果か? 日本人が考える社会的成功の決定要因
- 著者
- 緒方 里紗 小原 美紀 大竹 文雄
- 出版者
- 行動経済学会
- 雑誌
- 行動経済学 (ISSN:21853568)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.137-151, 2012 (Released:2013-06-06)
- 参考文献数
- 17
人々は社会的成功を努力で決まると考えているのであろうか,それとも運で決まると考えているのであろうか.本論文では,日本人が持つ社会的成功に関する価値観の形成要因を分析する.とくに,学卒時に直面する経済状況が価値観の形成に与える影響に注目する.分析には『くらしと好みの満足度についてのアンケート調査』(大阪大学)による回答を用いる.調査回答の特異性を利用して,個人のさまざまな異質性を捉えた上で,主観的な回答に対する同一個人の回答バイアスや測定誤差の影響を除いて分析した結果,学卒時に偶然にも不景気に直面した者は「社会的成功は努力よりも運で決まる」という価値観を持ちやすい可能性があることが示された.さらに,男性と女性の価値観の形成要因には大きな違いが見られることが明らかにされた.
162 0 0 0 OA 樋口直人著『日本型排外主義――在特会・外国人参政権・東アジア地政学』
- 著者
- 塩原 良和
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.156-157, 2015 (Released:2016-06-30)
162 0 0 0 OA 岡山県小田川流域における水害予防組合の活動
- 著者
- 内田 和子
- 出版者
- 一般社団法人 日本治山治水協会
- 雑誌
- 水利科学 (ISSN:00394858)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.40-55, 2011-08-01 (Released:2017-07-24)
- 参考文献数
- 16
161 0 0 0 OA いじめる・いじめられる経験の背景要因に関する基礎的研究 —自尊感情に着目して—
- 著者
- 伊藤 美奈子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.26-36, 2017-03-30 (Released:2017-04-21)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 11 8
昨今, 深刻化・複雑化するいじめについて, 小学生(3,720人), 中学生(3,302人), 高校生(2,146人)に調査をおこなった。いじめの被害・加害経験を尋ねた結果より, いじめの加害役割と被害役割が固定したものではないことが明らかになった。また, いじめの被害者は自尊感情が低く情緒不安定な特徴を有するが, それに加害経験が加わるとより一層, 自尊感情(とくに人間関係における自己肯定感)は低くなることが示唆された。また, クラスメートをからかうことを「悪くない」「おもしろい」と認知するものの割合は, 年齢とともに多くなること, その傾向は, とくにいじめ加害経験を有するものに多いこともわかった。いじめによる不登校や希死念慮は, ネット上のいじめ・集団無視・金品たかりといういじめでとくに強く経験される。またこれらの辛さは, 加害経験がなくいじめ被害のみのものに強く, 仕返し願望は, いじめ加害経験者により強い。いじめを見たときの反応(注意する・誰かに相談する・傍観する)も, 発達段階による違いが見られた。さらに, そうしたいじめに対する反応の背景にも, いじめ加害経験や自尊感情の低さが関与していることがうかがえた。
161 0 0 0 OA スパイスの化学受容と機能性
- 著者
- 川端 二功
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.1-7, 2013 (Released:2013-11-22)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 3
- 著者
- Naoki Nago Shizukiyo Ishikawa Tadao Goto Kazunori Kayaba
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- pp.1012070204-1012070204, (Released:2010-12-11)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 28 66
Background: We investigated the relationship between low cholesterol and mortality and examined whether that relationship differs with respect to cause of death.Methods: A community-based prospective cohort study was conducted in 12 rural areas in Japan. The study subjects were 12 334 healthy adults aged 40 to 69 years who underwent a mass screening examination. Serum total cholesterol was measured by an enzymatic method. The outcome was total mortality, by sex and cause of death. Information regarding cause of death was obtained from death certificates, and the average follow-up period was 11.9 years.Results: As compared with a moderate cholesterol level (4.14–5.17 mmol/L), the age-adjusted hazard ratio (HR) of low cholesterol (<4.14 mmol/L) for mortality was 1.49 (95% confidence interval [CI]: 1.23–1.79) in men and 1.50 (1.10–2.04) in women. High cholesterol (≥6.21 mmol/L) was not a risk factor. This association was unchanged in analyses that excluded deaths due to liver disease, which yielded age-adjusted HRs of 1.38 (95% CI, 1.13–1.67) in men and 1.49 (1.09–2.04) in women. The multivariate-adjusted HRs and 95% CIs of the lowest cholesterol group for hemorrhagic stroke, heart failure (excluding myocardial infarction), and cancer mortality significantly higher than those of the moderate cholesterol group, for each cause of death.Conclusions: Low cholesterol was related to high mortality even after excluding deaths due to liver disease from the analysis. High cholesterol was not a risk factor for mortality.
161 0 0 0 OA 科学という事業におけるジェンダー関与
- 著者
- 藤垣 裕子
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.12, pp.12_70-12_71, 2014-12-01 (Released:2015-04-03)