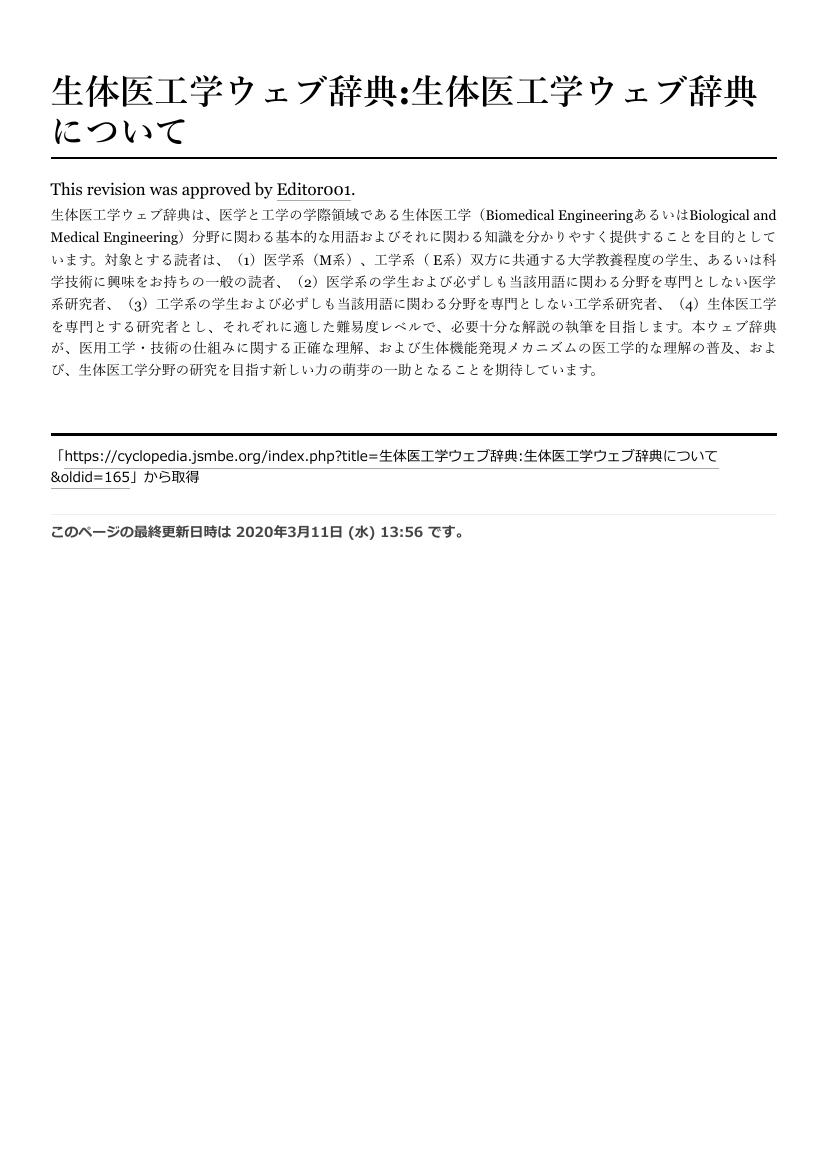2 0 0 0 OA β晶核剤を添加したポリプロピレンによる多孔質フィルムの調製
- 著者
- 岩崎 祥平 山崎 敦朗 畠山 広大 内山 陽平 井上 貴博 新田 晃平 山口 政之
- 出版者
- 一般社団法人 日本レオロジー学会
- 雑誌
- 日本レオロジー学会誌 (ISSN:03871533)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.171-179, 2022-04-15 (Released:2022-05-15)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 2
Microporous films were obtained from an extruded sheet of isotactic polypropylene (PP) containing N,N’-dicyclohexyl-2,6-naphthalene dicarboxamide as a crystal nucleating agent under suitable hot-stretching conditions. The crystalline structure before and after the stretching operations was evaluated by two-dimensional wide-angle X-ray diffraction, and it was found that the original sheet contains a large amount of β-form crystals oriented to the transversal direction (TD) by the extrusion at 200 °C, which is lower than the dissolution temperature of the nucleating agent in PP. During stretching of the sheet, α-form crystals oriented to the stretching direction appeared by the transformation from β- to α-form crystals. Moreover, numerous microvoids were generated by stretching around at 100 °C to the machine or flow direction (MD) of the sheet, although the microvoids were prolonged. The sequential TD stretching, however, expanded the area of voids, leading to a microporous film with a pronounced porosity.
2 0 0 0 OA 交通ネットワークの交通流制御に関するシステム理論的考察
- 著者
- 小林 正明 清水 光 藤井 温子 石川 洋
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告モバイルコンピューティングとユビキタス通信(MBL)
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, no.47(2005-MBL-033), pp.37-42, 2005-05-25
本稿では、交通工学と制御工学を統合させるシステム理論的観点から、交通ネットワークの交通流ダイナミクスを制御する信号制御システムや動的経路誘導システム、ならびにこれら2つのダイナミックシステムをオンラインリアルタイム結合させた交通流制御システムについて提案する。最初に、信号交差点の交通流ダイナミクスの基礎となる交通量収支において、捌け交通量の上限値を決定する交通処理量は、ある交通条件と信号制御条件のもとで道路設計によって決定される。交通流ダイナミクスを車線単位、サイクル長単位で解析するために、信号交差点の動的交通情報について調査する。つぎに、時々刻々と変動する交通流ダイナミックスシステムを記述しオンラインリアルタイムで制御する大規模システムを、3レベルの階層制御を用いて構成する。最後に、交通工学と制御工学の統合例として、信号制御システムと動的経路誘導システムの構成や機能、有効性などについて示し、交通流制御システムの構成や制御アルゴリズムについて提案する。
2 0 0 0 OA 高校生の制服に対する意識と学校教育との関連性について(第2報)
- 著者
- 福村 愛美 Manami Fukumura
- 雑誌
- 大分県立芸術文化短期大学研究紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.241-249, 1996-12-31
高校生が制服についてどの様な意識を持っているか、また制服と、家庭科及び被服実習、家庭科男女共修との関連性を調査をもとに分析した結果、次の様なことが明らかになった。1、学校を制服で選ぶかどうかという質問に対して高校1年生と2年生では、1年生のほうが学校を制服で左右されないと考えている。2、好きな制服のデザインでは、1年生男子は詰め襟の学生服を大半が支持しているが、2年生になるとブレザータイプの制服と半々に意見がわかれる。女子は全体的に差はなくセーラー服を好んでいる。3、制服の持っている枚数は、冬用を1枚、夏用を2枚持っている組み合わせが1番多い。4、音楽専攻の生徒が、スカートの長さや靴下の流行に最も敏感である。5、被服制作の完成時に充実感を感じない者ほど、制服の良くないところとして、温度調節がしにくいという理由を挙げている。6、家庭科男女共修に価値があると思う者ほど、学校を制服で選ばないと考えている。7、家庭科を男子も学ぶべきであると余り考えない者の方が、セーラー服をより好んでいる。8、制服のイメージは多面性を持っていると考えられる。終わりに、集計作業にご協力いただいた大分県立芸術文化短期大学の田仲謙司さん及び学生や副手の方々に深く感謝申し上げます。
- 著者
- Shiraki Shoki Shimomura Michitaka Kakui Keiichi
- 出版者
- Pensoft Publishers
- 雑誌
- Zoosystematics and Evolution (ISSN:14351935)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.1, pp.109-115, 2022-03-31
- 被引用文献数
- 1
We describe a new paranthurid isopod genus and species, Deltanthura palpus gen. et sp. nov., collected from a depth of 805–852 m off the southern coast of Mie prefecture, Japan. Deltanthura is similar to Pseudanthura Richardson, 1911 in having a triangular pleotelson, acute mandible with a 3-articulate palp, a maxillipedal endite, and a tapering uropodal exopod, but differs in having eyes and neotenous characters (reduced pereonite 7 and pereopods 7 lacking). Deltanthura and four paranthurid genera (Califanthura Schultz, 1977, Colanthura Richardson, 1902, Cruranthura Thomson, 1946, and Cruregens Chilton, 1882) share neotenous characters, but in Deltanthura the mandible is acute, with a 3-articulate palp and maxillipedal endites are present. Califanthura minuta Kensley & Heard, 1991 may belong in Deltanthura as they share the triangular pleotelson and tapering uropodal exopod, but we refrain from transferring it to Deltanthura as its description lacks the other diagnostic characters of Deltanthura. We provide a revised key to all genera in Paranthuridae Menzies & Glynn, 1968.
- 著者
- Munakata Mizuho Tanaka Hayato Kakui Keiichi
- 出版者
- Pensoft Publishers
- 雑誌
- Zoosystematics and Evolution (ISSN:14351935)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.1, pp.117-127, 2022-04-05
- 被引用文献数
- 2
We describe the cypridoidean ostracod Cavernocypris hokkaiensis sp. nov. from riverbed sediments in an alpine stream at an elevation of ca. 1850 m in the Taisetsu Mountains, Hokkaido, Japan. This species differs from congeners in having (1) the outer surface of the carapace smooth, with sparse, tiny setae, but without shallow pits; (2) the carapace elongate rather than triangular in lateral view; (3) the antennula consisting of seven podomeres; (4) first palpal podomere of maxillula with five dorsodistal and one ventro-subdistal setae; (5) the fifth limb lacking setae b and d; and (6) the fifth limb lacking a vibratory plate. We provided the key to the Cavernocypris species. We determined partial sequences for the cytochrome c oxidase subunit I (COI; cox1) and 18S rRNA (18S) genes in C. hokkaiensis. Our sample contained only females, and we obtained a partial 16S rRNA sequence for the endosymbiotic bacterium Cardinium from C. hokkaiensis, indicating the possibility that this ostracod species reproduces parthenogenetically. Our field survey and observations of captive individuals suggested that C. hokkaiensis may be endemic to the Taisetsu Mountains, with a low population density, narrow distributional range, and slow maturation to sexual maturity.
- 著者
- 中田 行彦
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織学会大会論文集 (ISSN:21868530)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.155-161, 2021 (Released:2021-08-21)
- 参考文献数
- 14
The use of EVs is accelerating around the world because CO2 emissions are zero while driving. However, considering the life cycle, the “inconvenient truth” that the decarbonization effect of EV is limited emerges. In addition to analyzing the organizational behavior of companies toward this “inconvenient truth,” the “inconvenient truth” were examined and considered new issues. The CO2 emissions seen from the life cycle of the automobile were estimated from the standpoint of a third party using published data. As a result, it was verified that “the decarbonization effect of EV is limited.” The most important issue is that “EVs need to significantly reduce CO2 during storage battery manufacturing.” For that purpose, it is necessary to improve the manufacturing process, materials, and structure of Lithium-Ion Battery (LIB). In addition, “promoting renewable energy” is an essential condition for decarbonization in all industries and products. In order to achieve decarbonization, it is essential to face the “inconvenient truth” and challenge and overcome it.
2 0 0 0 OA コスプレイヤーの協働的ポージング構築場面にみる物理的特徴の分析
本研究では,アニメのキャラクターなどに扮する遊びである「コスプレ」のポージングを協働的に構築していく状況に着目する.コスプレイヤーのポーズと表情をKinectを用いてキャプチャし,顔や身体の各部位間の位置について客観的な指標を得る.コスプレイヤーがキャラクターの特性に関する理想的な表現に近づけていく過程のデータ解析を通して,ポーズの修得や熟達に関する一人称視点での変容が,身体の動きとどのように関係しているのかを,客観的に見ていく.またあわせて,得られた結果に基づいて「表現力」を客観的な数値として自動判定する技術の可能性を検討する.
2 0 0 0 OA 臨床教育研究としてのフォーラムシアター ──社会学的考察の試み──
- 著者
- 秋葉 昌樹
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, pp.83-104, 2013-07-25 (Released:2014-07-28)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 3
本稿の目的は,「フォーラムシアター」と呼ばれる応用演劇の手法によって,養護教諭が日常的に抱える問題意識やその仕事の流儀と向き合う作業を支援する方法について考察し,「教育臨床の社会学」の新たな展開可能性を探ることにある。 「フォーラムシアター」は,観客ないし演じ手が日頃直面しがちな問題をとりあげ劇として上演し,観客を巻き込んだ 討論と劇の再演を繰り返しながら問題状況における変化,変容可能性を探っていく手法である。それはいわば演劇を用いた社会教育的実践とも言いうるものだが,その応用的性格からか,理論的定式化は必ずしも十分に進められてこなかった。 本稿では,この手法がもたらす当事者支援の可能性を視野に,筆者が養護教諭らのグループとともに運営してきたフォーラムシアターを事例として分析した。 その結果見えてきたことは,フォーラムシアターという手法によって,参加者である養護教諭が,日頃の葛藤や問題意識を共有しつつ再認識し,またそれらを乗り越えるべく主体的に探究を開始し,今後の変容可能性を見いだしているということである。そして本稿では,参加者によって主体的に見いだされる変容可能性が,フォーラムシアターが備える遊戯性および“未完”性という構造的特質によってもたらされることを明らかにした。
2 0 0 0 OA 生体医工学ウェブ辞典(第一分冊)
- 著者
- 相川 慎也 芦原 貴司 天野 晃 有末 伊織 安藤 譲二 伊井 仁志 出江 紳一 伊東 保志 稲田 慎 井上 雅仁 今井 健 岩下 篤司 上村 和紀 内野 詠一郎 宇野 友貴 江村 拓人 大内田 研宙 大城 理 太田 淳 太田 岳 大谷 智仁 大家 渓 岡 崇史 岡崎 哲三 岡本 和也 岡山 慶太 小倉 正恒 小山 大介 海住 太郎 片山 統裕 勝田 稔三 加藤 雄樹 加納 慎一郎 鎌倉 令 亀田 成司 河添 悦昌 河野 喬仁 紀ノ定 保臣 木村 映善 木村 真之 粂 直人 藏富 壮留 黒田 知宏 小島 諒介 小西 有人 此内 緑 小林 哲生 坂田 泰史 朔 啓太 篠原 一彦 白記 達也 代田 悠一郎 杉山 治 鈴木 隆文 鈴木 英夫 外海 洋平 高橋 宏和 田代 洋行 田村 寛 寺澤 靖雄 飛松 省三 戸伏 倫之 中沢 一雄 中村 大輔 西川 拓也 西本 伸志 野村 泰伸 羽山 陽介 原口 亮 日比野 浩 平木 秀輔 平野 諒司 深山 理 稲岡 秀検 堀江 亮太 松村 泰志 松本 繁巳 溝手 勇 向井 正和 牟田口 淳 門司 恵介 百瀬 桂子 八木 哲也 柳原 一照 山口 陽平 山田 直生 山本 希美子 湯本 真人 横田 慎一郎 吉原 博幸 江藤 正俊 大城 理 岡山 慶太 川田 徹 紀ノ岡 正博 黒田 知宏 坂田 泰史 杉町 勝 中沢 一雄 中島 一樹 成瀬 恵治 橋爪 誠 原口 亮 平田 雅之 福岡 豊 不二門 尚 村田 正治 守本 祐司 横澤 宏一 吉田 正樹 和田 成生
- 出版者
- 公益社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.Dictionary.1, pp.1-603, 2022 (Released:2022-03-31)
2 0 0 0 OA 「自己」への相互行為論アプローチ : 経験的探究に有効な再定式化のために
- 著者
- 中河 伸俊
- 出版者
- 大阪府立大学人文学会
- 雑誌
- 人文学論集 (ISSN:02896192)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.45-71, 2010-03-31
2 0 0 0 OA 太山寺本『曽我物語』とその時代 ―太山寺本奉納者明石長行と亡妻昌慶禅定尼をめぐって―
- 著者
- 村上 美登志
- 出版者
- 中世文学会
- 雑誌
- 中世文学 (ISSN:05782376)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.96-111, 1994 (Released:2018-02-09)
2 0 0 0 OA 被害者への自殺の強制と殺人罪
- 著者
- 奥谷 千織
- 出版者
- 京都産業大学法学会
- 雑誌
- 産大法学 (ISSN:02863782)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3/4, pp.816-800, 2014-01
はじめに1 16年決定の事案と裁判所の判断2 16年決定の評価と学説の状況3 殺人罪の実行行為についての若干の検討おわりに
2 0 0 0 OA 系統的脱感作法による視線恐怖反応の消去に及ぼすSELF-EFFICACYの役割
- 著者
- 前田 基成 坂野 雄二 東條 光彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.158-170, 1987-03-31 (Released:2019-04-06)
本研究の目的は,治療セッショソをおって継時的に評定されたセルフ・エフィカシーの変動と,視線恐怖反応の消去にともなう行動変容との関係を明らかにし,知覚されたセルフ・エフィカシーが行動変容の先行要因としてどのように機能しているかを明らかにすることである。学校場面において,極度の視線恐怖反応を示す14歳の少年に対し,系統的脱感作法を適用した。約10ヵ月にわたる治療的介入は,主観的・認知的(SUD,セルフ・エフィカシー),心理生理的(心拍数),行動的(日常生活における恐怖をともなわない行動遂行,行動の自己評定)測度のいずれにおいても顕著な改善をもたらした。各治療セッショソ後に実施された次セッショソまでの1週間を見通したセルフ・エフィカシーの評定と,1週間後に確認された行動変容の関係を詳細に分析したところ,セルフ・エフィカシーの変動が恐怖反応の消去と密接に関係していることが明らかにされた。すなわち,クライエソトがセルフ・エフィカシーを強く認知すればするほど,視線恐怖時の不安反応は弱くなることが観察された。同時に,その逆の現象も認められた。その結果,知覚されたセルフ・エフィカシーが,行動変容の先行要因として機能していることが示唆された。
2 0 0 0 OA 月経前症候群女性におけるサイトカイン変動と情動変化
- 著者
- 志賀 令明 本多 たかし
- 出版者
- 一般社団法人 日本女性心身医学会
- 雑誌
- 女性心身医学 (ISSN:13452894)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.492-497, 2007-11-30 (Released:2017-01-26)
21歳から32歳の9名の女性を対象にして,1月経周期に3回の採血と各種心理検査を行い,月経前症候群(PMS)に該当する者を抽出すると同時に,血液成分(エストラジオール,プロゲステロン,ACTH,コルチゾール,レプチン,IL-1β),及び心理検査(PMS調査票,POMS,Y-G性格検査)各項目の検討を行った.採血時の各人の最終月経からの経過日数は1日から37日であった.各人の最終月経からの経過日数を横軸,血液成分,心理検査各項目得点を縦軸にして単回帰分析を行うと,有意な相関が見られたのは,コルチゾール,PMS調査票得点であり,双方とも月経周期が後半になるにつれて上昇した.PMS調査票得点と月経周期との単回帰式から算出した予測値との差に基づき,月経周期20日以上でPMS得点が予測値より高かった者をgroup H(n=4),下回った者をgroup L(n=7)とし比較した.その結果,group Hはgroup Lに比し,IL-1βで有意に高い値を示し,コルチゾール,レプチンで高い傾向を示した.また心理検査でも抑うつ性に関する得点が有意に高い値を示した.特にgroup Hは平均22日目にあたる採血時において,平均15日目にあたるその他の者(n=23)に比し,有意に高いIL-1βを示した.上記から,PMS群と考えられるgroup Hでは排卵周辺に炎症反応が強まり,炎症性サイトカイン濃度が上昇し,それが視床下部-下垂体-副腎皮質系に影響を与えて特有の抑うつ症状を起こさせるだけでなく,レプチンを抑制するコルチゾールの上昇は,レプチン抵抗性を引き起こし高レプチン血症を生じさせると考えた.またIL-1βの上昇はバソプレッシンの分泌亢進を引き起こし水分貯留などの原因になると考えた.上記から,PMSにおいて,排卵ないしは月経そのものを「炎症」ととらえる免疫系のメカニズムの不全を示唆した.
2 0 0 0 OA 側頭骨の画像診断 ‘Leave me alone’ lesionsと錐体尖部破壊性病変
- 著者
- 岡本 浩一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.115, no.10, pp.887-893, 2012 (Released:2012-11-23)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 2
“外転神経麻痺”と“三叉神経第1枝 (V1) 領域の疼痛”の組み合わせはGradenigo症候群として知られ, 側頭骨錐体尖部 (以下, 錐体尖部) の病変を示唆する. Gradenigo症候群の患者のみならず, 耳鼻科的・眼科的疾患や脳病変の検索のために撮像されたCT・MRIで, 錐体尖部病変が認められることがある. これらの病変は, 耳鼻科的診察では直接視診・触診などすることができず, 内視鏡でも観察することが困難で, 生検なども容易ではない. 病変が積極的な耳鼻科的治療の対象か否かの判断に, 画像診断の果たす役割りが大きい.偶然発見される錐体尖部病変のうち, 治療的介入を要しない正常変異や病変は ‘Leave me alone’ lesionsといわれ, 介入を考慮する疾患と区別することが必要である. 偶然発見される代表的な ‘Leave me alone’ lesionsには(1)錐体尖蜂巣の左右差による非対称性錐体尖部骨髄, (2)錐体尖蜂巣内液体 (滲出液) 貯留, (3)脳瘤がある. これらの病態や疾患を, 耳鼻科的介入を考慮すべき錐体尖部 (破壊性) 病変と区別するためには, 錐体尖部の正常画像解剖の理解と, 日常臨床上重要な錐体尖部 (破壊性) 病変の画像所見の知識が必要である.
2 0 0 0 OA 大卒者の仕事の変容
- 著者
- 小杉 礼子
- 出版者
- 日本高等教育学会
- 雑誌
- 高等教育研究 (ISSN:24342343)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.71-92, 2017-07-31 (Released:2019-05-13)
- 参考文献数
- 21
本稿では,若年大卒者の仕事の変容について,3つの視点(①学卒未就職,失業,非正規雇用の状況,②就業先の企業規模,職種,賃金,③早期離職)から統計分析を行った.そこから,高卒者との比較においては,失業率も非正規雇用率も低く,また就業先は大規模企業が多いなど学歴間格差は拡大していること,一方,ブルーカラー職に就く男性卒業者が2割を占めるようになったり賃金の分散が大きくなるなど大卒内での就業実態の多様化が起こっていることが明らかになった.また,女性大卒就業者が大幅に増えていることも指摘した.こうした変容を踏まえて,大学が検討すべきことは,培うべき知識・スキルの認識を(産業)社会と共有する仕組み,女性卒業者のキャリア開発であることを指摘した.
2 0 0 0 OA 大学野球投手における体幹の伸張-短縮サイクル運動および動作が投球速度に与える影響
- 著者
- 蔭山 雅洋 岩本 峰明 杉山 敬 水谷 未来 金久 博昭 前田 明
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- pp.13014, (Released:2014-04-04)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 6 3
The present study measured isometric muscular strength and mean power elicited by trunk twisting and trunk rotation during pitching in 28 university baseball pitchers aged 18-22 years. Based on the correlations among these measurements, the purpose of the study was to clarify 1) the influence of ball velocity on isometric muscular strength, trunk power output during the stretch-shortening cycle (SSC) and trunk rotation during pitching and 2) the influence of augmentation which is an index of SSC elicited by trunk rotation on trunk rotation during pitching. We also determined mean power and augmentation during concentric (CT) and SSC rebound (RT) throws of medicine balls weighing 5 kg while twisting the trunk. Augmentation while throwing the medicine ball was positively correlated with ball velocity (r=0.619, p<0.01), and augmentation of the medicine ball was positively correlated with torso rotation velocity at 18-27% and at 46-75% (r=0.398-0.542, p<0.05), and trunk twist velocity at 60-66% (r=0.378-0.395, p<0.05) of the second phase (from stride foot contact to instant release of the ball) during the pitching motion. In addition, pitched ball velocity was positively correlated with the velocities of pelvic rotation at 37-78% (r=0.378-0.488, p<0.05), torso rotation at 46-87% (r=0.391-0.711, p<0.05) and trunk twist at 63-83% (r=0.375-0.499, p<0.05) during the second phase of the pitching motion. These results indicate that pitchers with a larger ball velocity can use SSC movement generated by twisting the trunk, which effectively increases trunk rotation from the first half to middle of the second phase, and they can also increase trunk rotation during the second phase.