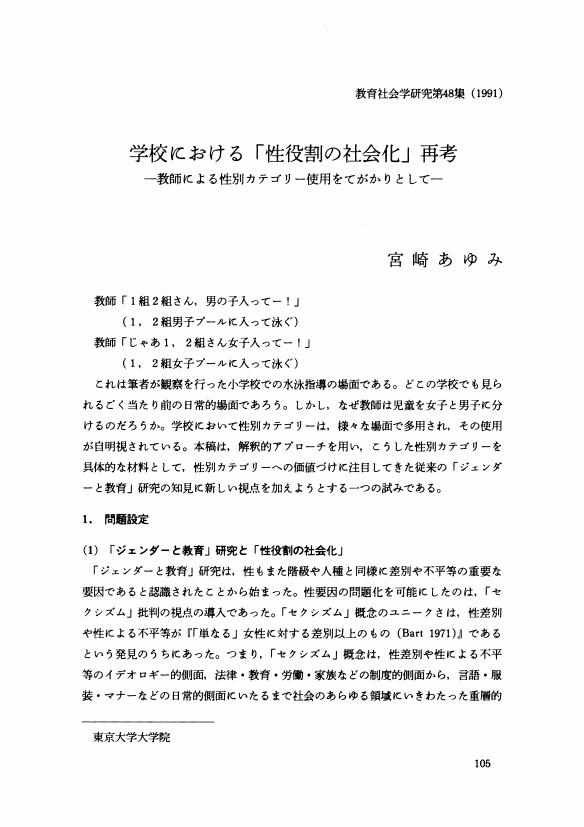- 著者
- Kensaku AMANO
- 出版者
- THE JAPAN SOCIETY OF HYDROLOGY AND WATER RESOURCES
- 雑誌
- JOURNAL OF JAPAN SOCIETY OF HYDROLOGY AND WATER RESOURCES (ISSN:09151389)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.34-38, 2015-01-05 (Released:2015-07-03)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
「国際水路の非航行的利用に関する条約」が,国連総会での採択から17年を経て,2014年8月に発効した.この条約は国境をまたぐ河川,湖沼,地下水を含む淡水資源の開発や管理に関する国際基準を示したもので,国際社会に大きな影響を及ぼすものと考えられる.特に,条文上最も重要視される「衡平利用原則」については,水資源をめぐる当事国間で紛争があった場合の一つの解決基準として用いられると期待され,事実,発効前にもかかわらず,これまで国際司法裁判所の判決でも引用されてきた.条約は当事国のみを規律するのが原則であるが,締約国以外にも当該条文が適用できるか,いわゆる国際慣習法化されているかは,条約発効後の国家実行や裁判例を待つ必要があろう.
2 0 0 0 DOIとJaLCの活動について
- 著者
- 波羅 仁 佐藤 竜一 三村 のどか
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.8, pp.428-431, 2020-08-01 (Released:2020-08-01)
2 0 0 0 OA 市川新松と市川鉱物研究室
- 著者
- 川崎 雅之 宮島 宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉱物科学会
- 雑誌
- 岩石鉱物科学 (ISSN:1345630X)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.34-40, 2013 (Released:2013-03-02)
- 参考文献数
- 29
Mr. Shinmatsu Ichikawa was a prominent mineralogist, although he was an ordinary citizen and not in government service. He lived from the late Meiji Period to the early Showa Period. He taught in elementary school and teacher training school despite not having a regular university education. He was self-taught in mineralogy and foreign language, and became a pioneer in the field of crystal morphology. His contributions include observations of the etched surfaces of natural minerals and of artificial etched quartz crystals and quartz spheres. He observed the etch pits, etch hillocks, growth hillocks and striations on the surfaces of several minerals found in Japan, engraved their positions, shapes and distributions on metal plates, and discussed his observations. He built the Ichikawa Mineral Laboratory in his house in 1918 to store his collection of minerals, rocks and fossils (more than 7000 specimens in all). His collection includes big quartz crystals twinned after Japan law from the Otome mine, twisted quartz from the Naegi region, amethyst crystals from Mt. Ametsuka and the Yusenji mine, natural etched minerals from various parts of Japan, and many minerals from the North America. The Laboratory is a historic cultural site in his hometown. Its preservation and enlightenment activities are cooperatively carried out by the local government and a neighborhood self-governing body.
- 著者
- 菅野 裕子
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.589, pp.213-220, 2005-03-30 (Released:2017-02-11)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1
This study deals with an analogy between architecture and music by taking the unit of measurement in the Italian Renaissance method. The aim of this study is to consider how the unit of measurement correlates with various parts that compose architectural and musical works. Concerning the unit of measurement, 'modulus' in architecture is analogous to 'tactus' in music. Vignola and Diruta measure all parts of architectural and musical works with these units of measurement. Therefore, all measurements are indicated by numbers.
2 0 0 0 OA 音楽に含まれる言語情報が文章課題の遂行に及ぼす影響
- 著者
- 門間 政亮 本多 薫
- 出版者
- 一般社団法人 日本人間工学会
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.5, pp.342-345, 2010-10-15 (Released:2011-06-17)
- 参考文献数
- 14
2 0 0 0 OA 北太平洋産ミンククジラの精巣における季節的変化
- 著者
- 井上 聡子 木白 俊哉 藤瀬 良弘 中村 玄 加藤 秀弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.2, pp.185-190, 2014 (Released:2014-03-20)
- 参考文献数
- 24
北太平洋産ミンククジラの精巣において,4 月から 10 月にかけての季節的変化を検討した。精巣重量の変化には 268 個体を使用し,うち 70 個体(各月 10 個体)の精巣組織を観察した。分析の結果,精巣重量は体長 7 m 以上の個体でのみ 7 月頃から増加が認められた。精細管直径は 5~6 月に縮小した後,徐々に拡大した。精母細胞など発達した精細胞は 7 月に最も減少し,その後増加した。これらのことから,ミンククジラの精子形成は 5 月から 6 月にかけて停滞し,8 月には次の繁殖期に向け準備が始まるという季節的変化が示唆された。
2 0 0 0 OA クリティカルケアにおけるアギュララの問題解決型危機モデルを用いた家族看護
- 著者
- 山勢 善江 山勢 博彰 立野 淳子
- 出版者
- 日本クリティカルケア看護学会
- 雑誌
- 日本クリティカルケア看護学会誌 (ISSN:18808913)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.8-19, 2011-03-31 (Released:2015-07-02)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA ヤンバルクイナ(Rallus okinawae)の鳴き声とデュエットについて
- 著者
- 池長 裕史 儀間 朝治
- 出版者
- Yamashina Institute for Ornitology
- 雑誌
- 山階鳥類研究所研究報告 (ISSN:00440183)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.28-39, 1993-03-30 (Released:2008-11-10)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2 2
沖縄島の北部のみから記録されているクイナ科の希少種であるヤンバルクイナは5種類以上の鳴き声を持つ。初めてビデオ撮影に成功したデュエットの映像と録音テープをもとに,本種の鳴き声についてソナグラフで解析し,以下の知見を得た。1) 5種類の鳴き声:コールI(ケッケッ(Kyo)-コール),コールII(ググッ(Gu)-コール),ソロソングI(クルル(Krr)-コール),デュエット(ケケケ(Kek)-デュエット)及びソロソングII(ケケケ(Kek)-コール)のソナグラムと波形を図示し,デュエットについては2羽を分別した。2) デュエットの際,2羽はお互いに向かい合わず,反対方向を向いて頭をふりながら同時あるいは交互に鳴き合わせた。3) デュエットは,先に鳴き始め,1秒間に7~8回の比較的安定した間隔で発声する個体と,これに同調し,やや分散的に鳴く別の個体とにより唱和され,この2羽は嘴の長さの差からそれぞれ雄と雌と考えられた。4) ソロソングII(ケケケ(Kek)-コール)はデュエットに類似していたが,他の個体が同調することなく,それより短い独唱のままで終わっており,導入部,声の連続性,後半の声の強さの変化においてデュエットとは差がみられた。5) 同じ種類の鳴き方でも鳴き声は変化し,ある特定の声の特徴について,それが雌雄の差によるのか,鳥の個体差によるものなのかは今後の課題である。
2 0 0 0 OA Voice Handicap Index日本語版による音声障害の自覚度評価
- 著者
- 田口 亜紀 兵頭 政光 三瀬 和代 城本 修
- 出版者
- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.4, pp.372-378, 2006-10-20 (Released:2010-06-22)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 17 13
近年, 音声障害の自覚的評価方法として, アメリカで提唱されたVoice Handicap Index (VHI) が注目されている.われわれは, VHIの日本語版を作成して音声障害患者に対して使用し, その有用性について検討を行った.対象とした音声障害症例は163例で男性79例, 女性84例であった.VHIスコアの平均は男性34.5, 女性41.6で女性のほうが高い傾向を示した.男性では40歳代以下のスコアが50歳代, 60歳代のスコアより低い傾向を示したが, 女性では年齢による差があまりなかった.疾患別では機能性発声障害, 反回神経麻痺, 声帯萎縮・声帯溝症の症例でスコアが高い傾向を示した.大部分の疾患では, 機能的側面および身体的側面のスコアが感情的側面のスコアより高かった.音声障害の治療後には, 多くの例でスコアが減少し, VHIは患者自身の音声障害に対する自覚度の把握, 適切な治療法の選択, および治療効果の評価を行ううえで有用と考えられた.
2 0 0 0 OA 本格焼酎の基本味を識別する脂質膜センサ
- 著者
- 中原 徳昭 古田 幸 境田 博至 甲斐 孝憲 榊原 陽一 西山 和夫 水光 正仁
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.8, pp.355-365, 2005 (Released:2007-04-13)
- 参考文献数
- 46
- 被引用文献数
- 1
センサにより本格焼酎の基本的な味を表現することを目的とし, 各脂質膜センサの特性 (意味づけ) について, 官能評価と化学分析を組み合わせた解析を行った. その結果,1. 水和シェルが存在し, ある程度エタノールポリマーの刺激を抑制すると考えられる6~18%のエタノール溶液においては, エタノールに対して主に「苦味」を, それ以上の濃度のエタノール溶液に対しては強い「刺激感」と共に「甘味」も感じることが確認された.2. 25%以上のエタノール溶液および本格焼酎を口に含んだ場合, 舌の表面においてエタノールと水の結合による発熱が起こり, この発熱が, 飲用温度による味覚感受性の変化と共に本格焼酎の味に何らかの影響をおよぼすことが示唆された.3. エタノール濃度に選択的に応答するセンサの特定を行った結果, プラス膜のAE1センサおよびブレンド膜の0E1センサが, 本格焼酎のエタノール濃度に良く応答することが確認され, この2つのセンサ挙動を比較することで, その他の味成分とエタノールの相互作用を確認できることが示唆された.4. 本格焼酎の官能評価における「酸味」は, pHおよび酢酸濃度に必ずしも一致しないが, AN0, CN0, AAEセンサのようにセンサの脂質膜にリン酸エステルを使用することで, 本格焼酎に含まれる「酸味」成分によく応答すると共にその他の成分との相互作用を確認できることが示唆された.今回の試験の結果, 本格焼酎におけるエタノールの味は, 刺激を伴う「苦味」が主体であることが確認できた. しかし, 日常において本格焼酎を飲用する際, このエタノール溶液のような強い「苦味」を感じることは希である. これは, 熟成の効果もさることながら, 本格焼酎独特の製法によって生み出される様々な成分が相互作用し, このエタノールの刺激を伴う「苦味」を抑制しているためと考えられる.今後はさらに, その他の各脂質膜センサの特性 (意味づけ) について解析を進めると共に, 本格焼酎の主成分であるエタノールの味を軸に, その他味成分との相互作用について官能評価と化学分析に味覚センサを組み合わせた検討を行っていく予定である.
2 0 0 0 OA 共働による労働統合型社会的企業における社会的承認
- 著者
- 森 瑞季
- 出版者
- 日本NPO学会
- 雑誌
- ノンプロフィット・レビュー (ISSN:13464116)
- 巻号頁・発行日
- pp.NPR-D-17-00008, (Released:2019-09-30)
- 参考文献数
- 25
近年,労働統合型社会的企業の研究の気運は高まってきているが,そこで働くスタッフの社会的関係ならびに承認の構造は先行研究をみてもいまだ明らかではない.本研究は,その社会的関係を参与観察から得た情報をもとに分析し,明らかにしようとしたものである.参与観察の結果,スタッフは「共働の論理」と労働者の生活を保障するための「ワーク・ライフ・バランス重視の論理」という二つの論理,また「私的な関係性」と「社会的な関係性」という二つの関係性のもとに,相互に承認しそれにもとづいて社会的関係を構築していることが判明した.とはいえ,これらの論理や関係性は両立しがたい性質を持っている.それでも職場組織が崩壊しないのは,共働のなかで他者への配慮がなされ,そしてそれにもとづく承認という共通した認識が寛容さに基いて暗黙裡に形成されていたからであった.そしてこれらによってできあがった社会的関係はまさに連帯と呼ぶにふさわしいものであった.本研究は,このように承認論の観点から労働統合型社会的企業に関する研究の発展に寄与するものである.
2 0 0 0 OA 江戸―東京市街地における坂の名称の継承に関する研究
- 著者
- 塚本 悠生 十代田 朗 津々見 崇
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3, pp.1123-1130, 2016-10-25 (Released:2016-10-25)
- 参考文献数
- 70
本研究は、江戸時代以前に命名された江戸墨引内の186の坂を対象とし、(1)江戸時代の切絵図等において名称が記載されている坂にはどのようなものがあり、また周辺の状況はいかなるものであったのか、(2)前述の坂の名称は、近代以降現代まで継承され続けているのか、を明らかにした上で、(3)現代まで名称が継承されている坂にはどのような空間的特徴や経緯があるのかを考察している。その結果、(1)幕末江戸では少なくとも186の坂が地図に表記されていること、(2)近代の旧東京15区内には174の坂で名称が継承されていたが、近代後期にはその数は少なくなっていったこと、(3)都区部では1972年以降、行政によって坂の名称や歴史を地域住民に伝える目的で標柱設置事業が行われ、それ以降、多くの名称が地図に表記されていること、(4)現在も坂の名称は消失しているが、明治から戦前、現代かけて消失する数は少なくなったこと、(5)武家を由来とした坂の名称は継承されやすく、一方で地名から名づけられた坂の名称は継承され難いと言えること、(6)坂の交通路としての格は、坂の名称の継承に対して強い影響を与えないこと、が分かった。
2 0 0 0 OA 兵庫県南東部の温泉の化学組成と粘土鉱物の産状
- 著者
- 宇野 泰章 寺西 清 礒村 公郎
- 出版者
- 日本鉱物科学会
- 雑誌
- 鉱物学雜誌 (ISSN:04541146)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.Special, pp.63-70, 1990-03-26 (Released:2009-08-11)
- 参考文献数
- 10
The mode of occurrence of clay minerals and the interaction between hot waters and wall rocks in Arima and Takarazuka have been investigated by X-ray powder diffraction, microscopic observation and chemical analysis. The alteration halo can be divided into three zones, such as, zone I (chlorite-mica zone), zone II (silica zone) and zone III (mica-kaolinite zone). Low, medium and high-temperature waters are mainly located in zone I, II and III respectively. Calcite veinlets are present in drilling cores of zone I and II. The pH values of hot waters in zone II calculated on the basis of the calcite-brine equilibrium equations are higher than those in zone I. Partial CO2 pressure of hot waters are almost constant, indicating a 3.8 atmospheric pressure in zone I, and a 4.9 atmospheric pressure in zone II. The most important factor controlling the chemical composition of hot waters seems to be the calcite-brine equilibrium in wall rocks.
2 0 0 0 OA 学校における「性役割の社会化」再考
2 0 0 0 OA 島根県のアブ科
- 著者
- 山内 健生 渡辺 護 林 成多
- 出版者
- 一般社団法人 日本昆虫学会
- 雑誌
- 昆蟲.ニューシリーズ (ISSN:13438794)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.24-30, 2013-01-05 (Released:2018-09-21)
島根県産アブ類について,野外調査と標本調査を実施し,20種を記録した.島根県におけるジャーシーアブの記録は,誤同定に基づいている可能性が非常に高いため,島根県のアブ科の種リストから本種を削除することを提案した.タイワンシロフアブ,マツザワアブ,アカバゴマフアブ,トヤマゴマフアブは島根県本土新記録となる.アカウシアブ,シロフアブ,ハタケヤマアブは隠岐諸島新記録となる.既知の記録と新記録を合計すると,28同定種が島根県に分布していることが明らかとなった.
2 0 0 0 OA 小中連携を意識した代数カリキュラム開発のための 基礎研究(その2)
- 著者
- 渡邉 伸樹
- 出版者
- 一般社団法人 数学教育学会
- 雑誌
- 数学教育学会誌 (ISSN:13497332)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3-4, pp.81-92, 2010 (Released:2020-04-21)
本研究は,小中連携を意識した,代数カリキュラムの開発を目指すものである。本稿では,「分数の乗除」に焦点をあて,小中連携の代数カリキュラムの中で,特に2nd stage(小学校第5・6 学年,中学校第1 学年)註1 の小学校高学年において有効であると考えられる一つの教育内容(代数的な分数の乗除) を開発し,実際に教育実践を通すことからその妥当性を検討した。その結果,「代数的な分数の乗除」の教育内容は,小学校第6 学年で十分に理解可能であることから,小中連携のカリキュラムの中で,特に2nd stage の小学校高学年における一つの教育内容として妥当性があることが示唆された。
- 著者
- 水沼 友宏
- 出版者
- 日本図書館情報学会
- 雑誌
- 日本図書館情報学会誌 (ISSN:13448668)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.4, pp.221-241, 2016 (Released:2017-01-08)
- 参考文献数
- 64
2003 年の地方自治法の改正により,指定管理者制度に基づく公の施設の運営が可能になったが,公立図書館への同制度の導入については否定的な意見も見受けられる。だが,その実態を表す研究は極めて少ない。そこで本研究では,公立図書館における指定管理者制度の実態を明らかにする一環として,レファレンスサービスに焦点を当て,同制度を導入している図書館(以下,指定館)と導入していない図書館(以下,直営館)のサービス実施状況やレファレンス質問の受付件数の異同,及び制度導入後の質問受付件数の変化を明らかにした。結果,指定館は直営館より,利用者が自分で情報を調べられる環境作りや教育に積極的であること,逆に直営館は指定館より,利用者の質問に直接答えようとする傾向が強い可能性が示された。また,指定館の方が直営館に比べ質問受付件数が多く,制度導入後に質問受付件数が増加していることが分かった。
- 著者
- 坪内 健治郎 尾崎 哲児
- 出版者
- 一般社団法人 色材協会
- 雑誌
- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.1, pp.2-6, 2000-01-20 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 19
アクリル樹脂の溶解性および溶解性パラメータ (SP値) に及ぼす極性基の効果をガスクロマトグラフィー (GLC) により検討した。アクリル酸エチル, アクリル酸とアクリル酸2-ヒドロキシエチルを用いて4種類のアクリル樹脂を合成した。得られたアクリル樹脂を固定相液体としたGLC測定を行い, 比保持容量と (重量分率) 活動度係数を求めた。エタノール, 2-プロパノールは樹脂に極性基を導入すると溶解しやすくなり, その効果はカルボキシル基のほうが水酸基より大きかった。また, ベンゼン, メチルエチルケトン, 酢酸エチルは樹脂にわずかではあるが溶解し難くなる傾向を示した。アクリル樹脂のSP値はカルボキシル基, 水酸基の導入によって増大し, その効果は水酸基の方が大きかった。
2 0 0 0 OA 管理会計における実験研究の位置付けを巡って
- 著者
- 田口 聡志
- 出版者
- 日本管理会計学会
- 雑誌
- 管理会計学 : ⽇本管理会計学会誌 : 経営管理のための総合雑誌 (ISSN:09187863)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.33-48, 2013-03-31 (Released:2019-03-31)
本稿では,管理会計における実験研究の方法論妁な意義を整理すると共に,管理会計研究をより豊かにしていくために実験が担っていくべき役割について検討を行う.実験研究は,(1)dataのハンドリングが容易,(2)事前検証が可能(意図せざる帰結の発見が可能),(3)内的妥当性が高いという優位性を持つ.また,実験研究には,2つのタイプがある(複数人間の意思決定を取り扱いメカニズムの検証が得意な経済実験と,個人単体の意思決定を取り扱いヒトの心理バイアスの検証が得意な心理実験).管理会計では,主にマネジメント・コントロールの領域で実験が用いられ,また,特に心理実験のウェイトが高い.今後は,心理実験と経済実験との融合を図り,また,他の研究手法と良好なコラボレーションを図っていくことが望まれる.
2 0 0 0 OA 野生チンパンジー薬草利用研究
- 著者
- ハフマン マイケルA
- 出版者
- Primate Society of Japan
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.179-187, 1993 (Released:2009-09-07)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 5 5
It has been proposed that chimpanzees use a number of toxic plant species for their medicinal value. Based on behavior, plant pharmacology, and ethnomedical information, hypotheses concerning the medicinal use of some of these plants by chimpanzees include the following: control of parasites, treatment of gastrointestinal disorders, regulation of fertility, and possible anti-bacterial or anti-hepatotoxic activity. With regards to bitter pith chewing and whole leaf swallowing behaviors, 20 medicinal plant species have been observed to be used not only by chimpanzees, but also by bonobos and lowland gorillas at 7 sites (Mahale, Gombe, Kibale, Kahuzi-Biega, Wamba, Tai, Bossou) across Africa. A detailed description is given of the research program currently being carried out by the author and colleagues of the international research team, The C. H. I. M. P. P. Group, and in particular, of the ongoing multi-disciplinary research into the chimpanzee use of Vernonia amygdalina (Del.) in the Mahale Mountains National Park Tanzania. The hypothesis that this species has medicinal value for chimpanzees comes from detailed observations by the author of ailing individuals' use of the plant. Quantitative analysis and assays of the biological activity of V. amygdalina have revealed the presence of two major classes of bioactive compounds. The most abundant of these constituents, the sesquiterpene lactone vernodalin, and the steroid glucoside vernoioside B1 (and its aglycones) have been demonstrated to possess antibiotic, anti-tumor, anti-amoebic, anti-malarial, anti-leishmanial, and anti-schistosomal properties. At Mahale, the particular parts of an additional 12 plant species ingested by chimpanzees are recognized for their traditional use against parasite or gastrointestinal related diseases in humans. Their physiological activities are now being investigated in the laboratory.