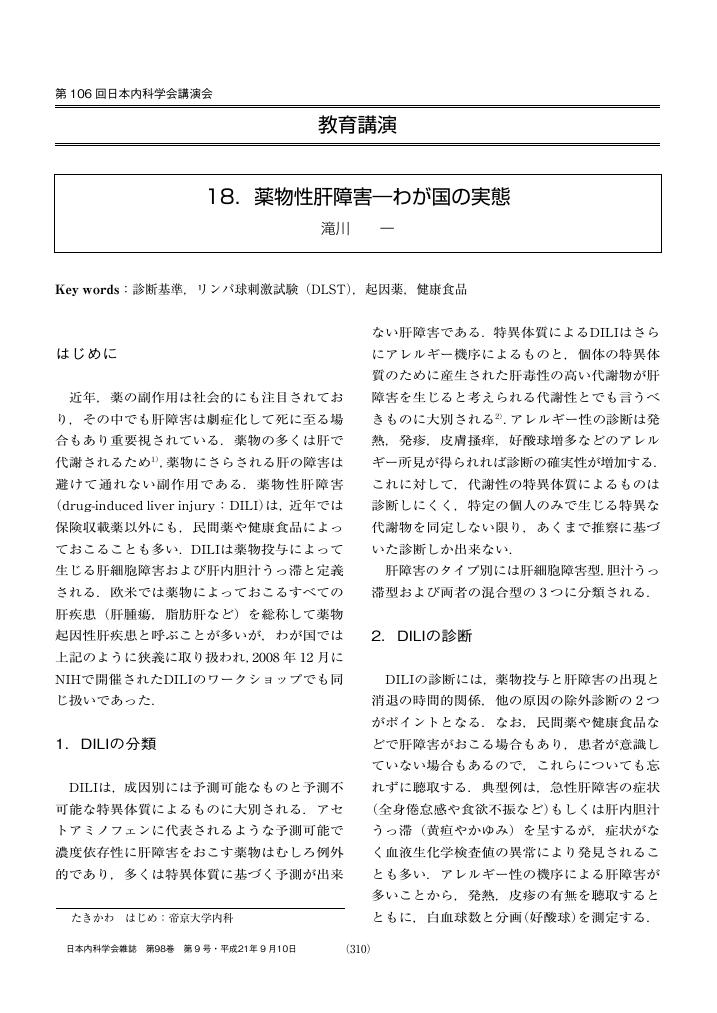- 著者
- 北原 麻理奈 児玉 千絵 羽藤 英二
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.806, pp.1271-1282, 2023-04-01 (Released:2023-04-01)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1
This study aims to clarify the dynamics of sawmill location in the mid-mountainous area in relation to infrastructure and factory power, using Tsukechi as a case study. As a result of the analysis, in the past, proximity to water for turning water mills was important for the location of sawmills, but with the spread of electricity and trucks, proximity to the old highway and the surrounding environment became more important for location. Distribution of locations was established, with factories clustered along the highway and scattered at the foot of the mountains.
6 0 0 0 OA Weather Modification in India
- 著者
- Bh. V. Ramana Murty K. R. Biswas
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.160-165, 1968 (Released:2008-05-27)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 2 4
Experiments on artificial stimulation of clouds using warm cloud seeding technique have been conducted, on randomized basis, from ground for 4 monsoon periods at Jaipur, 6 monsoon periods at Agra and 9 monsoon periods at Delhi, in North India. The seedings were also conducted from aircraft, during one monsoon period at Delhi. Orographic clouds have been seeded for two summer seasons at Munnar in South India.Results have been evaluated on the basis of rainfall amounts obtainedd from raingauges in the respective target and control sectors in each region. Evaluation has also been done on the basis of data obtained by high power microwave radar in the case of a few series of trials conducted at Delhi.A net increase in precipitation was suggested in each area as a result of seeing. The percentage increase in rainfall as a result of ground-based seeding varied from 18.6 to 58.5 according to the area. Statistical evaluation indicated that the results obtained could be significant.
6 0 0 0 OA 作業経験を知る:Well-being の入り口
- 著者
- Karen E. ATLER
- 出版者
- 日本作業科学研究会
- 雑誌
- 作業科学研究 (ISSN:18824234)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.12-29, 2022 (Released:2022-06-01)
- 参考文献数
- 47
日本作業科学研究会第24回学術大会の基調講演において,作業経験を知ることがいかに作業の複雑性 を知ることになるのかを探っていった.作業の複雑性を知ることは,well-being への入り口となりうる.本 論文では,作業を知ること,あるいは作業に関する主観的な視点を探求することが,どのように 1)作業と well-being の関係について作業科学者の理解を支援する,2)作業がどのように well-being に貢献したり影響を与えたりするか,他者が理解できるように作業科学者を支援することを可能にするか論じていく.はじめに私自身の研究,経験,その他の学術的研究から,作業経験と well-being,そしてそれらの交わりについて定義し,説明する.次に,作業経験の定量的評価である作業経験プロフィール(Occupational Experience Profile: OEP)を紹介する.そして,1)人々が直近で何をし,何を経験したかを評価し,2)作業経験と well-being の関係についてのユーザーの認識を促進するために,その価値を説明する.最後に,作業経験の定量的評価の拡大により,作業科学者が個人や集団の作業と well-being の関係を明らかにし続けることができるようになることを,いくつかの例を挙げて説明する.
6 0 0 0 OA がんの作業療法における病期別目標とアプローチに関する調査
- 著者
- 池知 良昭 三木 恵美
- 出版者
- 公益社団法人 北海道作業療法士会
- 雑誌
- 作業療法の実践と科学 (ISSN:24345806)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.31-35, 2023-05-31 (Released:2023-05-31)
- 参考文献数
- 9
本研究の目的は,がん患者の作業療法の病期別介入指針を明らかにすることである. 方法は,日本作業療法士協会事例報告システムに登録された67例を対象に予防~終末期に おける作業療法目標とアプローチを分析した.結果,自宅復帰,ADL能力の維持・改善 を全病期の目標に認めた.急性期,終末期の目標は患者の心理的苦痛の緩和が多く,創作活動を実施していた.維持期,終末期では家族や他職種への助言・指導が多かった.作業療法士の病期別介入指針として,患者の心理的ストレスが強い時期は,創作活動の導入により患者の心身の安寧を図り,維持期以降,支援者による補完によって作業の達成を図っ ていることが推測された.
6 0 0 0 OA 読解における語彙カバー率と理解度の関係
- 著者
- 相澤 一美
- 出版者
- 日本教材学会
- 雑誌
- 教材学研究 (ISSN:0915857X)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.23-30, 2011 (Released:2017-06-30)
- 参考文献数
- 13
This study is addressed to investigate the relationship between text coverage and reading comprehension by the EFL readers. Three reading texts with different text coverages by using non-words were given to three groups of students. They were told to guess the non-words and to answer the reading comprehension questions. The results showed that there was no particular relationship found between text coverage and reading comprehension scores. It was also found that the probability of success in guessing unknown words was not dependent on the text coverage. These results probably suggest that even though vocabulary plays an important role in reading a text, other factors probably exit in reading comprehension and guessing unknown words.
- 著者
- 坂本 優紀
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.3, pp.229-248, 2018-05-01 (Released:2022-09-28)
- 参考文献数
- 48
本稿は,長野県松川村におけるスズムシの鳴き声の地域資源化に着目し,サウンドスケープの持つ地域資源としての有用性を明らかにしたものである.観光資源の少ない松川村では,居住地の異なる住民主体の二団体により,スズムシの鳴き声という聴覚的地域資源を活用した取組みが行われてきた.スズムシの鳴き声は,古くから住民に親しまれており,地域資源としての活用が問題なく受け入れられた.しかし二団体の活用方法は異なっており,その要因として音を聞いてきた環境の違いによる,サウンドスケープの差異が指摘できる.また松川村においてスズムシの鳴き声は,地域アイデンティティ醸成の機能を果たしたが,特に注目すべきは,地域資源化の過程において,地域に対する再理解と新たな視点の獲得が行われたことである.本稿における考察の結果は,視覚的景観を重要視してきた日本の地理学において,聴覚を用いた地域理解の可能性を広げる点で重要な意義を持つ.
6 0 0 0 OA 日本人大腸の長さと内径に関するX線学的検討
- 著者
- 山崎 震一 山崎 健二 宮崎 高明 松岡 健司 丸山 寅巳 八木 禧徳 高桜 芳郎 伴野 昌厚
- 出版者
- The Japan Society of Coloproctology
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.31-39, 1994 (Released:2009-06-05)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 6 9 10
注腸二重造影像に示された腸管に紙紐を使って盲腸,結腸の各部分,直腸の長さと内径を測定し,性,年齢,身長,体重,肥満度,横行結腸下垂,S状結腸挙上,症状に対する統計学的分析を試みた.検査対象は男性120例,女性112例,平均年齢56.6歳であった.結果は大腸の長さは性と年齢に対して有意に関与するが,身長,体重,肥満度に対しては積極的関与はなかった.内径に対しては横行,S状結腸とも身長,体重に正の相関,年齢に負の相関があり,性差ではS状結腸の内径は女性の方が小であった.つぎに横行結腸下垂は性,年齢,身長,体重,肥満度,横行結腸大腸の長さに,S状結腸挙上は年齢,S状結腸,大腸の長さに,便秘は性,年齢身長,体重,横行結腸S状結腸大腸の長さに,便通異常は横行結腸大腸の長さに,出血は性に相関があり,腹痛はすべてに有為差を認めなかった.
6 0 0 0 近世日本イエズス会布教上のモラル神学的問題の考察
- 著者
- 川村 信三 DA SILVA EHALT ROMULO
- 出版者
- 上智大学
- 雑誌
- 特別研究員奨励費
- 巻号頁・発行日
- 2019-04-25
イエズス会の「良心例学」の過程における「奴隷問題」の位置とその解決につき、諸文書館の第一次史料における言及を確認することによって、当問題の取り組みの一つの歴史像をあらたに構築する。そのために原文書にアクセスすることを第一の課題として考えている。
6 0 0 0 OA 日本各地の縄文系対弥生系人口比率と日本人成立過程;ミトコンドリアDNAによる
日本人は先住の縄文人(狩猟採集民)と後入り渡来系弥生人(水田稲作民)の混血により成立した。渡来系弥生人は、今から3千~2千5百年前、大陸から朝鮮半島を経て、北九州近辺に入って来た。大陸の先進文化(稲作技術や金属器など)を携えていた。やがて彼らは縄文人を圧倒するようになり、更に日本列島上を東に進んで、3世紀末に畿内で大和朝廷を打ち立てた。それでは、縄文人の遺伝子は現代日本人の中にどれほど残っているんだろうか?また、山地や東北地方にはそれが多く残っているのではなかろうか?母方由来で伝わるミトコンドリアDNAの多型を使って、この質問に答えるための基礎理論を開拓し、その答を初めて明らかにした。
6 0 0 0 OA オタク分析の方向性
- 著者
- 田川 隆博
- 出版者
- 学校法人滝川学園 名古屋文理大学
- 雑誌
- 名古屋文理大学紀要 (ISSN:13461982)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.73-80, 2009-03-31 (Released:2019-07-01)
オタク文化の市場規模が大きくなり,海外でも注目を集めている.多くの若者はオタク系のイベントに集まる.オタク文化への言及も非常に多くなっている.本稿の目的は,オタク論の論点を整理し,課題を抽出し,研究の方向性を見出すことである.本稿では,オタクの行動や態度に着目する.オタクは,セクシュアリティ,二次創作,「萌え」,自己言及という特徴がある.これまでのオタク論では性別の違いについてあまり自覚的でなかった.今後は,性の違いを認識すること,その上でオタクとはいかなる過程を経てオタクになったのかなどを検討していく必要がある.
6 0 0 0 OA 液晶テレビ産業における日本企業の革新と衰退
- 著者
- 西澤 佑介
- 出版者
- 経営史学会
- 雑誌
- 経営史学 (ISSN:03869113)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.2_3-2_27, 2014 (Released:2017-11-10)
- 被引用文献数
- 1
This article explores the history of liquid crystal display (LCD) TV industry from its beginning stage of late 1980s to its popularizing stage of 2000s. Our purpose to consider the industry is examining following phenomena empirically. Although Japanese electronics firms had innovated on an electronic product, their market share fall behind as the product's market become expanding globally. Track of Japanese LCD TV industry is one of the typical cases of this pattern.Previous research has explained these phenomena stem mainly from the change of circumstances surrounding structure of electronic products and business model of electronic industry after 2000s.On the other hand, based on both primary and secondary sources, we emphasize on enterprises' organizational capabilities which was proposed by Alfred D. Chandler between Japanese firms and Korean and Chinese firms. This article shows Korean and Chinese electronics firms rapidly improve their organizational capabilities and had come to catch up with these of the Japanese firms during the 1990s, which became the omen to bring Japanese firms about decline in 2000s.Organizational capabilities of Japanese firms, which was once appreciated by researchers, certainly connected with its competitive advantage even in “the Japan's lost decade” 1990s, and made LCD TV commercialize fastest in the world. But especially in terms of Development, Marketing, and Branding capabilities, Korean firms were catching up with Japanese firms. And in terms of Production capabilities, Chinese firms came to catch up with Japanese firms. Finally, it is in the mid-2000s that they got ahead of Japanese enterprise's capabilities.
6 0 0 0 OA 足利義持と後小松「王家」
- 著者
- 石原 比伊呂
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.116, no.6, pp.1033-1063, 2007-06-20 (Released:2017-12-01)
This article is an attempt to 1) clarify the relationship between Shogun Ashikaga Yoshimochi 足利義持 and the Japanese imperial family (i. e., ret. Emperor Gokomatsu 後小松 and Emperor Shoko 称光 by reconstructing the manner in which Yoshimochi conducted himself as a member of the aristocracy and 2) place this shogun within the context of existing relations between the warrior and aristocratic classes. Within his role as a "member of royalty," Yoshimochi held the posts of deputy Kampaku 関白, serving as a quasi-imperial regent and the reigning emperor's personal secretary (Kuroudo-no-To 蔵人頭). He also served as instructor to Crown Prince Shoko and was by his side both at his initiation ceremony and coronation. In addition to his advisory role in connection with the emperor, Yoshimochi was involved with the retired emperor as a functionary in his household (Inshi 院司) and also internal minister of state (Naidaijin 内大臣), both advisory roles, to the point of being an indispensable member of his entourage. In this dual role, he was also called upon to settle disputes that arose between the two emperors. From such involvement on the part of Yoshimochi within the imperial household, the author describes his shogunate as an attempt to re-empower the Gokomatsu royal house.
6 0 0 0 OA 本人調査からみた発達障害者の「身体症状(身体の不調・不具合)」の検討
- 著者
- 高橋智 石川衣紀 田部絢子
- 出版者
- 東京学芸大学学術情報委員会
- 雑誌
- 東京学芸大学紀要. 総合教育科学系 (ISSN:18804306)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.73-107, 2011-02
6 0 0 0 OA 三重県における戦時交通統制と地域交通体系の再編成
- 著者
- 三木 理史
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.7, pp.548-568, 1992-07-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1 1
従来,国家的統制政策の所産と考えられてきた昭和初期から第二次世界大戦中の交通事業者の統合問題を,大手私鉄資本による地域交通体系の再編成という視点から再考して,その空間構造を検討した.事例は三重県における近鉄資本による事業者統合に求めた. その結果,大正期まで基本的に国鉄駅起点の路線形態をとり国鉄線中心の交通体系下にあった局地鉄道線は,大手私鉄資本下に統合されてゆくなかで,大手私鉄幹線中心の交通体系に再編成されてゆく過程を跡づけることができた.そうした地域交通体系の再編成構想の実施にあたっては,戦時交通統制という国家政策の利用が不可欠であった.
6 0 0 0 OA アスペルギルス・オリゼーの発見
- 著者
- 村上 英也
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.117-121, 1971-02-15 (Released:2011-11-04)
- 被引用文献数
- 1
我々日本の醸造屋は「コウジカビ」の大きな恩恵をうけている。明治9年に発見, 報告されてから現在までに多数の菌株が分離, 利用されているが, 筆者は長年, コウジカビの研究をし, 最近コンピュータを用いて, これがアスペルギルス・オリゼーという大集団で, フラブスとはちがうこと, 標準株と-致する株が50年来醸試に保存されていたことなどのいきさつを述べている。正しいコウジカビの知識のためにも, また研究者の喜びを理解していただく上にもぜひ一読を願いたい。
6 0 0 0 OA 18.薬物性肝障害―わが国の実態
- 著者
- 滝川 一
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.9, pp.2384-2389, 2009 (Released:2012-08-02)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 3 1
6 0 0 0 OA 仙台藩宿老後藤家文書―由緒・職務・武芸―
- 著者
- 野本 禎司 南郷古文書を読む会
- 出版者
- 東北大学東北アジア研究センター
- 雑誌
- 東北アジア研究センター叢書
- 巻号頁・発行日
- no.72, pp.1-254, 2023-01-19
6 0 0 0 OA 長崎半島東岸長崎市北浦町の上部白亜系層序の再定義とその地質年代学的意義
- 著者
- 宮田 和周 中田 健太郎 柴田 正輝 長田 充弘 永野 裕二 大藤 茂 中山 健太朗 安里 開士 中谷 大輔 小平 将大
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.1, pp.239-254, 2023-04-01 (Released:2023-03-31)
- 参考文献数
- 100
長崎半島東海岸に露出する上部白亜系“北浦層”を長崎北浦層と改定した.本層は下部の赤崎ノ鼻砂岩泥岩部層と上部の座頭浜礫質砂岩泥岩部層に二分でき,両部層は断層で接する.赤崎ノ鼻砂岩泥岩部層から産した2種のアンモナイト類(Polyptychoceras obataiとcf. Phylloceras sp.)と1種のイノセラムス類(Platyceramus japonicus),座頭浜礫質砂岩泥岩部層から産したハドロサウルス上科の鳥脚類恐竜の大腿骨化石を記載した.赤崎ノ鼻砂岩泥岩部層の軟体動物化石と砕屑性ジルコンのU-Pb年代から,長崎北浦層の時代は後期サントニアン期以降であり,おそらくカンパニアン期におよぶ.座頭浜礫質砂岩泥岩部層は岩相から長崎半島西海岸の三ツ瀬層の下部(中期カンパニアン期)に対比できる.長崎北浦層の層序は西九州の上部白亜系姫浦層群の下半部に関連すると考えられる.